|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
加速器は、電場や磁場を用いて電子や陽子などの荷電粒子を加速する装置である。高エネルギー放射線発生用加速器には、コッククロフト・ワルトン型加速器、ファン・デ・グラフ型加速器、電子線形加速器、陽子線形加速器、サイクロトロン、シンクロサイクロトロン、シンクロトロン及びベータトロンがある。また、中性子を発生する加速器中性子源もある。加速器施設の放射線遮へいでは、加速ビームの損失、放射線発生量、遮へいの方法、スカイシャインなどが問題となる。また、制動放射X線と中性子についても考慮しなければならない。加速器施設で求められる個人被ばく管理は主にX線と中性子に対する管理であり、また、100MeV以上の施設においては内部汚染の管理も必要となる。 <更新年月> 2015年02月
<本文>
加速器は、電場や磁場を用いて電子や陽子(プロトン)、イオンなどの荷電粒子を加速し、その運動エネルギーを大きくして取り出す装置である。加速された高エネルギー荷電粒子は、加速器窓から取り出され、物質との衝突によって物理的・化学的反応を起したり、あるいは別種の放射線を発生させる性質を持っている。 加速器が放射線利用の分野で脚光を浴びたのは、イギリスの物理学者コッククロフト(Sir John Douglas Cockcroft)とワルトン(Ernest Thomas Sinton Walton)が、1932年に600kVの高電圧の整流型加速器によって陽子を加速して原子核人工変換に成功(リチウムに衝突させ、2個のヘリウムを発生)したことが契機となっている。この実験により、両者は1951年にノーベル物理学賞を受賞している。その後、加速器の開発・進展はめざましく、原子核物理学や素粒子物理学などの基礎研究分野や高エネルギー放射線を利用する分野(化学、工学、生物学、医学)などで多種多様の装置が利用されている。荷電粒子を加速する方法には、直接加速方式と間接加速方式とがある。直接加速方式は、イオンや電子の発生源と取り出し口との間にかけた高電圧によって加速する方式である。また、間接加速方式には荷電粒子を回転させながら加速する方式、または高周波で加速する方式がある。表1に加速方式により分類した加速器の種類を示し、表2に加速する粒子の種類とその加速器の利用エネルギー範囲を示す。 1.各種加速器の特徴 1.1 直接加速方式 1.1.1 コッククロフト・ワルトン型加速器 交流電源を利用して、多数のコンデンサーと整流器を組み合わせた倍電圧回路と呼ばれる整流回路を利用し、直流高電圧を発生させる(図1)。この高電圧によって強い電場を作りイオン源から出てきた荷電粒子を加速する。1932年にコッククロフトとワルトンによって考案されて以来、広く利用されている。加速される荷電粒子のエネルギーは、最高で2〜3MeVである。高電圧整流型加速器とも呼ばれている。 1.1.2 ファン・デ・グラフ型加速器 1931年にファン・デ・グラフ(Robert Jemison Van de Graaff)が考案した加速器で、その原理を図2に示す。球状の高圧電極のなかの滑車と下端の滑車の間にあるベルトにコロナ放電で正電荷を与え、その正電荷を上方の電極内に運び込み高圧電極表面に蓄えることによって高電圧を発生させ、イオン源からの荷電粒子を加速する。その後、ベルト方式とは異なる金属ペレット方式が開発され、20MeV程度までの高エネルギーが得られるようになった。 金属ペレット方式は、ペレットチェーンに電荷を乗せて高電圧端子に運び上げ高電圧を発生させてイオンを加速する装置で、一つの高電圧で加速イオンの電荷を負から正へ変換して2回加速する装置としてタンデム(TANDEM=2頭立ての馬車)加速器がある。 タンデム加速器から得られるイオンビームは、そのエネルギー、イオン種、量を正確に制御できるため精密な原子核物理、物質科学などの研究に利用されている。 タンデム加速器に高周波超伝導を利用した超伝導ブースターを設置し、原子質量200程度までの元素同士の核反応を起こすことのできる高エネルギーの重イオンビームを加速して、基礎研究で利用することも可能となっている。 1.2 直接加速しない方式 直接加速方式では、絶縁の問題から加速エネルギーに限界がある。これを解決するために間接的な加速方式として、高周波電場を利用した線形加速器(リニアック、ライナックとも呼ばれ、LINACとも記される)と電場・磁場を利用した円形加速器が開発された。 1.2.1 線形加速器 電子と他の荷電粒子(陽子やイオン)には質量に著しい差があるため、効率よく加速するためには、それぞれに対応して線形加速器もその構造を変える必要がある。 (a)電子線形加速器:加速管は、図3(a)に示すように、襞(ひだ)あるいは中穴円板をある間隔で並べた円筒状の管であり、ここに波長が3〜30cmのマイクロ波を送り込むと、電子はその波に乗って加速する。マイクロ波を用いることで絶縁の問題が軽減されるので、20GeVのような高エネルギーまで加速できるのが特徴である。図3(b)に加速管(導波管)内で電子が電波に乗って速度を上げる様子を示す。なお、X線の場合は、電子線をタングステン等の金属に当てて発生させる。 北海道大学加速器中性子源HUNS(Hokkaido University Neutron Source)は、1973年に完成し、以来40年間、パルスラジオリシス(時間幅が非常に短いパルス状の放射線を物質に照射し、その後に物質中で生じる高速物理化学現象を分光により調べる方法)や照射など広い分野の実験に使用されてきた。建設当初から冷中性子発生のための中性子減速材研究を進め、高性能のメタン減速材の開発に成功し、加速器中性子源として初めて冷中性子源が附置された施設となった。35MeVの電子エネルギーで鉛をターゲットとした場合、加速器パワー1kWで毎秒1.6x1012個の中性子が発生する。 京都大学原子炉実験所電子ライナックは、原子炉中性子源と対照的かつ相補的なパルス中性子源として、1965年に建設された電子線形加速器である。最大加速エネルギーは46MeV、最高出力は6kWで、汎用小型ライナックとしては国内最高レベルの大電流が得られる。加速した電子ビームを水冷式タンタルターゲットに照射することにより、ターゲット内で生じる制動X線を用いて光中性子を発生させる。 (b)陽子線形加速器:加速部は、図4に示すように、交互に電気的に連結された中空の細い円筒状電極であり、円筒の長さは後方にいくほど長くなっている。この円筒電極に高周波電圧を加えると、陽子は、隣り合った電極間にできる高周波電場により加速される。約200MHzの高周波がよく使われる。陽子エネルギーとしては10MeVから200MeVのものが多く作られ、大型陽子シンクロトロンの前段加速器として使われている。陽子線形加速器には、800MeVの高エネルギーのものまである。 京都大学理学部では、タンデム加速器実験施設において、小型陽子加速器を利用した中性子源(KUANS)の開発を行ってきた。加速エネルギー3.5MeVの陽子リニアック(全長3.7m)を導入し、ビームパルス幅30〜120μs、ビーム繰り返し20〜120Hz(毎秒発生するビームの数)、定格平均ビーム電流100μAである。中性子の発生には9Be(p,n)反応を用いる。標的は50μm厚のBeで、Nbのバッキングを通じて水冷されている。 理化学研究所では、平成20年頃より非破壊検査測定の一部としての中性子ラジオグラフィの評価を行ってきた。小型中性子源でも最新の技術を組み合わせることで大型中性子源並みのイメージング画像が取得できることを確認し、その実証試験として小型中性子源(RANS Accelerator-driven compact Neutron Source)を建設して評価することとなった。陽子線形加速器を用いて陽子ビームを7MeVまで加速させ9Be(p,n)反応により中性子を発生させる。陽子の平均電流は最大100μAであり、その際に発生する総中性子量は1012n/秒程度と見積もられる。発生した中性子はポリエチレンブロックを利用した減速体で熱中性子ビームとして取り出される。この成果を利用して、鉄鋼業界と連携した研究を行い、塗膜下腐食並びに水の出入りの様子を世界で初めて非破壊で測定することに成功した。透過能が高く飛行時間法による画像の鮮明化が可能な高速中性子線を用いることにより、厚さ数十cm以上のコンクリート内部を非破壊で観察する新たな非破壊検査手法も可能と期待されており、このための技術開発がRANSの高速中性子成分を利用して進められている。 1.2.2 サイクロトロン 円形加速器の代表はサイクロトロンである。サイクロトロンは図5に示すように、N・S磁極(直流電磁石)の間に、2つの半円形の中空電極(ディーと呼び、D1とD2がある)に高周波を送り、中心部のイオン源からのイオン(陽子からウランまで)を加速する。全体が強い磁場のなかにあるので、このイオンは曲げられて、らせん軌道を描きながら繰り返し加速される。しかし、イオンの速度が高くなると相対論的質量が増加し、イオンの回転と加速周波数との位相がずれて加速できなくなるため、加速エネルギーには制限があり、陽子で20MeV、重陽子で20〜30MeV、α粒子で45MeV程度が上限である。得られるビームのパルス性は直流に近いので、ラジオアイソトープの製造(ベビーサイクロトロン)、中性子の発生、核構造・核反応の研究、陽子線治療などに幅広く利用されている。この上限を超えて加速するためには周波数変調を加えたシンクロサイクロトロンやシンクロトロンが用いられる。 1.2.3 シンクロサイクロトロン シンクロサイクロトロンは、サイクロトロンにおける磁場を一定にして、加速周波数を変化させてイオンを加速するのが特徴である。この加速器は、陽子ならば、数百MeVまでの加速に適している。 1.2.4 シンクロトロン(磁気共振型加速器) シンクロトロンでは、サイクロトロンの場合とは異なり、磁場を強くするとともに加速周波数を変化させて軌道半径を一定に保ちながらイオンを加速するのが特徴である。 ドーナツ型の真空加速管を用い、電磁石は中心部を除いた環状のものである。荷電粒子は、ドーナツのなかを回転しながら、加速管の一部分に設けた高周波電場を発生させる空洞発信器の間を通る時に加速される。荷電粒子の中で電子は比較的低いエネルギーで光速度に近い速度にまで加速されるので、加速周波数の変調がほとんど不要である。これに対し、陽子では、広い範囲で周波数の変調が必要となるので、装置の構造も異なる。 電子シンクロトロンの構造概念を図6に示す。電子では6GeV、陽子では400GeVまでの加速エネルギーで装置が運転されている。 高エネルギーの電子シンクロトロン放射光(放射光)は、赤外線からX線域まで平坦なスペクトル、強力光源、高い指向性、偏光性など優れた特徴を有しているため、最近では、この放射光を積極的に利用するための専用加速器が大学を含む国公立研究機関、民間研究機関に建設され、多くの分野における基礎研究や応用研究に利用されている。さらに、シンクロトロン放射光とは異なり、高速電子に蛇行やらせん運動をさせる自由電子レーザーの開発も進んでいる。 1.2.5 ベータトロン(磁気誘導型加速器) 磁気誘導によって電子(ベータ線)を加速する装置で、図7に構造の概念を示す。電磁石の間にドーナツ管とよぶ環状の加速管をはさんでいる。磁極は軸対称な円形である。電子は、ドーナツのなかを磁場の方向に垂直な面内で、磁場の強さで決まる円軌道に沿って運動する。電磁石が交流で励磁されると、この円軌道内の磁束の時間的変化に比例した電場が円軌道に沿ってできるので、この電場により電子は加速される。ベータトロンは、必要なエネルギーまで加速された電子を、その軌道を少し変えて金属のターゲットにあて、発生する制動放射のX線やγ線を用いる医療用や工業用などの放射線源として使用されている。製作が比較的簡単で、小型化できる利点があるが、他の加速器に比べて強度が低く、安定度も低いため、ベータトロンはリニアックに置き換えられつつある。 1.2.6 加速器中性子源 コッククロフト・ワルトン、ファン・デ・グラフ、サイクロトロンなどの加速器で加速した陽子、重陽子、α粒子(アルファ粒子)等各種ビームを比較的軽い原子核に衝突させると核反応、光核反応により核分裂が起こり高速中性子を発生させることができる。これを加速器中性子源と呼んでいる。特に、陽子ビームとトリチウム(3H)やリチウム同位体(7Li)との反応及び重陽子ビームと重水素(2H)やトリチウムとの反応などは、加速器を用いて得られる単一エネルギーの中性子線源として利用され、核融合炉の中性子工学や放射線防護、材料損傷の研究に広く用いられている。また、ベリリウム(Be)に加速したα粒子ビームを当て、1MeVから10MeVまでの広いエネルギー範囲の中性子線が得られている。 上記の中性子ラジオグラフィのほか、中性子は医療分野におけるホウ素中性子捕捉療法(BNCT)などに利用されている。わが国では、1968年から研究用原子炉を用いてBNCTが行われてきているが、利用時の制約の多さや使い勝手の悪さなどからその普及が滞っている。このような背景のなかで、加速器技術が向上したことを受け、2000年頃から世界的に加速器中性子源を用いたBNCT照射システムの実現を目指す動きが強まった。現在、最も実用化に近いのは京都大学・住友重機械が共同開発中のサイクロトロンを用いた照射システムとされている。 2.加速器施設の放射線防護 2.1 放射線遮へい 高エネルギー放射線を得る加速器施設では、予定外の放射線が副次的に発生する。そのためにこれらの加速器施設では放射線遮へいが必要となる。この放射線遮へい設計で検討すべき項目には、加速ビームの損失の評価、放射線発生量の評価、遮へいの方法、スカイシャインなどがある。また、遮へい設計上注目すべき放射線は、電子加速器の場合は制動放射X線と中性子線である。さらに、加速エネルギーが数GeVを超えると前方方向についてのミュー粒子が問題となり、陽子加速器では、中性子線が問題となる。 これらを防ぐ遮へい体の材料としては、コンクリート、鉄、鉛などが使われる。出力が数kW、加速エネルギーが8GeV程度の電子加速器の場合、普通コンクリートを使用すると遮へい体の厚さは1〜4mとなる。これは遮へい体の外部で「放射線障害防止法」等に定める線量の基準以内にするための措置である。鉛は中性子線に対する遮へい効果が少ないため、中性子線の寄与が大きい場合には、ホウ素、パラフィン、プラスチックなどの中性子線を遮へい、吸収しやすい材料を利用する。 2.2 放射線防護 加速器施設では、荷電粒子の加速中に軌道から逸れた粒子と加速器構成鋼材等との相互作用、及び粒子がターゲットに衝突した際に発生する2次放射線を遮へいする必要がある。この放射線は、主として制動放射X線と中性子線である。 加速器施設における個人外部被ばくの管理は、加速エネルギーが30MeV未満の施設では主としてX線、それ以上ではX線及び中性子線が対象となる。加速エネルギーが100MeVを超える施設では、特に中性子線の管理が重要になる。 内部被ばくの管理では、100MeV未満の施設の場合には全体としても放射化物生成量が少なく、その表面密度も低いため、ほとんど問題とならないが、100MeV以上の施設では、非密封放射線取扱施設と同様の汚染管理が必要となる。 施設の管理も個人被ばく管理と同様に、加速エネルギーが100MeV未満の施設では主としてX線、100MeV以上では施設周辺のスカイシャイン中性子及び施設から発生する放射化物の管理が重視される。 (前回更新:2010年2月) <図/表> 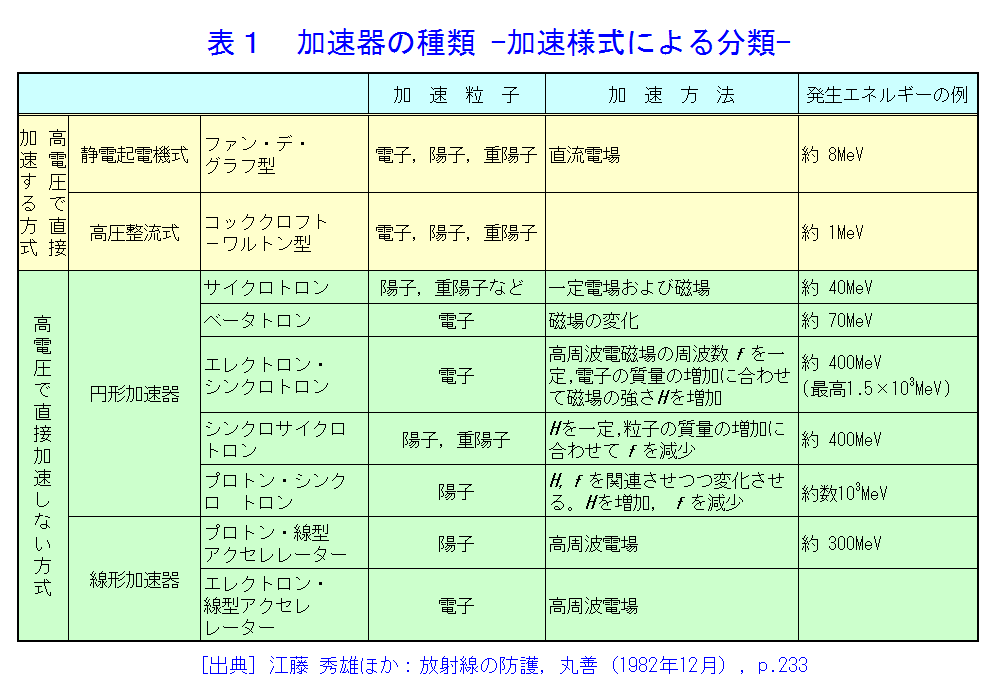
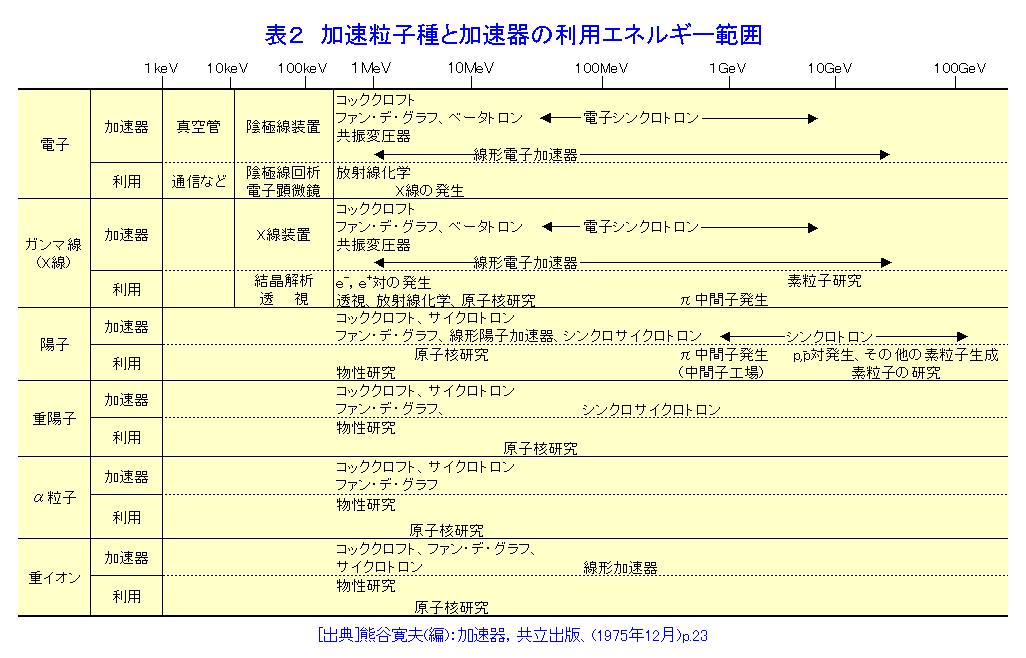
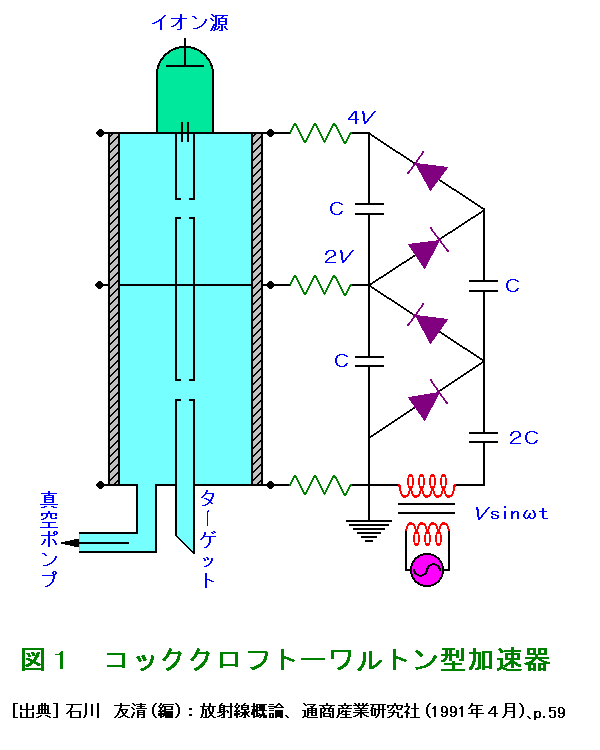
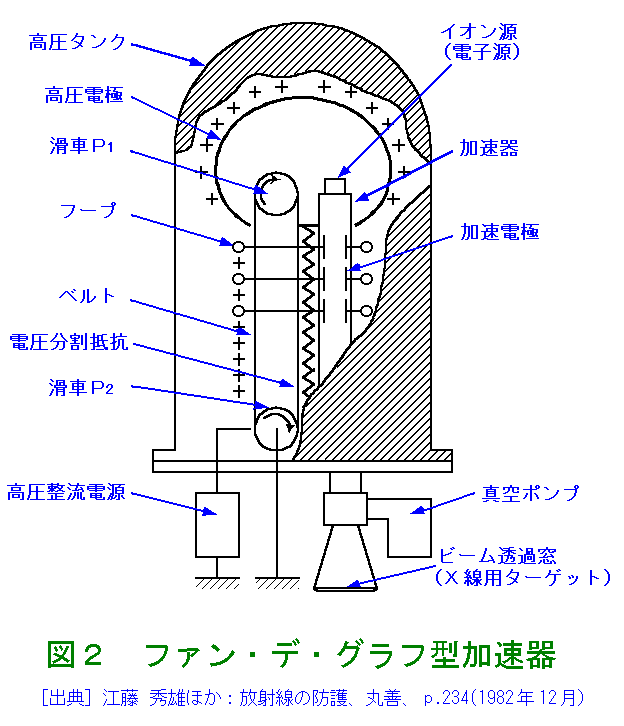
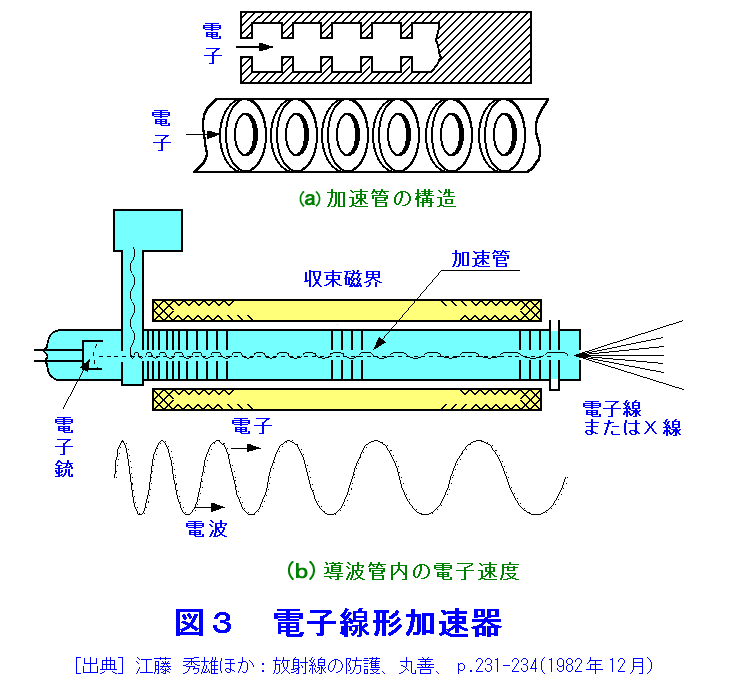
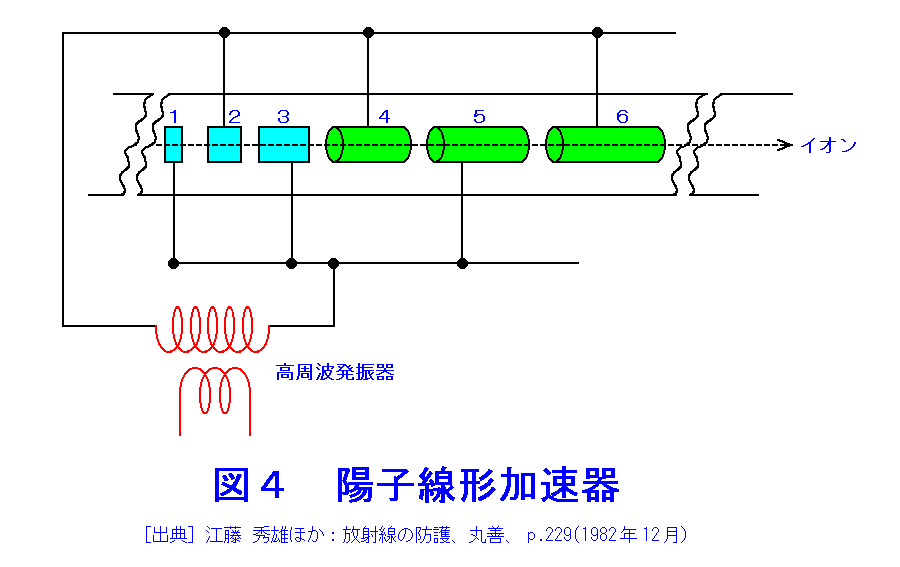
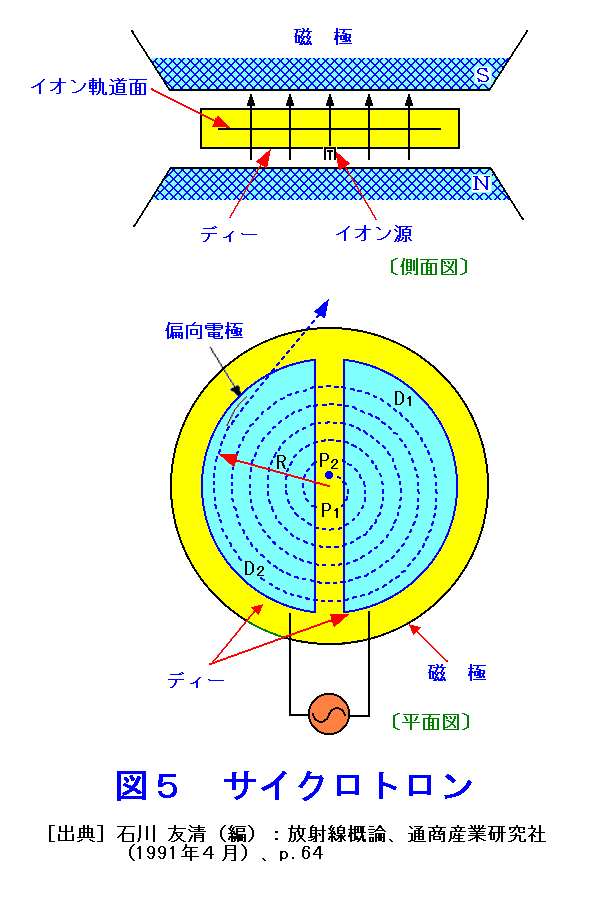
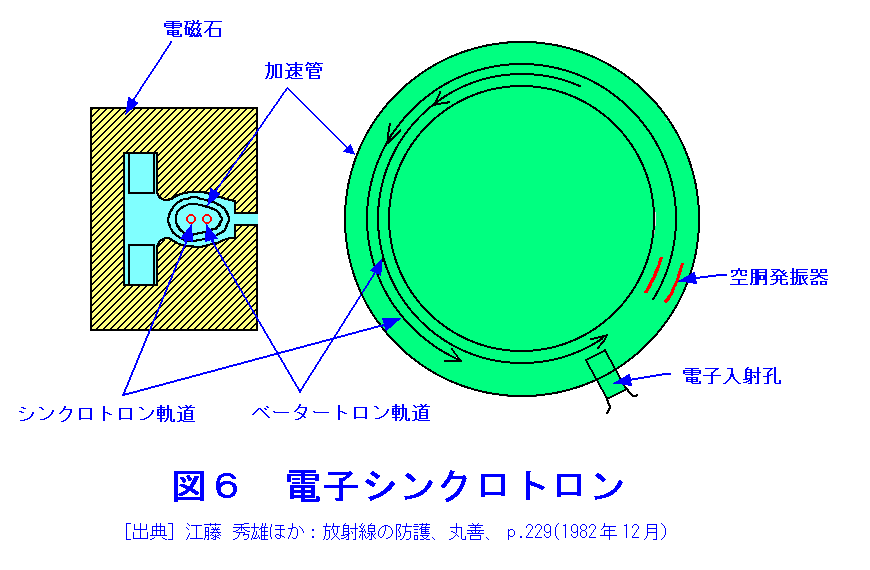
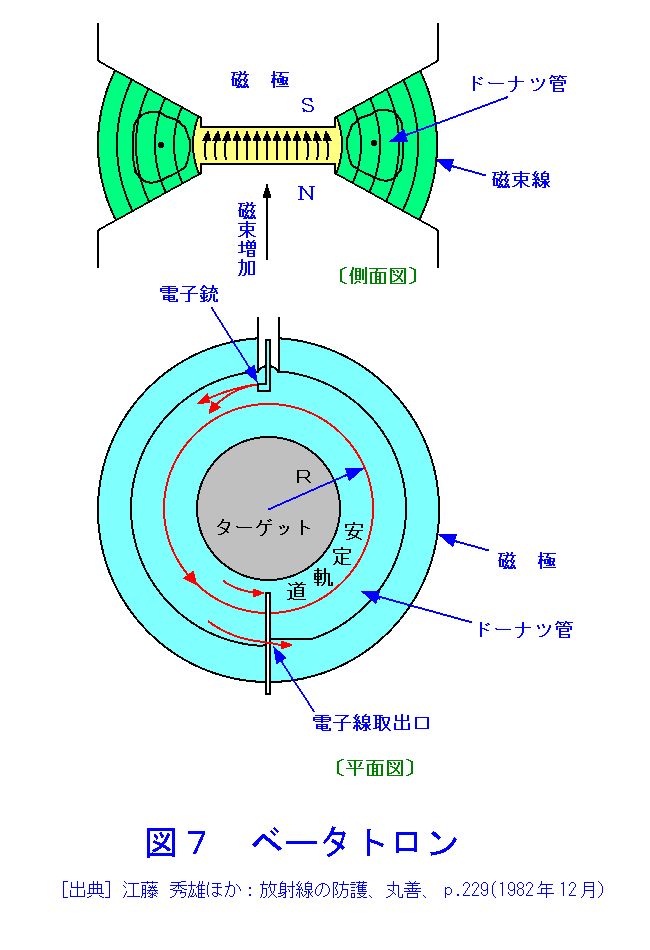
<関連タイトル> 電離放射線 (08-01-01-01) 放射線の分類とその成因 (08-01-01-02) 放射線の遮へい (08-01-02-06) エックス線発生装置の原理 (08-01-03-01) シンクロトロン放射光 (08-01-03-08) 冷中性子の発生と応用 (08-04-01-04) 放射線による外部被ばく (09-01-05-01) 内部被ばく (09-01-05-02) 放射線防護上の遮へい (09-04-10-03) <参考文献> (1)熊谷 寛夫(編):加速器、共立出版、(1975年12月) (2)久保 亮五 ほか(編):理化学辞典 第4版、岩波書店、(1989年12月) (3)加藤 和明(編):加速器の開発とその利用、日本原子力学会誌、31(9)、(1989) (4)近藤 健次郎:高エネルギー加速器周辺の放射線管理、保健物理、Vol.19、33、(1984) (5)加藤 和明ほか:高エネルギー加速器の放射線安全の考え方、原子力工業、33(11)、(1987) (6)加藤 和明ほか:放射線防護、日本原子力学会誌、32(1)、(1990) (7)加速器放射線防護研究専門委員会(編):加速器放射線防護の現状、日本保健物理学会、(1990年4月) (8)能澤 正雄・鹿園 直基(監):加速器の現状と将来、日本原子力産業会議・原子力システム研究懇話会、(1998年6月) (9)石川 友清(編):放射線概論、通商産業研究社、(1991年4月) (10)原研タンデム加速器及びブースター: (11)中村 尚司:放射線物理と加速器安全の工学[第2版]、地人書館、2001年4月 (12)江藤 秀雄ほか:放射線の防護、丸善、(1982年12月) (13)鬼柳 善明:日本の小型加速器中性子源施設、Isotope News、2014年1月(No.717) (14)大竹 淑恵ほか:世界初、小型中性子源システムを用いて鉄鋼材料における内部腐食を非破壊的に可視化、Isotope News、2014年6月(No.722) (15)日本加速器学会:国内主要加速器関連施設一覧、
|

