|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
放射線に被ばくしてから数ヵ月を経過した後、または致命的ではない程度の急性放射線影響が起こった場合でも、その影響が消退してから、しばらくたって身体に発生する病的状態を晩発影響という。放射線の身体への急性影響には急激な漏出性出血や水腫を伴う循環障害と、その組織の細胞集団の死などがある。死を免れた場合には、不可逆的な損傷が、急性影響から生きのびた細胞内に何らかの形で保持されていて、ある期間の後に病的状態として身体上に発現する。例えば(1)発がん、(2)非特異的寿命の短縮、(3)白内障などの加齢の促進である。一方、照射部位の組織の萎縮とその組織の有する機能が低下した後、修復の機転が働く結果、結合組織の増加(線維化)と硝子変性、さらに壊死部の瘢痕化(ケロイド)が起こる。 <更新年月> 2002年10月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
晩発性の身体的影響については、被ばくとその病的状態の発現までの期間が長く、その因果関係を明確にするには困難を伴うが、その究明のためにこれまで幾多の被ばく集団を対象とした疫学調査が行われ、また現在も継続されている( 表1 )。1986年4月におきたチェルノブイリ事故による被ばく者集団の継続調査も行われている。疫学調査の結果の不備を補う目的で動物実験のデータも利用されている。 1.発がん X線や放射性同位元素の発見に次いで、その研究、利用開発の初期には白血病の発症、皮膚の火傷潰瘍からのがんの発症が注目されており、キューリー夫人母娘の白血病はその一つの事例である。現在、放射線被ばくと因果関係が特に深いと考えられているがんは白血病、甲状腺がん、女性乳がん、肺がんである( 表2 )。白血病は骨髄性とリンパ性、さらにそれぞれに急性と慢性との病型に分けられるが、現在までに慢性リンパ性白血病の過剰の発症は認められていない。骨髄性白血病が放射線被ばくに特に深い関連があるのではないかとされている。しかし、以上4つのがん種には放射線に特異的な病理組織学的変化は認められておらず、ただ発生率の過剰が認められるのみである。次に発生率の過剰の認められるがんは唾液腺がん、食道がん、胃がん、膀胱がん、多発性骨髄腫などが挙げられている。放射線被ばく集団において比較的早期には白血病の発生が目立ったが、加齢が進むに従って、他のがんの発生率の増加が注目されるようになった。今後も各々の集団において検索が続けられているので発がん症例の頻度や種類に変化が認められるかもしれない。 2.寿命の短縮 発がんとともに寿命の短縮が注目されたことがあった。放射線防護が十分でなかった1900年代前半の放射線科医とそうでない一般医との間で寿命の差が認められるとの疫学調査報告がなされた。防護が確立した後は、英国での調査や原爆被ばく生存者のうち、がんでない人々についての調査では寿命短縮の傾向は認められなかった。なお、最近では、放射線に対する管理が行き届いていることもあって医師の間に寿命の有意差は認められない。 一方マウスを用いた動物実験では線量に比例して寿命の短縮がみられると報告された。しかし、その後の詳細な病理組織学的検討(動物を解剖して、各々の臓器の異常部位組織片を顕微鏡的に検査をする)の結果、少なくとも低・中線量に被ばくした動物にはがんが発生し、このがんが寿命短縮を惹起するとの結果から、非特異的寿命短縮はみられないと結論されている。よって、最近では一般的に非特異的寿命短縮はみとめられないとする傾向にある。 3.胎児への影響 次に、放射線被ばくの身体的影響の特殊な例として胎内被ばくが挙げられる。この場合、被ばく線量と胎令とが障害の程度に大きく影響を及ぼす。線量が2.5Gy以上の高線量で妊娠の初期(2〜3週令)では流産などの胚子の死が招来されることが多く、妊娠が進み、胎児の器官形成期(4〜11週)では多くの器官の重複奇形がみられ、その後の20週では中枢神経系の発育障害を来たし、精神発育遅鈍がみられる傾向が認められている。その後、出生した児にがんの発生の増加が予想される。しかし、原爆被ばく生存母親から出生した1000人以上の20数年に及ぶ追跡調査ではがんの増加は認められていない。なおこの項の詳細は胎児期被ばくによる影響(構成番号 <09-02-03-07>)を参照されたい。 4.局部被ばく(身体の部分的被ばく)による晩発性影響( 表3 参照) 身体の一部が放射線に被ばくした場合の組織に生ずる病変についての例には、白内障などが知られている。放射線によって惹起された病変には特異性はなく、急性期の血管損傷による循環障害から変性・萎縮・壊死に至る一連の受け身の退行性病変から、障害を受けた組織が修復の過程を経て回復するまでのごく一般的な損傷治癒過程がみられる。その過程で、晩発性変化として実質組織では、実質細胞の容積の縮小すなわち萎縮があり、加えて、その細胞の機能の低下が随伴することが多い。例えば腺組織であれば分泌が減少する。涙腺であれば、涙の分泌の減少から眼が乾燥してくる症状として現れてくる。実質細胞と実質細胞の間にある間質には結合組織の増生が起こり、さらに結合組織を構成している膠原繊維に硝子変性と言われる変化が起こって組織の柔軟性が減少して硬化を招来する。この病態が血管や導管に生ずると、その内腔が狭くなり、血流の減少、分泌物の通過障害、貯留が起こり、二次的な臓器障害へと進展する。また実質臓器では部分的萎縮と硬化が起こる。さらに、変化が変性萎縮以上に激しくなれば、組織には壊死が起こり、壊死に陥った組織は通常は早晩融解除去され、その跡は肉芽組織といわれる新たに増生した結合組織によって置換され、その後数週を経たこの組織が瘢痕(ケロイド)である。すなわち壊死病巣は瘢痕で置き換わると言える。実質細胞の放射線の感受性はかなりの差があり、細胞分裂により常に自己更新をしている細胞ほど感受性が高いという一般則がある(Bergonie-Tribondeauの法則)。 5.まとめ 放射線被ばくによる晩発性身体影響は、自己複製能を備えた細胞の突然変異による発がんと、細胞組織に惹起された変性・壊死の様々な過程を含んだ受け身の病変の後の修復像であると言うことが出来る。また発がんは線量により病状の重篤さは変わらず、発生率のみ変化し、防護上その発生率はしきい値のない確率的影響とされている。一方、組織障害はその発生にしきい値があり、また重篤さが線量に依存することから非確率的影響(確定的影響)といわれる。 <図/表> 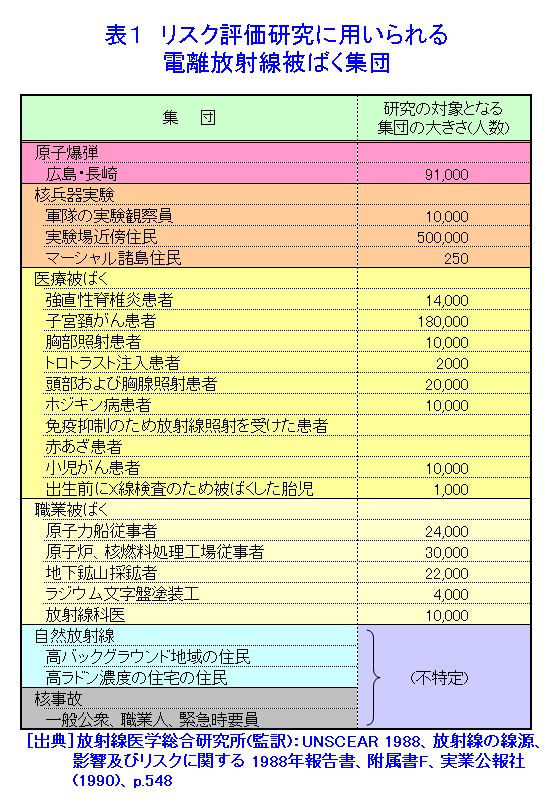
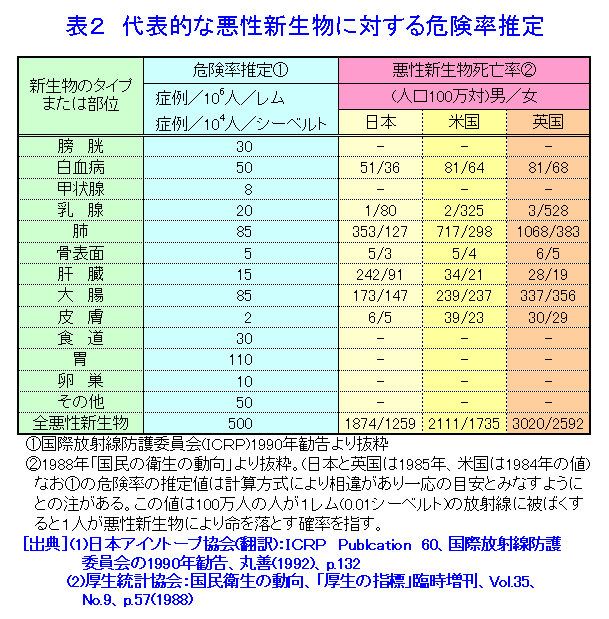
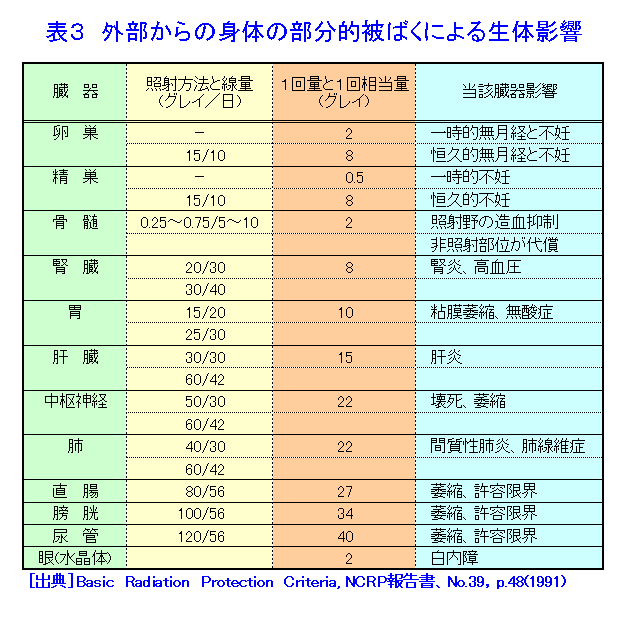
<関連タイトル> 放射線の身体的影響 (09-02-03-03) 放射線の遺伝的影響 (09-02-03-04) 胎児期被ばくによる影響 (09-02-03-07) 放射線の生殖腺への影響 (09-02-04-03) 白血病 (09-02-05-02) がん(癌) (09-02-05-03) 白内障 (09-02-05-04) 放射線が寿命に与える影響 (09-02-05-05) <参考文献> (1) ”Radiobiology for the Radiobiologist” 3rd ed., Eric J. Hall, Lippincott(1988) (2) E. J. Hall(著)、浦野宗保(訳):放射線科医のための放射線生物学、 篠原出版(東京)(1995) (3) 中尾(編):放射線事故の緊急医療、ソフトサイエンス社(東京)(1986) (4) 放射線医学総合研究所(監訳):UNSCER 1988、放射線の線源、影響及びリスクに関する 1988年報告書、附属書F、実業公報社(1990) (5) 菅原 努(監修):放射線はどこまで危険か、マグブロス出版(1982) (6) NCRP報告書、No.39, (1991) (7) 日本アイソトープ協会(翻訳):ICRP Publcation 60、国際放射線防護委員会の1990年勧告、丸善(1992)、p.132 (8) 厚生統計協会:国民衛生の動向、「厚生の指標」臨時増刊、Vol.35、No.9、p.57(1988) (9) UNSCERAR 1993 Report、実業公報社
|

