|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
1986年4月26日午前1時23分(日本時間同日午前6時23分)、旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所4号機(「黒鉛減速軽水沸騰冷却型-RBMK型」)で事故が発生、大量の放射性物質が周辺環境に放出された。事故が発生した原子力発電所は旧ソ連が開発し、旧ソ連国内でしか運転されていないものであった。事故は、外部電源が喪失した場合に、タービン発電機の回転エネルギーにより主循環ポンプと非常用炉心冷却系の一部を構成する給水ポンプに電源を供給する能力を調べる試験を実施しようとしていた最中に原子炉が不安定な状態になり、制御棒を挿入したところ急激な過出力が発生したために生じたものである。事故によって原子炉および原子炉建屋が破壊され、次いで高温の黒鉛の飛散により火災が発生した。火災は鎮火され、引続き除染作業と原子炉部分をコンクリートで閉じ込める作業が実施された。運転員と消火作業に当った消防隊員に放射線被ばくによって計31名が死亡し、発電所の周囲30kmの住民等、約13万5千人が避難し移住させられた。 <更新年月> 2007年01月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.チェルノブイリ原子力発電所4号機の概要 この原子力発電所は、ベラルーシ・ウクライナ低湿地と呼ばれる地区の東部で、キエフ市の北北西108km、チェルノブイリ町の北西15kmに位置し、ドニエプル川に流入するプリピアチ川の河岸にある。 図1aはチェルノブイリ原子力発電所とキエフ市の位置関係を、図1bにチェルノブイリ原子力発電所全体の敷地平面図(原子力発電所および冷却水貯水池)を示した。 同発電所では、事故発生時点で1、2、3、4号機の4基のRBMK-1000型原子炉が稼働中で、5、6号機の2基を建設中であった。これらの原子炉は、すべて減速材として黒鉛を用い、冷却材として沸騰軽水を用いる旧ソ連にしかない形式のものである。なお、1号機は1988年11月、2号機は1991年10月、3号機は2000年12月、4号機は1986年4月26日に閉鎖した。 事故を起したチェルノブイリ原子力発電所4号機(以下4号機という)の発電端電気出力は100万kWである。 原子炉の炉心の基本単位は、断面25cm×25cm、高さ60cmの黒鉛ブロックの中央に直径11.4cmの穴をあけ、鉛直方向に燃料集合体を収めたジルカロイ製圧力管(チャンネル)を通したものである。これを円筒状に積上げて直径11.8m、高さ7.0mの炉心を構成している。圧力管の数は1661本である。制御棒を通す穴をもつ黒鉛ブロックが 211本あり冷却管が黒鉛ブロックを貫通している。黒鉛ブロックは全体として耐圧 1.8気圧の鉄製容器に収められ、黒鉛の酸化防止および温度制御のためヘリウムと窒素ガスの混合ガスによって保護されている。 図2はRBMK-1000型炉のシステム概念図を示した。 燃料集合体は、図3に示す構造をしており、約7mの高さのもので、上下2段に分けられている。それぞれは18本の燃料棒(高さ約3.4m、直径1.36cm)から構成されている。燃料ペレットは酸化ウランを使用しており、ウランの濃縮度は2.0%である。 燃料棒で発生した熱は、圧力管を通る軽水に伝えられ、軽水は沸騰して、相当部分が蒸気となる。その結果、高温高圧(約284℃、70気圧)の気水混合流が得られる。この気水混合流から気水分離器によって蒸気が分離され、2基のタービン発電機に送られ、発電する。 冷却水を炉心に送る回路は2ループあり、各ループには予備1台を含む合計4台の循環ポンプがある。原子炉の熱出力は320万kW、電気出力は100万kWである。なお、この原子炉には格納容器はない。 2.チェルノブイリ4号機の事故に関係する特徴 日本で一般的に用いられている軽水炉(PWRとBWR)は、軽水が減速材と冷却材を兼ねているので、炉心内で冷却材の密度減少、たとえば蒸気(ボイドという)が発生すると、減速材が減ることになり、自動的に核分裂の連鎖反応が減少する。これに対し、減速材と冷却材が分離している原子炉では、冷却材の減少は、冷却材のもつ中性子吸収が減少する効果が発生することがある。4号機においては、炉心での蒸気発生に伴う正の反応度フィードバック効果は大きいが、燃料自身のもつ負の反応度フィードバック効果と相殺して、定格出力運転では安定な運転ができる。しかし、熱出力が定格320万kWの20%以下では、ボイド発生による正の反応度フィードバック効果が燃料の負の効果よりも大きくなり、不安定になる。 この正のボイド効果は、炉心内に挿入されている制御棒の数にも依存し、制御棒数が減少すると、正のボイド効果はさらに増大する特性をもっている。この特性のため、運転規則では、211本の制御棒の中最小限30本は炉心に残す(反応度操作余裕30本)ことを定めていた。 また、原子炉の緊急停止系にも問題があり、緊急停止信号が発せられても、制御棒の全引き抜き位置から全挿入までに約18秒以上が必要であった。異常発生時の停止機能としては、遅すぎたのである。なお、わが国で用いている軽水炉では、この値は2〜4秒である。 事故当時のRBMK炉では制御棒下端に黒鉛ディスプレーサーが取り付けられており、これが炉心最下端部まで達していなかったため、制御棒が挿入され始めると、まず黒鉛ディスプレーサーと炉心最下部との間にある水が排除されるため、正の反応度が印可される。この減少をポジティム・スクラムと呼んでいる。黒鉛ディスプレーサーは、制御棒を引き抜いた状態での中性子経済を良くすることを目的としていたが、黒鉛の量を節約するため、上端部および下端部がカットされていたものと理解されている。図4にポジティム・スクラムの発生機構を示した。日本の解析結果では、この正の反応度投入は、定量的にほとんど無視できることが判明した。アバギャン報告では、「クルチャトフ研究所を含む3つの研究所で実施された3次元の核熱水力解析では、いずれの研究所でも十分には出力の暴走を再現することが出来ず、事故を再現するには1.3ドル程度の正の反応度の添加が必要としていた。」 3.事故の概要 4号機では1986年4月25日に保守のため原子炉の停止が予定されていた。この機会に外部電源が切れた場合、タービン発電機の回転慣性エネルギーを利用してどれだけ主循環ポンプと非常用炉心冷却系の一部を構成する給水ポンプに電源を供給する能力を調べる試験を実施しようとしていた。計画では、この試験を熱出力が100万kWないし70万kWに下ったところで行うことになっていた。 1986年4月25日深夜1時6分に出力低下を開始し、同日13時5分に定格熱出力が半分の160万kWまで下った。ここで2台あったタービン発電機No.7を送電線から切り離し14時00分にECCSを多重の循環ループから切り離した。試験開始の予定出力にもっていくのに高出力領域での制御方式から低出力領域の制御方式に切り替える手順で目標値の設定を忘れるというミスがあって、原子炉熱出力は26日0時28分に3万kW(中性子出力はゼロ)まで下ってしまった。このため、予定の70万kW以上に戻すため、制御棒をさらに引き抜いた。しかし炉内に蓄積されたキセノンにより中性子が吸収された。0時41分にタービン発電機No.8を、空転運転に伴う振動を低下させるため送電線から切り離し、1時03分にやっと原子炉出力を20万kWに戻し出力は安定した。このあと、各ループの予備ポンプを投入して試験に備えた。この結果、炉心での冷却材流量の増加が蒸気ボイドの減少につながり、気水分離器の水位および冷却回路の圧力が不安定となった。そこで、気水分離器の水位と圧力に関する原子炉保護信号をバイパスして効かなくした。1時22分30秒、運転員は計算機のプリントアウトから反応度操作余裕が規定の30本よりもはるかに低い6〜8本であることを知ったが、原子炉を停止しなかった。試験がうまくいかなかったときに繰返して試験が可能なよう、タービン2台が止ったときに原子炉が自動停止する安全保護信号をバイパスし無効化した。 26日1時23分04秒、No.8タービン発電機への蒸気を止めて4台の主循環ポンプのコーストダウンを開始し、試験を始めた。この結果、8台のポンプの内4台が回転数を落し始め、流量低下とともに炉心ボイドの増加を招き、正の反応度フィードバック特性によって原子炉の出力が上り始めた。 同日1時23分40秒、運転員は原子炉の緊急停止ボタン(AZ-5)を押したが、出力は上昇し続けて、事故となった。後での計算によると、1時23分44秒、原子炉出力は定格の100倍に達したと推定されている。 出力暴走の結果として、2回の爆発音が約2〜3秒の間隔をおいて聞かれた。1度目の爆発は出力の急激な上昇によって、燃料が溶融飛散して圧力管に当るとともに冷却材の水に接触して水蒸気爆発を起したものと見られ、2度目の爆発音は水-ジルコニウム反応でできた水素と空気の混合気体の爆発によるものとされている。炉心の上部にある構造物は、2気圧で持上がり、10気圧では接続配管を引きちぎって持上がるといわれている。図5に破壊された4号原子炉建屋内の状況を、図6にRBMK-1000原子炉建屋の内部構造透視図を示した。 爆発の結果、炉心を構成する物質その他のものが多量に放出された。特に高温の黒鉛が飛び散ったため、各所で火災が発生し、タービン建屋の屋根のアスファルトの火災など消火に苦労したといわれる。消火作業で多数の犠牲者がでた。運転員と消防士の双方で計31名が亡くなった。 炉心の壊れたところでは、黒鉛の燃焼が続いたため、ヘリコプターによって、炭化ホウ素40トンをはじめ、石灰岩、鉛、土砂等計約5000トンを投下した。 図7に3、4号炉の原子炉建屋、共通建屋、タービン発電機建屋の垂直断面図を、図8に3、4号炉の原子炉建屋、共通建屋、タービン発電機建屋の水平断面図を示した。図9、図10、図11は、原子炉3、4号炉の破壊された状況を、図12は、1986年4月29日と5月8日における米国衛星写真の撮影結果を示した。図13は汚染除去剤を散布中の軍用ヘリコプターの写真である。またなお、図14に1、2号炉の原子炉ホール内部の写真を示した。 放射性物質の放出量は、事故後10日の1986年5月6日の時点に半減期補正した値に希ガスが約5000万キュリー、それ以外のよう素131等が3000〜5000万キュリーとされている。また燃焼した黒鉛の量は、約250トンと見積られている。 4.事故後にRBMK炉の事故再発防止策としてとられた改善策 事故後、旧ソ連はこのRBMK型原子炉の欠点を認め、同じような事故の再発防止策として次に述べる改善等をとった。 (1)制御棒引き抜き上限の設定 (2)反応度操作余裕の増加 30本→90本 (3)循環ポンプ キャビテーション計の設置 (4)緊急停止信号を発信する反応度操作余裕計算システム (5)運転員訓練の強化と管理制度の改善 (6)長期的対策の開発:燃料の濃縮度を2% から2.4%にあげる。および緊急停止時間約2秒の制御棒の開発。 <図/表> 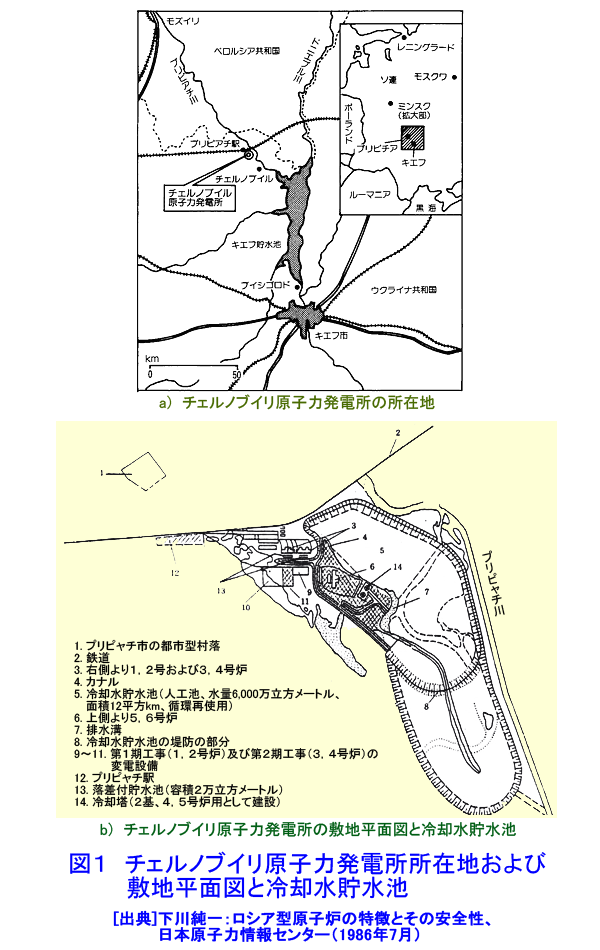
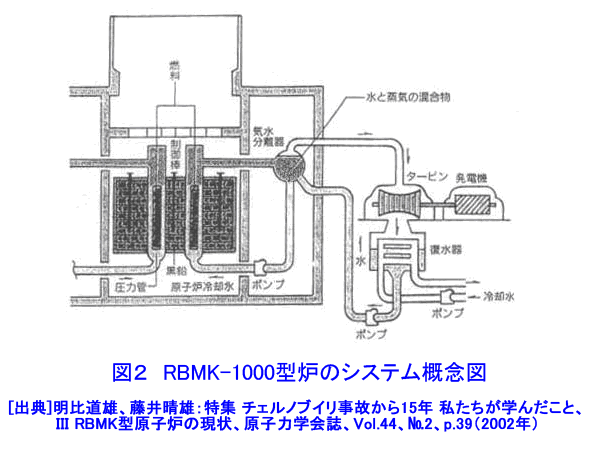
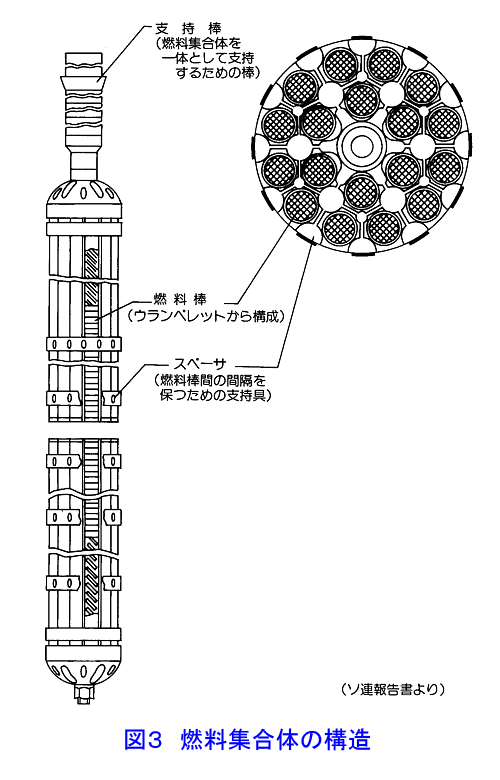
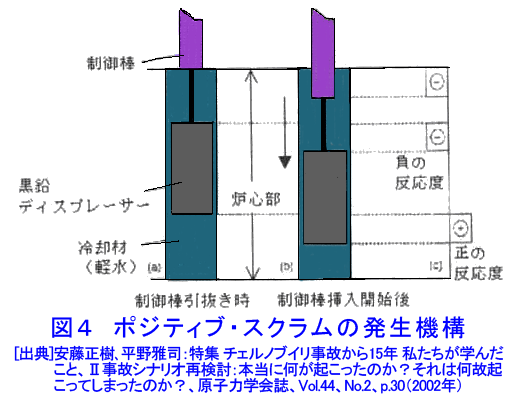
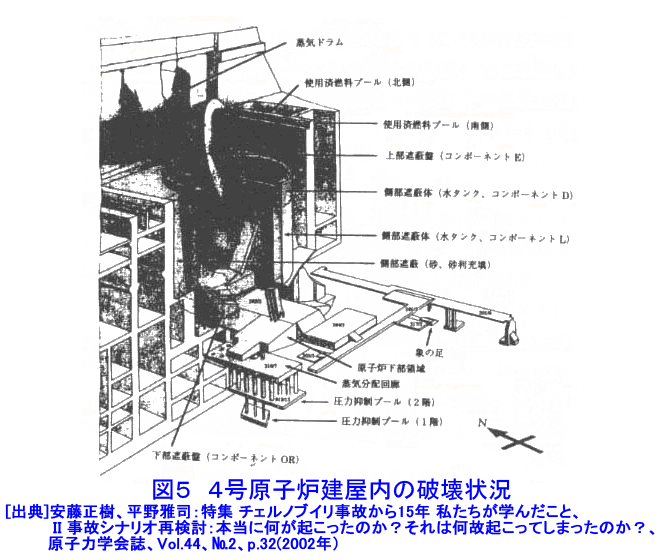
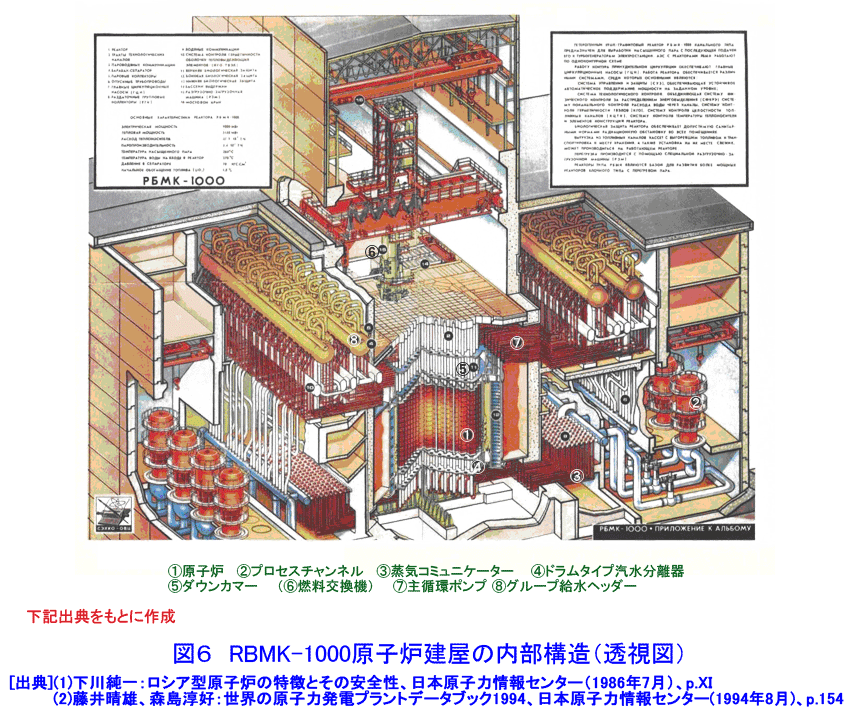
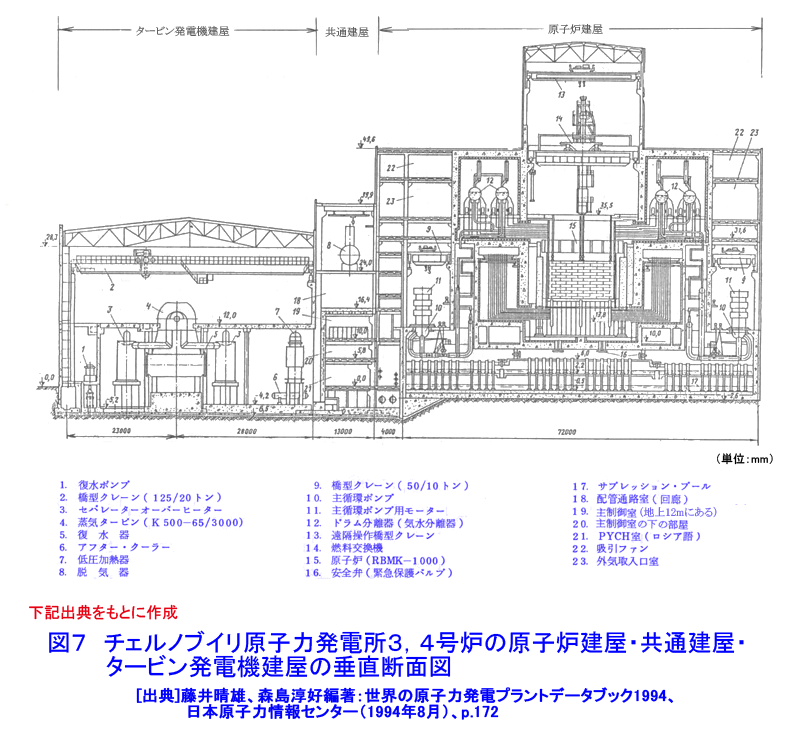
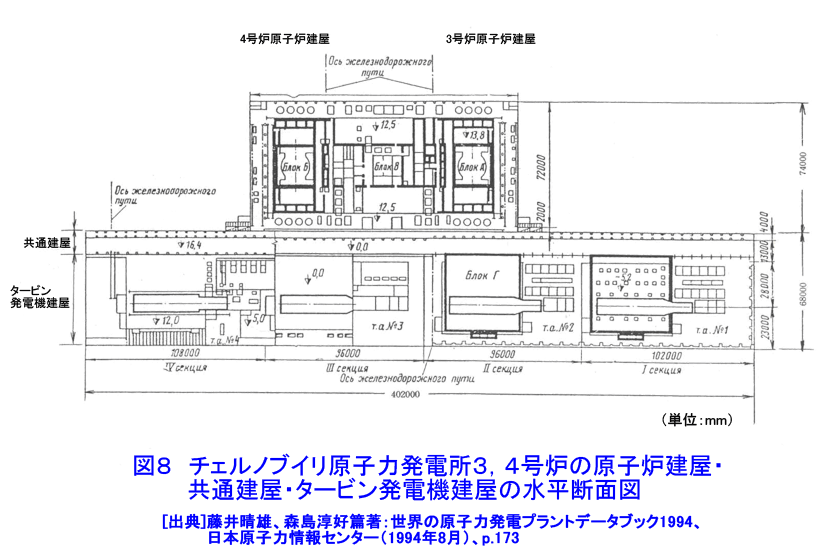
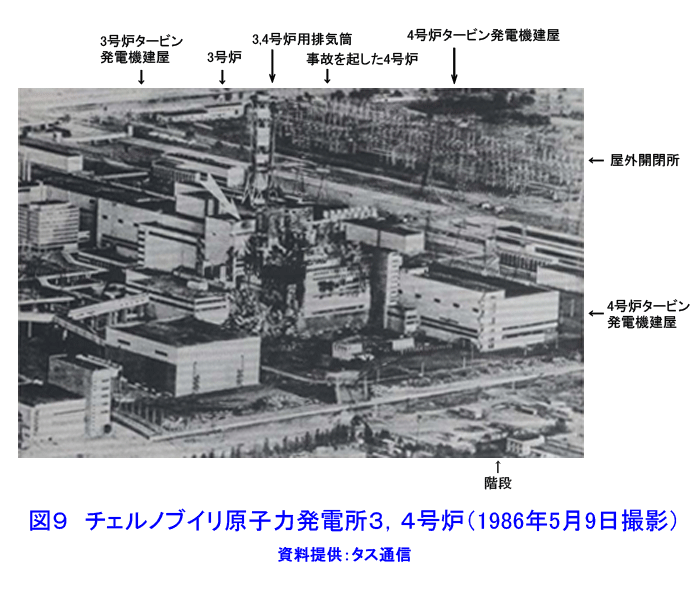
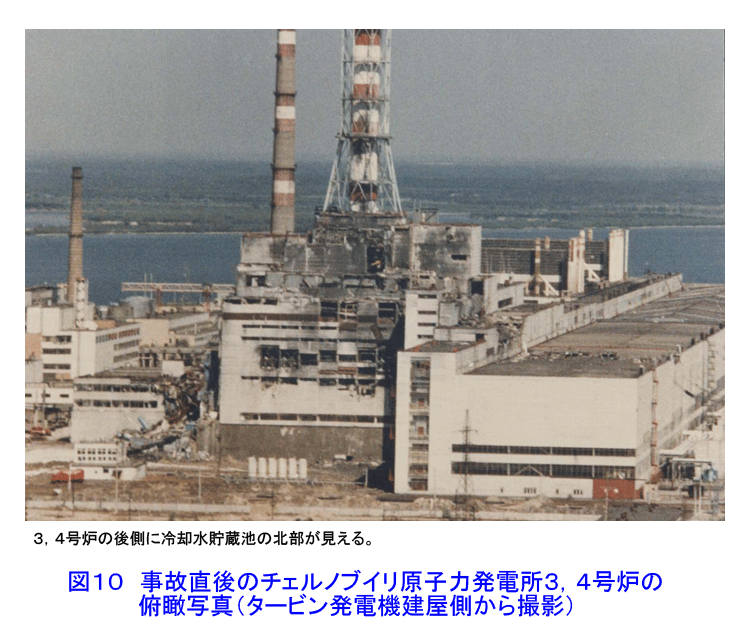
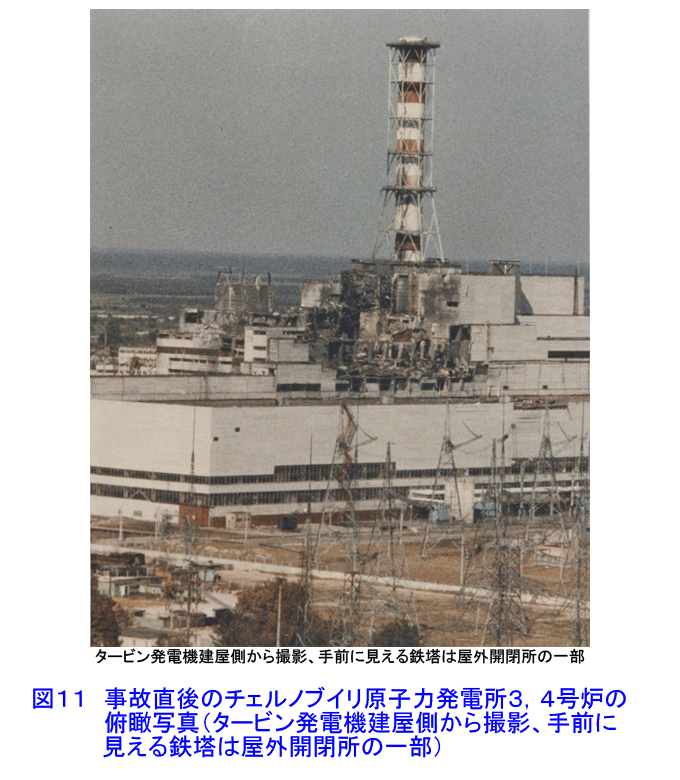
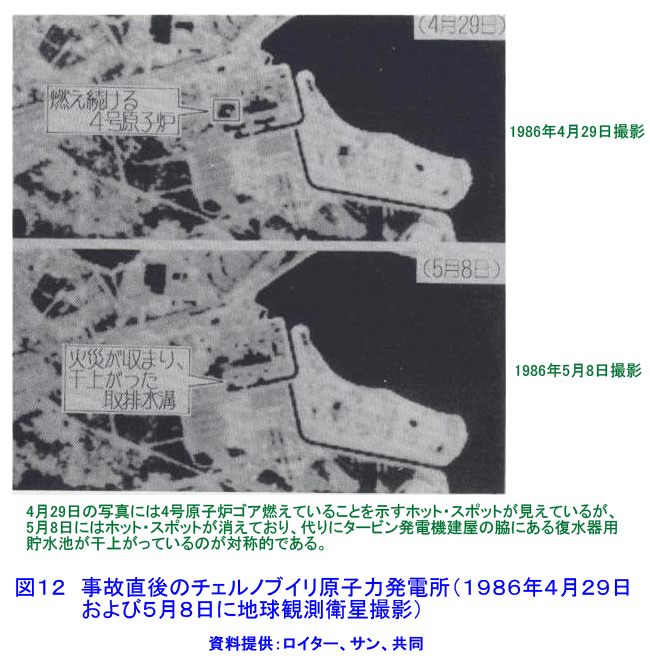

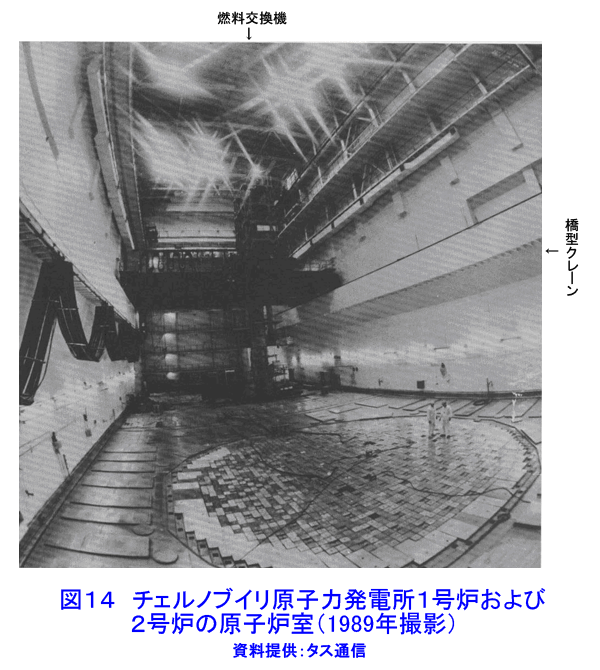
<関連タイトル> チェルノブイリ原子力発電所事故の経過 (02-07-04-12) チェルノブイリ原子力発電所事故の原因 (02-07-04-13) チェルノブイリ事故から20年 (02-07-04-20) 大気圏内核実験当時の体内放射能とチェルノブイリ事故後の体内放射能 (09-01-04-09) チェルノブイリをめぐる放射線影響問題 (09-01-04-10) チェルノブイル事故による健康影響 (09-03-01-06) 旧ソ連チェルノブイルから10年−放射線影響と健康障害−(OECD/NEA報告書) (09-03-01-07) チェルノブイリ事故による放射線影響と健康障害 (09-03-01-12) チェルノブイリ事故による死亡者数の推定 (09-03-01-13) 国際チェルノブイルプロジェクト (13-01-01-07) <参考文献> (1)原子力安全委員会編:原子力安全白書、昭和61年版(1987) (2) 安藤正樹、平野雅司:特集 チェルノブイリ事故から15年 私たちが学んだこと、II 事故シナリオ再検討:本当に何が起こったのか?それは何故起こってしまったのか?、原子力学会誌、2002年2月号 (3)明比道雄、藤井晴雄:特集 チェルノブイリ事故から15年 私たちが学んだこと、III RBMK型原子炉の現状、原子力学会誌、2002年2月号 (4)Atomic Science and Technology in USSR,I.D. Morokhov et al,Moscow Atomizdat,1977 (5)Chernobyl Nuclear Electric Power Station: Reactor RBMK-1000 by Ministry of Power and Electrification (6)Construction of Atomic Electric Power Station,Moscow Energija 1979,Second Turn of Chernobyl Nuclear Power Station,Energy Construction,April 1981 (7)下川純一著:ロシア型原子炉の特徴とその安全性、日本原子力情報センター(1986年7月) (8)藤井晴雄、森島淳好篇著:詳細 世界の原子力発電プラントデータブック1994、日本原子力情報センター(1994年8月)
|

