|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
1986年4月26日午前1時23分(日本時間同日6時23分)、ソ連(現在はウクライナ共和国)のチェルノブイリ原子力発電所4号機(黒鉛減速軽水冷却沸騰水型炉−RBMK型100万kW)で、タービン発電機の慣性運転により主循環ポンプと給水ポンプに電源を供給する実験中に事故が発生した。事故後、約10日間にわたり原子炉から放射性物質を放出したが、放出された核燃料物質は3〜4%で大半は炉内に存在する。原子炉の破壊後、燃料は崩壊熱等により過熱溶融し、炉内から下部遮蔽盤を溶融貫通し、原子炉下部で他の物質と溶融混合して、そこから垂直方向、並びに水平方向に流出し、固化して溶岩状燃料含有物質を形成した。事故終息のため実施されたヘリコプターからの物質投下等の対策は、あまり効果がなかったとの見解も出されている。炉内の燃料についてはすべてが確認されたわけではない。黒鉛の挙動については、あまり調査が進んでいない。いまだ解明すべき点が残されている。 <更新年月> 2007年12月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1986年4月26日、旧ソ連(現ウクライナ共和国)のチェルノブイリ原子力発電所4号炉で原子力の歴史上未曾有の事故が発生した。この事故の少し前の1985年にゴルバチョフが共産党書記長となり、ペレストロイカ(改革)とグラスノスチ(情報公開)を掲げて体制の変革に着手した。現在の目で見ると、少なくともチェルノブイリ事故当時は、体制変化の兆しは様々なところに現れていたが、それは不徹底で不完全なものだった。チェルノブイリ事故発生後4か月目の1986年8月25〜29日、ソ連はウィーンのIAEAで開かれたチェルノブイリ事故に関する国際会議で、当時のソ連政府の専門家から事故時のプラントデータや解析結果を含む事故の詳細を報告した。この事故以前は、原子力に限らず、ソ連国内での事故や災害について、国内外に公表されたことは極めて希だった。ソ連産業原子力安全監視委員会は、1991年1月に同委員会の科学技術評議委員会から報告書が公開された。これは、同委員会議長の名前から「シュタインベルグ報告」とよばれており、ウィーン会議報告(1986年8月に開催されたIAEA主催の国際会議の報告)以後に出された報告書の中で最も重要なものの一つと考えられている。表1-1および表1-2にシュタインベルグ報告に示されている事故の経過を示した。これはアバギャン報告のものとほぼ同一である。また何か所か新しい情報が加えられたり、変更が加えられたりしているが、全体としてウィーン会議のものと大きな相違はない。また、元チェルノブイリ原子力発電所に勤務し、1986年当時、ソ連電力電化省に勤務していた原子力発電の専門家グレゴリー・メドベージェフも「チェルノブイリ・ノート」(1989年刊)に事故当時の現場の状況を克明に書いている。 1.事故の経過 1.1 事故発生までの経過 チェルノブイリ4号炉は、保守のため1986年4月25日に停止することになっており、発電所への外部電源が無くなった場合に、タービン発電機の回転による慣性エネルギーを利用して、主循環ポンプと非常用炉心冷却系の一部を構成する給水ポンプに電源を供給する能力を調べる予定となっていた(注:参考文献4、p.13によれば、このような試験は多くのRBMKから提案されたが、実験の危険性を考慮して全て却下された。しかしチェルノブイリ原発指導部はこの実験に同意した。)。 3、4号炉の原子炉建屋、共通建屋、タービン発電機建屋の垂直断面図は、ATOMICAタイトル「チェルノブイリ原子力発電所事故の概要 <02-07-04-11>」の図7を、3、4号炉の水平断面図は、同タイトルの図8を参照されたい。図1にアバギャン報告に示された解析結果による4号炉の原子炉出力の変化を示した。 4月25日01時06分より全熱出力3,200MWt(320万kWt)から出力の降下を開始し、03時47分に原子炉熱出力は1,600MWtになった。04時13分から12時36分の間、原子炉熱出力を1,500MWtに保持し、4号炉に接続されている50万kWe(500MWe)容量のNo.7、8タービン発電機の振動特性を順次測定した。13時05分にタービン発電機No.7を送電網から切り離し、14時00分に試験に備えてECCS(緊急時炉心冷却系)を多重の循環ループ(MFCC)から切り離した。また14時00分に、キエフ給電指令所から50万kWeの発電を続けるよう要請され実験の実行は延期された(注:キエフ給電指令所は、チェルノブイリ4号炉の8号発電機(50万kWe)を遮断すると、他に代替電源を見付けることが出来なかったため、4号炉による運転継続を要請したものと思われる)。 23時10分にキエフ給電指令所が4号炉の出力低下を認めたので、運転員は出力低下を再開した。4号炉は、実験計画の延期を要請され50%電気出力の運転が続いたため、炉心にはすでにキセノン(Xe:ゼノン)が蓄積し、電気出力の維持、制御が困難な状態に陥った。4月26日00時05分に原子炉熱出力は720MWtで安定な出力降下を継続し、00時28分の原子炉熱出力は500MWtで局所出力制御系から低出力レンジ自動出力制御系1および2に切り換えたところ、移行中に予定されていない出力低下が起こり、熱出力が30MWtに(中性子出力ゼロ)となった。4〜5分後に熱出力は上昇を開始した(注:参考文献4、p.38、運転員は制御棒を引き抜き出力上昇を開始)。00時34分〜00時59分の間に、汽水分離器の水位異常、運転員が2台のタービン発電機停止による保護信号をブロック、タービン発電機No.8の空転運転に伴う振動を低下させるため送電線から切り離す操作をして、01時03分にやっと原子炉熱出力を200MWtまで上昇し安定化した。そこで、試験を強行することとして、計画に従い01時03分、01時07分に運転中の各ループ3台(計6台)の主循環ポンプ(Main Circulating Pump:MCP)に加え、各ループ1台の主循環ポンプ(7台目および8台目)を起動した。この結果、炉心流量が増加してボイド率(気ほう率)が減少した。すなわち、炉心でのボイドつまり蒸気量が減少し、ボイドによって押し上げられていた汽水分離器での水位が下がるとともに、その圧力が下がった。原子炉出力を維持するために自動制御棒が上限まで上昇する(注:引き抜かれること)とともに、運転員は手動制御棒を引き抜いて原子炉出力を制御しなければならない状況に陥った。このため、反応度操作余裕(ORM:Operational Reactivity Margin)が大きく低下した。01時19分39秒および01時19分44秒〜に「制御用制御棒−1の完全引き抜き」信号を発信した。 01時23分04秒に、運転員は実験対象としていた第8タービン発電機の止め弁を閉鎖して蒸気を止めて実験を開始した。これにより、タービン発電機がコーストダウン(回転数の減少)を開始し炉心流量が減少し始めた結果、炉心のボイド率が上昇し出力が増加し始めた。その30秒後の8月26日01時23分40秒に緊急保護系(EPS:Emergency Protection System)-5ボタン(ロシア語で“AZ-5”ボタン:第5種緊急防護ボタン)を押した。 この点に関し、ウィーン会議では、「運転員は出力の上昇を見てAZ-5ボタンを押したが制御棒の挿入速度が遅く、出力上昇を抑えられなかった」と報告されている。ただし、わが国の原子力安全委員会の下部機関であるソ連原子力発電所事故調査特別委員会によるソ連原子力発電所事故調査報告書(1987年9月9日付け)によると、「ソ連の発表によれば、運転員の証言からAZ-5ボタンを押した他の動機として(1)試験開始後40秒近くが経過し、データから見て試験が成功だったと判断したため、あるいは(2)自動制御棒が次々に挿入される事態になったのを見て原子炉の緊急停止が必要と判断したため、の2つの可能性を挙げているが、あいまいな点もあるとしている」と記載されている。すなわち、運転員がどのような状況でなぜAZ-5ボタンを押したのかについて、ウィーン会議ですでに議論があったことが示されている。シュタインベルグ報告にはこれに関する明確な記載がなく、未だに明確にはなっていない。しかし、参考文献4、p.53、55には、緊急事態と判断した当直班長が第5種緊急防護ボタン(AZ-5ボタン)を押したと書いてある。 表1-1および表1-2に通常運転から事故発生までの詳細な経緯と運転員の具体的な行動を追記した。(注:わが国の原子力安全委員会は原子力安全・保安院とともに2012年9月18日に廃止され、原子力安全規制に係る行政を一元的に担う新たな組織として原子力規制委員会が2012年9月19日に発足した。) 1.2 事故後の燃料の様子 事故後の4号炉全体の俯瞰写真を図2に示した。また、ATOMICAタイトル「チェルノブイリ原子力発電所事故の概要 <02-07-04-11>」の図9、図10、図11にも示されている。原子炉内のボーリング調査等を通じて、炉内の燃料の様子が明らかになった。また事故後の4号原子炉建屋内の破壊状況が同タイトルの図5に、また事故前の内部構造(透視図)が同タイトルの図6に示されている。事故後に炉心にあった燃料と黒鉛、下部遮蔽盤、また溶岩状燃料含有物質(LFCM:Lava-like Fuel-Containing Materials)がどのように生成し、原子炉の炉心下部に流れたルートと説明を図3に示した。 1.3 事故の進展の様子 これらの知見をもとに事故の経緯をまとめると次のようになる。 原子炉の暴走後、2回の爆発が起こり、建屋の上半分が完全に破壊した。建屋の外に高温の燃料や黒鉛が放出され、機械室の屋根など原子炉施設内の30か所以上で火災が発生した。4月26日1時30分、プリピアチ市およびチェルノブイリ市から消防隊が派遣された。消防士達の活躍の結果、火災は同日午前5時までに鎮火した。その後、原子炉内で黒鉛火災が始まった。この黒鉛火災を鎮火し、継続する放射能放出を抑え、また、再臨界を防止するため、4月27日よりヘリコプターによって原子炉にホウ酸40トン、燃焼抑制用の石灰岩800トン、遮蔽および放出抑制用の鉛2,400トン、フィルター効果のため粘土と砂を大量に投下した(上記タイトルの図13参照)。これらの投下によって、一旦は放射性物質の放出が抑制されたが、閉塞状態のため内部で温度上昇が起こり、再び放射性物質の放出が増大した。 原子炉からの放射能の放出は、4月26日の事故開始当時の大量放出後、一時減少したが、5月2日から再び増加し始めた。溶融燃料と水の接触を避けるため、5月3日に圧力抑制(サプレッション)プールの水抜き作業を実施した。また、5月5日には、溶融燃料の冷却のため、原子炉下部空間へ窒素注入を開始した。放射能の放出は事故から9日目の5月5日頃急激に減少し事故は一応終息した。(注:これら対策の効果は、1.6に記載) 1.4 原子炉の破壊について 1回目の爆発は、ウィーンの報告およびわが国の安全委員会報告では、「水蒸気の急激な発生による加圧破損」と推定している。2回目の爆発については、わが国の安全委員会報告では「なお不明な点が多いが、水-ジルコニウム反応等の化学反応により生じた可燃性ガスの空気との混合による熱爆発の可能性が高い」としている。現在、原子炉の破壊過程は、反応度事故に起因する燃料の微細化⇒冷却材の加熱、蒸発⇒圧力管内の圧力上昇⇒圧力管破損⇒上部遮蔽盤と炉心上部との間の空間の圧力上昇⇒上部遮蔽盤の持ち上がり、圧力管の破断⇒水素爆発等による建屋破壊といった過程を通ったと考えてよいであろう。この2回の爆発から判るように原子炉建屋の上半分が完全に破壊した。IAEAのINSAG-1報告書(INSAG: International Nuclear Safety Advisory Group)は「少なくとも黒鉛の10%(250トン)が燃焼した」としており、その後調査は進んでいない。 1.5 事故の継続と終息過程について ウィーン報告に示されるように、原子炉の破壊後も放射性物質の放出が続いた。環境中に放出された燃料物質は、ソ連内外の研究データをもとに3.5±0.5%と推定されている。これをもとに希ガス、揮発性核種は多く放出されたが、大部分の燃料は炉内に留まっていると考えられる(表2)。放射性物質放出の時間的経過は、図4に示すようないわゆるバスタブ曲線となっており、次に示す4段階に分けられる。 ・第1段階:事故発生時の激しい初期の放出(核種の組成は、燃料内の核種組成にほぼ一致している。ただし、I、Te、Cs等の揮発性核種および希ガスは多い。) ・第2段階:4月26日から5月2日までの放出量が減少した期間(核種組成は、燃料内の組成にほぼ近い。) ・第3段階:放出量の急激な増加(事故初期には、揮発性成分のうち特にIの放出が多い。その後は、再び燃料内の核種組成に近づいた。) ・第4段階:放出量が急激に低下した。 表3-1および表3-2に事故の継続と終息過程を、図5にA. R. Sichによる暴走後の事故シナリオを示した。 1.6 事故時の事故影響緩和のために実施した対策への評価 ・事故直後、ヘリコプターから炉心へホウ酸、石灰石、鉛、粘土や砂を大量に投下したが、大部分は炉心に到達せず、炉心からの放射性物質放出抑制にはほとんど役立っていない。 ・5月6日以降に液体窒素を炉心に注入したが溶融燃料は窒素注入までに原子炉下部から水平に東側に最大約50m移動した黒色セラミックスで、そのほぼ先端に象の足状に固化した(図6参照)と考えられ、この段階で液体窒素を注入しても役立っていない。 ・原子炉下の蒸気分配回廊を通り、さらに下の2段のサプレッションプール下部まで落下した溶融燃料は軽石状(図7参照)になっているので水と接触したと考えられ、サプレッションプールの水抜きは役立っていない。 ・原子炉建屋基礎に熱交換器を設置する案については、溶融燃料が早い時期に固化していることが判ったため、計画は中止された。 2.原子炉の暴走以降の事故の進展過程のまとめ (1)事故後、約10日間にわたって放射性物質放出が継続したが、放出された燃料物質は3〜4%で、大半の燃料は炉内に存在する。 (2)原子炉の破壊後、燃料は崩壊熱等により過熱溶融し、炉内から下部遮蔽盤を溶融貫通し、原子炉下部で他の物質と溶融混合して、そこから垂直方向、並びに水平方向に流出し、固化して溶岩状燃料含有物質(LFCM)を形成した。事故終息のため実施されたヘリコプターからの物質投下等の対策は、あまり効果がなかったとの見解も出されている。ただし、炉内の燃料についてはすべてが確認されたわけではない。また、黒鉛の挙動については、あまり調査が進んでいない。いまだ解明すべき点が残されている。チェルノブイリ炉はRBMKと呼ばれる旧ソ連独特の型式ではあるが、事故により燃料が溶融した後は、型式を問わず共通するものがあると考えられ、さらに研究を進めていく価値がある。なお、図8は破壊された4号炉、図9は石棺建設中の写真である。 <図/表> 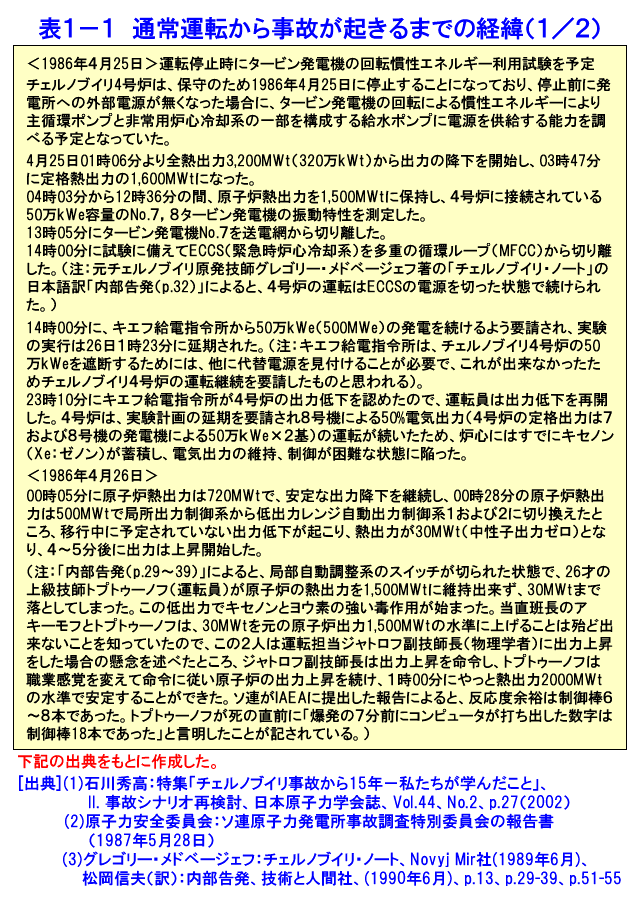
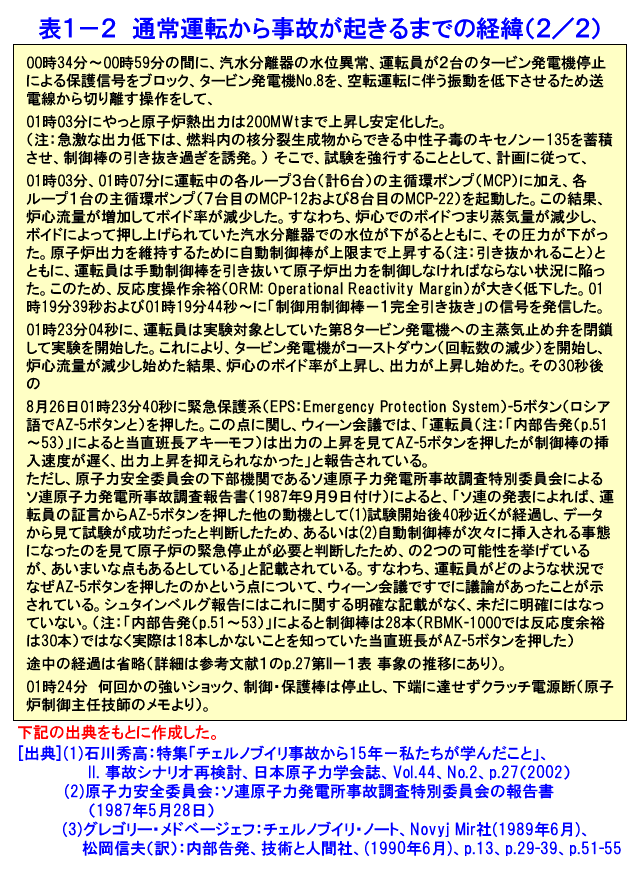
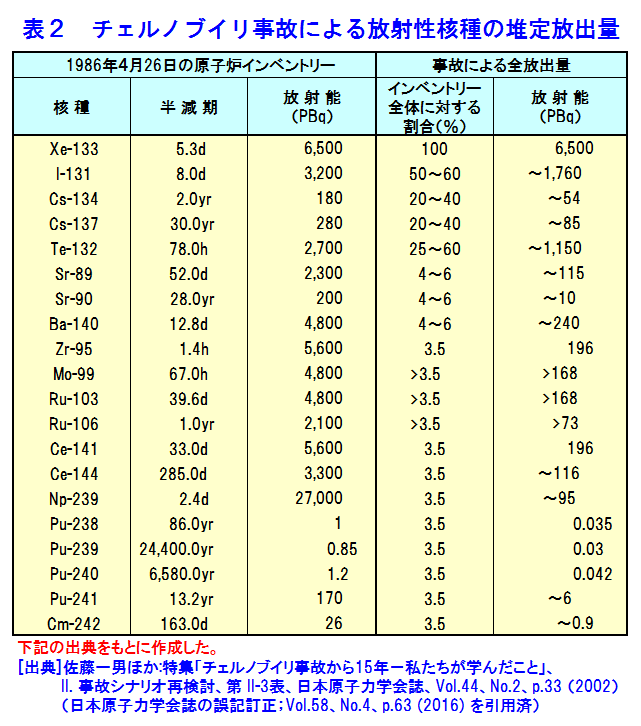
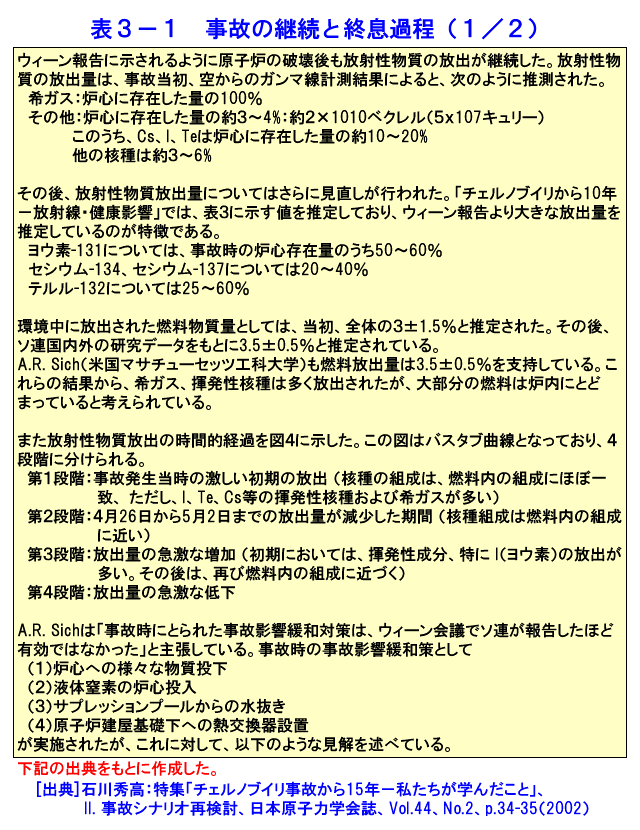
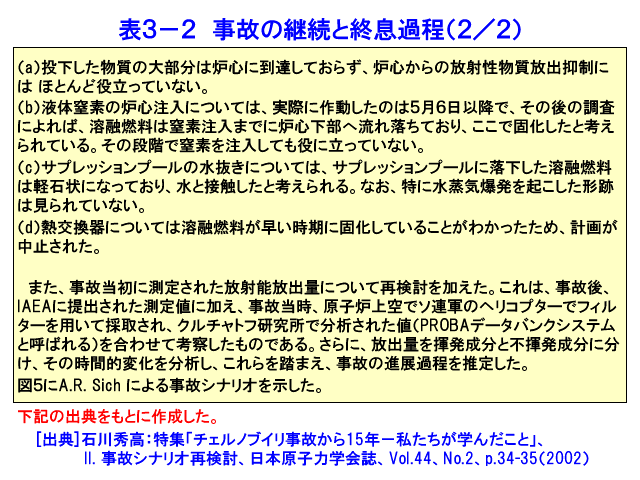
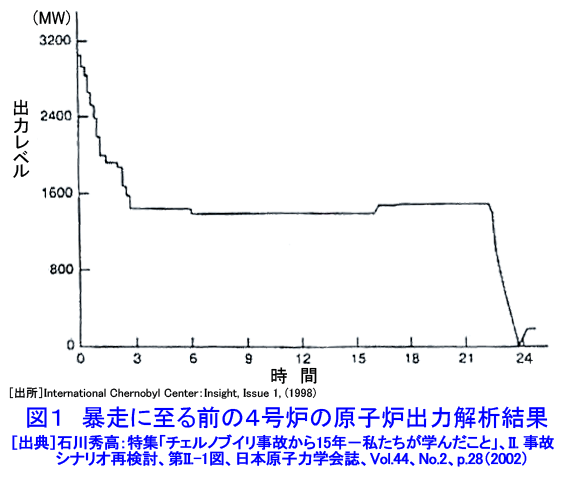
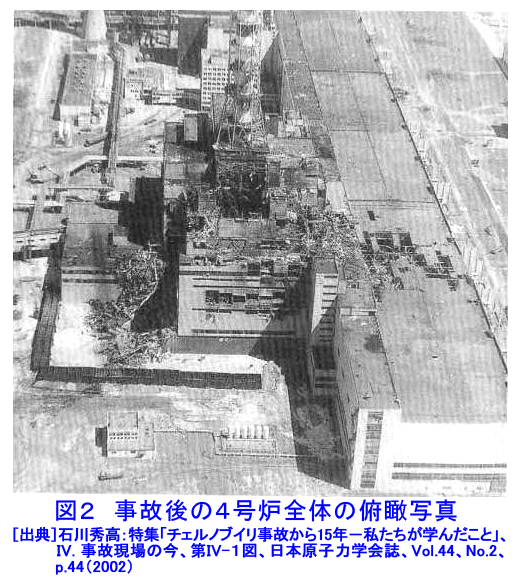
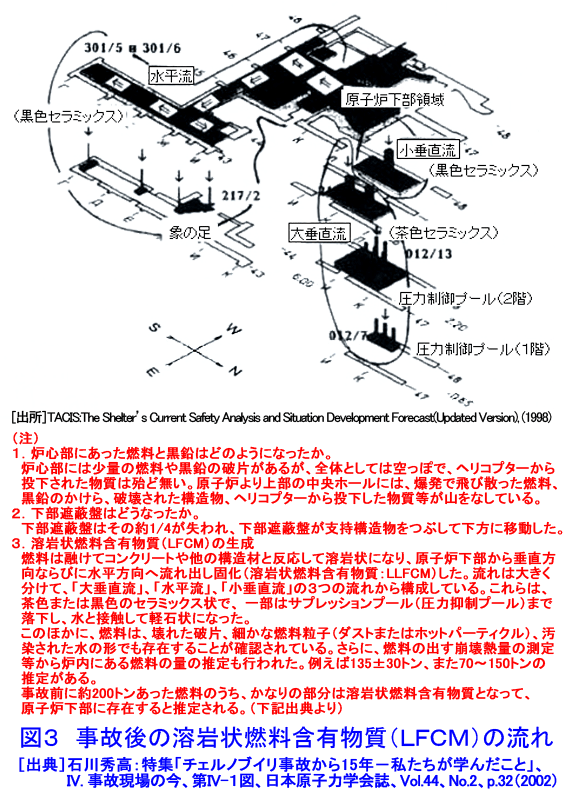
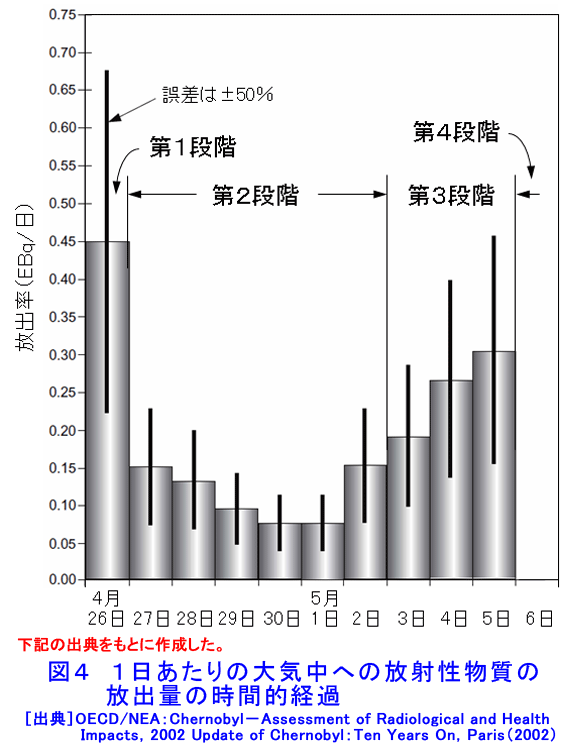
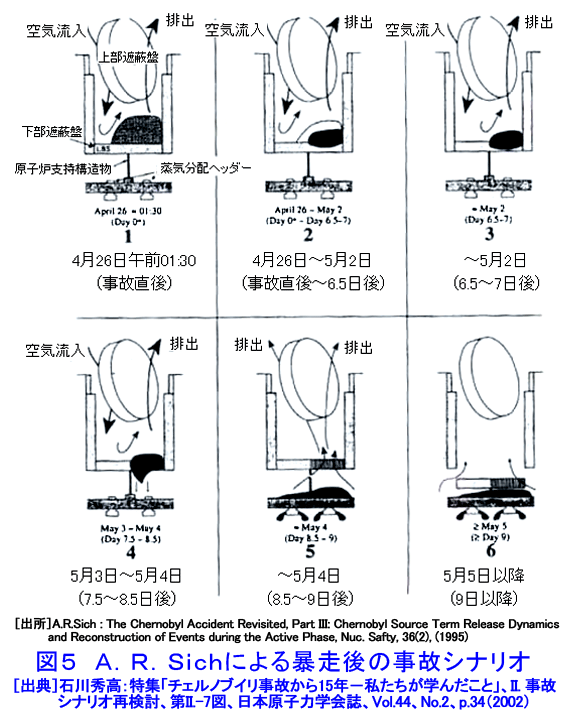


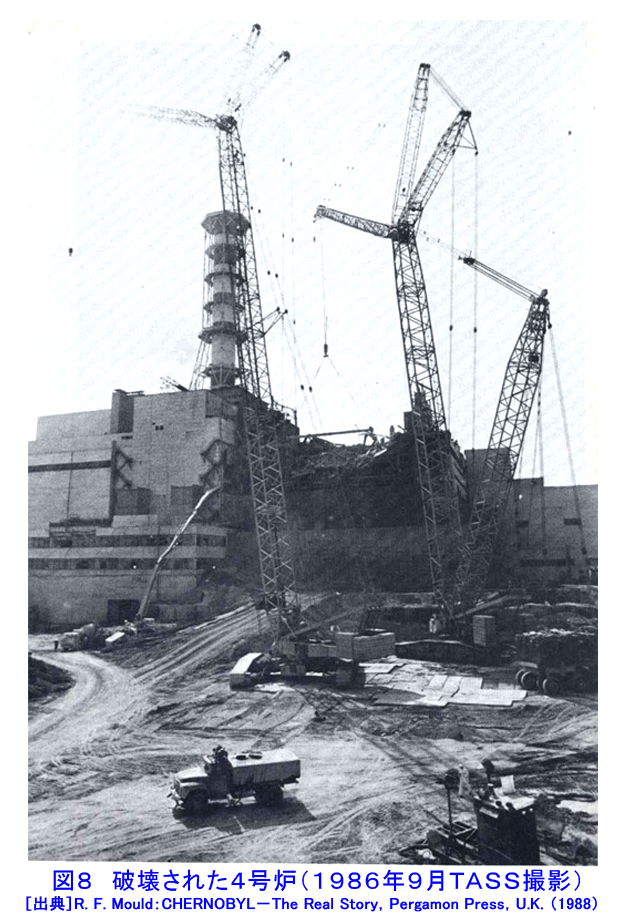
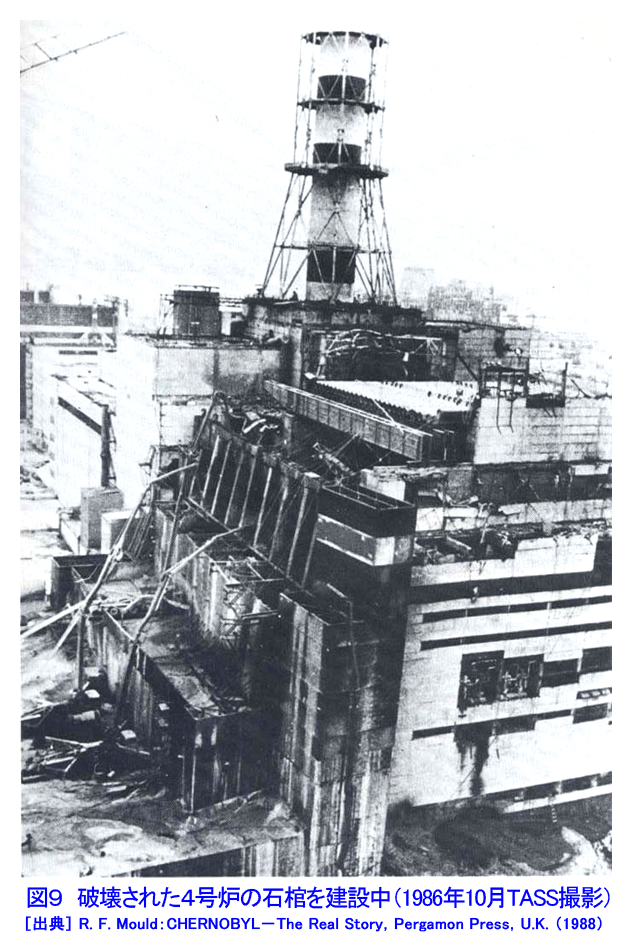
<関連タイトル> チェルノブイリ原子力発電所事故の概要 (02-07-04-11) チェルノブイリ原子力発電所事故の原因 (02-07-04-13) <参考文献> (1)石川秀高:特集「チェルノブイリ事故から15年−私たちが学んだこと」、II. 事故シナリオ再検討、p.26-36、IV. 事故現場の今、p.43-48、日本原子力学会誌、Vol.44、No.2(2002) (2)下川純一:ロシア型原子炉の特徴とその安全性、日本原子力情報センター(1986年7月、)p.XI (3)藤井晴雄、森島淳好:世界の原子力発電所プラントデータブック1994、日本原子力情報センター(1994年8月)、p.154、p.172-173 (4)グレゴリー・メドベージェフ:チェルノブイリ・ノート、Novyj Mir社(1989年6月)、松岡信夫(訳):内部告発、技術と人間社、(1990年6月)、p.13、p.29-39、p.51-55 (5)R.F.Mould:CHERNOBYL-The Real Story,Pergamon Press,U.K.(1988),p.104,p.111 (6)OECD/NEA:Chernobyl-Assessment of Radiological and Health Impacts,2002 Update of Chernobyl:Ten Years On,Paris(2002) (7)原子力安全委員会:ソ連原子力発電所事故調査特別委員会の報告書(1987年5月28日)
|

