|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
本報告書は、チェルノブイル事故に関して、OECD/NEA(経済協力開発機構/原子力機関)の放射線防護専門家の見解をとりまとめたものであり、事故による放射性核種の放出、被ばく線量評価、健康影響、得られた教訓等について述べられている。 <更新年月> 1998年03月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.放射性核種の放出、拡散及び沈着 チェルノブイル事故により、原子炉中に存在した放射性物質は、ガス、エアロゾル、細かな核燃料粒子といった形態で大気中へ放出された。放射性核種の推定放出量を 表1 に、1日当たりの大気中への放出量を 図1 に示す。外部へ放出された核種の割合は、事故時の炉心中の存在量に対して、希ガス(キセノン33)が100%、ヨウ素131が50−60%、セシウム、テルル等の揮発性の核種が20−60%、その他のストロンチウム、プルトニウム等の核種が数%と推定されている。大気中へ放出された放射性物質は、北半球全体へ拡散したが、地表への沈着量は放射性雲が通過した際の降雨の影響を強く受けたために、地域により大きな違いがみられた。旧ソ連邦におけるセシウム137による主な汚染地点を 図2 に、ヨーロッパにおける放射性雲の動きを 図3 に示す。 2.各国当局の対応 事故の規模と深刻さは、事故前に想定されていた原子炉事故を大きく超えたものであり、準備されていた基準や手続きも完全なものではなかった。このため、事故直後では、不十分な情報に基づき、必ずしも学識者の判断ではなく、不適切な対策がとられる傾向にあった。 旧ソ連邦国内では、チェルノブイル発電所近傍のプリピァチ市については、事故当日の4月26日遅くに避難が決定され、翌日には住民の避難が完了した。その後発電所から半径30km以内の住民の避難が行われ、合計13万5千人が避難した。30km圏外の汚染地域については、事故後数年間に複数の基準が適用され、最終的には、汚染地域からの移住の基準(セシウム137の地表面密度で1480キロ・ベクレル/m2)等が採用された。 旧ソ連邦以外の諸国では、事故による汚染が国境を越えて広域に及んだことから、各国で事故の影響に対する懸念が高まり、種々の対策がとられた。国際取引される食品に関する指針を 表2 に示す。これらの対策の決定には、放射線以外の社会・経済的、政治的、心理的要因などが大きな影響を与えた。 3.被ばく線量評価 事故により被ばくした集団は、(1)事故処理作業者、(2)30km圏内からの避難民、(3)旧ソ連邦の汚染地区の住民、(4)旧ソ連邦以外の国民、の4つに分類することができる。 事故処理作業者は、事故の際に消火作業に従事した発電所職員、消防士等数百人とその後の除染・復旧作業に従事した約80万人に分けることができる。前者のうち急性放射線症と診断された作業者の生物学的線量測定では、外部被ばく線量は数十人が数〜10グレイ以上と評価された。ロシアの除染作業従事者については国家登録がなされていて、被ばく線量が推定されている( 図4 )。後者については、緊急時作業ではないために被ばく線量管理が行われたが、数十から数百ミリシーベルトの線量を受けた。 発電所から30km圏内の住民13万5千人が、事故から数週間以内に避難した。プリピァチ市からの避難民のうち2千人の甲状腺中ヨウ素の測定が行われた。この結果に基づいた甲状腺の線量評価結果を 表3 に示す。3歳以下の乳幼児の平均が最も高く、1.4シーベルトであった。また、ウクライナの避難民が避難前に受けた全身線量は、平均15ミリシーベルトと評価された。ベラルーシの避難民の線量は、これよりいくぶん高かったと考えられている。 事故後、数十万人規模で甲状腺線量の測定が行われた。汚染地区住民で甲状腺線量が最も高かったのは、ベラルーシのゴメリ州の7歳以下の子供で平均約1シーベルトであった。牛乳中のヨウ素131が甲状腺線量の最大の原因であった。汚染地域では、1986年夏以降は汚染食品の規制が行われたため、その後は外部被ばくが主な被ばく経路となった。セシウム137の地表面密度が555キロ・ベクレル/m2を超える地域に居住する約27万人の1986年〜1989年の全身線量は、平均で40ミリシーベルトと評価された。 事故により放出された放射性ヨウ素及びセシウムは、北半球のほとんどの国で検出された。幼児甲状腺線量は、ヨーロッパで1〜20ミリシーベルト、アジアで0.1〜5ミリシーベルト、最初の1年間の全身線量は、ヨーロッパで0.05〜0.5ミリシーベルト、アジアで0.05〜0.1ミリシーベルトと評価された。 4.健康影響 事故による健康影響としては、急性の健康影響、ガン等の晩発影響及び健康に影響を与える心理的影響があった。 急性健康影響としては、事故後の消火作業、除染作業等に従事した作業者のうち、237人が急性放射線症と診断された。その中で28人が死亡し、他に火傷等で3人が死亡した。急性放射線症で入院した人の被ばく線量の評価結果を 表4 に示す。 晩発影響として重要なものは、汚染地域における小児甲状腺ガンの有意な増加であり、事故による放射線の影響であると考えられている。旧ソ連邦国内における小児甲状腺ガンの発生件数と発生率を 表5 に示す。しかし、甲状腺ガン以外のガン、白血病、先天異常等の増加は確認されていない。また、集団線量の評価結果からは、甲状腺ガンを除いたガンの発生率が有意に増加することはないと考えられている。 この他の影響として、特に旧ソ連邦国内の汚染地域住民の間に心理的ストレスが広がっていることがある。これには、放射線及び放射線影響の理解が困難であることによる恐怖や、政府、官僚に対する不信感、当時の社会的混乱等が関与したと思われている。 5.農業及び環境への影響 事故は、農業活動及び自然環境へも大きな影響を与えており、その影響は長期に及んでいる。 旧ソ連邦国内では、広い範囲の農地が汚染された。農畜産物中の放射性核種濃度を低減するために行われたカリ肥料、汚染されていない飼料の使用等の対策は、一定の効果をあげた。しかし、汚染レベルの高い地域では土地利用が制限されており、制限が撤廃される見通しはない。ヨーロッパにおいても事故後、セシウム137についての農畜産物の規制が行われたが、欧州連合各国の平均的な食品中レベルは、1990年末までに事故前のレベルに近づいた。しかし、一部地域では、規制を継続している。 環境への影響としては森林及び水域への影響が問題となった。森林は、放射性物質に対してのフィルタとして作用したために、農地よりも沈着量が多くなった。森林が猟獣肉、野イチゴ、キノコ等の供給源であることから、影響が懸念されている地域もある。また、汚染した木材製品の利用が長期間にわたり問題となると考えられている。水域の汚染による線量は、全被ばく線量の1〜2%を超えないと評価された。30km圏内では、ストロンチウム90による地下水汚染が長期の問題となっている。旧ソ連邦以外では、飲料水の問題はなかったが、一部の国では湖沼魚の規制が継続している。 6.潜在的な後遺症リスク 事故炉を覆う“石棺”と周辺に散在する廃棄物貯蔵施設は、潜在的な環境への放射性物質の放出源である。 石棺は、事故後、崩壊した原子炉を早急に閉じこめることを目的として建設された暫定的なバリアーと考えられている。石棺の建設後9年の時点では、全体的には健全であるが、長期的な耐久性が懸念されている。また、潜在的なリスクとして屋根や内部構造物の崩壊、臨界事故による放射性物質の放出、地下水を経由した長期的な放射性核種の漏洩等が考えられているが、最悪のシナリオでも30km圏外で再度重大な汚染が起こるとは考えられていない。 事故の復旧、除染作業で発生した放射性廃棄物と汚染機器の一部は、30km圏内に粘土層により地下水層と隔離されたコンテナ等で保管されているが、事故直後には、地下水層と隔離されていないトレンチに放射性降下物が埋められた。これらは、潜在的な地下水の汚染源であり、適切に処分されるまでモニタリングが必要である。 7.得られた教訓 事故では、緊急時についての準備、放射線防護についての欠陥が強調されたが、極めて特殊な事故であり、将来の緊急時計画の参考となるものではなかった。しかし、原子炉安全、介入基準、緊急時計画、緊急時医療等全ての分野について多くの教訓が得られた。これらの教訓の中で最も重要なことは、緊急時計画が1国のみでなく、国境を越えた計画とする必要性が証明されたことである。また、このことから、国際協力が促進され、放射線事故の早期通報・緊急時の援助に関する条約、国際原子力事故尺度、放射性汚染食品に関する国際協定等の国際協力及び情報交換の枠組みが整備された。 科学技術的側面では、原子力安全研究、シビアアクシデント研究に弾みを与えるとともに、急性健康影響と緊急時医療に対する知見を深め、放射性物質の環境中挙動、動植物への取込等の放射線生態学研究、環境モニタリング計画を活性化させた。 <図/表> 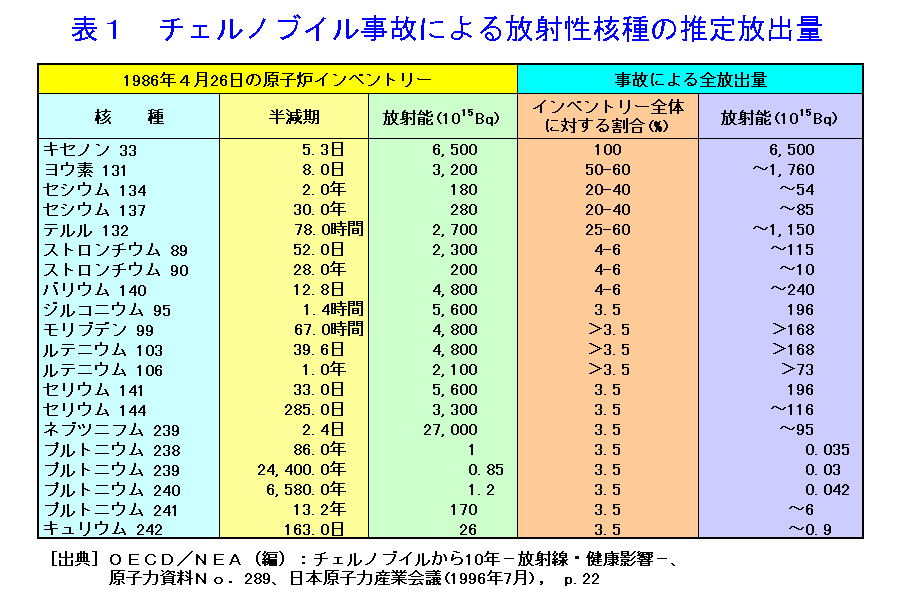
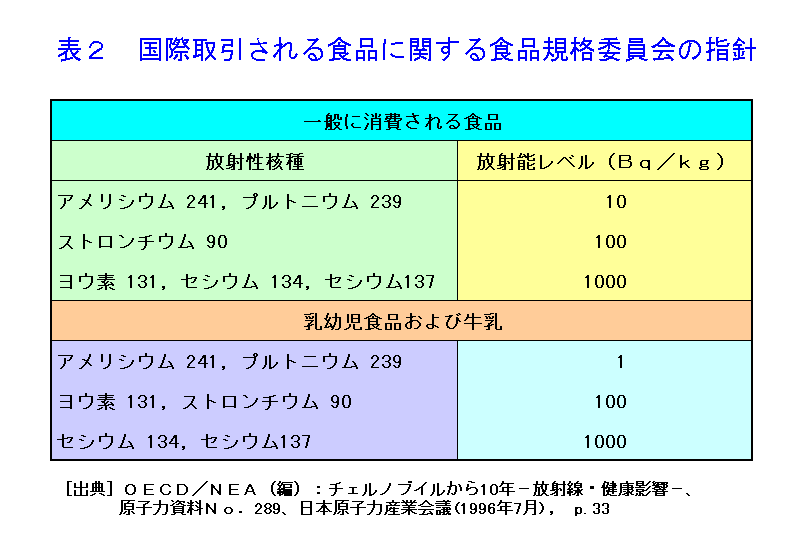
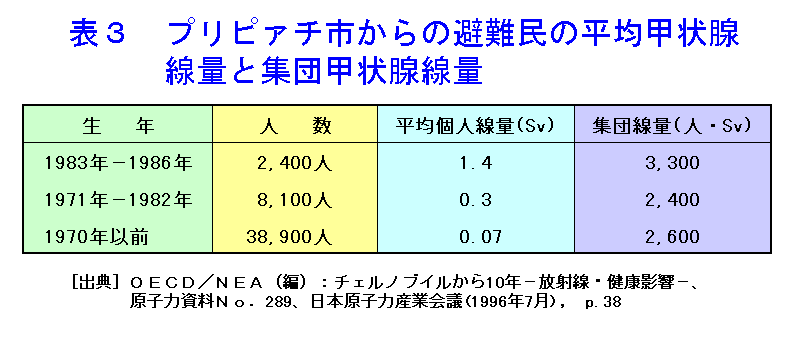
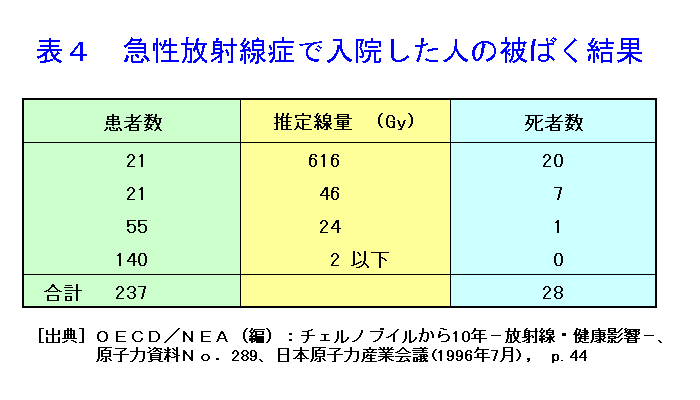
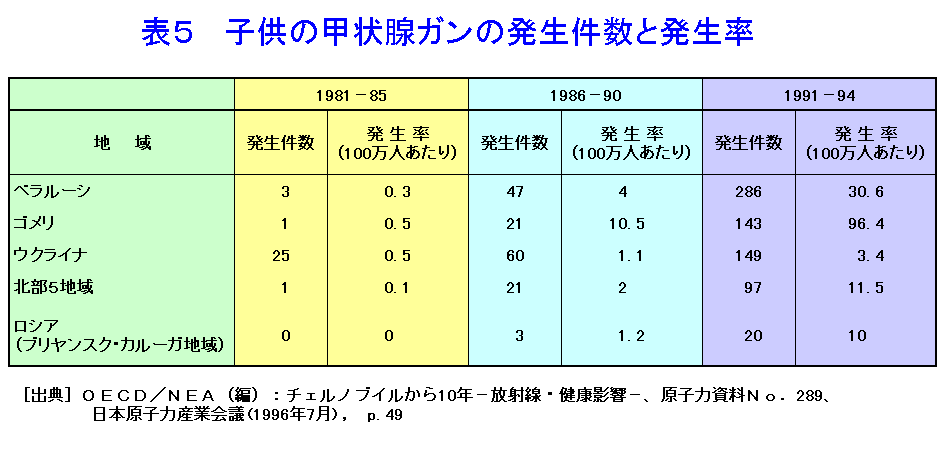
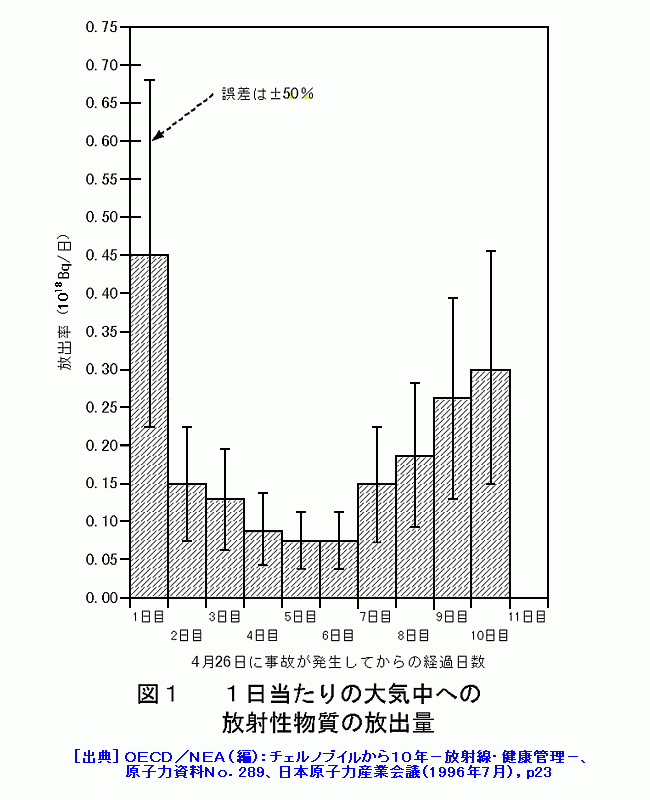
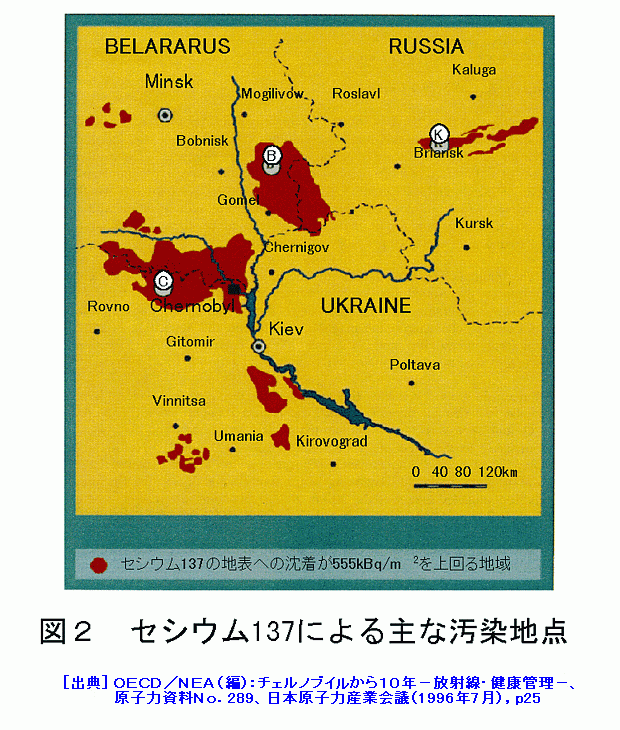
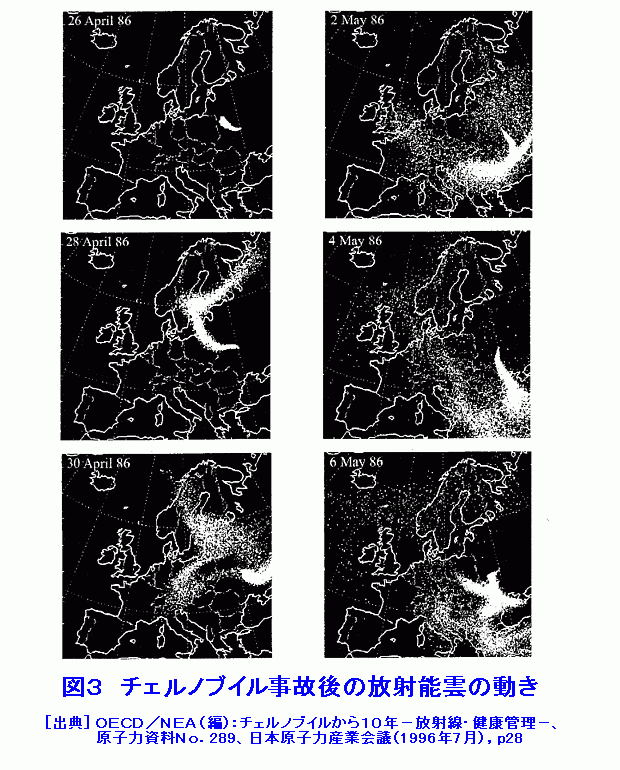

<関連タイトル> 日本の原子力防災対策の概要−考え方と体制 (10-06-01-01) 黒鉛減速沸騰軽水圧力管型原子炉(RBMK) (02-01-01-04) 大気圏拡散シミュレーションモデル (06-03-05-02) 飲食物摂取制限 (09-03-03-06) <参考文献> (1)OECD/NEA:Chernobyl Ten Years on Radiological and Health Impact,An appraisal by the NEA Committee on Radiation Protection and Public Health,OECD(November1995) (2)OECD/NEA(編):チェルノブイルから10年−放射線・健康影響−、原子力資料No.289、原子力産業会議(1996年7月) (3)科学技術庁(編):チェルノブイル事故後10年放射線による健康影響は?、放射線影響協会(1996.3) (4)健康・環境影響のアセスメントと防護対策の評価国際諮問委員会(編):国際チェルノブイル計画技術報告書、原子力安全研究協会(1993.8)
|

