|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
大気中に含まれる二酸化炭素やフロンなどの微量ガスにより、地表から宇宙空間に向かって放射される赤外線が吸収され、再び地表に放射されて大気及び地表が暖められることを地球の温室効果と呼ぶ。産業革命以来の人間活動の拡大によって、これら二酸化炭素などのいわゆる温室効果ガスが急激に増加し、温室効果が強まって気温が上昇する恐れがある。これが地球の温暖化問題である。地球の温暖化が既に起こりつつあることを示す相当数の証拠がある。温暖化による影響は、気候変動、海面上昇、生態系の破壊等、多岐にわたり、温暖化を防止するための方策を実施しなければ、2100年には約2℃の地球平均気温の上昇、約50cmの海面水位の上昇が予測される。 <更新年月> 2005年08月
<本文>
気候は通常・天気の平均と定義されている。ある期間、場合によっては特定の地域について、平均や変動を表す統計量として表現される。気候には、気候系内部の構成要素の相互作用に起因する大気の変動と外部からの強制力に起因する変動がある。気候系内部の構成要素には、大気、海洋、海氷、陸地や陸面(生物を含む)、積雪面積、陸氷、及び水分が含まれている。大気の組成の中で最も変動するのは水であり、水蒸気、雨滴、氷晶等いろいろの相に変化する(図1)。外部からの強制力と呼ばれるものには、太陽放射、地球の自転、地球と太陽の位置関係、海陸の分布やそれぞれの質量等の地球の物理的状態が含まれる。 地球に入射する太陽放射や出ていく赤外線放射の変化から生じる大気上端での正味平均放射量は「放射強制力」といわれている。人間活動の結果として起こる温室効果ガスの増加も外部からの強制力である。 全球のエネルギー平衡気候を駆動するエネルギー源は太陽からの放射である。このエネルギーの多くは電磁波スペクトルの可視光の部分にあるが、赤外線や紫外線も幾分かはエネルギー源として寄与している。大気圏外で太陽に面した1m2の面積に注がれるエネルギー量は毎秒約1370Wである。地球の断面積に入射したエネルギーを地球の表面積で等分すると、地球は球形をしており地球の半分は常に夜なので(図2)、大気圏外での平均入射放射量は1/4の342W/m2になる。空気分子や空中に浮かぶ小さい粒子(エアロゾル)、雲、あるいは地球表面は、入射したエネルギーの約31%を宇宙へ散乱したり反射してしまうので、残りの平均約235W/m2が地球の表面や大気を暖めている(図3)。入射エネルギーとバランスをとるためには、地球自身も同じ量のエネルギーを宇宙へ放射しなければならない。それは赤外線放射(熱放射)を出すことで行なわれている。ある表面から放出される赤外線放射の量は、温度とその表面の入射エネルギーの吸収率に関係している。入射エネルギーを完全に吸収する表面が赤外線放射エネルギー235W/m2を出すときの温度は約−19℃である。しかし地表面近くの年平均の全球平均気温は約15℃で、理論的に合わない。これは、大気最下層の地上から10〜15kmまでの対流圏の気温は高さとともに急激に減少するからで、ふつう中緯度では高さ5kmで−19℃の温度に達する。 大気圏外に出ていく赤外線放射の一部には、地表近くに放射源をもちながら大気中であまり減衰を受けないものがある。これは雲のない場所における大気の「窓(window)」として知られるスペクトル部分の放射である(図3)。しかし、地表付近からの赤外線放射のほとんどは大気によって途中で吸収され、再び上層や下層に放射される。通常は地表より温度の低い雲頂や大気中の気体からも宇宙への放射が行われる。大気の大部分(乾燥空気の99%)は、赤外線放射に対して透明な窒素や酸素から構成されている。地表から出ていく赤外線放射を吸収し、地表より低温で高度の高いところから宇宙に向かって放射を出すのは、0から約2%の範囲で量が変化する水蒸気、二酸化炭素、その他いくつかの微量ガスである。放射的に活発なこれらのガスは地表からの赤外線放射に対して毛布のように働き、地表の温度を上昇させるという点で温室と似ているので「温室効果ガス」と呼ばれている。人為的影響のない大気のもっている毛布効果は自然の「温室効果」である。雲も赤外線放射を吸収放出しており、温室効果ガスと同じ毛布を掛けた働きをする。しかし、雲は太陽放射をよく反射するので地表を冷却する働きもある。短波と長波における雲の放射強制力の相反する働きは平均的にはほとんど打ち消しあっており、現在の気候に対する雲の正味の全球的影響は、宇宙からの観測によると少し地表を低温化させている。 地球の気温は、太陽放射と、地表、大気、雲などから宇宙空間に放射される赤外線の収支バランスで決まる。もし地球に大気がなければ、地表は−20℃くらいの温度になるはずであることが、計算によって分かっている。にもかかわらず、地表温が平均15℃くらいで安定しているのは大気の持つ温室効果による。すなわち、大気中に含まれる、二酸化炭素などの微量の温室効果ガス(グリーンハウス・ガス、略してGG)と呼ばれるが、地表から放射される赤外線を吸収し、宇宙空間に逃げる熱を大気中にとどめることにより、地球全体があたかもビニールハウスの中に入ったかのような状態になって、大気や地表面が暖められ、生物が生活できる環境が維持されている。 太陽からの放射光は温室効果ガスによる赤外線の吸収と、オゾンによる紫外線の吸収により、地表の近くで減少する。また、地球のまわりを回っている人工衛星に積んだ観測機器によって、地表から宇宙空間へ向かって放射される赤外線の量を測ると、やはり温室効果ガスによる吸収によって、赤外線領域のスペクトルに深く欠けた部分が見られる。つまり、欠けた部分の波長に相当する光は、温室効果ガスによって吸収されてしまって、宇宙空間には放射されず、再び大気中や地表に戻っていることになる。このように、赤外線領域の光を吸収してしまう温室効果ガスには、二酸化炭素以外にも水蒸気、フロン(クロロフルオロカーボン:CFC[フロンの一種]など)、メタン(CH4)、対流圏オゾン(O3)、亜酸化窒素(N2O)など、54種類もの気体が含まれる。 人間の経済活動により、温室効果ガスの大気中の濃度が上昇し、その結果、温室効果が強まって、今後数十年の間に急激に気温が上昇する恐れがある。これを「地球の温暖化問題」という。気温の上昇とともに、海面上昇、降水量変化、蒸発量変化なども起こり、生態系や人間社会に大きな影響を及ぼすと考えられている。気温が上昇することによって、海水の膨張と陸上の氷の融解により海水面が上昇し、沿岸地域で浸水や浸食により被害が発生すると思われる。これは、世界中の臨海都市、エジプトのナイル川、バングラデシュのガンジス川などの大河川の流域、特に河口部、さらに珊瑚礁の上にあるモルジブなどの島国に重大な影響を及ぼす。降水量、降水時期の変化や、高温障害、病害虫の発生の様子の変化、土壌水分の変化等は、農作物に大きく影響する。動植物の生態系は、気候と密接な関係にあることから、急激な変化に耐えられず、植生が荒廃したり、種の絶滅が加速されることも考えられる。また、気候と関係のある感染症の分布変化等により、人間の健康にも影響する可能性がある。このように、地球温暖化はあらゆる範囲に影響を与える。 最近までは、地球温暖化の影響については不確定なことが多かった。また温暖化の観測そのものにも不確定要素が多いとして、まだ対策を講じる必要はないといわれてきた。しかし1995年12月に公表されたIPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change:気候変動に関する政府間パネル)第2次報告書によると、人間活動の影響により地球の温暖化を示す相当量の証拠があり、温暖化防止の政策を実施しないと、2100年には約2℃の地球平均気温の上昇、約50cmの海面水位の上昇が予測されると述べている。IPCC第3次評価報告書(2001年)では、1990年から2100年までの全球平均地上気温の上昇は1.4〜5.8℃と予測されている。 IPCC(1995年)の評価によると、最近の数十年、北半球の夏季は、1400年以降最も暖かかったものと見られている(図4)。過去1世紀の気温の上昇は、過去600年間のうちで比較的寒冷な一時期に始まっている。すべての地域において最近の気温の上昇は例外的なものではないが、いくつかの地点の氷床コアデータにより、20世紀は少なくとも過去600年間のどの世紀よりも暖かかったことが示唆されている。最終氷期(約20,000〜100,000年前)及び遷移期から現在の間氷期(過去10,000年間、完新世として知られる)にかけて、大きくかつ急速な気候変化が起きた。数十年で年平均気温に約5℃の変化が少なくともグリーンランドや北大西洋では起きたが、これは海洋循環の変化と関連していたものと思われる。 IPCC第3次評価報告書によると20世紀中に全球平均地上気温は約0.6℃上昇し、平均海面水位10〜20cm上昇した。 潮位記録の解析によれば、全球海面水位は過去100年間に約10〜25cm上昇した。上昇率の見積もりにおける不確実性の主な原因は、潮位計による海面水位の測定値に含まれている鉛直地殻変動の影響であったが、IPCCの1990年報告以降、長期の鉛直地殻変動の影響を取り除く手法を改良し、かつ、トレンドを見積もるために長期に使用する潮位計に高い信頼性を置いたので、不確実性は減少している。これにより、海水の体積が実際に膨張し、海面水位の上昇を引き起こしているという主張の信頼性が高まった。過去100年間の海面水位の上昇の多くが、同時に起きていた全球的な気温上昇と関係していた可能性があるといえる。この時間スケールでは、観測された海面水位上昇のうち約2〜7cmが温暖化とその結果生じる海洋の膨張によるものであること、また、2〜5cmが観測された氷河と氷帽の後退によるものであることが説明可能である。表面水と地下水の貯蔵の変化は、最近100年間の海面水位に小さな変化を起こしたかもしれない。観測された海面水位の上昇率は、グリーンランドや南極の巨大氷床からの正味の正の寄与があったことを示唆するが、氷床の観測からはそれらそれぞれの寄与について意味のある定量的な見積もりはまだできていない。過去100年間はこれら氷床に関しては、不十分なデータしかないので、氷床は海面水位の変化を説明する上での不確実性の主な原因となっている。 温暖化の将来予想については、地域的な気候変動の様子や具体的な温度上昇の時期に関していまだによく分かっていない面があるが、地球の平均気温が半世紀足らずの間に数度上昇し、一部の地域ではそれよりも高い温度上昇になる恐れのあることは、一般的な認識となりつつある。気候変動のメカニズムについては、二酸化炭素の吸収メカニズムの解明、他の温室効果気体の大気中での挙動の解明、雲の発生量とその影響の解明、陸地における水の蒸発散の正確な推定、海洋の深層循環を考慮にいれた海洋大循環モデルへの結合などに関して活発な研究が行われており、今後、科学的知見は一層深まると思われる。 1880年から2004年までの125年間に世界の観測所で観測した地上気温の解析によると、全球(全世界)で平均した地上気温は、長期的な傾向として100年につきおよそ0.6℃の割合で上昇している(図5)。気温の上昇率は南半球に比べて北半球の方が大きい。温室効果ガスの増大などの人為的な影響が、このような19世紀半ば以降の気温の上昇傾向に現れている可能性が高い。2000年の世界の地上気温は観測史上最も高温であった1998年に比べると低く、南半球では平年値を下回ったが、北半球では中高緯度を中心に依然として高い状況が続いた。世界各地の観測所(1300カ所以上)で観測された地上気温から求めた2000年の年平均地上気温の平年差は+0.51℃で、1880年以降で第4位であった。2000年を含め、世界の地上気温が高温を記録した年は1990年以降に集中している。この10年間は、過去120年間のどの期間と比べても世界的に気温が高くなった。この要因として、温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化や数十年程度の時間規模で繰り返される自然変動などが考えられる。 二酸化炭素は地球温暖化に及ばす影響がもっとも大きな温室効果ガスである。人間活動に伴う化石燃料の消費とセメント生産および森林破壊などの土地利用の変化が、大気中の二酸化炭素濃度を増加させつつある。人間活動にともなう排出のうち、およそ8割は化石燃料の消費によるものである(IPCC、第2次評価報告書)。図6にハワイのマウナロア、綾里、南極点における大気二酸化炭素濃度の経年変化を示す。南極点では1957年から、ハワイのマウナロアでは1958年から、また綾里では1987年からそれぞれ観測が開始された。南極点やマウナロアで観測が開始された当時、大気中の二酸化炭素濃度はおよそ315ppmであったが、その後年々増加し、WDCGG(温室効果ガス世界資料センター)の解析による全球平均濃度は1998年で365.9ppm、2003年で約375ppmとなっている。現在の濃度は産業革命(18世紀後半)以前の平均的な値である280ppmに比べて30%以上増加している。図7にWDCGGが、世界各地の観測所から報告された観測データに基づいて解析した、緯度帯別の二酸化炭素濃度と濃度増加率の1983年から2002年までの変化を示す。北半球では濃度が春から夏に急滅し、夏から翌春にかけて増加するが、南半球では季節変化の振幅が小さい。季節変化をならすと、南半球から北半球の中・高緯度帯に向かうにつれて濃度が高くなっている。これは、二酸化炭素の放出源が北半球の中・高緯度により多く存在することによるものである。また、両半球ともに二酸化炭素濃度が年々増加していて、全球平均濃度の増加率は1983〜2002年の平均で1.6 ppm/年の割合である。 IPCCでは2001年3月に第3次報告書を取りまとめた。その中で、すでにいろいろな地点で温暖化の影響が顕在化しつつあることから、温暖化の影響を受けやすい脆弱な地域を特定すること、そして、そうした地域では、温暖化する気候に対処すべく適応策の検討を行うべきであると指摘している。 <図/表> 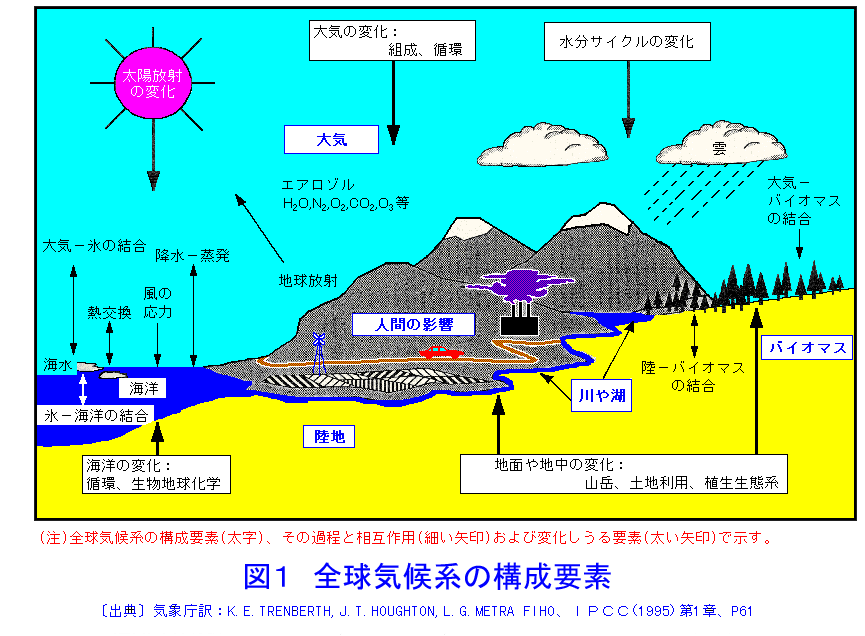
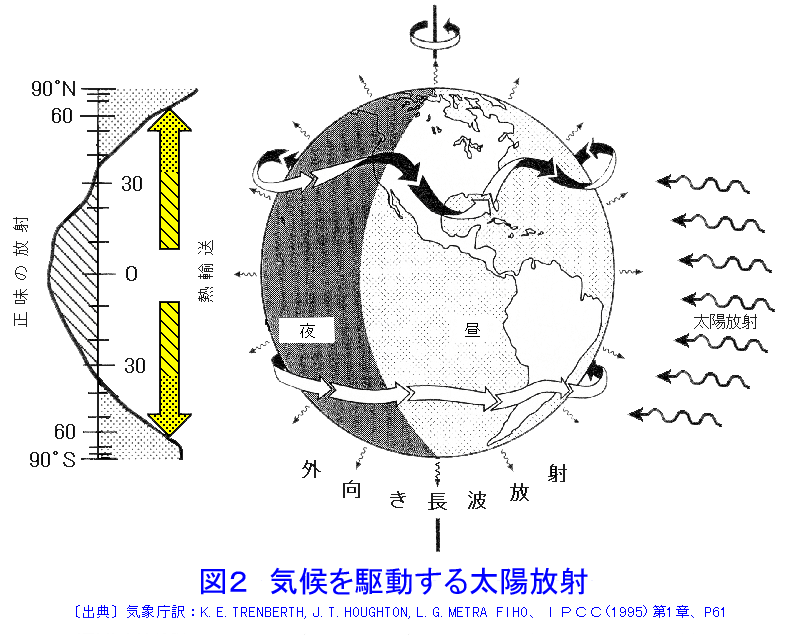
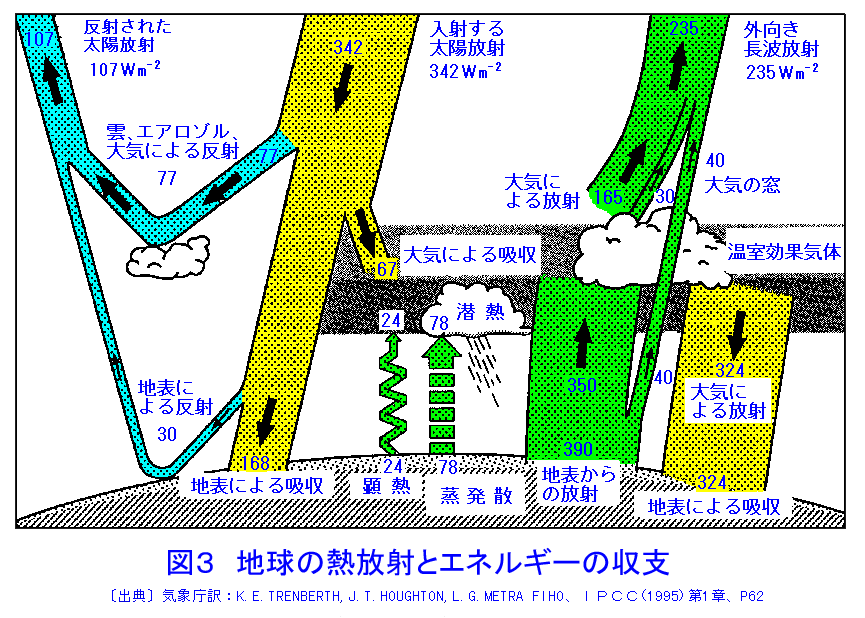
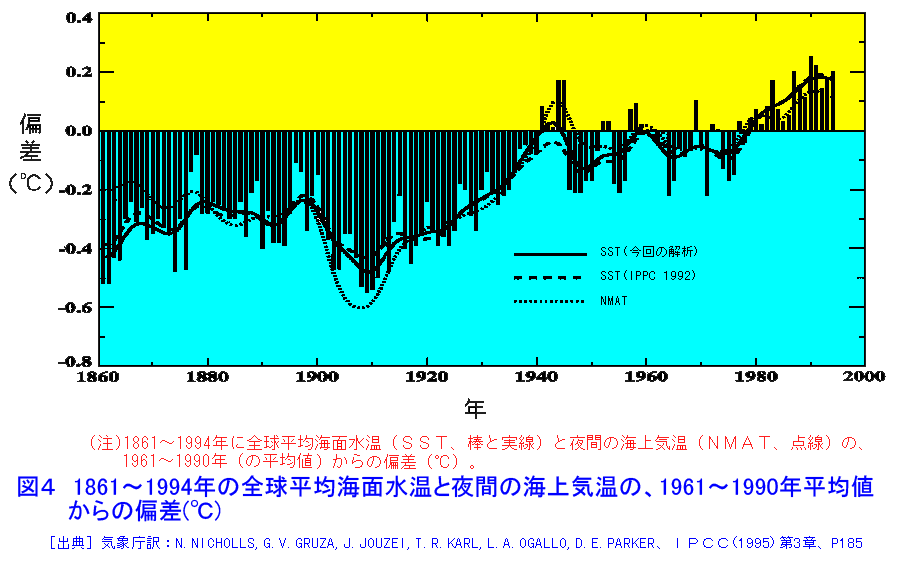
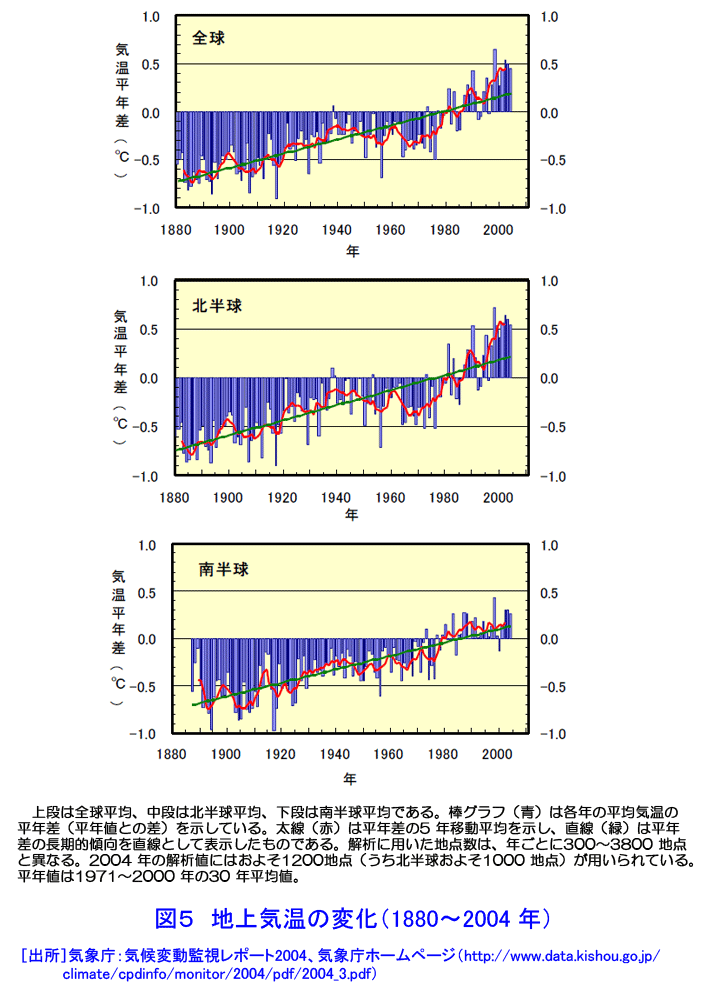
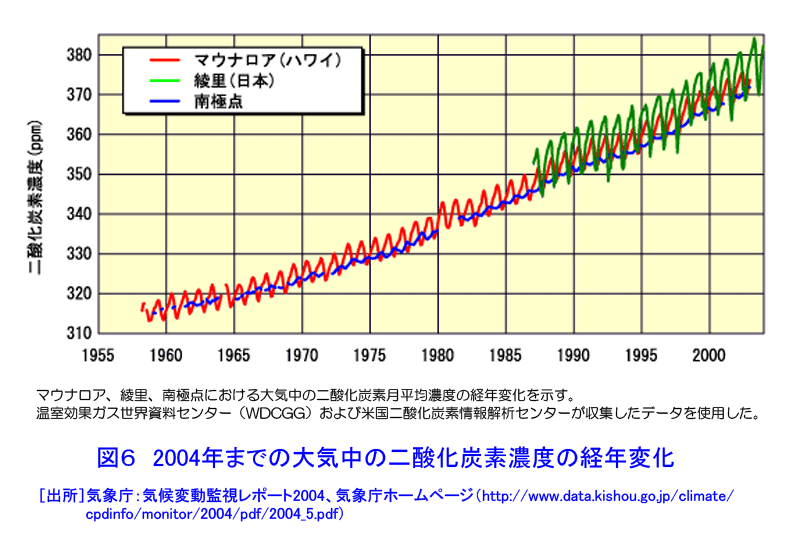
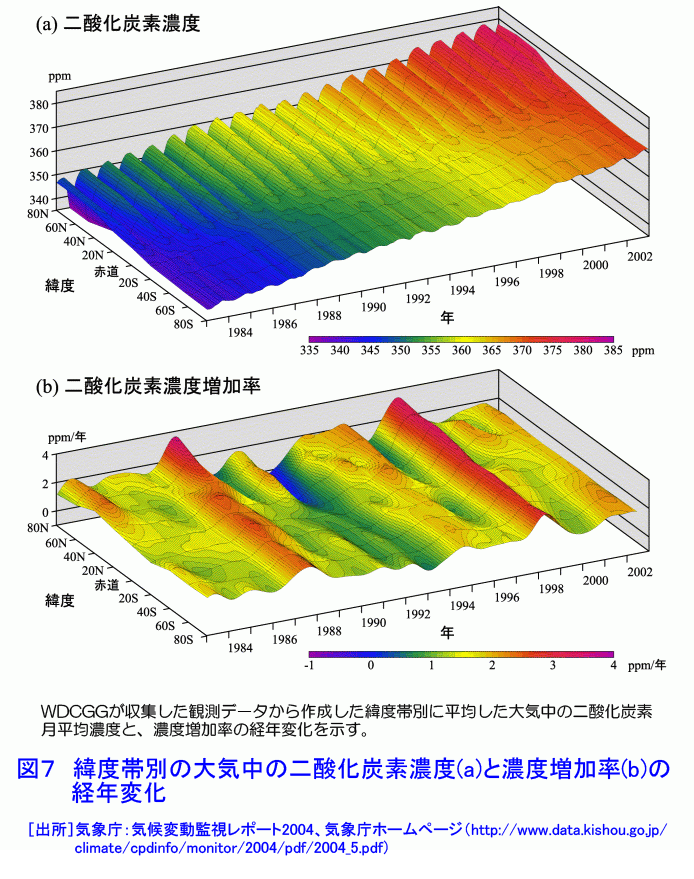
<関連タイトル> 温室効果ガス (01-08-05-02) 海面上昇の現状と予測 (01-08-05-11) 地球の炭素循環 (01-08-05-03) 気候変動に関する政府間パネル(IPCC) (01-08-05-07) IPCC第三次評価報告書(2001年) (01-08-05-08) <参考文献> (1) 気象庁(編):温室効果気体の増加に伴う気候変化(2)、気候問題懇談会温室効果検討部会報告(1990年) (2) 気象庁(編):地球温暖化の実態と見通し、気候変化1995、大蔵省印刷局(1996年10月) (3) IPCC(気候変動に関する政府間パネル):IPCC報告書(1990年8月) (4) IPCC(気候変動に関する政府間パネル):IPCC第2次報告書(1995年12月) (5) 気象庁(編):気候変動監視レポート2000、財務省印刷局(2001年4月27日)p.1−13,p.24−29 (6) 環境庁(編):平成13年版 環境白書、(株)ぎょうせい(2001年5月27日)p.37−46 (7) (財)地球産業文化研究所(編著):地球環境2000−’01 株式会社ミオシン出版(2000年2月21日)p.77−93 (8)福岡克也(監修):地球環境データブック2004−2005、(株)ワールドウォッチジャパン(2004年12月)、p.68−72 (9)茅 陽一(監修):環境年表2004/2005、(株)オーム社(2003年11月)、p.267−273 (10)環境省(編):環境白書 平成16年版、(株)ぎょうせい(2004年5月)、p.52−63 (11)気象庁:気候変動監視レポート2004、気象庁ホームページ
|

