|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
大気中に含まれる水蒸気や二酸化炭素などの微量ガスが、地表から宇宙空間に向かって放射される赤外線を吸収して大気にとどめることにより、大気及び地表が暖められる。これを温室効果と呼ぶが、このように赤外線領域の光を吸収し、温室効果を引き起こす気体を温室効果ガスという。温室効果ガスとしては、水蒸気、二酸化炭素のほかに、メタン、オゾン、一酸化二窒素、フロン類など多様な化合物がある。二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスは天然にも放出されているが、様々な証拠から工業化以前の時代には相当長期にわたって大気中濃度がほぼ一定に維持されてきたと推定されている。これに対して、近年には温室効果ガスの人為的な放出が急増して大気中濃度が増加し、これによって地球の放射平衡に無視できない影響を与え、気候変化を引き起こしつつあると考えられている。 <更新年月> 2009年12月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.温室効果ガスの概要 私たちの住む地球では、大気の約8割が窒素、約2割が酸素で構成されている。これらのガスは太陽光及び地球から宇宙空間に放出される赤外線に対してほぼ透明である。他方、大気中に含まれる微量ガスには、地表面からの赤外線放射を吸収し、宇宙空間に逃げる熱を大気にとどめる性質を持ったものがあり、これによって地表面及び大気が暖められ、生物の生存に好ましい温度が維持されている。この現象を温室効果といい、赤外線を吸収する性質を持ち、温室効果を引き起こす気体を、温室効果ガス(グリーンハウスガス、略してGHG)という。 温室効果ガスとしては、自然界に元々あった水蒸気、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)などの他、人間の経済活動に起因する二酸化炭素、ハロカーボン類(ハロゲン原子であるフッ素、塩素、臭素、ヨウ素を含んだ炭素化合物の総称で、その多くは本来自然界には存在せず、工業的に生産される)、メタン、一酸化二窒素、対流圏オゾン(O3)などが知られている。このうち水蒸気が最大の温室効果ガスである(温室効果全体の8〜9割を占めると考えられている)が、その大部分は自然起源のものであり、人為的な水蒸気の発生が地球の気候に有意な影響を与えるとは考えられていない。これに対し、水蒸気以外のガスは大気中濃度は小さいものの、人為的な排出が地球の放射平衡(本文末の注を参照)に無視できない影響を与え、気候変化を引き起こしつつあると考えられている。 このような温室効果ガスによる放射平衡への影響を放射強制力という。気候変動に関する政府間パネル(以下、IPCC)の第4次評価報告書(2007年)では、放射強制力とは「ある因子が持つ、地球大気システムに出入りするエネルギーのバランスを変化させる影響力の尺度であり、潜在的な気候変化メカニズムとしてのその因子の重要性の指標である。正の放射強制力には地表面を昇温させる傾向が、負の放射強制力には地表面を降温させる傾向がある」(IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書技術要約(Technical Summary)、気象庁翻訳)とし、各温室効果ガスの放射強制力の値を1750年の工業化以前の状態に比べた変化を単位W/m2で推定している。 IPCC第4次評価報告書で評価された主要な温室効果ガスの放射強制力を図1及び表1に示す。二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハロカーボン類等に対流圏オゾンを加えると、正の放射強制力は3W/m2程度と推定されるが、エアロゾルによる負の放射強制力が1W/m2以上あるため、人為起源の正味放射強制力の合計値は1.6(0.6〜2.4)W/m2と推定されている。なお括弧内は90%信頼区間の下限値と上限値を示す。この範囲は非常に広い(最良推定値1.6と比べると下限値は−1.0、上限値は+0.8)が、この理由はエアロゾルによる負の放射強制力についての科学的理解度が低く、不確実性が大きいためである。因みに長寿命温室効果ガス類全体の寄与は+2.63±0.26 W/m2とされ、高い信頼性でその大きさが推定されている。 将来的に温室効果ガスの排出量が増大した場合に、大気中濃度の増加を通じて地球の温暖化にどの程度影響するかを評価することは、今後の温室効果ガスの排出削減の対策を講じる上できわめて重要である。そこで、様々な温室効果ガスの排出による地球温暖化への寄与を示す簡単な尺度として地球温暖化係数(Global Warming Potential;GWP)の概念が考案された。この係数は、現時点で排出された単位質量の気体により生じる放射強制力を、現在から将来のある時点まで積分したものとして定義され、二酸化炭素を1とした時の倍数で表現される。ある将来時点までの温室効果ガスによる温暖化の度合は、GWPに当該気体の排出量をかけることにより見積もられる。逆に言えば、今後の温室効果ガスの排出抑制が温暖化の緩和にどの程度の効果があるかを推定することが可能となる。IPCC第4次評価報告書で推定されたGWPの値を表2に示す。 温室効果ガスのGWPの値を決定する主な要因は、大気中での寿命の長さ及び赤外線吸収特性で決まる放射効率(大気中濃度の単位量の増加による放射強制力の大きさ)である。なお、二酸化炭素に関しては大気中に排出された全量が海洋や陸地に吸収されて大気から除去されるわけではなく、地球の炭素循環に伴って指数関数的に大気中濃度が減少すると考えられているため、寿命の概念はない。表2に示されているように、当然のことながら大気中の寿命が長い温室効果ガスは、長期間で見た時のGWPの値が大きくなる。また、ハロカーボン類(表2では「モントリオール議定書による規制物質」以下に記されたガス)は、排出量と大気中濃度は二酸化炭素に比べてはるかに小さいが、放射効率がきわめて大きいものが多く、温暖化に無視できない影響があると考えられている。この要因の一つは、水蒸気や二酸化炭素による吸収のない8〜13μmの波長領域(大気の窓と呼ばれる)の赤外線を吸収することにある。 以下に主要な温室効果ガスの特徴についてまとめる。 2.各温室効果ガスの特徴 (1)二酸化炭素 大気中の二酸化炭素の1994年末時点における総量は7620億トン程度(炭素換算、以下同じ)と推定されている。大気と海洋及び大気と陸地はそれぞれ、さまざまなメカニズムで大量のCO2を交換しており、前者は大雑把に年間900億トン、後者は同1200億トンの規模と推定されている。人為起源の二酸化炭素の年間排出量は、これらの交換量と比べるとはるかに小さい。しかし、産業革命前には大気中濃度が280ppm(ここでのppmはppmv、つまり体積比で百万分の1を指す、以下同じ)、つまり6000億トン弱であったのに対して、1995年の濃度は約360ppmであり、人為的な排出によって大気中の二酸化炭素が約80ppm、1650億トン程度増加したと推定されている。近年には年間約2ppmの増加ペースとなり、2005年の濃度は約379ppmに達し、その後も増加を続けている(図2)。工業化以前の8000年間の増加量は20ppmと推定されており、以下に述べる人為的な排出が短期間に大幅な濃度増加を招いたと考えられている。 IPCCの第4次評価によると、1990年代の平均で人為的な二酸化炭素の年間排出量(化石燃料の燃焼とセメント製造から発生するもの)は64億トン、このうち海洋の正味吸収分が22億トン、陸域での正味固定量が10億トン(総固定量26億トンから森林破壊等の土地利用変化に伴う大気放出量16億トンを除いたもの)であり、残る32億トンが大気中濃度の増加への寄与と推計された。これに対して、2000〜2005年の期間には、人為的排出量が72億トンに増加したものの、海洋の正味吸収分は1990年代と同じ22億トン、陸域の正味固定量は9億トンとやや小さくなったため、大気中濃度増加への寄与分は41億トンへと増大したと推定されている。 このように、1990年代の平均値でみると、排出された二酸化炭素の半分が大気中濃度の増加に寄与するため、人為的な排出量を半減すれば大気中濃度の安定化を実現できると考えられていたが、2000年以降の二酸化炭素収支でみると、自然の吸収量とバランスさせるためには排出量を60%近く削減する必要があることになる。ただ、陸域の正味固定量には、森林減少、火災等による放出、植物の生長、植林の促進等による吸収ともに、不確かさが非常に大きく、今後これらの影響をより精度良く評価する努力が必要とされている。 (2)メタン メタンは、有機物の嫌気性発酵などで天然に発生する温室効果ガスの一つであるが、農業、ゴミ処理、化石燃料の生産・使用といった多様な人間活動によって大気に放出されている。メタンはハイドロキシルラジカル(OH)による酸化で消滅し、大気中の寿命は約12年と短い。このため、排出量と消滅量のバランスに応じて大気中の濃度が変動しやすい。IPCCの第4次評価によれば、大気中のメタン濃度は過去10,000年の間に580ppb(ここでのppbはppbv、つまり体積比で10億分の1を指す、以下同じ)と730ppbの範囲で緩やかに変動してきたが、2005年に約1774ppbの濃度となり、過去2世紀の間に約1000ppb増加し、工業化以前の水準の2倍以上となった。これによる直接的な放射強制力は約0.48W/m2と推定される。近年は濃度の増加ペースがやや鈍化しているが、2008年に約1797ppbに達したことが報告されている(図3)。 メタンの個別発生源からの排出量は精度良く定量化はされていないが、大部分は生物起源(湿地、反芻(はんすう)動物、米作、バイオマス燃焼等)であり、化石燃料の利用に関連した工業起源の排出は小さいと考えられている。しかし、過去65万年間のメタン濃度の自然変動の範囲が小さいこと、1750年から劇的に増加したことを考慮すると、近年に観測されたメタン濃度の上昇は人為起源の排出量の増加に起因する可能性が非常に高いと考えられている。なお、温暖化がこれまでのペースで進んでいく場合には、シベリアの永久凍土が徐々に融解し、その中にメタンハイドレートの形で閉じこめられている大量のメタンが大気に放出され、これが温暖化をさらに加速する可能性があると懸念されている。 (3)一酸化二窒素 一酸化二窒素には、自然発生源及び人為的発生源ともに、小さな発生源が多く存在し、個々の発生源の推定値にはまだ大きな不確実性があるが、総排出量の約40%が人為起源と推定されている。人為的発生源は、主に農業と多くの工業過程(例えばアジピン酸や硝酸の製造)である。一酸化二窒素は主に成層圏における光解離によって除去されるので、寿命は約114年と長い(表1)。IPCC第4次評価によると、工業化以前の11,500年間の大気中濃度の変動は10ppb未満であったが、過去数十年の間に年間約0.8ppbのペースでほぼ直線的に増加し、2005年の濃度は319ppbに達した。工業化以降の一酸化二窒素の濃度変化による放射強制力は、約0.16W/m2である。2005年以後もほぼ同じペースで濃度の増加が続いている(図4)。 (4)ハロカーボン類と他のハロゲン化合物類 ハロカーボン類は、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素のいずれかを含む炭素化合物である。それらの多くは、大きな放射強制力をもつ温室効果ガスである。これらの化合物の大部分は、人間活動が唯一の発生源である。塩素や臭素を含むハロカーボン類(塩素を含むものはCFC類やHCFC類、臭素を含むものはハロン類)は、オゾン層破壊の原因物質と考えられているため、その排出は「モントリオール議定書」及びその「調整」や「改正」文書により規制されている。また、オゾン層破壊への影響の小さいHCFC類等の代替フロンも大きなGWPを持つため、京都議定書では排出量を削減すべき温室効果ガスとして規定されている。その結果、これらの化合物の多くの増加率は既に減少しており、特にCFC-11とCFC-113の大気中濃度は現在、自然の除去過程によって減少しつつある(図5)。モントリオール議定書の対象となっているガスの2005年における放射強制力(直接的寄与)は、約0.32W/m2であった。なお、オゾンガスも大きな放射強制力を持つと考えられており、ハロカーボン類は成層圏オゾンの破壊を通じて、わずかではあるがマイナスの間接的放射強制力をもたらしている。 3.温室効果ガスに関するデータの収集 世界気象機関(WMO)は、1989年に、それまで実施されてきた全球オゾン観測システムと大気バックグランド汚染観測網の2つの監視プログラムを統合して全球大気監視(GAW)プログラムを開始した。GAWには6つの世界資料センター(WDC)があるが、その一つとして温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)が1990年に設立され、日本の気象庁が運営にあたることとなった。 これ以来、WDCGGは世界の各地域で観測された大気と海洋における温室効果ガス(CO2、CH4、CFC類、N2O、地上オゾンなど)及び関連ガス(CO、NOx、SO2、VOCなど)に関するデータを収集し、検証、形式の統一を行ってデータを保存するとともに、データ解析を容易にするための利用者支援情報と合わせて、世界中の利用機関にデータの提供を行ってきた。なお、WDCGGが対象とする観測データは、 観測プラットフォームや観測に用いた手法により、6つの観測カテゴリー(地上観測所での大気観測、大気の鉛直分布観測(タワーを用いた複数の高さでの観測など)、移動プラットフォームによる大気観測(航空機、船舶など)、氷床コア観測、表層海水とその直上の大気観測、船舶による海洋観測)に分類されている。 (注)放射平衡:気候科学の分野では、地球への太陽光入射エネルギーと地球から宇宙空間への赤外線放射エネルギーとが均衡している状態をいう。この平衡状態に影響する因子が生じた場合には、地球の表面気温が変化して地表からの放射エネルギーの量が調整され、平衡状態が維持される。例えば、温室効果ガスの大気中濃度の上昇によって地球から宇宙への赤外線放射が減少し始めると、地球の平均表面気温が上昇して地表からの放射エネルギーが増加し、放射平衡が維持される。逆に、火山噴火などで大量の二酸化硫黄等が放出され、大気中のエアロゾル濃度が上昇して太陽光入射エネルギーが減少すると、地球の平均表面気温が低下して地表からの放射エネルギーが減少し、放射平衡が維持される。 (前回更新:2004年2月) <図/表> 
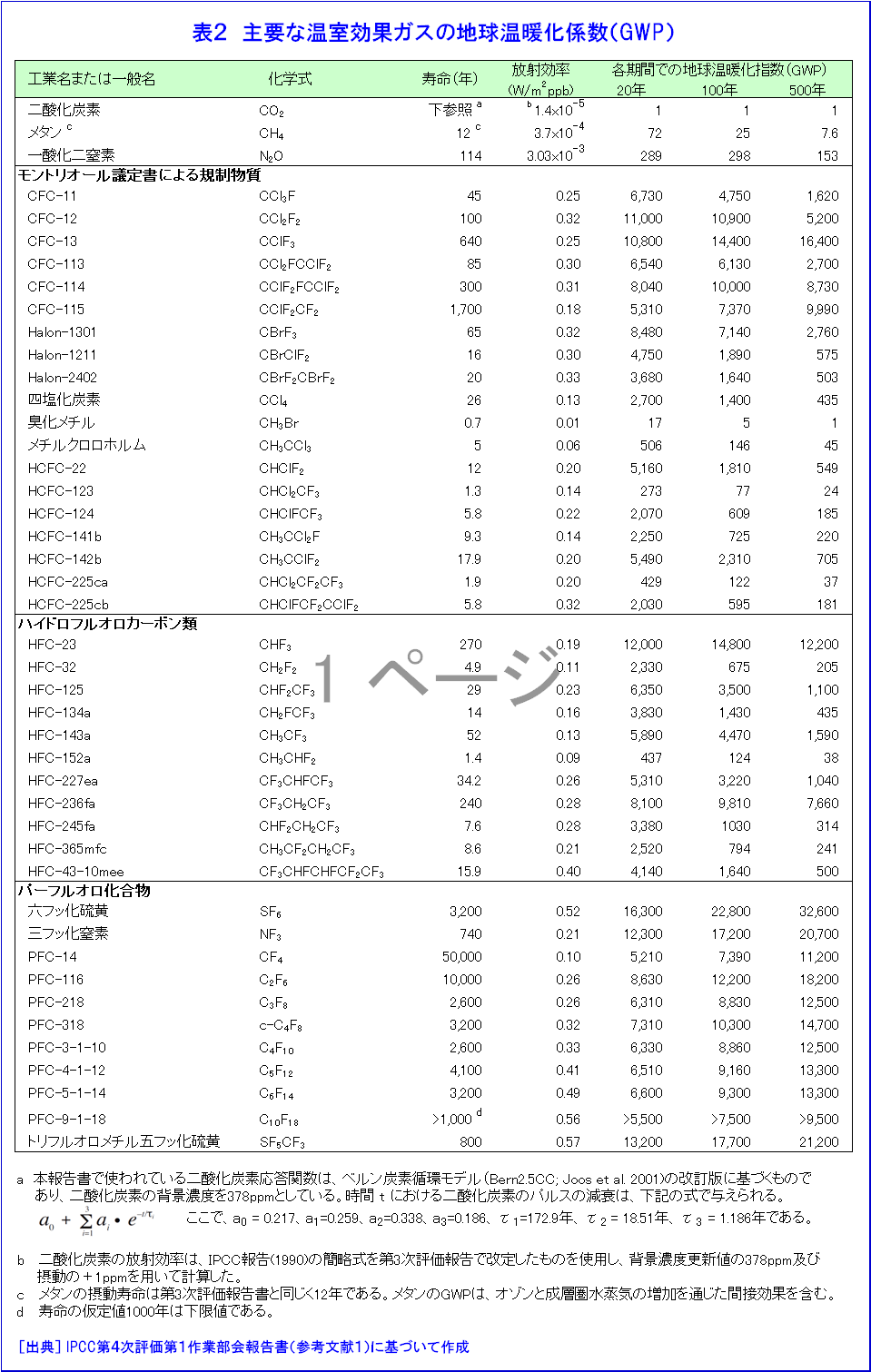
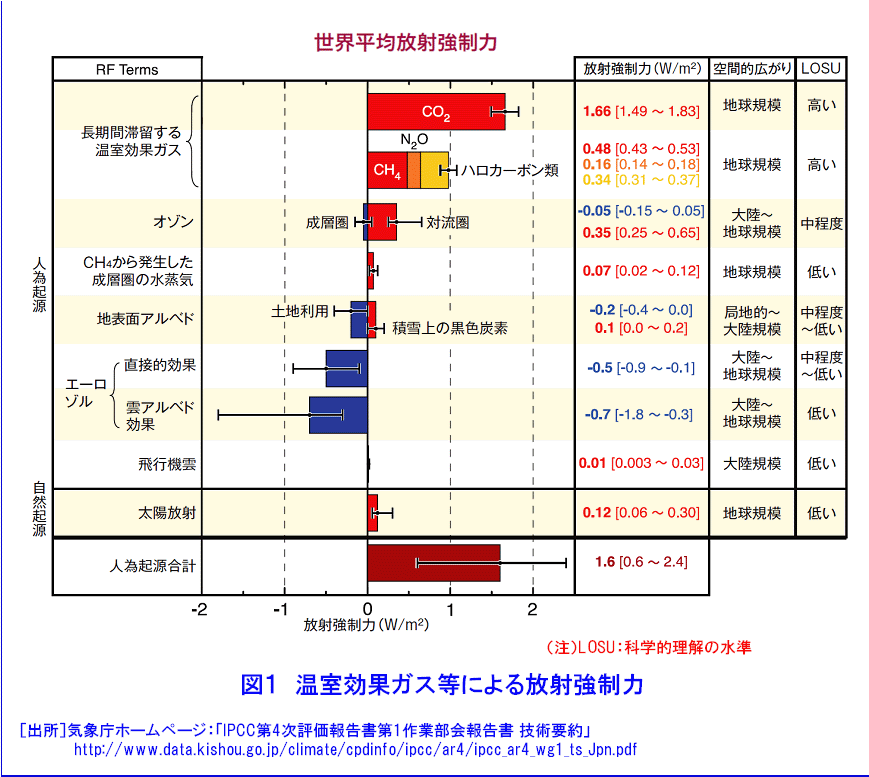
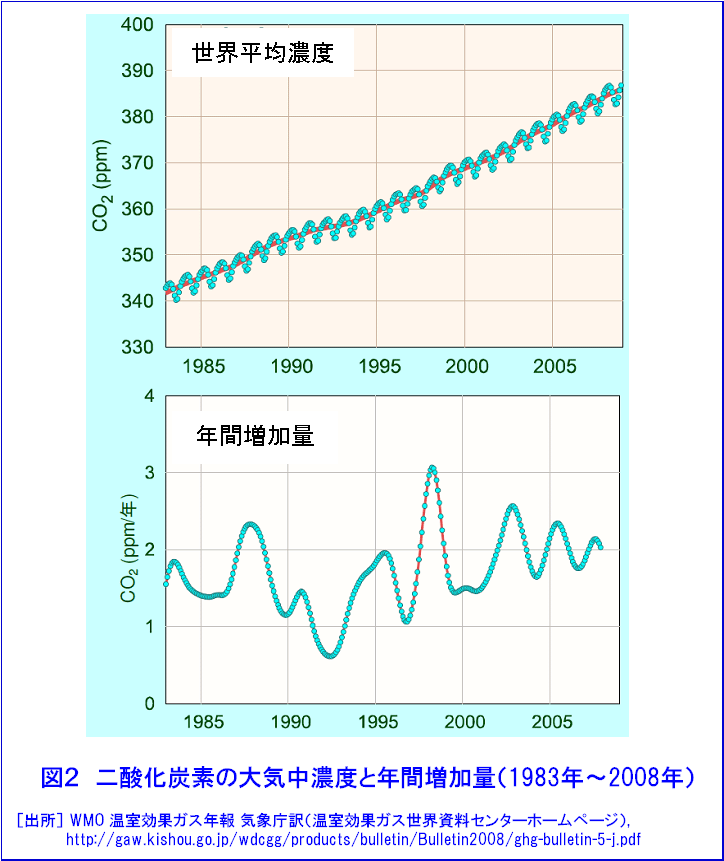
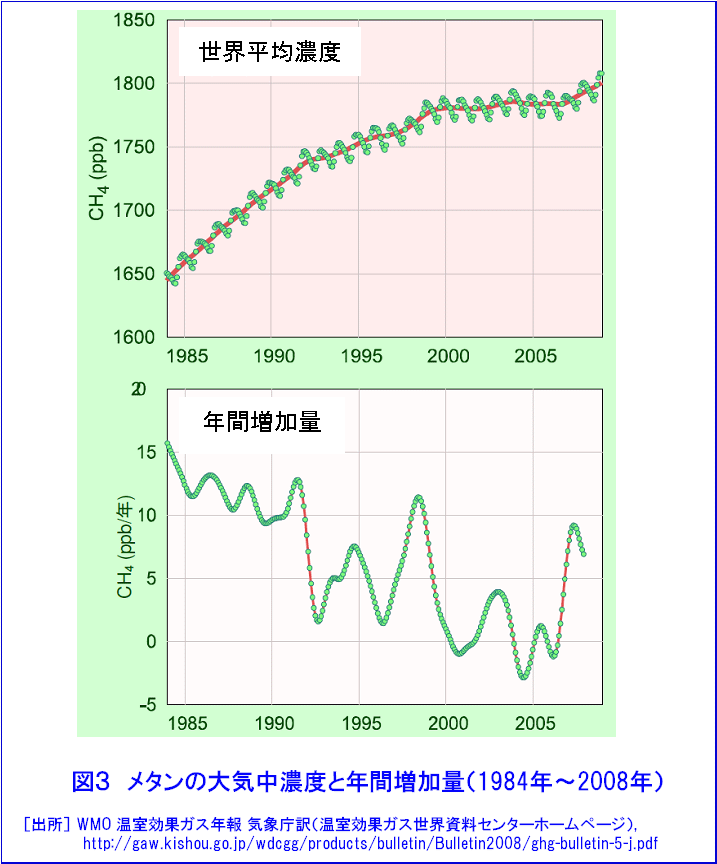
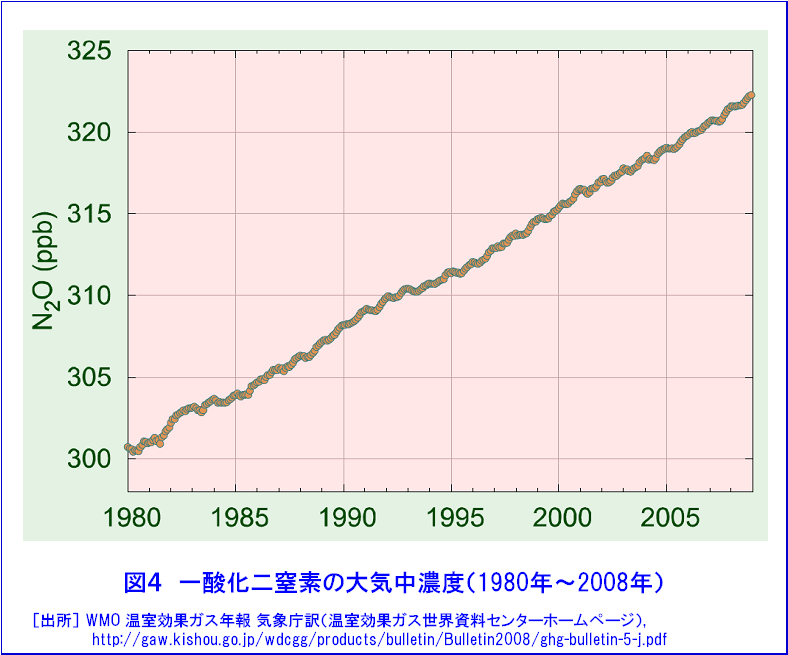
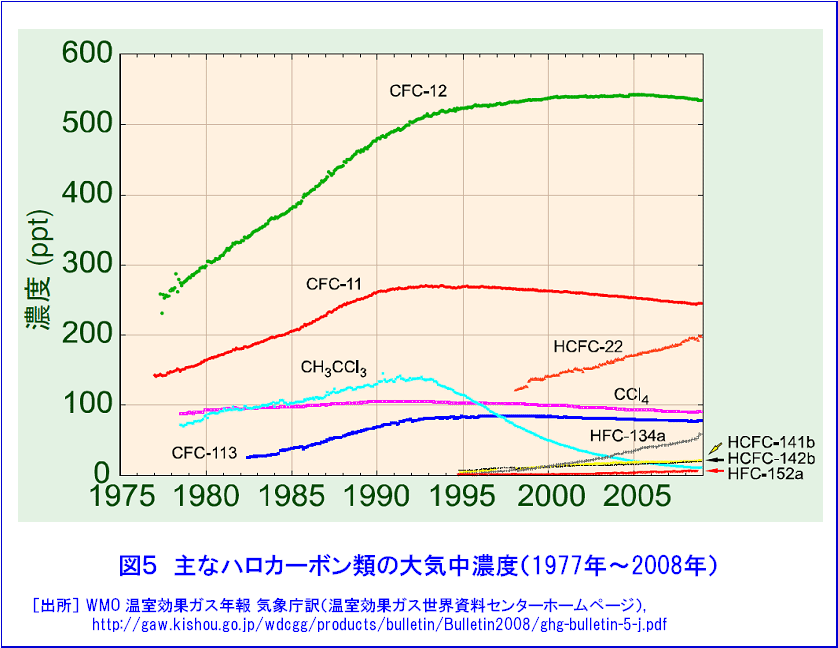
<関連タイトル> エネルギー源と排出係数 (01-08-05-05) 地球の温暖化問題 (01-08-05-01) 海面上昇の現状と予測 (01-08-05-11) 地球の炭素循環 (01-08-05-03) 二酸化炭素放出量の推計 (01-08-05-12) <参考文献> (1)IPCC:Climate Change 2007 - The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, (2)気象庁ホームページ:IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書 技術要約 (3)温室効果ガス世界資料センターホームページ (4)WMO 温室効果ガス年報 気象庁訳(温室効果ガス世界資料センターホームページ)
|

