|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
地球の炭素循環は、大きく地球上の炭素循環と海洋中の炭素循環に分けられる。大気中炭素の収支の主要な構成要素は、人間活動からの排出量、大気中の増加量、大気と海洋間の交換量、大気と陸上生物圏との間の交換量であるが、陸上生物圏との交換過程には、不確実さが多く、将来の予測も困難である。一方、海洋中の炭素貯蔵量も物理・化学および生物学的な過程を通して、気候のフィードバックにより影響されることが考えられるが、長期の温暖化による海洋循環の変化の研究は始まったばかりであり、したがって、海洋中の炭素循環へ与える気候の影響の解析も未だ初歩的である。大局的には、二酸化炭素は海流とともに地球の自転によって中緯度の辺りで下へ潜り、それが循環してきて赤道辺りで湧出し、大気中に放出されると考えられる。また、南半球と北半球でみると、北半球では海洋による二酸化炭素の吸収量があまり大きくないが、これは化石燃料を大量に消費する工業国が北半球の中緯度地方に集中しているためと考えられる。 <更新年月> 2007年09月
<本文>
炭素循環とは地球の生態系における炭素の流れであり、生物・大気・陸域・海洋・土壌間の炭素循環に、物理的・化学的・生物学的・社会的な作用が相互に働いている。 IPCC(気候変動に係る政府間パネル)第二次報告書(1995年)の炭素収支によると、石油・石炭など化石燃料の消費や、森林破壊などの人間活動によって大気中に放出される二酸化炭素は、炭素換算で年間約7.1Gt(Gt:10億トン)。このうちの約2Gtを海洋が吸収し、約0.5Gtを森林が吸収、その他の地球規模の吸収が約1.3Gtあるとしている。そして、残りの3.3Gtが大気中に残留すると見積もっている。大気中の温室効果ガスとりわけ二酸化炭素の増加が気候変動を起こすことは疑いない。化石燃料消費による年間二酸化炭素放出量と大気中二酸化炭素増加速度の推移は図1のとおりである。 <地球上の炭素循環> 大気成分の濃度は、その発生源(大気への排出量と大気内での生成)と吸収源(地球表面における除去と化学的消失)の大きさに依存している。これらの過程によつて、単一もしくは集合した大気成分の様々な寿命が決定され、その寿命の間放射強制力を発揮する。大気中炭素(炭素:C)の収支の主要な構成要素は、人間活動が起源の排出量、大気中の増加量、大気と海洋間の交換量、大気と陸上生物圏との間の交換量である。 IPCCの第一次評価報告書(1992年)によれば、「地球規模で大気中に存在する二酸化炭素量は、炭素換算で750Gt」であり、それが3Gt/年の割合で増加している(図2参照)。それに対して、土壌中の腐食を含めた陸上生態系の有機物量は炭素換算で2,050Gtであり、大気圏の約2.7倍量が存在している。さらに、陸上生態系に存在する有機物量の約2/3を森林生態系が占めている。このため、地球上の陸地の1/3を占める森林における生態系の有機物量の増減は、大気中の二酸化炭素濃度に大きな影響を与えているはずだが、IPCC報告書では不充分な精度の見積りで報告されている。この点に関しては、広範囲な様々な生態系における観測結果を統合した信頼できる見積りを求めて、森林生態系の二酸化炭素の吸収/排出量(フラックス)を定量的に評価することが国際的な緊急課題となり、わが国でも国立研究所地球環境研究センターが温室効果ガスフラックス観測をはじめとする森林生態系の総合的観測研究を行っている。 大気中二酸化炭素濃度の現在の測定値と過去数十万年にさかのぼるアイスコア中の二酸化炭素濃度の分析値との比較から、周期的な氷河期・間氷期において大気の組成と地球の平均気温とは明確な範囲内で変動してきたこと、そして現在はその範囲から明らかに逸脱してしまったことが分かってきた。現在、地球大気の二酸化炭素濃度は間氷期の最大値よりほぼ100ppmv(ppmv:百万分の一体積比)高い。最近の二酸化炭素濃度の上昇幅は、氷河期の最小値と間氷期の最大値の変動幅に匹敵する。 近年における大気中二酸化炭素の劇的増加は、疑うべくもなく人間活動の所産である。20世紀に観測された気候の温暖化は二酸化炭素の増加による可能性がきわめて高い。 現代の炭素循環において、数多くの重要なプロセスの背後にあるメカニズムは、いまだに我々の理解を越えている。例えば、(1)工業化や社会制度の変化が引き起こす要因、(2)陸域内外での炭素の流れを制御している土地利用、生態生理と擾乱などの相互作用、(3)陸域から沿岸−外洋へ向けての炭素の流れと蓄積、(4)大気・海洋表層・深層を通しての炭素輸送に関する生物学的・化学的・物理的な相互作用などがあげられる。 <海洋中での炭素循環> 海洋中の炭素貯蔵量もまた物理、化学および生物学的な過程を通して、気候のフィードバックにより影響されることが考えられる。初期モデルの計算結果は、海洋中の炭素循環におよぼす海洋循環の変化の影響は大きくないとしてきた。しかし、長期の温暖化による海洋循環の変化についての研究は始まったばかりであり、海洋中の炭素循環へ与える気候の影響の解析は未だ初歩的であるとみなされなければならない。 海洋は、つねに大量の二酸化炭素を吸収し、また放出している。その年間のやり取りの量(循環する)は、炭素換算で年間に100Gtに及ぶともいわれている。大気中の二酸化炭素は海水に溶け込んだり、海洋の生物活動を通して海洋に侵入する。その一部は再び大気へ戻り、一部は海底堆積物へ取り込まれる。海洋における炭素循環過程を調査するためには船上から採水による海水中の化学成分の分析、セジメントトラップ実験による沈降粒子の捕集、ピストンコアラーによる採泥等の海洋観察を行う(図3参照)。 二酸化炭素が海洋に吸収される過程には、溶解ポンプと生物ポンプ(生物炭素ポンプ)がある。溶解ポンプは、大気中の二酸化炭素が海面の表層へ物理的・化学的に溶け込む過程である。二酸化炭素は格段に水に溶けやすい性質を持ち、海水温度が低いほど良く解ける。一般に、高緯度海域で二酸化炭素が良く吸収され、赤道周辺で放出されるといわれているのはこのためである。生物ポンプは、陸上でいえば森林が二酸化炭素を吸収する過程に似ている。海中で森林の働きをするのは植物プランクトンである。植物プランクトンは、海中の窒素・リンといった栄養塩を取り込み、二酸化炭素および太陽の光エネルギーを使って光合成を行い、有機物を造る。植物プランクトンが活発に活動すれば、海中の二酸化炭素の濃度が低くなり、大気から溶解しやすくなる。植物プランクトンは、動物プランクトンや魚のエサとなり、その糞として、またあるものはやがて死骸となって深海へ沈んでいく。こうして二酸化炭素もいっしょに深海へ運ばれていく。このシステムが生物ポンプである。もちろん、そのすべてが深海底に堆積するわけではない。深海の海水に溶け込んだまま存在し、また、深層の大循環などによって再び表層へ押し上げられ、大気中に放出されるものも多い。生物ポンプは、海洋が大気中の二酸化炭素を吸収する上で大きな働きを担っているが、気温の上昇とともに海洋の表層水温が上がってしまうと軽くて温かい水が表層をフタのように覆い、表層部の栄養塩は不足し、植物プランクトンの量も減ってしまい、生物ポンプの機能が衰える。 地球全体では、植物が二酸化炭素から有機分子に炭素を取り込む全光合成生産量の1/3以上が海洋の植物によるもので、残りの光合成量が陸上の植物によるものである。年平均では、海産藻類(植物プランクトン)による炭素固定の総量は50Gt/年程度であり、その半分以上は有光層内で再循環する栄養塩によって支えられており、残りは主に海洋内部から、また大気や河川の流出を通じて陸から有光層へ運び込まれる新しい栄養塩によって支えられている。大局的にいえば、二酸化炭素は海流と共に地球の自転によって中緯度の辺りで下へ潜り、それが循環してきて赤道の辺りで湧出し、海洋中から大気中に放出される。また南半球では、中緯度の辺りでは海洋が大気中の二酸化炭素をよく吸収している。しかし北半球では海洋による二酸化炭素の吸収量があまり大きくなく、とりわけ北緯三十度から六十度の辺りでは二酸化炭素が放出されている。これは化石燃料消費の曲線とよく一致しており、二酸化炭素を多く放出する工業国が北半球の中緯度地方に数多くあることが原因であると考えられる。 大気中の二酸化炭素の循環経路に関する定量的な把握は、将来の地球環境を予測するためにも重要な課題といえる。なかでも、最大の吸収源である海洋の炭素循環のメカニズムの解明は急務とされている。現在、各国が様々な海域で物質循環研究を実施し、各海域におけるプロセス研究を行っている。研究がまだ遅れているのが北西部北太平洋と南極海である。そのため、わが国でも高緯度海域における物質循環研究を実施し、多くの研究者とともに、海洋の炭素循環をコントロールする生物地球化学的因子に関する研究が継続されている。 (前回更新:2002年3月) <図/表> 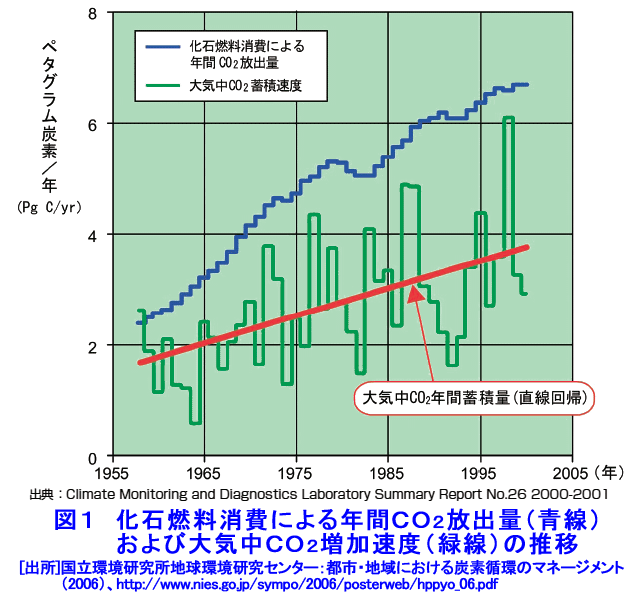
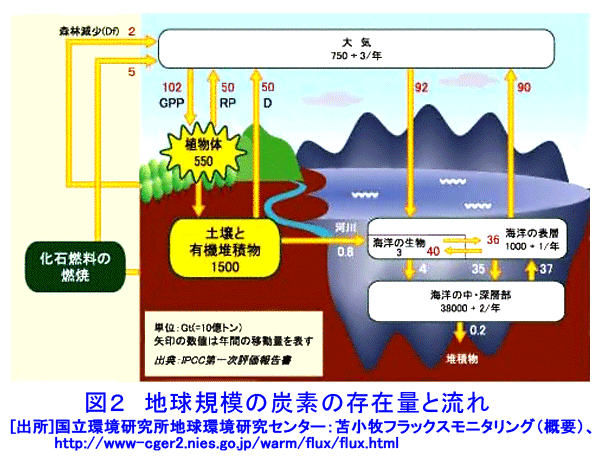
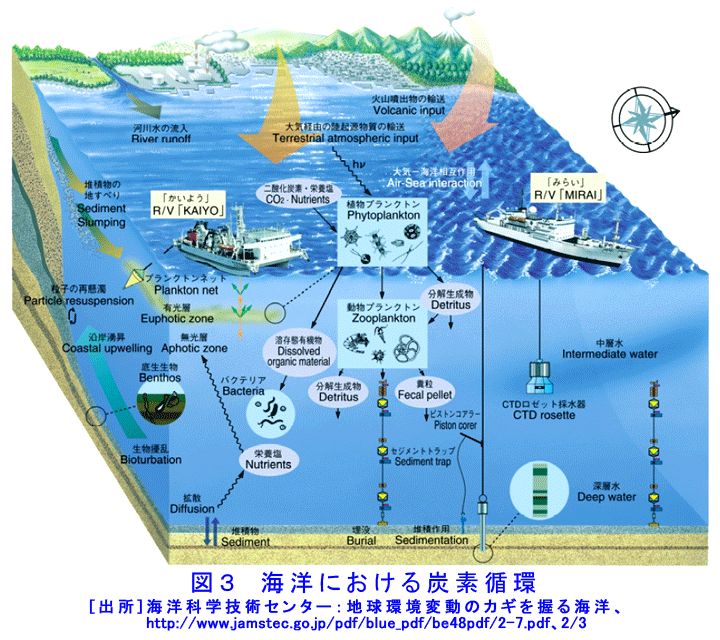
<関連タイトル> 地球の温暖化問題 (01-08-05-01) 温室効果ガス (01-08-05-02) <参考文献> (1)気象庁(編):温室効果気体の増加に伴う気候変化(2)、大蔵省印刷局(1990年) (2)気象庁(編):地球温暖化の実態と見通し、気候変化1995、大蔵省印刷局(1996年) (3)井上 元:炭素循環への挑戦、地球環境研究センターニュース(2002.1)、p.16−18 (4)海洋科学技術センター:地球環境変動のカギを握る海洋 (5)国立環境研究所地球環境研究センター:苫小牧フラックスモニタリング(概要) (6)国立環境研究所地球環境研究センター:都市・地域における炭素循環のマネージメント(2006)
|

