|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
放射線を用いた育種法は突然変異育種の一つであるが、放射線育種場では、放射線照射による突然変異の誘発技術開発、突然変異を利用した育種素材の作出及び変異体の遺伝子解析を重点課題として、種子及び栄養繁殖性作物、果樹、林木等、木本性作物、花卉等、様々な作物を対象として研究を行っている。 放射線照射施設は、ガンマーフィールド(半径100メートルの屋外照射施設)を主体として、組織、種子、植物個体あらゆる条件下における照射に対応でき、これまで多くの有用変異体作物を作出するとともに、全国からの依頼照射によって活用されてきている。近年の主な成果では、黒斑病耐病性ナシ「ゴールド二十世紀」「寿新水」「おさゴールド」、米アレルギー性疾患を対象とする「低アレルゲン米」、腎臓疾患に要求される「低グルテリン米」、この他常緑芝、花の変異体等、多くの品種を作り出している。放射線育種は、今後さらに多様化する農作物の要請に応える重要な技術分野として期待できる。 <更新年月> 2006年02月
<本文>
1.突然変異育種 遺伝的形質を利用して生物を改良し、新しい有益な品種を育成することを育種という。育種には分離育種(目的にあった個体を選抜していくだけ)、交雑育種(遺伝的に異なる品種を人為的に交配する)、倍数体育種、突然変異育種(人為的に誘発された突然変異を利用する)等がある。放射線育種に代表される突然変異育種法は、交雑育種と比べた場合、いくつかの利点を持つ。ひとつは既存の品種に存在しない遺伝子や野生種にしか見出せない遺伝子を、対象品種に誘発させて利用できること。もう一つは、原品種の遺伝子型を大きく変えずに特定の形質を突然変異で改良でき、品種育成の時間短縮等ができること。他にも、交雑育種を適用しにくい作物の改良に役立つということが挙げられる。突然変異は放射線や薬剤等を用いて人為的に起すことができるが、ここでは放射線による突然変異のみについて述べる。 2.放射線育種の手法 放射線により突然変異を起す方法としては三通りある。一つは、生物に放射性同位元素を吸収させ内部照射させる方法である。この場合、半減期が短く強いβ線を放出する32Pが用いられていることが多い。放射性核種を吸収させたものは、仮に半減期が何十倍の時間が経過して放射線が検出されなくなっても、汚染物質として扱わなければならないので、その世代はもちろん、次の世代も外部へは持ち出せない。そのため、この間は、通常の育種場所と違う場所で育てなければならないという欠点がある。 もう一つは強い透過力を持った放射線を外部から照射するという方法があり、現在はこの手法が多い。最後の一つは強い粒子線を外部から照射し、生体内の原子を放射化させるものである。この場合も、次々世代にならないと外に持ち出せないが、γ線等で起こせない変異が起きる事がある。突然変異に利用される放射線には、α線、β線、γ線、X線、熱中性子、イオンビーム、紫外線がある。放射化を利用しない外部照射にはγ線、X線がある。放射性同位元素が得られなかった戦前は医療にも使用される硬X線が使われていたが、X線を継続して照射しなければならず、それにX線管が耐えられないこともあった。そこで戦後、放射性同位元素が手に入るようになってからはγ線が主に使われてきた。近年では管理が簡便で通常の実験室でも照射ができる軟X線による照射も再び利用されつつある。 外部照射による突然変異育種が化学変異原による突然変異育種より優れている点は2つある。一つは、望ましくない突然変異を併発させる可能性が少ないことである。化学変異原は、γ線、X線よりも突然変異の効率が高いが、高い突然変異率をもたらす処理は、目的の突然変異を起こした個体を選抜しても、望ましくない突然変異を併発させる可能性がある。もう一つは大量の個体や大型の個体を処理するには、化学変異原の溶液を大量に準備する必要があることである。化学変異原は発がん物質である場合が多く、作業者の健康上の危険の他、作業上困難を伴うことがある。また、大型の個体では不均一に浸透する可能性があり、廃液処理も手数がかかる。 放射線育種は、放射線で突然変異を起したものそのものが一つの品種となる場合(直接利用)と、別の品種をかけ合わせる事により一つの品種として成立させる(間接利用)場合がある。日本の場合、γ線による突然変異体がそのままの品種として育成されたものとして2001年11月までに約120品種が種苗登録されている。イネの場合、直接利用は19種類であるが間接利用は109種である。直接利用の例としてはレイメイや美山錦が、間接利用の例としては、おくほまれ等が挙げられる。 3.育種の歴史 有望な個体を選び、他の個体と区別して毎年栽培し続ける分離育種の原型は栽培とともに始まっていた。人為的交配により新しい品種ができることは16世紀に知られ、交雑育種の試みは19世紀から盛んになった。近代遺伝学に基づく育種はメンデルの遺伝学が再発見された後であり、ほぼ20世紀からである。一般に認められている人為突然変異の報告は、1927年にマラー(Muller)がショウジョウバエにX線を当てた際の変異誘発の報告と、1928年に米国ミズーリ大学のStadlerが、トウモロコシや小麦の発芽種子にX線を照射して、人為突然変異誘発に成功させた例であろう。 1934年に、インドネシアでX線を用いた人為突然変異による最初の育成品種、「Clorina F1」がタバコで育成された。同じ年、日本では市島がイネのX線照射による突然変異の誘発を確認している。戦前(戦時中も含む)の日本では、京都大学の木原教授のX線発生装置による突然変異の研究や理化学研究所の仁科研究室を中心としたサイクロトロンによる突然変異の研究が行われていたが、さしたる成果はでなかった。 日本では1949年から放射性同位元素の輸入禁止が解除され、育種目的でも線源を使うことができるようになった。1950年に農林省農業技術研究所および農事試験場の設立された。農業技術研究所で初めて行われた放射線突然変異の手法は、水稲種子に放射性のリンを吸収させ突然変異を起させるというものであった。1956年に国立遺伝学研究所にガンマルームが設置され、1957年には農業技術研究所(神奈川県平塚市、1977年に筑波に移転)にも60Coを線源としたガンマルームが設置された。また1958年には国立遺伝学研究所に中性子線照射室が、林業試験場(現・森林総合研究所)、蚕糸試験場(→蚕糸・昆虫農業技術研究所→現・独立行政法人農業生物資源研究所)、富山県立試験場(現・富山県農業技術センター)にもガンマールーム(アイソトープ照射室)が設けられた。従来の照射箱やガンマルームでは、大きい個体の照射、大量の個体の照射、自然条件下での照射、低線量長時間照射等に対応できないことから、ガンマフィールドが必要となってきた。1957年にアメリカの原子力委員会から、日本の原子力委員会に、もし日本がガンマフィールドを作るのであれば、コバルト線源(200キュリー)と照射装置一式を寄贈してもよいと申し出があった事から、ガンマフィールドを設ける事とした。場所は複数の候補地の中から茨城県大宮町が選ばれた。1962(昭和37)年4月2日、本格的な照射試験が開始された。この試験場の施設として、1964(昭和39)年には亜熱帯・暖地性の生育期に照射するためのガンマーハウス、1967(昭和42)年2月には高線量率短期間の照射を行うためのガンマルームが設置されている。 1964年にFAOとIAEAの共同による原子力農業部門が設けられ、その中で遺伝育種科では放射線利用による突然変異育種のための研究、研修、成果の広報が行われている。現在、日本において、ガンマ線照射による突然変異誘発を用いた品種改良は、主として独立行政法人 農業生物資源研究所が所有する放射線育種場のガンマーフィールドにおいて行われている( 表1 および図1 参照)。このガンマーフィールドは、中央に60Coの線源を持ち、半径100メートルの円形圃場で、様々な植物を育てている。詳細は「農業生物資源研究所 放射線育種場 (原子力百科事典、10-04-08-02)」参照。現在、世界中で多くの品種が放射線照射による誘発変異から得られており、食糧の増産や農薬の軽減等にも貢献している。 4.最近の品種改良の研究 作物の品種改良には、今後ますます放射線が利用され、我々に有用な品種の植物が生産されることと思われる。最近の研究では、放射線育種場と日本原子力研究所高崎研究所(現日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究所)の共同研究により、菊の培養外植片にイオンビーム照射し、花色変異系統を多数作出することに成功している。イオンビーム育種については「イオンビームバイオ技術の現状 原子力百科事典(08-03-01-07)」参照。 <図/表> 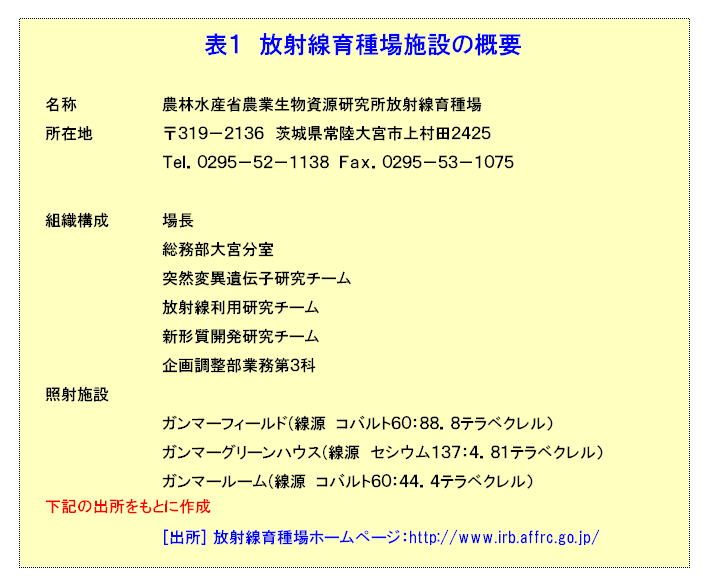

<関連タイトル> イオンビームバイオ技術の現状 (08-03-01-07) 放射線育種の利用例 (08-03-01-09) 放射線と突然変異 (09-02-06-02) 放射線による植物への影響 (09-02-01-05) 農業生物資源研究所放射線育種場 (10-04-08-02) <参考文献> (1)鵜飼 保雄、植物育種学、東京大学出版センター(2003年) (2) 農業生物資源研究所 放射線育種場:放射線育種場のあゆみ:40年を顧みて (3)日本文化振興財団:「放射線の話」 (4)(財)原子力安全技術センター:「放射線利用」 (5)科学技術庁:「放射線と人間環境」 (6)農林水産省農業生物資源研究所放射線育種場:パンフレット (7)山口 勲夫、突然変異育種の成果と展望−−我が国における突然変異育種の成果と展望(1)、農業技術、55(4) (2000) (8)鵜飼 保雄、突然変異育種の成果と展望−−放射線育種における照射方法の効率(2)、農業技術、 55(5)230-234 (2000) (9)永冨 成紀、突然変異育種の成果と展望−−植物の培養系を用いた放射線育種技術の成果と展望(3)、農業技術、 55(6) 274-278 (2000) (10)天野 悦夫、突然変異育種の成果と展望−−突然変異育種を巡る国際情勢と展望(8)、農業技術、55(11) 565-569 (2000) (関連ホームページ) (突然変異育種のデータベース)IAEA/FAO (突然変異育種の育種マニュアル)アジア原子力協力フォーラム(FNCA)
|

