|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
個体は細胞により構成されており、その細胞はDNAに刻まれた遺伝情報にもとづいて働いている。この遺伝情報に生じた異常が突然変異である。生殖細胞(精子、卵子)に生じた突然変異は遺伝病の原因になりうるが、劣性の突然変異として隠されたままのことも多い。放射線誘発突然変異は、マウスでは明瞭な結果が得られているが、人間では十分なデータがない。血液細胞などの体細胞にも突然変異は生じるが、この場合にはがんなどの原因になる可能性がある。しかし異常が子孫に伝わることはない。原爆被ばく者の血液細胞に関する調査では、被ばく放射線量に比例した突然変異細胞頻度の上昇が認められている。 <更新年月> 2000年03月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.遺伝子とは ヒトの細胞核には46本の染色体がありその各々は遺伝物質であるデオキシリボ核酸(DNA)と種々のタンパク質により構成されている。DNAの模式図を 図1 に示す。DNAは糖とリン酸の長い鎖にアデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)とよばれる4種の塩基がくっついた格好をしており、通常2本鎖の状態で存在する。AはT、GはCとのみ向いあって並ぶ性質があるので、この2本鎖は互いに補いあう情報を備えているわけで、写真のポジとネガの関係にたとえられる。この対合したAとT、GとCを塩基対とよび、1個の細胞中には60億(6.E9)個の塩基対が存在する。これらの中の一部は遺伝子とよばれる構造をつくっており、種々のタンパク質合成に必要なアミノ酸配列の情報と、身体のどういう組織でその遺伝子を働かせるかという情報をあわせてもっている。 2.突然変異の種類 この遺伝子を構成する塩基の並び方に異常(即ち突然変異)を生じると、その遺伝子からつくられるタンパク質が異常なものになり物質代謝が正しく行われなくなる。 突然変異の中には、遺伝子を構成している数1000個の塩基対のうちたったひとつが別のものに変化する場合(塩基対置換)もあれば、遺伝子の一部もしくは全体が失われる場合(欠失)、余分なDNA断片が遺伝子内に挿入されたり、あるいは遺伝子の一部が重複したりする場合もある。 こうして生じた突然変異遺伝子は、すぐに病気に結びつくとは限らない。というのは、体を構成している細胞は、父親と母親から受け継いだ23対の染色体をもっているので、ほとんどの遺伝子は細胞当り2コピーずつ存在する。従って、もしどちらか一方に異常が起こっても、残った一方が正常にはたらいている限りは病気として発症しないことが多い。このような、正常遺伝によって隠されるような変異を劣性突然変異とよぶ。赤緑色盲や血友病はX染色体に起こった劣性突然変異なので男性では発症するが女性はX染色体が2本あるので普通は発症しない。他方、正常遺伝子が存在していても変異が発現する場合を優性突然変異とよぶ。家族性大腸ポリープ症、ハンチントン舞踏病などの病気が知られている。 3.放射線と突然変異 劣性突然変異は、親が被ばくしても次の世代ですぐに病気としてあらわれることは大変まれである。集団にあらかじめ隠された形で存在していた突然変異遺伝子とたまたま組合せになった場合にのみ病気が出ることになる。細胞には、多数の遺伝子(10万個とも言われている)が存在しているので、ヒトにおいて、親の被ばくによって劣性遺伝病が増えたかどうかを調査するには何世代もの大規模な追跡が必要となり、実際上は不可能である。例外は母親が被ばくしたことによりX染色体に突然変異が生じ、それが男児に伝えられた場合である。このような時には、女性にとっては隠されるはずの劣性突然変異でも、男性にはX染色体が1本しかないので発症する。 他方の優性突然変異の場合には、その名の示す如く、異常は次の世代で出現する。 もともと突然変異は頻度が低いため、実験には 100万匹以上の動物が必要で、このような研究にはマウスをおいて他にはない。詳細は紙面の都合で割愛せざるをえないが、結果を要約すると、 (1) 放射線により生殖細胞に生じる突然変異頻度には精子と卵子でちがいがある。 (2) 同じ合計線量でも、長期間にわたって少しずつ与えた方が変異の出来方が少ない。(線量率効果) (3) この線量率効果は、精原細胞の場合には急照射の場合の1/3位にまでしか下がらないが、卵母細胞の場合にはほとんど対照群と同じ位まで低下する。 (4) 中性子線は、X線やガンマ線と比べて、線量は同じでも効果が何倍も大きい。しかも、少しずつ長期にわたって照射しても、変異頻度は低下しない(即ち、線量率効果がない)。 (5) 放射線によって生じたと考えられる変異の中には、遺伝子の一部あるいは全体が欠失したものが多い。同様の観察は、試験管内で培養した細胞を照射して得られた突然変異についても知られている。 (6) 雄の場合には、精子のつくられてくる段階によって放射線に対する感受性が変化する。精子や精細胞は体内にとどまっている期間は数週間にすぎないが、精原細胞よりも感受性が高く、線量率効果もほとんどないと考えられている。 (7) 優性突然変異は、白内障と骨格形成異常についてのデータが得られている。 以上述べてきたのは生殖細胞に生じた突然変異についてであるが、放射線に被ばくすると血液などの細胞にも種々の突然変異が生じる。赤血球のアミノ酸変化やリンパ球の突然変異を生じた細胞の頻度を調べれば、染色体異常頻度と同じように、被ばく線量の評価ができる可能性がある。原爆被ばく者の赤血球における突然変異頻度は現在でも放射線の影響が認められるので、恐らく生涯にわたって生じた変異は保持されていると思われる。しかし、低線量率長期被ばくの場合にどこまで低線量の放射線による突然変異が検出されるかはまだ明らかではない。 4.突然変異検出の実際がいかに大変か 放射線の細胞に及ぼす作用は、主としてDNAのでたらめな切断にあると考えてよい証拠がある。この切断が修復されなければ細胞は分裂をつづけられなくなるので遺伝的影響はない。しかし、修復の誤りにより欠失などの突然変異が生じる。欠失が全DNAの1%にも達すると、流産や奇形を生じ易くなるというマウスの実験結果がある。しかし人間の流産や奇形はまれではないし、その大半は原因不明である。従って、流産や奇形の頻度から、生殖細胞における低線量放射線の被ばくを推定するのは無理である。他方、被ばくした親から生まれた子供における突然変異の調査も大変な労力がかかる。マウス精原細胞における毛色遺伝子の劣性突然変異誘発率は、0.10Gy急照射の場合、遺伝子当りの平均値は2.4×10E−6である。つまり、あるひとつの遺伝子について100万個の細胞を調べて2.4個の変異が過剰に見られるにすぎない。非被ばく対照群でも100万個の細胞を調べれば数個の変異は存在するから、0.1Gyの放射線の遺伝的影響を示すのはほとんど実現不可能である。人間についての調査を考えると、100万人を対象にはできないから、例えば1000人を対象にして各々1000個の遺伝子を調べて合計100万遺伝子を調査するというような方法になるのだが、いかにしても0.1Gyの影響をきちんと測定できるものではないことは理解していただけるだろう。 体細胞に起こった突然変異は、一部はがんの原因になる可能性がある。先に述べたように放射線による突然変異には欠失型のものが多い。現在の知識では、がんをいくら顕微鏡で調べても、放射線によるものか自然に起こったものかは区別できない。しかし、放射線が自然には余り起こらない欠失突然変異を生じ易いとすれば、がんの遺伝子を詳しく調査する事によって、将来は放射線の関与を示すことができるようになるかもしれない。 <図/表> 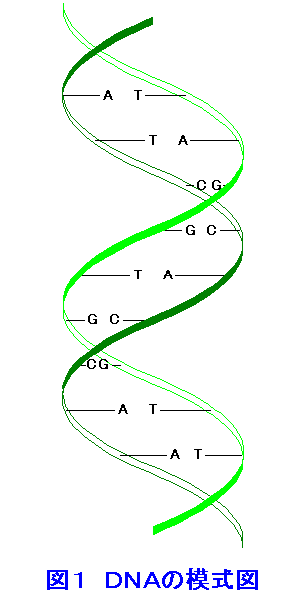
<関連タイトル> 遺伝子と遺伝子暗号DNAの構成 (09-02-02-02) 染色体の構成 (09-02-02-03) 放射線のDNAへの影響 (09-02-02-06) 被ばく線量に応じた細胞の反応にかかわる諸モデル (09-02-02-09) 放射線の遺伝的影響 (09-02-03-04) 放射線と染色体異常 (09-02-06-01) 現在の環境における遺伝疾患の種類と自然発生率 (09-02-08-07) <参考文献> (1)サンカラナラヤナン(著),村上昭雄ほか(訳):電離放射線の遺伝的影響、サイエンティスト社 (1987) (2)放射線被曝者医療国際協力推進協議会(編):原爆放射線の人体影響1992、文光堂 (1992) (3)川上 正也(著):遺伝子についての50の基礎知識、講談社ブルーバックス
|

