|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
高温を要しない核融合反応の一方式としてミューオン触媒核融合反応がある。これは重水素−重水素(D-D)あるいは重水素−三重水素(D-T)分子の周りを回る電子をマイナスミューオンに置き換えクーロン障壁を変化させ、分子内の核間距離を電子とミューオンの質量の比である約200分の1程度まで縮めることで低温での大きな核融合反応率を達成しようとするものである。基礎的パラメータの確定やメカニズムに関する基礎研究とともに、この反応を利用するエネルギー生産に関する研究も進められている。 <更新年月> 2004年07月
<本文>
1.ミューオンとは 低温核融合反応を実現させるための一つの方式としてミューオン(μ)触媒核融合(μ-catalyzed cold fusion, μCF)がある。ミューオンは電子の207倍の重さを持つ不安定な素粒子であり、正及び負の電荷を持ったものがある。人工的にミューオンを作りだすには、非常に高いエネルギーを持った陽子や重イオンをベリリウムや銅等の金属に照射する。この時π中間子(パイオン)と呼ばれる素粒子が発生するが、正あるいは負の電荷を持つパイオンは金属中から飛出す。真空中のパイオンは0.026マイクロ秒程度の寿命で正及び負電荷のミューオンに変換する。できたミューオンの寿命は約2.2マイクロ秒であり、やがて陽電子及び電子に変る。 2.エネルギー利用への最初の提案 ミューオン触媒核融合の可能性は、1947年にFrankによって提案されたパイオンがミューオンに崩壊する過程の解釈に関する仮説(文献1)のなかにすでに見出される。この現象はそれより約10年後に実験的に確認(文献2)されることとなったが、当時の評価ではエネルギー源としては役に立たないと考えられていた。しかし1970年代に入って、理論の展開(文献3,4)、さらには旧ソ連を中心とした先駆的な実験(文献5)等を基盤に関連研究が急速に発展し、以後着実に基礎データが蓄積されるとともに、ミューオン触媒核融合利用の夢が再燃し、1980年代になってこのミューオン核融合反応を利用するエネルギー生産にとって必要な色々な研究が並行して進められることとなった。1990年代以降、加速器技術の進歩に伴う加速エネルギーの増大などでパイオンの生成効率が向上するなど実験面での進展が図られており、2000年代に入っても加速器の新設計画が進むなど、基礎的な段階ではあるが活発に研究が続けられている(文献6)。 3.ミューオン触媒核融合の原理 ミューオン触媒核融合ではDDあるいはDT分子の周りを回る電子を“重い電子”であるマイナスミューオンに置き換えクーロン障壁を変化させ、分子内の核間距離を電子とミューオンの質量の比である約200分の1程度まで縮めることで(10-8cm→5×10-11cm)大きな核融合反応率を達成する(図1参照)。1粒子が1秒間に起こす核融合反応率は、代表的熱核融合装置であるトカマク炉中での反応と比較すると千倍程度も大きくなると試算されている。 4.ミューオンをどうして得るか ミューオン触媒核融合で重要な役割を果たすミューオンは自然界から多量に得ることができないうえに短寿命であるために、加速器で発生したミューオンを利用することになる。ミューオンは図1に示したように、ミューオン分子を作って核融合反応を起こしたのち、再び自由になってこのサイクルを繰り返すので、結局ミューオンは反応を促進する触媒としての役割を果たしていることになる。したがって、一つのミューオンが何回触媒として利用し得るかということが、ミューオン触媒核融合がエネルギー生産技術として成り立つか否かを支配する。ミューオン触媒核融合サイクルの中でDTミューオン分子が1回の核融合反応を起こす時間は10-11秒程度と、ミューオンの寿命約2.2マイクロ秒と比べても20万分の1程度と極めて短いので寿命自体が問題とはならない。このサイクルを支配する大きな要因はミューオン分子の生成の速さと、核融合後にミューオンがヘリウム原子核(即ちα粒子)に捕束されてしまう確率(α-付着率)である。特に現状では後者が最大の支配因子であると考えられている。 5.ミューオン当たりの核融合反応率が決め手 ミューオン触媒核融合を応用面から考える時重要な量は、ミューオン当たりの核融合反応率である。これはミューオンの寿命、巡回率、及び損失率の関数として表される。ここでミューオンの巡回率は主にミューオン分子生成率(温度と密度に依存する値)とトリチウム濃度(DT反応を例にとった場合)から決る量である。一方損失率は、主としてα−付着率で決定される。このパラメータは反応直後には大きな値(初期付着率)をとるが、その後の再活性化過程でミューオンがαから開放され、小さな値に落ち着くものと考えられており、再活性化効率の高い高密度状態で低い値が得られている。 現在ミューオン触媒核融合研究の中心は、このような基礎的パラメータを確定することと、この過程を支配するメカニズムを明らかにすることであり、そのための理論的、実験的研究が精力的に進められている。 6.エネルギー生産プロセスへの展望 現在の実験データと理論上の評価に基づく限りでは、未だ入力エネルギーを超えるエネルギー出力が得られる条件は達成されておらず、ミューオン触媒核融合は純核融合炉として成り立つかどうか明確な段階にはない。しかし、最近の実験結果では、陽子ビームをDTターゲットに衝突させる方法で6000−7000個/秒のミューオンを発生させた後、その触媒反応で100万回/秒の核融合反応を起こすことに成功している。これは発生した1ミューオン当り約150回のDT核融合反応、即ち2.6GeVのエネルギー発生に対応している。当面の目標である科学的ブレークイーブン(入出力エネルギーの平衡)条件達成には、この約2倍(1ミューオン当り約300回、約5GeV)の性能が必要であり、さらに経済的ブレークイーブン条件には、現状の約6倍(1ミューオン当り約900回、約16GeV)の核融合反応効率が必要とされている。 これらの条件達成に向けた課題は以下のとおりである(文献6)。 ・DTターゲットの高密度化、温度の上昇、トリチウム/重水素比率の最適化などを行い、DT反応の高効率化を図る。 ・重水素分子やDT分子レベルの活性度をレーザー光などで上げDT共鳴分子の生成率を上昇させる。 ・α−付着率を下げ、ミューオンの再活性化率を上げる各種試みを実施する。 ・高密度ミューオンビームを高圧高密度の固体DT燃料に入射することで、付着したミューオンの再活性化につながるα粒子同士の反応を促進する。 7.他の利用法 熱核融合炉の点火手段としてミューオン触媒核融合を利用する方式の提案もなされている(文献7)。この場合の最大の課題はミューオンの収束と減速とを効果的に行い、必要な領域で集中的に反応を起こさせる方法を開発することである。しかし現状では著しく困難であると考えられている。 これに対して現行の核分裂炉によるエネルギー生産システムにおいて、ミューオン触媒核融合反応を大いに活用しようとする概念がある。例えば、核融合反応で発生する大量の中性子を利用してブランケット内でウラン、プルトニウムなどの核分裂をおこさせ、そのエネルギーを得ようとするもの、あるいは同様にしてプルトニウムなどの分裂炉用の核燃料を生産してこれを利用しようとするものなどがその例である。これらが現行のミューオン触媒核融合炉概念の主体である。 <図/表> 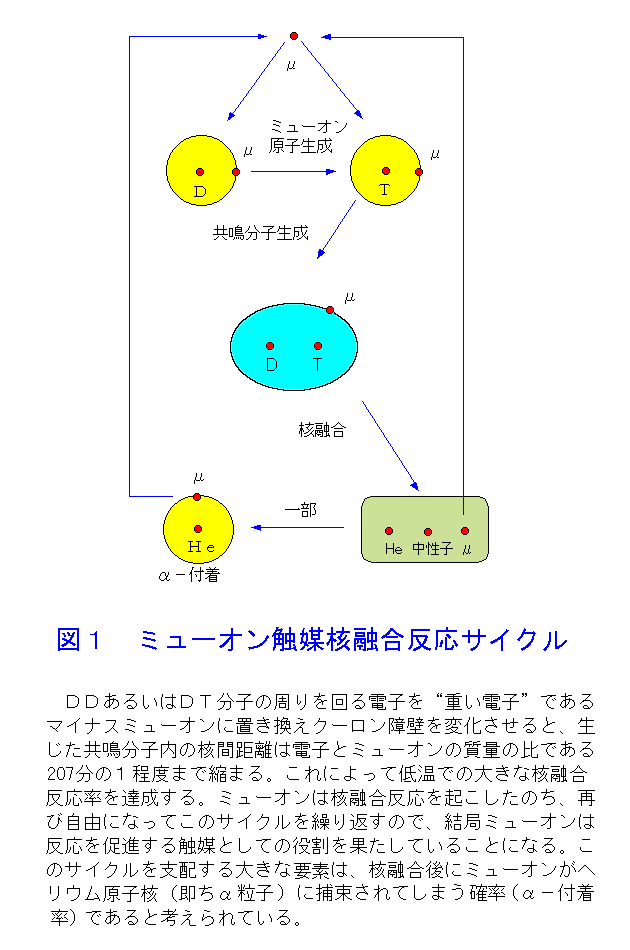
<関連タイトル> 核融合反応の分類 (07-05-06-01) 低温核融合はエネルギ−生産プロセスとなりうるか (07-05-06-05) <参考文献> (1)F.C.Frank:Nature,160,525(1947) (2)L.W.Alvarez,et.al.:Phys.Rev.,105,1127(1957) (3)E.A.Vesman:Sov.Phys.JETP Lett,5,91(1967) (4)S.S.Gerstein & L.I.Ponomarev:Phys.Lett.,72B,80(1977) (5)V.M.Bystristky,et.al.:Sov.Phys.JETP,49,232(1979). (6)K. Nagamine, ”Introductory Muon Science (Chapter 5: Muon catalyzed fusion),” Cambridge University Press (2003). (7)W.P.S.Tan:Nature,263,656(1976)
|

