|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
これまでに報告されている重水素-重水素核融合反応(D-D)あるいは重水素−三重水素(D-T)核融合反応の種類は、反応原理、反応条件等の違いによって幾つかに分類できる。反応温度の違いに基づくと、核融合反応は大きく高温核融合と低温核融合(ミューオン触媒核融合反応)とに分類できる。 <更新年月> 2010年07月
<本文>
核融合反応とは2個、あるいはまれにそれ以上の原子核が衝突して核同士が融合する反応をさす。衝突する原子核が水素やリチウムのように軽い場合には、融合により大量のエネルギ−が放出される。エネルギ−生産をめざして現在進められている核融合反応研究の主対象は重水素−三重水素(D-T)及び重水素−重水素(D-D)の核融合反応である。原子核はそれぞれプラスの電荷を持っているため、ク−ロン力によって反発しあう。この反発力を超えて複数の原子核が近づき融合するためにはそのク−ロン障壁を乗り越えなければならない。重水素原子核同士を例にとると、その障壁の高さは約0.3MeVであり、これは30億度の温度に相当するエネルギ−である。 1.高温核融合−太陽のエネルギーを生み出している原理と同じもの− したがってこの障壁を乗り越え反応を起こさせるための方策の一つは、原子核を十分高温に加熱することである。これがいわゆる「高温核融合反応」である(図1参照)。これは熱核融合反応とも呼ばれるが、単に“核融合”と呼ぶだけでこれをさす場合も多い。この反応系では原子核は電子を遊離したプラズマ状態となっており、磁場を利用してプラズマを一定の空間内に閉じ込めることによって原子核同士が反応しやすくする。反応の確率はプラズマ温度とともに大きくなる。外部から注入するエネルギ−と、プラズマ中の核融合反応から生じるエネルギ−とが等しくなる「臨界プラズマ」条件を達成するためには、一億度のプラズマ温度、百兆個/cm3のプラズマ密度、1秒間のプラズマ閉じ込め時間、という反応条件(ロ−ソン条件)を作りだすことが必要である。 核融合反応を起こさせる他の方策として、上記の場合のような高温を必要とせず、低温で実現するミューオン触媒核融合反応、及び最近注目されている常温核融合反応とが提案されている。これら2種類の異なった方法を、反応温度を尺度として「高温核融合反応」と対比する意味で、「低温核融合反応」と総称している。 2.ミューオン触媒核融合−通常の電子を重い電子で置き換えられると実現する方法− 「ミューオン触媒核融合」でD-DあるいはD-T分子の周りを回る電子を“重い電子”であるマイナスミューオンに置き換えることで電子軌道が極端に小さくなり、結果として原子同士をより近づけることが可能となる。これにより分子内の核間距離を電子とミューオンの質量の比である200分の1程度まで縮めることで大きな核融合反応率を達成する。 3.いわゆる「常温核融合」 1989年3月下旬に公表された米国の2件の実験結果(ユタ大のポンズーフライシュマン、ブリガムヤング大のジョーンズ)に端を発して、「常温核融合反応」と新聞紙上、TV等で取り上げられ、簡易な装置で核融合反応が実現できるとの触れ込みで世界中で追試が行われた。その後の詳細な検証の結果、核融合反応の証拠はまったく得られず、当初大量に発生しているとされた過剰発熱も、熱量測定の結果、あったとしてもごくわずかであることが分かった。以上から「常温核融合反応」は化学反応による可能性が高いことが判明し、その化学反応の解明と実用性について検討するため、通産省(現経済産業省)は1994年に「新水素エネルギー実証試験プロジェクト」を開始した。このプロジェクトは5カ年計画で実施され1998年に終了した。実施結果の概要は以下のとおり。(1)過剰熱計測試験では、装置の計測精度をこえた過剰熱は観測されず、現状の学問的基盤と技術で新水素エネルギーの利用は困難と判断される。(2)反応生成物計測では有意な放射線は検出できなかったが、ヘテロ構造のPdからは統計上有意と考えられる中性子ならびに重陽子照射によるDD反応の異常増加が認められ、これらの結果の確認には、今後の基礎的な取り組みが必要と考えられる。 (前回更新:1997年3月) <図/表> 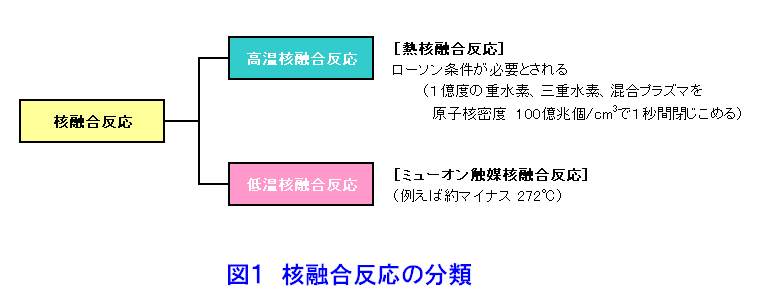
<関連タイトル> 常温核融合研究騒動 (07-05-06-02) 常温核融合反応追試実験 (07-05-06-03) ミューオン触媒核融合の原理と現状 (07-05-06-04) 低温核融合はエネルギ−生産プロセスとなりうるか (07-05-06-05) <参考文献> (1)立川圓造ほか:“常温核融合反応のすべて”、原子力工業、37(4),10-58(1991) (2)原研「常温核融合」検討グループ:常温核融合研究の最近、原子力工業、41(6),5-46(1995) (3)狐崎晶雄:解説核融合、JAERI-M 90-150(1996年5月改) (4)エネルギー総合工学研究所:新水素エネルギー実証技術開発総合研究報告書、NEDO-NHE-9704(1998)
|

