|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
致死効果をもたらさない低線量放射線の生物影響に関しては、染色体異常や突然変異の誘発が「急性効果」として、さらには遺伝的影響、畸形やがんの発生等々が「晩発効果」として古くから知られているが、低線量の放射線の作用については障害の誘発という心配よりもむしろ細胞の増殖が促進されたり、障害が減少したりする効果が認められている。これらの放射線の効果を逆に有益と解釈する現象(放射線ホルミーシス)が既によく知られている。 この効果が本当に有益かどうかは未だ議論のあるところであるが、1984年にオリヴィエらが発見した現象は、リンパ球をごく低濃度の放射性チミジン液で処理してから放射線を照射して染色体異常頻度を観察すると、その発生頻度は逆に通常の発生頻度より減少するという報告で、以来、この効果は「適応応答現象」と呼ばれることになった。その後、細胞実験系を中心として適応応答現象が広く知られ、その分子機構に関するモデルも提唱されているが、この現象が低線量放射線効果の研究、すなわち障害発現、がんの誘発、遺伝的影響、リスクなどの研究に重要な関連があるものとして注目されている。 <更新年月> 2004年02月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.放射線生物学および医学における適応応答 適応応答として最初に報告されたのは、オリヴィエら(Olivieri et al.;1984)によるヒトリンパ球に誘発される染色体異常頻度に関する研究で、370Bq/ml濃度のトリチウムチミジンで前処理したリンパ球に対して分裂間近いG2期で1.5GyのX線照射をすると、照射効果として染色体に誘発された染色分体型(クロマチッド型)異常頻度は前処理なしに照射した対照群のリンパ球より著しく低下したことを示した(表1)。その後、この適応応答現象は、植物細胞、昆虫、各種哺乳類培養細胞、培養リンパ球などの系から生体内細胞、職業被ばく者など生体における研究でも同様に知られてきた。リンパ球の長期培養では適応応答の欠失も報告されているが、さらに長期間の観察によると適応応答の欠失は一時的なものでなく、また一過性の生理学的条件に依存しているという訳でもないことが明らかになっている。種々の細胞で観察された適応応答現象を表2に示す。このようにヒトをはじめとして哺乳類(マウス、ハムスター)のいろいろな組織細胞で適応応答現象が観察されている。 2.ヒトの疫学調査および臨床医学の例 ヒトの疫学データを分析して微量線量域の放射線影響調査が行われている。例えば、中国の広東省には自然放射線が平均より約3倍高い地域があり、その地域住民の10年間にわたる健康診断を調べた結果が報告されている。それによると高バックグランドの住民の総死亡率は対照群の値とほとんど変わらないが、癌による死亡率は子宮頚部癌を除いて高バックグランドの住民の死亡率は統計的に有意に低いと報告されている。また、環境中のラドン濃度と肺癌の発生頻度との関係を統計的に解析した報告では、ラドン濃度の高い場所で、肺癌の発生頻度が低い傾向にあり、両者の間に直線的な線量効果関係は認められなかったとしている。 臨床医学の分野においては、微量照射により免疫機能が高まり、その結果抗腫瘍効果が促進される結果を示す実験的証明も出ている。この現象をふまえ、現在では試験段階ではあるが、悪性リンパ腫などの放射線治療に微量放射線が使われる様になってきている。 3.適応応答の研究 3.1 細胞生物学的研究法 細胞にあらかじめ前処理線量(Adapting or Conditioning dose) として低線量(例えば1cGy)の照射を行い、その後に実験線量(Challenging dose)として高線量(例えば1−2Gy)の照射を与えると、予想される実験結果は(1)前処理線量と実験線量から期待される複合効果より低い結果になる(適応応答)、(2)複合効果と同等の結果になる(相加効果)、(3)複合効果より大きな結果となる(相乗効果)、のいずれかになる。 3.2 薬理学的研究法 2種の薬剤が一つの標的に作用させたとき、期待される複合効果は、前記同様、(1)個々の薬剤効果の加算効果より減少した結果を得る(拮抗作用)、(2)個々の効果の加算効果と同じ結果を得る(加算効果)、(3)個々の加算効果より大きな効果を得る(相乗効果)のいずれかになる。 3.3 適応応答の機構 適応応答の機構としては、少なくとも2つのステップが必要と考えられている。その一つはポリメラーゼ関与する過程と新しいタンパク質の発現が関与する過程があると考えられている。とくに後者の過程は低線量放射線によって発現が誘導される遺伝子が重要であると考えられる。多分、これらの遺伝子のなかでDNA修復系の活性化、細胞周期、アポトーシス、さらには活性酸素解毒作用などを制御するものがあり、その活性を通じて適応応答現象を誘起していると考えられる。したがって、この現象を通じて低線量放射線の生物影響に関する研究が進むことは、ヒトの放射線障害や発がん、遺伝的影響などリスク評価に有効な発展があるものと期待される。 4.今後の進展 低線量放射線による刺激効果の機構が解明されることによって、微量線量域の線量・効果関係が明らかになるばかりでなく、放射線の生物作用として今まで考えられなかった特色ある実験事実を、様々な分野に応用するという点からも、重要な分野の一つになると考えられる。 <図/表> 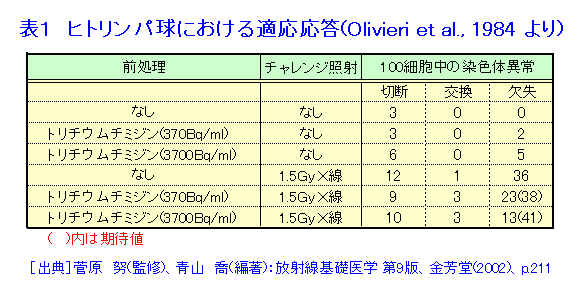
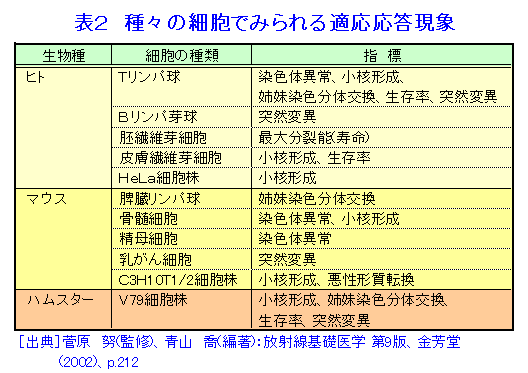
<関連タイトル> 線エネルギー付与(LET)・生物学的効果比(RBE)・放射線荷重係数(WR) (09-02-02-11) 放射線効果と修復作用 (09-02-02-12) 放射線の種類と生物学的効果 (09-02-02-15) 放射能泉と健康 (09-02-07-10) 放射線生物効果の年齢依存 (09-02-02-18) 放射線生物効果の年齢依存 (09-02-02-18) 中国の高自然放射線地域における住民の健康調査 (09-02-07-01) 米国自然放射線の疫学調査(アーチャーら) (09-02-07-07) <参考文献> (1)MACKLIS, R.M. and BERESFORD, B., 1991, Radiation hormesis, Journal of Nuclear Medicine, 32, 350-359 (2)松平寛通(監訳):「放射線ホルミシスI,II 」、ソフトサイエンス社(1990) (3)菅原 努(監修)、青山 喬(編著):放射線基礎医学 第9版、金芳堂(2002) (4)Mortazavi, S.M. Javad, 2004, An Introduction to Radioadaptive Response, http://www.angelfire.com/mo/radioadaptive/introrar.html
|

