|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
生体には、いくつかの防御機構があり、放射線障害から正常な状態に戻す能力が備わっており、これを回復または修復という。この中には、DNA 分子や細胞内構造の損傷を修復する細胞内修復と細胞集団レベルでの再生を含む機能の回復があり、個体レベルでの回復は、これらの総合結果である。細胞内修復現象は、高LET放射線では観察し難い場合がある。また、低LET放射線の線量率効果は主に修復によると考えられる。 <更新年月> 2002年11月
<本文>
生体が放射線を受けると、水を含む生体構成分子はそのエネルギーを吸収して、励起や電離を生ずる。これが原因となってDNAなど生体にとって重要な高分子に変化が起こり、次に生化学的変化をひき起こし、種々の生物学的障害が起こす。一方生体にはいくつかの防御機構が備わっていて、あらゆる段階において損傷を正常な状態に戻す能力がある。物理化学的なレベルで生成される損傷に対して、その細胞の生存率などによる放射線感受性を比較すると99%以上の損傷は修復されていると計算できる事から、損傷の修復が放射線に対する感受性を決定する上で極めて重要な意味を持つ。ここで、細胞または細胞集団でみた機能の障害(生存率の低下、突然変異の上昇、器官の機能低下など)が軽減される現象を「回復(Recover)」と呼び、DNA損傷などの分子レベルでの損傷が治される現象を「修復(Repair)」と呼ぶ。 1.細胞内回復(修復) 放射線照射により損傷を受けた分子または細胞内構造が修復される。DNAは生体機能の維持にもっとも重要な役割を担っていて、DNA損傷の修復によって細胞の機能が回復される。DNA損傷には主に紫外線によって生じるヌクレオチド二量体(ダイマー)の形成や、主に電離放射線によるDNA単鎖切断、DNA二本鎖切断、塩基欠失や塩基損傷、DNA間あるいはDNAと蛋白の架橋などがある。これらの損傷の修復には機構の明らかになっている光回復、除去修復、非相同末端結合や相同組換え修復などが知られている。 1.1 DNAの塩基損傷・一本鎖切断の修復 紫外線によるヌクレオチド二量体形成によるDNA損傷は、一部の生物では光回復酵素と可視光線によって修復されて細胞が機能を取り戻すことから光回復と呼ばれる。また別に除去修復があり、暗所でもダイマーを含むDNAの損傷部分を切り出し、あとを他のヌクレオチドで埋める修復過程(除去修復)がいくつかの酵素によって行われる。この除去修復は高等動物の細胞でも認められている。電離放射線による損傷も障害部分の切り出しと再合成で大部分は修復される。 1.1.1 光回復 ヌクレオチド二量体の形成は、殺菌灯などの短波紫外線によって効率的に形成されるが、一方長波長紫外線によって効率よく修復される。光回復酵素と呼ばれているフラビン酵素が長波長紫外線を吸収し、そのエネルギーで二量体を直接切出して傷をもとどおりにする。 1.1.2 塩基除去修復 除去修復には塩基除去修復とヌクレオチド除去修復が知られていて、損傷のある塩基の部分だけを切り出した後、正しい塩基を挿入する修復である。損傷塩基に特異的なDNAグリコシラーゼにより塩基の切出しが行われ、塩基欠失(AP)部位の糖をAPエンドヌクレアーゼ等が切出した後、DNA合成酵素等が正常なヌクレオチドを挿入してもとどおりにする。DNAグリコシラーゼにはそれぞれの損傷の種類に対応した多くの種類が存在することが知られている。 1.1.3 ヌクレオチド除去修復 ヌクレオチド除去修復は複数の酵素が損傷を受けた塩基を認識し、損傷のある塩基の周辺の広い範囲の塩基を取り除いた後、DNA合成酵素が修復合成を行い最後にリガーゼが間隙を結合する。ヒトでこの過程に関連する遺伝子を欠いた遺伝疾患があり、色素性乾皮症と呼ばれて紫外線に高感受性である。 1.1.4 組換え修復 DNA複製が修復前に開始した場合には損傷部分でDNA複製が一旦停止し、相同なDNA間で組換えが起こり、複製が完了した側のDNAのテンプレートを基にして複製でできなかったDNA部分が合成される。損傷は残ったままであるが、その後ヌクレオチド除去修復によって修復される。 1.1.5 SOS修復 SOS修復は損傷を取除いて正しい塩基を組み込んで修復を行う機構ではなく、DNA複製における複製の正確さを犠牲にして、DNA合成の伸長を強硬に続ける補助経路である。このため複製後のDNAには間違った塩基(情報)を多く取り込むかもしれないが、確率的に間違った塩基が入ってもDNA合成を終わらせることが生命にとって有利である場合があるかもしれない。 1.2 DNA二本鎖切断と修復 二本鎖DNA切断は細胞死の原因となるが、これも多くは再結合によって修復される。近年知られてきた哺乳動物のDNA二本鎖切断の修復機構には主に相同組換え修復と非相同末端結合による修復がある( 図1 )。 1.2.1 相同組換え修復 相同組換えは二本鎖切断を受けた染色体DNAがヌクレアーゼとヘリカーゼによって一本鎖部分が残るように切断端の前後が切出され、組換え修復と同様に損傷を受けていない相同な染色体DNAとの交叉が起こって正常染色体の遺伝情報を用いてDNA合成がなされ、最後に交差部分が切断・再結合されて修復を終える。このため、間違った修復を起こさないので、細胞の機能が完全に回復する。 1.2.2 非相同末端結合修復 非相同末端結合は相同な染色体DNAの遺伝情報を用いないで、切断端の損傷部位が取り除かれた後、直接ヌクレオチドが挿入されて再結合が起こる。この場合、正しい遺伝情報に基づかない塩基の切出し・挿入が起こるので間違った遺伝情報を持つようになる場合が多く、染色体の組換えなども起こしやすいので、修復が起こっても細胞の機能は回復できない場合もある。 1.3 亜致死損傷・潜在的致死損傷と回復 現象論的な立場から、放射線による損傷は、回復し得ない致死損傷(LD)と回復可能な回復性損傷に分けられる。回復性損傷はさらに、亜致死損傷(SLD)と潜在的致死損傷(PLD)に分けられる。この二つの損傷の修復(または障害からの回復)がそれぞれ亜致死損傷修復・回復(SLDR:Repair SLD)、潜在的致死損傷修復・回復(PLDR)と呼ばれ、現象諭的に知られている。しかしそれらに関与する遺伝子や損傷の実体については知られていなく今後の課題である。 1.3.1 亜致死損傷回復と線量率効果 培養細胞の放射線効果は増殖能の存否を指標にして生存率曲線と呼ばれる線量効果関係を表すことができ、低LET放射線の低線量域では致死効果が現れにくく、生残曲線に肩ができる。しかし、同じ線量を数回に分けて照射すると生残率が増加し、その増加は第1回照射によって生じたSLDの修復によることが明らかになった( 図2 )。これは放射線によって細胞の中に死に至らないSLDが誘起され、これがあるレベルまで蓄積すると、致死損傷に転化して細胞が死ぬことを示す。 1回線量を小さくして分割回数を多くした多分割照射や、単位時間当たりの照射線量を小さくした低線量率照射では、急性照射の生存率曲線の初期勾配に斬近する生存率曲線となり生存率は上昇する。これは線量率効果の原因となっていて、生存率は亜致死損傷の生成と修復のバランスで決まる。また、がん治療では多分割照射が行われているので亜致死損傷修復は臨床的に重要である。 1.3.2 潜在的致死損傷回復 照射後の環境条件によって生存率の上昇が見られることがあり、潜在的致死損傷回復と呼ぶ。この条件は低栄養、低酸素、低pH、接触増殖阻害、定常増殖などの細胞を増殖抑制の起こる環境で、増殖抑制によってPLDを修復する時間が与えられることに依ると考えられている。反対に通常修復されるPLDが修復されずに致死損傷として固定される場合もある。この条件は高・低調液、カフェイン、βアラビノフラノシルアデニン、ヒドロキシウレア、ある種の抗がん剤などが知られている。 PLDの固定は細胞核マトリックス構造の変化、染色体凝縮、核酸合成阻害などにより、いくつかのモデルが提唱されているが分子機構はよく分かっていない。しかしその時間的経過、温度依存性、核酸合成阻害剤に対する感受性等から判断して、SLDとは別のものと考えられる。 2.細胞集団における回復 造血組織、小腸、生殖腺の細胞再生系組織では、照射により障害を受けた細胞が排除され、細胞数が減少するとある種のフィードバック機構により、生き残っている幹細胞の増殖が起こり、新生細胞に再生・置換されて、全体として回復する。この損傷細胞の配所にアポトーシスが大きく関与している。この機構は細胞内修復とは全く異なるもので、個体としての回復に大きな働きをもつ。 3.個体における回復 高等動物の個体レベルでも同じ線量を分割して照射すると生残率が増加するような分割照射による効果あるいは線量率効果による回復現象が示されている。マウス等をいろいろな時間間隔で2分割照射した場合の生存率から作った回復曲線は、培養細胞の場合のパターンと一致した( 図3 )。さらに、骨髄死を起こすような線量を2分割照射した場合には造血幹細胞の回復と時間的経過が一致し、腸死を起こす線量の分割照射の場合には、小腸幹細胞(クリプト細胞)の回復曲線と一致した。このことから決定器官の幹細胞の細胞内回復(亜致死障害の回復)と細胞集団の再生によって、個体レベルの回復が起こることが考えられる。 4.回復現象とLET 培養細胞の生存率曲線はX線やγ線などの低LET放射線に対しては大きな肩を持つ場合が多い。しかし、高い放射線生物学的効果比(RBE)を持つ放射線(陽子線や重粒子線などの高LET放射線や中性子線)に対しては肩のない直線的な生存率曲線を示す。また、DNA損傷の修復遺伝子を欠損した細胞は低LET放射線に対しても高感受性で直線的な生存率曲線を示す。このようなことから培養細胞の生残曲線の肩で示される損傷の修復は、高LET放射線では観察されないため、高LET放射線による損傷は修復できないと考えられている。 <図/表> 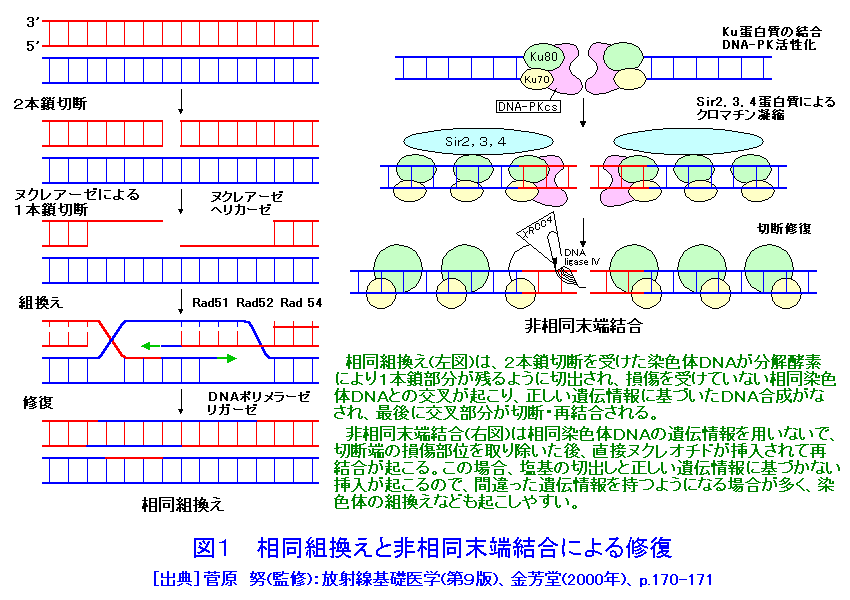
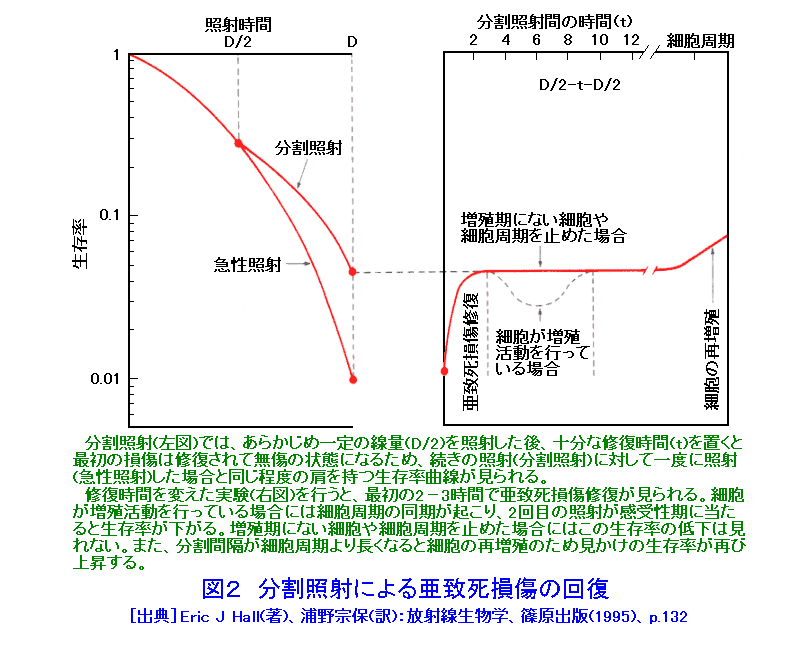
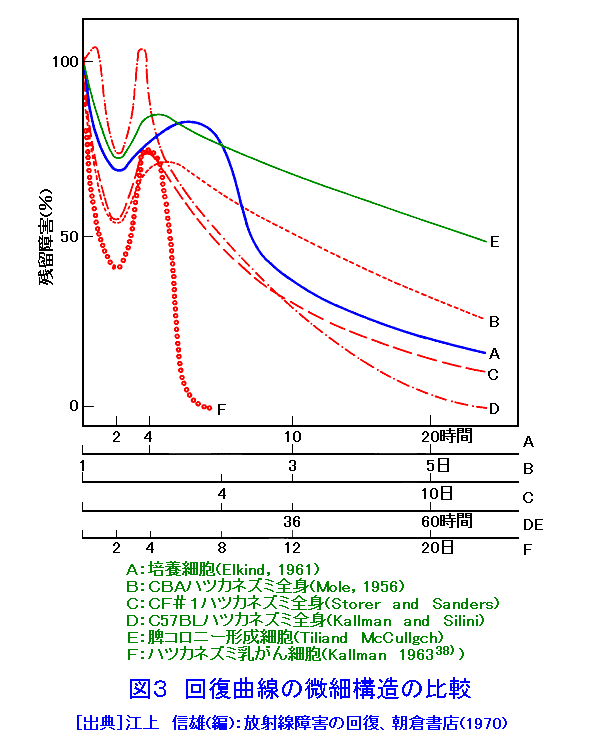
<関連タイトル> 放射線のDNAへの影響 (09-02-02-06) 放射線の細胞への影響 (09-02-02-07) 放射線の細胞系への影響 (09-02-02-08) 被ばく線量と生物学的効果 (09-02-02-13) 線量率と生物学的効果 (09-02-02-14) 放射線の種類と生物学的効果 (09-02-02-15) <参考文献> (1)江上 信雄(編):放射線障害の回復、朝倉書店(1970) (2)菅原 努ほか(編):放射線細胞生物学、朝倉書店(1967) (3)Eric J Hall(著)、浦野宗保(訳):放射線生物学、篠原出版(1995)
|

