|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
軽い原子核同士が互いに近接して融合し、より重い原子に変換する過程を核融合反応という。核融合反応では原子間の結合エネルギーが質量欠損のかたちで放出される。自然界では太陽のエネルギーが核融合反応から発生している。地上で実現される、最も起こりやすい核融合反応は重水素と三重水素の場合である。核融合反応をエネルギー源として利用するためにはプラズマ密度、閉じ込め時間、及びプラズマ温度が一定の値以上となる必要がある。核融合炉の実現のためにはローソン図で示した自己点火条件を実現する必要がある。 <更新年月> 2005年04月
<本文>
自然界での核融合反応の例として太陽がある。太陽では、水素同士の核融合反応でヘリウムが形成される。現在利用されている原子力発電では、重いウランの原子核に中性子を当て原子核が分裂し、より軽い原子に変換されるとき放出されるエネルギーを発電に利用している。核融合と核分裂でのエネルギー発生量を図1に示す。 1.核融合反応の種類 反応のしやすさの順に以下のような核融合反応がある。 (1) 重水素+三重水素 : ヘリウム(3.5MeV) + 中性子(14.1 MeV) (2) 重水素+重水素 : 三重水素(1MeV)+陽子(3MeV) : ヘリウム3(0.8MeV)+中性子(2.5MeV) (3) 重水素+ヘリウム3: ヘリウム4(3.7MeV)+陽子(14.7MeV) 括弧内はそれぞれの粒子の持つ運動エネルギーをeV(電子ボルト)の単位で示す。 これらの反応に関係する物質のうち、重水素(D)は通常の水に含まれ、ほぼ無尽蔵に存在するといえる。三重水素(T)は半減期12.7年で弱いβ線をだす放射性物質で天然にはわずかしか存在しない。上記(1)のD−T反応で発生した中性子をリチウムに当てると三重水素が発生する。ヘリウム3(He−3)は地球上には極くわずかしか存在しないが、月には豊富に存在することが確認されている。D−T反応で発生する中性子は14.1MeV(約1,400万電子ボルト)と高いエネルギーを有し、この運動エネルギーを熱エネルギーに変換する炉構造物(ブランケット)を放射化する。安全上、実用の核融合炉の構造材には放射化しにくい材料(シリコンカーバイトやバナジウム合金等)の利用を考慮する必要がある。(2)のD−D反応の中性子のエネルギーは2.5MeV(約250万電子ボルト)と低く、中性子による構造材の損傷は低減するが、この反応を維持するのにはプラズマのパラメーター(プラズマ粒子密度,プラズマ温度等)をより高くしなければならない。(3)のD−He3反応もより高いプラズマパラメーターを必要とするが、その特徴は核融合反応の結果発生する粒子はすべて荷電粒子であり、粒子の運動エネルギーを効率良く直接電力に変換する、いわゆる直接発電が原理のうえで可能なことである。しかし、陽子による構造材の損傷は小さいが、高速の陽子の長時間照射で材料はかなり放射化するので、この場合も低放射化材料の開発は必要となる。さらに資源としてのヘリウム3の確保に課題がある。核融合炉としての利用の観点からは、比較的に容易なD−T反応を第一候補とし、研究の進んだ段階でさらなる性能向上にD−D、D−He3反応の利用を考慮することが妥当といえる。 2.高温核融合プラズマの物理的実現条件 核融合反応をおこすためには、2つの正電荷をもつ原子核を電気的反発力に打ち勝って近接させなければならない。このためには、粒子を約1,000km/秒以上の速度、即ち温度に換算して1億度の高温状態が必要となる。このような高温状態では水素は「プラズマ」と呼ばれる状態となる(図2)。常温の気体の温度が上昇すると、まず分子は原子にわかれ、さらには原子が正の電荷をもつ原子核(イオン)と、負の電荷をもつ電子に分離する。それぞれの粒子が自由で気ままな熱運動をするいわゆるプラズマ状態となる。水素の場合は、約14万度でイオンと電子が分離する。 1回の核融合反応で出てくるエネルギーは一定なので、必要なエネルギーを核融合反応から取り出すためには、頻度良く粒子が衝突する必要がある。衝突の頻度は、一定の領域に反応粒子が多いこと、その領域に1個の粒子が長く滞在することで向上する。即ち密度が高く、高温粒子の滞在の時定数(閉じ込め時間)が長いプラズマを実現しなければならない。 以上の3つの条件、温度、密度と閉じ込め時間の積を変数として、高温プラズマを保つための加熱入力と核融合出力が等しい条件を臨界プラズマ条件と呼び、高温プラズマを保つための核融合入力と核融合出力のアルファ粒子の持つ成分が等しい条件を自己点火条件と呼び、これらを図3に示す。図3は最初の提案者にちなんでローソン図といわれる。アルファ粒子は高温プラズマ中に発生すると水素と同様に荷電粒子として磁場容器内に閉じ込められ、自らの持つエネルギーでプラズマを加熱する。自己点火条件は外部からの入力なしで 核融合反応が持続しうる条件である。磁場閉じ込め方式は、一度プラズマが自己点火すれば、定常燃焼が自動継続するので、エネルギー利得が自動的に定まる電力発振源と見做せる。3つのプラズマ条件の積、温度×密度×閉じ込め時間を核融合積と呼びプラズマパラメータの指標として用いる場合がある。図3から閉じ込め時間が数秒で密度は1020/m3(100兆個/cm3)、温度10keV(約1億度)以上が自己点火条件の範囲にはいる。 <図/表> 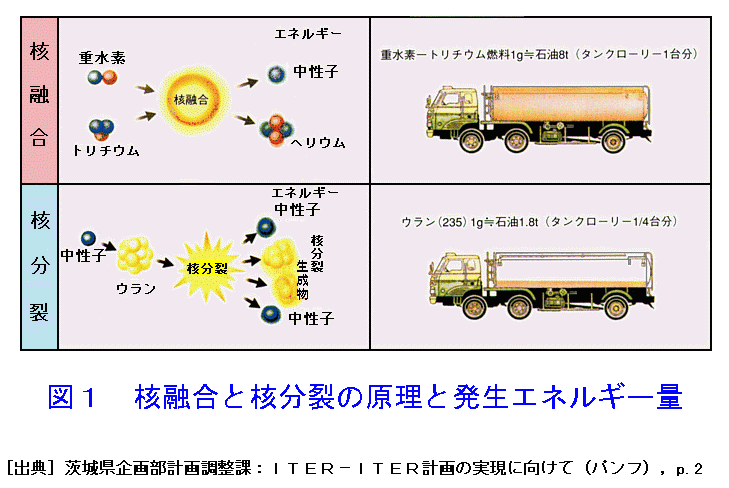
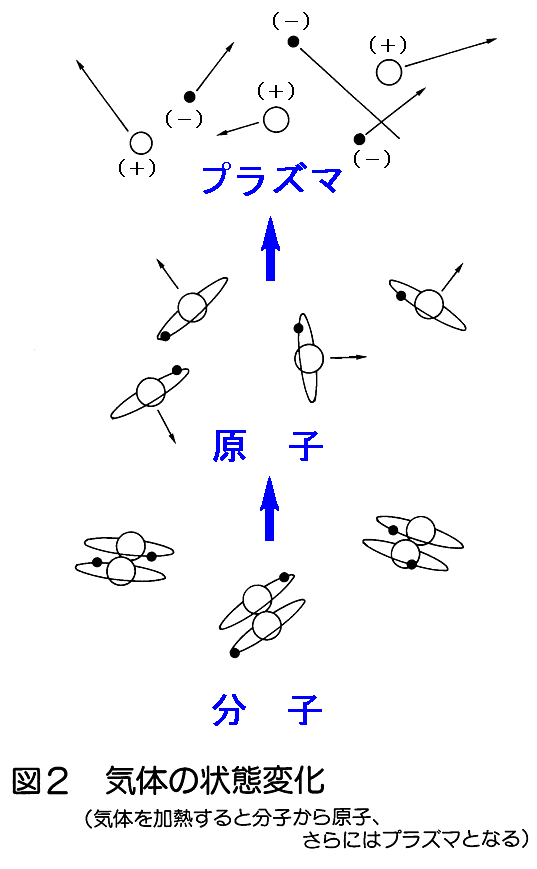
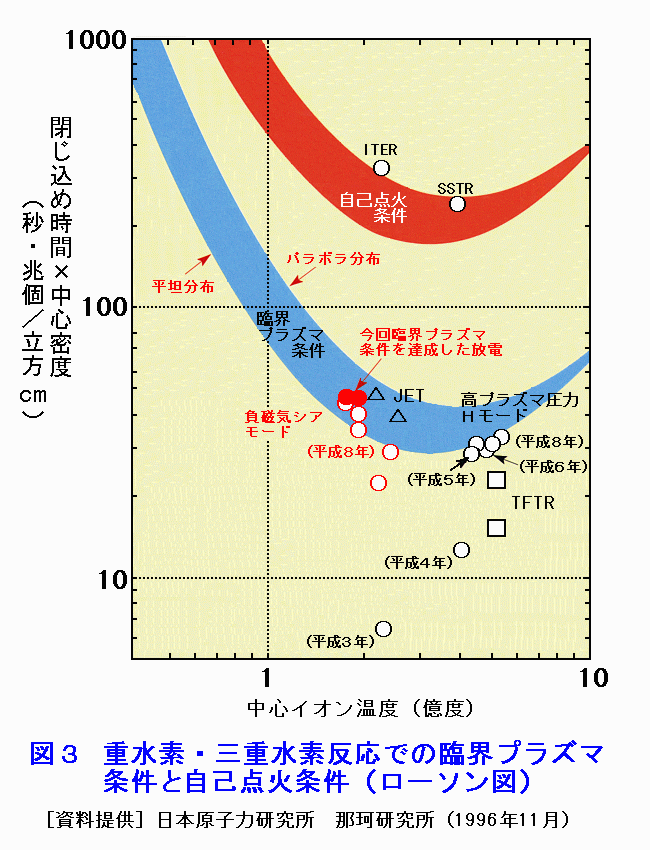
<関連タイトル> 核融合研究開発の経過 (07-05-01-03) 核融合炉開発の展望 (07-05-01-04) 核融合反応装置の形式と作動原理 (07-05-01-05) 幅広いアプローチ活動の概要 (07-05-04-01) <参考文献> (1)田中裕二:原子力基礎講座第5版−8「核融合」、日本原子力文化振興財団(1996) (2)日本原子力研究所核融合計画室・那珂研究所(編):核融合をめざして−核融合研究開発の現状1997年(1997年11月) (3)狐崎 晶雄・吉川 庄一:「新・核融合への挑戦」講談社ブルーバックス(2003) (4)ジョセフ・ヴァイス 本多 力(訳):「核融合エネルギー入門」文庫クセジュ(2004) (5)関 晶弘(編):「核融合炉工学概論−未来エネルギーへの挑戦」日刊工業新聞社(2002) (6)近藤 育朗、栗原 研一、宮 健三:「核融合エネルギーのはなし」日刊工業新聞社(1996) (7)核融合フォーラムHP
|

