|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
再処理施設を含む核燃料施設では核分裂性の物質を取り扱うが、原子炉と違って核分裂の連鎖反応(臨界状態)を目的にしていない。したがって、臨界状態の発生は事故であり、この防止のため各種の安全対策を実施してきた。しかし、1999年9月に茨城県東海村で発生したJCOウラン加工工場の臨界事故を含めて、これまでに22件の臨界事故の発生が核燃料取扱施設で報告されている。海外での事故の内訳は、米国7件、英国1件、ロシア13件である。これらのうち1件を除いて、溶液(またはスラリー)系の臨界事故で、エネルギー放出は核分裂数は最大でも10E19個程度である。 <更新年月> 2001年03月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.はじめに 再処理施設を含む核燃料取扱施設(製錬施設、加工施設、濃縮施設など)では、原子炉のように核分裂の連鎖反応を(臨界状態を)維持させながら核燃料物質を利用する施設とは違って、施設内で核物質の臨界状態を発生させることはない。万一、臨界状態が発生すれば被害の有無に係わらず事故として扱われる。 核燃料物質取扱施設では、先ず臨界状態の発生を防止すること、万一発生してもその影響が施設従業員および公衆に及ばないようにすること、影響がある場合はその影響を緩和することを考慮して、施設の最善の設計、製作、運転、保守等を心掛けている。臨界状態の発生の防止に関しては、核燃料サイクル施設では安全上の最大級の配慮がなされている。 海外の核燃料物質取扱施設では、 表1 (欧米)、 表2−1 、 表2−2 および 表2−3 (ロシア)に示す21件の臨界事故が報告されている。さらに1999年9月には、日本のJCOウラン加工工場での臨界事故1件が加わった( 表3 )。これらの22件の事故のうち21件は、溶液系あるいは粉体と溶液が混合した系(スラリー)で発生しており(1件は金属系)、また、21件の事故のうち1965年以前に16件が発生している( 図1 )。これらの事故に共通することは、初期においては関係者の知識不足を含む不注意が多く、例外的な作業の場合にその感が強い。これらの事故経験は、核燃料サイクル施設に於ける臨界現象の解明、臨界に係わる各種パラメータの整備、設計手法の開発の進展とともに、施設の臨界安全設計に反映されている。 2.溶液系の臨界現象の特徴 ウラン235やプルトニウム239のように核分裂しやすい核種が中性子を吸収し核分裂しても、一つの核分裂の際に数個発生する中性子が次の核分裂を誘起しないで系外に去り、連鎖的な核分裂現象を呈さなければ臨界状態とはいわない(臨界未満状態である)。系内の核分裂性物質が多い(量、濃度)、中性子が核分裂物質の核分裂に十分なエネルギーをもつ(系内の水等の減速材によって減速して)、系が中性子が逃げにくい幾何学的形状をもつ等の条件が揃うと臨界状態になる。 一方、中性子を捕獲する物質の存在、系の温度変化および形状変化、気泡発生等により臨界状態の維持が困難になれば、臨界反応の停止となる。核分裂によって生ずる熱、気泡は、停止機構を形成することが多い。 このような訳で、溶液系の(即発臨界を超える)臨界現象は、 図2 に示すように、最初に臨界に達した直後のエネルギー放出は、急激な温度上昇および溶液の放射線分解により生じる気泡(ガスボイド)の効果で、短時間のうちに終わる。これを「バースト」というが、気泡はやがて浮力により系外へ逃げてしまうため、しばらく経つと再びバーストが生起する。これを何回か繰り返しながら、温度上昇により系が未臨界となるまでエネルギー放出が行われる(バーストは一回だけのこともある)。 バーストの大きさ、繰り返しの数、継続時間等は、溶液の組成、量、容器の形状、核分裂反応を支える燃料物質、減速物質等の系への補給の状況等によって大差があるが、図1に示したように、過去の例から核分裂数のオーダーで1.0E15〜1.0E19個であることがわかっている。例えば、核分裂数1.0E18の場合、核分裂したウラン235の量は0.4ミリグラム、放出エネルギーは約3.4E7ジュール(熱エネルギーとすれば約10リットルの水を蒸発させる程度)であり、熱量でTNT爆薬に換算すると約7キログラムとなる。最初のバーストは十分の一程度である。したがって諸般の状況にもよるが、今までの事故例でも装置の大きな変形は起こっていない。火薬の爆発や核爆弾の爆発とは全く異なった現象である。 これらの臨界超過現象は、臨界実験装置で実験的にも確認されている。代表的なものにフランスのCRAC実験がある。 図3 にこの実験の代表的な出力暴走挙動を示す。 海外における実験はいずれも高濃縮ウランを使用したものである。日本では、日本原子力研究所東海研究所(現日本原子力研究開発機構原子力科学研究所)の燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)に建設した過渡臨界実験装置TRACYを用いて、低濃縮ウラン溶液の臨界事故を模擬した実験を平成7年(1995年)より開始した。 図4 にTRACY装置の外観を示す。 3.臨界事故例 以下に、いくつかの臨界事故の概要を示す。 (1)ロスアラモス国立研究所Pu回収施設(LASL、ニューメキシコ州、米国)、1958年12月30日 この施設は、Pu金属製造工程から生ずる廃棄物からプルトニウムを回収するものである。工程は、廃棄物を硝酸に溶解し、ろ過後、カラムでプルトニウムをTBP溶媒抽出し、ミキサセトラで逆抽出して、シュウ酸沈澱法で回収する。抽出残液の僅かなPuを回収するため回分式で臨界安全形状でない抽出槽で処理していた(取扱量が臨界質量以下として)。事故は、この抽出槽にPuを含む劣化溶媒の エマルジョン(水和物)が蓄積していたことに気付かないで濃硝酸をいれ空気攪拌したので、分離した溶媒相にPuが抽出され、攪拌停止後、抽出槽内で約40gのPuを含む約300リットルの水相と約3,300gのPuを含む約160リットルの溶媒相に分かれた。この状態では未臨界であったが、抽出槽の傍にいた操作員が機械式攪拌機のスイッチを入れたところ、そのため溶媒層の層厚20.3cmが21.6cmに膨れ、臨界状態に到達してしまった。バースト(青い閃光、核分裂数1.5E17)は一回のみであったが、この操作員は約12,000ラドの線量を受け約35時間後に死亡した。事故後、残液は臨界安全形状の管状貯槽を臨時設置して処理した。その後の処置として抽出処理槽の臨界安全形状化、配管の整理、関連貯槽に中性子吸収用ラシヒリング充填、プルトニウムの定期サーベイ、操作マニュアルの見直し、要員の再訓練等が行われた。 (2)ウィンズケールPu回収施設(BNFL、セラフィールド(B-205)、英国)、1970年8月24日 この施設(PRP、図5 参照)は1954年に完成した。種々のプルトニウム含有物からプルトニウムを回収する施設である。処理試料を溶解槽2で硝酸に溶解し、調整槽4で抽出工程の供給液として調整する。調整液は真空サイフォンで移送トラップ5を経由して計量貯槽6に送られ、パルスカラム7でTBP-ケロシン溶媒によりプルトニウムが抽出される。溶媒の流れは次のカラム8へ送られる。抽出残液(水相)は廃液貯槽9に送られるが、プルトニウムが残っている場合は調整槽4にリサイクルされる。 1970年8月24日の夕刻、ウィンズケール再処理工場のPRPおよび隣接するプルトニウム燃料製造棟の臨界警報装置が発報した。両棟の従業員は退避したが、彼らの個人被ばく線量計に有意の記録は見出されなかった。当時のPRPの作業は、調整槽4で6gPu/リットル溶液を作り計量貯槽6に送ることであった。調査委員会がこの溶液を分析したところ核分裂生成物が検出され、移送トラップ5内で小規模の超臨界(核分裂数約1E15)が発生したことが推定された。約50リットルの水溶液のみでは臨界超過になる可能性はないことから、調査した結果、移送トラップ内に55gPu/リットルを含むTBP-ケロシン溶媒約40リットルが発見された。α線による有機相(溶媒)の程度から、数箇月から2年間、このトラップ内に閉じ込められていたと推定された。有機相は比重が0.96と小さいので、容器に入ると硝酸溶液(比重、約1.3)の上に浮き、構造上、トラップ内に閉じ込められる。有機溶媒は調整液中のプルトニウムを逐次抽出して蓄積し、約2.5kgのプルトニウムが存在したと推定される。模擬装置で事象の研究がなされ、 図6 に示すように、給液中は有機相中央部に注入水の穴があるので未臨界であるが、注入停止で臨界に達し、数秒後分散相が消滅して未臨界に戻ったとされた(水相と有機相の混合分散状態は核的反応度を増大させることがあるという知見を得た)。事故後、非臨界安全形状の容器には中性子モニタが装備され、各容器は完全な排水と洗浄ができるように改造された。 (3)アイダホ化学工場(ICPP、ユタ州、米国)、1978年10月17日 この工場は、軍艦の推進用原子炉、MTR,EBR等の高濃縮ウラン燃料やトリウム燃料等雑多な燃料を処理する。表1のように、1959年と1961年に臨界事故を経験し、その都度調査委員会の勧告により諸種の改善策を取ってきたが、1978年10月17日、3度目の事故が発生した。事故は、抽出第一サイクルで高濃縮ウランの回収を5%TBP-ケロシン溶媒で行っていた時、洗浄カラム1Bで発生した。 図7 に工程フロー概要図を示す。 この工程では燃料溶解時にフッ素イオンや硫酸イオンが溶解液に混入するので、その腐食作用と錯化作用を抑えるため硝酸アルミニウムを添加する。また硝酸アルミニウムは塩析剤として作用し溶媒相へのウランの抽出と保持を助ける。1Bカラムでは1Aカラムでウランを抽出してきた溶媒流1AP(約5gU/リットル)を、約0.75モル/リットルの濃度の硝酸アルミニウム溶液で洗浄する。硝酸アルミニウム溶液の作用で1Bカラムの塔底液1BRのウラン濃度は0.5gU/リットル程度の筈であった。事故の直接的な原因は1Bカラムの洗浄液1BSの硝酸アルミニウムの濃度減少である。 1BS調整槽周りの計装の不備があり、事故一箇月前から徐々に硝酸アルミニウム溶液の濃度が減少してきたのに気付かなかった(9月15日;0.7モル/リットル、9月27日;0.47、10月27日;0.08、事故後推定、サンプル分析は継続的には行われず)。このためウランが1BRに逆抽出され、1Aカラムに還流し続けたと思われる。そのため1AFF,1AR,1AP等のウラン濃度も上昇し、1BRは21〜23gU/リットルに達し、10月27日20時15分から25分間、1Bカラムの塔底部(太い径)で遅発臨界状態(遅発中性子による緩やかな連鎖反応の継続)が発生した。20時40分、異常に気付いた操作員がカラム圧を下げようと塔底部の排出回路を開いたが、この操作によってカラムの中間部(細い径)のより高濃度のウラン溶液が塔底部に下がり即発臨界状態(即発中性子によるバースト)に達してしまった。温度上昇、発泡、ウランの流出等で反応は停止したが、この事故の全核分裂数は2.74E18個で、その97%は1B塔底部で発生したと推定される。この事故は重遮へい、適切な換気系を持つセル内で起こったため、被ばく、汚染、物的損害は無かった。 1974年の安全解析書には、硝酸アルミニウムの濃度低下と臨界の可能性について指摘していたが、安全対策の記述は無く、比重計の故障は放置され、それを補う試料分析もされなかった。運転管理の不備、怠慢といえる。 (4)JCO加工施設(JCO、東海村、日)、1999年9月30日発生(表3参照) JCO転換試験棟では、濃縮Uの精製を行い、UO2や硝酸ウラニル水溶液を製造していた。事故当時、同施設では高速実験炉「常陽」で使用する濃縮度18.8%のウラン燃料の精製作業を行っていた。事故は、精製したU3O8を溶解し、硝酸ウラニル水溶液を製造する過程で発生した。この施設では、形状制限と質量制限により臨界管理を実施しており、20%以下の濃縮Uの質量制限は1バッチ当り2.4kgUであったが、6ないし7バッチ分の溶液全体を均質化する必要があり、事故以前より安全形状の貯塔(170mm径)を未許可で使用していた。(他に、溶解塔を使用せず、ステンレス製バケツで酸化ウランを溶解する等の規則違反が行われていた。) 事故の前日(9月29日)に、作業員(3名)は作業の効率化のため貯塔に代えて非安全形状の沈殿槽(450mm径)の使用を決定し、4バッチ分の溶液を上部の監視口(ハンドホール)からステンレス製容器(容量4リットル)を用いて手作業で投入した。翌9月30日に、残り3バッチ分を投入したところ、10:35に臨界となった。作業者は閃光(青い光)を見た。同時に放射線警報(エリアモニタ)が作動し、全職員が退避した。その後も臨界は継続し、15:00に施設から350m以内の住民に避難要請、22:30に10km圏内の住民に屋内退避勧告が出された。臨界停止のために、同日深夜より沈殿槽外周にある冷却用水ジャケット(約2.5cm厚)の水抜き作業を開始。翌日6:15に水が全て抜け、臨界が終息した。その後、8:50にホウ酸水を注入した(再臨界防止措置)。同日16:30に10km圏内の屋内退避勧告が解除、2日後の10月2日18:30に350m圏内避難が解除された。後日の調査の結果、沈殿槽には370gU/リットルの溶液が約45リットル投入されたことがわかった(ウラン量で16.6kg)。また、溶液分析結果、総核分裂数は2.5E18であった(これは、ウラン1mgに相当する)。 この事故により、当日の作業者3名が大量の被ばく(約 1-4.5、6-10、16-20 Gy Eq.)をし、このうち2名が死亡した(12月20日及び4月27日)。 また、この3名を除いた従業員169名が最大48mSvを被ばく。事故当日、作業者を救出した消防署員3名を含む防災業務関係者260名が最大9.4mSv、さらに一般住民235名が最大21mSvを被ばくした。(2000年10月13日時点)なお、短半減期の放射性ガス以外の放出は無く、JCO敷地周辺土壌の有意な汚染はなかった。 <図/表> 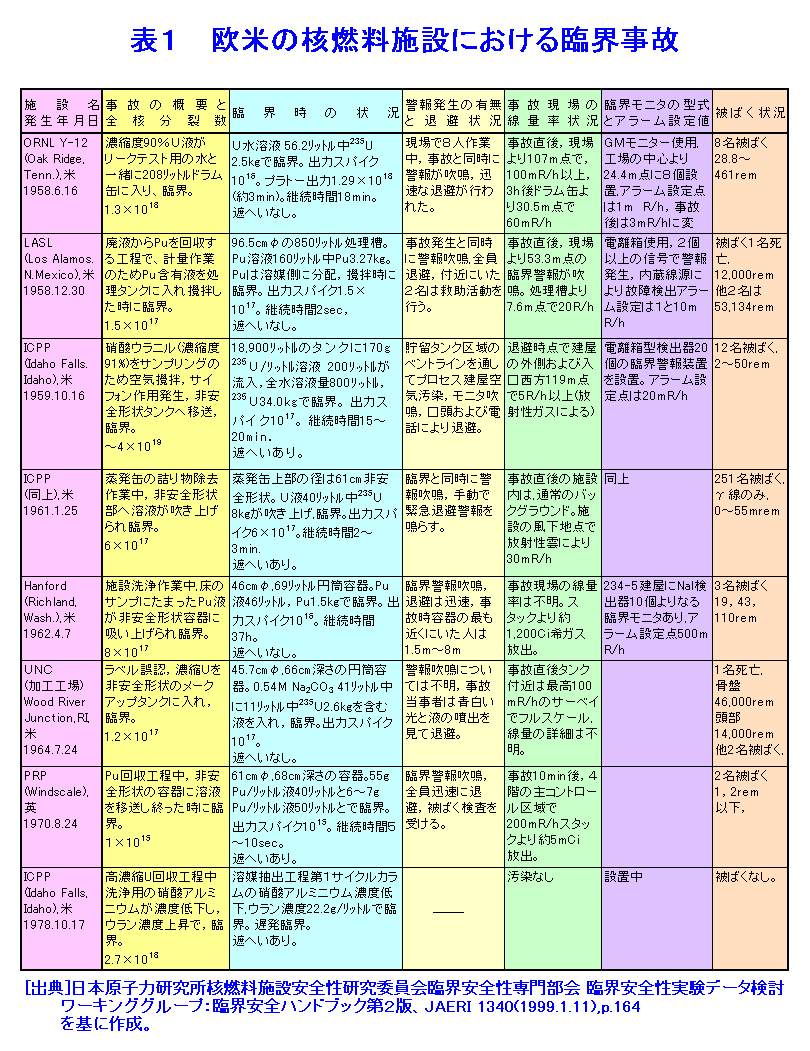
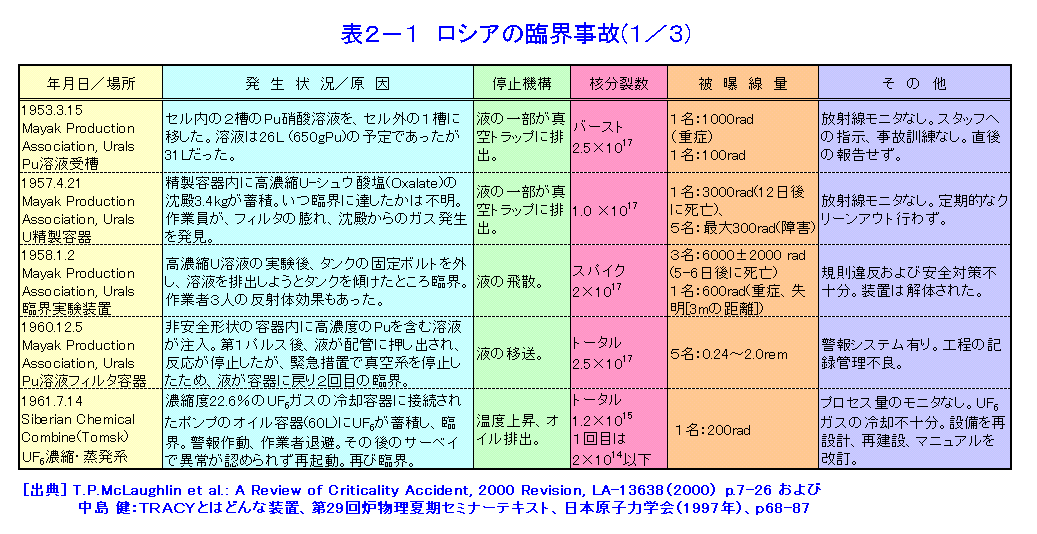
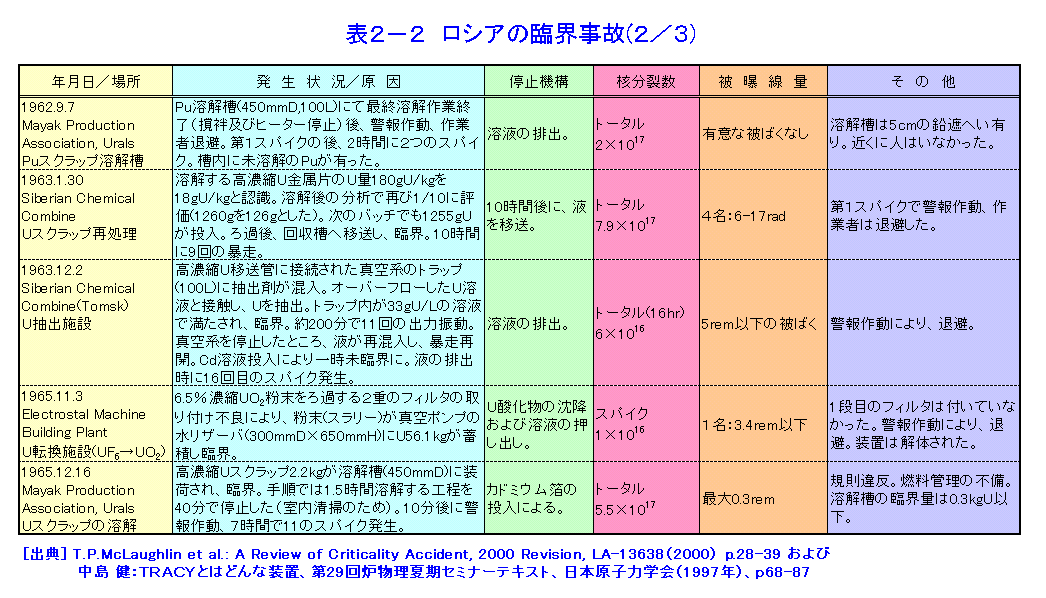
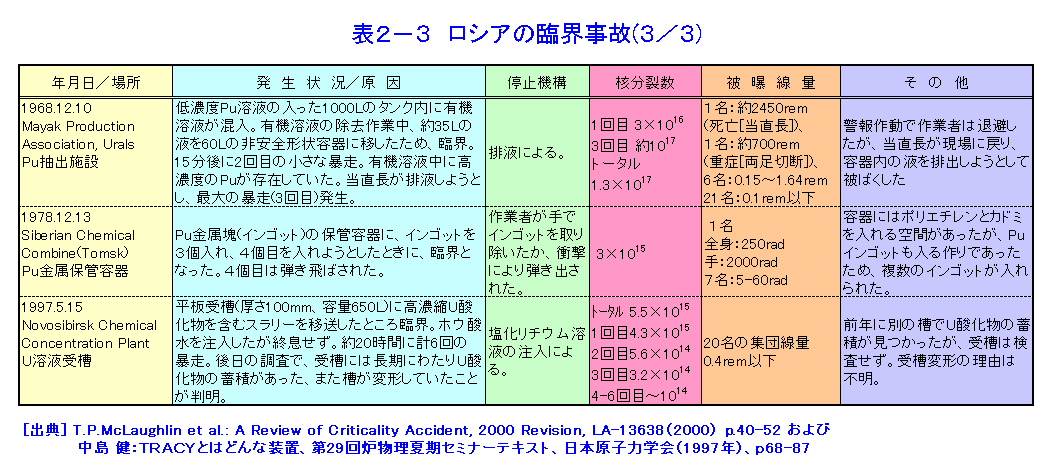
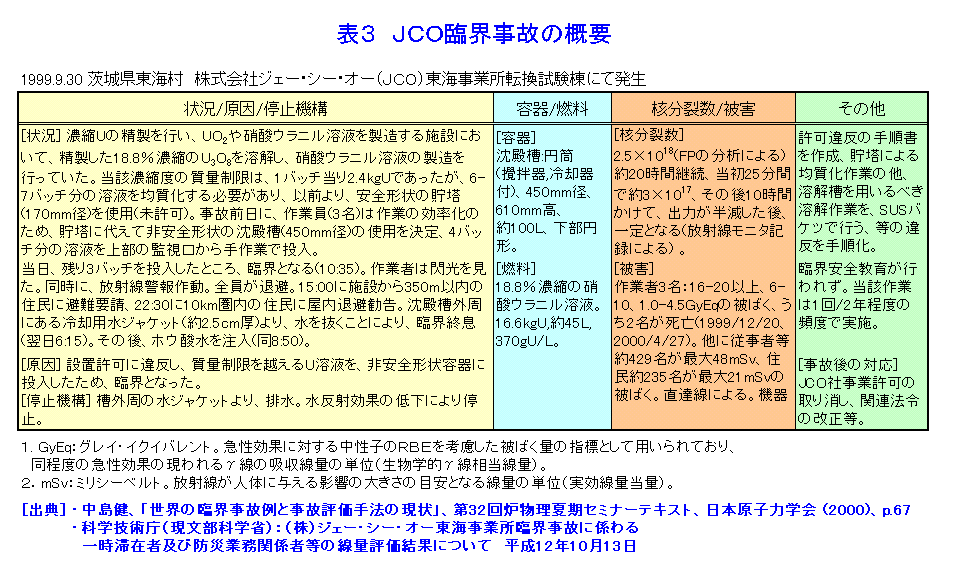
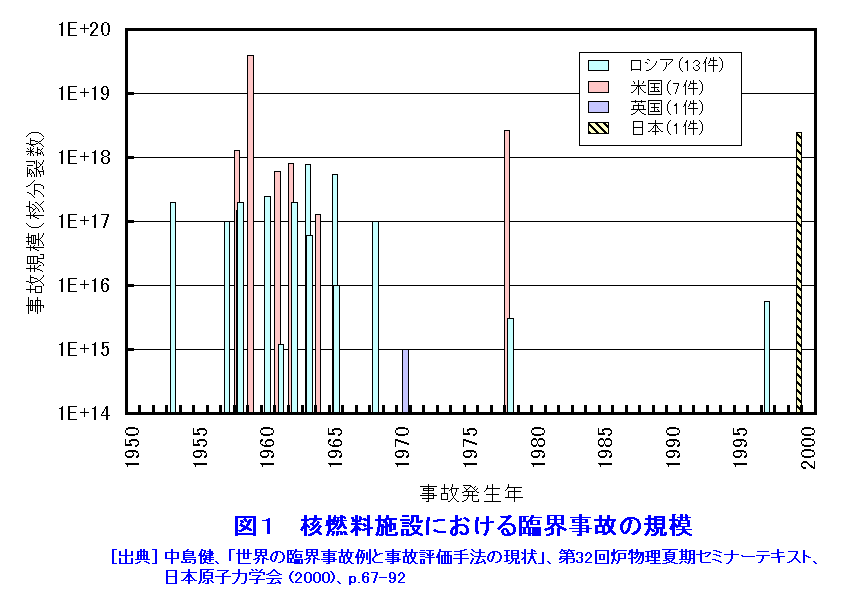
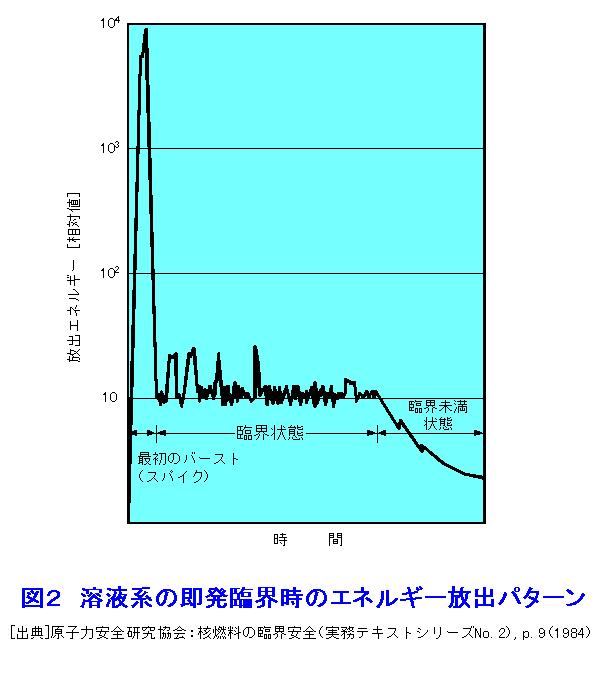
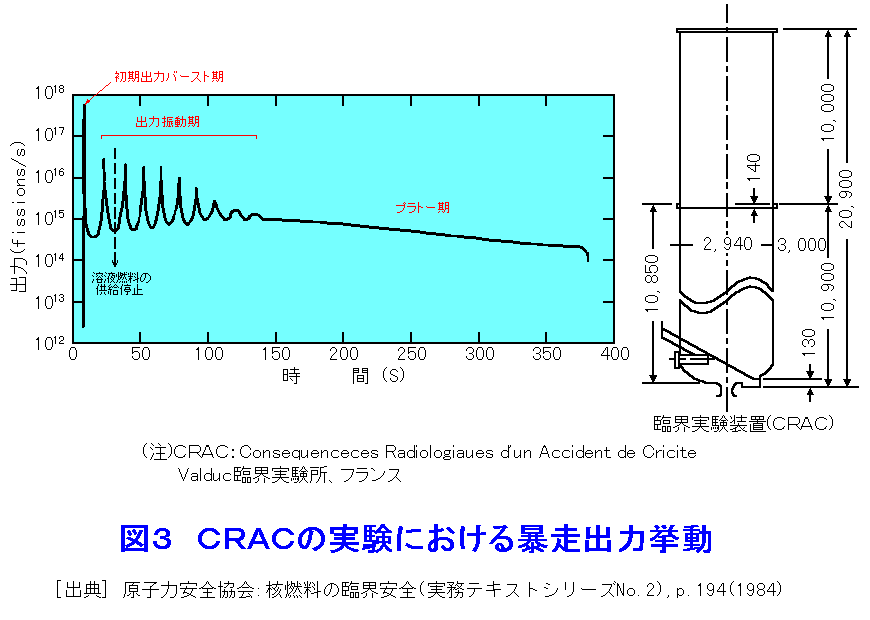
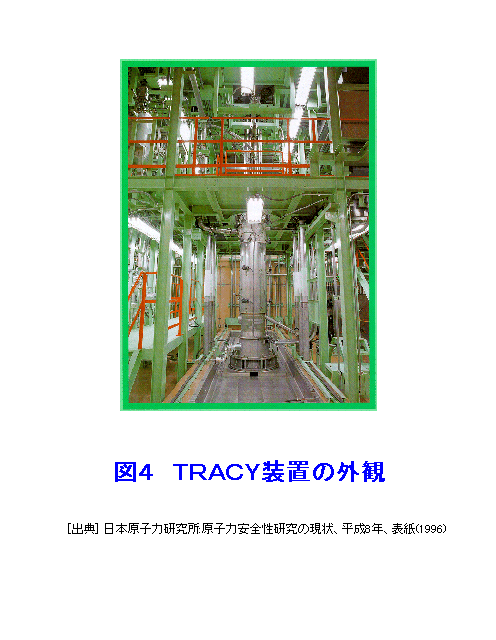
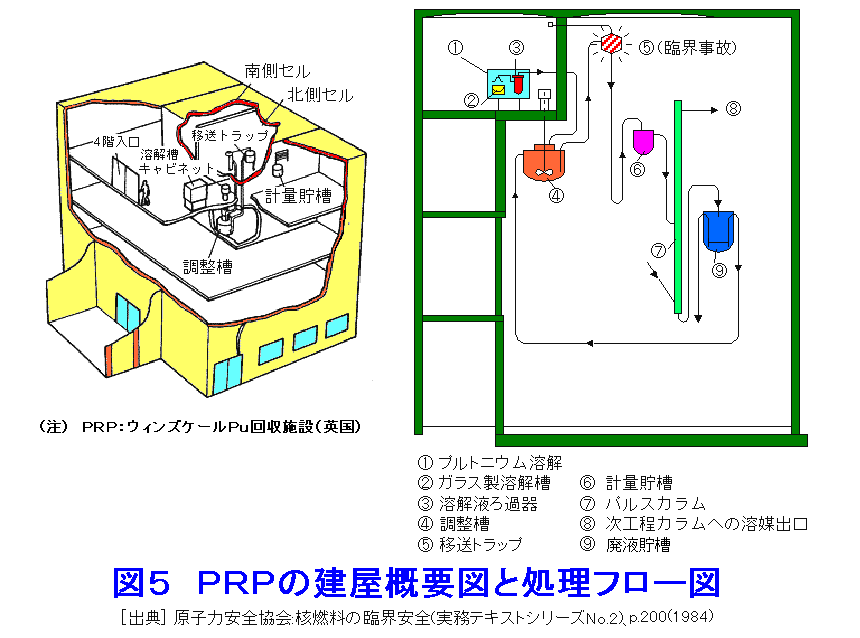
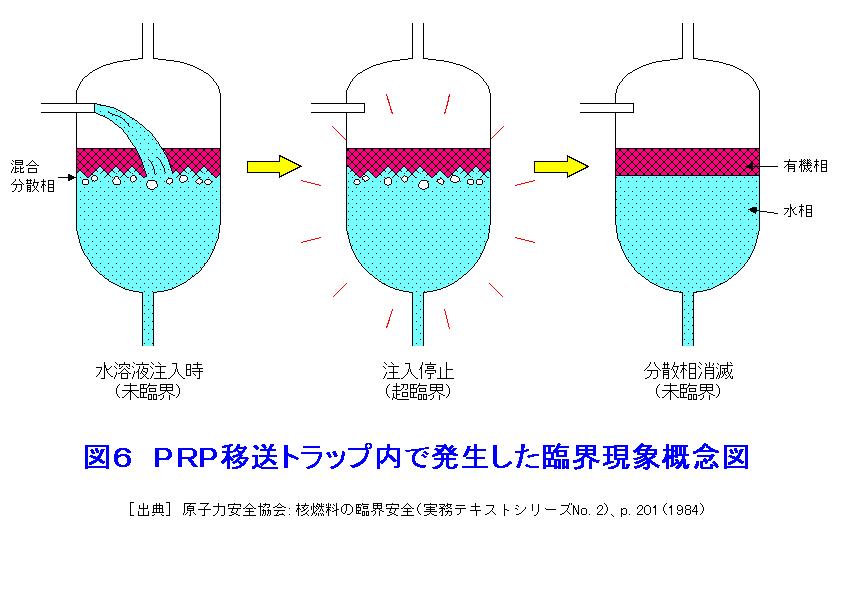
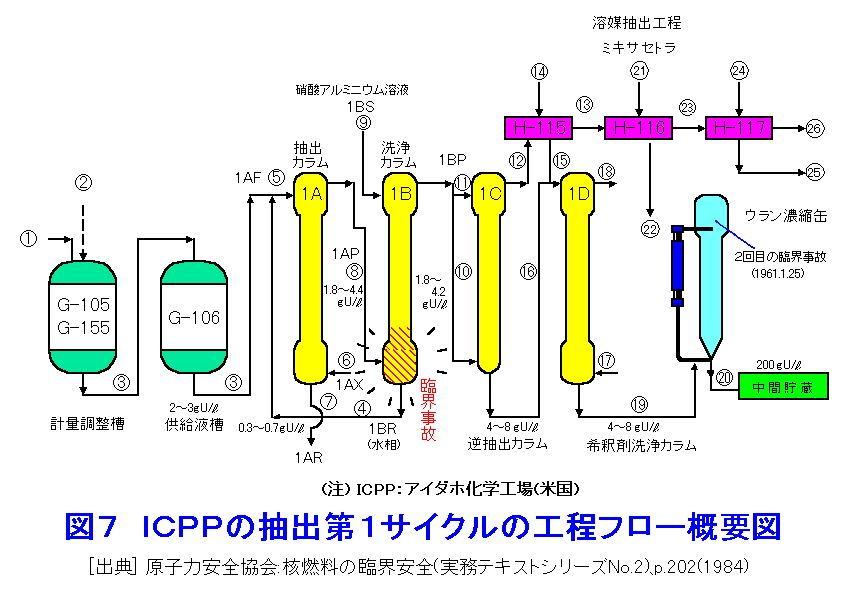
<関連タイトル> NUCEF (03-04-02-06) 再処理の安全と規制 (04-07-01-08) 再処理施設の安全設計 (04-07-03-01) JCOウラン加工工場臨界被ばく事故の概要 (04-10-02-03) 世界の原子力施設における臨界事故 (04-10-03-05) 臨界安全性に関する研究 (06-01-05-02) 臨界実験装置 (08-01-03-06) <参考文献> (1) 館盛 勝一 ほか:核燃料取扱い施設における臨界事故例の解析、JAERI-M 84-155(1984) (2) T.P.McLaughlin et al.: A Review of Criticality Accident,2000 Revision,LA-13638(2000): (3) 中島 健:TRACYとはどんな装置、第29回炉物理夏期セミナーテキスト、日本原子力学会(1997年)、p68-87 (4) 中島 健:世界の臨界事故例と事故評価手法の現状、第32回炉物理夏期セミナーテキスト、日本原子力学会(2000年)、p67-92 (5) 住田 健二 ほか:特集 ウラン燃料加工施設における臨界事故、日本原子力学会誌、42[8]、691(2000) (6) 原子力安全協会(編):核燃料の臨界安全(実務テキストシリーズNo.2),(1984年12月) (7) P.Lecorche,R.L.Seale : A Review of the Experiments Performed to Determine the Radiological Consequences of a Criticality Accident,Y-CDC-12(1973) (8) 中島 健ほか:特集NUCEF計画−燃料サイクル安全工学研究の現状と今後の展開、3.TRACYによる実験、その研究成果、原子力工業、43(9)、(1997),p14-25 (9) 日本原子力研究所:原子力安全性研究の現状、平成8年(1996) (10)日本原子力研究所:臨界安全ハンドブック第2版、JAERI-1340(1999年3月)
|

