|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
小児(15歳以下の子ども)は、活発に運動し、代謝も活発であり、成長も急激である。 放射線の生物影響の一般論を言えば、生物体とくに動物のそれは幼若なほど放射線に対する感受性が高いといえる。これは生物体が幼若で成長が急なほど分裂している細胞が多く、そのような細胞は分裂を休止している細胞に比べて放射線に対する感受性が高いことによる。このことは放射線の人体への健康影響にも当てはまると考えられている。すなわち、成人に比べれば幼若で成長過程にある小児のほうが放射線に対する感受性が高い。しかし、個々の生物影響についてみれば、チェルノブイリ事故からも明らかにされてきた甲状腺腫瘍のように小児とくに若い小児ほど高い感受性が顕著に見られた例もあるが、年齢による違いがほとんど見られない健康影響も多数あり、実態は多様であるといえる。 <更新年月> 2005年10月
<本文>
1.小児の放射線影響に関する一般的特長 成人と違って、小児は成長を続けており、一般的には活発に運動し、体重あたりの呼吸量が大きく、代謝も活発で体重あたりの食事の摂取量も多い。この傾向は一般的には小児の中でも幼若なものほど顕著である。 動物実験から得られた放射線の生物影響の一般論を言えば、生物体は幼若なほど放射線に対する感受性が高い。これは生物体が幼若なほど分裂している細胞やこれから分裂する細胞が多く、そのような細胞は分裂を休止している細胞より放射線に対する感受性が高いことによる。このことは放射線の人体への健康影響にも当てはまると考えられている。すなわち、人を対象とした疫学調査で、成人に比べて成長が急激である小児のほうが放射線に対する感受性が高くなることが明らかにされている。ただし、これはすべての放射線生物影響について言えるわけではなく、その種類によっては小児か成人かで何ら違いが見つからず、実際にはそのように違いの顕著でない影響のほうが多い。国際放射線防護委員会では放射線のリスクが人の年齢に依存することを認めているが、それは人のリスク推定値そのものに付随する不確実性から考えてそれほど大きなものではないとし、全年齢群に同一のリスク推定値を与えている。 以下にいくつかの種類の健康影響の例について、小児の放射線影響の特性を概観する。なお、幼若な生物体として胎児があるが、胎児は小児とは考えられず、また胎児期被ばくについては別のタイトルで述べられているので、ここでは触れない。 2.放射線による確定的影響 小児は放射線による組織反応において感受性が高いかどうかについては、人でのデータはほとんどなく、わずかに動物を用いての研究が行われているに過ぎない。なお、確定的影響とは後述する放射線誘発がんおよび遺伝的影響を除いたすべての放射線健康影響であり、ある量以上の線量を受けると発生する影響である。マウスにX線を照射して造血障害を見た動物実験によれば、造血障害による半致死量(LD50)に関する放射線感受性は、生後間もないマウスでは高いが成長するとともに低くなり、さらに老齢になると再び高くなる(図1)。 きわめて特殊な例であるが、人の組織反応に関連して子供と大人の放射線感受性を比べることができるものがある。白血病治療における骨髄移植法の場合、自家移植でない限り免疫的拒絶反応を防ぐ必要があり、そのための処理の一つとして全身放射線照射がある。そのとき子供も成人も同じ線量が用いられる。このことは子供と成人の間で放射線感受性の違いはそれほど大きくないことを意味している。 3.放射線誘発がん 放射線を受けるとがんが発生することが知られており、その発生確率は線量に比例して増加することから放射線誘発がんは確率的影響とされている。がん年齢という言葉があるように自然に発生するがんは発生しやすい年齢があり、がんにとって年齢は重要な修飾因子である。放射線が誘発するがんに年齢がどのように影響しているかは、前述した確定的影響に比べると詳しく研究されている。 動物実験により放射線影響における年齢依存性あるいは幼若期被ばくの特徴について詳細な研究がある。誕生前の子宮内での時期を含め種々の時期に1.9Gyを照射したマウスの寿命にかかわる相対リスクは誕生直後から7日齢で最も高く、照射時年齢が増大するにつれて相対リスクは低下している(図2)。固形腫瘍に関するリスクについても類似のことが言える(図3)。腫瘍について詳しく見ると感受性が高い時期は腫瘍の種類によって異なる。たとえば、肝腫瘍は生後0から7日に感受性が高いのに対し骨髄性白血病では105日で高い。 放射線による発がんは、人の場合、広島と長崎での原爆被爆者、チェルノブイリ事故で被ばくした人々、その他に医療被ばくした患者を対象とした疫学調査によって、被ばく時の年齢の影響を受けることが明らかにされている。原爆被爆者のデータから被ばく時年齢10歳、30歳および50歳の固形がんにかかわるリスクの経時変化を図4に示した。10歳での被ばくでは相対的にリスクが高いが、時間の経過とともに急速に低下することが特徴的である。 個々のがんについてみると、胃がんでは被ばく時年齢の増加に伴い過剰相対リスクが減少することが認められる。肝臓がんでは過剰リスクは20歳台はじめに被ばくした人で最大であるが、10歳未満あるいは45歳以上で被ばくした人では過剰リスクはほとんどないといえる。肺がんでは過剰相対リスクは被ばく時年齢にほとんど関係がない。骨および結合組織のがんでは、例数が少ないため統計的には有意ではないが、小児期での被ばくでリスクが高いことが示唆されている。皮膚がんは、イスラエルで頭部白癬治療のため照射を受けた患者の調査で、被ばく時年齢の増加とともに過剰相対リスクが減少することが示されている。乳がんも被ばく時年齢が大きく影響し、小児期の被ばくで過剰相対リスクが増大するが、成人期では低下し、特に40歳以降ではきわめて低くなっている。甲状腺がんは、原爆被爆者の間にも見られたがチェルノブイリ事故で被ばくした人の間でも見られ、比較的顕著な被ばく時年齢依存性がある。生後の若い小児ほど感受性が高く、また被ばく後の早期に発現するといえる(図5)。白血病は原爆被爆者に早期に発現したことから放射線との関係の強さが良く知られている。広島長崎での疫学調査の結果、白血病の放射線による過剰相対リスクは顕著に被ばく時年齢に依存する。ただし小児の高いリスクは被ばく後の時間とともに比較的急速に減少するが、成人期の被ばくではこの傾向は顕著ではない。 4.遺伝障害 被ばくした人の子あるいは孫に発生する障害が遺伝障害であり、その発生確率はがんと同様に線量に依存する確率的影響である。放射線の遺伝的影響についてはアメリカのマラーがショウジョウバエを用いた実験で見出し、その結果に対しノーベル賞が与えられたことなどで有名である。その後マウスを用いた実験でも放射線が遺伝障害を起因し、その発生確率は線量に依存することなどが確認されている。しかし、人については広島長崎での被爆者を対象としたものを含めた疫学調査では放射線被ばくによって遺伝的影響が増大しているとの知見は得られていない。放射線被ばくによって遺伝障害が引き起されることはないといえる。したがって、遺伝障害において小児期の被ばくのリスクが成人のそれに比し高いということはないといえよう。 <図/表> 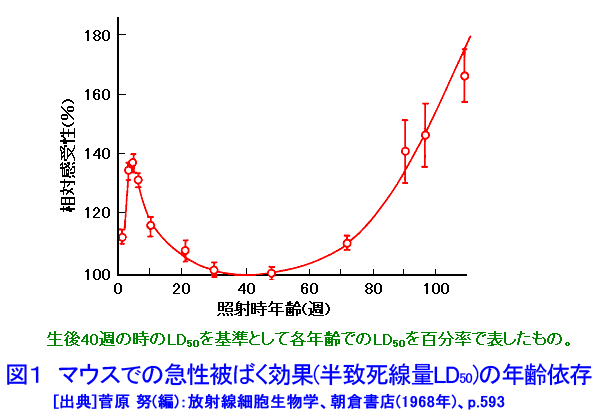
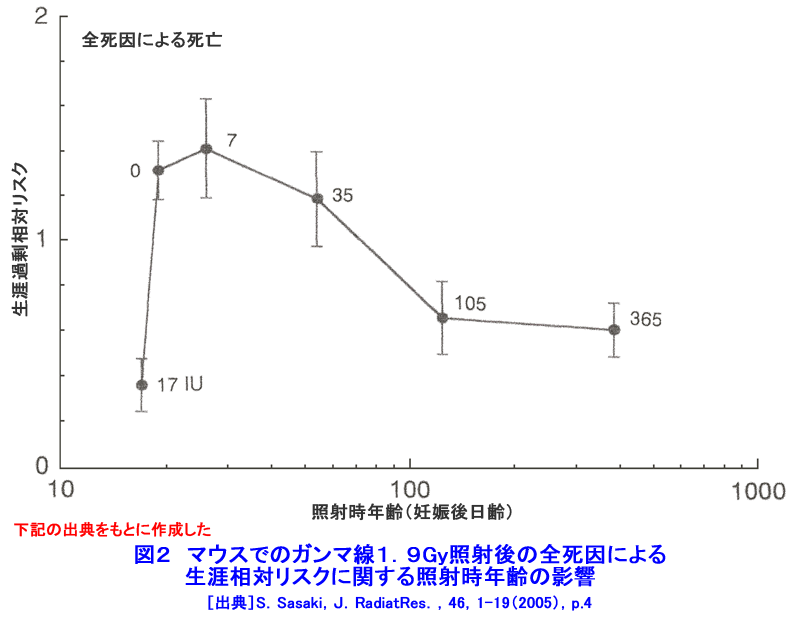
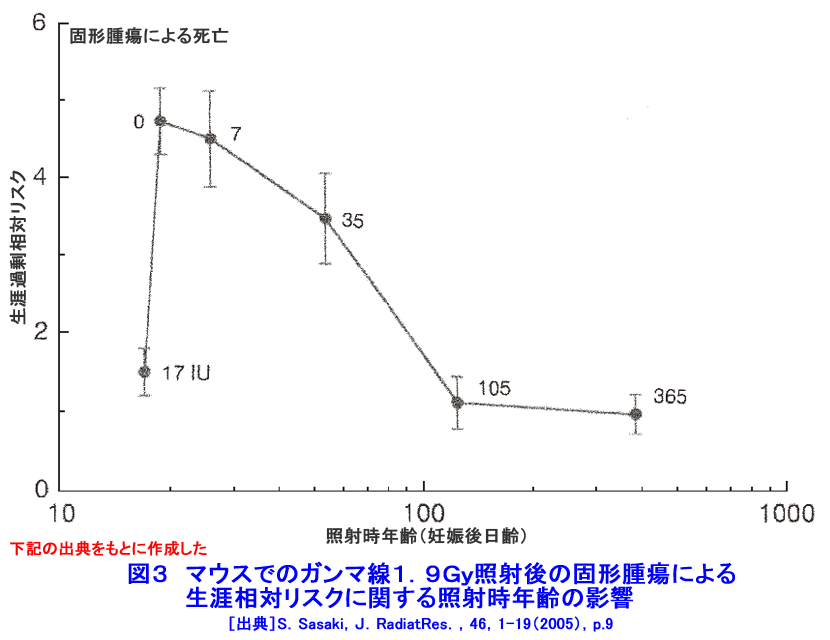
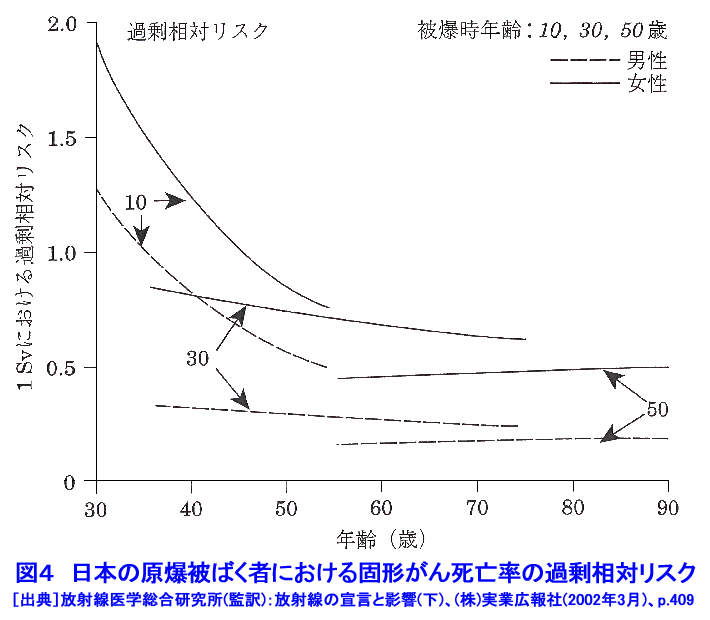
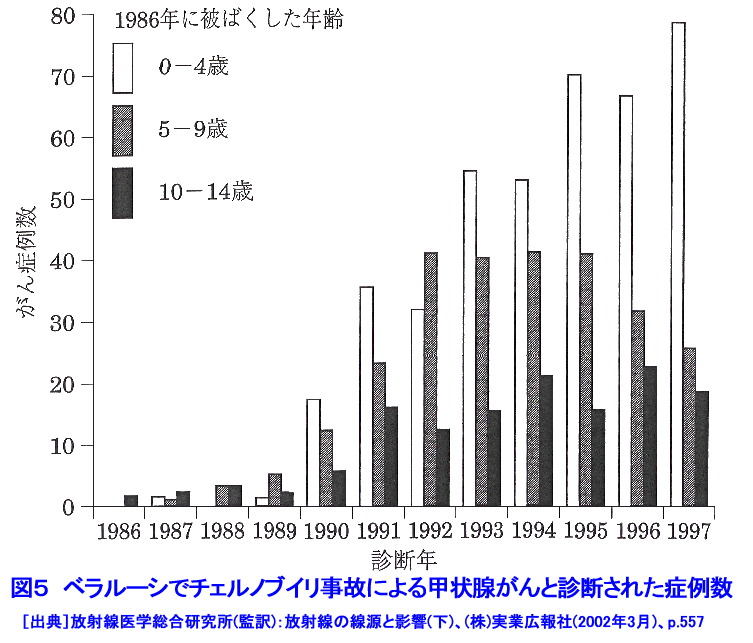
<関連タイトル> 放射線生物効果の年齢依存 (09-02-02-18) 放射線の遺伝的影響 (09-02-03-04) 胎児期被ばくによる影響 (09-02-03-07) 原爆放射線による人体への影響 (09-02-03-10) 放射線が寿命に与える影響 (09-02-05-05) 原爆被爆生存者における放射線影響 (09-02-07-08) <参考文献> (1)菅原 努ほか(編):放射線細胞生物学、朝倉書店(1967) (2)日本アイソトープ協会訳:ICRP Publication 60 国際放射線防護委員会の1990年勧告、丸善(1991) (3)Sasaki,S.:J.Radiat. Res.,46,1-19(2005) (4)佐々木俊作:出生前および幼若期被ばくによる長期的影響、放射線生物研究、23巻2号、71-91(1988) (5)放射線被爆者医療国際協力推進協議会(編):原爆放射線の人体影響、分光堂(1992) (6)放射線医学総合研究所(監訳):放射線の線源と影響、国連科学委員会UNSCEAR 2000年報告書、実業公報社(2002)
|

