|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
1945年8月、広島と長崎に原子爆弾が投下され、その熱線と爆風及び放射線は、数か月以内に多くの人々を死亡に至らしめた。死亡を免れた人にも、その際の放射線が長期にわたり健康に影響を与え続け、種々の臓器にがん(ガン、癌)や機能異常をもたらしている。これらの健康影響については、日米の協力の下、放射線影響研究所(放影研:前身は原爆傷害調査委員会)で1947年以来今日まで科学的調査が続けられ、膨大な数の報告書が発表されている。特に12万人の固定集団を設定して1950年から長期追跡を行なっている寿命調査のデータに基づくがんリスクの研究は、世界的に高い科学的評価を受けている。その研究結果は、国連科学委員会の報告書に収録され、国際放射線防護委員会が放射線防護基準を策定する際の基礎となっている。 <更新年月> 2005年02月
<本文>
1.原爆放射線 広島型原爆にはウラン235が使われ、エネルギーはTNT火薬の16kt相当、長崎型原爆はプルトニウム239で、TNT火薬の21kt相当といわれている。原爆の特徴は爆風の他に強烈な熱線と放射線を伴うことであり、そのエネルギー分布は爆風50%、熱線35%、放射線15%といわれている。 1.1 放射線 爆発によって生じた放射線は、爆発1分以内に放射された初期放射線(主要成分はガンマ線と中性子線)と、その後長時間にわたって地上で放射された残留放射線(核分裂生成物:いわゆる死の灰と、誘導放射能)に分けられる。原爆投下の翌日に爆心地に入り1週間作業をした人の被ばく線量は、広島で約10rad(0.1Gy)、長崎で30〜40rad(0.3〜0.4Gy)と推定されている。 1.2 被ばく線量の推定 原爆被爆による健康影響を知るためには、正確な被ばく線量を把握することが必要である。そのため、放影研は原爆被爆者の被ばく線量(初期放射線)の推定方式をこれまで何回か改訂してきた。1965年に暫定1965年線量(Tentative 1965 Dose: T65D)が提唱され、放射線リスク研究に広く使用されてきた。このT65Dは1970年代後半になって再評価され、1981年から1985年にかけて日米専門家が共同作業を行ない、コンピュータ計算によって推定する新たな線量評価方法(Dosimetry System 1986: DS86)が発表された。現在このDS86に基づいて放射線リスクが推定され、放射線防護基準の勧告を策定する際の基礎となっている。しかし、DS86にもいくつかの疑問が生じ、2003年にDS86に修正を加えたDS02(Dosimetry System 2002)線量方式が放影研の評価委員会で承認された。今後のリスク推定には、このDS02線量が使用されることになっている。 2.人体影響 原爆投下から数か月以内に、広島で約11.4万人(人口の33%;軍人および朝鮮半島出身の人々は含まない)、長崎で約7万人(人口の28%)の人々が死亡した。爆心地から半径2km以内の死亡総数を100%としたとき、被ばく2週間以内に88.7%が、第3から第8週までに11.3%が死亡した。半径1.2km以内での死因の内訳は、爆風による外傷が20%、放射線障害が20%、熱線と二次的な火災による熱傷が60%であった。 2.1 急性障害 急性障害は1945年12月末までの症状をさすが、表1のように3期に分けられる。急性症状では、即死者は崩壊建物下での圧死や、焼死及び全身熱傷による。大量の放射線を被ばくした者では全身の脱力感、吐き気、嘔吐等の症状が現れ、数日の間に発熱、下痢、吐血等による全身衰弱で10日前後までに死亡した。病理学的には造血組織や腸の上皮細胞の障害が認められた。 亜急性症状の主なものは、吐き気、嘔吐、下痢、脱力感、各種出血、白血球減少、赤血球減少等であった。特に骨髄、リンパ節、脾臓などの組織が破壊され、その結果、顆粒球や血小板が減少し、感染に対する抵抗力の低下および出血症状が現れた。この時期の死因の多くは敗血症であった。放射線被ばくによる主要な急性障害は、脱毛、出血、口腔咽頭部病変及び白血球減少であるが、これらの発生率は被ばく線量の増大とともに顕著となり、50rad(0.5Gy)での5〜10%から、300rad(3Gy)での50〜80%まで直線的に増加した。脱毛は被ばく後8〜10週に起こった。 このような放射線障害からの回復は、被ばくの3〜4か月後から始まり、内臓諸器官の機能回復、脱毛からの発毛、各種血球の増殖、正常化が起こりはじめた。 2.2 後障害 原爆放射線による後障害とは、1946年以降に発生した放射線による人体影響である。個々の症例は一般に見られる疾病と同様な症状を呈するので、放射線に起因するのかどうかを識別するのはむずかしい。しかし、被ばく集団としてみたとき、集団中に発生する頻度が高い疾病は放射線に起因している可能性が高いと判断される。つまり、放射線の影響は統計的解析によってはじめて明らかにされる。このため、原爆による後障害を正しく評価するためには、科学的な調査が必要である。 以下に放影研が行なっている主要調査について述べる。 放影研では、1950年の国勢調査で把握した原爆被爆者とその対照者からなる約12万人の調査集団(寿命調査集団)を設定し、1950年から死亡追跡調査を行なっている。また1958年に開始された広島市・長崎市の腫瘍登録とレコードリンケージをして、がん罹患調査も行なっている。さらに寿命調査集団のうち約2万人については2年に1回の定期検診が行なわれている。これとは別に3600人からなる胎内被爆者、約8万人からなる原爆被爆者の子供(被爆二世)の調査集団を設定し、死亡追跡調査、がん罹患調査を行なっており、この2つの調査集団の一部についても定期検診を行なっている。以上の3つの調査集団について、被爆者個人ごとの線量を被爆状況の聞き取り調査により推定している。なお、以下に示す結果はDS86線量を使用した解析結果である。上述の通り最近線量推定方式が変更されたが、がん死亡のリスクにおいてDS86線量からDS02線量への変更の影響は小さいことが判明しているので、以下の結果が線量方式の変更により大きく変化することはないと思われる。 2.2.1 放射線誘発がん 後障害の中で最も重要なものは悪性腫瘍の発生である。図1に、1Svの放射線を被ばくした時のがん死亡率(甲状腺がん、皮膚がんについては罹患率)が、0Svの死亡率に比べて何倍高いかを示す相対リスクとその90%信頼区間を示す。図2に原爆被爆者におけるがん死亡者の中で放射線に起因すると思われる割合を示す。白血病と白血病以外のがん(例えば肺がん、乳がん等)とでは、被ばく後の発生パターン(図3)や線量反応関係が大きく異なっていた。そこで、白血病と白血病以外のがんに分けて以下に述べる。 (a)白血病 種々の後障害の中でも、白血病は最初に認められた悪性疾患で、広島では1948年、長崎では1947年が最初とされている。この年から白血病が多発しはじめたことは明らかであるが、寿命調査集団が設定された1950年以前では被ばく者集団が不明確なため、この期間(1946〜1950年)での白血病発生のリスクを正確に推定することはできない。白血病発生は1950〜1953年の間でピークに達したが、その後徐々に低下し、現在では殆どバックグランドレベル近くまで下がっている。白血病の中でも慢性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病は放射線によって誘発される可能性が高く、ついで急性骨髄性白血病が高い。しかし、慢性リンパ性白血病や成人T細胞白血病(*1)は、原爆被ばくによる増加が認められていない。白血病の相対リスクは固形がんに比べて高いが(図1)、死亡数は少ない(図2)。表2に被ばく線量別の白血病死亡数、放射線に起因すると思われる死亡数および割合を示す。1Sv以上の線量を被ばくした白血病死亡者のうち84%は放射線に起因すると推定される。発生の相対リスクは、同じ被ばく線量でも被ばく時年齢が若いほど高い(図4)。男女で差は認められていない。線量反応曲線は、3Sv以上ではリスクは減少もしくは横ばいになっており、0−3Svでは直線ではなく高線量域で急激に増加する上向きの線形ニ次曲線を示している(図5)。 (b)白血病を除くその他のがん 白血病以外の固形がんは、部位別の発生パターン、線量反応関係、放射線の影響を修飾する要因等は大きく異ならない。固形がんの相対リスクは白血病に比較して低く、すべての部位で信頼区間は重なっており、統計的に部位により相対リスクが異なるとは言えない(図1)。放射線被ばくによって死亡した人の割合は低いが死亡数は多い(図2)。表3に被ばく線量別の固形がん死亡数、放射線に起因すると思われる死亡数および割合を示す。1Sv以上の線量を被ばくした固形がん死亡者のうち、39%が放射線に起因すると推定されるが、0.005−0.2Svの被ばくでは2%のみが放射線に起因していると推定される。一般的に、固形がんは被ばく者ががん年齢に達したときに発生し、その後がん自然発生率に比例してリスクが増加している。したがって、被ばく時年齢が若いほど、潜伏期は長く、放射線誘発の固形がんの最小潜伏期は通常10年とされている。また一般的に、相対リスクは被ばく時年齢の若い方が高く、男より女の方が高い。線量反応関係は、3Sv以上では白血病と同じくリスクは減少もしくは横ばいになっているが、0−3Svでは白血病と異なり直線である(図6)。胃がん、肺がん、乳がん等ほとんどの部位で直線関係を示すが、皮膚がん(悪性黒色腫以外)は直線でなく、1Sv程度まではリスクのないしきい値のあるモデルを示唆していた。 2.2.2 遺伝的影響 原爆被爆者の子供に対する遺伝的影響を調べるため、1940年後半から胎児の流早産や死産、胎児・新生児における奇形の発生が調べられたが、統計的に有意な影響は検出されなかった。また、遺伝生化学的手法で血中の変異タンパクをマーカーとして突然変異の出現率を調べたが、影響は検出されなかった。さらに、DNAまたはRNA中の突然変異を直接検出する調査が1985年から行われているが、これまでのところ遺伝的影響があることを示す結果は得られていない。また、原爆被爆者の子供のがん死亡率、がん罹患率、がん以外の疾患による死亡率ともにリスクの上昇は認められていない(表4)。 2.2.3 胎内被ばく 母親の胎内で放射線に被ばくし、原爆時から1946年5月31日までの期間に出生した者を胎内被ばく者という。爆心地から2km未満の胎内被ばく者数は約1,100人と推定されている。胎児期の脳は放射線感受性が高く、原爆放射線と精神遅滞及び小頭症との関連が明らかにされてきた。特に受胎後8〜15週齢の胎児に重度精神遅滞の頻度が高く、16〜25週ではその頻度は低くなる。この感受性期は、増殖したニューロンが大脳皮質へ移動する時期に当たっている。線量反応関係は0.2Gy以上から直線的に増加している(図7)。胎内被爆者の発がんリスクは、10才未満までは上昇しなかった。その後追跡調査が継続され、成人でがんのリスクの上昇が示唆された。そのリスクの大きさは、幼児被爆者と同等であることが判明した。しかし、がん発症者数は少ないので今後の追跡調査が必要である。 2.2.4 その他の影響 その他の影響としては、白内障、若年被爆者における発育遅延がある。また甲状腺疾患(良性甲状腺結節、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症)も原爆放射線との関連が示唆されている。さらに最近、循環器疾患等がん以外の疾患でもリスクは小さいが死亡率の上昇が示唆されている。しかし、その理由やメカニズムは不明であり、今後の研究結果に注目する必要がある。 [用語解説] (*1)成人T細胞白血病 成人T細胞ウィルスによって起る白血病で、「血液のがん」である。造血機能に障害が起り、白血球が異常増殖する病気である。九州、四国、沖縄などの西南日本に多く発生し、しかも原因が分かっていることから一種の感染症と見られている。 <図/表> 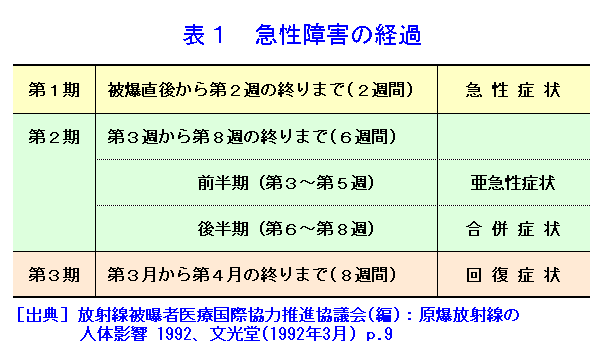
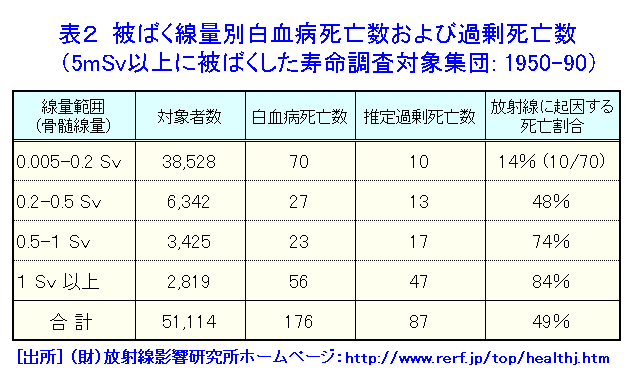
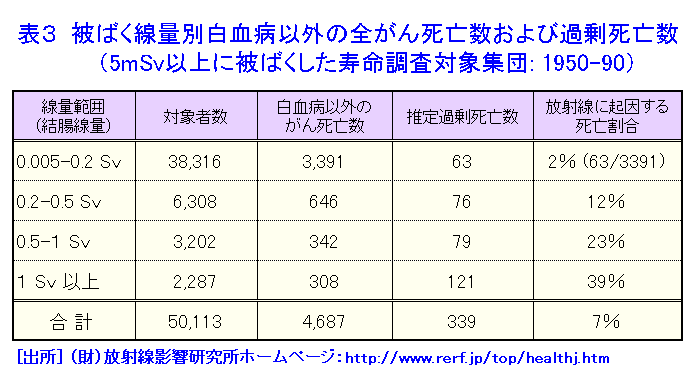
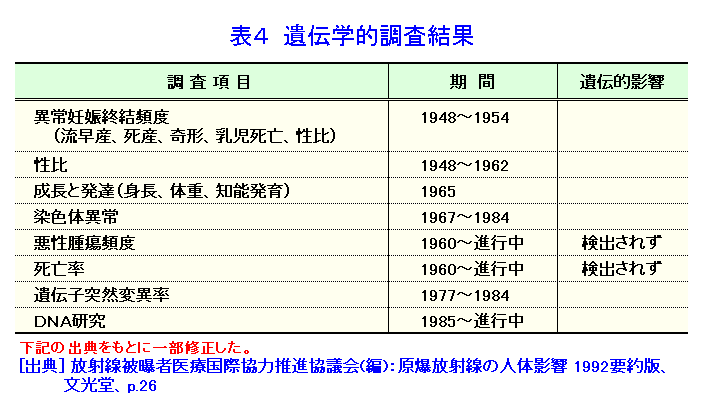
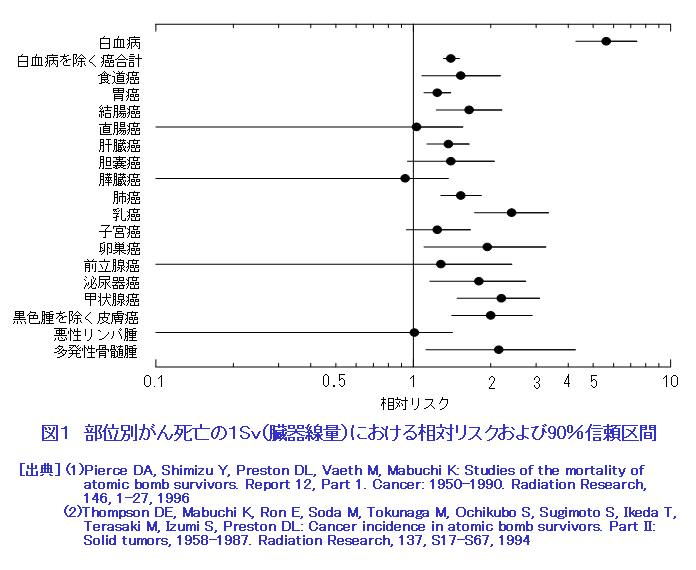
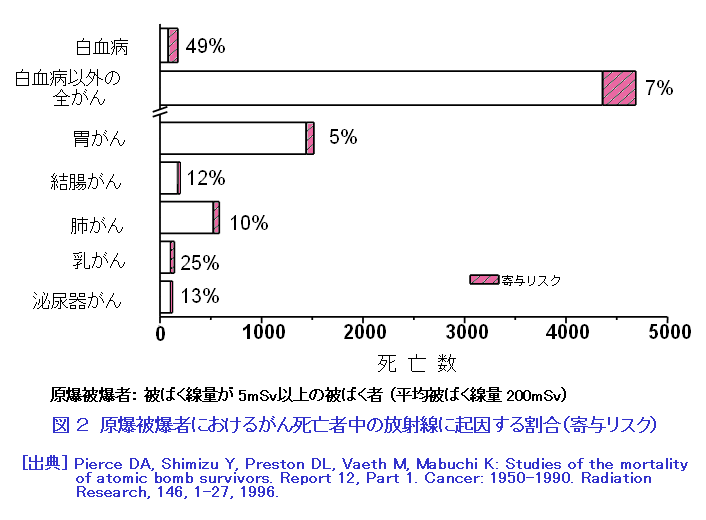
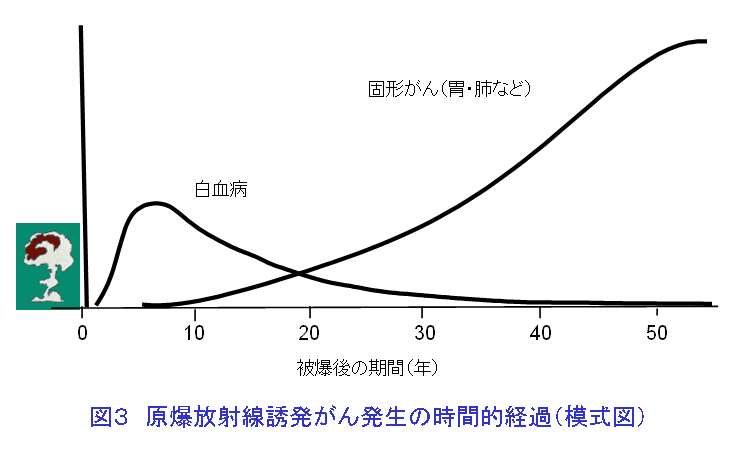
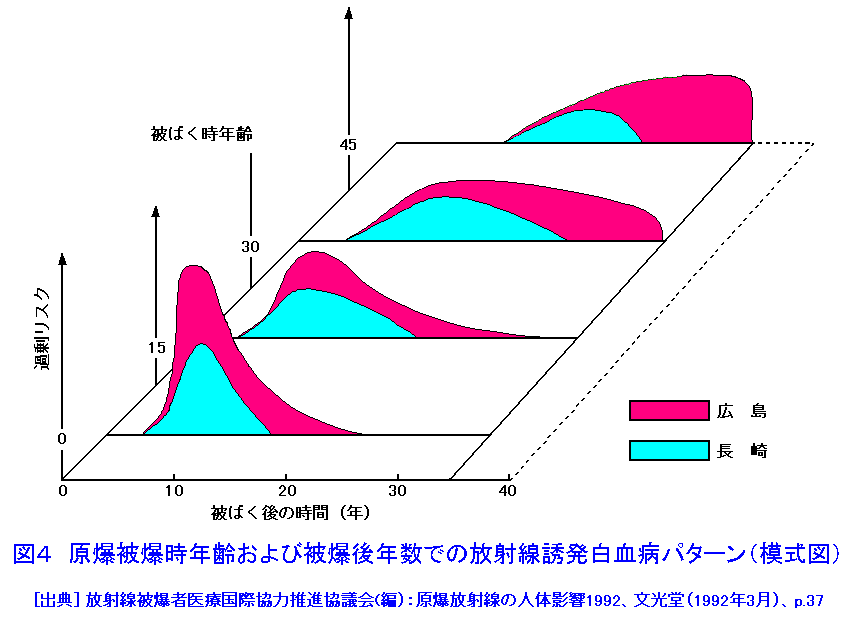
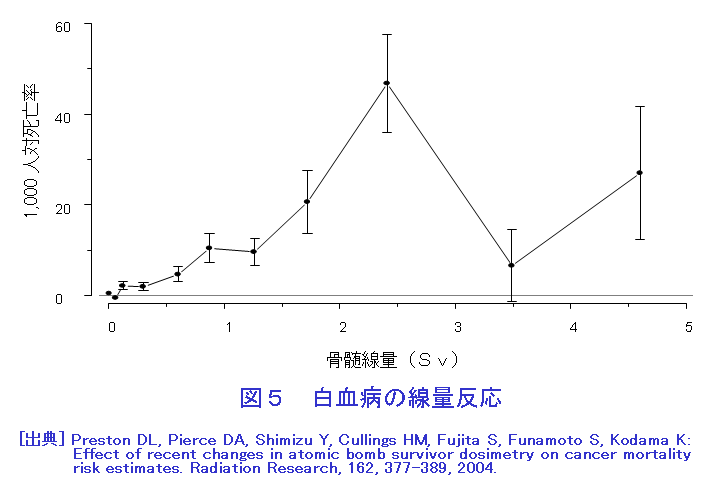
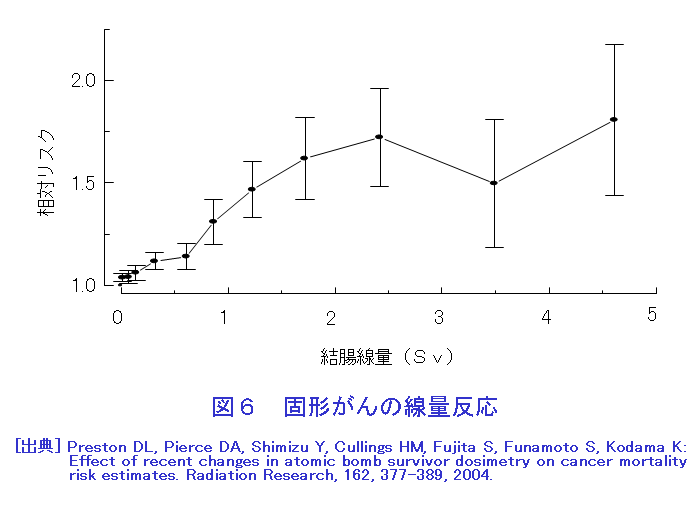
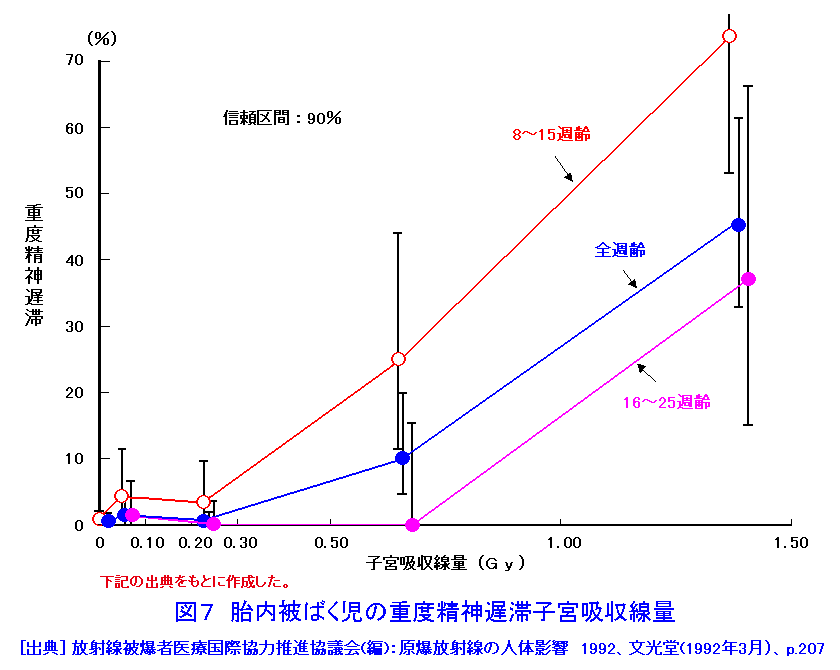
<参考文献> (1)放射線医学総合研究所(監訳):放射線の線源と影響、国連科学委員会(UNSCEAR)2000年報告書、実業公報社(2002年3月) (2)放射線被曝者医療国際協力推進協議会(編):原爆放射線の人体影響 1992、文光堂(1992年3月) (3)放射線影響研究所要覧、(1993年4月) (4)放射線影響研究所ホームページ (5)Pierce DA,Shimizu Y,Preston DL,Vaeth M,Mabuchi K: Studies of the mortality of atomic bomb survivors. Report 12,Part 1. Cancer: 1950-1990. Radiation Research,146,1-27,1996. (6)Thompson DE,Mabuchi K,Ron E,Soda M,Tokunaga M,Ochikubo S,Sugimoto S,Ikeda T,Terasaki M,Izumi S,Preston DL: Cancer incidence in atomic bomb survivors. Part II: Solid tumors,1958-1987. Radiation Research,137,S17-S67,1994. (7)Preston DL,Shimizu Y,Pierce DA,Suyama A,Mabuchi M: Studies of mortality of atomic bomb survivors. LSS Report 13: Solid cancer and noncancer disease mortality 1950-1997. Radiation Research,160,381-407,2003. (8)Preston DL,Pierce DA,Shimizu Y,Cullings HM,Fujita S,Funamoto S,Kodama K: Effect of recent changes in atomic bomb survivor dosimetry on cancer mortality risk estimates. Radiation Research,162,377-389,2004.
|

