|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
世界の高速炉は、40MWt以上の実験炉、原型炉及び実証炉合わせてこれまでに10基が閉鎖された。稼動中の発電炉は、ロシアのBN-600(600MWe)のみである。また日本の「もんじゅ」は、本格稼働の準備段階にある。 閉鎖した世界の高速炉は、米国のフェルミ1号炉、実験炉EBR-2及び高速中性子照射炉FFTF、フランスの実験炉ラプソディ、実証炉スーパーフェニックス及び原型炉フェニックス、ドイツの実験炉KNK-2、イギリスの実験炉DFR及び原型炉PFR、カザフスタンの原型炉BN-350がある。これらの炉の廃止措置(デコミッショニング)の概況に関して、回収ナトリウムの安定化処理、残存Naの安定化処理を含め安全貯蔵、解体計画等を中心に紹介する。 <更新年月> 2010年11月
<本文>
これまでに世界中で10基の高速炉が閉鎖されている。それらの廃止措置の概況を表1に示す。ナトリウム冷却高速炉の解体においては、軽水炉などの他の炉と比較して冷却材に用いたナトリウムの安全な処理、炉内残存ナトリウムの安定化処理が重要である。これらのことを含め各炉の概況を次に示す。 1.フェルミ1号の廃止措置概況 フェルミ1号は、最大出力65MWeのナトリウム冷却ループ型高速増殖炉として設計され、デトロイト・エジソン社の所有でミシガン州のエリー湖岸に建設された。1966年8月に本格運転したが、同年に冷却材流路閉鎖により燃料溶融事故を起した。修理を終えて、1970年に運転再開したが、結局1972年に閉鎖し、「安全貯蔵」の措置がとられた。その後、2000年に早期解体する許可を取得し、残存ナトリウム、アスベストの除去等の安全対策が実施された。施設の老朽化などの危険性が高まるとともに、コストが増大するため、解体を先送りすることはできるだけ避けるべきであるとして、2009年に認可終了書をNRCに提出し、2012年に廃止措置を完了する予定である。 2.ラプソディの廃止措置概況 ラプソディ(Rapsodie)は、フランスの商業用高速増殖炉開発のため、ループ型高速増殖炉の実験炉としてカダラッシュ研究センターに建設された(図1参照)。この炉は、運転技術の確立、及び材料/燃料照射試験のため、1967年から1983年4月まで運転された。また、原型炉であるフェニックス炉、実証炉であるスーパーフェニックス炉を建設するための基礎を築く役割を果たした。ラプソディ主容器から微少なナトリウム漏れが発生したため、材料/燃料照射試験等の役割をフェニックス炉に譲り、1984年に閉鎖された。 デコミッショニング計画は、完全解体(ステージ3)を目標として1984年に開始したが、1986年にIAEAステージ2へ計画変更、1991年に原子炉圧力容器閉じ込め作業(一次ナトリウム系を分離)を行い、1990年〜1993年に一次ナトリウム系解体作業等を行い、回収ナトリウムの処理を含め、ステージ2(原子炉本体の密閉処置状態、図2参照)を1994年に達成した。 回収ナトリウムの安定化処理には、NOAH法が開発され、適用された。1994年にその作業中に、重アルコールを使用したため、死者1名、負傷者4名を伴う爆発事故を起こした。その後、作業方法を改良し、軽アルコールに変更して無事処理を完了した。この事故は、フランスのみならず諸外国でもナトリウム安定化処理を行う際の貴重な教訓となっている。このNOAH法とは、次の化学反応を利用するものである。塩化ナトリウム(NaCl)は、放射性のNa-22が減少するまで保管し、その後に処分する。 Na+H2O → NaOH+1/2・H2、 NaOH+HCl→NaCl+H2O このプロジェクトにおける作業者の被ばく量は、0.31人・Svである。コストは1994年までに2.1億フランを要した。初期の計画では、25年間の安全貯蔵費用2.5億フラン(1千万フラン/年)及び原子炉本体の解体費用約0.6億フランを見込んだ。その後、安全貯蔵期間の短縮とコストの低減の観点から早期解体に向けて検討が行われた。2006年の規制当局への安全レポートの提出により、許可後5年以内の解体が可能となり、2010年代に廃止措置を完了させる計画である。 3.KNKの廃止措置概況 ドイツのカールスルーエ研究センターに建設されたKNKは、当初、電気出力20MWで1971年から1974年の期間、ナトリウム冷却ループ型原子炉の安全性を実証するために熱中性子炉心(KNK-I)で運転された。その後、高速増殖炉(SNR-300)開発のため、高速中性子炉心(KNK-II)に変更して1977年から1991年まで運転された。しかし、ドイツ政府が政策変更し、高速増殖炉開発を中止したことにより、閉鎖された。廃止措置計画は、1996年末、当初の「安全貯蔵」から「完全解体」に方針変更した。詳細な計画は10段階に区分して実施しており、すでに使用済燃料の撤去、炉内構造物の撤去、一次系及び二次系ナトリウム処理、タービン及び蒸気系の解体が完了している。第9段階での原子炉容器、炉内構造物などナトリウムの付着した機器の解体は、火災の危険性から機械切断のみで行っている。一次遮へい及び生体遮へいの解体方法を図3に示す。解体廃棄物は、コンラッド処分場の基準容器及びドラム缶に入れ、最終処分までの期間、カールスルーエ中間貯蔵センターで保管される。第10段階では、補助施設の撤去、建屋の除染作業、サイト解放の確認測定を行い、2011年末までに緑地化される計画である。 4.EBR-2及び高速実験炉FFTFの廃止措置概況 米国のEBR-2は、アルゴンヌ国立研究所(ANL-West:アイダホ州)に建設された実験炉で、熱出力62.5MW、電気出力19.5MWのナトリウム冷却タンク型高速増殖炉である。米国の高速炉開発計画の終結決定に基づき、1994年9月に恒久停止された。一次系ナトリウム約325m3、二次系約50m3及びナトリウム−カリウム(NaK)約2m3が抜き取られ、2001年1月までに水酸化ナトリウムに安定化処理された。また、残存ナトリウムの不働態化処理(酸化膜を形成し金属の耐食性を向上させる処理)も行われ、2002年から安全貯蔵されている。 米国のFFTFは、高速中性子照射試験を目的とする熱出力400MWのナトリウム冷却ループ型高速炉でワシントン州ハンフォードに建設された。この実験炉は、1980年の臨界以後、照射試験に用いられたが、米国の高速増殖炉開発の中止に伴って1992年に閉鎖された。廃止措置計画は、第一段階の放射性物質の撤去、第二段階の安全貯蔵、第三段階の解体撤去の3段階に区分している。第一段階の主な作業は、984m3のナトリウムと約3m3のNaK及び使用済燃料の撤去であり、2006年までに完了した。2005年の環境影響報報告書に基づくFFTFサイト閉鎖計画で、もし、遮へい隔離(ENTOMB)方式を採用すれば2012年〜2014年の間に完了することができるとしている。 5.高速増殖炉PFR及び高速実験炉DFRの廃止措置概況 英国原子力公社(UKAEA)は、2000年10月、ドーンレイ・サイトの環境復旧計画を発表した(ATOMICAデータ「英国ドーンレイ・サイトの環境復旧計画 <05-02-04-11>」を参照)。この計画は、高速実験炉DFR、高速原型炉PFR等のデコミッショニングを含む大規模なものである。DFR及びPFRの外観をそれぞれ図4及び図5に示す。DFRでは、一次系のナトリウム−カリウムのセシウム等による汚染レベルが高く、その除去、処分が課題である。そこで、まず炉内の残存ナトリウム、1000体の使用済燃料を撤去し、引き続き施設の解体撤去を進める計画である。PFRは、政府の高速炉開発中止の方針に従って1994年に停止された。その後、炉心燃料及びナトリウムが抜き取られた。回収ナトリウム500トンを処理する装置は、2001年1月にタービン建家内に竣工した。この装置はフランスのラプソディにおけるNOAH法の経験を応用したもので、ナトリウムを塩水に溶かして海に安全に放出する。この処理プロセスの概要を図6に示す。PFR安全貯蔵のための建屋の設計・建設を行い、また、2008年までに1500トンのナトリウムの処分を行った。DFR及びPFRの廃止措置は、2009年の計画によると、コスト低減の観点から作業を速め、ドーンレイ・サイトの全クリーンアップ計画の中間目標である2024年までに完了させる予定である。2008年から2024年までのコストは、DFRが2億3000万ポンド、またPFRは3億3800万ポンドと評価している。 6.スーパーフェニックス及びフェニックスの廃止措置概況 フランスの高速増殖炉スーパーフェニックスは、タンク型で実証炉として建設され、1985年から運転を開始したが、多くのトラブルにより1996年12月に停止し、運転認可が失効していた。最後は経済性等の理由により、1998年12月に閉鎖が決定された。その後、炉心から約600体の燃料が取出され、1999年から3年間かけて一次及び二次系のナトリウムが抜き取られた。全ナトリウム量は5,500トンであり、一次系容器内が3,300トン、二次系とその他のループ内が2,200トンである。現在、一次容器内に残留している約1%のナトリウム(37トン)の除去作業中で、コア−キャッチャ部(炉心溶融事故時の対策として設置)等にトラップされているナトリウム回収のため、遠隔操作可能な穴あけ用ドリル・マシンを炉心上部に設置し、作業が行われる(図7参照)。今後、実験炉ラプソディの経験に基づき、回収ナトリウムの安定化処理が行われる計画である。原子炉本体は、放射能の減衰を計算に入れて40〜50年間安全貯蔵し、その後に解体される。廃止措置費用は運転停止後費用5.8億ユーロと解体撤去費用8.8億ユーロの総額15億ユーロ(約2,000億円)と見積もられている。 原型炉フェニックスは、1991年から始めた長寿命の超ウラン元素の核種変換プログラムの終了に伴い2009年3月に通常運転を終了した。また、2010年2月に試験運転も終了した。今後の計画では、廃止措置方式に即時解体を選択し、使用済燃料の取出しとナトリウムの抜き取り、ナトリウム処理施設及び遠隔解体装置を準備し、さらに合計1450トンのナトリウム安定化処理、各ナトリウム系の撤去、原子炉容器の解体、建屋のクリーンアップ作業を2023年までに実施する。フェニックスの廃止措置コストは、2003年に、スーパーフェニックスの解体シナリオを参考に6億5000万ユーロ(−5000又は+3億5000万ユーロ)と評価した。その内訳を表2に示す。 7.BN-350の廃止措置概況 カザフスタンのBN-350は、旧ソ連時代にカスピ海に面するアクタウ(旧称シェフチェンコ)に建設されたナトリウム冷却ループ型高速増殖炉(燃料は高濃縮ウラン)で発電兼淡水製造用である。営業運転は1973年7月に開始したが、初期段階に蒸気発生器でのナトリウム漏洩事故が発生し、5基の蒸気発生器伝熱管の全数を交換した。その後もトラブルや燃料破損が起こり、その対策として1976年以降、熱出力を1,000MWtから650MWtに下げて運転してきた。しかし、老朽化のため廃止時期を早めることとし、約28年間の運転実績を残して1999年4月に停止された。 廃止措置に当たって、まず炉心燃料の取出し作業が行われた。BN-350では燃料破損が多く、ナトリウム中に核分裂生成物(FP)が多量に混入している。そこでFP除去技術が必要となり、その対応のため、燃料破損集合体の撤去、不純物除去用コールドラップ及び精製系の整備等を含む技術開発が、米国等の協力で進められている。また使用済燃料のドライ保管、ナトリウム処理など停止後の安全処置の検討が急務となっている。これらの計画は、IAEA、米国、日本などの国際協力を得て検討が進められている。廃止措置方式としては、IAEAステージ1(監視付き貯蔵)を選択し、約50年を経て解体をする方針である。 <図/表> 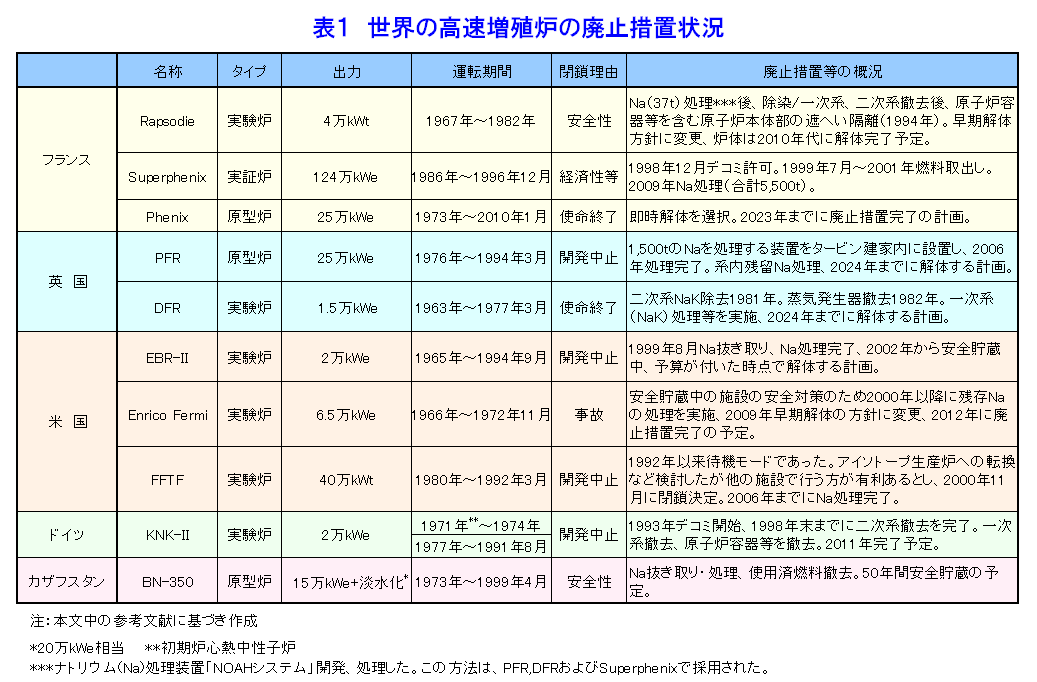
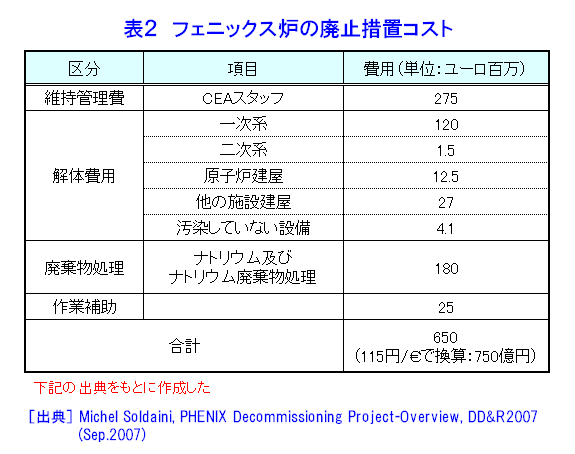
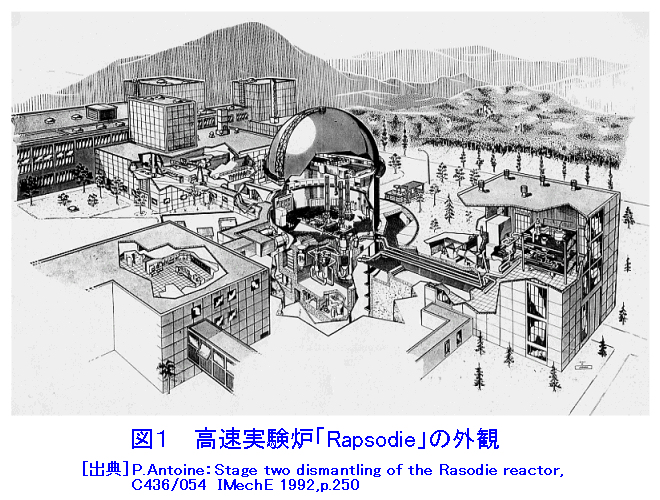
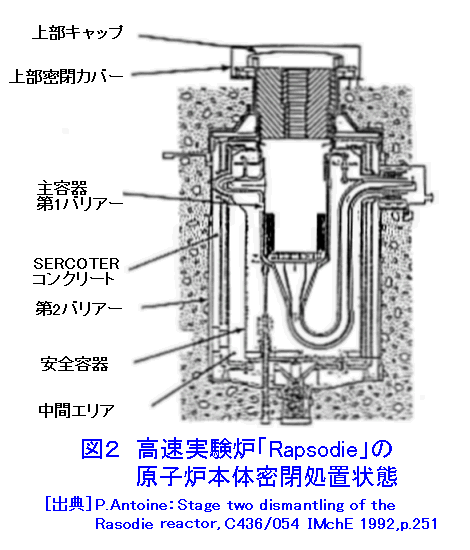
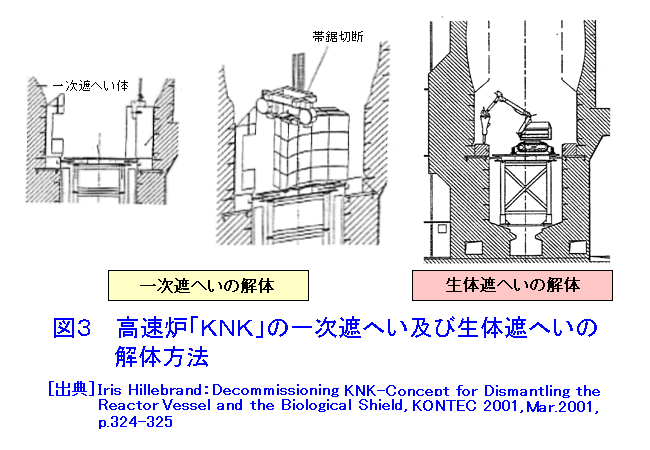

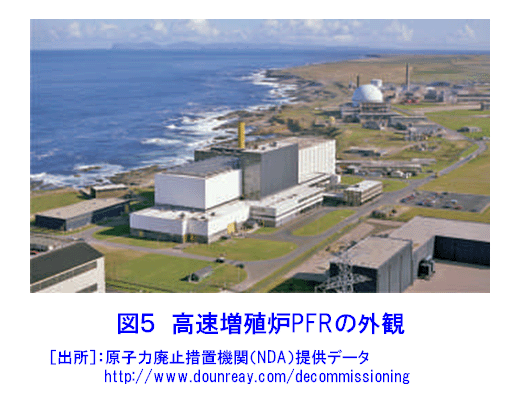
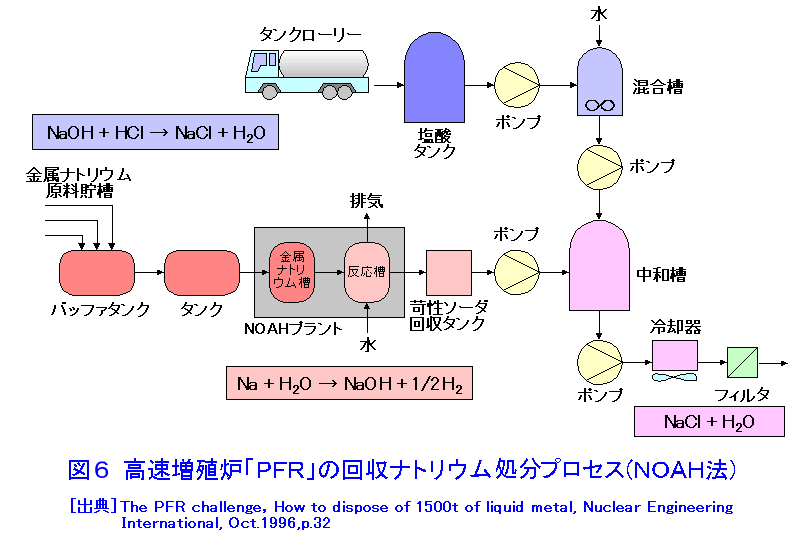
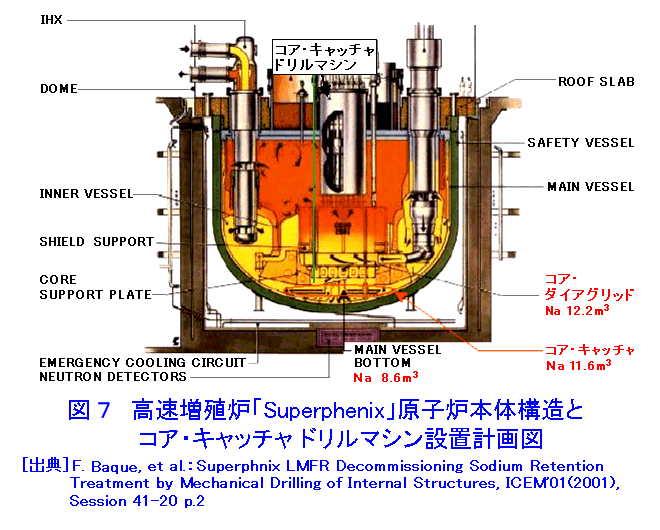
<関連タイトル> スーパーフェニックスの研究炉としての利用計画と廃止の決定 (03-01-05-14) スーパーフェニックスの研究炉としての利用計画と廃止の決定 (03-01-05-14) 原子力施設廃止措置に関するOECD/NEA国際協力 (05-02-01-08) 原子力施設廃止措置に関するOECD/NEA国際協力 (05-02-01-08) 英国ドーンレイ・サイトの環境復旧計画 (05-02-04-11) 英国ドーンレイ・サイトの環境復旧計画 (05-02-04-11) 高速増殖炉スーパーフェニックスの即時閉鎖(1998年12月30日) (14-05-02-12) 高速増殖炉スーパーフェニックスの即時閉鎖(1998年12月30日) (14-05-02-12) <参考文献> (1)日本原子力産業会議(編):原子力ポケットブック2010年版、日本原子力産業会議(2010年8月) (2)The NEA Co-Operative Programme on Decommissioning, The First Ten Years 1985-95, OECD 1996. (3)Gilles RODRIGUEZ, The French Sodium School:Teaching Sodium Technology for the present and future generations of SFR users, IAEA, Paper ID:FR09P1025. (4)Danny Swindle et al.:Resuming Decommissioning Activities at Fermi-1:Problems Encountered and Lessons Learned, Radwaste Magazine, July/August 1999. (5)Danny Swindle:Detroit Edison’s Fermi 1-Preparation for Reactor Removal, DD&R 2007, Sep. 2007. (6)P. Antoine:Stage two dismantling of the Rapsodie reactor, C436/054 Imech E 1992. (7)Jean Fontaine al.:Orientation for the Final Decommissioning of the RAPSODIE Fast Breeder Reactor, DD&R 2007, Aug. 2005. (8)Iris Hillebrand:Decommissioning the KNK-Concept for Dismantling the Vessel and the Biological Shield, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, KONTEC 2001, Mar.2001 (9)The Compact Sodium-cooled Nuclear Reactor Decommissioning Project at a Glance, (10)John A. Michelbacher, et al.:Shutdown and Closure of Experimental Breeder Reactor-2, 10th International Conference on Nuclear Engineering, April 2002. (11)Experimental Breeder Reactor-II (EBR-II) Facility, http://www.dd.anl.gov/projects/ebrII.html (12)T. M. Burke, al.:Closure of the Fast Flux Test Facility:Current Status and Future Plans, DD&R 2007, Aug. 2005. (13)The PFR challenge, How to dispose of 1500t of liquid metal, Nuclear Engineering International, Oct.1996. (14)Dounreay Site Restoration Ltd-Decommissioning, DOUNREAY LIFETIME PLAN RESEARCH & DEVELOPMENT PROGRAMME FROM 2009, Prototype Fast Reactor, Dounreay Fast Reactor, (15)F. Baqe, et al.:Superphenix LMFR Decommissioning Sodium Retention Treatment by Mechanical Drilling of Internal Structures, ICEM 2001 (2001) (16)Michel Soldaini, PHENIX Decommissioning Project-Overview, DD&R 2007 (Sep. 2007)
|

