|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
我が国の火力発電は、最初の発電所が明治20年(1887年)に日本橋茅場町に設置されて以来110年余の歴史を有する。我が国の地形的、気象的な要因により、電源開発は「水主火従」の形で進められてきたが、高度経済成長に伴う電力需要の急増と経済的な残存水力資源の減少、火力発電設備の信頼性と経済性の向上などによって、電源開発の主体は「火主水従」へと移行した。 燃料の燃焼で発生する熱エネルギーを電気エネルギーに変換するのが火力発電であり、これを原動機別にみると、蒸気タービンによる汽力発電、ディーゼル機関などによる内燃力発電、ガスタービン発電、そしてガスタービン発電と汽力発電を複合したコンバインドサイクル発電(複合サイクル発電)に分類される。 一般電気事業用電源の中で、火力発電は幅広い役割を担っており、石炭火力は原子力に次ぐベースロード電源として、LNG火力及びLNGコンバインドサイクルはミドルロード電源として、石油火力は主にピークロード電源として用いられている。 <更新年月> 2011年12月
<本文>
1.火力発電とは 石炭、石油、天然ガスなどの燃料の燃焼で発生する熱エネルギーを運動エネルギーに変え、さらに電気エネルギーに変換するのが火力発電である。使用する原動機の種類あるいは組合せによって、汽力発電、内燃力発電、ガスタービン発電、コンバンドサイクル発電(複合サイクル発電)などに分類される。現在、我が国では火力発電の多くは汽力発電であるが、天然ガスを燃料とする場合には熱効率及び運用性能の優れたコンバインドサイクル発電が広く採用されている。 各電気事業者が所有する火力発電所の種類別の数と認可最大出力(平成23年9月時点)を表1に示した。 2.火力発電の歴史 我が国における最初の火力発電所は、明治20年(1887年)に日本橋茅場町に設置された25kWの直流式火力発電所である。電気事業の初期には、電力消費地を中心として火力発電所を建設し、地区ごとに電気を供給していた。発電はすべて火力であったが、その後水力発電技術と長距離送電技術の発達に伴い、山間地の水力発電所から消費地の市街地まで送電できるようになり、消費地相互の送電連系もでき、発電の規模は次第に大きくなってきた。 我が国では地形的にも気象的にも水力発電が比較的容易であったため、年とともに数多くの新規地点が開発された。一方、渇水期に減少する水力発電の出力の補給用として火力発電も必要であり、いわゆる「水主火従」の形で建設が進められてきた。 第二次世界大戦後の高度経済成長に伴う電力需要の急増と経済的な残存水力資源の減少、火力発電設備の信頼性と経済性の向上などによって、1960年頃から電源開発の主体は火力(特に汽力発電、後述)となり、1962〜63年には「火主水従」の電源形態へと移行した。燃料もそれまでは石炭が中心であったが、1960年代には石油へとシフトした。我が国の火力発電の著しい発展は、当時のアメリカを中心とする最新技術の導入によるところが大きい。1970年代に入ると、技術の国産化に合わせて自動化・省力化などが進められ、1970年代初頭には燃料コストが低かった石油火力発電所が積極的に建設された。設備として、1967年には我が国初の超臨界圧を採用した600MW機が導入され、1974年には単機容量1,000MW機(蒸気圧力:24.1MPa、温度:538℃/566℃)が完成している。また、1969年には燃料としてLNGが導入された。 その後、1973年及び1979年の二度にわたる石油危機を経て、エネルギー情勢は激変し、火力発電は脱石油を目指した燃料の多様化と、より一層の高効率化、負荷調整能力の拡大を求められることとなった。熱効率の向上と負荷追従特性の改善のため、超臨界圧変圧運転方式やコンバインドサイクル発電方式の導入が進められ、1989年には31MPaの超々臨界圧の蒸気圧力をもつプラントが導入されている。 一方、脱石油依存を目指してLNG及び石炭の利用拡大が積極的に進められ、一般電気事業者(一般需要家に供給する電力10社)をみると2008年度の総発電電力量に占める比率はそれぞれ34%、18%となり、石油依存度は1973年度の75%から2008年度には10%にまで下がった。 3.火力発電の種類 3.1 汽力発電 汽力発電は燃料の燃焼熱でボイラを加熱し、高圧高温の蒸気を発生して、蒸気タービン、発電機を回転させて電力を発生する一種の外燃機関である。1880年代の初頭に実用化され、1898年に現在の原型が実現した。それ以前は、往復運動を回転運動に変えるピストン形の蒸気機関が産業を支える主力原動機であったが、効率が低く容量も小さいことから主力は蒸気タービンヘと移行した。今日の火力発電の中では、汽力発電が発電出力、発電電力量ともに圧倒的に高い比率を占めている。汽力発電の仕組みを図1に示す。なお、原子力発電、地熱発電、廃棄物発電(ごみ発電)も発電方式の分類上は汽力発電の一種であるが、以下では火力発電のみを対象として解説を行う。 汽力発電所の設備は、ボイラ、タービン、発電機などの主要機器のほかに、種々の付属設備から構成される。これらの設備を機能別に分類すると、およそ次のとおりとなる。 (1)燃料受入・貯蔵設備:揚炭機、貯炭場、コンベヤ、取引用計量装置、燃料(重油、原油、LNG、LPG)タンク、燃料油ポンプ、LNGポンプ、気化器など (2)ボイラ設備:ボイラ本体、微粉炭機、重原油ポンプ、バーナ、通風機、空気予熱器、集じん器、灰処理装置、煙突など (3)蒸気タービン設備:タービン本体、潤滑油装置、調速装置など (4)復水・給水系統設備:復水器、循環水ポンプ、復水ポンプ、給水加熱器、給水ポンプ、給水処理装置など (5)発電機及び電気設備:発電機、励磁機、変圧器、開閉装置、ケーブルなど (6)計測制御装置:各種計測装置、監視装置、プラント総括制御装置、自動バーナ装置、計算機制御装置など (7)諸設備:所内冷却水設備、所内空気設備、排水処理設備、保安防災設備など 3.2 内燃力発電 内燃機関とは、燃焼器内で燃料を燃焼させ、その燃焼ガスを作動流体として機械的仕事に変換する装置であり、燃焼を連続的に行うガスタービンと断続的に行うガソリン機関及びディーゼル機関の総称である。一般的にはディーゼル機関による発電を内燃力発電と呼んでいる。 ディーゼル機関は単機容量数十kWから10,000kWと幅広く、燃料が重油で熱効率も30〜40%と高く、かつ運転操作が容易で無人運転も可能なことから、電気事業用としては離島や非常用電源として、また民生用としてはホテルや病院の予備電源として数多く利用されている。さらに、ディーゼル機関は、その450℃前後の高温排ガスを熱源として温水を作り、発電とともに給湯も行うコージェネレーション(熱併給発電)設備としても利用されている。 なお、日本では重油の油種にA、Cの2つがあり、このうち軽油とほぼ同じ油種のA重油がディーゼル機関(非自動車用)に使用されている。(注:規格上はB重油もあるが最近では使用されていない。また、ボイラ用燃料としては、小型の場合にA重油、大型の場合にはC重油が用いられる。) 3.3 ガスタービン発電 ガスタービン発電は、燃焼器で燃料を連続的に燃焼し、その燃焼排ガスを用いて直接タービン発電機を回転させ、発電を行う機関である。我が国では重油を燃料とした2MW機が1956年に自家用として建設され、1980年代前半になって、A重油あるいは軽油を燃料としたものが電気事業用の非常用あるいはピーク用電源として使われ始めた。 ガスタービンは、単機容量が60〜70MW程度と小さいので増設が容易である。建設費が他の発電方式に比べて小さいので、稼働率が低くても設備費はあまり負担にならないが、発電効率が蒸気タービンよりも低く、稼働率が高くなると燃料費の負担が大きくなる。さらに、蒸気タービンに比べて起動時間が短いという特長もあり、これらの特性から一日のピーク時間帯の電力需要に対応する役目を担っている。現在では灯油、軽油の他、LNGなども用いられ、燃料は多様化している。 3.4 コンバインドサイクル発電 高温の燃焼ガスをガスタービンで用い、ガスタービンから排気される低温ガスを蒸気タービンで利用して発電するのが、コンバインドサイクル発電である。この仕組みを図2に示す。 1980年代に入ってガスタービンの単機容量が100MW級へと増大したこと、天然ガスが安価に供給され始めたことなどに伴い、急速に建設が進められ、2000年代の我が国の火力発電の主流となった。特に、天然ガスを燃料として低NOx燃焼器を導入したことにより、環境特性もよくなり、また、ガスタービン翼の冷却技術の向上からガスタービン入口燃焼ガス温度も1500℃と上昇し、所内率を控除した送電端の発電効率が50%を超える水準になった。(注:「所内率」とは全発電電力量のうち発電所内部で消費する電力量の比率をいう。)最近建設される大型LNG火力のほとんどはコンバインドサイクル方式であり、また、既存の石油火力、LNG火力の出力増強(リパワリング)にもコンバインドサイクルが活用されている。 4.環境保全技術 環境問題の重要性が認識されるに伴い、火力発電の環境保全に対する要求も強くなり、さまざまな技術対策が講じられている。火力発電所から排出される大気汚染物質としては、二酸化炭素(CO2)、粒子状物質(煤じん)、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)などがある。 火力発電では、炭化水素燃料を用いているので、原理的にCO2の発生は免れない。排ガスからCO2を回収し、貯留する技術の開発も行われているが、発電コストへの影響が大きい上、貯留技術(CCS)が十分に確立されたわけではなく、まだ本格的な実用段階にはない。火力発電のなかでは、H/Cの比の大きいメタンを用いるLNG火力の排出量が小さいが、高効率のLNGコンバインドサイクルでは排出量をさらに低減できる。石炭火力では高効率化によってCO2の低減を図っているが、図3に示すように発電電力量当たりの排出量は電源の中で最も大きい。 その他の大気汚染物質に対しては、次のような対策技術が採られている。 (1)粒子状物質(煤じん)の低減 重油・原油燃焼時の未燃焼炭素を主体とした煤じんや、石炭燃焼で発生するフライアッシュ(石炭灰)を捕集する技術として、圧力損失が低く、メインテナンスが容易な電気集じん機(ESP:Electrostatic Precipitator)が、ガス燃焼以外のすべての火力発電所に設置されている(図4)。 (2)硫黄酸化物(SOx)の低減 SOxは、燃料中の硫黄分が酸化されて発生し、その排出量は燃料中の硫黄分含有率でほぼ定まる。したがって、国の環境規制を満足するためには、全硫黄分が0.5%の石炭を用いた場合でも、排煙脱硫装置を設置する必要がある。石油の場合には、輸入原油の重質化・高硫黄化に伴い、精製過程での脱硫(水素化脱硫)がほとんどの製品に適用されているので、最近では重油の硫黄分含有率もかなり低くなってきている。全硫黄分0.1%以下の燃料を使用している石油火力では、脱硫装置は設置されていない。 火力発電所に設置されている排煙脱硫装置のほとんどは、水と混ぜた石灰石スラリーと排ガス中のSOxを反応させ、硫黄分を石こうとして回収する湿式脱硫方式を採用している(図5)。 (3)窒素酸化物(NOx)の低減 燃料の燃焼により発生するNOxは、燃料中の窒素分の酸化による燃料寄与NOxと空気中の窒素の酸化による空気寄与NOxとに分類される。燃料寄与NOxの発生量は、燃料中の窒素含有率と燃焼方法により大きく影響される。窒素含有率が低い場合には、燃焼条件の調整だけで新たな排煙処理装置を設置せずに、NOx排出量を低減できる。 空気寄与NOxの発生量は、燃焼温度に強く依存し、高温下で多く生成する。石炭ではNOx発生量のうち20%程度が空気寄与NOxであり、天然ガスでは100%が空気寄与NOxである。このように、空気寄与NOxが主体の天然ガスと燃料寄与NOxが多い石炭では、燃焼時のNOx生成抑制法が異なる。 そこで、NOxの対策としては、窒素分含有率の少ない燃料の使用、燃焼法の改善による発生量の抑制、及び排煙脱硝装置による分解、低減があげられ、これらの方策を組み合わせてNOx排出量の低減を図っている。アンモニア選択接触還元法による排煙脱硝装置を図6に示す。 5.火力発電の位置付けと課題 我が国の電力需要は、民生部門における冷暖房用電力の増加などによって季節間及び昼夜間の格差が大幅に拡大してきている。そこで、流れ込み式水力、原子力を専らベースロード電源に利用するとともに、火力発電を燃料と方式に応じてベースロードからピークロードまで幅広く利用している。例えば、設備費は高いが燃料費の安い石炭火力はベースロード電源に、高効率でLNG火力の中でも燃料費の小さいコンバインドサイクルはミドルロード電源に、また、設備の減価償却を終えた旧式の石油火力や設備費の安いガスタービンはピークロード電源として用いている。 我が国では火力発電に用いる燃料のほぼ全量を輸入している。また、燃料は炭化水素なので多かれ少なかれCO2を環境に排出する。そこで、燃料の安定的な確保を図りつつ、CO2の排出削減を進めていく必要があるが、現実にはその実施は容易ではない。石炭は低コストで安定的に輸入可能であるが、CO2排出量が最も多い。他方、CO2排出量が少ない天然ガスは、これまではアジア地域から調達していたが、今後輸入を増やす場合には中東またはロシアに依存せざるを得ず、供給安定性に不安が生じる。そこで、今後の火力発電開発の重要課題としては、より一層の熱効率向上を目指した高温ガスタービンの開発とこれを利用した高効率コンバインドサイクルの利用、永年にわたり開発を行ってきた石炭ガス化複合サイクル発電(IGCC)の早期実用化等が挙げられる。 <図/表> 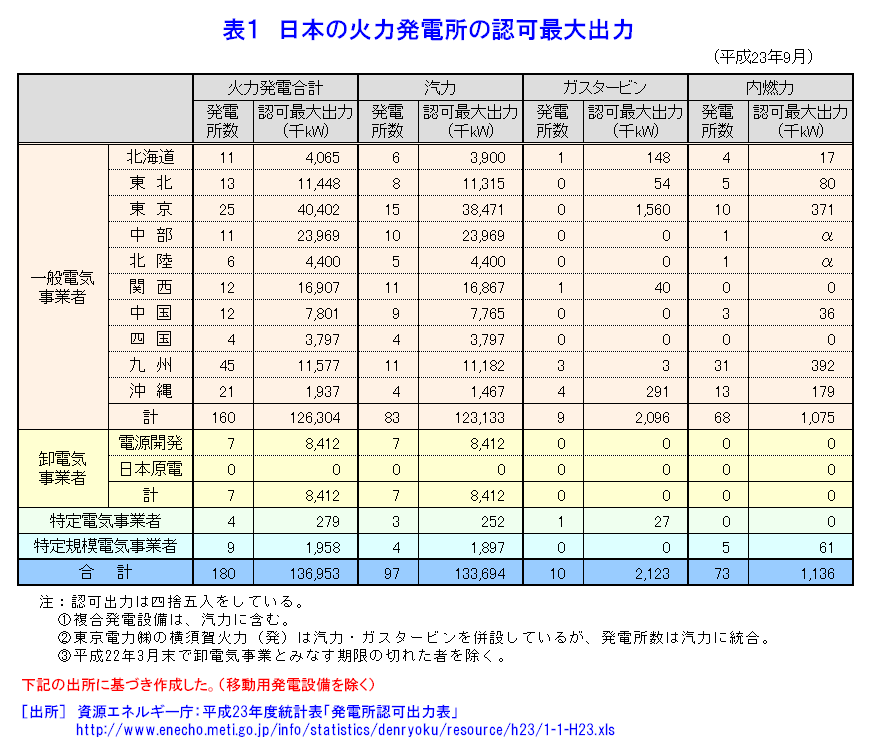
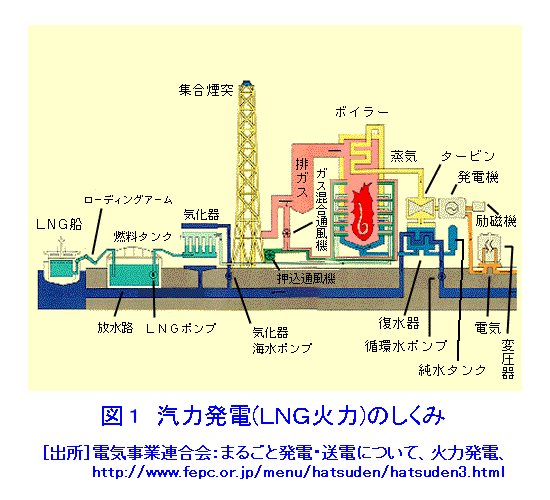
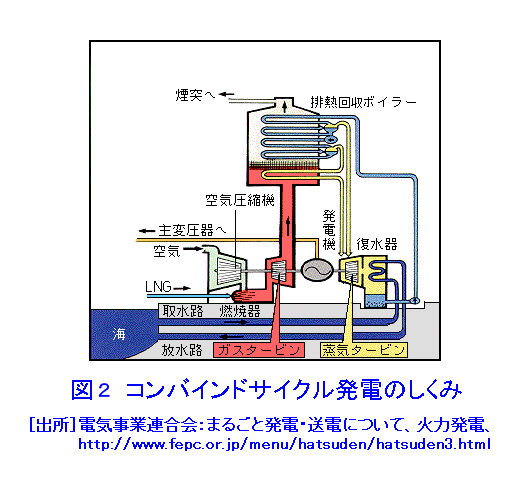
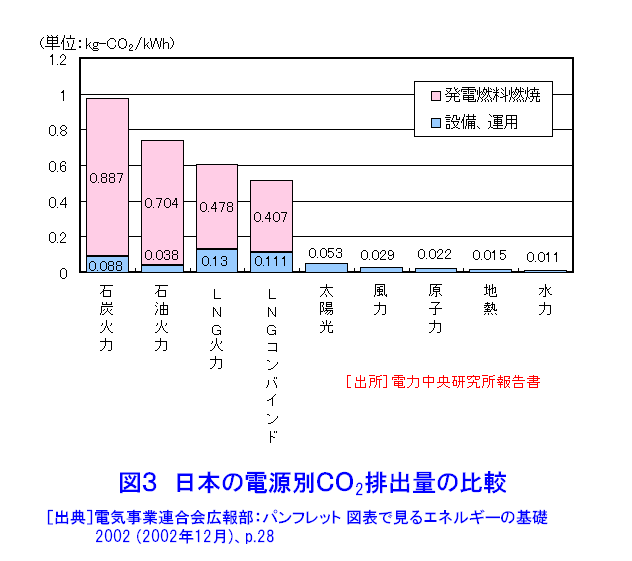
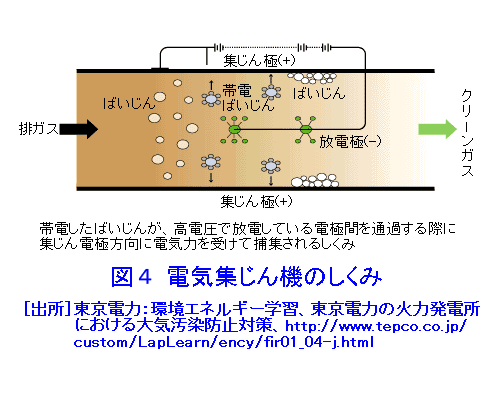
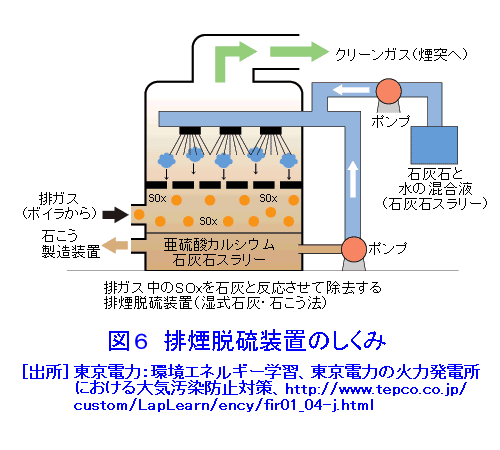
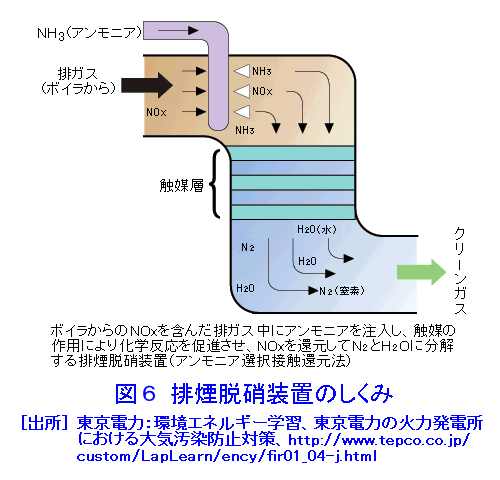
<関連タイトル> 水力発電 (01-03-05-01) 最新鋭石炭火力発電 (01-03-07-02) <参考文献> (1)瀬間 徹(監修):火力発電総論、(財)電気学会出版事業委員会(2002年10月)、p.1-14、93-112 (2)電気工学ハンドブック 第6版、(財)電気学会(2001年2月)、p.1077-1080 (3)電気事業連合会:まるごとわかる!エネルギー入門、 (4)(財)エネルギー総合工学研究所:?を!にするエネルギー講座、主な発電方式の特徴 (5)電気事業連合会広報部:パンフレット電気事業の現状 2002-2003(2002年11月)、p.7 (6)電気事業連合会広報部:パンフレット図表で見るエネルギーの基礎2002(2002年12月)、p.21、28 (7)資源エネルギー庁(編):エネルギー2003、(株)エネルギーフォーラム(2002年11月)、p.270 (8)広島国際学院大学 電気工学科 酒井研究室ホームページ:火力発電の歴史 (9)東京電力:環境エネルギー学習、東京電力の火力発電所における大気汚染防止対策 (10)資源エネルギー庁:平成23年度統計表「発電所認可出力表」
|

