|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
放射線の生物学的効果は、同一の吸収線量であっても放射線の種類や線量率によって異なる。高線量率で短時間に照射したときに得られる生物効果に比べて、線量率を下げて時間をかけて照射すると生物効果は減弱する。これを線量率効果という。このとき、同じ効果を得るのに要する線量の逆比を線量・線量率効果係数(DDREF)という。また、線量、線量率は同一でも小線量に分け間隔をあけて分割照射すると生物効果は減弱する。このような効果は照射中や照射後におこる細胞の回復によると考えられている。また、標的の大きさとトラック数の関係を考慮したマイクロドシメトリー的な考察では線量効果は線量レベルによって異なる。 <更新年月> 2002年10月
<本文>
1.線量率と生物学的効果 放射線の生物学的効果で問題となるのは放射線が生体構成物質に吸収されたエネルギーの量(吸収線量)と、単位時間当りの吸収線量(線量率)であるが、同一の吸収線量であってもその生物学的影響は線量率によって大きく異なってくる。たとえば、高線量率で短時間に照射(急照射)することにより得られる生物効果とくらべて、同じ種類の放射線を線量率を下げて時間をかけて照射した場合には効果が減弱するので、より多くの線量を照射しないと同じ効果はえられない。このように同じ種類の同じ線量の放射線でも線量率によって効果の異なることを線量率効果という。線量率効果は対象となる生物効果の指標によっても、線量率の範囲によっても、また放射線の種類によってもことなる( 図1 参照)。まれであるが、高線量率より低線量率の方が効果の大きくなる場合があり、これを逆線量率効果という。 一般に、線量率効果がもっとも顕著にみられるのは低LET放射線であるエックス線やガンマー線による生物効果であるが、これは低線量率にすると放射線によって生じた細胞の障害が照射中に回復するためと考えられている。しかし、高LET放射線(中性子線、アルファ線など)では回復はおこらず、このような線量率効果はみとめられない。 ヒトは自然放射線を低線量率(1ミリシーベルト/年)で被ばくしているが、自然放射線による被ばくでは障害の発生は実証できていない。そこで低線量・低線量率での晩発影響を高線量率で被ばくしたヒトのデータをもとにしたリスク推定、とくに発がんのリスク推定のために動物を用いた発がん実験による線量・線量率効果係数(DDREF:Dose and Dose Rate Effectiveness Factor)を求める努力が続けられている。 一方、がんの放射線治療では、大量の放射線により腫瘍細胞を効率的に殺す必要があるが、低LET放射線、例えば コバルト60 のガンマー線やエックス線、電子線などは線量率効果が大きいので高線量率の線源をもちいて照射したり、あるいは線量率効果の殆どない中性子線や重粒子を用いることにより治療効果を高めることができる。 2.分割照射 線量率効果とは異なるが、分割照射による回復という現象がある( 図2 参照)。線量率が同じ放射線でも一度に照射した時と二回以上に分けて照射したとき(分割照射)では、同じ吸収線量の放射線でも生物効果がちがってくる。小量の線量に分けて時間をおいて照射するとその間に回復がおこり、放射線の生物学的効果は一度に照射した時より減弱する。しかしこの効果も放射線の種類、線量、照射間隔の長さ、細胞の種類等によって変わる。また、放射線治療では、がん細胞だけでなく、その周囲にある正常組織もある線量を受けることになる。したがって腫瘍に対して最大限の損傷を与える一方、正常組織の損傷を最小限にとどめる必要がある。そのため両組織のごくわずかの回復能の差を利用して放射線を小線量ずつ、間隔をおいて分割照射することにより、正常組織に対する損傷を軽減させるようにしている。 <図/表> 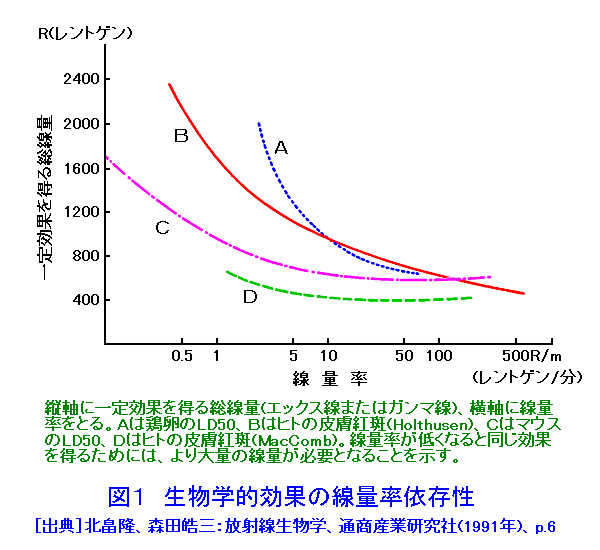
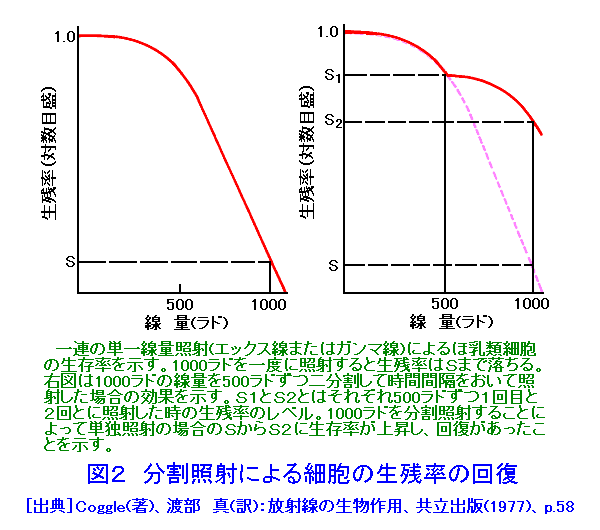
<関連タイトル> 被ばく線量に応じた細胞の反応にかかわる諸モデル (09-02-02-09) 放射線効果と修復作用 (09-02-02-12) 線量率と生物学的効果 (09-02-02-14) 放射線の種類と生物学的効果 (09-02-02-15) <参考文献> (1)Eric J. Hall(著)、浦野宗保(訳):放射線科医のための放射線生物学、篠原出版(1995年) (2)低線量電離放射線の被ばくによるヒト集団への影響、BEIR-3 報告書、ソフトサイエンス社(1983年) (3)菅野晴夫、杉村隆、山本正、太田邦夫:癌の科学第5巻、南江堂(1992年) (4)北畠隆、森田皓三(著):放射線生物学、通商産業研究社(1991年) (5)Coggle(著)、渡部真(訳):放射線の生物作用、共立出版(1978年) (6)国連科学委員会 1993年報告書、附属書F、実業公報社(1995)、p.629
|

