|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
わが国での食品照射研究は1950年代から開始され、1967年から1983年にかけてナショナルプロジェクトとして原子力特定総合研究が実施された。本プロジェクトでは国の代表的な食品である馬鈴薯、タマネギ、米、小麦、ウインナソーセージ、水産練製品、ミカンが取り上げられ、安全性、照射効果、照射技術などの研究が行われた。研究実施機関は各省庁の国立研究機関や公立研究機関、大学であり、それぞれ専門分野の研究が分担された。7品目の研究は全て安全性に問題がないことが明らかにされ、照射効果や照射技術も満足する結果が得られた。しかし、安全性評価では試験食品の動物への過剰投与や個体差によるデータのバラツキなどの問題があったが、再試験や総合的な評価によって安全性に問題のないことが明らかになっている。これらの成果を受けて1974年には馬鈴薯のコバルト60照射施設が北海道士幌に設置され世界初の商業照射が開始された。しかし、照射馬鈴薯の流通とともに反対運動も活発となり、国の食品照射実用化に対する姿勢は慎重になった。 <更新年月> 2007年01月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
多くの人は「放射線処理した食品」を「放射能処理」と勘違いして拒否反応を示すと思われる。これは、「放射線」と「放射能」を混同した誤解である。放射線はレントゲン撮影と同じであり、食品中に放射線は残留しない。すなわち、食品照射に用いられる放射線は可視光線と同じ仲間であり、可視光線のエネルギーが約1eV(エレクトロン・ボルト)に対して食品照射に用いられるガンマ線やX線、電子線のエネルギーは1万〜1,000万eVの透過力の強い電磁波または電子であり、誘導放射能の生成は無視できる。放射線による殺菌、殺虫などの生物作用は二次的に生成するフリーラジカル(活性種または遊離基)によるものであり、フリーラジカルは水存在下では0.001秒以下で消滅する。食品照射の利点は包装済みの食品や冷凍食品でも殺虫・殺菌ができ、生鮮状態の食品でも処理でき、固形食品の処理法としては最も優れた方法である。食品照射の研究は第2次世界大戦後にアメリカ、イギリス、フランス、ソ連等で開始され、安全性評価の研究を含め60年以上の歴史がある。その結果、放射線で起こる食品成分の分解、化学変化は加熱調理と似ており、遺伝毒性物質(発癌性物質など)の生成は加熱処理の方が多い傾向があることが明らかになっている。しかも、加熱や放射線で若干量生成する遺伝毒性物質(変異原性)の多くは野菜や果実によって無毒化することが報告されている。 しかし、一般消費者の多くは新しい食品加工処理技術に対して拒否反応を示す傾向がある。たとえば、加熱滅菌(完全殺菌)した缶詰食品は今でこそ一般食として普及しているが、19世紀初期のナポレオン戦争の時代に発明されて軍用食として利用されたにもかかわらず、拒否反応によって一般に普及するのに約100年かかっている。牛乳による加熱消毒殺菌(菌数低減のための殺菌)も19世紀半ばに開発され、生牛乳中の病原菌による小児の死亡率が加熱処理で著しく減少するのが明らかであったにもかかわらず、反対運動のため普及するのに50年以上かかっている。 食品照射初期の研究は貯蔵期間延長を目的としていたが、1980年代以降は食中毒防止など食品衛生の改善、海外からの農業害虫侵入防止のための植物防疫を目的とした応用が注目されている。本項では、わが国における食品照射の研究開発の経緯について解説する。 1.初期の研究および原子力特定総合研究 わが国の食品照射研究は欧米諸国より遅れ1950年代前半より開始され、冷凍アサリの殺菌効果、馬鈴薯やタマネギの発芽防止、各種微生物の放射線感受性試験などの基礎的研究が行われた。当時はアメリカなどで食品照射の研究が活発に行われており、わが国の食品関連学会関係者の間では食品照射は最先端の技術として注目されていた。1960年代に入ると多くの研究機関や大学で研究が行われ、1965年には学会としての食品照射研究協議会が発足した。当時、食品照射技術が注目されたのは、簡単な操作で大量の食品を処理でき、処理後も生鮮状態が維持できる点にあった。このような研究の進展を受けて原子力委員会は食品照射をナショナルプロジェクトとして原子力特定総合研究に指定した。この研究には各省庁の研究機関や公的研究機関、大学が参加し、選ばれた食品類は馬鈴薯、タマネギ、米、小麦、ウインナソーセージ、水産練製品、ミカンの7品目であった。研究項目は発芽防止や殺虫・殺菌などの照射効果、照射食品の安全性や栄養適性を評価する健全性、均一照射や線量測定などの照射技術等であり、図1に示すように国公立の研究機関、大学によって研究が分担された。 これらの研究では初めての経験ということもあって、照射および非照射食品の過剰投与による実験動物への異常発生、タマネギの発芽活動開始後の照射による発芽開始、ウインナソーセージの照射による異臭発生などの問題に直面した。ことに、照射タマネギの動物による安全性試験では投与量が多すぎたために非照射タマネギや照射タマネギを含む飼料で異常が発生し、最適投与量を求めて試験をやり直さざるを得なかった。このため、特定総合研究も1974年終了の予定が延長となり1983年まで研究は継続された。このような多分野にわたるプロジェツト研究により表1に示すように7品目全ての食品類で安全性に問題がないことが明らかになり、照射効果もほぼ満足する結果が得られた。 2.原子力特定総合研究の成果 照射効果では馬鈴薯の発芽防止線量は0.06〜0.15kGyであり、0.15kGy以上では腐敗が増加すること、照射後に遊離糖が増加する傾向があることが明らかになった。タマネギでは発芽活動開始後の照射は発芽防止効果がなく、休眠期での発芽防止線量は0.02〜0.15kGyであることを明らかにした。米や小麦の殺虫線量は0.2〜0.5kGyであり、殺虫線量ではカビの発生も抑制された。ウインナソーセージでは窒素ガス置換包装することによって照射による異臭発生を防止でき、3〜5kGy照射と低温貯蔵の組み合わせによって貯蔵期間を3〜5倍に延長でき食中毒菌も殺菌できた。水産練製品では3kGy照射で貯蔵期間が2倍以上に延長でき、エロモナス菌などの食中毒菌も殺菌できた。温州ミカンでは0.5MeV、1.5kGyの電子線で表皮のカビを殺菌することによって貯蔵期間が2〜3倍に延長された。健全性の研究では馬鈴薯やタマネギは薬剤と同じ100倍量の考えで「飼料中への食品の投与量x吸収線量」により表2に示すような過剰投与による飼育試験が行われた。このため、タマネギでは過剰投与による異常が生じたため2または4%で試験をやりなおした。慢性毒性試験(長期飼育試験)で使われたラットやマウスは雌雄30〜50匹であり、個体差によるデータのばらつきはあったものの7品目とも照射による異常は認められなかった。また、3世代にわたる繁殖試験(催奇形性を含む)、変異原性試験(遺伝毒性試験)でも照射による異常は認められていない(表3)。照射技術の研究もほぼ満足する結果が得られた。しかし、照射の有無を判別する検知法の研究では実用的な方法は確立できなかった。すなわち、当時の研究は簡単な化学分析や生物学的方法に依存しており、今日のような精密な物理的、化学的方法や生化学的方法は採用されていなかった(今日では実用的な検知法が開発されている)。栄養成分についても7品目とも特に問題はなかった。 3.照射馬鈴薯の実用化と反対運動 1970年頃に旧厚生省(現厚生労働省)は馬鈴薯等の照射を許可する前段階として食品への放射線処理を原則的に禁止するという法令を定めた。これは、照射食品が危険ということではなく法的規制のための処置であった。この後、1972年に馬鈴薯のガンマ線による発芽防止処理が認可され、馬鈴薯照射施設が北海道の士幌農協に建設された。本施設はコバルト60・20万キュリー、月間1.5万トンの設計であった。本施設は1974年から運転が開始され、毎年約1万トンが青果物市場に出回り、端境期の価格安定化に役だった。馬鈴薯照射には士幌農協など5農協が参加している。そして、商業化成功の要因としては従来の生産ラインの中間に照射施設を設置して人件費や輸送費などの増加がほとんどなく、照射時期が10月から3月まで取れることや、農協の実用化への熱意などが関係していたと思われる。 一方、世界初の照射食品実用化ということもあって、一部の消費者団体による反対運動も激しく起こった。この運動はマスコミの「放射能ジャガイモ」との誤報も重なって拡大し、その後の食品照射研究低迷の原因となった。食品照射反対運動の主要な論点は、1)旧ソ連のクチン氏らの照射馬鈴薯でラジオトキシンが生成するという報告やインドでの照射小麦を栄養失調児に与えた場合の血液中のポリプロイド(染色体異常の一種)増加の報告、2)原子力特定総合研究における動物試験で特定食品の過剰投与により非照射でも見られた動物の異常を照射のせいにする、3)動物試験での個体差程度のデータを拡大解釈する、などであった。しかし、旧ソ連やインドのデータは試験方法そのものに問題があり、各国の追試によっても再現性がないことから国際的に否定されている。国内のデータについても専門家による総合評価や再実験の結果によって安全性に問題のないことが明らかにされている。しかし、国内のデータについては今でも反対運動の論点にされてきている。その中でも、馬鈴薯やタマネギで得られた卵巣重量の減少と骨の奇形が取り上げられている。たとえば、照射馬鈴薯の飼育試験でラットの卵巣重量が減少したと指摘しているが、たしかに0.6kGy照射群の6ヶ月では非照射、0.1kGy、0.3kGy照射群と比較して減少しているが、他の飼育期間の3ヶ月、12ヶ月、24ヶ月では逆の傾向も示しており、線量との相関性は認められず、個体差によるデータのばらつきである。しかも、有意に減少した卵巣の組織学的観察でも異常は認められていない。また、照射タマネギでマウスの骨に異常が認められたというが、マウス胎児や新生児の剄肋(骨の奇形)発生は2世代目では照射タマネギで高いが、1世代や3世代では非照射と逆であったり、標準飼料群の方が著しく奇形が高い傾向を示しており、線量との相関性は認められない。剄肋は胎児や新生児で発生するが、成長に伴って消滅し、動物試験では重要な試験項目ではない。このように、反対運動側はデータの一部だけを取り上げて反対の理由にしている。 食品照射のナショナルプロジェクトは1983年に終了し馬鈴薯以外の品目についても研究成果が次々と得られ原子力委員会に報告された。しかし、許可になったのは馬鈴薯のみであり、他の品目については許可は得られなかった。この原因としては農業政策の転換なども関係しているが、反対運動によって旧厚生省(現厚生労働省)や農林水産省の許可や実用化に対する姿勢が慎重になったことが大きく関係している。 <図/表> 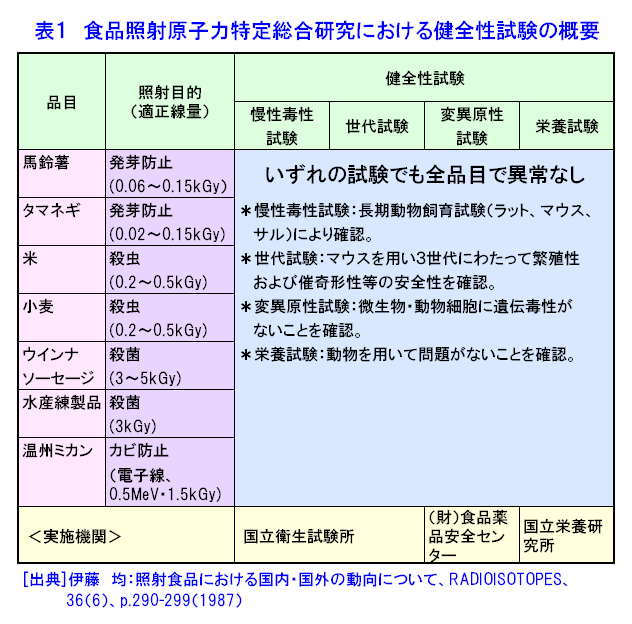
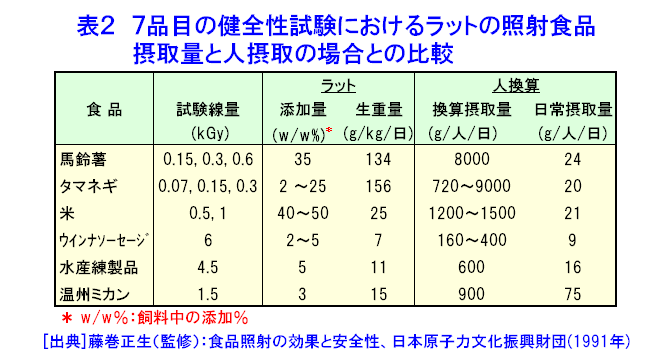
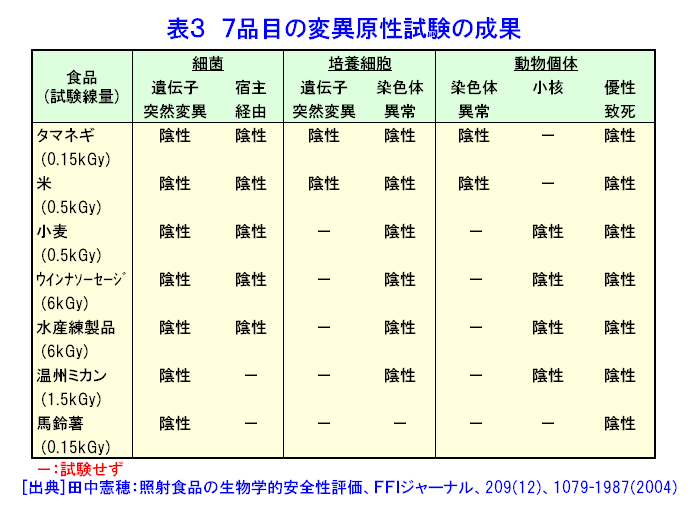
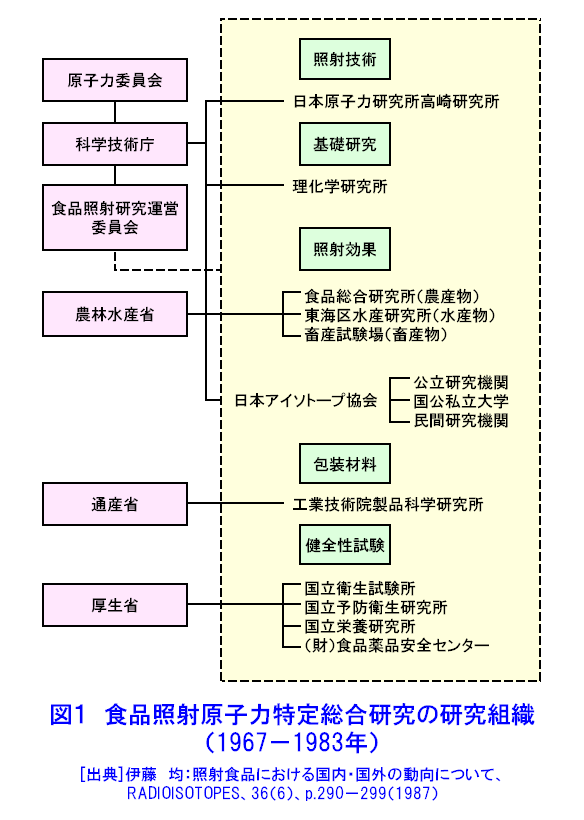
<関連タイトル> 動物用飼料の放射線処理 (08-03-02-03) 海外における食品照射の現状 (08-03-02-05) 米国における食品照射の動向 (08-03-02-06) わが国における食品照射技術の開発(その2)1980年以降の研究開発 (08-03-02-10) 電子線による殺菌の原理と応用研究の現状 (08-04-01-08) <参考文献> (1)伊藤 均:照射食品における国内・国外の動向について、RADIOISOTOPES、36(6)、p.290-299(1987) (2)藤巻正生(監修):食品照射の効果と安全性、日本原子力文化振興財団(1991年) (3)松山 晃、降矢 強、市川富夫、内山貞夫、伊藤 均、林 徹:照射食品、総合食品安全辞典、産業調査会・辞典出版センター(1994年)p.842-877、 (4)伊藤 均:食品照射の基礎と安全性、JAERI-Review 2001-029、日本原子力研究所(2001)
|

