|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
1989年、FleischmannとPonsら、及びJonesらによって、「パラジウム、チタン等の固体中に大量の重水素を吸蔵する電極を用いた電解法によって、DD核融合反応が起こる」という“常温核融合反応”の可能性が指摘され、新しいエネルギー生産技術の出現として大きな反響を呼んだ。以後、上記電解法(湿式法)による反応追試実験が広範に進められ、又乾式法でもこの反応が起こり得ることが指摘されてきたが、いずれもデータに再現性がなく、現状でも反応を確認するに至っていない。但し、過剰発熱と言われるものは核融合反応ではなく、従ってエネルギー発生機構の可能性については、ほぼ否定されており、核融合反応が固体中でこれまでと異なるメカニズムで起るかどうか、という観点で各種実験が一部で継続して行われている。 <更新年月> 2005年06月
<本文>
1.ことの始まり−1989年3月− 従来の核物理の理論によれば、核間距離0.074nmの重水分子内の核同士が低温で表1に示した核融合反応(1)、(2)を起こす確率は毎秒10−64/DD程度と見積られ、事実上零である。1989年3月下旬、英国サザンプトン大学のFleischmannと米国ユタ大学のPonsらは「パラジウムを陰極として重水電解質溶液中で長時間電解することによって、DD核融合反応によると思われる過剰の発熱を検出した」と公表した(文献1)。その発熱量は13〜17 W/cm3Pdにも及び、室温付近での核融合によって新しいエネルギー生産が可能であるとした。彼らの実験では発熱量に見合った中性子発生が検出されていないということから、従来考えられてきた(1)及び(2)式で表したような反応とは別の核融合が起こっていることも主張された。これに続いて同じユタ州のブリガムヤング大学のJonesらは「パラジウム、チタン、あるいはチタン合金などを陰極として、各種金属イオンを微量に含む重水中で電解した時、DD核融合によって発生するエネルギー2.45 MeVの中性子の検出に成功した」と公表し(文献2)。その反応確率自体は毎秒10−23/DD程度と小さいものの、従来の理論に基づく確率をはるかに上回るものであった。また同時に、このような僅かな確率の核融合反応はほとんどエネルギー源としての利用価値はないことも指摘された。これら2つの報告が図1に示す分類に見られるいわゆる“常温核融合反応”の出現である。 2.実験装置の解説 このような水素吸蔵性の金属を陰極とし重水溶液中で電解した時に起こるとされる核融合反応(重水電解反応)の概念図を図2に示す。従来の説を大きく覆すこれらの結果には発表と同時に強い関心が寄せられてきたが、とくに過剰発熱を伴うとされる反応には、科学においてのみならず新しいエネルギー源としての可能性が重要視されてきた。 常温核融合反応とは次のような現象と考えられている。パラジウム、チタン、それらの合金等は水素吸蔵金属、合金と呼ばれ、時には固体容積の1000倍程度にも達するほど大量の重水素を吸蔵する性質を持っている。したがって吸収された重水素の密度は固体重水素と比較しても十分に高い状態となっており、さらに重水素は固体中でイオンとして存在すると考えられている。このようにして固体中に凝縮された重水素はある条件下においてお互いに衝突し合い、常温においてさえある確率でDD核融合反応が起こる、というものである。この常温核融合反応を検知するには、表1の(1)、(2)式であらわした反応、あるいは通常確率的には極めて低いと考えられている(3)式で示したような反応の生成物、すなわち中性子、トリチウム、陽子、ヘリウム同位体、γ線、あるいは二次的に発生するX線、発熱量などを測定すればよい。 3.その他の種々の実験 1989年3月下旬のFleischmannとPonsら及びJonesらによる2件の衝撃的な“電解法による常温核融合反応発見”の報道以来、世界中で反応確認実験が行われた。内容は彼らが提案した反応の追試実験及び新しい反応系の探索、関連基礎研究など多岐にわたる。反応を肯定する結果を得たとする報告をもとに、国外、国内における研究の経過を概説する。 国外での経過は以下のとおりである。ユタ大学ではいち早く低温核融合研究所を設立し、ここでは電解に伴う過剰発熱現象の再現、その機構、及び核反応生成物の確認に重点を置いた研究が進められた。最初の報道から1カ月も経たないうちにフラスカティ国立研究所(伊)の研究グループは、電解法とは異なった重水素ガス加圧法によってチタン粒中に重水素を導入しこれを繰り返し冷却−昇温するとサイクル中に1秒当たり5000個にも達する中性子の瞬間的な放出(中性子バースト現象)が起こるということを発表した(文献3)。同様の現象がロスアラモス国立研究所からも報告された(文献4)。こうして電解法と乾式法の2つの基本的な反応系が出そろい、以後の反応確認実験がより広範に進められることとなった。 1989年5月中旬には米国サンタフェにおいて米国エネルギー省主催のワークショップが開催され、ここでは電解法、乾式法についての追試結果、理論的考察の結果などの多くの発表がなされ(文献5)、新たにテキサス農鉱大、スタンフォード大などの電解法による過剰発熱検出、及びテキサス農鉱大、ロスアラモス国立研究所の中性子発生確認等の肯定的実験結果が公表された。 1989年9月には京都で国際電気化学会が開催され、Fleischmann、Ponsらの熱バーストに関する最新データ、テキサス農鉱大の研究者らによる電解法における大量のトリチウム発生の結果等が示された。この間に新しい系での反応検証実験も幅広く行われた。それらのうち特に注目されたのは重水分子のクラスターを加速して重水素化したチタンターゲットに照射するという新しい方式であった(文献6)。 このようにして反応を肯定する結果の発表が続くなかで、その件数とは比較にならないほど多くの実験において反応に否定的なデータが得られた。さらに理論的にも常温核融合反応は決して起こり得ないとする論文も相次いだ。とくにFleischmann−Ponsの説に対する反論は数多く、彼らの熱測定法、及びγ線測定法、解析法の誤りが鋭く指摘された(文献7)。米国エネルギー省は常温核融合反応に関する調査委員会を設立し、調査と評価を進めてきたが、1989年秋に公表された調査・評価報告書で「反応を支持する根拠は得られなかった」と結論した(“A Report of the Energy ResearchAdvisory Boad to the USDOE”, Washington,DC 20585, DOE/S−0073(1989).)。 1989年10月にはロスアラモス国立研究所のグループが全く新しい乾式電解法によって大量のトリチウム生成に成功したことを発表した(文献8)。同年12月にはインドのバーバ原子力研究センターで大規模に行われてきた実験結果が公開されたが(文献9)、その内容は多岐にわたり、電解法、乾式法の追試の他に新しい各種の試みがなされている。彼らによると電解法による多くの実験において明らかにトリチウム生成が確認され、同時に計測した中性子の発生量はトリチウム生成量と比較して最大9桁程度低いものであったことが述べられている。 発端以来1年を経過した1990年3月、米国ユタ州ソルトレーク市において低温核融合研究所主催の第1回常温核融合反応国際会議が開催された。そこでは1年間の関連研究結果を総括する趣旨で、それまでに反応に肯定的な結果を公表した研究者による成果の発表が行われた(文献10)。ユタ大学の低温核融合研究所から過剰発熱確認、インドのバーバ原子力研究センターから電解法、乾式法によるトリチウム検出、ロスアラモス国立研究所から乾式法での中性子バースト検出、イタリアのフラスカティ研究所から乾式法による中性子及びトリチウム検出、オークリッジ国立研究所から過剰発熱検出などに関する結果が報告された。後にオークリッジ国立研究所の研究グループは電解法における中性子、過剰発熱、及びγ線の同時発生を示唆するような実験結果を公表した(文献11)。1990年10月には、ブリガムヤング大学でシンポジウムが開催され、中性子、荷電粒子及びトリチウムの生成に関する多数の報告がなされた(“Anomalous Nuclear Effects in Deuterium/Solid System”, Cot. 22−24, Provo, Utah, 1990.)。 一方、国内での経過を以下に示す。わが国での反応確認実験で反応を肯定する結果を得たとして次のような報告例がある。 ・北海道大学、水野ら:1989年6月、電解法において、2.45 MeVの中性子を検出(文献12)。 ・名古屋大学、和田ら:1989年11月、重水素ガス中パラジウム電極間放電法によって大量の中性子を検出(文献13)。 ・大阪大学、荒田ら:1989年12月、大容積パラジウム陰極を用いた重水電解法によって大量の中性子を検出(文献14)。 ・東京農工大学、小山ら:1990年、電解法における過剰発熱の検出及び“熱バースト”現象の観測(文献15)。 ・大阪大学、高橋ら:パルス状の定電流を印加する電解法における中性子検出(文献16)。 ・日立エネルギー研究所、泉田ら;乾式法における中性子検出(文献17)。 ・NTT基礎研究所、山口ら:重水素外方拡散制御型の試料を用いる乾式法における大量の中性子検出(文献18)。 ・青山学院大学、松本ら:電解法による微量中性子及びトリチウム検出(文献19)。 この間、原子力学会、物理学会、電気化学会等での特別セッッション、日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)主催の討論会、科研費総合研究成果報告会、等の各種会合において、常温核融合反応に関するテーマが積極的に取上げられ、討論がなされてきた。その後も実験、および理論説明の努力が続けられている。 上述の反応の存在を肯定する報告をみる限りでは、“常温核融合反応”はより広範な系で確認されたとの報告はあるが、データの再現性は極めて低く、常温核融合反応に否定的な見解を示す報告も数多い(文献20)。 4.常温核融合の理論的説明 「もし常温核融合反応が事実起こるとすれば」という前提にたって、当初から色々な反応機構に関する理論が提案されている(文献21)。宇宙線ミューオンが高密度の重水素を含む固体中に注入され、これを触媒として反応が起こるという説が初期の頃提案された。現在ではこの説は実験的に否定されたと受け止められている。また原理的に、重水素同士の核融合が起こるためには核の間に働くクーロン斥力に打ち勝って二つの核が衝突する必要がある。この観点に立って、電子の実効質量が増加することによって、あるいは金属格子中に重水素プラズマが存在することによって、クーロン障壁が遮蔽されるために反応確率が増加するという説や、高圧下でクーロン障壁が変形することによるという説などが提案されている。結晶中に生成するクラックの両面に発生する強い電場によって重水素核が加速され付近の重水素核と衝突することによって核融合が起こるというフラクトフュージョン説もある。 5.追試実験とその結果 “常温核融合反応”成功の報道以来、世界各国で広範な視点から精力的な反応確認のための実験が進められてきた。追試実験によって過剰発熱、中性子、及びトリチウム生成を確認したとする結果が報告されている。(文献22)、いずれの場合にもそのデータの再現性は極めて低く、反応条件の系統的な検討などによる理論的な研究には至っていないのが現状である。一方で、反応を肯定する結果と比較すると圧倒的に多数の否定的追試結果が得られている(文献23, 20)。このように当初より新しいエネルギー源の出現として衝撃的に受け止められた“常温核融合反応”は、その後の追試実験を通して、少なくとも現在の状況ではエネルギー源としての可能性はほぼ否定されたと結論してよいであろう。また、微量中性子の発生を伴う低い確率の常温核融合についてはこれを支持する結果も比較的多く、又これを裏付ける理論も幾つか提案されているが、これについてさえ微量中性子計測法における問題点、宇宙線等に起因するバックグランドの正確な評価の問題等(文献24)によって、明確な結論は得られないままである。このように追試などが一段落して、簡易な核融合エネルギー源実現の可能性はほぼなくなる。一方で、新たな核融合反応の可能性を探る研究はその後も続いている(文献25)。 6.最近(2005年)の動向 現在、パラジウムの吸蔵により、複数の重水素が原子核に取り込まれ、核変換が起きているのではないかという実験が話題となっている。これも真偽の程は明確ではないが、常温核融合の研究は、地道な凝縮系固体物理の研究として現在も続いているという状況である。成功のインパクトは計り知れないという核融合の課題だけに、僅かの可能性であっても夢の追求の研究として継続されている。 なお、“常温核融合”に関して多くの著書、解説記事等が刊行されているが、分りやすく全体を述べたものに次のようなものがある。 (1)岸田純之助、“つづく常温核融合への関心”、テクノカレント、No 43,(1990)(2)高橋真理子、“検証に10年かかる?低温核融合のお疲れさま”、 科学朝日、1989年12月号(3)岡本眞實、“常温核融合”日刊工業新聞社(1989) <図/表> 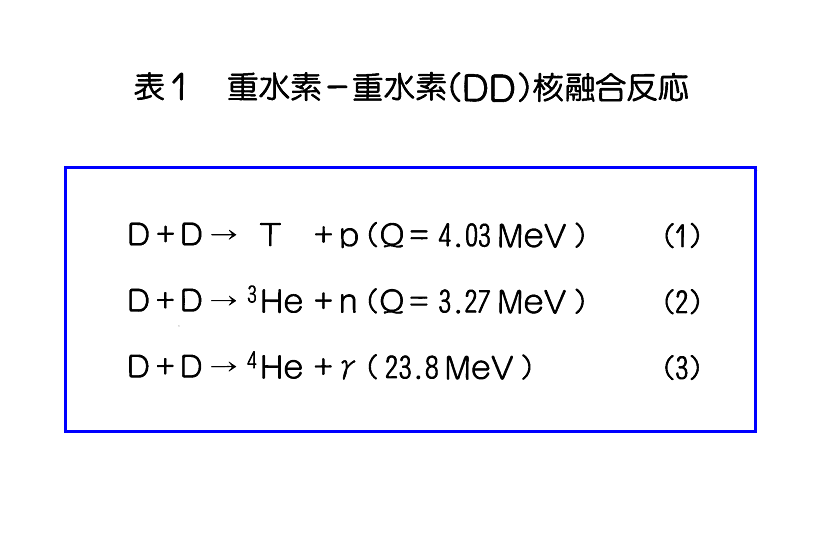
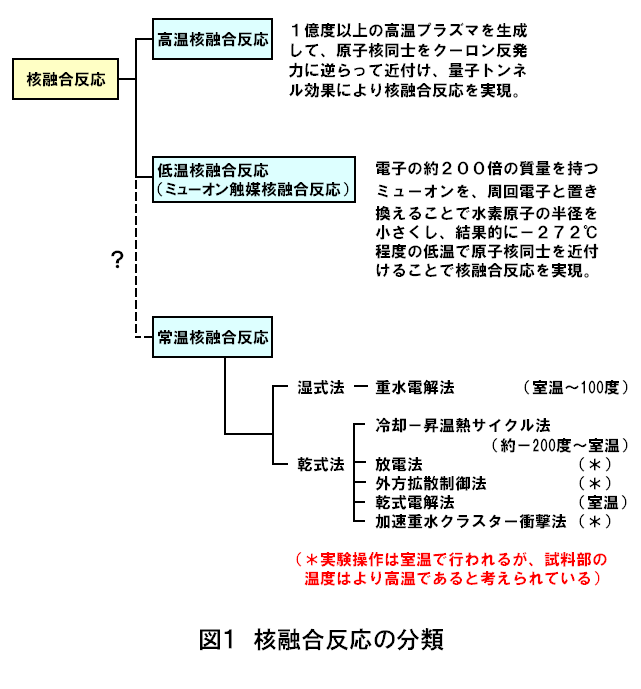
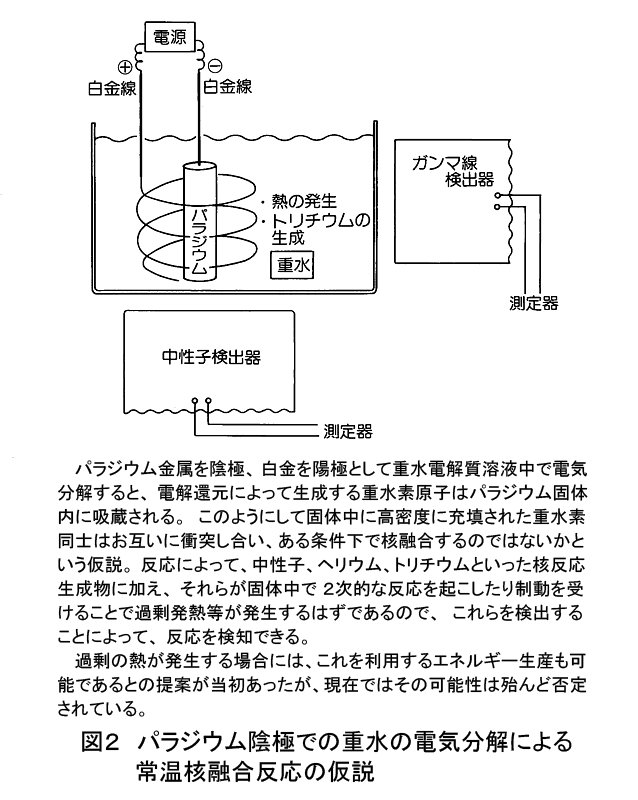
<関連タイトル> 核融合反応の分類 (07-05-06-01) 常温核融合反応追試実験 (07-05-06-03) ミューオン触媒核融合の原理と現状 (07-05-06-04) <参考文献> (1)M. Fleischmann,et. al.,J. Electroanal. Chem.,261,301(1989) (2)S.E.Jones,et. al.,Nature,338,737(1989) (3)A. De Ninno,et. al.,Europhys. Lett.,9,221(1989) (4)H.O.Menlove,et. al.,LA−UR−89−1974(1989) (5)Proc. Workshop on Cold Fusion Phenomena (Santa Fe,May,1989) (6)R.J.Beuhler,et. al.,Phys. Rev. Lett.,63,1292(1989) (7)M. Gai,et. al.,Nature,340,29(1989) (8)T.N.Claytor,et. al.,LA−UR−89−39−46 (9)P. K. Iyengar,et. al.,BARC−1500(1989) (10)The 1st Annual Conference on Cold Fusion,Salt Lake City,March 28−31(1990) (11)C. D. Scott,et. al.,Fusion Technol.,18,103(1990) (12)T. Mizuno,et. al.,電気化学,57,742(1989) (13)N. Wada,et. al.,Jpn. J. Appl. Phys.,28,2017(1989) (14)Y. Arata,et. al.,核融合研究, 62,398(1989) (15)N. Oyama,et. al.,Bull.Chem. Soc. Jpn.,63,2659(1990) (16)A. Takahashi,J. Nucl. Sci. Tech.,26,558(1989) (17)T. Izumida,et. al.,Fusion Technol.,18,641(1990) (18)E.Yamaguchi,et. al.,Jpn. J. Appl. Phys. 29,666(1990) (19)O.Matsumoto,et. al.,電気化学,58,147(1990) (20)日本原子力研究所化学部等共同実験チーム:JAERI−M 89−142(1989);JAERI−M 90−134(1990) (21)立川圓造他:“常温核融合反応のすべて”、原子力工業、Vol.37,10−58(1991) (22)例えば、T. Braun,J. Radioanal. Nucl.Chem., Letters 136,1(1989),137,407(1989),144,161(1990),144,323(1990),145,1 and245(1990) (23)例えば、M. Gai,et. al.,Nature,340,29(1989);N. S. Lewis,et. al.,Nature,340,525(1989) (24)T. Kimura,J. Nucl. Sci. Tech.,27,1147(1990) (25)原研「常温核融合」検討グループ:“常温核融合研究の最近”、原子力工業、Vol.41,5−46(1995)
|

