|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
ミラー型核融合装置は、プラズマをシンプルな磁場で閉じ込める核融合装置の一方式である。この方式は、核融合研究開発の初期から追及されている。ミラー型閉じ込め容器の基本形は、2個の円形コイルを向かい合わせて置き、これらのコイルに同方向の電流を流したときに発生する、ちょうど納豆を入れるわらの「つと」のような磁力線束で作られる。電離した原子(イオン)や電子の荷電粒子で構成されるプラズマは、磁力線に巻き付くように磁力線に沿って移動するが、両端の磁界の強いくびれた部分で大半の粒子が反射され引き返す。これが磁気ミラー閉じ込めの原理である。ミラー型の核融合研究においても、いくつかの難問に直面したが、その都度新しいアイデアを加味して難問を解決し、世界最大のミラー型磁場装置である筑波大学のGAMMA−10に代表されるタンデムミラーへと発展してきた。 ミラー型装置は、単純な装置で高温プラズマを得ることができ、装置の端部から磁力線に沿って超高速のプラズマ粒子を出すこともできるので宇宙ロケットの推進エンジンや、材料開発の中性子源などとして利用することも考えられている。 <更新年月> 2004年07月
<本文>
1.1950年代 磁気ミラー閉じ込め装置によるプラズマ閉じ込めの研究は、1950年代の核融合研究の最も初期の段階から米ソを中心として欧州、日本なども加わり、世界的に活発に進められてきた。初期の段階の装置は、図1に示す単純ミラーと呼ばれる磁力線配位を基本としたものであった。磁気ミラー装置のプラズマ閉じ込め原理は、プラズマを構成する電子、イオン等の荷電粒子が磁力線の周りに巻き付くようにぐるぐると回り磁力線を横切る運動はしにくいことから、横の壁から遊離させることができ、また、端部の磁界を中央部の磁界に比べて強くしておくと大部分の粒子は磁力線が強くなっているところで反射され、中央部方向に戻っていく性質を利用している。粒子が強磁界部で反射されることから磁気ミラーと呼ばれる。 しかし、この単純ミラーには大きな欠点があることが研究が始まってまもなく明かになった。それは2つのコイルの中心を結ぶ中心線に沿って磁界の強度を見ると、2つのコイルの中間のプラズマ閉じ込め領域よりもコイルに近い外部領域の磁界が強いので、かつ、この中心線に垂直な面の上ではプラズマ領域の中心部で磁界が強く周辺に行くほど弱くなるため、プラズマが不安定な状態になり、磁力線を横切って極めて速い速度で側面に逃げ出してしまうことである。当時のミラーの実験は全てこの不安定性による速い損失に悩まされていた。 この問題を解決したのは、旧ソ連のヨッフェ博士の提唱した「極小磁界配位」の方法である。図2の(b)はヨッフェ博士が用いて優れた成果を上げた極小磁界配位のミラー装置の原理図である。 2.1960年代〜1970年代 ヨッフェの研究成果は、1961年にザルツブルグで開催された国際原子力機関(IAEA)の主催する第1回プラズマ物理及び制御核融合に関する国際会議において発表され、それ以後世界の磁気ミラー型装置は一斉に極小磁界の原理を採用することになった。これに伴って磁気ミラーの研究は急速に進歩し、一つの重要なハードルを乗り越えることが出来た。極小磁界配位は、ヨッフェ棒以外にも図2の(c)、(d)に示すように、ベースボール・コイルや陰陽コイルによっても作ることが可能で、米国ローレンス・リバモア国立研究所のベースボール2装置や2X−2装置が作られた。 磁気ミラーの研究は、極小磁界配位の導入によって、急速に磁場を横切る側面へのプラズマ損失を避けることができるようになったが、次の問題は磁力線に沿って端部に逃げ出す粒子をいかに少なくするかである。端部の磁界を中央部に比べて強くするにつれて反射されて閉じ込められる粒子は多くなるが、強くできる磁界には限界がある。この問題の解決策として1976年に米国及び旧ソ連から夫々独立に提案されたのが「タンデムミラー」方式である。 タンデムミラー方式の原理は、磁気ミラー端部に電気的な山や谷(電位の高低)を作り、中央部からきたイオンや電子を電気的に跳ね返してしまう方法である。電位の山や谷を作るために磁気ミラーの両端部に別の小型ミラー部を作ることから、磁気ミラーが連なった形状となり、丁度二人乗りの自転車がタンデム自転車とよばれるのと同様に、このミラー型はタンデムミラーと呼ばれる。タンデムミラー端部の電位は、高速のイオンを注入して局所的にイオン密度の高い部分(電位の山)を作ったり、マイクロ波を入射して局所的に電子をイオンから引き離したりして作られる。 図3にタンデムミラーの磁界コイルの配置、磁界分布、電位分布の例を示す。中央ミラー部(セントラル部)に隣接した極小磁場部はプラズマを安定に落ち着かせることからしばしばアンカー(錨)部とよばれ、この中に磁気的に反射されて閉じ込められるプラズマのイオン(正)と電子(負)の様子が図3の(b)に示されている。また、イオンを電気的に跳ね返す電位の山や電子を跳ね返す電位の谷は、それぞれプラグ部、(熱)バリア部と呼ばれる。 磁気ミラーの研究は、タンデムミラー方式の採用によって格段の進歩を示した。筑波大学のGAMMA−6、米国のローレンス・リバモア国立研究所のTMX、少し遅れて旧ソ連のノヴォシビルスク原子物理学研究所(現在のブドカ原子物理学研究所)のAMBAL等は、いずれもタンデムミラーの有効性を示す優れた成果を挙げた。 3.1980年代以降 タンデムミラー方式での研究は、1980年代に入って、電位形成の検証から高温プラズマ閉じ込めの研究へと進展した。日本のGAMMA−10(筑波大学)、HIEI(京都大学)、米国のTMX−U(ローレンス・リバモア国立研究所)、TARA(マサチュセッツ工科大学)、PHAEDRUS−A(ウィスコンシン大学)等が建設され、さらに大型のタンデムミラーMFTFも米国で建設された。しかし、MFTFは建設が完了した時点で財政上の理由から計画が中途で中止され、高度な技術開発を経て製作した大型の超電導コイルは一度も冷却もされずに不要物となってしまった。これは米国の政策の過度な柔軟性を象徴する事態であり、その後のSSC計画の中止などともあいまって米国の国際的な信頼性に疑問を残した。このように、米国では1980年代の後半にミラー方式での研究は中断された。旧ソ連ではAMBALを改造してタンデムミラーAMBAL−Mにする計画が始まったが、ロシアになった後の国状からAMBAL−Mへの改造が大幅に遅れ、世界のタンデムミラーの研究はGAMMA−10、HIEIを中心とした日本の研究に大きく依存することとなった。 GAMMA−10は、全長27m、中央部の磁界の強さは0.6テスラで、現在運転中の世界最大のタンデムミラーである。電位形成にはマイクロ波を用いた方法を主体として研究を進めており、最大2kVのプラグ電位を得ている。これまでの実験結果によると、磁力線に沿った端部へのプラズマ損失は理論から予測される通りである。高周波(〜10MHz)を用いたイオンの加熱では、電位閉じ込めの効果を合わせて核融合研究の科学目標である1億度を超えるイオン温度を達成している。これに伴い重水素を用いた実験では、核融合反応の結果生成された中性子を観測している。磁気核融合研究における熱核融合反応中性子の観測は、トカマク方式(ドーナッツ型磁場閉じ込め方式で、現在核融合研究の主流)についで2番目である。 また、プラズマの生成維持時間も約0.2秒、電位閉じ込めでの閉じ込め時間(保温特性時間)は10msである。これは、単純ミラーの4〜10倍の閉じ込め特性である。さらに詳細なプラズマ閉じ込めの研究が進行している。特に、プラズマ中の電位によって、プラズマがより安定になりプラズマの揺動による磁力線を横切る損失が押さえられるなど、タンデムミラーの特徴を生かした研究が進行している。 4.核融合炉への展望 通常の核融合炉では、水素の仲間(同位元素)で普通の水素よりも2倍、3倍重い重水素と三重水素を用いることを想定している。この場合、核融合反応生成物として中性子が生じ、炉の構成物質中に放射性物質が誘導される。中性子が発生しない核融合反応として、ヘリウムの仲間でやや軽いヘリウム3と重水素を用いる反応があるが、この場合反応が起こる温度が重水素・三重水素反応に比べて数倍高い。したがって、より高圧のプラズマを閉じ込める必要がある。ミラー方式では、ドーナッツ型磁場閉じ込め方式(トカマク方式等)に比べて高圧のプラズマを閉じ込められる可能性が理論的に予測されている。このためタンデムミラーは、将来のヘリウム3を用いた核融合炉の有力候補となる可能性もある。 ミラー型装置は、ヘリカル型やトカマク型にくらべて単純な装置で高温プラズマを得ることができる。装置の端部から磁力線に沿って超高速のプラズマ粒子を出すこともできることから宇宙ロケットの推進エンジンとしての利用や、核融合炉の面からは閉じ込めが不十分でも強力な粒子ビームや高周波を入射して核融合反応を継続して、14MeV(DT反応)あるいは2.4MeV(DD反応)の中性子源として材料開発に利用すること、なども考えられている。 <図/表> 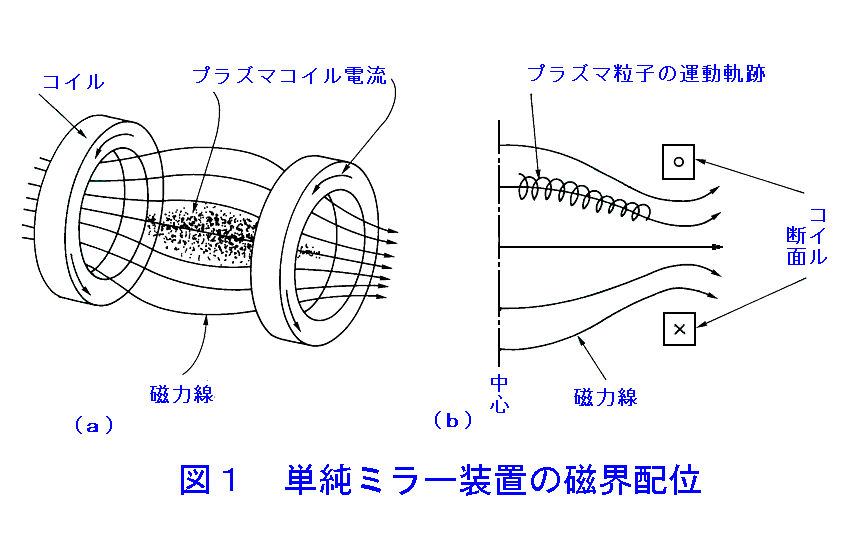
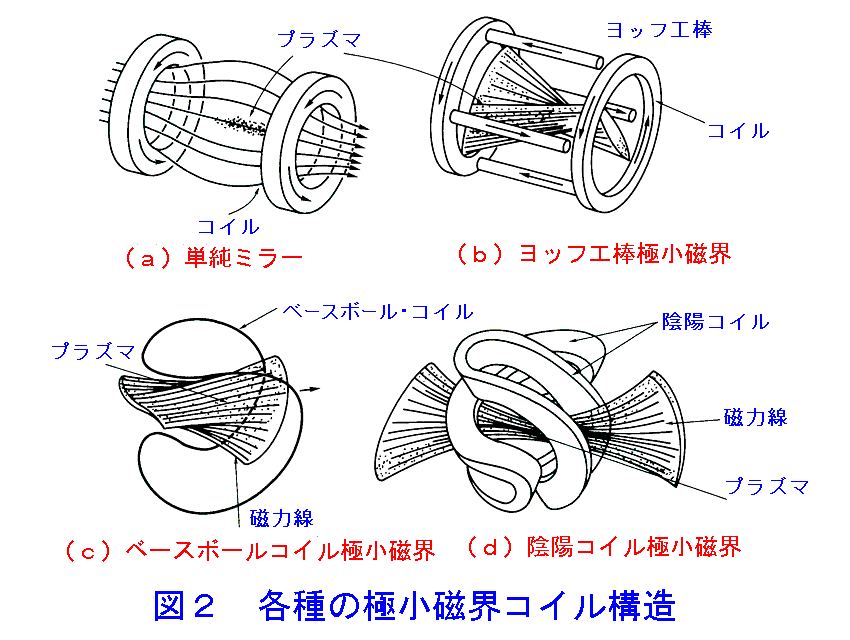
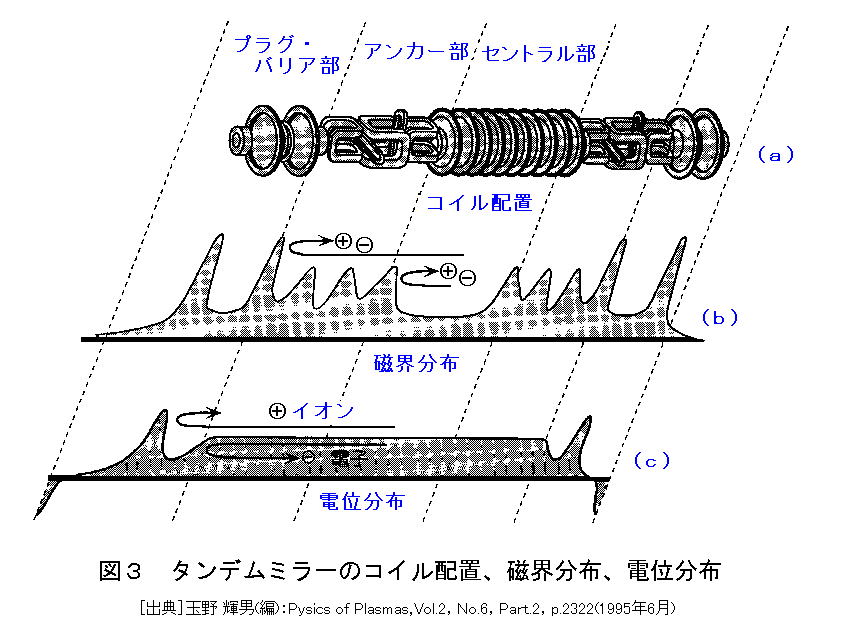
<関連タイトル> 核融合反応と熱エネルギー (07-05-01-01) 核融合炉の概念 (07-05-01-02) 核融合研究開発の経過 (07-05-01-03) 核融合反応装置の形式と作動原理 (07-05-01-05) トカマク型核融合装置の研究開発 (07-05-01-06) ヘリカル型核融合装置の研究開発 (07-05-01-08) 慣性核融合装置の研究開発 (07-05-01-10) <参考文献> (1)日本原子力文化振興財団(編):「原子力の基礎講座」第8分冊「核融合」、(1996年3月) (2)核融合の総合的体系化の推進研究代表者・飯吉淳夫(核融合科学研究所):核融合研究の課題と展望(平成3−5年度) (3)玉野輝男(編):Pysics of Plasmas, Vol.2, No.6, Part.2, p.2322(1995年6月) (4)筑波大学:プラズマ研究センター、http://www.prc.tsukuba.ac.jp/
|

