|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
放射性物質を環境に放出する際の管理基準は、これまで環境中の生物濃縮等により、飲料水、食品等を経由した一般公衆の被ばく線量を、合理的に達成できる限り低く制限することを目的としてきた。ヒト以外の生物種個体群、複数の生物種で構成される生態系の保全、持続可能性の維持については、ヒトが他の生物種と比較して放射線感受性が高いことを根拠として、「ヒトが防護できていれば、環境における生物も防護されている」という考え方によって説明されてきた。環境保全への国際的な関心の高まりにより、環境中に放出される有害物質については、環境の持続可能性、生物の多様性が維持、保全されることを明確な証拠、根拠に基づいて透明性をもって説明することが要求されるようになってきた。このような国際的な流れを受けて、放射線の影響から環境、ヒト以外の生物を防護するための枠組みについての検討が国際原子力機関、国際放射線防護委員会、国際放射生態学連合、経済協力開発機構原子力機関等の国際機関によって行われるようになり、(1)放射線の環境およびヒト以外の生物への影響の評価とその防護のための枠組みを国際的な合意として構築していくこと、(2)ヒトの健康と環境、ヒト以外の生物への影響を統一的に防護する国際的な安全基準(BSSなど)を策定するために検討を進める行動計画を策定すること、等が国際的に確認されている。 <更新年月> 2004年09月
<本文>
従来、放射線、放射性物質の利用において、放射線の影響を合理的に低く制限するための基本的な考え方は、国際放射線防護委員会(International Commission on Radiological Protection、以下ICRP)が勧告する放射線防護体系に示されてきた。ここでいう放射線の影響とは、被ばくした「ヒト」における急性放射線障害(確定的影響)と、長期の潜伏期を経て、がんや遺伝的疾患等の発生率が被ばく線量に応じて増加するとされる晩発性放射線障害(確率的影響)のことであり、共にヒトの健康に関心が払われている。特定の施設から、放射性物質を環境中に放出する際の環境管理基準においても、放射性物質の環境挙動のうち、食物連鎖等を通じて、ヒトの摂取する水や食品としての生物の可食部位への放射性物質の移行について、調査研究データが整備されてきたが、環境におけるヒト以外の生物への被ばくの影響については、これまで関心が払われてこなかった。 これは、ICRP1977年勧告(文献1)、1990年勧告(文献2)において、「ヒトが適切に防護されていれば、ヒト以外の生物種も十分に防護され」、生物のなかでもヒトの放射線感受性は高いことから、「ヒトを防護するのに必要な環境管理基準が満たされている限り、ヒト以外の生物種の個体に障害が生じるかもしれないが、その種の存続をおびやかしたり、種間に不均衡をもたらしたりすることはないと信ずる」という記載に基づいており、放射線の影響からの環境の防護と管理原則の核心をなす考え方となっている。 近年、ICRPは、2003年第91報告書「ヒト以外の生物種への放射線の影響評価の枠組み」(文献3)を刊行した。この報告書では、「ヒトが適切に防護されていれば、ヒト以外の生物種も十分に防護される」という従来の考え方を変更しなければならないような証拠は存在しない、としながらも、環境が十分に防護されていることを、十分な証拠に基づいて透明性の高い実証的なプロセスによって明らかに示すことが不可欠としており、そのための枠組みが論じられている。この放射線防護における環境への関心の高まりは、2005年に予定されている新しいICRP基本勧告においても、中心的な課題の一つとして取り上げられようとしており、またICRPでは、放射線環境防護に関する検討を推し進めるため、2005年中に新たに第5委員会が発足することになっている。 2003年国際原子力機関(IAEA)主催「電離放射線の影響からの環境の防護」に関する国際会議(ストックホルム会議)では、ICRP、IAEA、国際放射生態学研究連合(IUR)、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)の国際機関が連携して、放射線の環境およびヒト以外の生物への影響の評価とその防護のための枠組みを国際的な合意として構築していくこと、ヒトの健康と環境、ヒト以外の生物への影響を統一的に防護する国際的な安全基準(BSSなど)を策定するために検討を進める行動計画を策定することが確認されている。 1.放射線環境防護の背景 21世紀は、「環境」の世紀と言われる。1965年に米国の経済学者K.E.Bouldingが示した「宇宙船地球号(Earth as a space ship)」という概念は、「地球環境」という認識を与え、1972年にストックホルムで開催された国連人間環境会議では、「人間環境宣言(ストックホルム宣言)」と「国際環境行動計画」が採択され、これらを実現するため、国連環境計画(UNEP)が設置された。1992年にリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議」において、持続可能な開発を実現するためのリオ宣言と、そのための行動計画であるアジェンダ21や、生物多様性の維持に関する協定等が結ばれた。アジェンダ21では、放射性物質の環境管理に関してIAEAを実施機関と指名しており、IAEAは、これに応えて専門家会合を開催し、環境倫理についての技術報告書の取りまとめなど検討を進めてきた。 一方で、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)は、「環境への放射線影響」についての1996年UNSCEAR報告書をとりまとめ(文献4)、チェルノブイリ事故周辺地域や南ウラル地域(マヤック核施設事故周辺地域)の放射能汚染による環境、ヒト以外の生物、生息地への影響についての学術データを集成している。また、その結果を基にして、陸生の動植物、水生の動植物について、いくつかの影響評価項目(エンドポイント)において、影響が見いだされない放射線量率(無影響線量率)を推定評価している(表1)。 北東大西洋の環境保護として、周辺諸国が海洋への人工放射性核種の放出をゼロに近付けるというオスパー(OSPER)協定等の関係国間の環境防護の枠組みに関する議論も、各国の思惑を反映しつつ、環境への関心の高まりを受けて活発である(http://www.osper.org)。 2.ヒト以外の生物への放射線影響評価の現況 UNSCEAR1996年報告書(文献4)は、それまでの放射線のヒト以外の生物への影響に関する包括的なレビューである。生物種毎、系統毎に異なるとするSparrowら(文献6)の研究成果が引用されており(図1)、ヒトを含めた哺乳類は、他の生物と比較して相対的に放射線感受性が高いとされている。急性致死効果を影響評価点(エンドポイント)とした研究では、マウスやサルはヒトより感受性が低いが、ヒト<ヤギ<犬<豚<羊の順に、放射線感受性が高いことが報告されている(文献6、7)。わが国においても、ヒト以外の生物への放射線の影響についての精力的な研究が、江上らを中心に行われ(文献8)、その成果は、UNSCEAR1996年報告書に多く引用されている。Sparrowらの研究成果(文献6)は、79種の生物についての急性致死効果(半数致死線量)を比較しており、これらの生物種において、ヒトより放射線感受性が高い生物は見いだされていないということであって、「野生生物種において、ヒトより放射線感受性が高い生物は存在しない」ことを意味するわけではない。 欧州共同体共同研究プロジェクトとして、欧州の主だった放射線防護・影響に関する研究所、大学等が行った放射線のヒト以外の生物への影響に関するデータベース構築プロジェクト、FASSET(Framework for Assessment of Environment Impact)がある。FASSETは、論文や報告書としてまとめられているヒト以外の生物に関する放射線影響と線量評価に関するデータを、生物種毎に取りまとめ、検索可能なデータベースとしたものである。 影響の評価点としては、morbidity(健全性への影響)、acute mortality(急性致死)、observable DNA damage(検出可能なDNA損傷)、reduced reproductive success(繁殖価の低下)について調査されている。環境生物個体への放射線影響として確定的影響のみを考える場合、FASSETによるサーベイの結果から、軽微な影響のしきい値は100μGy/hr(2.4mGy/day)、明確な影響が観察される被ばくレベルは1000μGy/hr(24mGy/day)以上であるとされている。放射線の種類による生物学的な効果比(RBE)、慢性被ばくによる影響については、データが不足している。 FASSETは、基本的な枠組みについてよく練れたデータベースであるが、整備された一覧表(look−up table)には、学術調査研究データがほとんど記載されていない生物種、核種が多い。レファレンス動物、レファレンス植物等の選定によって、対象とする生物種の分類を科(family)について選定して、対象を絞り込むことにより、まず代表的な生物種について調査実験データを整備する考え方が提案されている(文献9)。レファレンス生物の考え方は、その選定の妥当性、適用範囲についても議論の多いところであるが、環境における生物とその相互作用についての影響をすべて把握することは実際には困難であり、実現可能性の高い方法論として注目されており、ICRPにおける検討も行われている(文献3)。 3.ヒト以外の生物の環境線量評価 放射性物質の環境と生態系における食物連鎖等による移行については、放射生態学において研究されてきた(http://www.iur-uir.org)が、ヒトの被ばく線量評価のために食材の可食部と飲用水への放射性物質の移行と濃縮の経路を探索してきたものであり、実際の環境において、特に高い放射線被ばくを受ける生物の有無を調べるための移行経路の探索は、ほとんど行われておらず、ヒト以外の生物が受ける放射線量を評価するためには新たな環境調査が必要である。 米国エネルギー省は、ハンフォード地域での施設周辺の環境防護対策の妥当性を示すための影響評価のために、環境中の放射性核種濃度(水中、地表媒質中の放射能濃度)から、あらかじめ選定したモデル生物への一日あたりの吸収線量(mGy/day)を評価するシステムとして、環境生物被ばく線量評価プログラム(ResRad-Biota,Rad-BCG)を開発している。 このプログラムで採用されている線量評価上の仮定とモデルについての仕様と、一連の計算システムは、インターネットからダウンロードできる。このモデルにより、実環境のサンプリング調査を行って採取した、環境中の水や空気、土壌試料の放射能濃度から、モデル生物が受ける吸収線量率を推定し、詳細な調査を必要とする地域であるかどうかをふるいにかける「スクリーニング」に限って、用いるべきであるとしている。 <図/表> 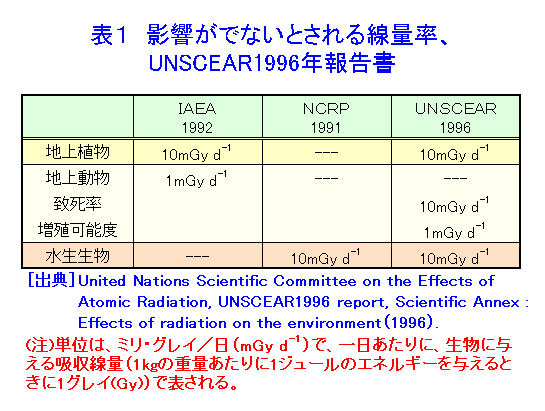
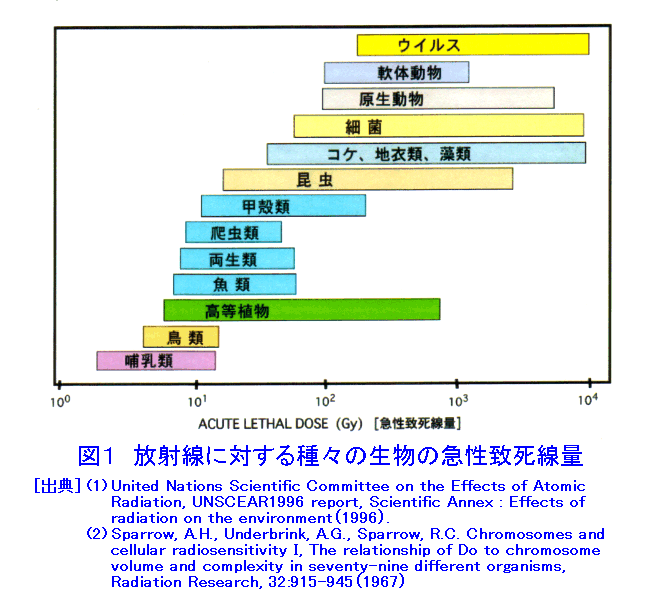
<関連タイトル> 比較環境影響研究 (06-03-05-06) 国際放射線防護委員会(ICRP) (13-01-03-12) <参考文献> (1)International Commission on Radiological Protection, ICRP 1977 recommendation (Publication 27), paragraph 14(1977) (2)International Commission on Radiological Protection, ICRP 1990 recommendation (Publication 60), paragraph 16(1990) (3)International Commission on Radiological Protection, A Framework for Assessing the Impact of Ionising Radiation on Non−human Species(Publication 91)(2003) (4)United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR1996 report, Scientific Annex : Effects of radiation on the environment(1996). (5)OECD/NEA, Radiation Protection of the Environment : The Path Forwarded to a New Policy ?, Workshop Proceedings Taormina, Sicily, Italy(2002). (6)Sparrow, A.H., Underbrink, A.G., Sparrow, R.C. Chromosomes and cellular radiosensitivity I, The relationship of Do to chromosome volume and complexity in seventy−nine different organisms, Radiation Research, 32:915−945(1967) (7)Thames, H.D., Hendry, J.H. Fractionation in Radiotherapy, p297, Taylor and Francis, London(1987) (8)江上 信雄(著):放射線生物学、岩波書店(1985) (9)Pentreath, R.J., Woodhead, D.S., A System for protecting the environment from ionizing radiation : selecting reference fauna and flora, and possible dose models and environmental geometries that could be applied to them, Sci. Total Environment, 277, 33−43(2001)
|

