|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
減速材として重水を用い、冷却材として炭酸ガスを用いる圧力管型炉は、ガス冷却重水炉(HWGCR又はGCHWR)と呼ばれる。その特徴は重水減速による中性子経済の良さを保持しつつ、ガス冷却による高温と、従って熱効率の良さを実現しようとしたものである。しかし中性子経済の良さを生かし切るために当初計画されたベリリウム系の燃料被覆管の開発に成功しなかったことが主原因となって重水炉の主流たり得ず、今日迄に世界で発電炉は4基のみが作られ、かつそのすべてが既に運転を終了してしまっている。ここでは、それらについて略述し、日本においてもかつて若干の検討がなされたことを付記する。 <更新年月> 1998年03月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.重水炉における冷却材の選択 重水炉(Heavy Water Reactor:略称HWR)は、重水を減速材として使用する原子炉、特に動力炉の場合を指して云う用語である。類似の語として軽水炉(Light Water Reactor:略称LWR)があり、LWRの場合は、軽水が減速材兼冷却材として用いられている炉を指して云うが、HWRの場合は、減速材が重水であれば、冷却材は重水でなくても重水炉と呼ばれる。 すなわち、HWRの場合でも、LWRと同様、圧力容器型を採用すれば、冷却材は事実上、減速材兼用の重水に限られてしまうわけであるが、HWRの場合は、圧力容器型もあるが、多くの場合、圧力管型が採用される。この場合は圧力管の中は燃料バンドルと冷却材だけになり、減速材である重水は圧力管の外(殆どの場合、圧力管の外に空気又は熱伝導性の低いガスの層を介してもう一つカランドリヤ管という構造物があり、重水はその外)に分離される。従って、圧力管の中を通過する冷却材は重水に限る必要はなく、相当自由に選べることになる。 この圧力管型重水炉における冷却材の候補には、重水、軽水、有機材、ガスなどが挙げられる。ここでガスが採用された場合、重水炉の中でも特にガス冷却重水炉(Heavy Water Gas−Cooled Reactor:略称HWGCR、或は逆順にしてGCHWR)と呼ばれる。ガスとしては殆どの場合、炭酸ガス(二酸化炭素:CO2)が用いられる。 2.ガス冷却重水炉の特徴 ガス冷却重水炉HWGCRの特徴は、重水減速炉としての中性子経済の良さ(中性子の無駄な吸収が少なくて、燃料の転換比が高く、その有効利用が図れること)を保持しつつ、冷却材ガスの温度を高くして、熱効率の向上が図れることである。これに対して、中性子経済が最も良いと云われる加圧重水冷却重水炉(一般略称PHWR、CANDU 型と呼ばれるカナダ型重水炉はその中の主力的なもの)の場合は、冷却材の温度が運転圧力に対応する沸点以下に制限されるので、あまり高くとれず、蒸気発生器を介して得られるタービン駆動用の(軽水)蒸気も飽和蒸気に限られてしまう。一方、HWGCRの場合のガスの温度は、炉心(特に燃料被覆管)の特性と圧力管及び蒸気発生器の材料によって制限を受けるものの、多くの場合、タービンは過熱蒸気によって駆動できる。 HWGCRの次の特徴は、重水は減速材として用いられるだけなので、多くの場合、低圧・低温のまま使用でき、従って重水が漏洩する可能性が少ないことである。これは重水が高価であることと、中性子の照射を受けて、その中に三重水素トリチウム(ベータ放射線源である)を含むようになることを考えると、運転管理上、PHWRに比して有利である。 HWGCRのその他の特徴は、冷却材ガスに温度や圧力の変化に伴う相変化がないので運転上の安定性が良いこと、万一の事故時における冷却にも不連続性が少なく、又、燃料と冷却材の間の化学的相互作用の発生が考えられないこと、重水炉の一つの特徴である出力運転中の燃料交換のための機器の設計が楽になること、冷却材系に腐食生成物が少なく、放射線レベルが低くてすむことなどである。 3.ガス冷却重水炉における燃料被覆管の問題 上記のHWGCRの特徴の第一である中性子経済の良さと熱効率の向上とを、最大限に発揮しようとすれば、中性子吸収が少なくて高温に耐える燃料被覆管が存在することが重要になる。1950年代後半から1960年代前半にかけて、こうした燃料被覆管材の探求が仏・英・米を中心にかなり盛んに行われ、炭酸ガスとの両立性ということも考慮すると、ベリリウム(Be)又はその系統の合金に可能性があるとみられていた。 しかしながら、Be又はその合金は、薄肉の管に成形することが困難であり、更に、放射線損傷に耐えて、長時間にわたり高温の燃料を被覆しきる(核分裂生成物等を漏洩させない)ことに対する信頼性が得られにくかった。そのような信頼性のあるBe系の被覆管を開発するには長期間が必要であり、そうしたとしても、なおかつ成功の見通しがはっきりしないということで、後述する英及び仏で採用が見送られたことが、事実上HWGCRの長期的運命を決めた。すなわち、英国は圧力管型重水炉を作ったものの、沸騰軽水冷却型(蒸気発生重水炉:SGHWR)ということになり、仏国はHWGCRであるEL−4炉を作ったが、ステンレス鋼被覆管でスタートせざるを得なかった。このことだけが原因とはいえないが、早期に良い燃料被覆材を開発しきれなかったことが、HWGCRの魅力を半減させ、それを成功に至らしめなかった大きな要因となったとはいえる。 4.英国における動き 英国は、蒸気発生重水炉(SGHWR)と呼ばれる圧力管型重水炉の原型炉(10万kWe)の建設をウインフリスにおいて1963年に始め、1968年〜1990年の間運転した。この炉自身の運転性能は必ずしも悪くはなく、一時は英国の国策に沿った炉として採用されかかったが、経済性その他の要因で、その炉型式は結局は主流になり得なかった。しかしこのSGHWRの炉型式決定に先立ってガス冷却重水炉の採用が相当本気で検討されたこと(文献2)は、記録にとどめられてよい。すなわち、このガス冷却重水炉のために設計された圧力管の寸法・材料は結果としてSGHWRに使われたものと非常に近く、SGHWR自体の設計を容易にしたと云われる。また、ジルコニウム製の圧力管を線膨張係数の異なる炉心外冷却系の配管に接続するのにロールド・ジョイント法と呼ばれる方法を採用することも、このガス冷却重水炉の検討過程で決められたことである。 さらに、圧力管を縦置きにし、その長さ、従って炉心の有効高さを一定に保ったまま、圧力管の数(炉心の相当直径)を増やすことによって、大出力の炉を形成できるという、いわばモジュラー型炉の考えは、この英国でのガス冷却重水炉の設計で得られたものと云われる。 しかしながら、この英国のガス冷却重水炉の検討は、先に述べたBe系燃料被覆管に早期の見通しが立たなかったことに加えて、約660℃,約40気圧と予定された炭酸ガス冷却材から伝熱して蒸気を発生させる大型の蒸気発生器のコストが高くなりすぎるとの理由で1958年に中止された。しかし、この設計は、圧力管以外の系統においてもSGHWRに相当生かされたと云われる(文献2)。 5.仏国のEL−4炉 仏国は後年は加圧水型炉PWRに傾斜して行ったが、その動力炉開発の初期においては英国のマグノックス炉に似た、黒鉛減速の炭酸ガス冷却炉を相当数建設した。その流れで同国は炭酸ガス冷却重水炉に関心を持ち、EL−4という名の7万kWe原型炉(冷却材の炉出口の温度500℃)をブレンニリスに建設し、1966年に臨界を達成した。 この炉は、最初Beが燃料被覆材として計画されたが、結局採用されず、初装荷燃料にはステンレス鋼が用いられた(後にジルコニウム・銅合金が用いられたとも云われる(文献2))。なお、燃料は微濃縮の酸化ウランである(文献1)。 EL−4は1967年に発電を開始したが、翌年16基ある蒸気発生器のうちの 5基の伝熱管溶接部に割れを生じて運転を停止した。その後、新しい蒸気発生器に取換えてから1971年〜1975年の間順調に運転されたが、1975年、ブルターニュ独立派が仕掛けたといわれる2度の爆発事件が起き、損害を受けたEL−4炉発電所は、その頃に定着して来た仏の国策としてのPWRへの傾斜のためもあって、遂に再建されることなく、1985年にはプロジェクトが終了する結果となった(文献2)。しかしEL−4は、現実に運転されたガス冷却重水炉として貴重な記録を残したと云える。特徴は水平圧力管型で、その両端が、出力運転中の燃料交換を容易にする配置になっていた(文献1)。 6.その他のガス冷却重水炉 ガス冷却重水炉として実際に運転された炉は少なく、文献1によれば、EL−4を含めて4基にすぎない。すなわち、チェコスロバキア(現スロバキア)の11万kWe炉・ボフニツェA−1(Bohunice A−1)、西ドイツ(現ドイツ)の10万kWe炉・KKN(Kernkraftwerk Niederaichbach)、スイスの8千kWe炉・リュサン(Lucens)である。これらの炉の分る範囲の仕様を、文献3より 表1 に示す(出力等、文献1とやや相違があるが、文献3の方が新しい)。 スロバキアのボフニツェ発電所は垂直の圧力管が更に鋼製の圧力容器に収められた型式のもので、それから出入りするガス用の配管によって3基の蒸気発生器に連結されていたと伝えられる(文献1)。この炉は1965年に運転を開始し、1977年迄運転された。 ドイツのKKN炉は、1970年に建設されたステンレス鋼被覆の微濃縮酸化ウラン燃料ピンクラスターを用いたもので、垂直圧力管の頂部から出力運転中に燃料交換がなされたと伝えられる(文献1)。 スイスのリュサン炉は、実験用発電炉という程度のもので、国家計画として開発することを目指して人工洞窟中に1962年に建設されたが、1969年に閉鎖された。燃料は微濃縮金属ウランのピンにマグネシウム・ジルコニウム合金の被覆管をつけたもので、黒鉛の支持材で支持し、重水中に置かれた垂直圧力管中に置かれ、冷却ガスの流れは炉頂から入れ、再び炉頂に集めるという設計であったと伝えられる(文献1)。 7.日本における検討 わが国では圧力管型重水炉の原型炉(ふげん)が1979年以来運転されているが、これが新型転換炉(Advanced Thermal Reactor:略称ATR)計画として、ナショナルプロジェクト化する以前(動力炉・核燃料開発事業団(現日本原子力研究開発機構)発足前)には、国産動力炉計画として日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)において検討がなされていた。1963年から1965年当時、国産動力炉が重水炉ということのみ早く決まり、冷却材についての比較研究・調査がなされていた頃、炭酸ガス冷却は、結局採用された沸騰軽水冷却と並んで最後迄有力な候補の一つに挙げられていたことがある(文献4)。その他検討されたが、早目に落ちた冷却材の候補には、加圧重水、加圧軽水、軽水フォッグ、有機材等があった。炭酸ガス冷却型が結局は沸騰軽水冷却型に勝てなかった理由は、Be系の燃料被覆管に見通しが得られなかったことが第一、次いで沸騰軽水冷却なら軽水炉技術の活用が期待できるということであった。 8.廃炉措置の実施対象 近年発行された資料(文献5)の中に「各国の原子炉廃止措置の実施例」という記事があり、その中の表に上記したHWGCRの4基中の3基の名を見ることが出来る。その表からの抜粋を 表2 に示した。これによりガス冷却重水炉は動力炉の主流になり得なかったが、廃炉措置技術の習得・向上という点で、年を経て再び原子力界に寄与していることが知られる。 <図/表> 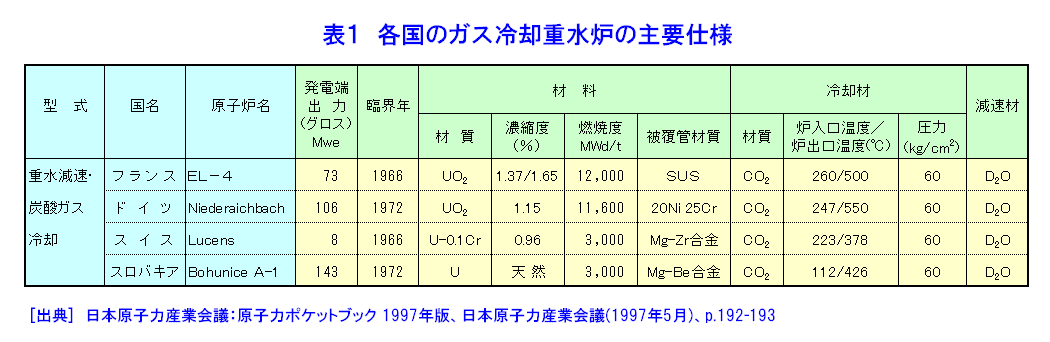
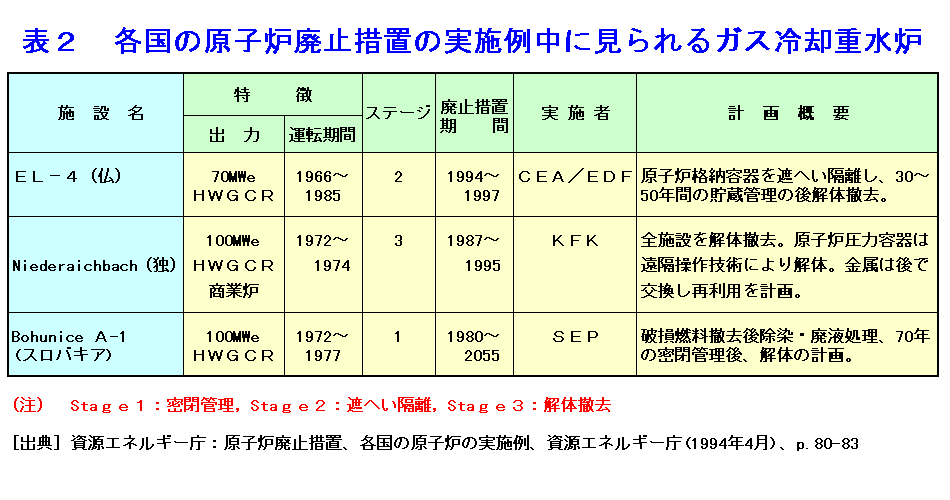
<関連タイトル> 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉 (03-02-02-01) 海外の重水減速沸騰軽水冷却圧力管型原子炉 (03-02-05-01) <参考文献> (1)W.マーシャル(編)、住田 健二(監訳):原子炉技術の発展[上]、筑摩書房(1986年9月)、p.178−182 (2)W.マーシャル(編)、住田 健二(監訳):原子炉技術の発展[下]、筑摩書房(1986年10月)、p.443−457 (3)日本原子力産業会議:原子力ポケットブック1997年版、日本原子力産業会議(1997年5月)、p.192−194 、p.484−499 (4)安川 茂:国産動力炉開発の経緯、原子村第17号、p.19−31 、原子村編集人 下桶 敬則(1996年1月) (5)資源エネルギー庁:原子力発電関係資料 各国の原子炉廃止措置の実施例、資源エネルギー庁(1997年4月)、p.81−83
|

