|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
日本放射化学会 (The Japan Society of Nuclear and Radiochemical Sciences)は、核化学・放射化学に関連する関連分野の研究者相互の連絡を図り、基礎および応用研究の発展と教育に寄与する目的で、1999年(平成11年)に発足した。学会は、会長、理事、監事、総会および事務局で構成される。学会の目的の遂行のため、企画委員会、広報委員会、刊行物編集委員会、インターネット管理運営委員会などを置き、会員相互の調査・研究の連絡、総会、討論会、分科会、研究発表会、講演会などを開催し、会誌・研究報告および資料を刊行する。また、国内外の関連分野の学会や協会と協力し国際会議、シンポジウムなどを共催する。2009年現在の会員は約350人となっている。 <更新年月> 2009年12月
<本文>
1.設立の経緯と目的 日本放射化学会(The Japan Society of Nuclear and Radiochemical Sciences)は、1957年(昭和32年)以来42回にわたって続けられてきた放射性化学討論会の実績を基に、1999年(平成11年)に発足した。 学会の目的は、放射化学が学際研究分野であるとの認識の下に、関連する基礎および応用研究分野を広く包含する研究交流組織として、相互に啓発を図り、研究の活性化と若手研究者の育成を図ることにある。また、核化学、放射化学および関連分野の研究の重要性に対する社会的認識の向上を図るため、放射能や放射線に関する教育の普及を積極的に支援するとともに、世界との交流を深め、当該分野の指導的役割を果たすことを目指している。 日本の核化学や放射化学(以下、放射化学と総称)は、1920年代に理化学研究所を中心に基礎が築かれ、戦後は原爆投下によるフォールアウトの研究、1954年の第5福竜丸の「ビキニの灰」の分析と解析などその業績は大きい。 1957年(昭和32年)に、日本化学会と同関東支部の共催により、第一回放射化学討論会(以下、討論会)が開催された。それ以降、討論会では (1)天然放射能、(2)放射性同位体の製造、(3)放射能測定、(4)放射化分析および放射化学分析、(5)ホットアトム化学、(6)核燃料再処理および廃棄物処理に関する放射化学的問題、(7)フォールアウトおよび放射能で汚染された物質中の放射性核種の分離定量に関する問題などをテーマに開催された。討論会は研究者の自主組織「放射化学研究連絡委員会」により運営された。 1996年に開催された第40回討論会で「放射化学の学会」を設立する機運が芽生え、1998年に「放射化学研究連絡委員会」の中に「学会準備小委員会」が設置された。その後の検討を経て、1999年(平成11年)に「日本放射化学会」が発足した。 2.組織と運営 日本放射化学会は、会長、副会長、監事、顧問、理事会、事務局、総会で構成される。学会の事業の推進を図るため、図1に示すように、学会には企画委員会、広報委員会、ジャーナル編集委員会、放射化学ニュース編集委員会、インターネット管理運営委員会が設置されている。 学会の最高議決機関は総会である。総会は、年1回開催される。総会においては、前年度の事業報告、収支決算の承認、新年度の事業計画、役員の選任、並びに会則の変更などが検討され決定される。 理事会は、会則に基づき、総会において会員のうちから選出された下記の役員によって構成され、任期は2年で、毎年その半数を改選している。 (a)会長 1名、副会長 若干名、理事 20名以内 (b)監事 2名、顧問 若干名 理事会は学会の業務遂行に関する重要事項を決定し、学会はその事業を円滑に行うため、企画委員会、広報委員会、編集委員会、インターネット管理運営委員会、学会賞委員会などを設けている。また、各専門分野別に分科会ならびに研究会を設置している。学会の事務は事務局が処理する。2009年現在の正会員は約350人、賛助会員は約30社となっている。 3.主な活動 日本放射化学会は、前記の目的を達成するために、次の事業を行う。 (a)討論会の開催 (b)分科会、研究会、講演会などの開催 (c)放射化学ニュース、会誌(英文)、研究報告および資料の刊行 (d)会員相互の調査、研究発表などの連絡 (e)その他学会の目的を達成するために必要な事業 3.1 討論会 討論会は、「日本放射化学年会・放射化学討論会」の名称で、放射化学討論会の開催回数を受け継いで秋に開催される。開催日時、場所は学会誌、ホームページなどに公開される。 討論会のテーマは(1)放射化分析(同位体分析、加速器を用いた分析含む)、(2)核化学、(3)アクチノイド化学、(4)環境放射能(自然環境、放射線施設、環境放射能)、(5)同位体化学(標識、RI製造、基礎反応、トレーサ利用など)、(6)原子核プローブの化学(メスバゥアー分光、陽電子・ミュオン・パイオンなどの素粒子化学、ホットアトム、核相関など)、(7)核エネルギー・バックエンド化学、(8)医学・薬学・生物学におけるRI利用、(9)放射能測定および放射線利用、(10)関連分野(放射線化学、放射線教育)など多岐にわたる。発表内容は放射化学討論会要旨集で予告される。 また、日本放射化学会は、特定の課題について講演会やシンポジウムを開催するほか、他の学協会と同様の活動を共催、協賛、あるいは後援する。 3.2 分科会など 研究開発の進捗を図るため分科会を設けている。分科会の名称は課題の重点を示すため変更されることがある。2009年には、「原子核プローブ分科会」、「アルファ放射体・環境放射能分科会」、「放射化分析分科会」、「核化学分科会」、および交流の促進を図る「若手の会」がある。また、重要な課題、新しい課題などに関する不定期の講演会、勉強会「夏の学校」、アイソトープ・放射線研究発表会などは、会誌やホームページに掲載される。 3.3 国内・国際協力 国際協力にも積極的に取り組み、国内外の関連の組織団体、学会(日本化学会、日本原子力学会、日本分析学会、日本薬学会)などと随時国際会議やシンポジウムの開催に協力している。 3.4 刊行物 年2回の「放射化学ニュース」を発行、年1〜2回の英文学術論文誌「Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences(日本放射化学会誌)」を発行している。 3.5 顕彰事業(学会賞) 年度ごとに放射化学およびその関連分野で優れた業績・貢献のあった者に、日本放射化学会賞、日本放射化学会賞奨励賞、木村賞を授与している。受賞内容は、「放射化学ニュース」(和文)、「日本放射化学会誌」(英文)に掲載される。 <図/表> 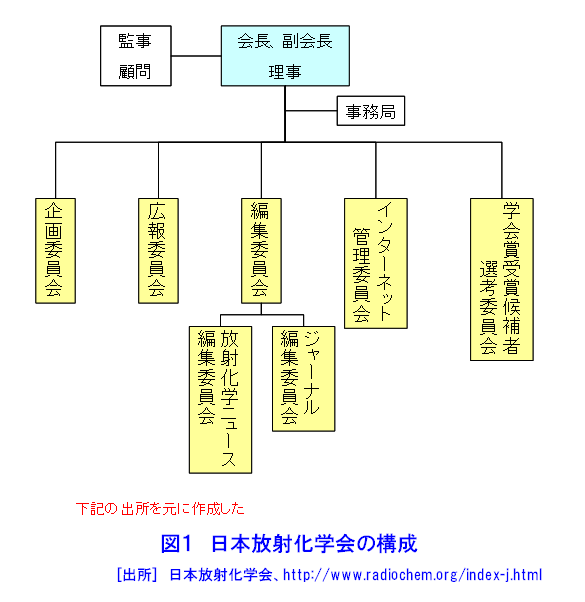
<関連タイトル> 日本原子力学会 (13-02-02-04) 日本保健物理学会 (13-02-02-07) 放射線利用の概要 (08-01-04-01) 生物学における放射線利用 (08-01-04-04) 医療分野での放射線利用 (08-02-01-03) RIの化学的作用の応用原理 (08-04-03-06) 第五福竜丸 (09-03-02-16) 放射化分析 (09-04-03-20) <参考文献> (1)日本放射化学会:http://www.radiochem.org/index-j.html (2)日本放射化学会会則: (3)放射化学ニュース、第17号、p.65 (2008): (4)日本放射化学会刊行物:http://www.radiochem.org/publ/index.html
|

