|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
考古学の研究は、自然科学的手法の応用により画期的な成果を上げつつある。中でも放射線を用いた手法は最も古く、1934年に行われた古墳内の棺内部の調査まで遡る。現在、最も利用されているのは、14Cの年代測定に代表される放射線を用いた絶対年代の推定、X線透過試験などによる遺物の非破壊調査、放射化分析や蛍光X線分析などによる遺物の材料の調査、及び遺物に含まれる特定元素の分析による産地、流通経路などの推定である。 ここでは、年代測定についてはその種類と適用できる年代範囲、ラジオグラフィではその種類と実際の応用例、元素分析については考古学における分析の在り方をもとに、須恵器を例にとり産地同定についてそれぞれの概要を述べる。 <更新年月> 2010年12月
<本文>
はじめに 日本における20世紀最後の25年間は、考古学の研究に自然科学的手法が著しい勢いで導入され(文献1)、その大きな成果が得られた画期的時代であったと考えられる。それは年代測定、古環境、生業、材質・技法、産地、探査・調査法ならびに遺物・遺構の保存・修復に係わる研究と多岐にわたる。 そのような中にあって、放射線の利用は1934年のX線透過試験による古墳内の棺内部の調査まで遡る(文献2)。考古学への放射線利用の例として、年代測定、非破壊透過試験(ラジオグラフィ)、元素分析の3部門をとりあげる。 1.年代測定(文献3、4、5) 考古学における年代推定は遺跡の文化層(地層)の新旧関係、土器など遺物の型式編年が基本である。この年代は「相対年代」であって、「絶対年代」ではない。絶対年代を与える年代測定法には自然界の放射線を伴う現象を応用した方法が多くあり、放射年代測定法と呼ばれている。これらは原子核の壊変現象を利用する方法と結晶による放射線の吸収現象を利用する方法に分類することができる。(図1、表1) 1.1 原子核の壊変現象を利用する方法 (1)放射性炭素法 14Cの壊変(半減期5,730年)を利用する方法であり、最もよく利用されている。14Cは大気の上層部で宇宙線の作用で作られた中性子と空気中の窒素との相互作用で生成される。 大気中における14Cを含むCO2濃度は、生成と減衰の平衡状態で一定になる。生物の体内に取り込まれた14C濃度も一定である。生物は死ぬと、新しい14Cが体内に取り込まれなくなり、14C濃度は時間経過とともに減衰する。14C濃度を測定することによって生物の生命活動停止後の年代を知ることができる。14Cが放出するベータ線の比放射能を測定する方法と、加速器質量分析器で炭素同位体の存在比(14C /12C、14C /13C)を測定する方法がある(図2)。木炭など有機質遺物に適用され、約300年前から5.5万年前までの年代が測定可能。縄文土器の年代が1万6000年まで遡ることがこの方法でわかった。加速器質量分析法(AMS:Accelerator Mass Spectrometry)による炭素14の検出効率が飛躍的に高まった現在では、自然界の放射線及び装置自身の発する放射線によるバックグラウンドが無視できないこと、測定に多くの試料量が必要なことなどから、ベータ線計数法は炭素14年代法における主役の座をAMSに譲っている。 (2)フィッショントラック法 天然のウラン中99.3%を占める238Uは、半減期44億7000万年でアルファ壊変するほかに、わずかの確率で自発核分裂をする。鉱物中のウランの自発核分裂で生じた原子核は飛跡(フィッショントラック)を残す。フィッショントラックは熱によって消失するので、人為的な加熱や火山の噴火後に形成されたトラック数から年代を知ることができる。雲母やジルコンなどの微量のウランを含有する鉱物、釉薬などガラス質の遺物に適用され約1万年より古い年代が測定可能である。大阪層火山灰から取り出されたジルコン結晶に含まれる微量ウランのフィッショントラックの例を図3に示す。 (3)カリウム−アルゴン法 天然のカリウムは、主として39K(93.22%)と41K(6.77%)の安定同位体から構成されているが、放射性同位体40K(半減期12億8000万年)を0.012%含む。40Kの10.7%は40Arに壊変する。火山の噴火によって形成された岩石が閉鎖系であれば、その中に含まれる40Arは40Kの壊変によって生じたものである。アルゴンは空気中にも含まれているが、質量分析計による岩石中の36Arの測定値と大気中のアルゴンの同位体比から、40Kの壊変による40Arと大気中の40Arを区別することができる(図4)。カリウム−アルゴン法では、速中性子により39Kから39Arを生成させ、アルゴン同位体の測定のみで40Kの量を決定する。これらの方法により角閃石、雲母、長石などの鉱物を試料として、数万年より古い年代が測定可能である。 (4)ウラン系列法 238U系列中の234U、230Th、226Ra、210Rbと238Uの放射非平衡関係を利用する方法である。過剰230Th法、238U /230Thアイソクロン(isochron:等時線)法及び230Th/234U法がある(文献4)。230Th/234U法は海生生物が硬組織を形成するとき、ウランは取り込むが、トリウムは取り込まないことを利用する。形成直後の硬組織中の230Th234U放射能比はゼロであるが、234Uの壊変によって230Thが蓄積されていくので、230Th /234U比を測定することによって硬組織形成後の経過年数がわかる。化石骨、歯に適用され、約1万年から30万年の年代が測定可能である。 1.2 放射線エネルギーの吸収現象を利用する方法 (1)ルミネッセンス法 放射線エネルギーを吸収させた石英や長石などの鉱物を加熱すると発光する(熱ルミネッセンスという)。この発光量は放射線エネルギーの吸収量(放射線量)に比例する。ルミネッセンスの発光過程を図5に示す。鉱物が加熱されるとそれまでに吸収した放射線による熱ルミネッセンスは消失する(この現象をタイムゼロイングまたは単にゼロイングという)。土器焼成や火山噴火などによってゼロイングされた鉱物の熱ルミネッセンスの強度は、ゼロイング以後に鉱物が吸収した放射線量(蓄積線量)に比例する。一方、高感度の線量計素子や遺物の分析によって放射線量率(年間線量)を評価する。年代は(蓄積線量)÷(年間線量)である。鉱物を含む遺物・遺構に適用され、約100年前から100万年までの年代が測定可能である。日本の前期旧石器遺跡のほとんどはこの方法によって年代測定されている。熱のかわりに光によって発光させる光ルミネッセンス法では、太陽光によるゼロイングを利用して、レス(*1)などの風成堆積物も試料となる。 (2)電子スピン共鳴法 物質が放射性元素からの放射線や宇宙線を浴びることにより、古い試料ほど不対電子が蓄積し、その量は浴びた放射線量に比例する。放射線によって形成された結晶中の格子欠陥や不純物中心の不対電子は、磁場中でマイクロ波を吸収させると共鳴吸収を起こす。この共鳴吸収の現象を利用してルミネッセンス法と同じ原理で年代測定をする。石英を含む遺物、歯、骨などの遺物に適用し、約1,000年から数100万年までの年代が測定可能である。 2.ラジオグラフィ(内部構造の解明) 考古遺物を含む文化財へのラジオグラフィ(放射線透過試験法)の応用は、下記の目的で利用されている。 a.内部構造、内部の各部分の把握 b.異種材料の部材との組み合わせの把握 c.各材質や顔料の同定 d.鋳造品の鋳込み状態・鋳掛け・鍛造品などの技術的把握 e.本来の部分と修理箇所の把握 f.欠陥、欠損部分や腐食や腐朽状態の把握 g.土砂や錆に覆われている考古遺物では、その形状把握と遺物自体が何かの解明 h.文化財の修理前後、保管・展示中の経時変化を外面のみならず内部の状態をも把握するための記録と各種試験方法及びその事例を次に述べる。 2.1 X線透過試験とγ線透過試験 X線及びγ線透過試験、特にX線透過試験は文化財において日常的に使われ、上記の目的に最も利用され効果を上げている。特に出土金属器については、X線透過試験を行わないと保存処理や修復が出来ないと言っても過言ではない。最も大きな成果は約20年前の埼玉県行田市稲荷山古墳出土の鉄剣に象嵌(ぞうがん)された『辛亥年』と『獲加多支鹵大王』を含む115文字の発見であった(文献6)(図6)。これは西暦471年にあたり、日本史では最も謎に包まれた時期であり、文献が無い中にあって最も古い日本語である。後者の文字が雄略天皇を表すことから大きな成果となった。 2.2 X線CTスキャナー X線透過試験を三次元で立体的に捉えようとする手法で、医学関係ではコンピュータ断層写真の形で利用されている。これを文化財に応用するため、国立歴史民俗博物館や奈良国立文化財研究所に機材が設置され、出土金属器や土器に多くの成果を上げている。特に錆に被われた刀の柄頭や鍔などに象嵌(ぞうがん)がある場合、一般のX線透過写真では、前後の象嵌が重なって写り分離しにくいが、CTスキャナーによる画像処理により立体的に表現でき、分離も可能で的確に象嵌のイメージを把握出来る(文献7)(図7-1、図7-2)。 2.3 中性子ラジオグラフィ X線やγ線は、原子番号が増大するにつれて質量減衰係数が増加するのに対し、中性子は有機物を構成する軽元素の質量減衰係数が大きい(文献8)(図8)。このことを利用するとX線やγ線透過試験と異なった画像が得られる。その結果、内部を観察できない経筒(きょうづつ)の内にある経巻が朽ちて本来の形を損なっていることが観察できる(文献9)(図9)。 2.4 エミシオグラフィ エミシオグラフィは、通常のX線透過試験のように被試験体を透過したX線による画像を得るのではなく、X線照射により被試験体から生じた電子線を発生装置側においたフィルムで捉え、画像を作るものである。したがって、カンバスや板に書かれた絵画をカンバスや板を透過して得る画像にくらべて、透過の影響なしに画像に出来、また顔料などに含まれている元素からの二次電子の発生状況から肉眼では得られない画像や顔料構成分析が可能である(文献10)(図10)。考古遺物の例では、通常のX線透過試験では判読できなかった江田船山古墳出土国宝象嵌銘大刀の棟(みね)の銀象嵌文字の判読に成功している。 3.元素分析(生産地解明)(文献11) 一般に考古遺物の元素分析では資料採取に厳しい制限がある場合が多いので、試料はできるだけ少量であること、できることなら、完全非破壊分析であることが望ましい。この点から、蛍光X線分析と中性子放射化分析が最も重要な分析法となる。いずれの方法も、考古遺物に放射線を照射することによって発生する二次放射線を元素分析に利用する。 大型放射光施設であるSpring-8では、これまでに古代陶器、古陶磁器(片)、仏像、鉄器、青銅鏡などの考古遺物と呼ばれるものについて、蛍光X線分析法を用いて分析を行っている。物質にX線を照射すると物質から元素固有のX線が発生するので、そのX線のエネルギーと強度を測定することにより、物質に含まれる元素の種類と量を知ることができる。この方法は、分析する物体(試料)を非破壊で測定することができるため、破壊したり化学処理を加えたりすることが許されない貴重な遺物の分析を行うことができる。考古遺物に含まれる微量元素の分析結果から、遺物の産地や輸送経路の推定ができるとともに、遺物の製法の推定にも利用されている。 1960〜70年代にかけて優れた性能を持つ半導体検出器や分光結晶が開発されて、中性子放射化分析法による多成分系試料の同時多元素分析が著しく進歩した。さらに、最近ではコンピュータの制御によって完全に自動化された装置が普及している。この様な測定装置の改良につれて、考古遺物の元素分析も単なる検査目的ではなく、元素分析によって得られた情報を使って新しい考古学を展開しようとする方法に向かって行われている。 考古学の中で最も重要な問題が考古遺物の産地問題である。この問題は歴史研究の立場からは「ものの生産と供給」を通して古代を再現することに結びつく重要な問題であるにもかかわらず、従来の考古学的手法では満足できる解答が与えられない。ただ、単なる検査目的で土器や石器を分析してみても直ちに産地が推定できる訳ではなく、どの元素を使い、どのようにして遺跡出土の土器や石器を生産地に結びつけるのかという方法論を開発しておかなければならない。この産地推定法を開発するためには、前以て生産地の遺物を大量に分析し、各生産地の化学特性を整理しておかなければならない。石器(サヌカイト、黒曜石)の場合は原石の露頭が生産地であり、土器の場合には土器を焼成した窯跡が生産地となる。したがって、全国各地に窯跡が残っており、そこから大量の破片が出土している須恵器が方法論開発に最適の分析対象となる。 須恵器(*2)は、5世紀代に製作技術が導入され、10世紀頃まで生産は続いた。前半の5〜7世紀代では生産はそれ程普及しておらず、この時期の生産の中心は陶邑(すえむら:大阪府堺市)で、地方窯は数少ない。古墳での祭祀道具として使用されたため、各地の古墳から出土する。 陶邑産の須恵器は、北は岩手県から南は鹿児島県に至るまでの全国各地の古墳から出土することが確認されている。その分布範囲は前方後円墳の分布範囲と一致する。須恵質土器の一例を図11に示す。5〜7世紀は、倭の五王の時代から畿内大和政権が次第に政治的な基盤を固めていく時期に当たり、勢力拡大の状況を須恵器の伝播を通して探ることが可能である。 須恵器胎土(粘土)中には多くの元素が含有されているが、ルーチン分析で測定できるのは数元素に限られる。どの元素が有効に地域差を示すかは、実際に各地の窯跡出土須恵器の蛍光X線スペクトルを測定し比較すればよい。その結果、K、Ca、Rb、Srの4元素が有効因子として選択された。 初期須恵器の窯群である陶邑群と朝倉群(あさくら:福岡県甘木市)の2群間判別図を図12に示す。現在、K−Ca、Rb−Srの両分布図と2群間判別図を併用して、初期・古式須恵器をはじめ、平安時代の須恵器の生産と供給に関する研究が進められている。石器についても京都大学原子炉実験所の研究があり、広域にわたる石器の伝播・流通図の作成が行われている。 用語解説 (*1)レス:黄土(黄砂)、loess;風で運ばれ堆積した淡黄色または灰色がかった黄色のシルト質堆積物をいう。黄土の特色は、均質で0.05〜0.005mmの微砂が50%以上あること。中国北部、ヨーロッパ、北米、北アフリカ、ニュージーランドなど広く世界的に分布しており、日本では玄海砂丘、山口県の安岡付近においてレス状砂からなる古砂丘が報告されている。なお、地層をつくる堆積物はその成因により主なものは3通りある。(1)水成堆積物:川水や海流による堆積物、(2)火山噴出物:いわゆる火山灰や溶岩流、(3)風成堆積物:細粒の砂塵などが大気中を気流によって運ばれてくる堆積物。 (*2)須恵器(すえき):土師器(はじき)は弥生土器の後身にあたり、赤褐色の素焼きの土器で、須恵器は、一部をロクロを利用して作り、密閉構造の窯の中で高温で焼いた灰色硬質の焼き物の総称で陶器(すえき)の当て字である。5世紀始めごろに朝鮮半島から渡来した技術者が作り始め、新羅(しらぎ)焼の系統に属する。貯蔵用、祭り用、食事用として土師器と併用し、煮炊きには土師器をもっぱら用いた。なお、陶器は陶邑(すえむら)で大量に焼かれたことに由来する。 <図/表> 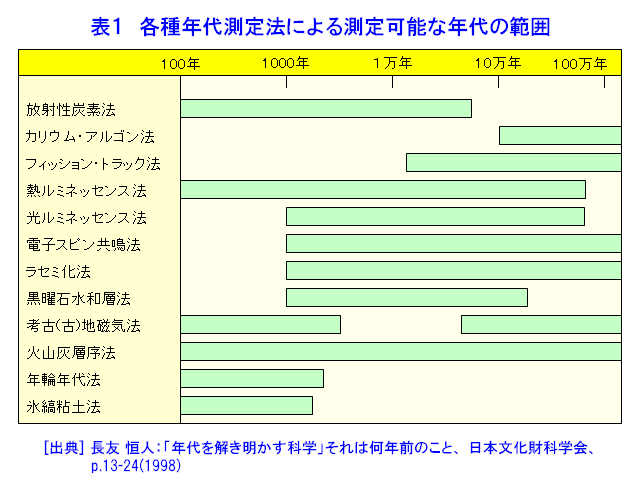

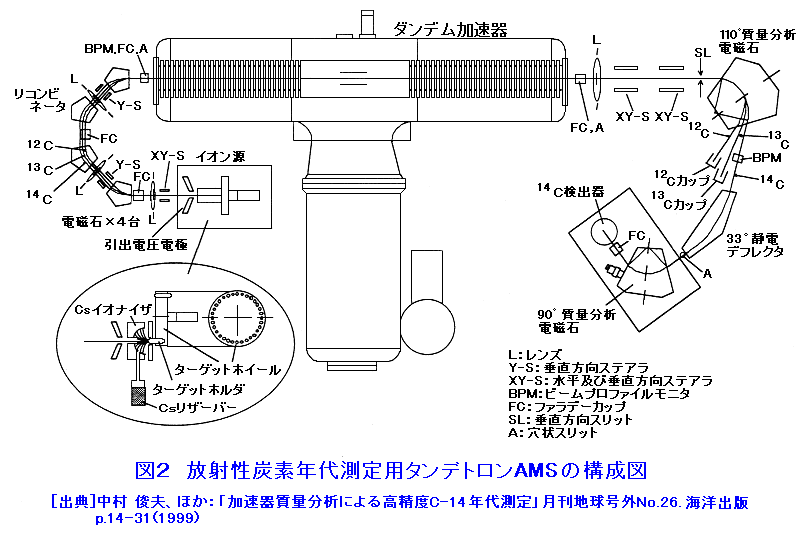
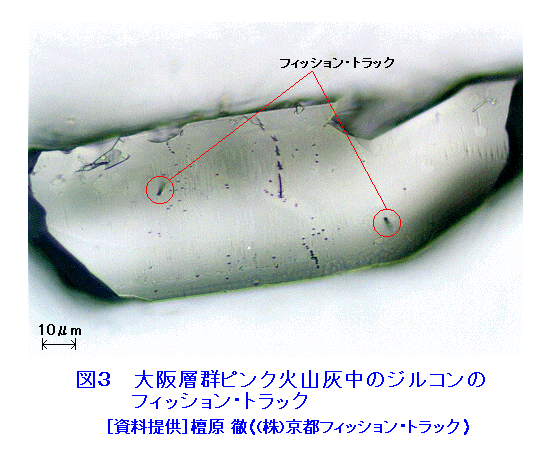
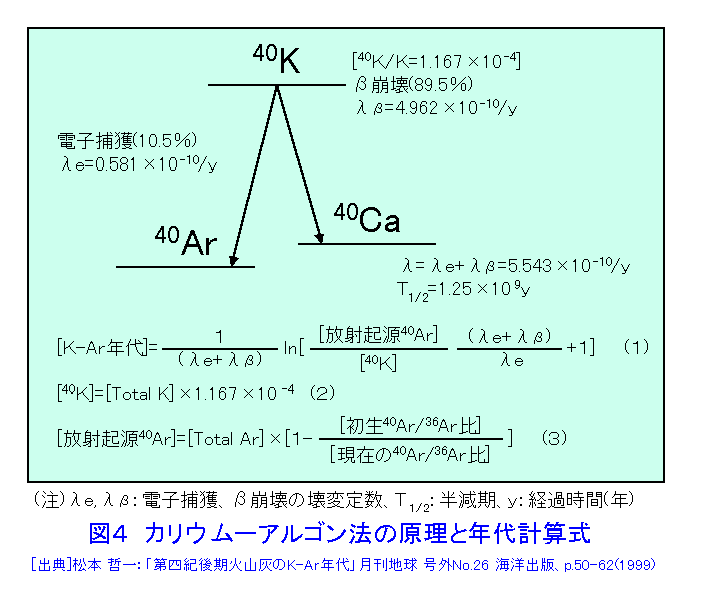
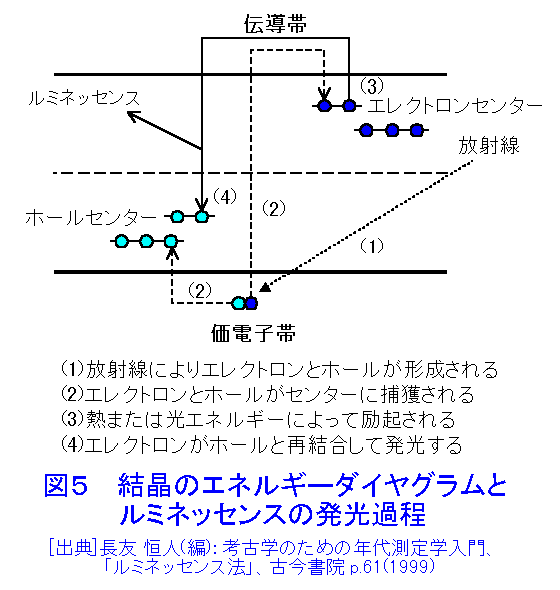
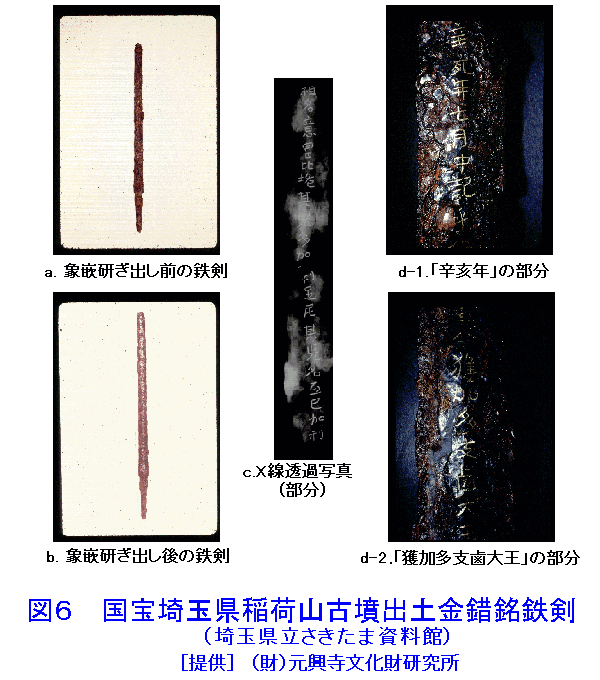
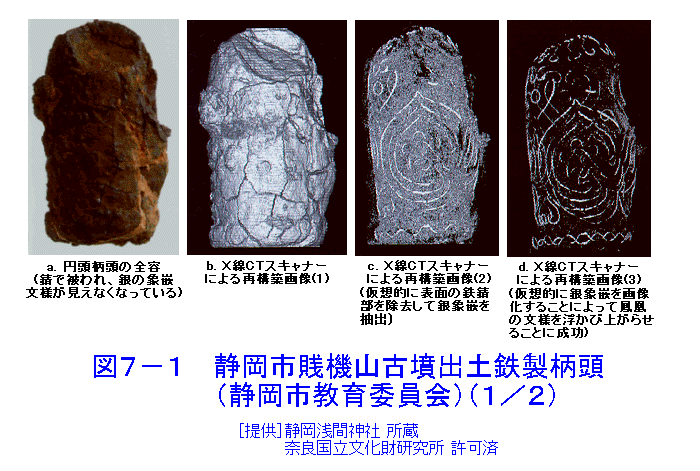

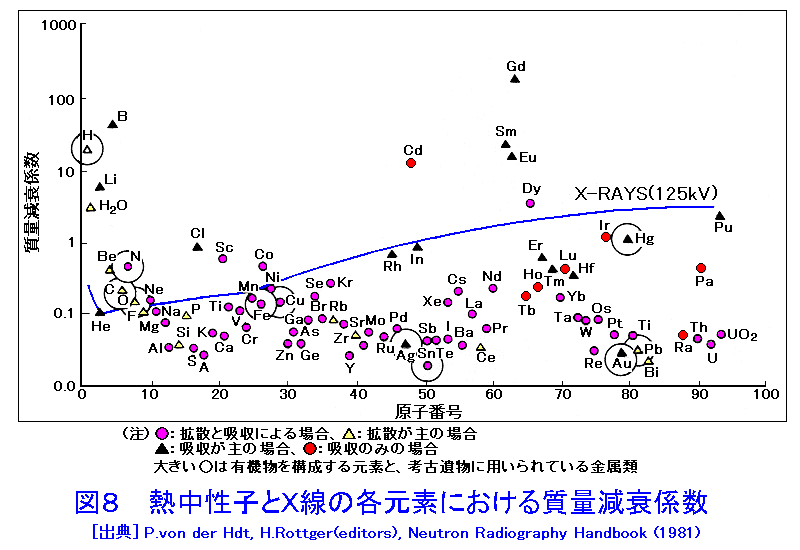
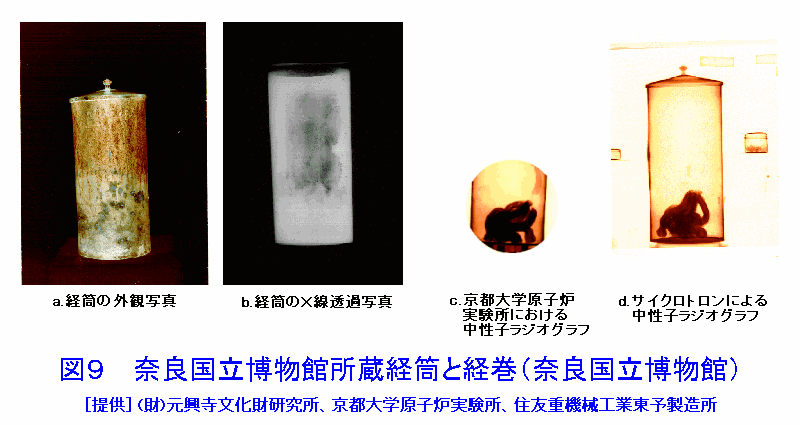


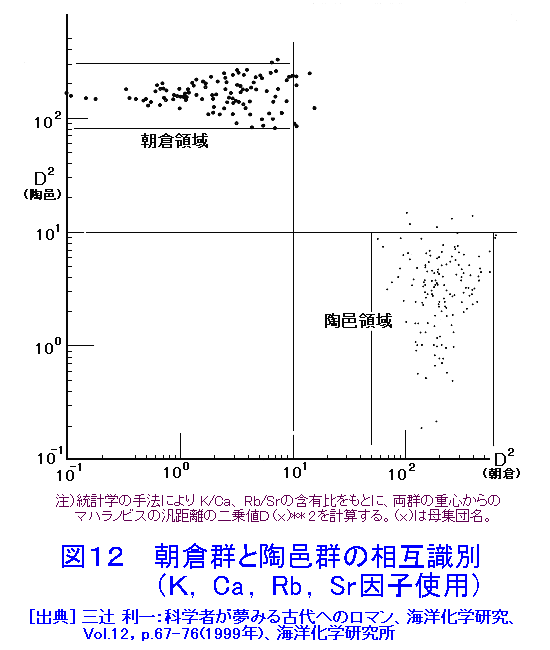
<関連タイトル> 放射線の蛍光作用 (08-01-02-05) 中性子ラジオグラフィの原理と応用 (08-04-01-01) 放射線測定による年代推定 (08-04-01-11) 工業用ラジオグラフィ(放射線透過試験) (08-04-02-03) 天然の放射性核種 (09-01-01-02) <参考文献> (1)文部省科学研究費特定研究特定研究「古文化財」総括班:「自然科学の手法による遺跡・古文化財等の研究」(1980) (2)梅原 末治:「摂津阿武山古墳調査報告書」「大阪府史跡名勝天然記念物調査報告第7緝」(1936) (3)「高精度年代決定法とその応用」月刊地球 号外 No.26、海洋出版(1999) (4)長友 恒人(編):「考古学のための年代測定学入門」古今書院(1999) (5)日本文化財科学会:「それは何年前のこと?」日本文化財科学会設立15周年記念公開講座(1998) (6)増澤 文武:X線透過試験、再度のX線透過試験、「埼玉稲荷山古墳辛亥銘鉄剣修理報告書」埼玉県教育委員会 8-9,21(1982) (7)村上 隆、沢田 正昭、伊藤 寿夫:高エネルギーX線CTスキャナーを用いた静岡市賤山古墳出土銀象嵌の3次元ダイナミック構造解析、日本文化財科学会第12回大会研究発表会講演要旨集 182-183(1995) (8)P.von der Hdt, H.Rottger(editors), Neutron Radiography Handbook(1981) (9)増澤 文武:文化財の研究、「中性子ラジオグラフィ写真集」日本非破壊検査協会、80-89(1995) (10)三浦 定俊:エミシオグラフィによる調査、「江田船山古墳出土国宝銀象嵌銘大刀」吉川弘文堂(1993) (11)松涌 秀治、上杉 陽、藁科 哲男(編):「考古学と年代測定・地球科学」、同成社(1999) (12)三辻 利一:「初期須恵器の産地推定法」『X線分析の進歩』第23集、アグネ、205-224(1992) (13)三辻 利一、岡井 剛、野中 俊宏、松井 敏也:「統計学の手法による古代中世土器の産地問題に関する研究(第一報)、5世紀代の須恵器の産地推定」『情報考古学』vol.1-25(1997) (14)坂本 稔:考古学と炭素14年代法、放射線と産業、Vol.123(2009)p46-51
|

