|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
ロシア連邦では、シベリア地方や極東地方の高緯度地方にある豊富な鉱物資源・エネルー資源を開拓するため、また北極海に面していくつかの都市の経済活動を維持するため、北極海の冬季でも航行できる原子力砕氷船に世界でも早くから関心を寄せていた。今までに、レーニン号、アルクチカ号、シビーリ号、ロシア号、セブモルプーチ号、タイミール号、ソヴィエツキー・ソユーズ号、バイガチ号、およびヤマール号の9隻の砕氷船を建造し就航させている。レーニン号は世界最初の原子力砕氷船として1959年に就航し、1970年に改造を行なって再度就航し、30年間におよぶ運航実績を経て1989年に退役した。またウラル号は建造1994年に進水したが、経済的事情により中断している。さらに2隻の砕氷船、スーパー砕氷船とペベック号を計画中である。 砕氷船に搭載している原子炉の炉型としては、レーニン号はループ型加圧水型炉を搭載していたが、アルクチカ号からは半一体型加圧水型炉を搭載した。半一体型加圧水型炉の原子力船での実用化はロシア連邦が世界で最初である。 <更新年月> 2005年04月
<本文>
1.原子力砕氷船開発の歴史 (1)原子力砕氷船開発の背景 図1 に示すように、ロシアはシベリア地方や極東地方の高緯度地方に開発中および未開発の豊富な鉱物資源、エネルギー資源を有している。また海岸線の半分以上が北極海に面しており、ムルマンスク(Murmansk,不凍港)、セベロドビンスク(Severodvinsk)、アンチャゲル(Anchagel)、アンデルマ(Anderma)、サレクハード(Salekhard)、ノルドビック(Nordvik)、オレネック(Olenek)、ブルン(Bulun)、ペベック(Pevek)、ペトロパブロフスク(Petropavlovsk)など極地にある多くの都市の経済活動を維持するため、また鉱物資源、エネルギー資源を運び出すため、寒冷が厳しい北極海洋を1年中航行させるのに砕氷船が不可欠である。 このような要因からロシアでは早くから砕氷船(例:1897年にYermak号、8,000トン、10,000馬力)を建造し、就航させてきた。その後もこれら資源の開発が進むにつれますます北洋航行が必要となり砕氷船の数も増えてきたが、気象・海象が厳しい北極海洋を1年中無事航行することは大変困難なことであった。事実1938年には1隻の砕氷船がLaptev海で812日間氷海に閉じ込められたこともあった。このような事が動機で、燃料補給(燃料交換)が長い期間不要であり、また燃料消費にともない喫水線([用語解説]参照)変動がないことで、原子力砕氷船に世界でも早くから注目をしてきた。ロシアの造船界にとっては北極圏を安全に航行できる原子力砕氷船の建造が急務であった。 (2)原子力砕氷船用原子炉開発の歴史 ソ連政府が原子力砕氷船を開発し建設することを決定したことにより、原子力潜水艦や原子力船の建造しようとする動きが出てきた。ソ連閣僚会議は、1953年11月20日に北極圏を航行する原子力砕氷船の開発を、決議案No.284011203により決定した。その後、中型機械製作省(MMBM: Ministry Middle Building Machinery)の下部機関としてSDBBM(Special Design Bureau of Building Machinery)がノブゴロド(Novgorodo)に置かれた。原子力砕氷船レーニンの開発プロジェクトは、政府決定により1954年8月18日に発足し、I.アフリカントフ(I. Afrikantov)が主任建設者に任命された。 原子力砕氷船レーニンに搭載する原子炉OK−150は、1955年6月に中型機械製作省により承認された。レニングラードのアドミラルテイスキ工場(Admiraltejskiy Plamt)で建造されたレーニンは、1959年12月5日に実験運転を開始した。1966年に、原子炉OK−150(ループ型加圧水型炉)は新規の原子炉に取り替えることが承認された。SDBBMはレーニンでのOK−150の運転経験を生かし、セヴェロドビンスクの“Star工場”で1967年から1970年の38カ月をかけて新しい原子炉OK−900(半一体型加圧水型炉)を開発してレーニンに装備し、ムルマンスクに移送して1970年6月に就役した。 1968年初期に、ソ連政府は新しい原子力砕氷船アルクチカ号に搭載するOK−900Aを開発することになった。OK−900A炉は第二世代の原子力砕氷船シビーリ、ロシアおよびヤマールに搭載することになった。 KLT−40はOK−900Aより安全性が高くなっている。KLT−40およびKLT−40M(いずれも一体型加圧水型炉)は、第三世代の原子力砕氷船であるセブモルプーチに使用された。KLT−40Mは、河川用原子力砕氷船タイミールおよびバイガチに使用された。 2.原子力砕氷船の建造と運航 (1)原子力船の炉型 一般に原子力船では、どこの国でも民生用、艦艇用にかかわらず、熱水力上の都合と放射線管理の点から、ほとんど加圧水型炉(PWR)を搭載している。 図2 に加圧水型炉の3炉型を示す。ループ型炉は、原子炉容器、蒸気発生器、一次系ポンプなどの一次系機器が長い大口径配管(ループ)で連結されている原子炉システムである。現在発電用原子炉に採用されている加圧水型原子炉の炉型である。豊富な建設経験、運転経験を有していること、個々の機器の点検作業が簡単であることなどのメリットがある。場所をとること、建設時に据え付けと溶接箇所が多いこと等のデメリットがあり、大口径一次系配管の破損による原子炉冷却材喪失事故(大 LOCA)を想定した安全対策を設計上考慮しなければならない。またループ型炉は艦艇用原子炉を含む舶用原子炉でも最も多く採用されている炉型である。民生用では、米国の貨客船サバンナ号、日本の原子動力実験船「むつ」、ロシアの砕氷船レーニン号で採用されている炉型である。 半一体型炉は、一次系機器を原子炉容器に直接短管で連結吊す原子炉システムである。熱出力2,000MW程度までは可能であるが大型炉には向かない。ループ型炉と比べると場所をとらず、建設時の据え付けと溶接箇所が少なくて済む。大口径の一次系配管が無いので、大LOCA事故の想定をしなくて済み安全対策上有利になる。世界で半一体型炉の搭載は、ロシアにおけるアルクチカ号以降の原子力砕氷船のみである。フランスではCAS(3G)炉が設計済みの半一体型炉である。 一体型炉は、蒸気発生器、一次系ポンプなど放射能を含む一次系機器を原子炉容器内に内装した原子炉システムである。半一体型炉より中小型炉向きである。原子炉容器は大きくなるが、原子炉のシステム全体ではコンパクトとなる。工場でかなりの組み立て作業ができ、現地据え付け作業が少なくなる。自然循環による炉心冷却能力が高く、一次系配管が無いためLOCA対策上安全性が高くなる。一次系の加圧には自己加圧方式と、ループ型同様原子炉容器の外に設ける方式とがある。大型原子炉容器の輸送と現地据え付け作業に難がある。また原子炉容器内は複雑な構造となる。原子炉容器内の一次系機器の保守が大変難しいので、信頼性の高い機器を使用しなければならない。また二次系水の放射化の問題もある。一体型炉の搭載はドイツの鉱石運搬船オットハーン号が世界最初である。フランスの高速炉スーパーフェニックスでも採用された。現在ロシアで設計中の海上発電炉、実用化を進めている中型発電炉VPBER−600および地域熱供給炉AST−500、日本で設計研究中であった砕氷船用原子炉MRX、潜水調査船用原子炉DRXは一体型炉である。 (2)原子力砕氷船の建造と運航 表1にロシア連邦の原子力砕氷船の主要目を示す。ロシアでは、現在までレーニン(Lenin)号、アルクチカ(Arctica)号、シビーリ(Sibir)号、ロシア(Rossiya)号、セブモルプーチ(Sevmorput)号、タイミール(Taimyr)号、ソヴィエツキー・ソユーズ(Sovetsky・Soyuz)号、バイガチ(Vaigachi)号、およびヤマール(Yamal)号の9隻の原子力砕氷船を建造、就航させている。レーニン号はすでに退役し、ウラル(Ural)号は進水したがその後は経済的事情で建造が中断している。またスーパー砕氷船(Super Icebreaker、砕氷能力3.5m以上)とペベック(Pevek)号の2隻を計画中である。 表2 にロシアの原子力砕氷船で採用している舶用炉型式を示す。世界で最初の原子力砕氷船レーニン号は、サンクトペテルブルク海軍工廠で建造、1959年9月に完成し12月には就航し、ムルマンスク(Murmansk)を基地として北極海商船隊を先導した。 図3 に就航中のレーニン号を示す。 レーニン号の原子炉システム全体は、独立した原子炉3基で構成され、通常時は原子炉2基の運転である。原子炉1基は原子炉容器、直管貫流型蒸気発生器2基の2ループで構成され、それぞれのループは、一次系ポンプ2基、加圧器2基で構成されている。原子炉システムからの蒸気は4つのターボ発電機に導かれ電気(直流:1,200ボルト)を起し、この電気が3つの推進スクリューを回転させる電動モータに送られる。 中性子の漏洩、一次系ポンプの故障、蒸気発生器伝熱管からの漏洩などのトラブルを経験した。1966年には全面的オーバーホールに入り、原子炉も3基から新しいループ型炉2基に減らし、一次系ポンプの交換なども行なって、1970年から再び運航に戻った。1989年には退役したが、その間30年間に65万4,400海里(121万2,000km)航行し、そのうち86%が氷海航行であり、3,741隻の商船を支援した。 図4 にレーニン号の北極海における航路を示す。 レーニン号の経験をもとに新に開発した炉型の原子炉システム(OK−900A、半一体型炉)を搭載した第2世代の大型原子力砕氷船として、アルクチカ号、シビール号が建造された。レーニン号より砕氷能力も高められている。アルクチカ号は1975年から北極海航路に就航した。また、1977年8月17日には原子力砕氷船として世界で最初に北極点に到達した。 図5 にアルクチカ号原子炉システム断面図を、 図6 に就航中のアルクチカ号を、 図7 に原子炉制御室を、および 図8 にターボ発電機室を示す。 シビール号は1978年からベーリング海航路に就航した。 図9 に就航中のシビール号を示す。第2世代の原子力砕氷船はその後ロシア号、ソヴィエツキー・ソユーズ号、ヤマール号とつぎつぎと建造された。ロシア号では原子炉安全性の強化、急速傾斜システムの採用、特殊耐氷塗料の採用などの改良が図られている。 図10 に就航中のロシア号を示す。 ソヴィエツキー・ソユーズ号とヤマール号はロシア号の改良型で原子炉格納容器気密性の改善、耐氷電気防食装置の採用などが図られている。ロシア号は1985年に、ソヴィエツキー・ソユーズ号は1989年に、ヤマール号は1993年に完成、就航している。 OK−900A(半一体型炉)をさらに改良したKLT−40を搭載したセブモルプーチ号は砕氷ライター/コンテナー船(ラッシュ船)である。370tライター(はしけ)74隻を搭載しシベリア地方に輸送し、また20ftコンテナ1,336個を搭載して北極圏を含む国際航路での輸送に従事している。セブモルプーチ号だけは他の砕氷船(電動モーター駆動推進)と異なりタービン船である。また核燃料も高濃縮ウラン(60%濃縮以下)を用いたU−Zr合金を用いている。 図11 に原子炉システム断面図を、 表3 に設計主要目を示す。1989年には黒海からベトナムを経てウラジオストックまで航行した。 1986年に就航したタイミール号(図12参照)と1990年に就航したバイガチ号はシベリア地方の開発拠点の河川を遡航できるように浅い喫水線をもつ大型砕氷船である。フィンランドのマサ造船所で船体部の建造と制御装置の搭載を、ロシアのバルチック造船所で原子炉の建造と搭載を行った。全プロセスが自動化されている。 [用語解説] 喫水線(吃水線とも書く)の喫水(draught)とは、浮かんでいる船体の水面と船体横断門の最低点との垂直距離(深さ)をいう。喫水は船の航行する海域、季節、載貨量で異なる。船体の舷側にT(熱帯満載喫水線),S(夏期満載喫水線),W(冬期満載喫水線),TF(熱帯淡水満載喫水線),F(夏期淡水満載喫水線),ENA(冬期北大西洋満載喫水線)等の乾舷標(freeboard mark)が印してある。砕氷船は氷上に船を乗り上げて重力で氷を割って進むので、喫水が変わると砕氷航行しにくくなる。 <図/表> 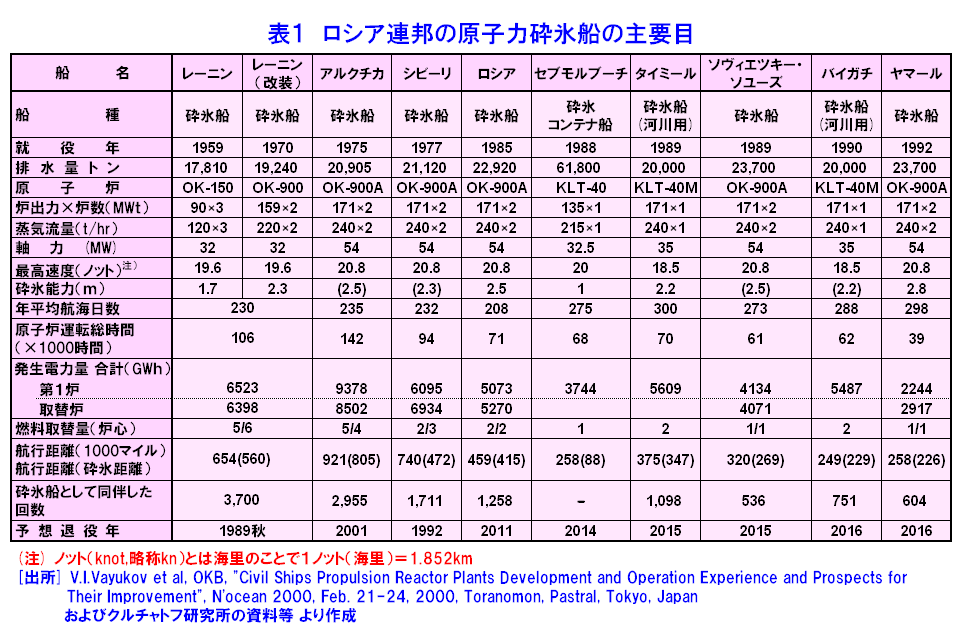
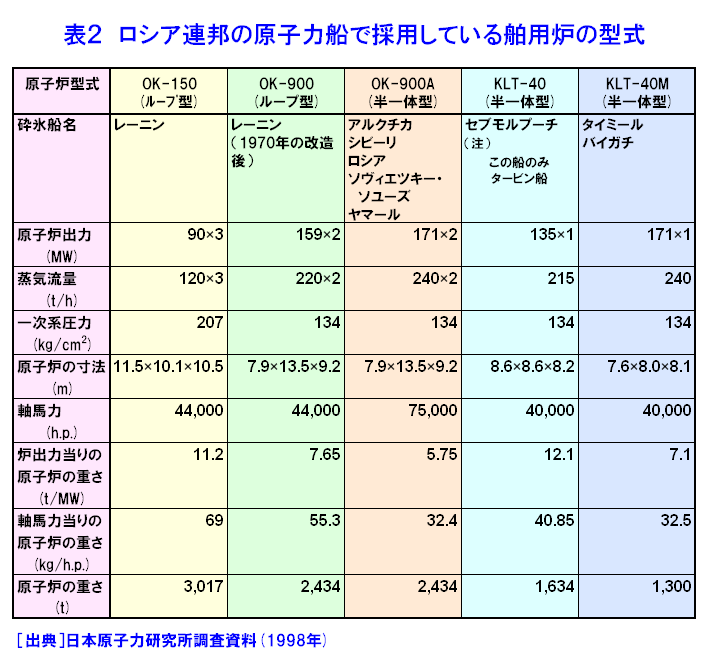
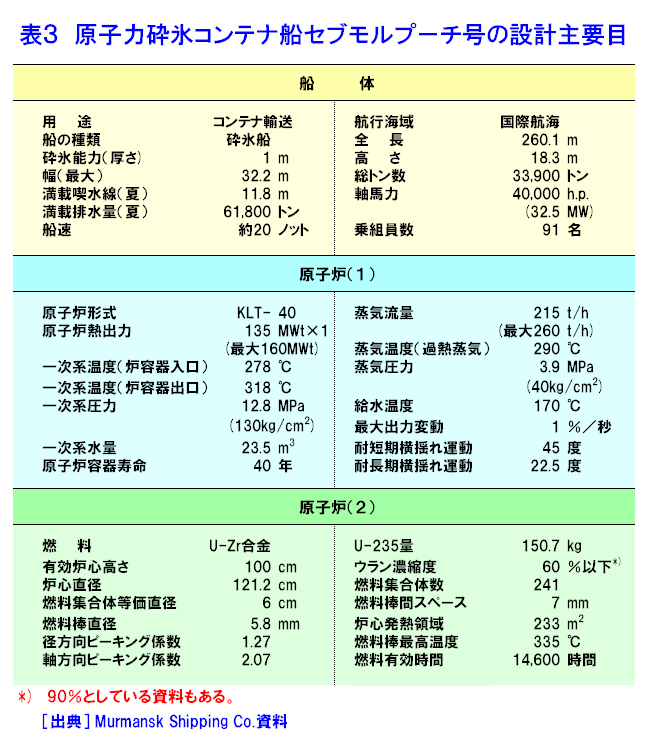
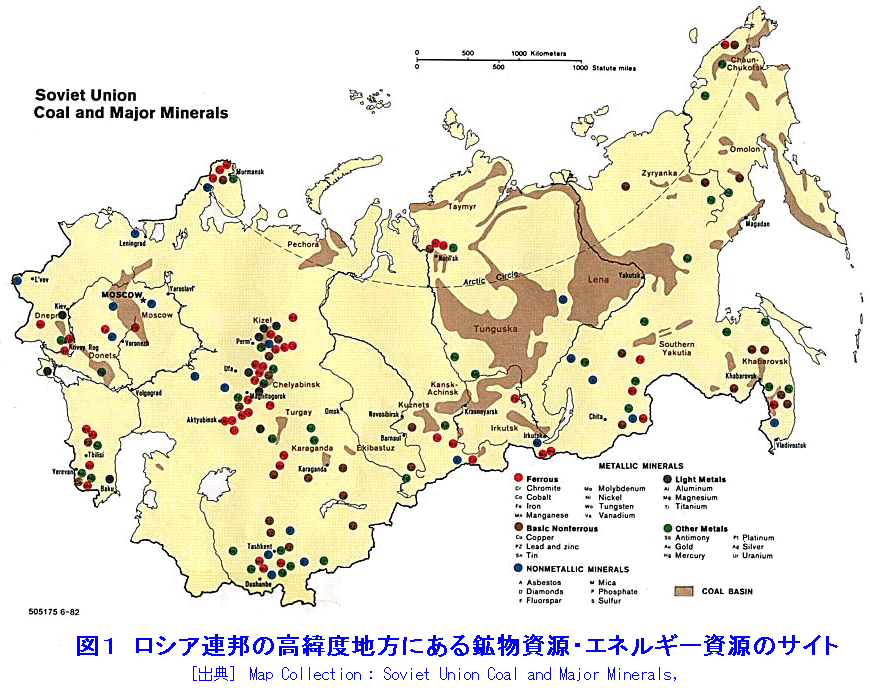
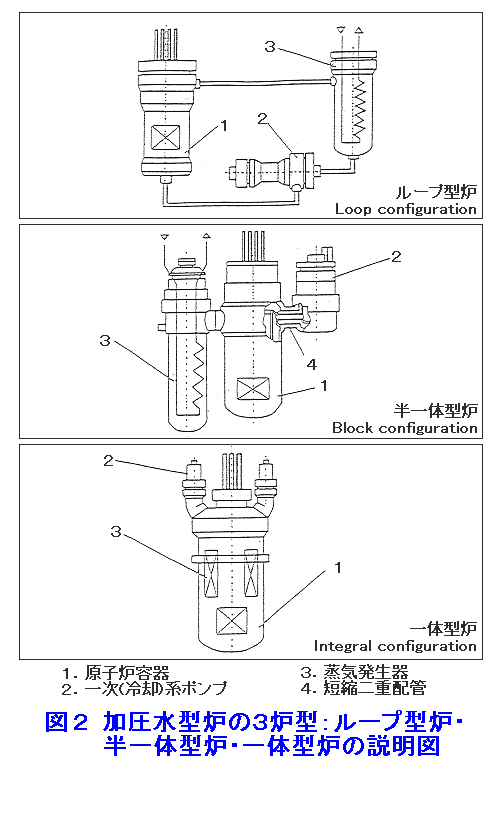

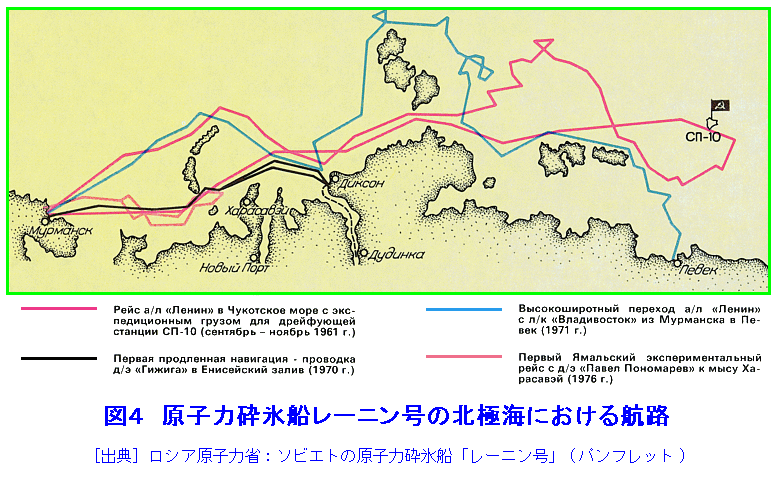
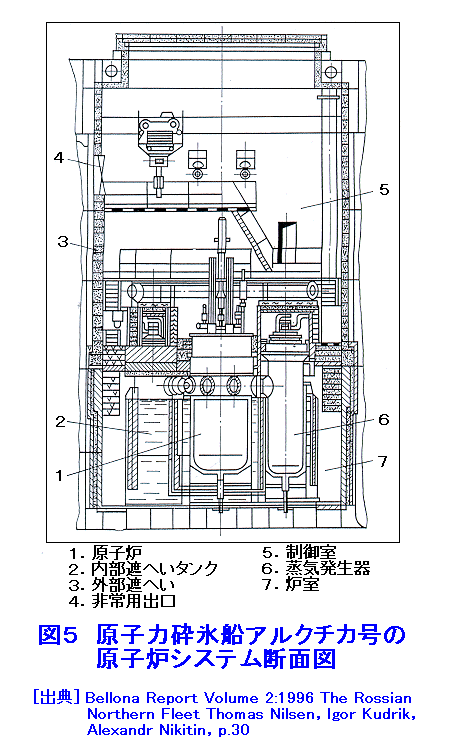
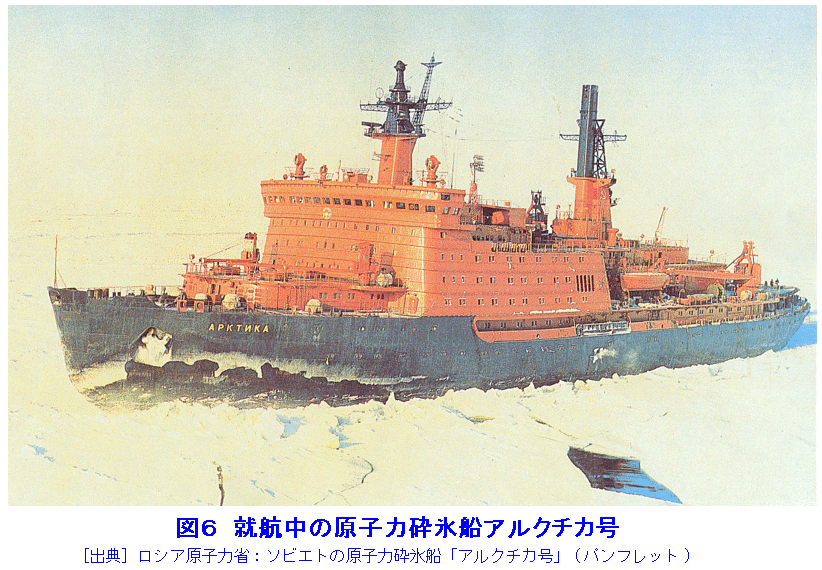
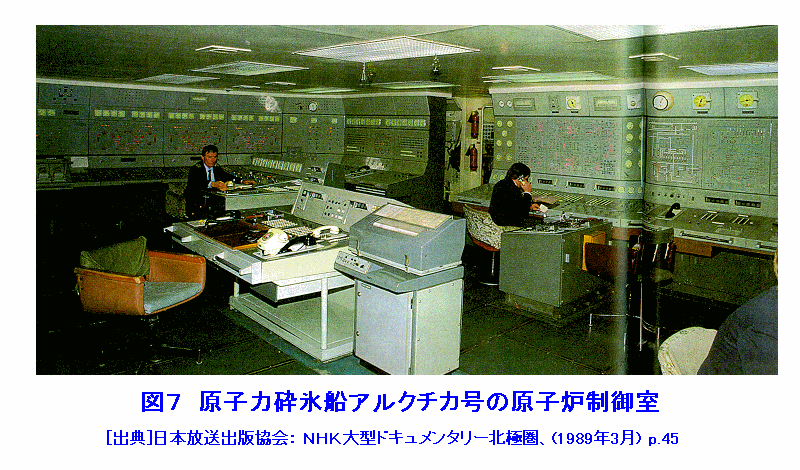
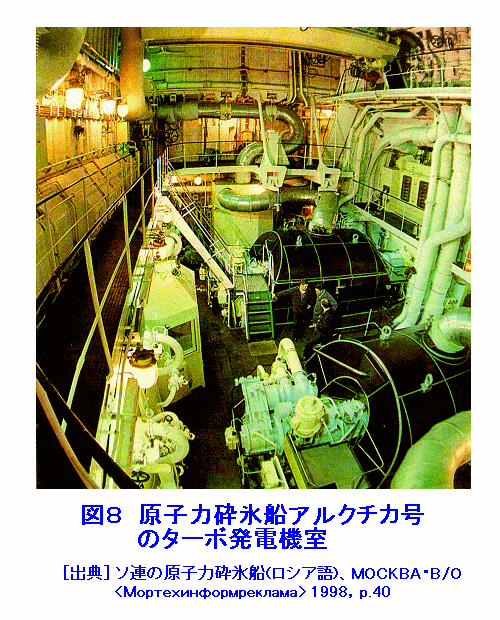

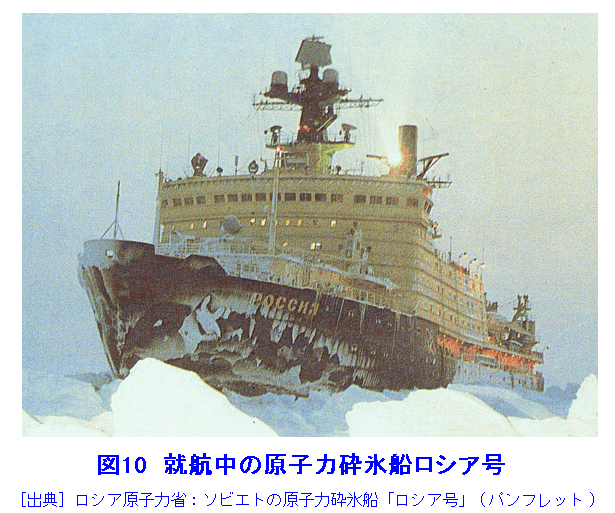
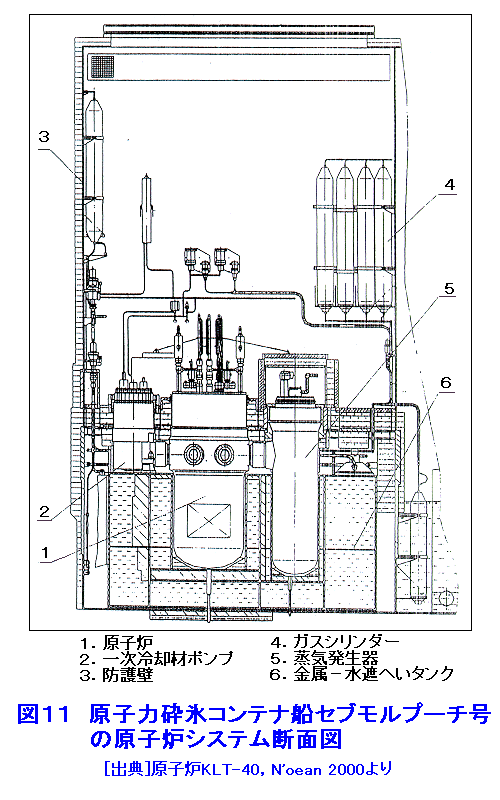

<関連タイトル> 原子力船「むつ」開発の概要 (07-04-01-01) 原子力船「むつ」の概要 (07-04-01-02) 原子力船「むつ」の安全性 (07-04-02-01) 我が国における原子力船設計研究 (07-04-04-01) 世界における原子力船研究開発と運航実績 (07-04-05-01) <参考文献> (1)ソ連の原子力砕氷船船(ロシア語のパンフレット) (2)Bellona(編):Murmansk Shipping Company (3)原産(編):原子力年鑑2000年、2000年10月 (4)原産(編):原子力ポケットブック、2000年7月 (5)日本原子力研究所調査資料 (6)Murmansk Shipping Company資料 (7)Nuclear industry of Russia. Moscow, Atomenergoizdat, 2000, pages 502−505 (8)The Half a century in atomic machine building under editing F.M.Mitenkov. House publisher Kitizdat, N.Novgorod, 1997, pages161−185. (9)Makarov V.I., Pologikh B.G., Hlopkin N.I. and at al. Experience of the creation and operation of civil ship’s reactor’ installations. Atomic energy, 2000, v. 89, issue 3, p. 179−189. (10)Memorials of Science and Technology, MINATOM, 1999, p.86
|

