|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
原子炉施設の幾つかの構築物、系統および機器は、通常運転の状態のみならず、これを超える異常状態においても所定の機能を果たすべきことが「発電用軽水型原子炉施設の安全設計に関する審査指針」において求められている。したがって「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」では、原子炉施設の安全設計の妥当性を確認するため、異常状態すなわち「運転時の異常な過渡変化」および「事故」について解析し、評価を行うことを求めている。ここでは、BWRの事故解析例として、原子炉冷却材喪失事故(LOCA)、主蒸気管破断事故および制御棒落下事故を採り上げた。ABWRの事故解析の特徴についても付記した。 (注)東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)に伴う福島第一原発事故を契機に原子力安全規制の体制が抜本的に改革され、新たな規制行政組織として原子力規制委員会が2012年9月19日に発足したため、本データに記載されている「事故の概念」、「事故の解析プロセスと安全評価の判断基準」等について見直しや追加が行われる可能性がある。 <更新年月> 2010年01月
<本文>
1.事故の概念 「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって、発生する頻度は低いものの、発生した場合は原子炉施設および周辺公衆に重大な影響を及ぼすおそれのある想定事象が「事故」である。 BWRでは次に示す4つのカテゴリーの12の事象を事故として想定している。 (1)原子炉冷却材の喪失または炉心冷却能力の著しい変化 a.原子炉冷却材喪失 b.原子炉冷却材流量の喪失 c.原子炉冷却材ポンプの軸固着(ABWRを除く) (2)反応度の異常な投入または原子炉出力の急激な変化 a.制御棒落下 (3)環境への放射性物質の異常な放出 a.放射性気体廃棄物処理施設の破損 b.主蒸気管破断 c.燃料集合体の落下 d.原子炉冷却材の喪失 e.制御棒落下 (4)原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化 a.原子炉冷却材喪失 b.可燃性ガスの発生 c.重荷重の発生 BWRの事故に対する解析プロセスと安全評価の判断基準を表1に示す。「運転時の異常な過渡変化」と異なり炉心の損傷や放射性物質の原子炉施設外への放散を伴う事象であるため、それらを前提とした判断基準(例えば、炉心の冷却可能性や周辺公衆の実効線量)が採用されている。事故に対する解析評価の例として、110万kW(1100MWe)のBWR(BWR-5)の「原子炉冷却材喪失」、「主蒸気管破断」および「制御棒落下」について以下に述べる。なお、これらのうち原子炉冷却材喪失と主蒸気管破断の事故は、原子炉施設の立地の適否を評価するための重大事故および仮想事故に対する評価の際にも取り上げられる事象である。 2.BWRの事故解析 2.1 原子炉冷却材喪失(LOCA) 定格出力運転中に原子炉冷却材再循環ポンプの吸込側の再循環配管に大破断が発生し、破断口の両端から原子炉冷却材が喪失すると想定する。 再循環配管破断が起きると、原子炉格納容器に原子炉冷却材が放出されるので、安全保護系(「原子炉水位低」信号あるいは「ドライウェル圧力高」信号によるスクラム)により原子炉が緊急自動停止(スクラム)する。炉心シュラウド外水位(ダウンカマ内水位)は急速に低下し、ジェットポンプノズルに達すると炉心流量はさらに低下し、事故発生後約10〜15秒に炉心が一時的に露出する(図1)。高圧炉心スプレイ系(HPCS)による注水が事故発生約30秒後に開始し、低圧注水系(LPCI)による注水が事故発生約50秒後に開始することにより、事故発生約80秒後には炉心水位が回復(再冠水)する( 図2)。原子炉圧力は低下に向かい最高使用圧力の1.2倍を超えない。燃料被覆管温度は炉心流量の低下に伴って上昇するが、再冠水前は蒸気冷却等により、また、再冠水後は膜沸騰冷却によって上昇が抑制され、除熱機能の回復とともに低下する(図3)。ドライウェルに流出した高温高圧の水と蒸気はサプレッションプールに導かれ凝縮し、さらに原子炉格納容器スプレイ系作動により除熱されるので、原子炉格納容器内の圧力は低下する。 また、燃料被覆管の酸化層の増加はきわめて小さいため、燃料被覆管の延性が失われることはなく、燃料棒の破裂はない。燃料被覆管のジルコニウムと水との反応も無視し得る程度であるので、発生する水素は可燃性ガス濃度制御系の使用により可燃限界以下に十分抑えることができる。非常用ガス処理系の自動作動により、原子炉格納容器の外へ放散される放射性物質の量は少ないので、原子炉施設周辺の公衆に放射線被ばくによる大きなリスクを与えない。 2.2 主蒸気管破断事故 定格出力運転中に主蒸気管が格納容器外で破断し、主蒸気隔離弁が閉鎖するまでの間、主蒸気が流出すると想定する。 4本の主蒸気管のうち1本が原子炉格納容器外で瞬時に完全破断すると、安全保護系(「主蒸気管流量大」の信号)により主蒸気隔離弁(MSIV)が事故後最大5秒で閉鎖し、あわせて同弁の10%閉鎖の信号により原子炉がスクラムする。破断管を流れる蒸気は直接上流側の破断口から流出し、他の3本の健全な管を流れる蒸気はタービン主蒸気止め弁の上流側にある連絡管を通って破断管を逆流し、下流側の破断口から流出する。主蒸気隔離弁が閉じるまでに破断口を通して流出する量は、蒸気約13トン、水約22トンである(図4参照)。炉心が露出し始めるには81トンの冷却材が流出しなければならないので、事故時に炉心が露出することはない。事故後原子炉は逃がし安全弁、原子炉隔離時冷却系および残留熱除去系によって冷却される(図5参照)。 一方、環境に放出される放射性物質の量については、事故発生時の原子炉内の核分裂成生物の濃度は運転上許容される最大濃度であり、主蒸気隔離弁閉鎖前に破断口から放出された冷却材とともに環境に放出され、主蒸気隔離弁閉鎖後には隔離弁から30%/日で原子炉が大気圧まで冷却される事故後10時間まで漏洩するとの仮定の下に評価を行っている。敷地境界外における実効線量の評価結果は0.02mSvであり、本事故による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さい。 2.3 制御棒落下事故 原子炉が臨界または臨界近傍にある際に、原子炉制御系機器の故障と運転員の誤操作とが原因となって、制御棒駆動軸から分離して炉心内にとどまっていた制御棒が急激に落下する場合を想定する。 原子炉の初期状態としては4種類、すなわちサイクル初期低温時臨界状態、サイクル初期高温待機時臨界状態、サイクル末期低温時臨界状態、サイクル末期高温待機時臨界状態について考慮する。(サイクルとは燃料を装荷してから取り出すまでの期間をいう。)原子炉冷却材流量が定格の20%のとき、最大反応度価値を有する制御棒1本が制御棒落下速度リミッタの制限により0.95m/秒の速度で落下すると想定する。原子炉出力が急激に上昇し、安全保護系(「中性子束高(平均出力領域モニタ)」の信号)により定格出力の120%に達した後0.09秒遅れでスクラムが作動する。この時、燃料温度上昇に伴うドップラー効果によって負の反応度が与えられるため、急激な出力上昇は抑制される。ピーク出力部の燃料エンタルピーはサイクル末期低温時で約2.9秒後に約203cal/gUO2で最大となるが(図6参照)、制限値の230cal/gUO2を下回っている。他方、燃料エンタルピー92cal/gUO2の破損しきい値を超えることによって破損する燃料棒の本数は、サイクル初期高温待機時に最大となり、破損本数は1,485本である。また、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、主蒸気隔離弁を閉じていると仮定しても約84kg/cm2であり、最高使用圧力の1.2倍の圧力を下回る。一方、破損した燃料棒から環境に放出される放射性物質の量については、事故発生の30分前まで定格出力で長期間(1,000日)運転されていた原子炉が高温待機状態にあり、主蒸気流量は定格の5%であり、主蒸気隔離弁は安全保護系(「主蒸気管放射能高」の信号)により5秒で全閉すると仮定して評価した。その結果、敷地境界外の実効線量は0.0016mSvであり、本事故による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいと評価された。 3.ABWRにおける事故解析の特徴 ABWRにおいては、従来の炉外設置の再循環ポンプに代えてインターナルポンプを採用したこと、および電動式改良型制御棒駆動機構、その他の安全上の向上により、以下の例で示すような特徴がある。 インターナルポンプの採用により、液相部における大口径配管の破断がなくなったので、中小口径配管の破断を重視した設計となり、高圧系の非常用炉心冷却設備(ECCS)が強化されている(高圧炉心注水系2系統+原子炉隔離時冷却系のECCS化)。これらの変更により既存BWRで見られる「原子炉冷却材喪失」事故時における炉心の露出がなくなり、事象を通じて炉心の冠水が維持される(図7(1)参照)。炉心露出による燃料被覆管の温度上昇がないので、燃料被覆管温度は、(外部電源喪失の仮定による再循環ポンプトリップのため発生する)沸騰遷移によって事故直後に最高となる(図7(2)参照)。 電動式改良型制御棒駆動機構を採用したことから「制御棒落下」事故の可能性は低減されている。従来のBWRの「制御棒落下」では制御棒と制御棒駆動機構の接合部がはずれて落下する想定であったが、ABWRではこの接合部がバイオネット方式のため、制御棒が制御棒駆動軸とともに落下することを想定している。このため、落下速度が従来の0.95m/秒に対し0.7m/秒と遅くなったが、基本的事故事象の進展は変わらない。 <図/表> 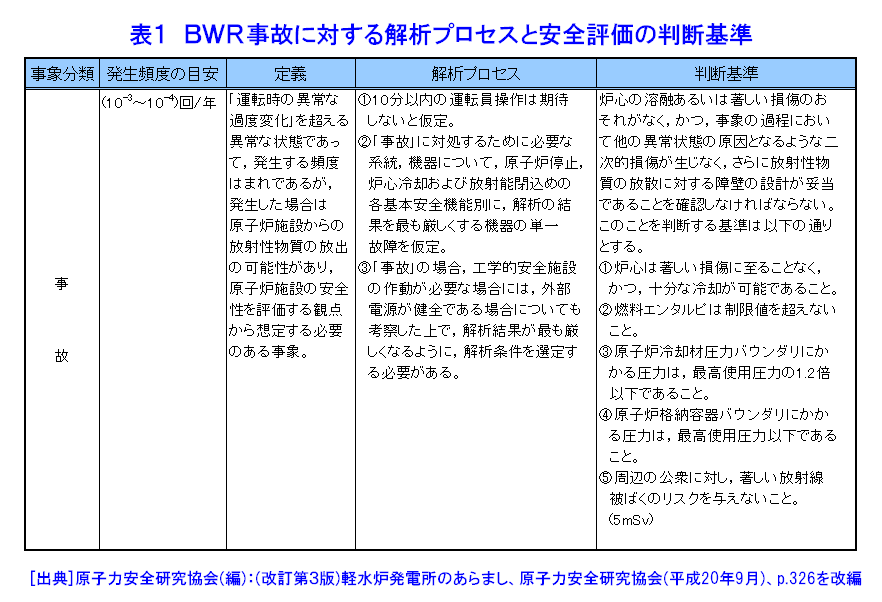
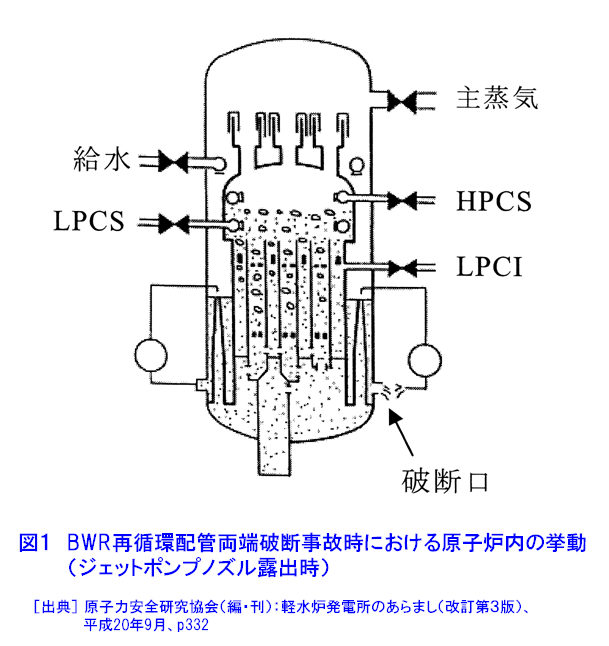
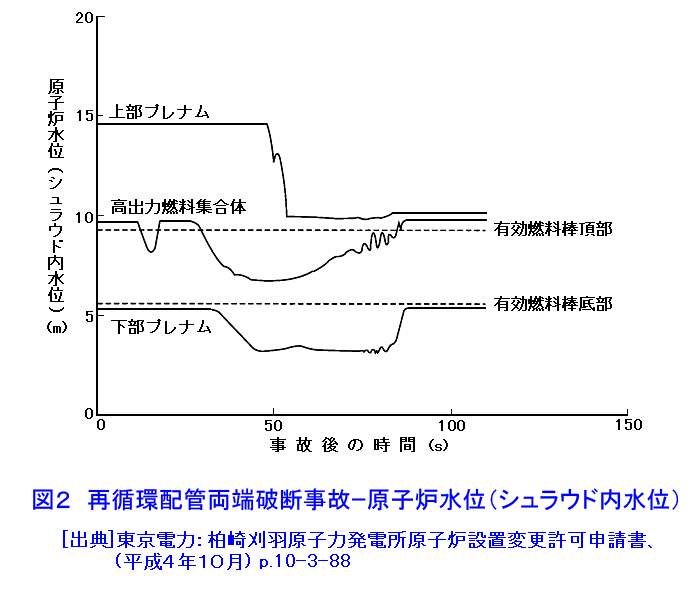
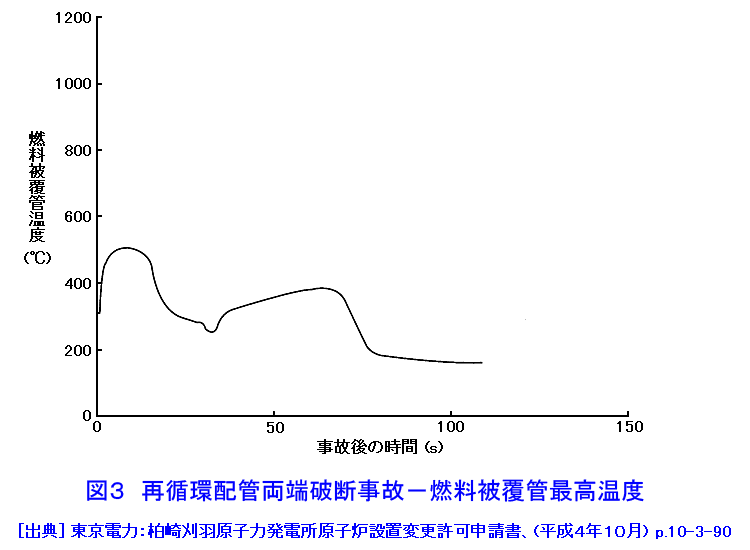
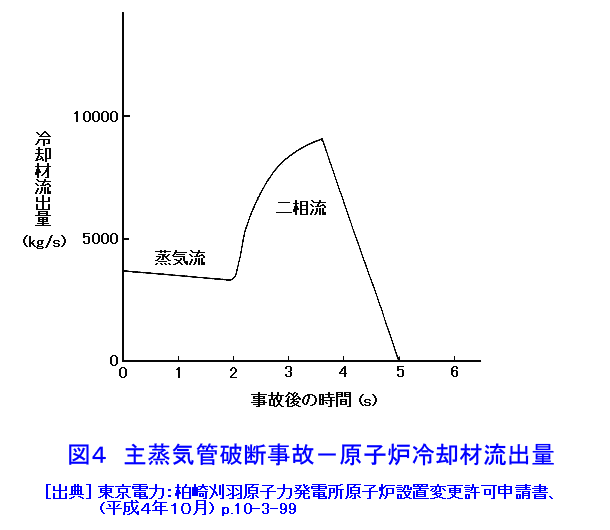
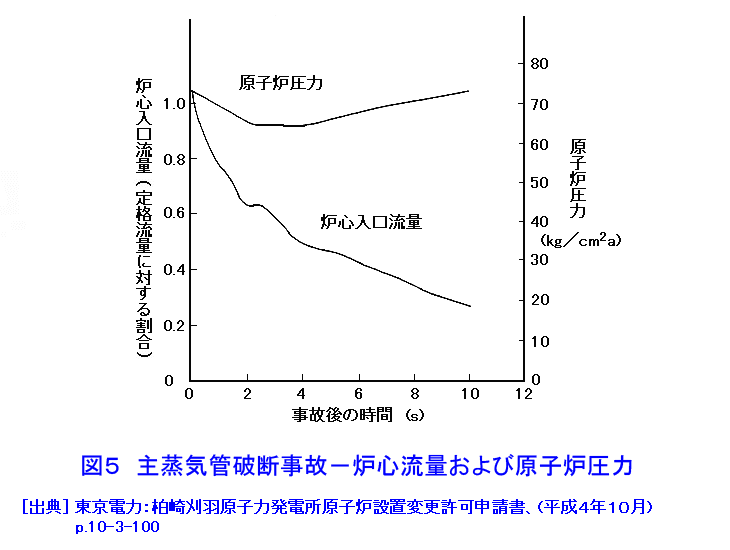
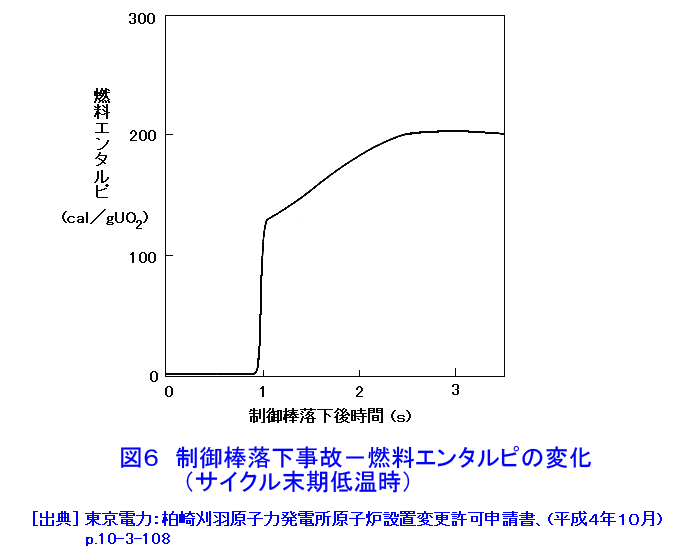
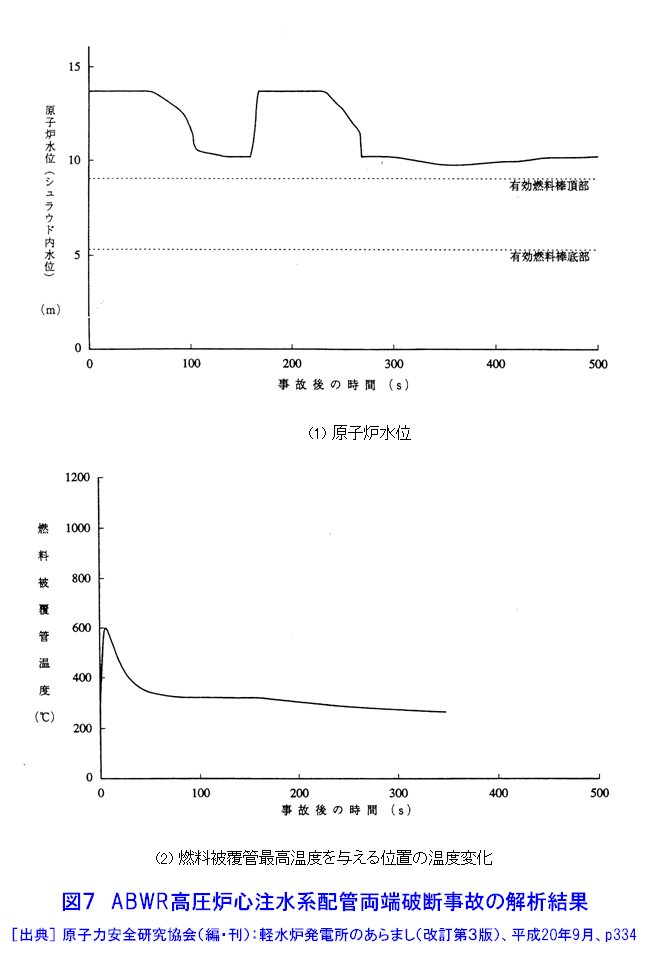
<関連タイトル> 原子炉機器(BWR)の原理と構造 (02-03-01-02) BWRの原子炉冷却系統 (02-03-03-02) BWRの工学的安全施設 (02-03-04-01) BWRの原子炉保護設備 (02-03-07-01) 運転時の異常な過渡変化(BWRの場合) (02-03-13-01) 重大事故(BWRの場合) (02-03-13-03) 仮想事故(BWRの場合) (02-03-13-04) 改良型BWR(ABWR) (02-08-02-03) <参考文献> (1)原子力安全研究協会(編):軽水炉発電所のあらまし(改訂3版)、原子力安全研究協会(平成20年9月) (2)火力原子力発電技術協会(編):やさしい原子力発電、平成2年6月 (3)原子力安全研究協会(編):軽水炉発電所のあらまし、平成4年10月 (4)東京電力:柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書、平成4年10月 (5)内閣府原子力安全委員会事務局(監修):改訂12版原子力安全委員会安全審査指針集、大成出版(2008年3月)
|

