|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
世界エネルギー会議の2010年調査報告に基づき、石油、天然ガス、石炭、水力資源について世界全体の資源量をまとめた。石油の在来資源の埋蔵量は1630億トン(1兆2400億バレル)で、その6割が中東地域に存在している。可採年数(2008年生産量を基準)は、世界平均で41年である。石油価格の高騰を背景に、天然ビチューメン、超重質油等の非在来型資源の商業利用も既に始まっている。天然ガスの在来資源の埋蔵量は186兆m3(原油換算で約1700億トン相当)であり、石油ほどの偏在はないが、中東地域とロシアに資源が多い。非在来型資源のうち炭層メタン、稠密地層ガスは米国が既に商業利用している。メタンハイドレートは賦存量が膨大であるが、商業生産の目処は立っていない。石炭の埋蔵量は8600億トン程度と推定されている。石炭資源は先進諸国とアジア地域に幅広く存在し、中国、インド等では主要なエネルギー源となっている。発電用の水力資源の推定には大きな不確かさが伴うが、技術的に利用可能な資源量の推定結果によるとアジア地域の資源が最も大きく、南米、欧州、北米がこれに続いている。 <更新年月> 2011年11月
<本文>
エネルギー資源の埋蔵量、資源量等に関して世界には幾つかの情報源があるが、ここでは世界エネルギー会議(WEC:World Energy Council)が各種情報源を用いてとりまとめた報告(2010年調査)に基づいて解説する。対象としたのは石油、天然ガス、石炭、水力資源であり、いずれも2008年末の資源量を評価したものである。なお、以下の点について留意が必要である。 埋蔵量、資源量等については学術的に明確に定義された共通の概念はない。大雑把に言えば、不確かさの大きい順に未発見資源量(unidentified resources)、推定資源量(estimated resources)、原始資源量(in-place resources)、可採資源量(recoverable resources)、埋蔵量(reserves)、確認可採埋蔵量(proved recoverable reserves)などの概念があるが、エネルギー資源の種類、評価機関ごとに利用する概念は異なっている。 また、例えば確認可採埋蔵量のように不確かさの最も小さい埋蔵量概念でも、探査技術の進歩、探査活動の拡大、賦存状況の見直し等を通じて、評価値の修正が行われている。さらに、石油の場合には通常のポンピングで得られる一次回収量を確認可採埋蔵量と定義するが、より高コストの二次回収、三次回収等によって埋蔵量は事実上、大幅に増加する。他のエネルギー資源の場合にも、これと同様に回収費用とともに利用可能な資源の量が増加する傾向があるため、資源の規模を評価する際には現状の技術、コストを前提とするのが通例である。(例外的に、ウランのように回収コスト範囲を予め区分し、各区分について資源量を評価する場合もある。) 以下のエネルギー資源別の解説では特に断りがない限り、通常の採掘法によって回収可能な「確認可採埋蔵量」を埋蔵量、「原始資源量」を資源量と呼んでいる。 1.石油 原油の地域別埋蔵量を図1に、また、埋蔵量の合計とその地域別構成比率を図2に示した。これらの埋蔵量に関する情報は英国石油(BP:British petroleum)、オイルアンドガスジャーナル(Oil & Gas Journal)等に基づいている。なお、この原油埋蔵量には天然ガス液(NGL:Natural Gas Liquid)を含む。NGLは原油とともに油田から産出する軽質の石油であり、地中では気体であるが、地上に取り出すと自然に液状になるペンタン以上の重い炭化水素である。 世界全体の原油埋蔵量は1630億トン(1兆2400億バレル)で、その6割が中東地域に存在している。また、2008年の生産量で計算した可採年数は、世界平均で41年であるが、地域別には中東地域が78年と最も長い。国別の埋蔵量をみると(図3)、上位3ヶ国が中東諸国であり、中でもサウジアラビアの埋蔵量が最大で、世界全体の21%を占めている。中東地域以外ではベネズエラ、ロシアの埋蔵量が大きい。 上記はいわゆる在来型の石油資源を通常の採掘法で回収した場合の埋蔵量であるが、近年、開発時期が古く通常の方法での回収が困難になった油田を対象として、増進回収技術が広く導入されている。常自噴及びポンピングによる原油の回収法(一次回収)では、原始資源量の10%〜25%程度しか回収できないとされる。これに対して、二次回収(油層に水またはガスを圧入して油層圧を維持する回収法)では30%以上、三次回収(水蒸気を圧入または地下で原油を燃焼させて熱を供給する熱攻法、炭酸ガスや高圧天然ガスを圧入するガス攻法など)では40%以上に回収率が増大する。米国を中心に利用され、商業ベースで回収率を上げることに成功している。世界の石油消費量は長期にわたって増加してきたが、新規油田の発見の他に、こうした増進回収技術の導入によって、石油の可採年数は永らく40年程度の水準に維持されてきた。 他方、新興国の石油需要の急増による需給逼迫とこれに伴う石油価格の上昇を見越して、これまではあまり利用されていなかった品質の悪い非在来型の石油も商業的に生産されるようになった。代表的なものとしてはカナダのオイルサンドから抽出される天然ビチューメン、ベネズエラのオリノコタールからの超重質油である。これらの確認埋蔵量を考慮した場合の国別埋蔵量を図4に示した。カナダは在来型石油資源の量はあまり大きくないが、アルバータ州で産するオイルサンドから回収可能な天然ビチューメンの量は膨大であり、これを加えるとサウジアラビアに次いで、世界第2位の石油資源国となる。すでに、カナダの石油生産の過半がオイルサンドによるものとなっている。 ベネズエラは在来型資源も元々多いが、オリノコタールの埋蔵量(原油換算)を含めると世界第3位となる。オリノコタールはオリノコ川北岸の広大な地域に賦存し、その可採埋蔵量はWECの報告値よりも大きく、サウジアラビアの原油埋蔵量並みとの推定もある。(参考文献4)オリノコタールからの超重質油は、原油と比較して比重が重い上、硫黄分、重金属を多量に含み、通常の製油所では精製できないので、改質工程で軽質化、脱硫、脱重金属化して、合成原油を製造する。改質手法としては、熱分解法と水素化添加法の2種類があるが、この他、水と界面活性剤を加えた上で発電用燃料(商品名「オリマルジョン」)としても市場に出されている。なお、オリマルジョンは超重質油の利用方法としては非効率なため、ベネズエラ政府はその生産を中止する方針を2006年に決めた。(天然ビチューメンと超重質油については本文末の補注を参照。) 非在来石油資源としてはこれらの他にシェールオイルがある。これは、オイルシェール(油母頁岩−不溶性有機物を多量に含むち密な堆積岩の総称)を乾留して回収される石油である。シェールオイルの推定資源量(原油換算)は、図5に示すように在来原油資源の数倍とされ、特に米国には莫大な資源がある。シェールオイルの生産方法としては、採掘したオイルシェール鉱石を地上で乾留して粗原油を生産、精製する方法(地上乾留法)と地下の鉱床内でそのまま熱分離し、採取井から粗原油として地表に取り出して精製する方法(地下乾留法)とがある。このうち、地上乾留法については企業化が検討されており、各国でプラントの建設・試運転を行ってきた。しかし、オイルシェール鉱石は含有率が5〜20%と低いため、効率的な鉱石処理技術の開発や廃鉱石の処分問題等の解決が必要であり、まだ本格的な商業生産には至っていない。 2.天然ガス 天然に地下から産出し、地表条件では気体となる物質で、通常はメタンを主成分とする低級のパラフィン系炭化水素ガスを指す。その在来型資源は、地質学的産状によって油田系ガス、水溶性ガス、炭田ガスなどに分類される。このうち、これまで主に商業的生産の対象となってきたのは油田系ガスである。油田系ガスは、油田において原油とともに産出する随伴ガス、又は油田地帯の含油地質系統中に遊離型鉱床を成して存在する構造性ガスに分類されるが、生産量としては構造性ガスが多い。水溶性ガスは原油や石炭の鉱床のない地質中で主として地層水中に溶解状態を成して存在するものをいう。 天然ガスの本格利用の歴史は石油に比べて浅いが、近年、主要な石油代替エネルギーとして、また、化石燃料の中では環境に優しいエネルギーとして注目され、資源開発と利用が急速に進展しつつある。 天然ガスの地域別埋蔵量を図6に、また、埋蔵量の合計とその地域別構成比率を図7に示した。石油ほどの偏在はないが、中東地域が世界の埋蔵量の41%を占め、また、可採年数は164年と地域別にみて最も長い。欧州の埋蔵量がこれに次ぎ、世界の27%のシェアを占めるが、ロシアの埋蔵量が大きいことがその要因である。世界全体の埋蔵量は186兆m3であり、これは発熱量で原油に換算して約1700億トン相当であり、原油の埋蔵量と同程度である。世界全体の生産量がまだ原油より少ないため、可採年数は54年と原油よりやや長い。国別に埋蔵量をみると、図8に示すように、ロシアが世界の24%を占め、最も大きい。中東地域ではイランとカタールの埋蔵量が大きく、世界の中でそれぞれ2位と3位を占めている。 天然ガスにも石油と同様に何種類かの非在来型資源がある。代表的なものとして炭層メタン、稠密地層ガス、メタンハイドレートが挙げられる。炭層メタン(CBM:coal-bed methane)は石炭の生成過程で生れ、地下の石炭層、またはその近傍の地層中に存在するメタンである。かつては炭鉱時に坑道内に漏出し、爆発事故を引き起こす原因の1つであった。しかし、近年になって一部の炭田地帯でボーリングにより資源として採掘され、すでに米国では、図10に示すとおり、商業的な生産が行われている。 稠密地層ガスは、浸透性が低い地層中に含まれている天然ガスの総称である。地層の種類に応じて砂岩層に貯留するタイトガス、頁岩層に貯留するシェールガスがある。稠密地層ガスの貯留層は、地質学的には在来型に類似しているが、浸透性が低いために一般に採取速度が遅く、在来資源と比べて採掘コストが高くなる。しかし、稠密地層ガスの中でもシェールガスの推定資源量は、図9に示すように在来型天然ガスの埋蔵量の2倍以上あると推定されており、豊富な資源を保有する米国では政府が税制優遇措置を設けて開発を進めてきた。 その結果、地下深くのシェール層を破砕して天然ガスを回収する低コストの生産技術が開発され、米国では図10に示すように生産量が2008年以降急増しつつある。これによって世界の天然ガス市場は大きな影響を受け、「シェールガス革命」とも呼ばれる状況を呈している。米国エネルギー省は長期見通しの中で将来的にはシェールガスの比率がさらに増加すると想定しており、また、米国が開発した低コストの回収法は世界の他の地域でも利用可能なことから、今後シェールガスの生産が長期にわたって世界の天然ガス市場に影響を及ぼす可能性がある。他方、シェールガスの回収に伴って広範囲の地下水がメタンに汚染される事例が報告されており、急速な開発利用に関しては環境影響に対する配慮も必要とされている。 未利用の天然ガス資源としてはメタンハイドレートが注目されている。メタンハイドレートは、水分子が形成する篭状構造にメタンが取り込まれてできた氷状の固体物質である。一般に低温・高圧の条件で安定であり、純粋なメタンハイドレートは1m3あたり標準状態のメタンを約170m3含んでおり、この濃縮度合いは他の非在来型ガスに比べて最も高い。凍土が発達するシベリア等の極地域と大陸・島弧の縁辺海域に分布する。特に、日本の近海にも大量のメタンハイドレートが存在することが確認されているが、まだ経済的な回収技術を開発する目処はたっていない。 3.石炭 発熱量ベースで評価して、最も大量に存在する化石燃料である。太古の植物が地中で炭化して生成したものであるが、炭化度の高い順に無煙炭、瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭、亜炭と呼ばれる。各炭種の特徴は以下のとおりである。 無煙炭(anthracite):石炭化度が高く、燃焼時に煙の少ない良質の石炭。炭素量は93〜95%。家庭用の燃料やカーバイドの原料に使われる。揮発分が低いため、着火性は悪い。 瀝青炭(bituminous coal):粘結性が高いものが多く、それらは強粘結炭とも呼ばれ、製鉄用のコークス製造の原料として使われる。炭素量は70〜80%である。 亜瀝青炭(subbituminous coal):瀝青炭と性質は似ているが、水分が多く(15〜45%)、あまり使われていない。ただし、埋蔵量が豊富なので、効率的な利用技術の開発が進行中である。 褐炭(brown coal):亜炭が加圧、乾留で変化した低品位の石炭。石炭化度は低く、水分・酸素が多い。練炭・豆炭等の原料としても使用される。名前のとおり褐色の石炭。 亜炭(lignite):日本では石炭には含めていない。褐炭の質の悪いものに付けられた俗名であり、褐炭との区別は極めて曖昧である。太平洋戦争中には燃料としても利用されたが、現在は肥料原料などにごく少量が利用されている。 石炭の地質学的な賦存量は約11兆トンで、このうち無煙炭と瀝青炭が5.3兆トン、亜瀝青炭と褐炭が5.7兆トンと推定されている。しかし、技術的、経済的に採掘できるのはその10分の1以下の8600億トン程度とされる。石炭の地域別埋蔵量を図11に、また、埋蔵量の合計とその地域別構成比率を図12に示した。 在来型の石油、天然ガスが中東(及びロシアと周辺国)に偏在しているのに比べ、石炭資源は先進諸国とアジア地域に幅広く存在し、中国、インド等の発展途上にある人口大国の主要なエネルギー源となっている。国別の埋蔵量は、図13に示すように、米国が最も多くロシア、中国、オーストアラリアがこれに次いでいる。日本では近年、石油代替エネルギーとして石炭の利用が増加してきており、そのほとんどすべてを輸入しているが、豪州炭の輸入比率が年々増加し、2009年度には全輸入量の69%に達している。 4.水力資源 山間部の降水は潜在的に発電用エネルギー源として用いることができるが、発電用として利用可能な水力資源の規模を精度良く見積もることは困難である。水資源は発電用以外に、農業用、飲料用等にも用いられるので、資源の規模が分かっても、他の用途との関係を踏まえて発電用に利用可能な量を推定する必要がある。また、降水量自体が時間的に安定したものではなく、年間量でみてもかなりの変動がある。地球温暖化は既に地域別の降水量にも影響を与えていると考えられている。 こうした中で、WECでは加盟国からの情報に基づき、理論的包蔵水力、技術的包蔵水力、経済的包蔵水力に分類して、各国の発電に利用可能な潜在的資源量をまとめている。このうち理論的包蔵水力は現実的にはあまり意味をなさないと考えられるので、ここでは地域別の技術的包蔵水力(年間発電量換算)と、2008年の発電量を図14に示した。また、技術的包蔵水力の地域別構成比率を図15に示した。 地域別にはアジア地域の資源量が突出して大きいが、中国がその44%を占めており、中国一国で北米とほぼ同規模の資源量を保有している。南米、欧州、北米がこれに続いており、これらの3地域では2008年の資源利用率(水力発電量/技術的包蔵水力)が20%を超えている。なお、WECは経済的包蔵水力の地域別集計値を報告していないが、主要国の経済的包蔵水力は公表されており、これを技術的包蔵水力と比べると、大雑把に、北米では約1/3、欧州では約1/2強の水準である。 したがって、経済的包蔵水力を基準にして水力資源の利用率をみると、北米では7割以上、欧州でも5割程度となり、先進地域では既に潜在資源の多くを利用していることになる。他方、アジア、アフリカ地域では未利用の水力資源がまだ多く残されている。ただ、水力資源の発電利用は他の水資源利用、自然環境、人間の居住環境等に大きな影響を与えるので、開発に際しては経済性の評価だけでなく、総合的な見地からのアセスメントが不可欠である。 [補注] 天然ビチューメンと超重質油:ともにAPI比重が10度以下で常温では流動性の低い重質油である。両者の性状に大差はなく、定義も国や機関によって異なるが、世界石油会議では粘性が一定基準以上のもの(流動性がより低いもの)を天然ビチューメン、それ以下のもの(流動性がより高いもの)を超重質油と呼んでいる。ビチューメンは日本語では瀝青と訳される。石油精製の蒸溜残渣であるアスファルト、ピッチもビチューメンと呼ばれるので、地層中に存在するものを天然ビチューメンと呼んでいる。超重質油はウルトラヘビーオイルとも呼ばれ、低温では流動性に乏しいが、オリノコタールの場合には鉱床が地下深くに存在し、油層が流動化しているため、そのままポンピングによる汲み上げが行われている。 (前回更新:2004年12月) <図/表> 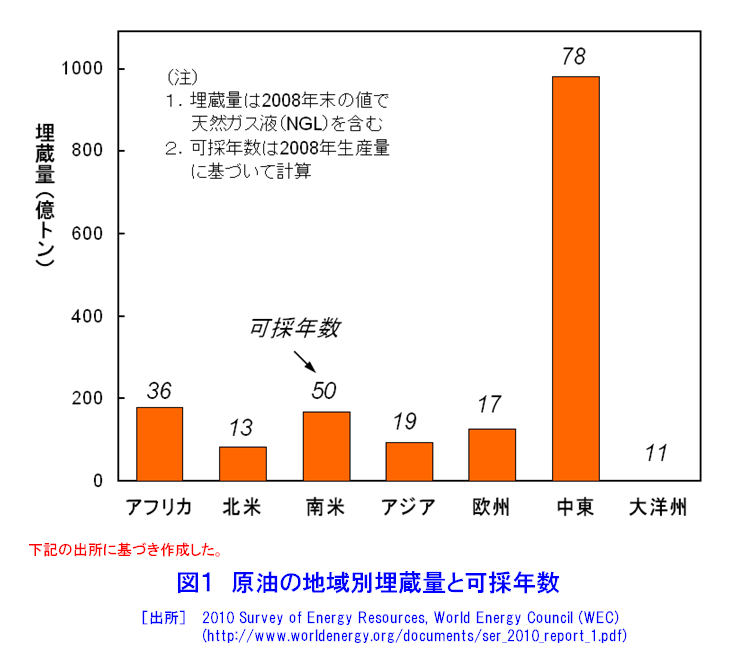
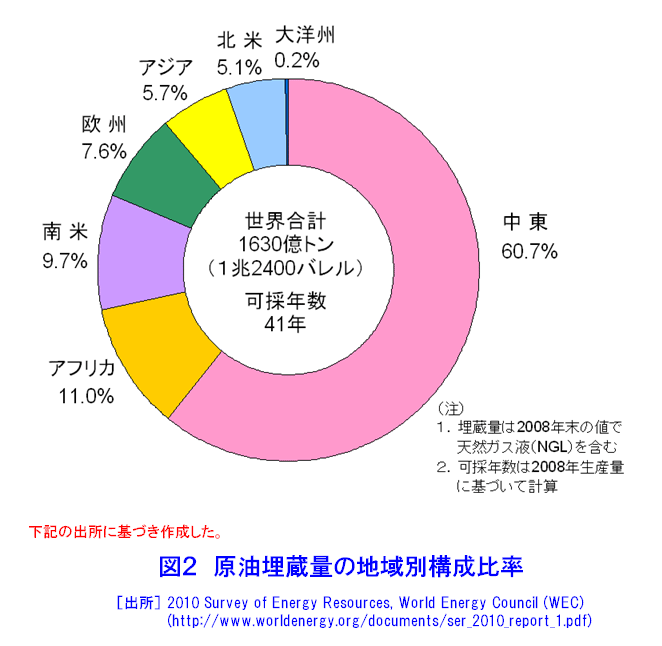
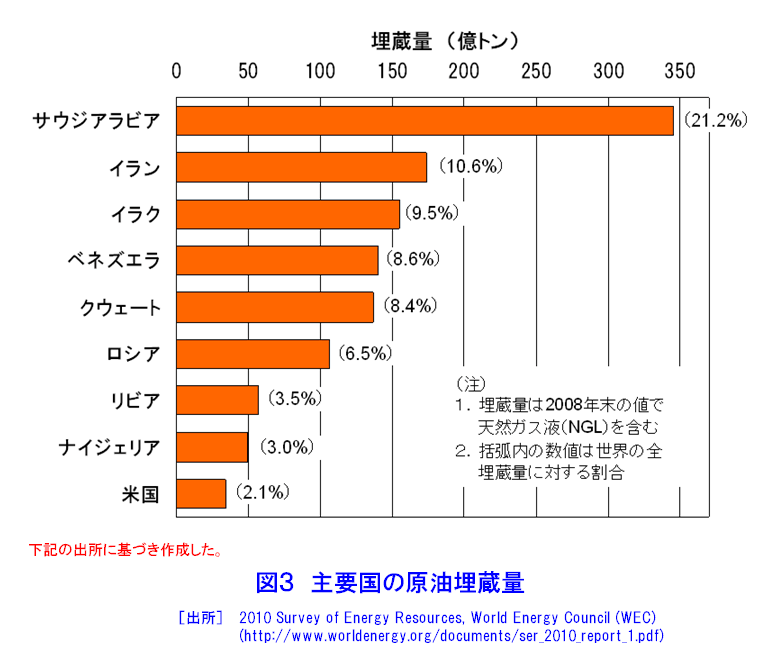
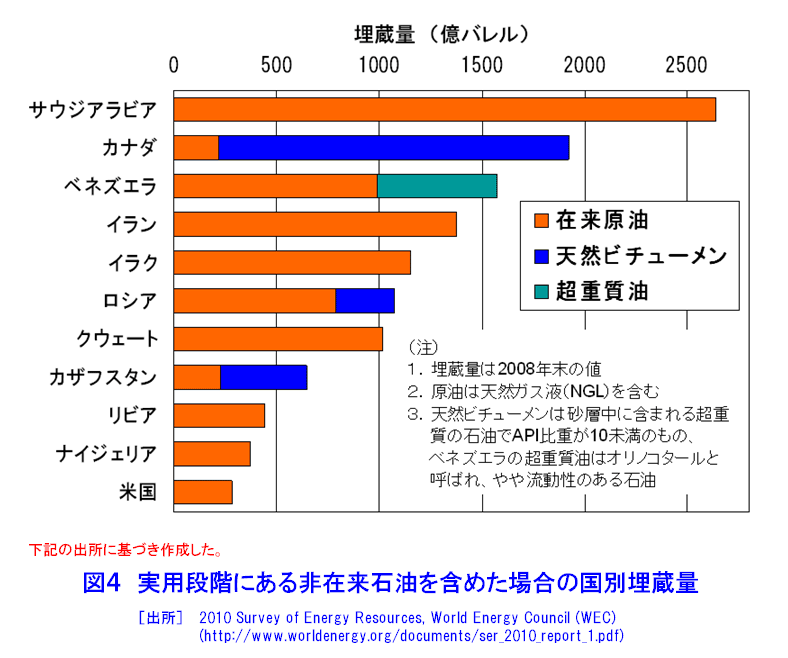
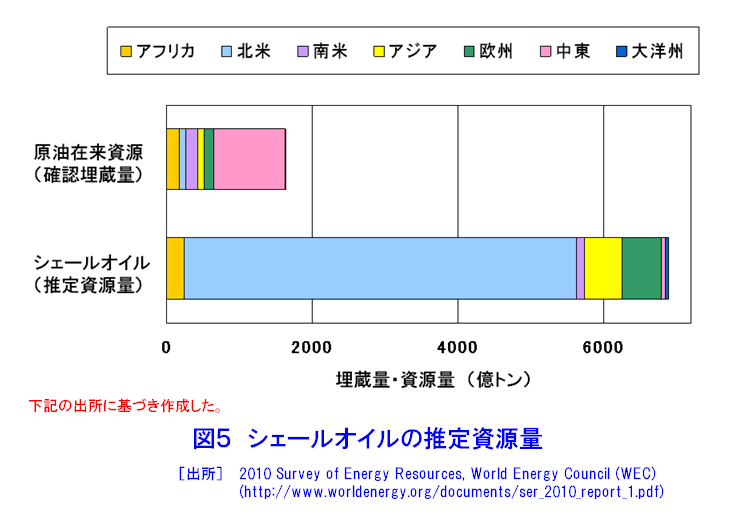
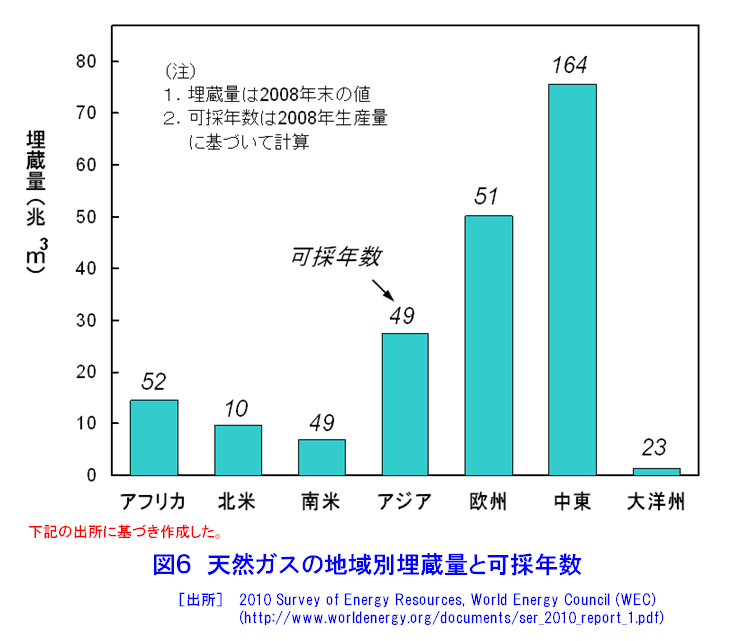
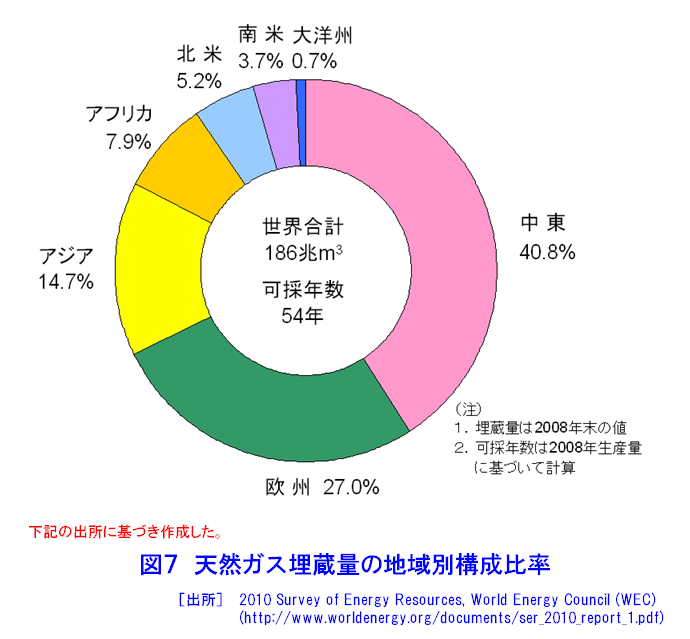
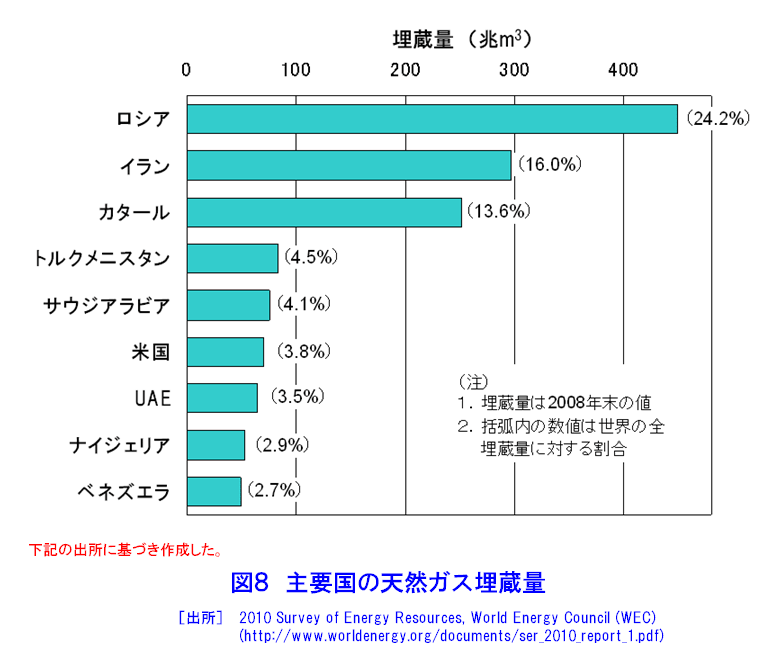
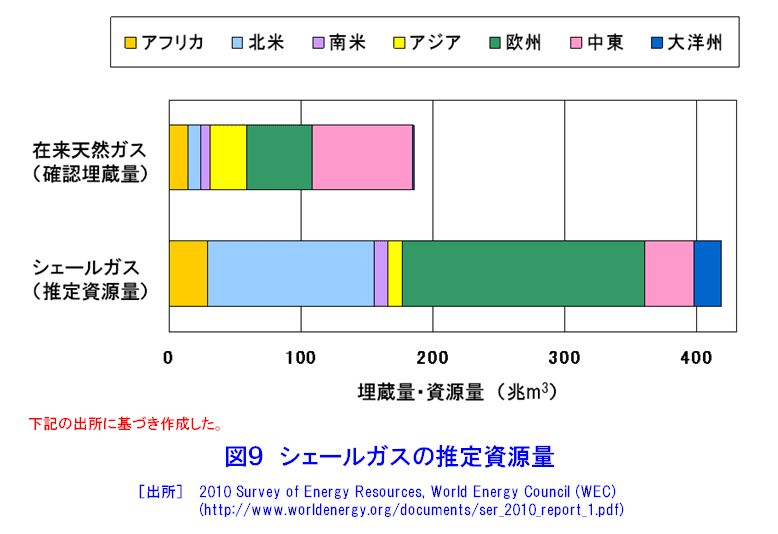
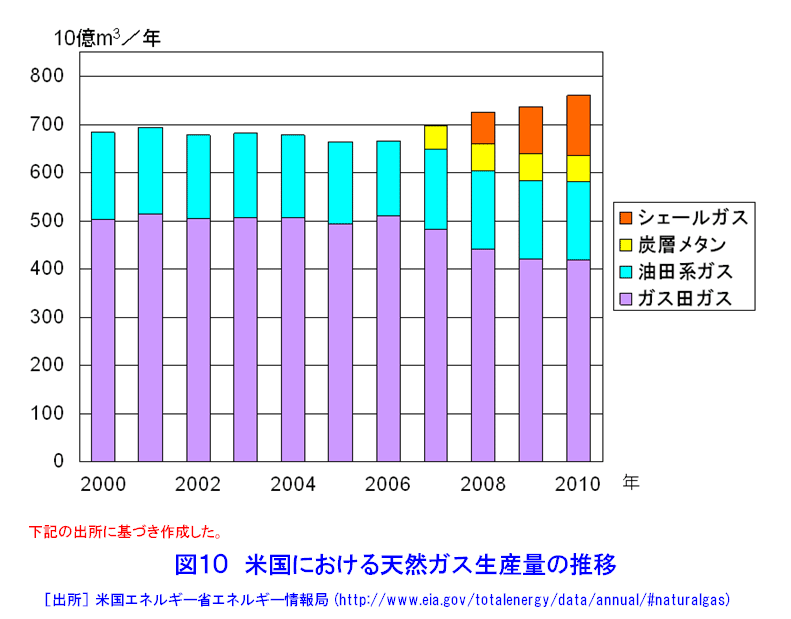
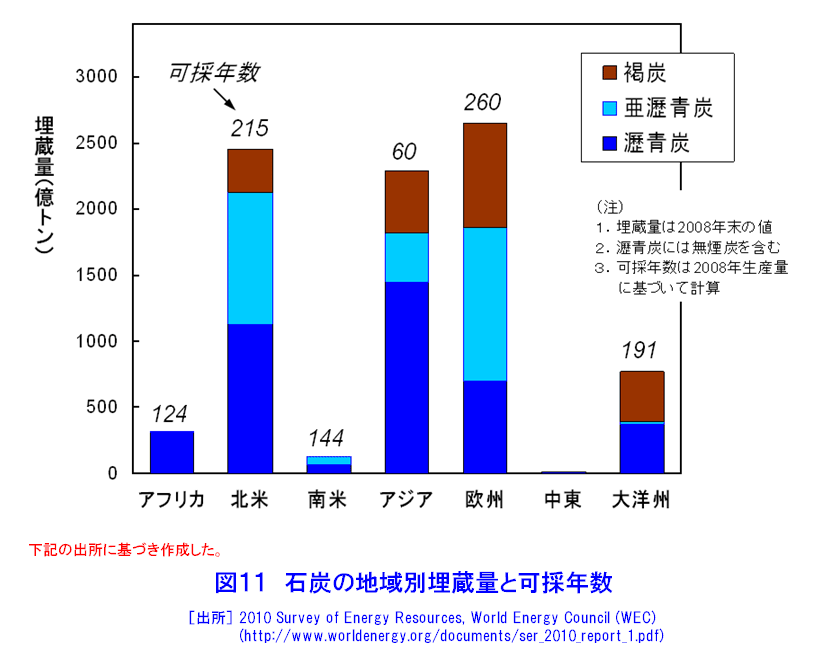

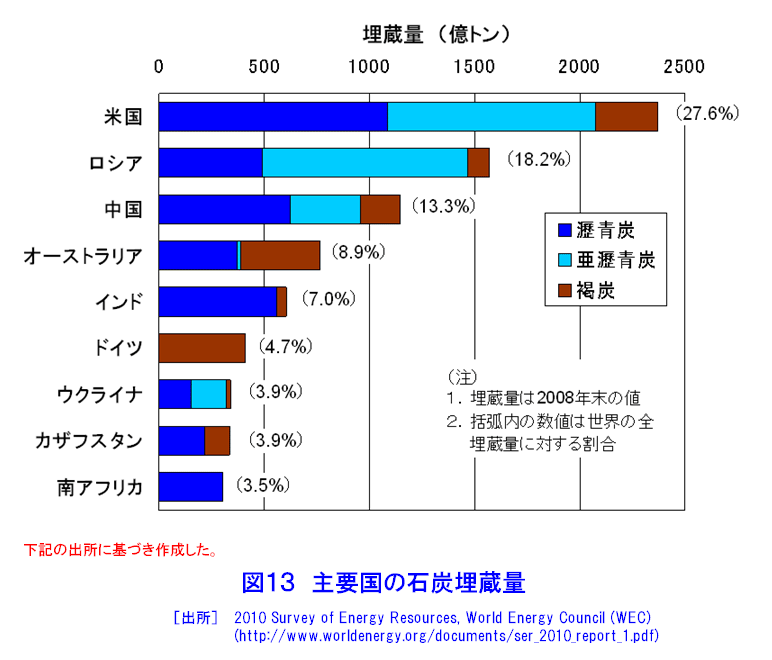
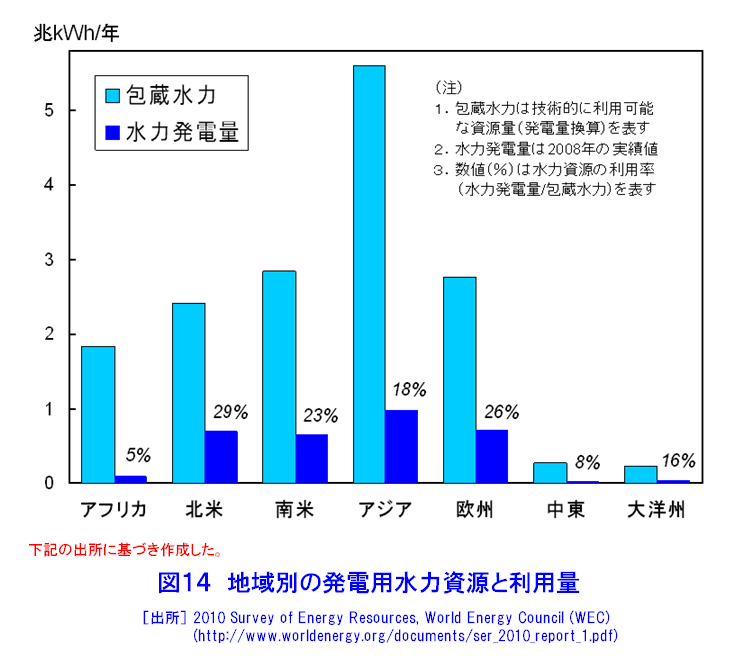
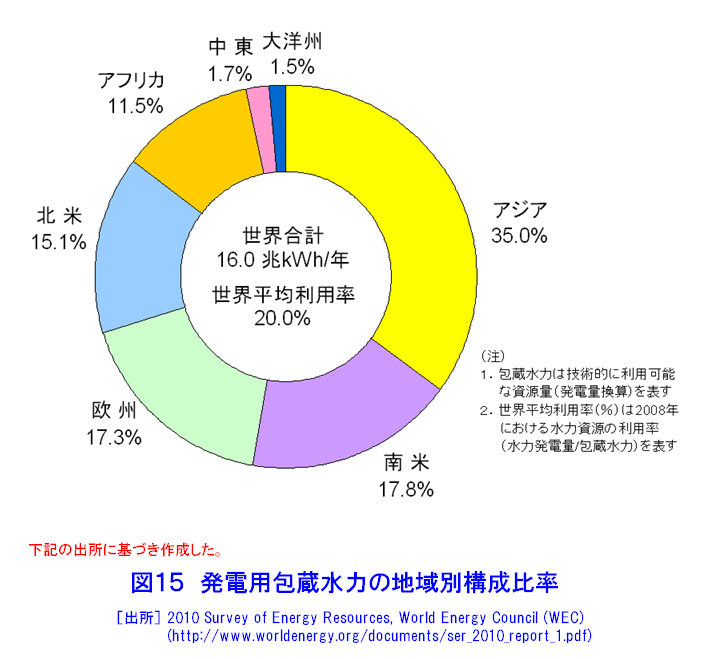
<関連タイトル> 日本の石炭情勢 (01-03-01-01) 日本の天然ガス情勢 (01-03-03-01) 国際エネルギー情勢と今後の展望 (01-07-02-01) 世界のエネルギー需給の長期展望 (01-07-02-16) 世界の一次エネルギー消費の推移 (01-07-03-01) <参考文献> (1)2010 Survey of Energy Resources, World Energy Council (WEC), (2)Survey of Energy Resources: Focus on Shale Gas, World Energy Council 2010, (3)米国エネルギー省エネルギー情報局ホームページ、 (http://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/#naturalgas) (4)(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構、石油・天然ガス用語事典
|

