|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
世界の一次エネルギーの総消費量は1965年の38億トン(石油換算)に比べ、2010年には120億トン(石油換算)に増加し、45年間に約3.2倍になった。エネルギー種別には第二次石油危機までは石油の消費量が増大し、それ以降は、主に発電分野で石油代替エネルギーの導入が進んだが、輸送用燃料としての石油に対する需要は根強く、1980年代半ばから再度、増加傾向に転じた。天然ガスは欧州を中心に利用が増大したが、近年はアジア、中東地域の消費量も急増しつつある。原子力の利用は1980年代半ばまでは順調に増加したが、1986年のチェルノブイリ事故の後は、伸びが鈍化している。石炭は、1960年代の「流体革命」でエネルギーの主役の座を石油に明け渡した後、石油危機を経て再び利用が増加した。特に、2000年を過ぎると中国の急速な工業化に伴って消費量が急増した。 一次エネルギー消費量を地域別にみると、1970年頃までOECD諸国の消費量が世界全体の70%を超えていたが、1985年には60%、2010年には47%まで下がった。他方、発展途上地域の比率は1965年の12%から、2010年には45%にまで増加した。特に、アジア新興国の2010年の比率は30%を超え、北米の23%を大幅に上回った。アジアの中でも中国の増加が著しく、2010年には米国を抜いて世界最大のエネルギー消費国となった。なお、GDP当たりのエネルギー消費量を比較するとロシアと中国が突出して大きいが、近年は西欧諸国との差が徐々に縮まりつつある。 <更新年月> 2011年12月
<本文>
世界のエネルギー消費量は石油危機や金融危機などによる一時的な鈍化、停滞はあったものの、第二次世界大戦後は急速な増加が続いている。以下に、英国石油(BP:British Petroleum)の統計(以下BP統計)に基づき、世界の一次エネルギー消費量の長期推移をエネルギー種別、地域別、主要な国別に概観する。また、主要国について国内総生産(GDP)との関係で一次エネルギー消費の動向を吟味する。なお、水力と原子力による発電量を一次エネルギーに換算する方法は調査機関によって異なるが、BP統計では火力発電の平均的発電効率である38%を用いて、一次エネルギー量を求めている。 1.エネルギー種別消費量 エネルギー種別にみた世界の一次エネルギー消費量の長期推移を図1と図2に示した。また、エネルギー種別の構成比率を図3に示した。 一次エネルギーの総消費量は1965年の38億トン(石油換算)に比べ、2010年には120億トン(石油換算)に増加し、この45年間に約3.2倍になった。同一期間における世界人口は33億から69億へと約2.1倍に増加しているので、一人当たりの平均消費量が約1.5倍となったことを示している。 エネルギー種別には第二次石油危機(1979年)までは石油の消費量が増大し、日本、ドイツ、その他の先進諸国の急速な経済発展を支えた。石油危機以降は、主に発電分野で石油代替エネルギーとして天然ガス、原子力の利用が進んだが、輸送用燃料としての石油に対する需要は根強く、1980年代半ばからの世界景気の回復とともに再度、増加傾向に転じた。その後は、アジア新興国を中心に需要が増大している。 石油代替エネルギーのうち、天然ガスは欧州を中心に利用が増大したが、近年はアジア、中東地域の消費量も急増しつつある。また、米国はもともと天然ガスの消費量が突出して多いが、1980年代前半の景気後退期に消費が低迷した後、1980年代半ばから再び徐々に増加してきている。他方、原子力の利用は1980年代半ばまでは順調に増加したが、1986年のチェルノブイリ事故の後は、伸びが鈍化している。1990年以降も新規原子力発電所の運転開始や既存発電所の出力増強は行われているが、老朽化した発電所の閉鎖も多数あり、2000年以降の発電量は微増に留まっている。 石炭はかつて化石燃料の中心的役割を果たしていたが、1960年代の「流体革命」で主役の座を石油に明け渡した。その後、石油危機を経て先進諸国では石油代替エネルギーの一つとして利用が増加したが、環境汚染への懸念から欧州諸国を中心に石炭離れが進み、1990年代の世界全体の消費は概ね横ばいで推移した。2000年を過ぎると中国の急速な工業化に伴って消費量が急増した。2000年〜2010年の期間の世界全体の石炭消費量の増加分の8割を中国が占めている。2010年の世界全体の消費量に占める中国の比率は48%である。 水力発電は長期にわたって着実に増加してきているが、一次エネルギーに占める比率は5%〜6.5%の範囲で上下しており、化石燃料に対する補完的エネルギーとしての役割を担っている。水力を除く自然エネルギー(太陽光、風力、バイオマス等)の利用は近年急速に増大しつつあるが、一次エネルギー全体に占める比率は2010年でも1.3%に留まっている。 2.地域別消費量 地域別にみた世界の一次エネルギー消費量の長期推移を図4と図5に示した。地域別の傾向として、二度にわたる石油危機を経て省エネが進んだこと、また、経済成長が鈍化したことから、OECD諸国、すなわち北米、欧州、OECD太平洋地域(日本、韓国、豪州、ニュージーランド)では、1980年代以降、エネルギー消費の増加が緩やかになった。旧ソ連圏は、ソ連崩壊後の市場経済移行期における経済混乱のためにエネルギー消費が大幅に落ち込み1990年代末からようやく増加に転じ始めた。これに対し、発展途上地域では1990年頃からエネルギー消費の増加が目立ち始め、2000年を過ぎるとその傾向が一層顕著になった。これは図5に示すとおり、アジア新興国におけるエネルギー消費の急増が原因である。 地域別の一次エネルギー消費量の構成比率を図6に示した。1965年には世界全体に占めるOECD諸国の比率は70%を超えていたが、1985年には約60%、2000年以降はさらに急速に低下し、2010年に47%まで下がった。ただ、北米と欧州がともに大幅に比率を下げたのに対して、OECD太平洋地域は1965年の5.2%から2010年には7.4%へと比率を上げている。他方、発展途上地域(中南米、中東・アフリカ、日韓を除くアジア)の比率は1965年の12%から、1985年の22%を経て、2010年には45%まで増加している。特に、アジア新興国の2010年の比率は30%を超え、北米の23%を大幅に上回る規模となっている。 3.アジア地域のエネルギー消費量 上記のように、アジア地域の一次エネルギー消費量は著しく増加しつつある。そこで、日本、韓国を含めたアジア地域の国別一次エネルギー消費量を図7に、また、国別構成比率を図8に示した。近年におけるアジア諸国の経済発展は顕著であり、図7に示すとおり、日本以外のほとんどの国で一次エネルギー消費量が急増している。 他方、構成比率でみると、かつてはアジア地域全体の40%以上を占めていた日本が、2010年には11%まで低下し、インドとほぼ同程度の比率となっている。これに対して、経済成長の著しい韓国や東南アジア諸国が2000年頃まではシェアを伸ばしているが、その後は中国の急増に伴って横ばいまたは減少の傾向にある。アジア全体の中で中国が占める比率は1965年には33%であったが、2010年には55%にまで増加した。 4.世界の主要国のエネルギー消費量 主要国の一次エネルギー消費量の推移を図9と図10に示した。図9は2010年における消費量の上位5ヶ国を示し、図10はこれに続いて消費量の多い9ヶ国を示している。永らく米国が世界最大のエネルギー消費国であったが、2010年に中国が米国を上回る消費国となった。主要国の中で中国の2000年以降の増加は歴史に類をみない速度であり、2000年から2010年までの10年間に2.3倍に増加している。これはこの期間に中国経済が高い経済成長率を維持し続けたこと、また、社会インフラ整備に向けて素材産業の生産規模が急速に拡大したことなどによる。 中国と米国に次いでロシアのエネルギー消費が多い。これは国土の大部分が寒冷地域にあり、冬季の暖房・給湯用のエネルギー需要が多いこと、国内に石油・天然ガスの資源が多いことなどによる。日本は1990年代半ば以降石油換算5億トン程度の水準で推移してきており、世界第4位のエネルギー消費国であったが、エネルギー消費量が最近急増しつつあるインドが2010年に日本を上回って第4位となった。 先進諸国の中でもドイツと英国では、エネルギー消費量が長期にわたってほとんど増えていない。これは、省エネルギーの他、エネルギー源として効率の悪い石炭から石油、天然ガスの利用にシフトしたことが大きな要因となっている。なお、原子力に大きくシフトしたフランスでは、上記のとおり原子力発電量を一次エネルギー量に換算するための効率を38%に固定しているため、ドイツ、英国と異なってエネルギー消費がかなり増大している。この他、先進諸国の中では米国、カナダ、イタリアの伸びが著しい。 他方、発展途上諸国は1965年時点では先進諸国に比べるときわめてエネルギー消費量が小さかったが、その後の増加は急速であり、韓国、ブラジルは2010年にはフランスと同程度の消費量になっている。また、イラン、サウジアラビアといった産油国のエネルギー消費量も急速に増えており、2010年には英国と同程度の水準に達している。 5.国内総生産(GDP)とエネルギー消費量 主要国の実質GDPを市場レートで米国ドルに換算した場合と購買力平価(PPP:本文末の注を参照)で米国ドルに換算した場合を、それぞれ図11及び図12に示した。米国の実質GDPの値は定義により両者で同一である。政府が厳格な為替管理を行っている中国では、市場レートでの元の価値を低く抑えているために市場レートで米国ドルに換算したGDPは小さいが、PPPで換算したGDPはすでに2002年に日本を上回っている。また、同様に市場レート換算のGDPが小さいインドも、PPP換算のGDPではすでに2008年にドイツを上回っている。このように、市場レート換算値とPPP換算とは大きく差があり、かつ、後者の方がより適正に国の経済規模を示していると考えられるので、以下にPPP換算GDPを用いて、エネルギー消費との関係を吟味する。 主要国のGDP当たりエネルギー消費量の推移(1971年〜2008年)を図13に示す。ここで、GDPはPPPで米国ドルに換算した実質GDPである。このグラフは単位量の経済価値の生産にどれだけのエネルギーを消費したかを表している。つまり、値が小さいほど、少ないエネルギーでより大きな経済価値を生産したことになり、経年的な数値の低下は、概ね産業構造の変化、省エネ技術の普及、輸送モードの変化等に起因するものである。他方、国別比較に際してはその他の要因、例えば気象条件や国土面積(人口密度)の大小も考慮する必要がある。 中国は第一次産業主体の1970年代にはGDP当たりエネルギー消費量がきわめて大きかったが、その後工業化の進展とともに急速にその値が低下してきた。しかし、2008年時点でもまだ先進諸国の2倍程度の水準にある。この要因としては、省エネ技術の普及の遅れだけでなく、産業の中で鉄鋼、セメント等のエネルギー多消費産業の比率が高く、第3次産業の比率が小さいことも挙げられる。ロシアはソ連邦崩壊後の大不況でGDP当たりエネルギー消費量が増加したが、その後の経済回復の中で1990年代末から急速に低下してきている。ただし、冬季の民生用エネルギー需要が大きいため、2008年時点でも中国よりもさらに大きな値となっている。 発展途上諸国の中では、インドとブラジルが中国とは異なり、1970年代前半から2008年までのGDP当たりエネルギー消費量が先進諸国と概ね同一水準である。この理由は十分に明確ではないが、これらの諸国は居住地域のほぼ全域が温暖で中国や高緯度に位置する先進諸国に比べて暖房用エネルギー需要が小さいことが要因の一つと推定される。さらに、現在に至るまで中国ほどに工業化しておらず、第一次産業が中心で非商業的なエネルギー利用が多い(これらは統計値に反映されていない)ことも理由と考えられる。 先進諸国の中では米国のGDP当たりエネルギー消費量が1970年代に特に大きかったが、産業構造の転換、省エネルギーの進展等により、2000年以降は他の先進諸国の水準に近づきつつある。これまでは特に輸送部門における自動車利用がエネルギー多消費の要因であったが、ガソリン価格の高騰、二酸化炭素排出削減への取り組みの中で小型の低燃費車への移行、公共輸送機関の整備が徐々に進み、エネルギー消費量の低減に寄与している。西欧諸国と日本は1970年代にはGDP当たりエネルギー消費量がやや高めであったが1990年代半ば頃までにかなり低下し、その水準を維持している。その主たる要因として産業構造の転換と省エネルギーの進展が挙げられる。 [注] 購買力平価:Purchasing Power Parities(PPPと略記)の日本語訳で、国家間の通貨の交換比率を財・サービスの価格の違いを反映して表示した指標をいう。OECD、IMF、世界銀行等で推定が行われている。このうちOECDはGDPを構成する商品・サービスを対象とした価格調査を3年ごとに実施し、これに基づいて米国ドルを基準とした購買力平価(米国ドルと等しい購買力を持つ各国の通貨量)を推計している。これはGDPを多国間で比較するためには、市場レートで換算するよりもPPPで換算した方が経済規模の実態により近い評価が可能になるためである。ただ、比較対象とする財・サービスの数には実務的な限界があり、また、一国内でも都市部と農村部での物価の違いがあるなど必ずしも「一物一価」ではないため、PPPの値には元々かなりの幅が生じ得る点に注意が必要である。 (前回更新:2004年2月) <図/表> 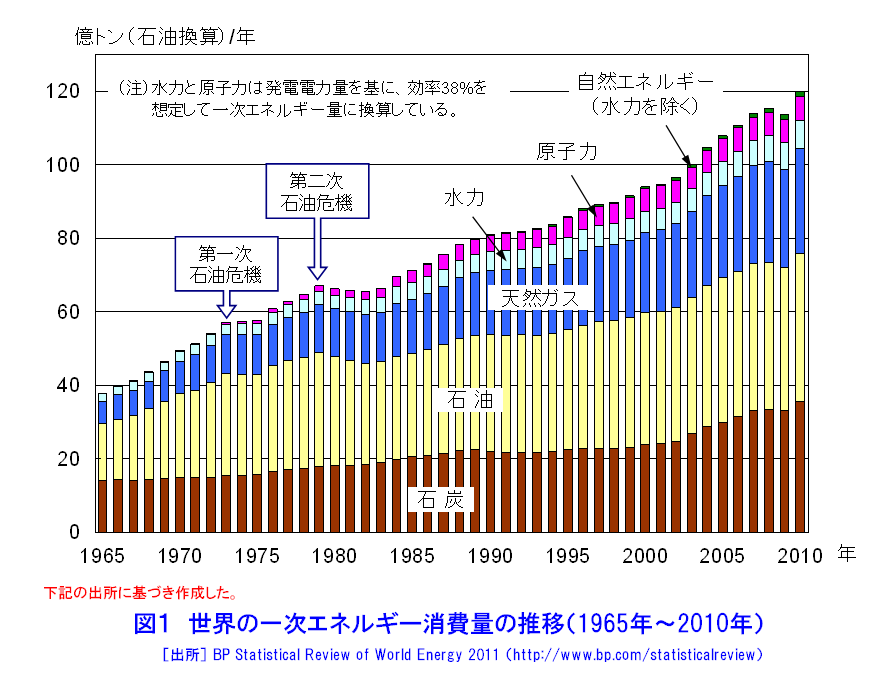
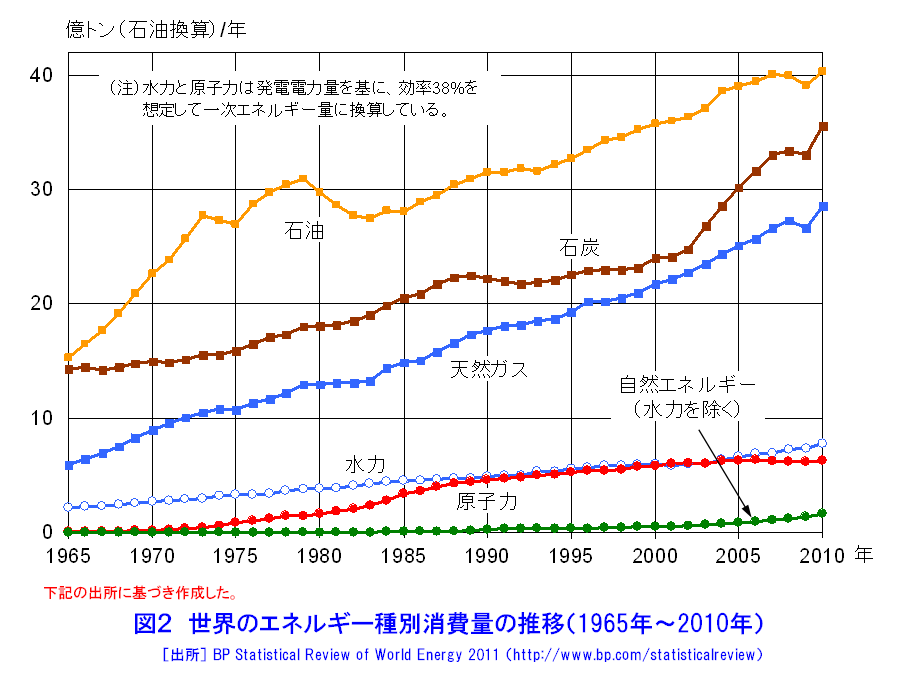
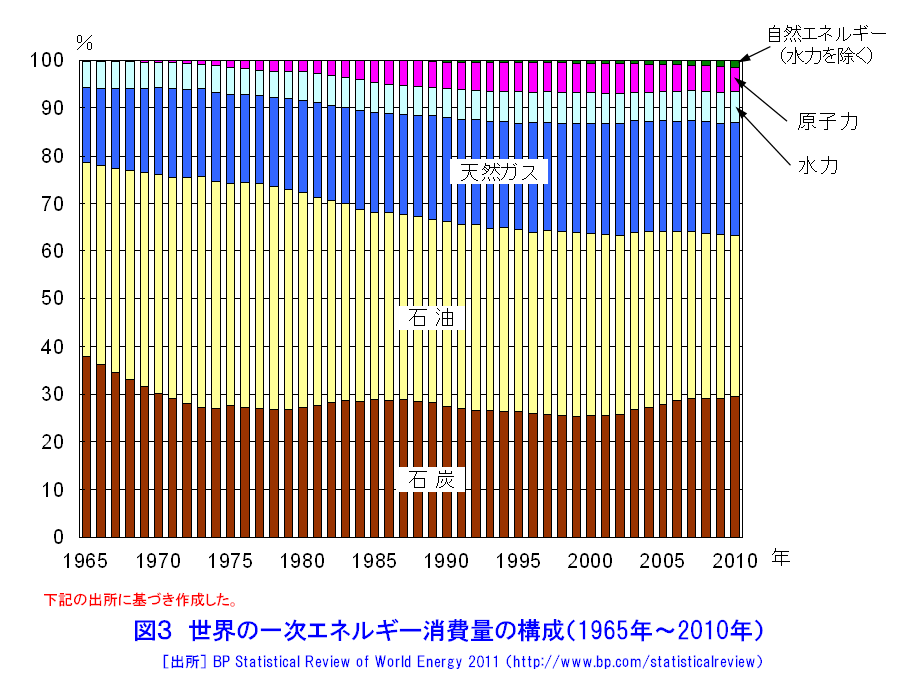
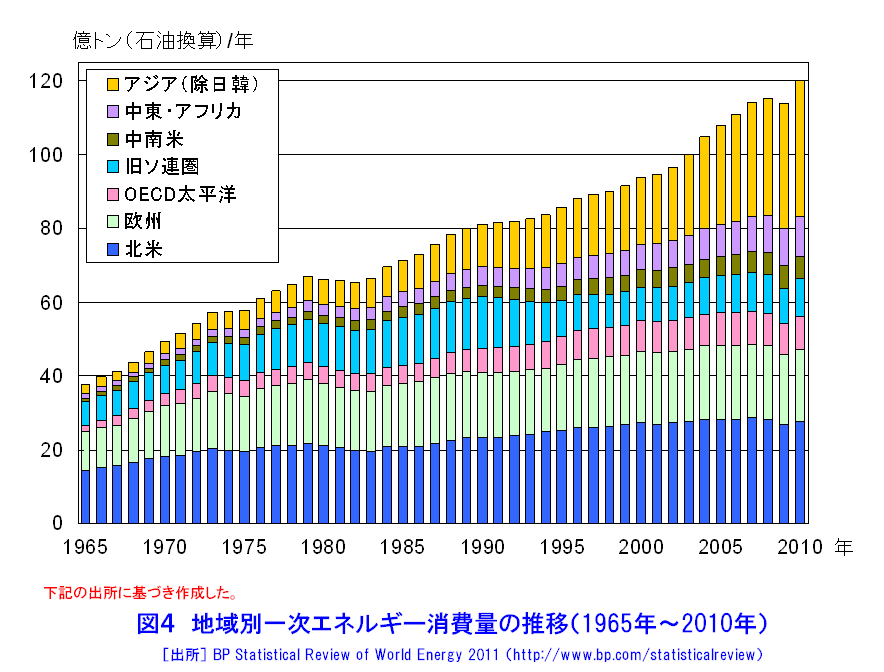
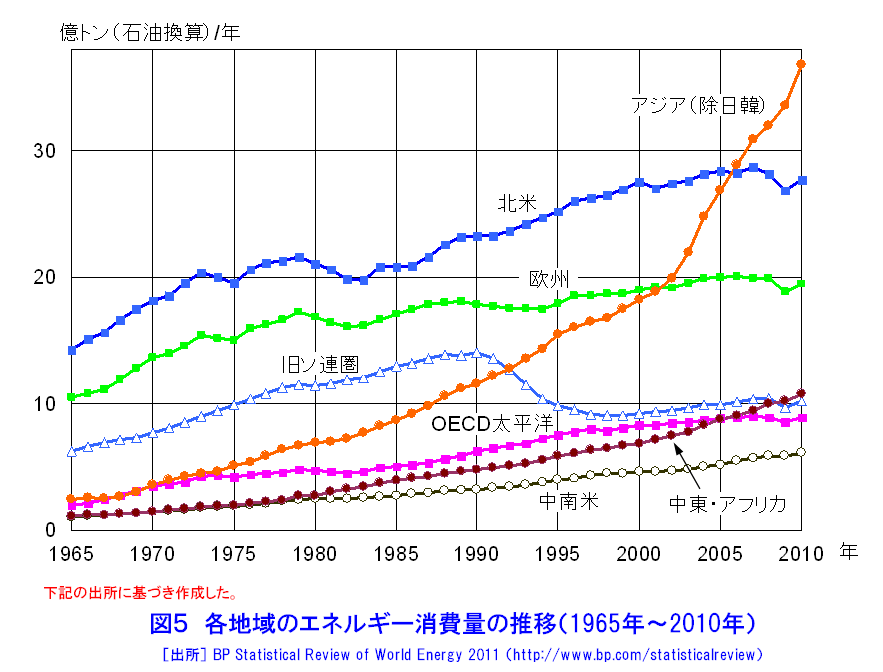
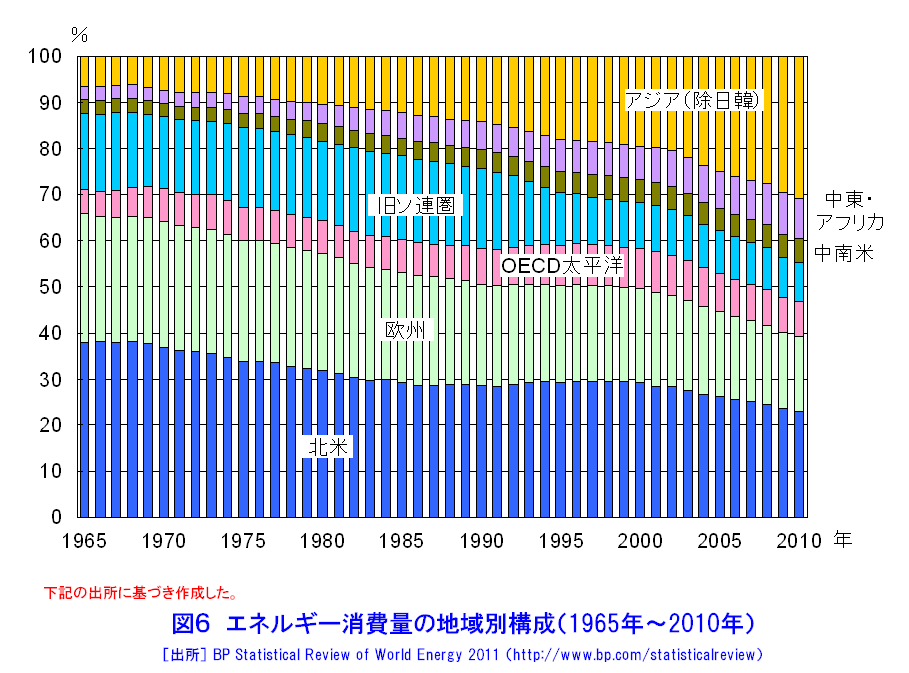
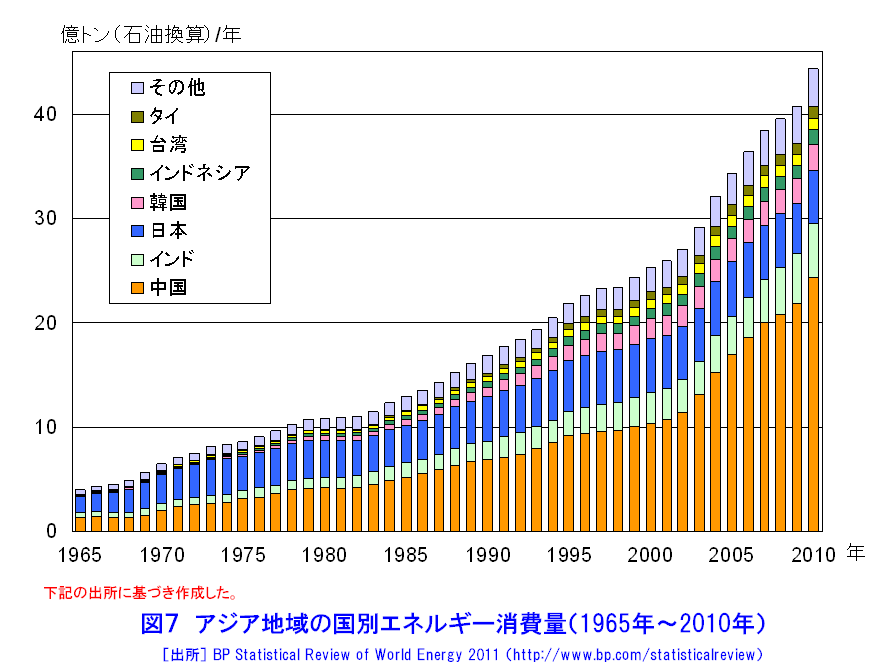
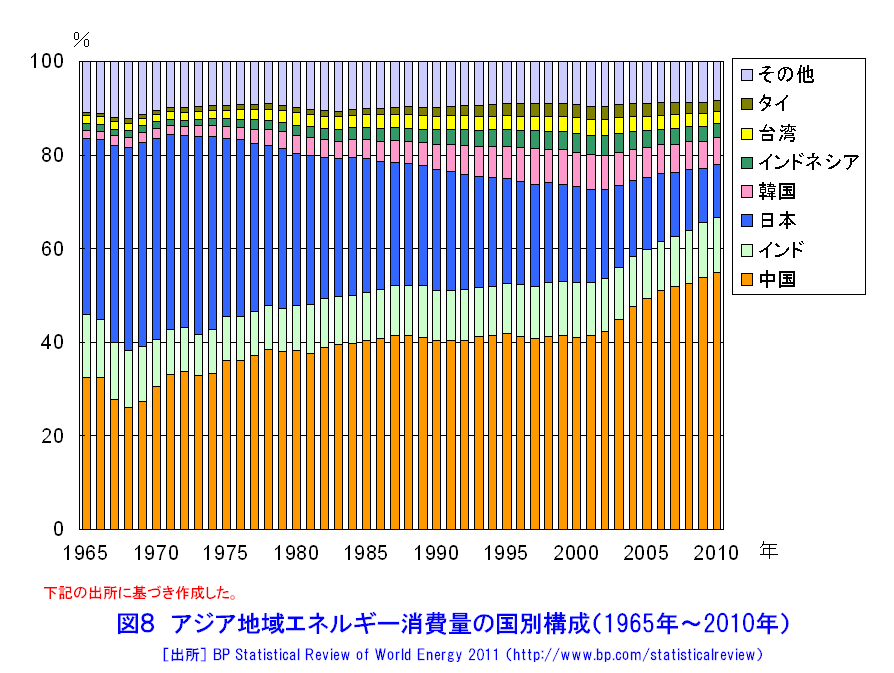
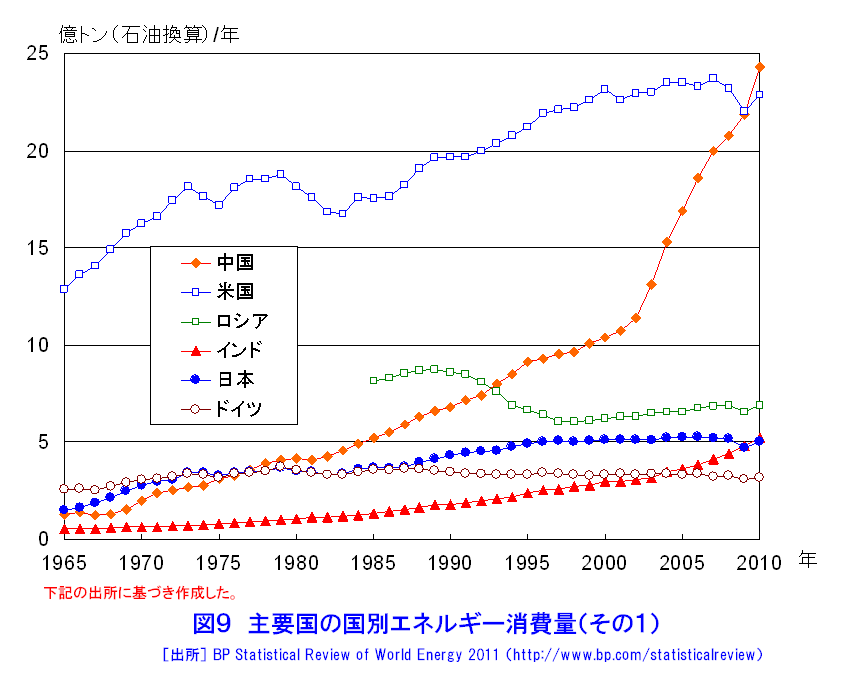
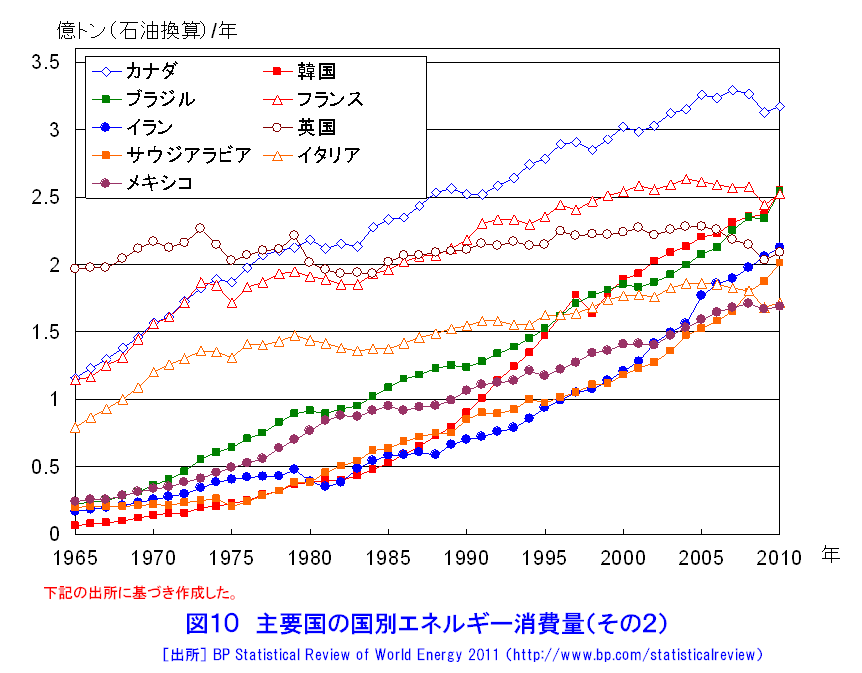
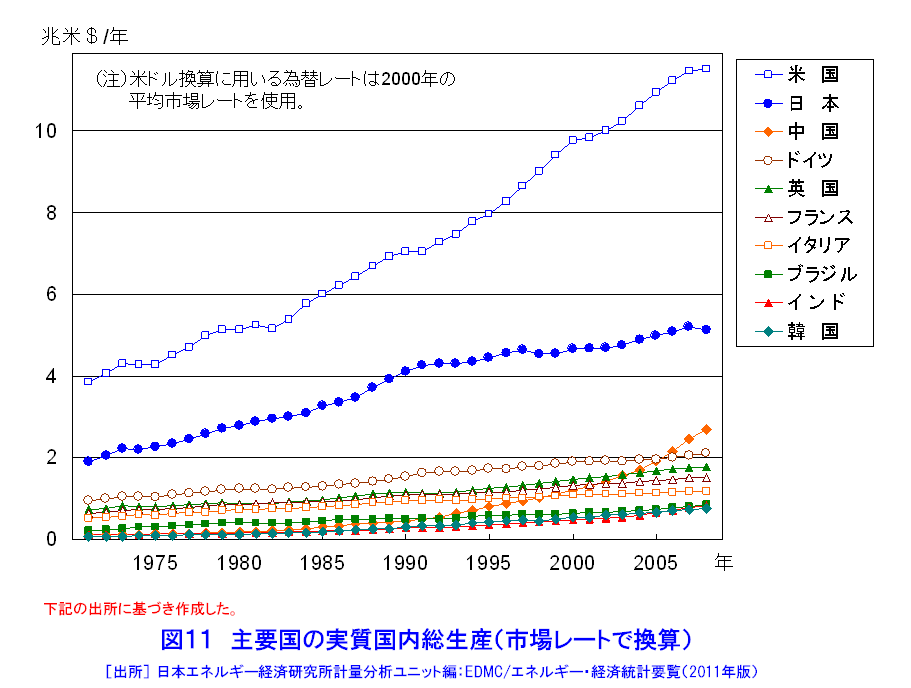
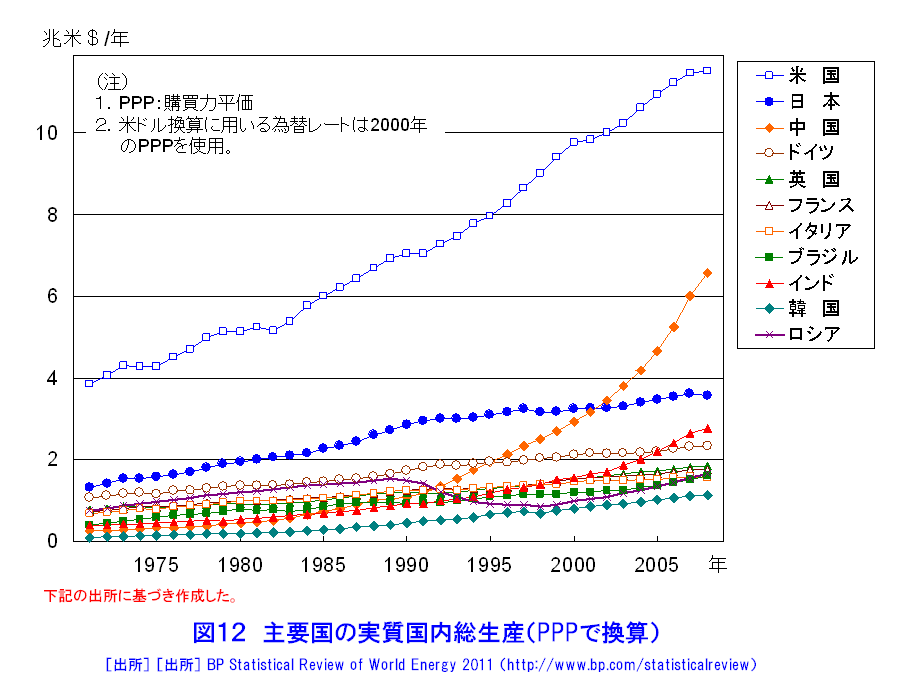
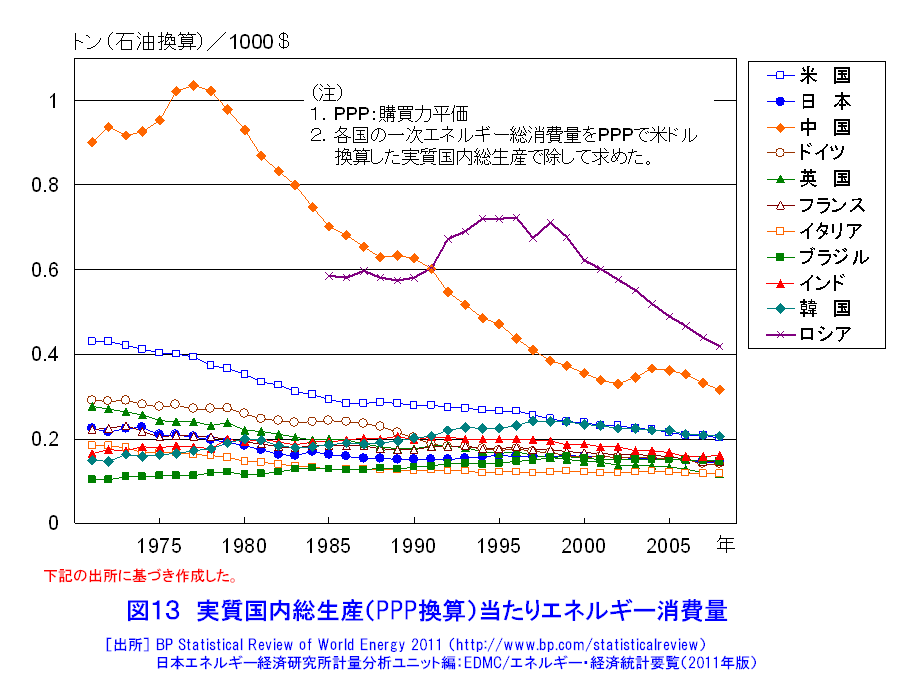
<関連タイトル> 主要国の省エネルギー政策 (01-06-01-03) 国際エネルギー情勢と今後の展望 (01-07-02-01) 主要先進国のエネルギー需要の動向 (01-07-02-08) 国別一人当たりの一次エネルギー消費量 (01-07-03-03) 世界のエネルギー消費の展望 (01-07-03-05) <参考文献> (1)BP Statistical Review of World Energy 2011,( http://www.bp.com/statisticalreview ) (2)日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット編:EDMC/エネルギー・経済統計要覧(2011年版) (3)OECD:Purchasing power parities (PPPs) and exchange rates , (http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE4)
|

