|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
2011年3月の東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機に、原子力施設等の安全規制と災害対策に係るそれまでの体制が抜本的に見直され、原子力規制を一元的に担う組織として原子力規制委員会が発足するとともに、原子力災害対策特別措置法(原災法)が改定された。改定原災法は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(以下、「原子力災害対策」)の円滑な実施を確保するための指針として、原子力規制委員会が原子力災害対策指針を定めることを規定しており、また、この指針には、災害対策として実施すべきこと、その実施体制、その対策を重点的に実施する区域等を定めて公開することを求めている。指針の対象となるのは、原子力事業者、国の原子力災害対策本部、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関など原子力の防災に関わる広範囲の組織である。いわば、オンサイト(事業者施設とその敷地内)とそれを取り巻くオフサイト(周辺地域)の関係者・関係機関が、原子力災害対策の各局面、特に「緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の影響を最小限に抑える防護措置を確実なものとする」ためには、どのような具体的な判断・行動・処置をとるのが望ましいかを示したものが指針である。本稿では、異常事態発生時に事故進展シナリオ(初期対応段階、中期対応段階、復旧段階)に対応して、オンサイトで採るべき措置を中心に解説する。なお、オフサイトにおける平常時の対応(準備段階)としての原子力災害予防対策の内容についてはATOMICAデータ「原子力施設等による災害の対策について(原子力災害対策指針-その2)」にまとめた。 <更新年月> 2014年03月
<本文>
1.原子力災害対策指針決定の経緯 昭和54年(1979年)3月の米国のTMI事故を契機として、我が国でも原子力災害特有の事象に着目し、原子力発電所等の周辺における防災活動がより円滑に実施されるように技術的、専門的事項について、原子力安全委員会の専門部会で検討がなされた。この検討結果は昭和55年(1980年)6月に原子力安全委員会により「防災指針」として決定された。さらに平成11年(1999年)9月30日のJCOウラン加工施設において、日本で初めて住民避難等が必要となるような臨界事故が発生し、これを受けて原子力災害対策特別措置法(原災法)が制定された。 これにより、防災の対象施設が発電所のみならず原子力施設全般に広がり、また、原子力事業者の責務が明確化されたことから、防災指針の表題も変更され、その後もより実効性のある内容を目指して、数度にわたって修正が行われた。平成18年(2006年)にはIAEA等の防災に関するガイドラインを参考に国際的な基準を取り込むべく本格的な改訂作業に着手したが、関係機関との調整が難航して作業が進まないまま、平成23年(2011年)3月の東京電力福島第一発電所の事故を迎えることになった(以下では、この時点までの防災指針を「旧防災指針」と呼ぶ)。 この事故を契機に、原子力施設等の安全規制と災害対策に係るそれまでの体制が抜本的に見直され、原子力規制を一元的に担う組織として原子力規制委員会が発足するとともに、原子力災害対策特別措置法(原災法)が改定された。改定原災法は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(以下、「原子力災害対策」)の円滑な実施を確保するための指針として、原子力災害対策指針を定めること、また、この指針の中に災害対策として実施すべきこと、その実施体制、その対策を重点的に実施する区域等を定めて公開することを求めている。指針の対象となるのは、原子力事業者、国の原子力災害対策本部、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関など原子力の防災に関わる広範囲の組織である。 福島第一原子力発電所事故はJCO臨界事故と比較して桁外れの規模の汚染・放射線被ばくと住民避難を伴い、結果的に旧防災指針の内容の不備が多面的にかつ顕著に認められた。このため原子力安全委員会は震災直後の平成23年(2011年)7月から、防災指針検討ワーキンググループにおいて国際基準に沿った形のものを導入すべく急遽検討を進め、一部課題を残して平成24年(2012年)3月に中間報告として暫定案をまとめた。原子力安全委員会廃止後に平成24年(2012年)9月に発足した原子力規制委員会はこの暫定案を継承し、同年10月に原子力災害対策指針(初版)として策定した。この初版に対し、福島第一原子力発電所事故に対する国会・政府・民間の各事故調査委員会報告書による指摘事項を考慮しながら本格的な検討が重ねられ、平成25年2月27日に第1次改訂、6月5日に第2次改訂、9月5日に第3次改訂が行われ、詳細な課題の抽出と対策が順次提示されつつある。 こうした防災対策の抜本的見直しともに、安全規制に係る組織と法令も見直されたが、本来、安全規制と防災は安全確保の仕組みとして「対を成すもの」、「車の両輪」となるべきものである。すなわち、安全規制は、人知を尽くして科学的・合理的に事故が起こりにくい設計を原子力施設に求めるプロセスであり、防災は、それでも事故に至った場合において早急に事態を鎮静化するとともに近隣住民を放射線から防護することを求めるプロセスである。原子力法体系の中での原子力災害対策指針の位置づけを図1に、また、原子力災害対策への取り組み体制を図2に示した。 改定原災法に基づく原子力緊急事態への対応は、準備段階、初期対応段階、中期対応段階、復旧段階に区分される。以下の章で、一連の事故進展シナリオ(初期対応段階、中期対応段階、復旧段階)に対応する形で、原子力災害対策指針(参考文献1)の内容を整理する。なお、オフサイトにおいて最も大切な平常時の対応(準備段階)としての原子力災害予防対策の内容については、ATOMICAデータ「原子力施設等による災害の対策について(原子力災害対策指針-その2)(11-03-06-05)」にまとめた。 2.事故の発生と施設外への影響進展 内部起因あるいは外部起因の異常状態が原子力施設(以下、単に施設という)内に出現し、それを各種の検出器を通じて認知した場合、その異常の原因を判断して、事業者は直ちに所要の対応を行う。この対応が有効でない場合には、異常状態はさらに深刻化する。異常状態への対策は多重に用意されているが、そうした対策を実行しても管理区域外への放射線の漏れや放射能物質の放出に至る(ただし敷地内に留まる)場合がある。さらに異常事態が進展すると、排気筒など(気体の場合)、排水口など(液体の場合)を経由して敷地外部へ、放射性物質の放出や放射線が漏れる段階となる。これらの放射線の検出は、まず建物の中に多数置かれたエリアモニタやダストモニタ、最終的には排気筒、排水口モニタで一括検知される。臨界状態の発生など、場合によっては中性子線モニタなどの検出器で直接捉えられる場合もある。 一方、建物外の敷地及び周辺には事業者の管理するモニタリングポスト(MP)が配置され、さらに敷地周辺から県の管理する複数個のMPが市町村の主要なポイントに設置されており(全国で約300台)、これらの検出器が基準値を超える放射線を検知した場合には、放射性物質が大気中に拡散している状況を示しており、近隣住民の避難が必要となる。住民防護の観点から重要なことは、敷地外のMPが反応するまでの所要時間は、敷地内で発生した異常や事故の種類、場所と採られた対策の内容に大きく依存する点である。核暴走、爆発、(航空機等の)衝突などに起因する事象の場合には所要時間が著しく短くなる可能性がある。 また、一旦放射能放出が始まるとある程度の時間、放出が継続する点も見逃せない。例えば、TMI事故では最初のトラブルが検知されてから約52時間後に敷地外で放射能が検出され、放出継続は約18日(参考文献2)、JCO臨界事故での放出継続は約20時間(参考文献3)、チェルノブイリ事故での放出継続は約11日(参考文献4)、そして複数号機が同時被災した福島第一原子力発電所事故では約14時間後に放射能が検出され、放出継続は約18日(参考文献5)とされている。換言すれば、施設内での異常・事故の状況をいち早く把握し、その情報を即座に地元住民を含む関係者が共有すれば、必要な対策・行動を開始するまでの時間的余裕が大きくなることを示している。このため、指針では以下のように初期対応について定めている。 2.1 緊急事態区分とEALの導入・設定 IAEA等が定める防護措置の枠組みの考え方を踏まえて、緊急事態の初期対応段階を3つに区分し、各区分を判断する基準となる施設の状況を緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)として整理した(参考文献6)。緊急事態の3つの区分とは、1)警戒事態(AL:Alert)、2)施設敷地緊急事態(SE:Site Emergency)、3)全面緊急事態(GE:General Emergency)であり、それぞれに対応する緊急時活動レベルをEAL1、EAL2、EAL3と呼んでいる(表1)。 事業者は施設ごとにその異常・事故について予め綿密に分析し、緊急事態の発生時には当該施設のEALに基づいて緊急事態の区分を判断し、通報基準(後述)に基づいて国や地方自治体に即座に報告せねばならない。国はその内容を確認し、適切な対策を発令する。我が国でEALを初めて採用するにあたり、原子力規制委員会は国内外の調査及び関係者との打合せを通じ、発電炉に関してBWR、PWR、FBR、ATR等の典型的なEALの例示を行った(表2-1、表2-2、表2-3、表3-1、表3-2、表3-3、表4-1、表4-2、表4-3、表5-1、表5-2、表5-3、表6)。 なお、緊急事態の区分のうち、警戒事態(AL)は、早い段階で施設の異常を認知し、体制構築や情報収集を行い住民防護のための準備を開始するものである。ただし、「早期」と「確実」は相反する要素を含んでおり、いわゆる「空撃ち」リスクがあることに留意が必要である。一方、施設敷地緊急事態(SE)は概ね従前の原災法第10条相当の事象発生に、全面緊急事態(GE)は概ね従前の原災法第15条相当の事象発生に相当するものである。 上記のとおり、事業者は保有する施設に応じたEALを作成し、原子力事業者防災業務計画の中に記述せねばならない(原災法に基づき原子力事業者が作成すべき事業者防災業務計画等に関する省令の一部を改正する命令等による;施行日平成25年12月1日)。また、その内容は原子力規制委員会によって精査され、必要に応じて修正が求められる。具体的に発電事業者が施行日までに作成した詳しいEALは、原子力規制庁のウェブサイトにマトリックス形式の表(縦軸にAL/SE/GEの固有番号、横軸に判断基準/測定パラメータや物理的な意味を解説・定義/備考)で転載されている。(参考文献7) 2.1 異常事態の通報基準及び緊急事態判断基準(EAL)の例 新規制基準に適合した施設の「通報とその判断基準」は表2-1〜表6にまとめられているが、この中で主要なものを以下に示す(ただし、除外規定等も定められているため、詳しくは、原子力規制委員会の基本例示あるいは当該事業者の定めるEALを参照のこと)。 (1)警戒事態(AL)の通報基準:1)原子炉から一定以上の冷却水の漏洩が発生し、定められた時間内に対処出来ないとき、2)原子炉給水機能が全て喪失したとき、3)原子炉残留熱除熱機能の一部が喪失したとき、4)外部電源喪失が3時間以上、あるいは非常用交流母線への電源供給が15分以上1種類のみとなった場合、5)使用済燃料プールの水位が一定値以下となった場合、他11〜17種類(炉型依存)の条件に適合する場合には事業者は速やかに、原子力規制委員会、当該地方自治体等に連絡する。 (2)施設緊急事態(SE)の通報基準:1)原子力事業所の敷地境界付近において、空間放射線量率が1地点で5μSv/h以上検出されたとき、2)排気筒等経由で拡散した後、敷地境界付近において5μSv/h以上で10分継続検出されたとき、3)火災、爆発等が生じ、境界付近において、50μSv/h以上を10分継続検出されたとき、4)原子炉から冷却水が漏洩し、非常用炉心冷却系が作動したとき、5)全ての交流母線からの電源供給が30分間以上喪失したとき、6)使用済燃料プールの水位を維持出来ない場合、又はその状況下で水位が不明のとき、他13〜15種類(炉型依存)の条件に適合する場合には事業者は速やかに、原災法10条相当事象の発生として、国、地方公共団体等関係機関等に連絡する。 (3)全面緊急事態(GE)の通報基準:1)原子力事業所の境界付近において、空間放射線量率が1地点で5μSv/h以上が10分間以上、又は2地点以上で同時に5μSv/h以上検出されたとき、2)火災、爆発等が生じ、管理区域外の場所で5mSv/h以上となったとき、3)原子炉心の外部で臨界状態となったとき、4)全ての交流母線からの電源供給が60分以上喪失したとき、5)使用済燃料プールの水位が2m以下となったとき、又はその状況下で水位が不明のとき、6)非常停止が必要な時に制御棒の挿入による原子炉の停止ができない、又は確認できないとき、他12〜14種類(炉形依存)の条件に適合する場合には事業者は速やかに、原災法15条相当事象の発生として、国、地方公共団体等関係機関に連絡する(現状では書式は10条を流用)。 施設外への放射能の大量放出がほぼ確定的となる全面緊急事態(GE)に至った後も、事業者は、1)施設の状況、2)放射性物質の放出状況(量、組成、継続時間等)及び敷地境界等における空間放射線量、3)今後の見通しについても所定の書式(原災法25条)で報告を行う。 したがって、平常時に事業者が作成する防災業務計画の内容とこれに基づく防災訓練(EAL通報訓練を含む)は防災上極めて重要であり、原子力規制委員会はその内容提示と訓練結果についての報告を求めている。 3.教育・訓練の実施と安全文化の醸成 まず、事故の責任は第一義的に事業者にあることを十分に認識し、その上で、原子力災害対策を円滑かつ有効に実施するためには、事業者内の防災業務関係者に対して原子力災害対策に関する教育及び訓練を行うことが重要であり、この防災業務関係者は、常時、各種の緊急対応の発生を想定しつつ自らの業務に習熟することが必要である。 また、下記の教育及び訓練を通じて、組織の風土として「安全文化」を醸成し、これを維持・向上させていく必要がある。その際、原子力事業者においては経営陣から現場の職員及び協力会社等の関係者の全てが、また規制機関においては全職員が、安全を最優先することを深く認識し、「安全文化」への理解とその維持・向上に努める姿勢を育成するべきである。なお、事業者と規制側は、共通の目的である安全確保のために、「フランクでオープンでありながらもフォーマル」な関係(参考文献8)を築く過程でお互いの「安全文化」の醸成・維持に努めなければならない。 1)教育について 防災業務関係者に対して、それぞれの責任範囲、任務内容、手順等を理解させ、特に、原子力発電所施設等においては現場の職員全てに、緊急事態の通報及びそれに伴う措置に関する対応手順を教えることが必要である。 また、これらの教育については、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人放射線医学総合研究所等の関係指定公共機関が実施している原子力防災に係る研修コースを活用することや、原子力災害以外の分野における緊急事態への対応や他国での実施体制等を学ぶことが有効である。 2)訓練について 訓練の目的は、想定した状況と実際のオペレーションとの違いを認識し、実効性の観点から防災体制の課題を抽出することである。様々な事故を考慮し、複合災害や過酷事象、広域汚染・放出の長期化等の状況を想定して、可能な限り実地に近い形の多面的な訓練を計画することが重要である。 訓練に当たっては、個々の防災活動の熟練度を高めていくとともに、PAZ及びUPZ内の住民等も含めた関係者間の連携を確認するための総合的な防災訓練を行うことも必要である。また、訓練の結果を評価し、防災計画、施設・設備・機器の機能、対策の準備状況、対応者の判断能力等の全体的な確認と補充・改善を図ることが必要である。なお、原子力災害と一般災害との共通性を踏まえ、訓練では一般の防災対策との連携も留意すべきである。 4.核燃料物質等の輸送時の防災対策 原子力施設外における核燃料物質等の輸送時における事故により原子力災害が発生する場合も考えられるため、同様に対策を講じる必要がある。事故発生場所があらかじめ特定されないこと等の輸送の特殊性を踏まえ、原子力事業者及び原子力事業者から運搬を委託された者並びに国が主体的に防災対策を行う。 <図/表> 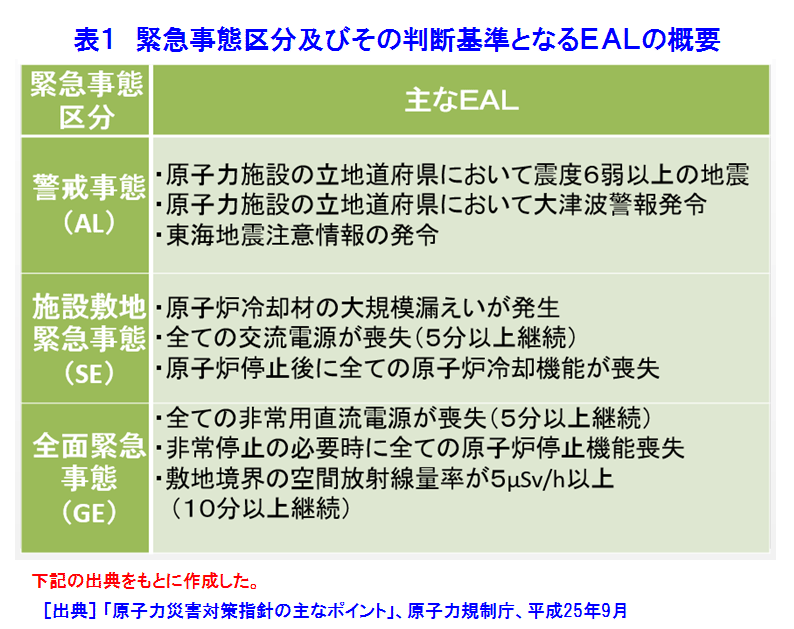
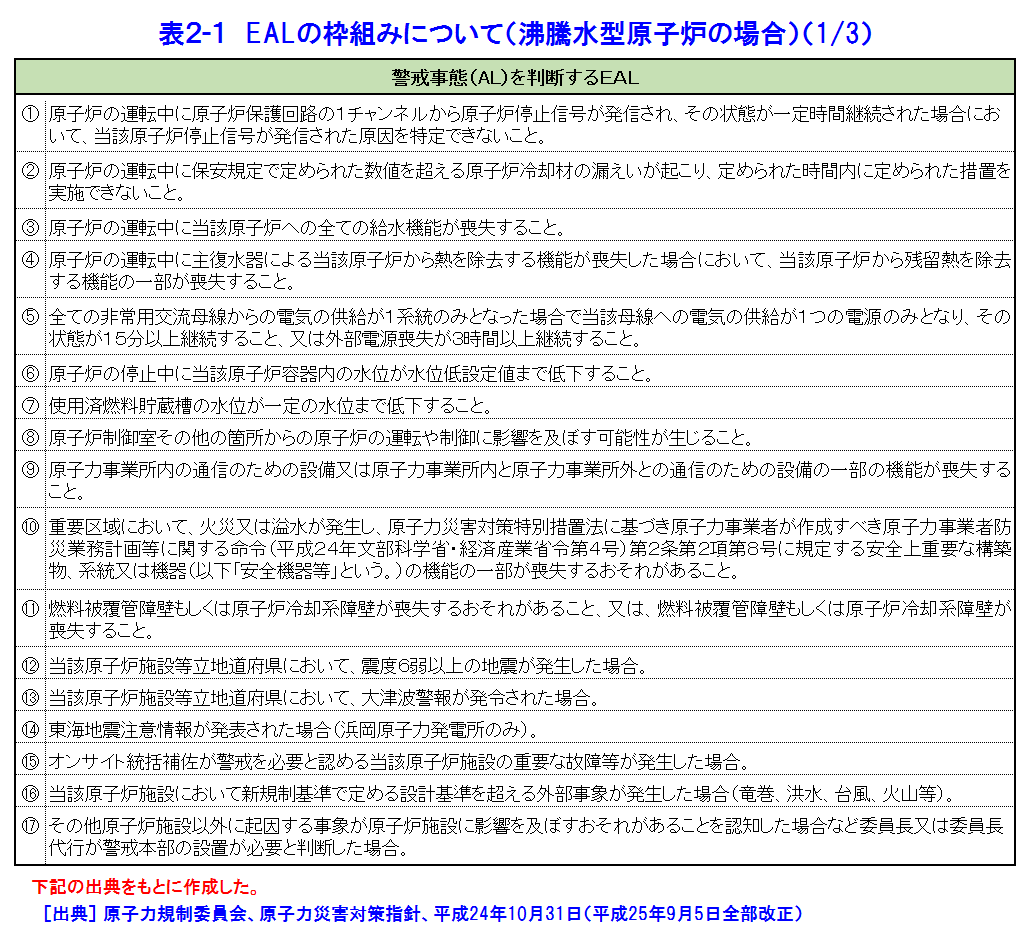
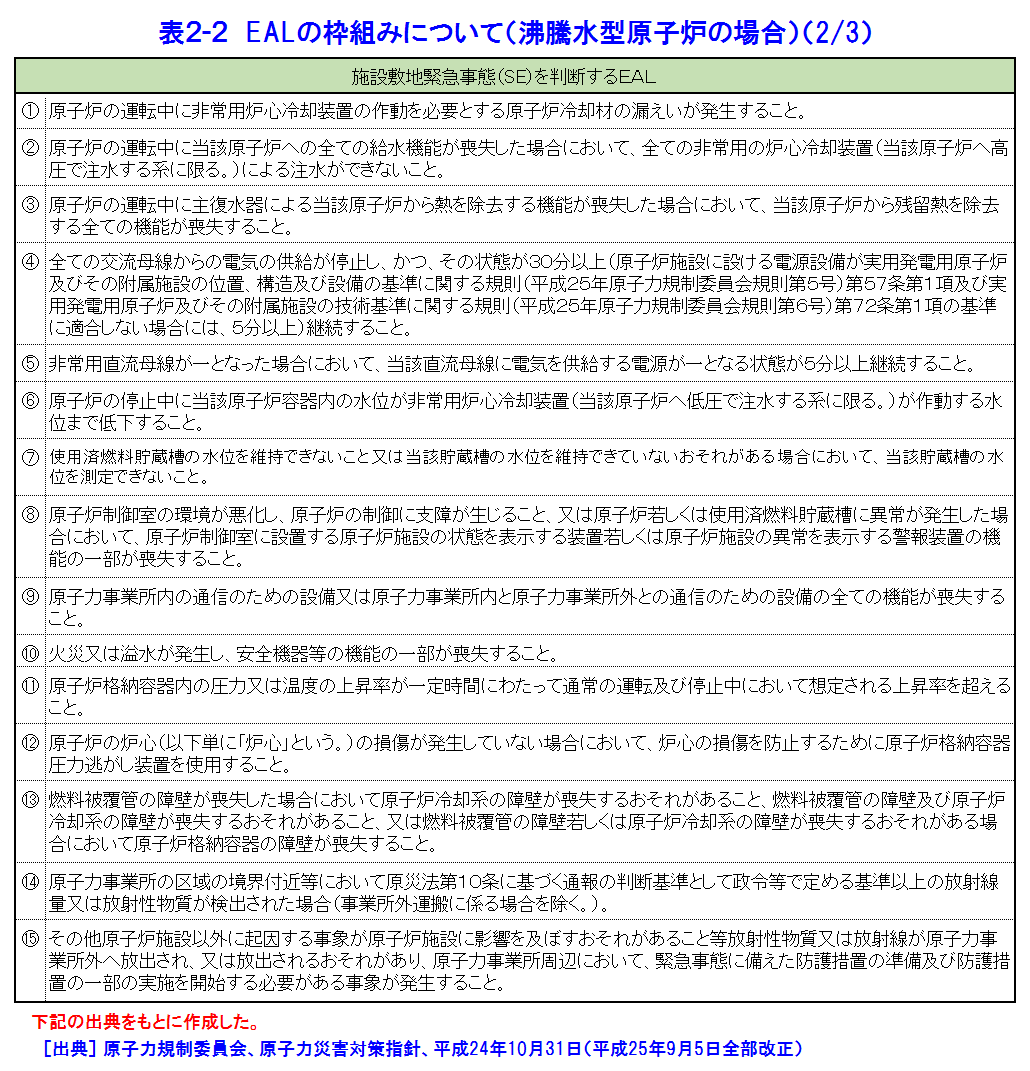
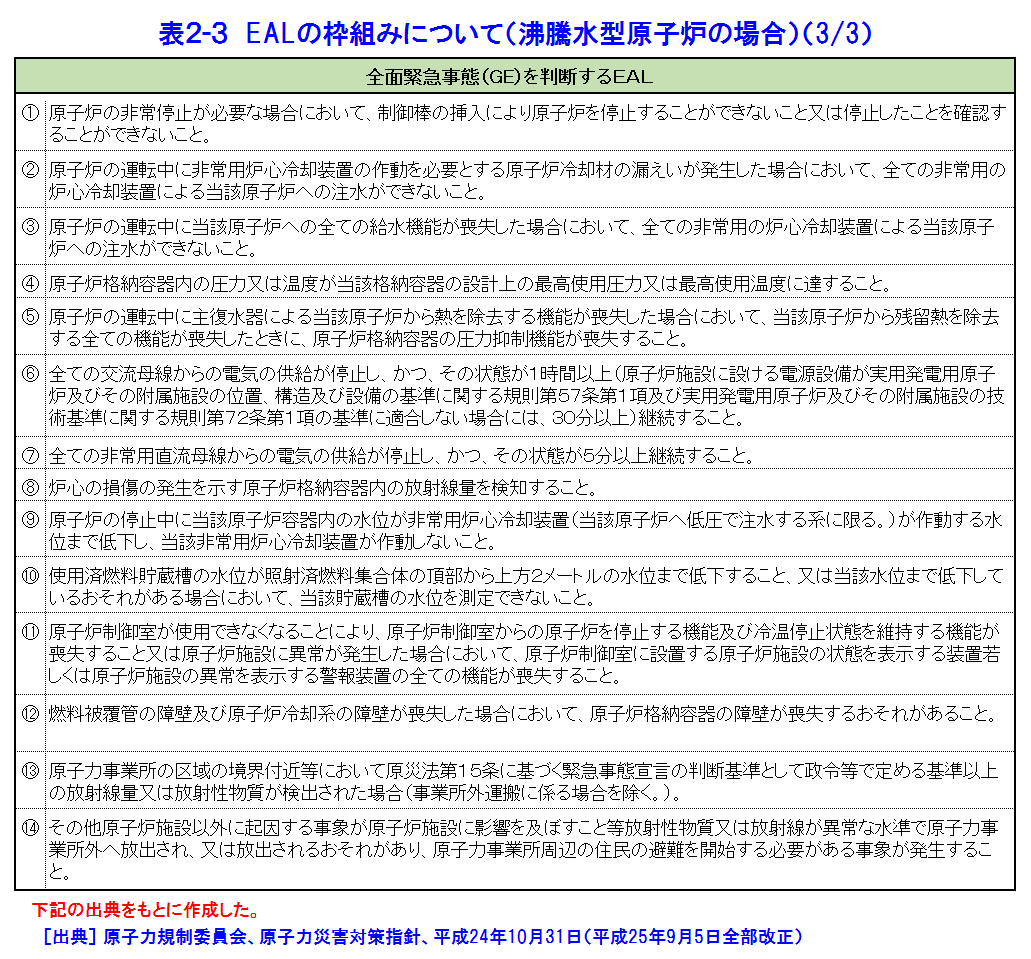
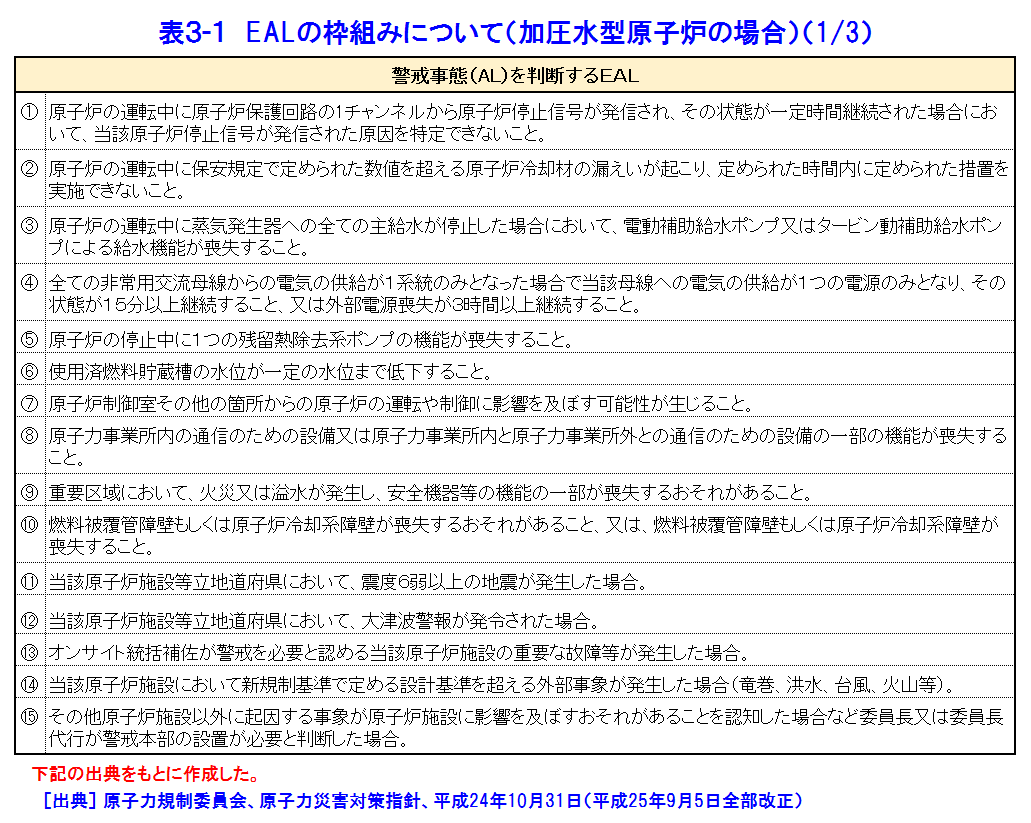
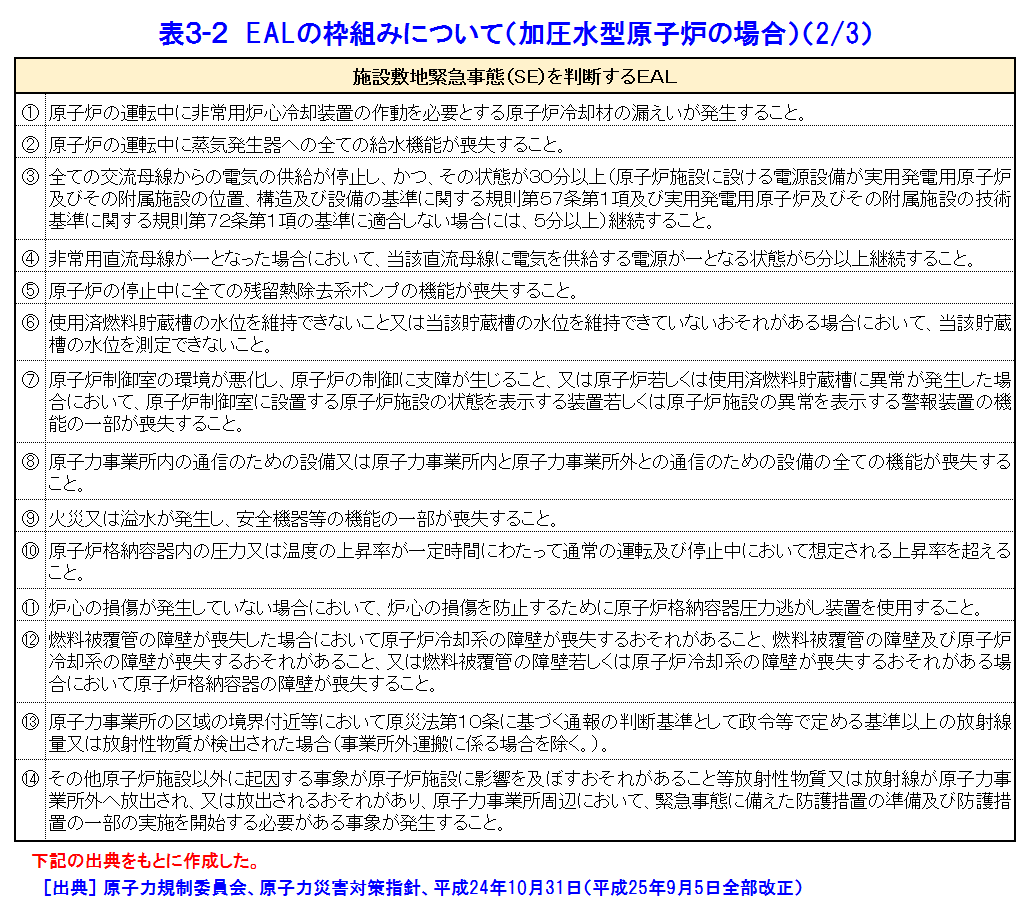
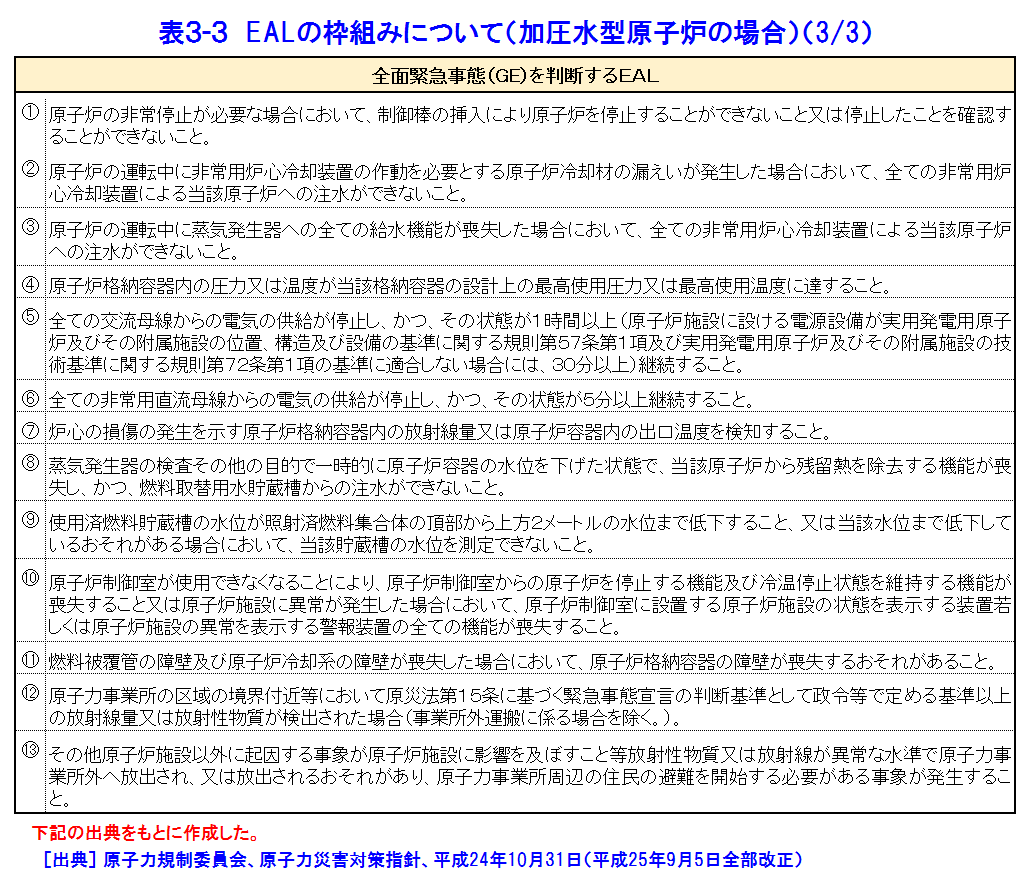
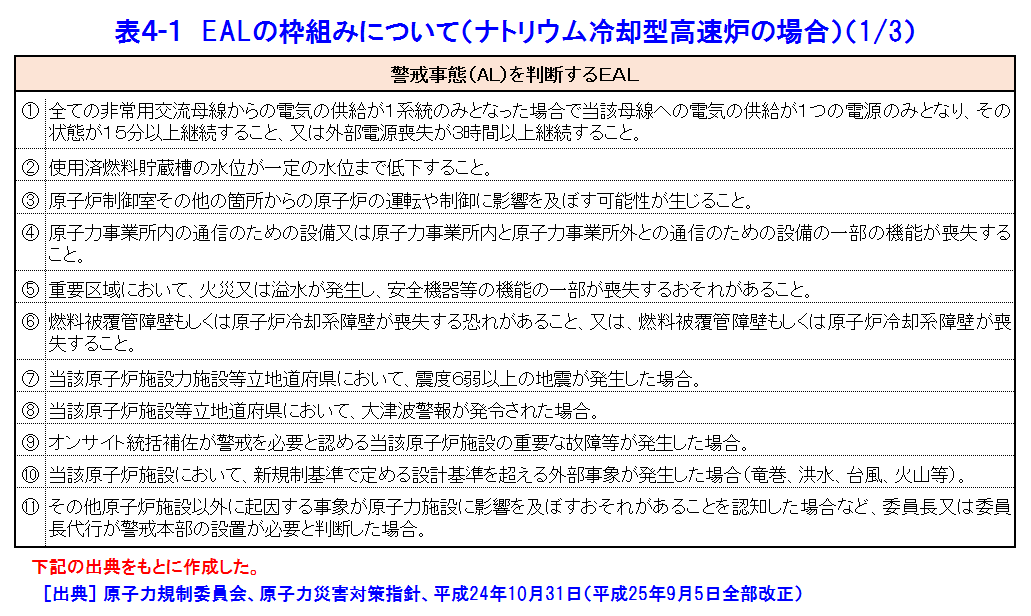
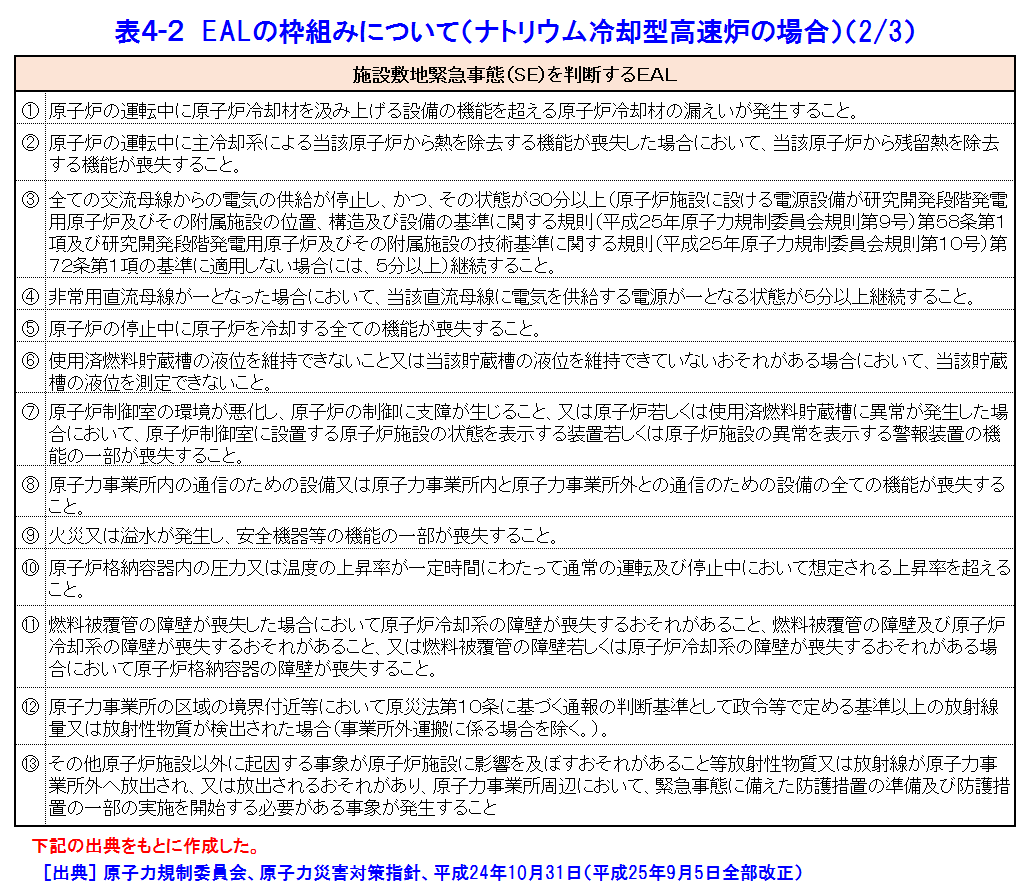
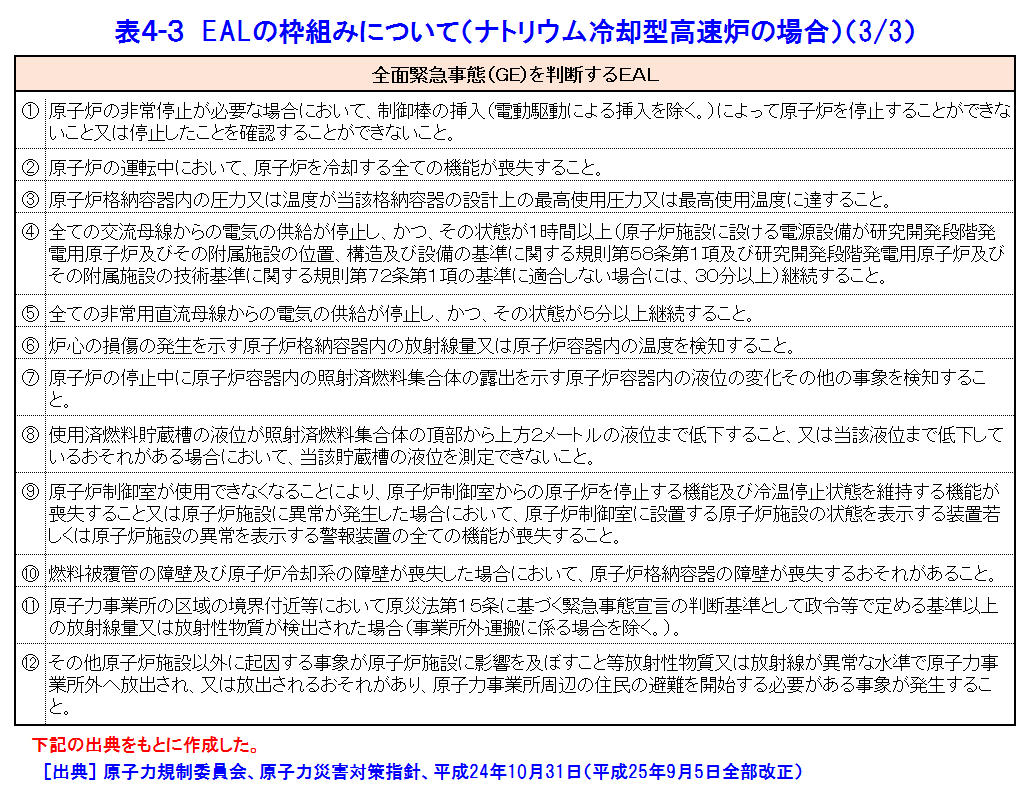
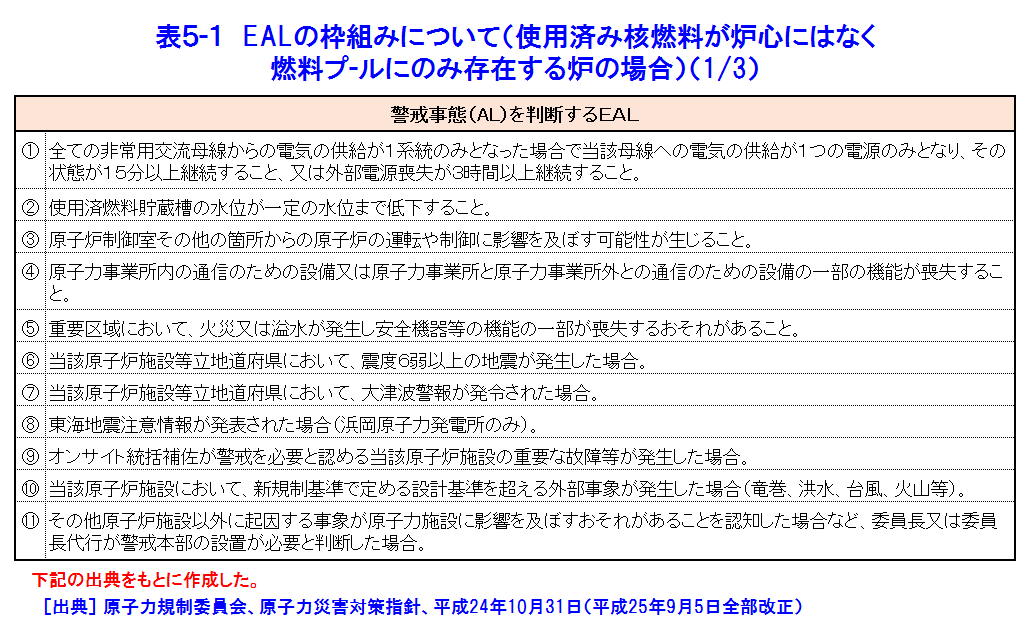
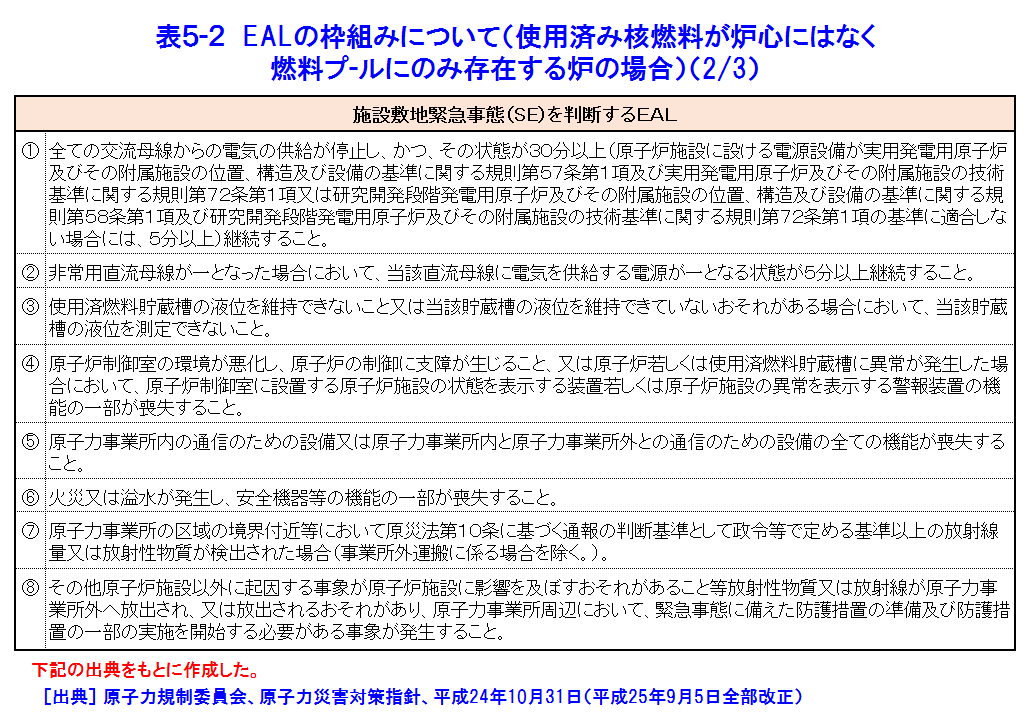
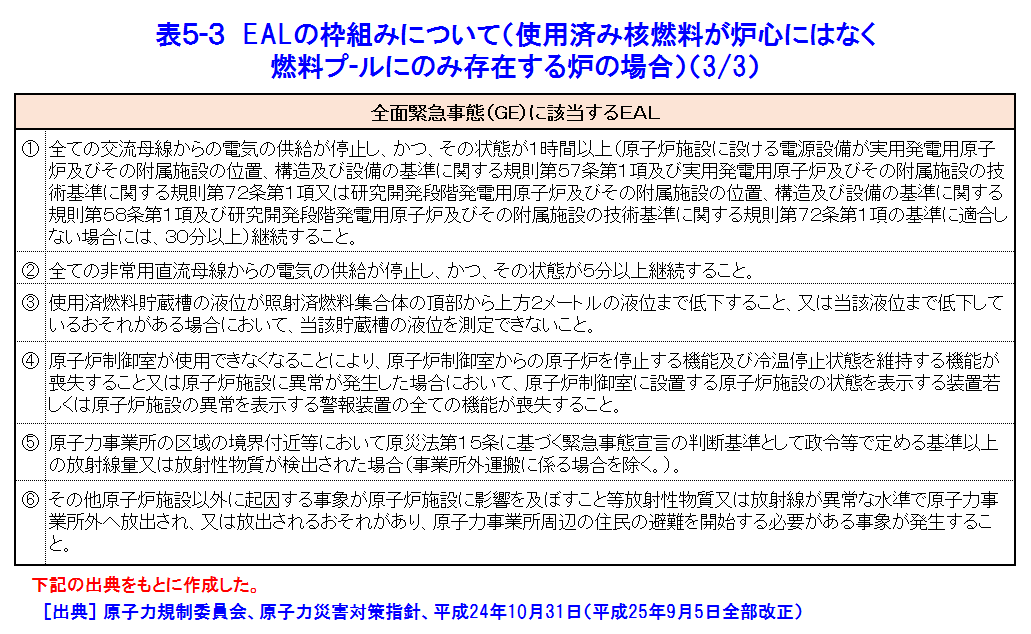
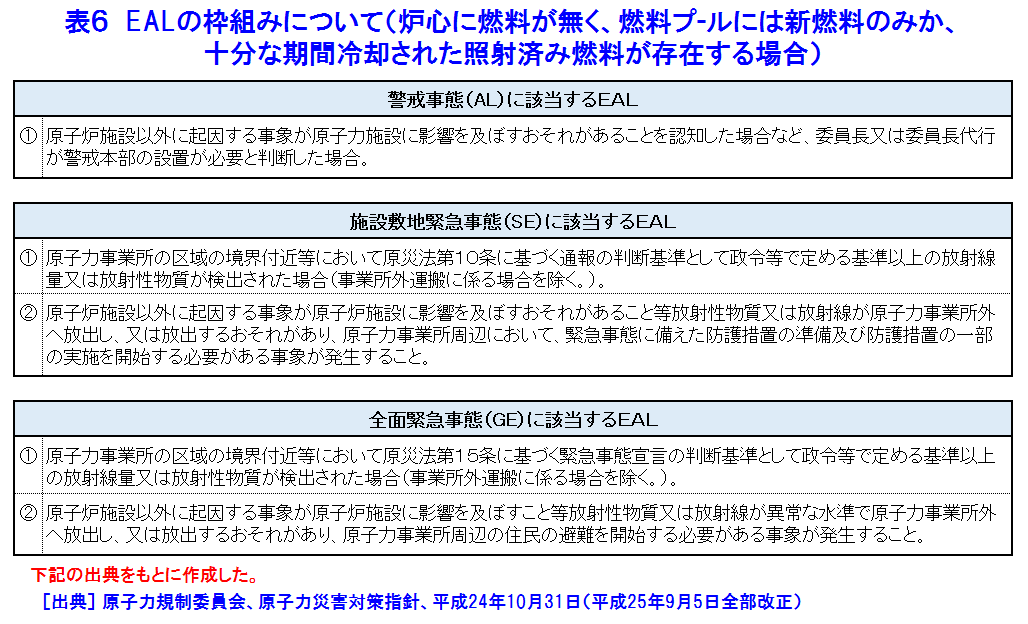
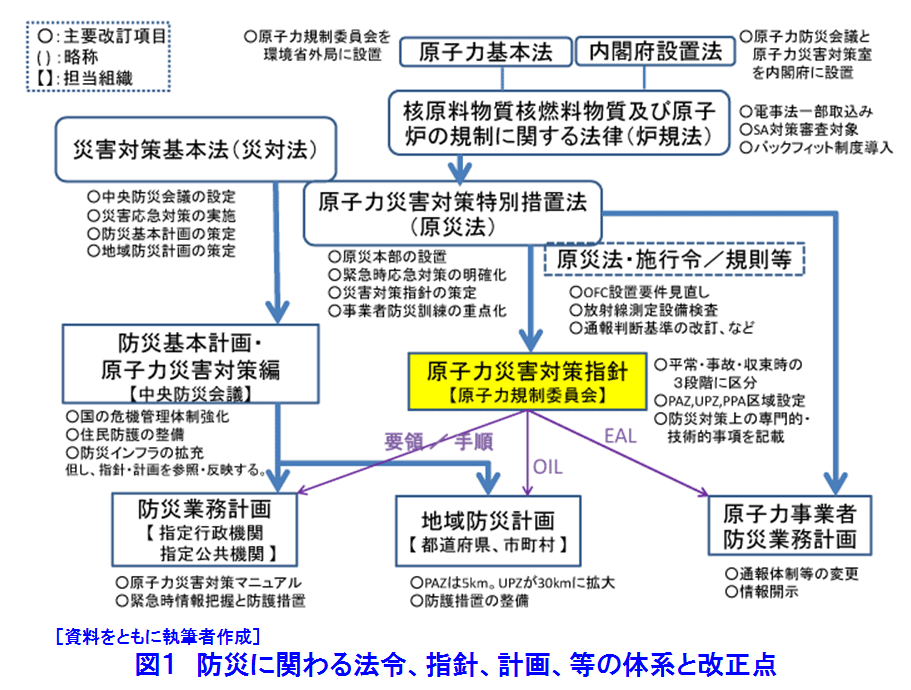
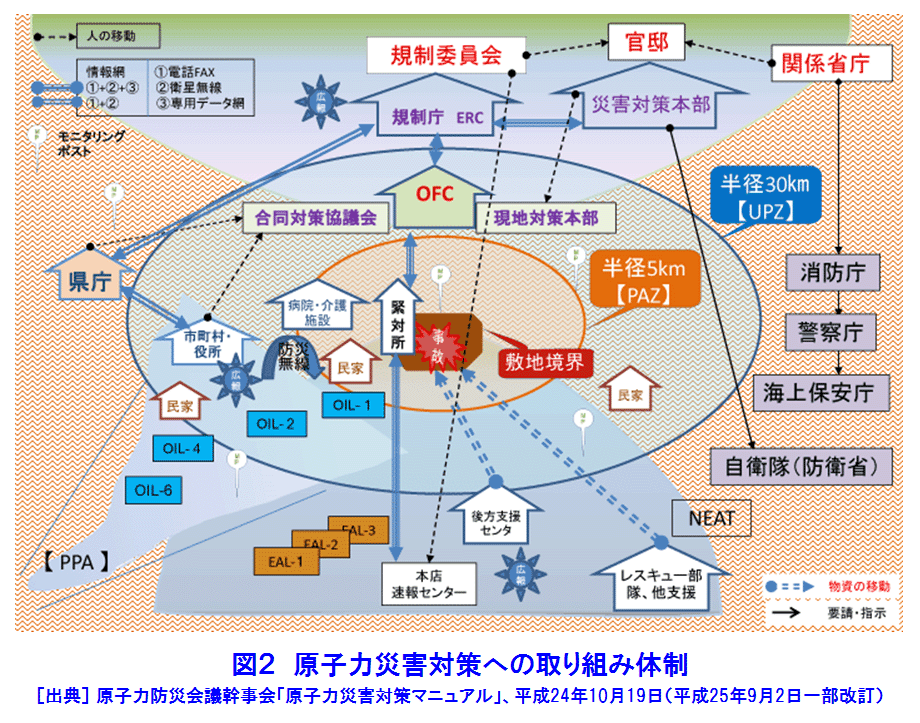
<関連タイトル> 原子力防災対策のための国および地方公共団体の活動 (10-06-01-04) 緊急時の医療活動 (10-06-01-07) 原子力防災のための訓練 (10-06-01-08) オフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点施設) (10-06-01-09) 原子力災害対策特別措置法(原災法:2012年改定以前) (10-07-01-09) TMI事故時の避難措置 (02-07-04-03) JCOウラン加工工場臨界被ばく事故の概要 (04-10-02-03) チェルノブイル事故による健康影響 (09-03-01-06) 原子力施設等による災害の対策について(原子力災害対策指針−その2) (11-03-06-05) <参考文献> (1)原子力災害対策指針、平成24年10月31日、(平成25年2月27日全部改正) (平成25年6月5日全部改正)(平成25年9月5日全部改正):原子力規制委員会、 (2)JCOウラン加工工場臨界被ばく事故の概要:ATOMICA (04-10-02-03) (3)「福島第一原子力発電所事故における放射性物質の大気中への放出量の推定について」平成24年5月、東京電力株式会社、 http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120524j0105.pdf (4)「原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説」平成25年9月5日、原子力規制庁、 (5)「原子力事業者防災業務計画の公表について」:原子力規制委員会、平成25年2月4日、 (6)「原子力安全規制評価サービス(IRRS)」日本政府への報告書;日本国東京 2007年6月25〜30日、
|

