|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
本指針は、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」を受け、放射線防護の観点から、原子炉施設の事故時に必要な放射線計測系の設計の妥当性について審査する際の指針であり、事故時の放射線又は放射能に関する情報を得、状況の把握や事故処理操作に有効に活用することを目的としたものである。 (昭和56年7月23日 原子力安全委員会決定、一部改訂 平成元年3月27日、一部改訂 平成2年8月30日) (注)東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)に伴う福島第一原発事故を契機に原子力安全規制の体制が抜本的に改革され、新たな規制行政組織として原子力規制委員会が2012年9月19日に発足した。本データに記載されている事故時の放射線計測に関する審査指針については、原子力規制委員会によって見直しが行われる可能性がある。なお、原子力安全委員会は上記の規制組織改革に伴って廃止された。 <更新年月> 1998年05月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
本指針は、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」を受け、放射線防護の観点から、原子炉施設の事故時に必要な放射線計測系の設計の妥当性について審査を行う際の指針を示したものである。以下に本指針及び本指針解説の概略を示す。 1.事故時の放射線計測の基本的考え方 原子炉施設の事故時には、一般公衆はもとより従事者を放射線から防護するため事故の規模、事故の拡大の可能性等事故の状態を的確に把握し、迅速に対応することが重要である。 事故時における放射線計測は、一般公衆及び従事者に対する放射線防護の観点から、次の目的のために事故時の放射線又は放射能に関する情報を得ることである。 (1) 放射能障壁の健全性の把握 (2) 放射性物質の放出量の把握 (3) 周辺環境における放射線量率の状況の把握 (4) 従事者の建家(BWRでは原子炉建家、PWRでは原子炉補助建家)立入りのための放射線量率の状況の把握 2.放射線計測系の設計上考慮すべき事項 2.1 考慮すべき事故 放射線計測系の設計に当たり考慮すべき事故として、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」で示された「原子炉施設の安全設計の観点から想定される」事故を想定するが、放射線計測系は、その目的を考慮して、余裕のある設計であることが必要である。ここで、放射性物質の放出を伴う可能性のある事故事象として以下の事象を対象とする。 (1) 放射性気体廃棄物処理施設の破損(PWR、BWR) (2) 主蒸気管破断(BWR) (3) 蒸気発生器伝熱管破損(PWR) (4) 燃料集合体の落下(PWR、BWR) (5) 原子炉冷却材喪失(PWR、BWR) (6) 制御棒飛び出し(PWR) (7) 制御棒落下(BWR) また、測定上限値としては、事故時の放射線量等の様相が最も厳しくなる「原子炉立地審査指針」でいう仮想事故、すなわち、原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断又は蒸気発生器伝熱管破損も対象として検討し、これに十分な余裕をもたせることとした。 2.2 放射線計測系の分類 放射線計測系をその要求される機能に応じて3分類する。 分類1:放射能障壁の健全性を確認するための情報を与える主たる放射線計測系(電源及び記録・表示に加えて、耐震設計、多重性・独立性も配慮する) 分類2:事故の経過及び影響範囲を推定するための情報を与える主たる放射線計測系(電源及び記録・表示について配慮する) 分類3:分類1及び2の放射線計測系による情報を確認するための補足的な放射線計測系(一般産業レベルの規格・基準による設計) 2.3 放射線計測系共通の設計条件 放射線計測系の具体的な設計に当たっては、前記2.2の分類によらず、一般に以下の各項が考慮されねばならない。 (1)放射線計測系は、信頼性の高い設計とし、事故時の環境条件によって、その機能が損なわれることがない設計であること。(事故時における、予想される圧力、温度、湿度、放射線等の環境条件下で、その機能を達成する能力が失われないように考慮された設計であること) (2)放射線計測系は、平常時に使用される系統と共用できる系についてはその共用は許容されるものとする。共用することにより、事故時に所定の機能が確保できない恐れのある場合には、独立な系統として設計すること。 (3)放射線計測系は、計画的に試験及び検査の可能な設計であること。(事故時の放射線計測系は、事故時に十分な機能を確保するため、適切な方法により、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる設計であること) (4)放射線計測系は、従事者の被ばくを合理的に達成できる限り低くするため、自動化、遠隔化等の措置を構じた設計であること。 (5)原子炉冷却材及び格納容器内雰囲気の放射線計測系は、事故時の格納容器バウンダリの機能をサンプリングの実施によって影響が生じるほど損うことがない設計であること。(原子炉冷却材及び格納容器内雰囲気の事故時のサンプリングについては、バウンダリの健全性を損なうことのないように隔離弁を有し、必要に応じてこれを開いてサンプリングを行った後、バウンダリの隔離を行えるよう考慮された設計であること) 2.4 放射線計測系の分類固有の設計条件 2.3の共通の設計条件に加え、放射線計測系の分類に応じて以下の各項についても考慮されなければならない。 (1)分類1の放射線計測系は、耐震Aクラスで設計するとともに、多重性を有する設計とし、その系を構成する、チャンネル間の独立性を実用上可能な限り考慮した設計であること。(放射能障壁の健全性の把握の重要性に鑑み、耐震Aクラスの設計を適用し、実用可能な限り多重性・独立性を考慮した設計とする) (2)分類1の放射線計測系は、非常用所内電源系に接続された設計であること。分類2の放射線計測系は、原則として分類1と同等であること。 (3)分類1及び2の放射線計測系は、原則として連続表示し、かつ、その結果を記録できる設計であること。 なお、放射線計測系は、事故時に十分な機能を発揮し、必要な前記設計条件と同等の設計条件を満足するならば、必ずしも固定設備としなくてもよい。(事故時における敷地周辺放射性物質濃度の測定は、可搬型計測設備を用いることにより必要な機能を発揮できるものである。このように計測の目的に照らして十分な妥当性を有する場合には、必ずしも固定設備である必要はない) 2.5 放射線計測系の計測対象等 事故時の放射線計測系は、前記1.の基本的考え方で示す目的を達成するために計測の対象、項目、方法、測定上限値、設置場所等について組み合せを考慮し、適切な選択をしなければならない。(具体的な例を表1-1及び表1-2に示す) <図/表> 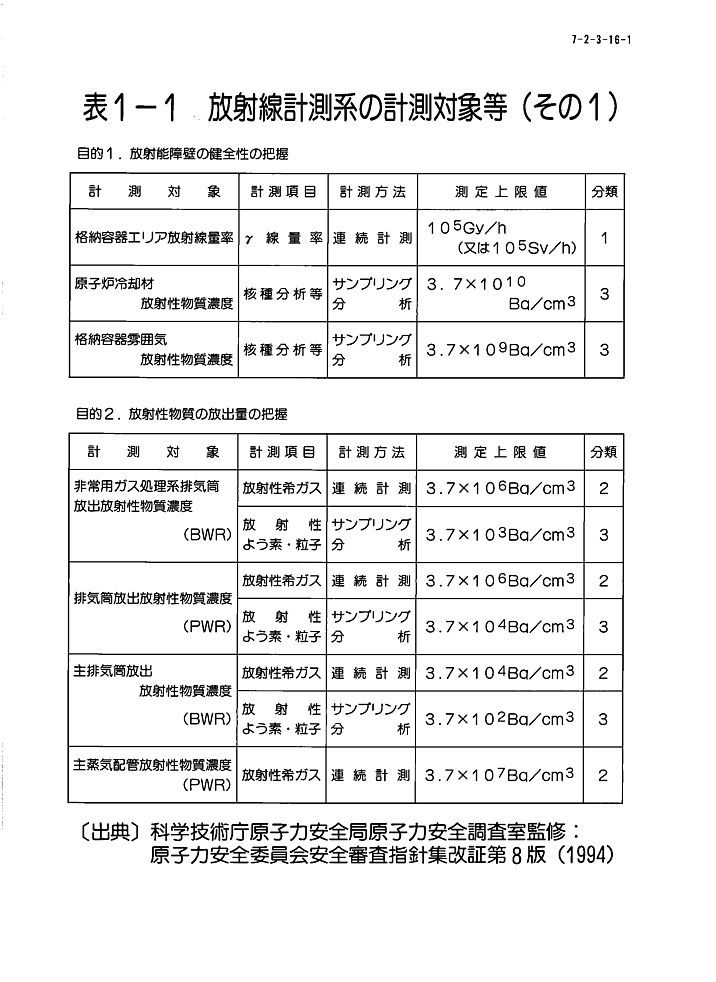
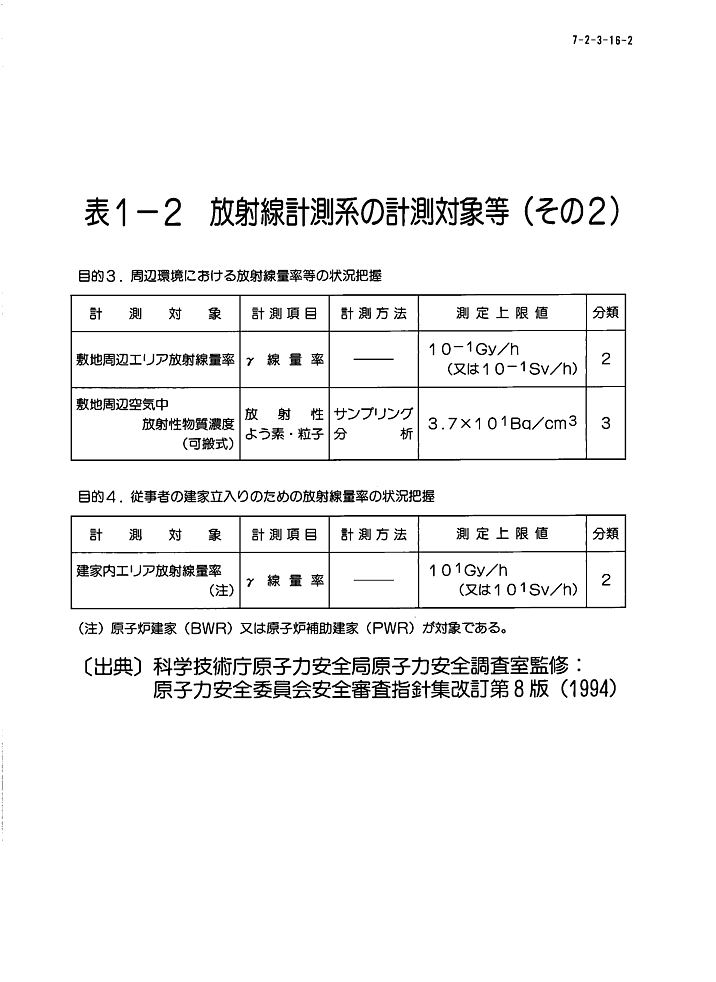
<関連タイトル> 原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて (11-03-01-03) 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針 (11-03-01-05) 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 (11-03-01-10) 我が国の安全確保対策に反映させるべき事項について (11-03-01-18) 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針 (11-03-01-23) <参考文献> (1) 科学技術庁原子力安全局原子力安全調査室(監修):改訂8版 原子力安全委員会 安全審査指針集 大成出版(1994)
|

