|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
放射能の大気中への異常放出や、平常時における定常的な微量放出が及ぼす公衆への放射線影響を評価するため、他の一般公害に対してと同様に、原子力分野においても放射能の大気拡散シミュレーションモデルに関する研究が進められている。最も実用的なモデルは、煙が風下に直線的に流されながら、ガウス分布に従って広がることを仮定した、ガウスプルームモデルである。このモデルは長年にわたり、安全評価や緊急時用モデルとして使われてきたが、近年、高精度評価を目指したより物理的な大気モデルの開発、実用化の進展が著しい。ここでは、現在、実用的・研究的に開発されている大気拡散シミュレーションモデルを概説し、さらに原子力分野での利用の現状について言及する。 <更新年月> 1998年05月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.大気拡散モデル 気象・拡散現象は、地球物理学の分野ではあらゆるスケールについて盛んに研究が行われている。一方、原子力分野においては、原子力発電所立地に関係した公衆への被曝評価の関連から、サイト周辺住民の安全問題すなわち局地スケールの拡散の研究が主体となっており、チェルノブイリ原子炉事故を契機に広域拡散に視点が移りはじめている。 大気拡散のモデル化に関する研究は、19世紀後半から20世紀にかけてエネルギ−源として化石燃料が大量に使用されはじめた事に伴う大気汚染の問題がきっかけとなっている。現在では、最も実用的なモデルとして、Pasquillにより提案された、煙の分布をガウス分布で表現するいわゆるガウスプルームモデルが広く使用されている。ガウスプルームモデルは、排出ガスが定常的に放出され、地形が平坦で建物などの影響が無視でき、かつ風速場が時間的空間的に一様であるという仮定の基に、移流・拡散方程式を解いた場合に得られる濃度の分布式で拡散を評価するモデルである。この場合、図1のように、煙は風下方向に直線的に流され、煙の軸のまわりにガウス分布型で広がっていく。このモデルに対する仮定が充たされることは、現実の大気ではほとんどないが、ひとつの式で解析的に濃度が計算できるというモデルの取り扱いの容易さにより広く実用的に使われている。 これに対し、複雑地形にも対応できるような計算機を用いた大気拡散の数値計算モデル(ここでは解析式に値を代入して解くのではなく計算機を用いて数値計算を行うという意味でこの用語を用いる)の開発は、計算機・計算技術の発達や、複雑な地形上への各種施設の進出に伴う環境影響評価の必要性等の外部条件が重なって1970年代以降からかなり進展した。数値計算モデルでは、気流の地形による変化や非定常性を評価するためにあらかじめ気流計算を行い、これを入力として大気中物質の移流・拡散方程式を数値的に解く方法が一般的である。 気流計算モデルは、大別して対象領域内にある気象観測データを積極的に計算に取り入れ現況を解析する診断型のモデルと、観測値を初期条件として用い流体を支配する運動方程式、熱力学方程式等の物理方程式を数値計算により解く予報型のモデルが提案されてきた。診断型のモデルのうち最も簡単なものは内挿モデルであり、このモデルは、数地点の観測データを2〜3次元の格子点に内外挿し計算領域全体の風速場を推定するモデルである。このような内挿モデルで得られた風速場は質量保存則という物理法則を満たさないため、計算された風速場は非現実的な収束や発散を含むことになる。そのため、内挿モデルの結果に変分解析法による最小の修正を加え、質量保存則を満たす風速場を計算する多くの質量保存風速場モデルが提案され、この手法が現在の診断型モデルの主流となっている。予報型のモデルは、流体を支配する運動方程式、熱力学方程式等の物理方程式を数値計算により解き、現地の風や乱れを予測する。診断型モデルの精度が気象観測点の質と量に強く依存するのに対して、予報型のモデルは、観測点のない地域でも予測計算が可能であり、また乱れの構造も予測できるというという特徴がある。このモデルは計算時間がかかり、境界条件の扱いなどに難しさがあるためまだ研究目的に使われることがほとんどである。 気流計算に引き続く放出物の移流・拡散計算では、大気中物質の移流・拡散方程式に基づいて拡散するという仮定を用いることが一般的である。診断型の気流計算モデルによる結果と移流・拡散方程式の解析解を組合せた拡散モデルは、煙をガウス型の気塊(パフ)で表わすパフモデルやガウス型のプルームの断片(セグメント)で表わすセグメントモデルが提案されてきたが、これらはガウスプルームモデルで直線として扱われてきた煙軸の空間的時間的変化を考慮したものといえる。図2に各モデルの概略を示す。例えば、パフモデルではガウス分布型の丸い煙(パフ)が時間とともに広がりながら、時々刻々変化する風によって流されていくモデルである。移流・拡散方程式を数値計算により解くモデルでは、放出点が広い範囲にあるような公害関係の研究では差分近似による解法が一般的に用いられてきたが、スタック放出のような点源に対しては、粒子拡散モデルという放出物を多数の仮想的な粒子群で表わすモデルが用いられる。また粒子拡散モデルには、粒子の乱流運動をランダムウオークモデルで扱うものもある。 2.原子力分野での利用 一般環境中への原子力施設からの放射能放出に着目して大気拡散の問題が初めて論ぜられたのは、1955年の第1回国際原子力平和利用会議に米国気象局が公表した’Meteorology and Atomic Energy ’によってである。この報告は、前半は、当時の拡散研究についての現状、後半に被曝評価、安全解析について述べており、放射能の大気拡散研究に関する有力な手引書となった。拡散モデル開発の歴史のなかではこの時期は解析解型のモデルの研究が行われていた時期であり、この報告でもガウスプルームモデルが提案されている。ここでの被曝評価は、原子力施設立地時のアセスメントにあたるものである。 日本の原子炉の安全審査(立地審査)の中で、平常時及び事故時における放出放射能の大気拡散の評価方法は、原子力安全委員会の「発電用原子炉の安全解析に関する気象指針」に記述されている。これによれば、大気拡散評価にはガウスプルームモデルを適用している。世界各国の立地審査の方法を比較してみると、基本的にはガウスプルームモデルを使用しているが、日本の審査方式の最大の特徴は、日本のような複雑地形にも適用できるように、サイト周辺の地形模型を入れた風洞実験により実効放出高と呼ばれる地形を考慮したモデル用の放出高度を求め、これをガウスプルーム式に入力して濃度計算を行っている点にある。(注:原子力安全委員会は原子力安全・保安院とともに2012年9月18日に廃止され、原子力安全規制に係る行政を一元的に担う新たな組織として原子力規制委員会が2012年9月19日に発足した。) 安全解析で行われている事故を想定した拡散評価は、放出および気象条件を厳しく設定し最悪の被曝線量値に着目する安全側評価を目的としており、拡散の扱いは定常状態を仮定している。しかしながら現実の事故に対する防災対策上からは、サイト特有の非定常状態、すなわち複雑地形上での大気拡散の特徴の把握が重要であり、地形の効果や時間的空間的気象変化を大気拡散に考慮できる数値モデルを用いた評価が必要である。このような観点に立ち、米国のARAC(Atmospheric Release Advisory Capability)システムや、日本のSPEEDI(System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information)等では、3次元風速場計算のための質量保存則モデルと空間濃度及び沈着量計算のための粒子拡散モデルを、事故時の放射能拡散予測に用いている。数千kmスケールの大規模事故に対する拡散予測については、チェルノブイリ事故以降各国で研究が進められ、現在精力的に国際的な広域モデル比較研究が行われている(図3参照)。 <図/表> 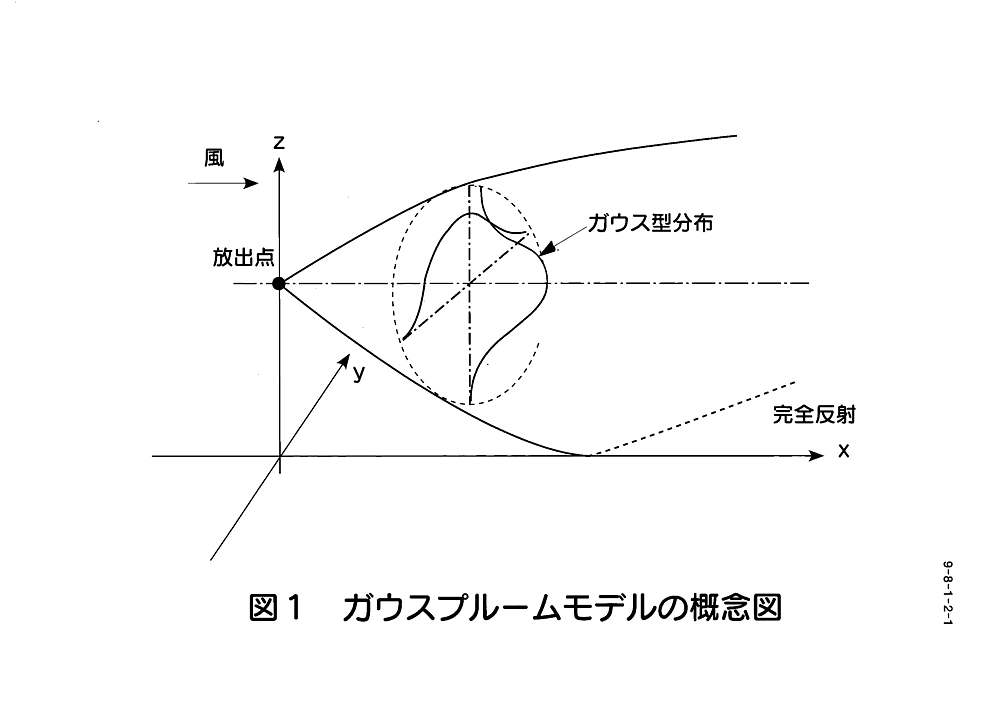
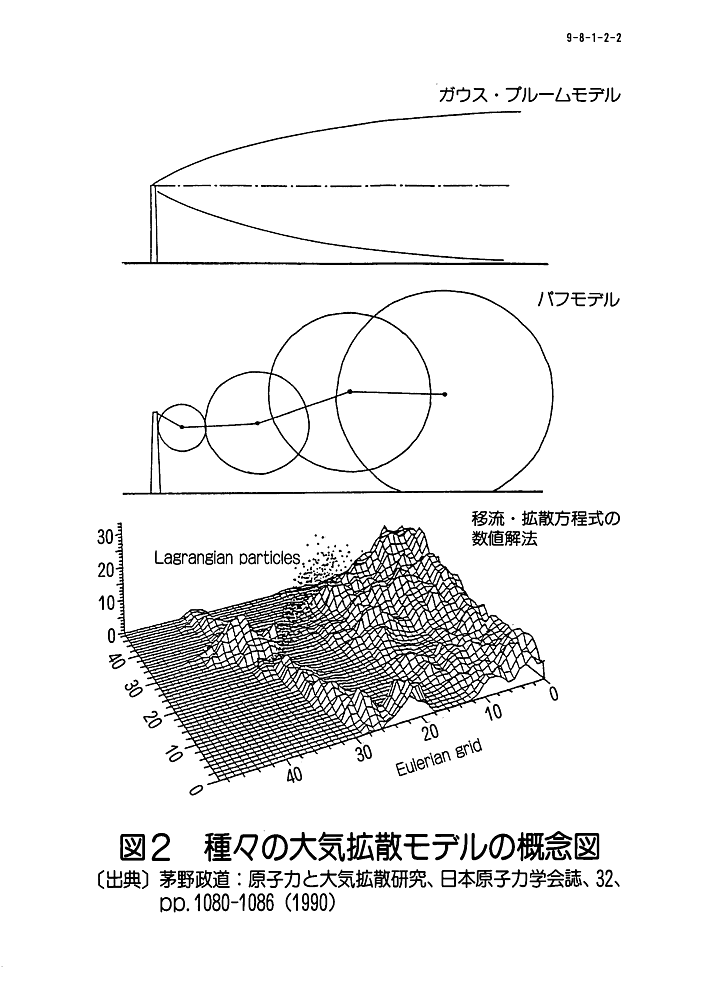
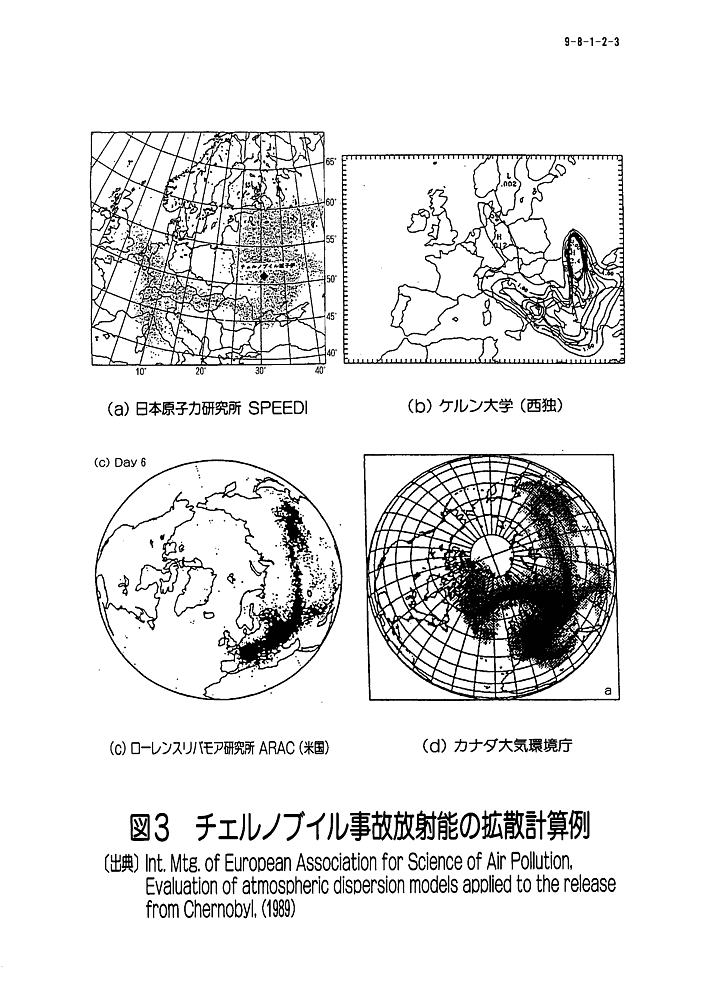
<関連タイトル> 放射能の大気拡散、移行 (09-01-03-02) 緊急時環境線量情報予測システム(SPEEDI) (09-03-03-01) <参考文献> (1) Pasquill,F.:Atmospheric Diffusion, Ellis Horwood,(1974) (2) 科学技術庁原子力安全局原子力安全調査室(監修):改訂8版原子力安全委員会安全審査指針集,大成出版(1994年10月) (3) 茅野政道:原子力と大気拡散研究,日本原子力学会誌,32,pp.1080-1086(1990) (4) 日本原子力研究所:原研における原子力安全性研究−第20回安全性研究成果報告会記念−、平成4年10月 (5) 日本原子力研究所:原子力安全性研究の現状−平成6年、平成6年10月
|

