|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
原子炉や加速器で発生する中性子は、X線や電子などともに波動性と粒子性を持つが、その特徴(軽元素検出、同位体識別、磁性検出、高透過性など)を活かし「探索子」、「分析子」、「作用子」としての役割を果たす。そのため物質科学・生命科学などの基礎研究や、材料・機能評価などの応用研究から産業利用に至る幅広い分野で利用されている。大型陽子加速器による大強度の中性子は、ライフサイエンス、ナノ・材料、環境・エネルギーなどの分野での基礎研究、応用研究、産業利用への貢献が期待されている。 <更新年月> 2006年05月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.まえがき 1932年にチャドウィック(英)が発見した中性子は、すでに発見されていたX線(電磁波の一種)や電子線(粒子線の一種)と同じように粒子性と波動性を併せ持ち(二重性)、結晶での回折現象も検証された。この性質を利用して物質の構造を探索する中性子散乱(中性子回折とも呼ぶ)の手法が開発された。しかし、本格的な実験は、十分な強度の中性子を安定して発生する研究用原子炉が利用できるようになるまで待たなければならなかった。欧米では1940年以降、日本では1960年以降である。この中性子散乱のパイオニアであるシャル博士(米)とブロックハウス博士(加)は、実験手法の開発と物質科学への貢献の業績により、1994年のノーベル物理学賞に輝いた。 2.中性子の果たす役割と利用 中性子は回折現象を利用した物質構造や機能の解明とともに、原子核反応を利用した元素分析や核変換による物質改変にも利用されている。 2.1 「探索子」として 中性子を物質の内部構造の「探索子(プローブ)」として利用する中性子散乱の原理は、X線回折や電子線回折と同じであり、物質を構成する原子間距離と同程度の波長を持つ中性子を利用する(熱中性子〜冷中性子)。中性子は原子核に力を及ぼして散乱するので(核散乱)、X線では見えにくい水素などの軽元素の検出能力に優れており、さらに水素と重水素などの同位元素も明瞭に識別できる特徴がある。従って、水素を多く含むタンパク質、酵素などの生体分子、ポリマーなどのソフトマターの研究に不可欠な実験手段となっている。中性子はまた最小の磁石の性質を持っているため、物質中の磁気モーメントと相互作用して散乱するので(磁気散乱)、物質の磁性の研究や、最近の高密度磁気記録材料や磁気ヘッド開発にも応用されている。さらに中性子散乱に用いる中性子のエネルギーは、物質中の原子の運動エネルギーと同程度なので(格子振動、拡散など)、非弾性散乱測定により物質中の原子の動きを精密に知ることが出来る。このような原子の動きを知ることは、物質の性質(例えば高温超伝導)発現機構解明の鍵を与えてくれるので、特に基礎研究では重要である。 中性子の物質に対する屈折率は1よりわずかに小さいので、物質表面にすれすれに臨界角以下の角度で入射する中性子は全反射する。この性質を利用して物質表面の構造や表面から深さ方向の構造の情報を得ることが出来るため(反射率測定)、液体表面・界面の研究や最近著しく発展している磁性薄膜の開発などにも利用されている。 中性子は、電気的に中性なので物質中に深く進入して内部の情報を得ることが出来る(高透過性)。この性質と中性子散乱法を利用して、大型構造物である自動車エンジン、航空機タービン、金属パイプなどの内部歪みの評価を行うことが出来る(残留応力測定)。一方、中性子を用いた人体のX線レントゲン写真のように、物体の内部のコントラストを明瞭に撮影することができる(中性子ラジオグラフィー)。これにトモグラフィーを併用すれば、パイプ中の二層流や燃料電池セパレーター中の水の挙動、植物の根の生育、木材や種中の水分分布などを非破壊で3次元的に可視化できるので、近年急速に需要が高まっている。 2.2 「分析子」、「作用子」として 中性子は、レーザーやイオンビームのように物質を加工する能力はないが、特定の原子の原子核と直接反応する。この性質を利用して反応後に出てくるガンマー線を検出し、元素分析を行うことが出来る(即発ガンマー線分析、放射化分析)。この「分析子」の性質を利用して、ppm-ppbの極微量元素分析を行うことが出来る。一方、中性子が原子核と直接反応した後、その原子核が他の元素に変換することがある(核変換)。この「作用子」としての代表例は、自然存在比約3%のシリコン30Siが中性子と反応してリン31Pに換わるもので、自然界に92%存在する28Si中に不純物Pを均一に混入(ドーピング)してn型半導体を製造することができる。原子炉を用いた不純物半導体製造法としてかなり以前から知られていたが、最近の大口径、高品位半導体の必要性から、このシリコンドーピングはますます注目されている。 3.中性子発生源 シャル、ブロックハウス両博士の1940−50年代の初期の中性子散乱実験は、研究用原子炉を利用して行われたものである。日本では1960年代に建設されたJRR-2、JRR-3(ともに10MW、原研東海(現日本原子力研究開発機構原子力科学研究所))、KUR(5MW、京大原子炉)の研究用原子炉が、中性子利用実験の道を拓いた。そして高度化した実験に対応するために1980年代後半にJRR-3を改造・高度化したJRR-3M(20MW、冷中性子源設置)によって、中性子利用研究分野で先行していた欧米先進国に追いつき世界第一線に躍り出た。 一方、1960年代半ばには、東北大核理研において加速器で発生した中性子による中性子散乱実験が、世界に先駆けて成功した。そのパイオニア的実績は、KEK(現高エネルギー加速器研究機構)に1980年に設置された世界初の加速器中性子源専用施設KENS(陽子ビーム出力3kW)に引き継がれた。その後欧米ではKENSを上回る性能の加速器中性子施設を相次いで建設し、特にISIS施設(160kW、英国ラザフォードアップルトン研究所)は現在世界最高性能を誇り、パイオニアであるわが国は後塵を拝してきた。しかし、2001年に原研(現日本原子力研究開発機構)とKEKの共同事業として大強度陽子加速器プロジェクトJ-PARC(Japan Proton Accelerator Research Complex)がスタートし、2008年利用開始に向けて建設が進んでいる(東海村)。このプロジェクトの中核的実験施設である中性子施設JSNS(Japan Spallation Neutron Source 仮称)は、ISISを大きく上回る1MWの出力の大強度中性子発生を誇り、米国オークリッジ国立研究所で建設中のSNS施設(1.4MW、2006年完成予定)とともに世界最高レベルの性能を有する。 加速器からの中性子は時間的にパルス状に飛来し、広いエネルギー範囲をカバーする一方、原子炉からの中性子は時間的に定常的である。前者では数10ミリ秒ごとに、時間幅数10マイクロ秒のパルス中性子が利用されるが、そのパルス強度は定常中性子の数百倍であり、その特徴を生かして時間飛行法による測定が行われる。一方原子炉の定常中性子強度の積分値は、多くの場合パルス中性子の時間平均強度を凌ぐので、両者を実験目的に応じて使い分けるのが最先端の中性子利用方法である。事実、米国においてはオークリッジ国立研究所(テネシー州)に原子炉中性子源HFIRと加速器中性子源SNSを、欧州においてはILL研究所(グルノーブル、仏)の原子炉中性子源HFRとラザフォードアップルトン研究所(英)の加速器中性子源ISISをヨーロッパ連合としての戦略的中性子利用施設と位置付けている。わが国においては上述のように、原子炉中性子源JRR-3Mと加速器中性子源JSNSが、原子力機構東海サイトの同一敷地内にわずか800m離れて併設されることになるので、その先端的な利用に世界中の注目が集まっている。 4.大強度中性子ビームの拓く世界 大強度の定義は必ずしも明らかではないが、陽子ビームパワーMWクラスの加速器から発生する中性子のことを意味することが多い。その意味では、日本で建設中のJSNSと米国のSNSがそのカテゴリーに入り、現在世界最強パルス中性子源(ISIS)の約10倍以上の強度が得られる。 J-PARCの中性子施設に設置予定の中性子散乱装置の一部の配置図(案)を図1に示す。これらの装置は、プロジェクトチームである原子力機構とKEKが建設するもの、それ以外の第三者(茨城県、科研費などの競争的資金など)が固有研究のために建設するもの、将来は外国の研究機関が建設するものなどに分類できる。いずれの装置も未踏の大強度中性子を最大限利用するための新しいビーム制御、検出、解析方法などを採用している。これらの装置の目的とする研究や評価対象は概略次の通りである。 (1)生体高分子の水素・水和構造解析による創薬への貢献(図中装置2、3) (2)生体物質の運動による非弾性散乱を観測する生体の機能の研究(6) (3)新物質・新材料の開発研究と構造評価(4、5、13) (4)物質中の原子や分子の運動状態と機能研究(7、8)、 (5)高温超伝導体の発現機構研究(1)、 (6)ナノ物質・材料の開発研究と構造機能評価(9)、 (7)液体・非晶質・ガラス等の構造と機能研究(14) (8)表面・界面の構造研究(10) (9)残留応力測定(12) (10)超高エネルギー分解能測定(11) パルス強度が定常中性子源の数百倍である優位性を活かした構造解析(1)(3)(6)においては、これまでの数十倍のスピードでの測定が可能である。例えば年間数個のタンパク質構造解析(特に水素・水和構造解析)しか出来なかったものが、100〜150個程度解析可能になり、製薬会社などの産業利用も大いに期待できる。また、無機材料測定においては、1個数分で解析可能になるので、年間1万個以上の試料を取り扱えることになり、構造解析ソフトの充実とともに試料交換ロボットなどの導入が検討されている。非弾性散乱実験(2)(4)(5)(10)においては、広いエネルギー範囲にわたる高分解能実験が可能となり、生体分子の運動と機能解明、高温超伝導体の超伝導現象と原子やスピン揺らぎの研究など学術的に重要な問題の解決が期待できる。さらにまた、パルス中性子の波長分布が広い特長を活かして精密な局所構造解析ができる液体やガラス物質の構造研究(7)、飛行時間法の特長を活かし全主軸方向の残留応力を一度に測定し、従来の約百倍効率を高める測定(9)などがある。 このように未踏の大強度パルス中性子は、学術的基礎研究から、応用研究、そして産業利用に至る広い利用分野と、物理、化学、生物、薬学、高分子、地球科学、工学応用などの広い研究分野に大きなインパクトを与えることが期待される。 <図/表> 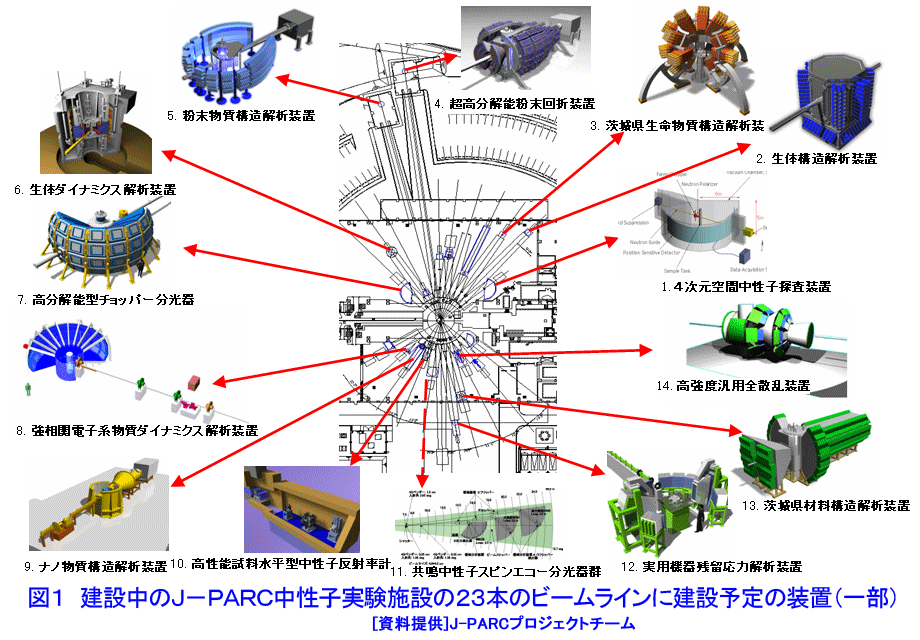
<関連タイトル> JRR-3(JRR-3M) (03-04-02-02) J-PARC計画とその利用研究 (07-02-01-15) 中性子照射によるシリコン半導体製造の原理 (08-04-01-25) <参考文献> (1)日本結晶学会編集委員会(編):結晶解析ハンドブック、共立出版(1999年9月) (2)藤井保彦(編):実験物理学講座第5巻「構造解析」、丸善(2001年9月)
|

