|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
トカマク装置の研究開発は1970年以降核融合炉の実現をめざす目的研究として進められてきた。日本(日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構))のJFT-2装置をはじめとする世界の中型装置による原理実証と技術基盤の整備に基づいて、1980年代には世界の三大トカマク装置(日本のJT-60、米国のTFTR、EUのJET)による臨界プラズマ条件(外部からのプラズマ加熱入力パワー=核融合反応出力パワー)の実現の研究開発が行われた。旧ソ連のT-15を加えて、4大トカマク装置と呼ぶこともあるが、T-15は厳しい経済状況のもとでいまだに未完成である。JT-60での臨界プラズマ条件(Q=1、JT-60ではTは使用しないので、DプラズマでQ=1に必要な温度、密度、閉じ込め特性を達成した。達成値はQ=1.25)の達成や5.2億度、JETでの短時間DT燃焼での16MW発生など、三大トカマク著しい進展を得た。これらの成果をベースとして1988年以後、日、米、EU、ロシアの国際協力により、本格的なDT燃焼を実証するための国際熱核融合実験炉(ITER)の設計研究と関連する工学技術の研究開発(R&D)が行われ、2004年夏現在、ITERの建設地を決める政府間交渉が進められている。 <更新年月> 2004年07月
<本文>
1.トカマク型大型装置 1968年に旧ソ連で、T-3トカマク装置での成果発表以来、多くのトカマク型核融合装置による実験が世界の主要国で実施され、1960年代に一時停滞したかに見えた核融合の研究開発は大きく進展の方向に転換した。わが国のJFT-2トカマクが当時の閉じ込め時間の世界記録を塗り替えた1970年代前半には、核融合出力パワーとプラズマを加熱する外部からの入力パワーがバランスする臨界プラズマ条件を具体的な目標とし、そのための大型装置を計画する機運が高まってきた。それまでの実験結果と装置諸元を関連づけることで臨界プラズマ条件を実現する大型装置への経験的な外挿を行う比例則を求めることができる。主としてプラズマの閉じ込め時間を長くするために装置を大型化しプラズマ電流を増大することが必要なことが判明した。これを用いて大型な次世代のトカマク装置を建設する計画が日本、米国、ECでほぼ同時に開始された。(手続き的にはわが国がすこし早かった。)JT-60は、計画開始時にはJFT-2に続くものとしてJFT-3と呼ばれていたが、後にそのプラズマ体積60立米をとってJT-60となった。(表1参照)。JT-60の当初のパラメータはプラズマの主半径3mであったが、米国のTFTRやEC(当時、現EU)のJETもJT-60とほぼ同じサイズをとり、TFTRのプラズマ主半径は2.5m、JETも3mであった。同じ臨界プラズマ条件を目指したので、似たサイズになることは当然であったが、よく見ると、米国のTFTRは磁場をできるだけ強くして装置の小型化を図り、JETは逆に磁場は中程度だがプラズマの断面を非円形(縦長)として大断面、大体積のプラズマとした。JT-60はJFT-2aで世界に先駆けて高い成果を出したダイバータを有することを特徴としていた。磁場さえ強ければ(米国)、プラズマが大きければ(EC)、純度の高いプラズマこそが鍵(日本)と、同じ目標を狙うのに、これだけの考え方の違いが出たことは特筆に価する。その後の改造なども含めて、JT-60が最高の成果を得たことも、わが国の科学技術の歴史の中で特筆される。この三つの装置を世界の3大トカマク装置(表1)と呼んでおり、これに旧ソ連のT-15を加えて、4大トカマク装置と呼ぶ場合もある。T-15は残念ながら厳しい経済状況の中で建設が保留になり未完成のままである。 (1)JT-60(日本、日本原子力研究所:原研(現日本原子力研究開発機構))(図1参照) JT-60は1975年に設計を開始し、1985年4月にファースト・プラズマを作って、実験を開始した。当初の緒元は、表1とすこし異なり、主半径3m、円形断面の副半径0.9m、磁場4.5Tだった。(プラズマ体積は48立米。設計開始当初は副半径1mで約60立米だった。)ドーナツ型プラズマの外側横にダイバータ・コイル(プラズマが外側に移動しないように抑える副ダイバータ・コイル2本を含めて3本のコイル)があった。1989年にはJT-60で全プラズマ電流の80%をプラズマ自身が流す(自発電流)の実証に成功し、この成果から定常核融合炉概念を創出する道を開き、自発電流の多い(凹状の電流分布)による革新的炉心プラズマ概念が生まれた。1989年10月よりプラズマ電流値を当初設計の最大3.2MAより7MA(プラズマ体積100m3)にあげ、プラズマ断面形状をD型に変更するための大電流化改造(JT-60U)を開始し、同時に重水素ガスを用いた運転ができるよう装置を整備した。1991年以降実験を開始し、1994年には核融合積の当時の世界最高値1.2E21keV秒/m3を達成し、現在も最高値の1.5E21keV秒/m3を得た。1997年にはダイバータ形状をW型に改造(図2参照)し排気ポンプを付けて、不純物の発生の抑制、核融合反応後のHe灰の排気を実証した。1997年にはさらに高性能プラズマの長時間(約9秒)維持に成功した。1998年にはプラズマ電流の半径方向分布の改良に成功し(負磁気シアモード(図3、図4参照))、エネルギー増倍率(D-T等価Q値)1.25を達成した。(図5参照。2003年に出たフランスの本にも、臨界条件はJT-60で達成したと書かれている。)JT-60のトロイダル・ベータ値は2.7%、規格化ベータ値は4.8である。さらに、2000年には、トカマク装置では世界唯一の負イオンを利用した中性粒子入射装置を用いて、約80%の自発電流による負磁気シアモードを数秒間維持することに成功して高性能定常炉への道を開いた。2000年にはプラズマ断面の中心部に電流が流れていない「電流ホール」を発見し、世界に新しい研究テーマを提供した。この間、プラズマ内部の詳細な物理情報の観測と制御および理論解析により、磁気再結合現象、乱流、非線形現象などのプラズマ複雑現象の物理機構解明が行われ、プラズマ物理学の構築に貢献している。さらに、100秒程度に放電時間を延ばし定常化の実験研究を進めるため、トロイダルコイルを超電導コイルへ改修する計画を提案している。 (2)JET(EU)(図6参照) JETは1983年6月に実験を開始し、その後、装置各部の改良や補強をおこない、1991年の重水素放電で、D-T等価Q値1.1(核融合積は9.E20keV秒/m3)を達成した。1991年には世界で初めて三重水素を重水素中に約10%程度まぜる予備的なD-T放電を実施し、1997年には1秒以下の短時間ながらD-T反応出力16MWを実現した。その後、ITERの物理データーベース整備のため、ダイバータ構造を改造し実験を継続している。 (3)TFTR(米国) TFTRは1982年末に実験を開始した。1988年の重水素放電では、D-T等価Q値0.3(核融合積3.2E20keV秒/m3)を達成した。その後は三重水素取扱施設を整備し、1993年からは三重水素と重水素比率1:1のD-T放電を行った。1994年には温度5.1億度、核融合出力10MWを得た。その後、米国では財政圧縮、核融合研究開発計画の再編から1997年4月にはTFTRの実験運転を終結した。 (4)T-15(ロシア) T-15の特徴は超電導コイルを有し、長時間放電継続の能力を有する点であろう。旧ソ連からロシアへの体制移行など厳しい経済状況のもとで建設は中断され、実験活動は行われていない。 2.研究開発課題と波及効果 大型装置の開発に伴う工学分野の技術開発の成果が著しい。プラズマの加熱装置としてはJT-60で正イオンビームを用いた中性粒子入射で120kV、20MW、負イオンを用いた中性粒子入射では400kV、10MWが稼働している。ITER用では1MVが試作されている。高周波加熱では2GHz(低域混成波帯)や120MHz(イオンサイクロトロン周波数帯)で、それぞれ1MWの発振管が開発され、またITER用に110−170GHz(電子サイクロトロン共鳴帯)で1MWの発振管も開発中である。 プラズマと対向する第一壁材として炭素複合材、ベリリウム技術が進展している。JT-60は当初はTiCをコーティングしたモリブデン板やステンレス板が第一壁に使われていたが、その後、すべての壁面をカーボン・タイルに変更し、よい特性を得ている。 こうした技術成果がもたらす他分野との相互作用や波及効果が大きい。100万ボルトという高エネルギー負イオン源の開発で培われた技術は、広く工業的に利用されている。例えば、液晶画面用の半導体の電気絶縁物であるガラス基板の製造、また、集積回路(LSI)の基板のミクロンサイズ(100万分の1メートル)精度での加工、さらに、歯車など磨耗の激しい機械部品の表面の、窒素イオンビームで照射による硬い窒化被覆層の生成技術に応用されている。これらの利用に加えて、イオン源技術は、光電効率(太陽光を電気に変換する効率)の高い太陽電池の製作への応用にも期待され、原研(現日本原子力研究開発機構)では、100万ボルト級の高エネルギー水素負イオンビームを基板に照射し、10ミクロン程度の厚さの単結晶シリコン薄板を切り出す方法を開発した。 超伝導磁石は、物性研究用の小規模コイルから核融合炉用の大規模コイルまで広い範囲に応用されている(表2参照)。トカマク型核融合炉用超伝導コイルは、大電流・高磁場であり、低交流損失であることが要求される。従って、他の超伝導コイルに必要な多くの特性がトカマク型核融合炉用超伝導コイルには兼ね備えられている。先陣をきる核融合コイルの開発は、他の超伝導コイル応用への貢献が大きく、その中でもほぼ同じ特性が要求される超伝導コイルの応用として、超伝導磁気エネルギー貯蔵器(SMES)がある。核融合炉用に考案された超伝導コイルの導体構造は、安定性や交流損失等に優れ、SMES用超伝導コイルの導体の設計に採用されている。 このように波及している分野として以下がある。 (a)中性子工学、(b)高真空技術、(c)超電導、(d)極低温技術、(e)高エネルギービーム技術、(f)高周波エネルギー技術、(g)計測・制御技術、(h)コンピュータ・通信技術、(i)材料、(j)生産・加工技術、(k)システムエンジニアリング、(l)保守点検技術 <図/表> 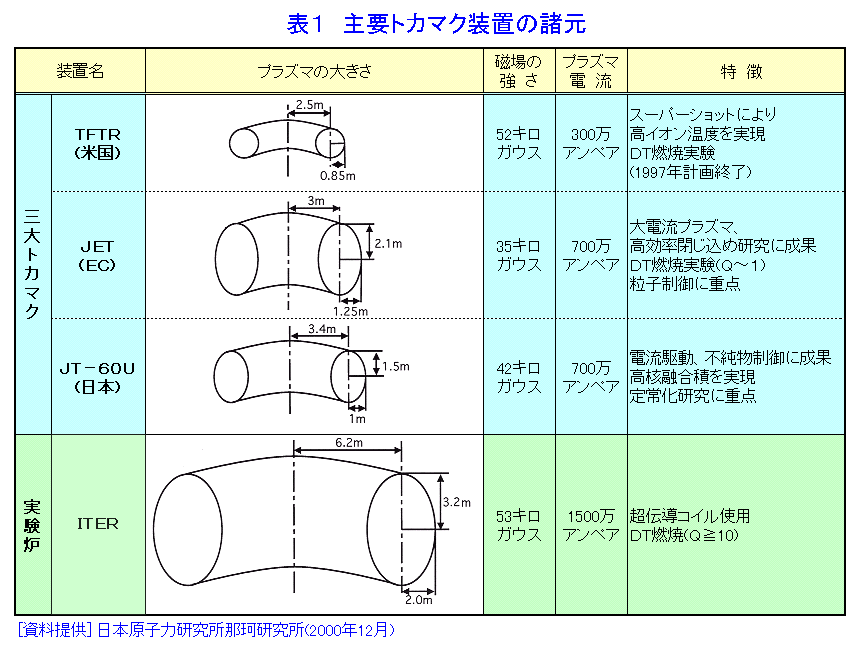
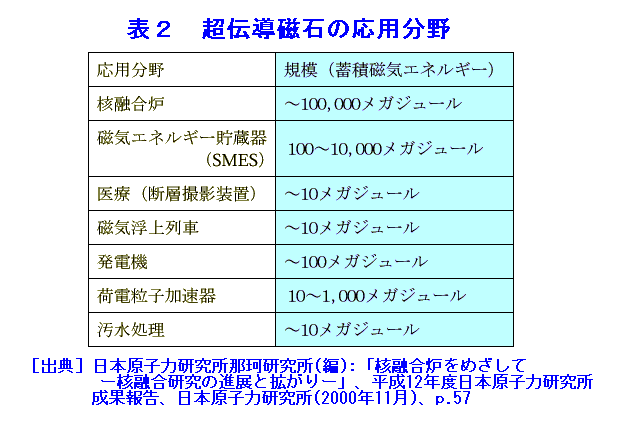
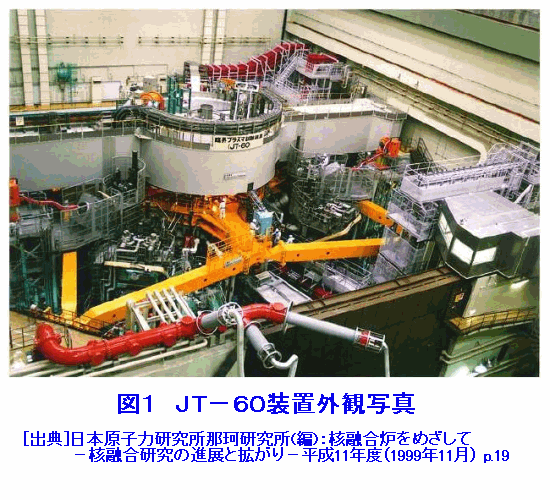
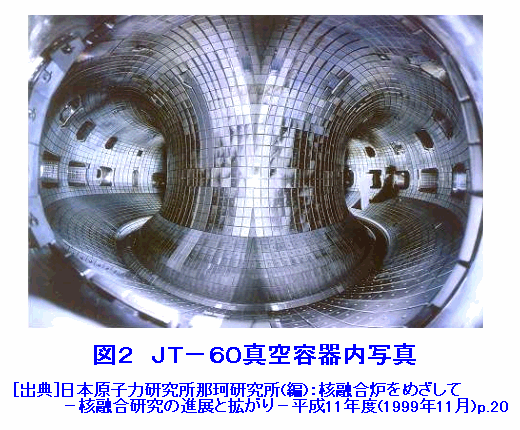
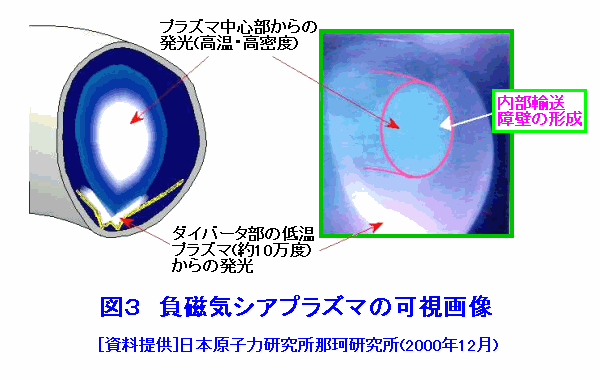
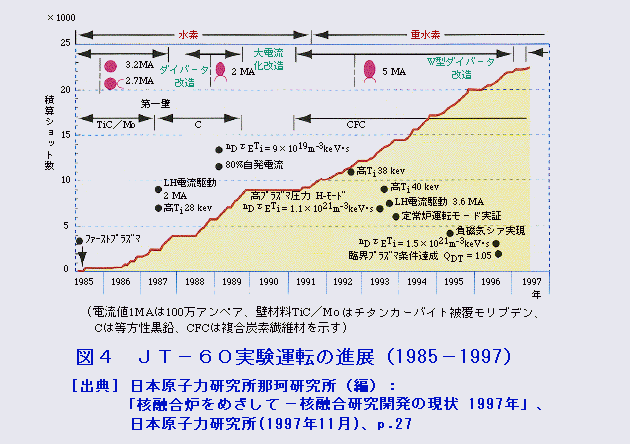
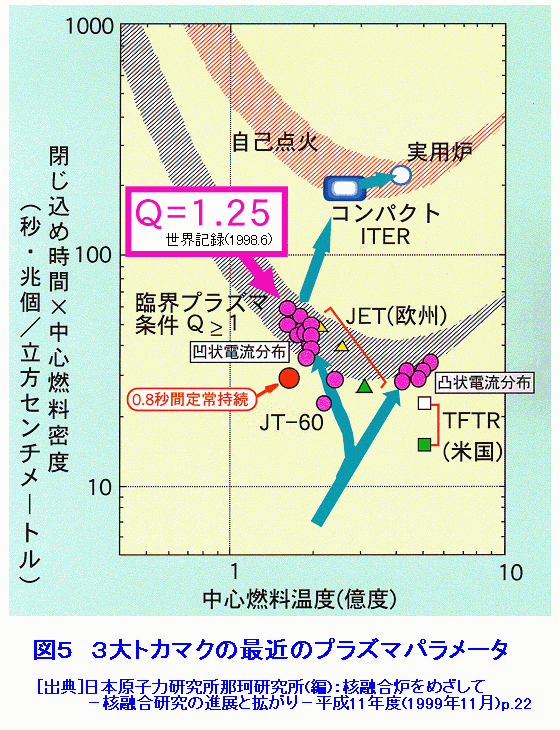
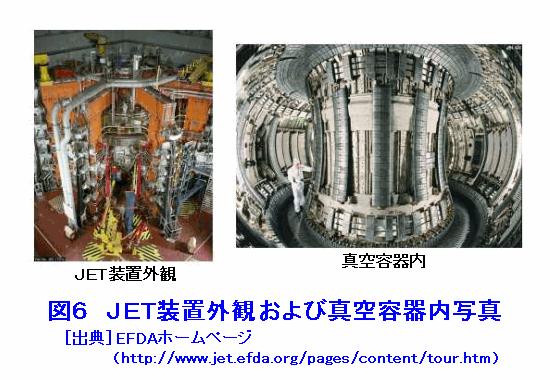
<関連タイトル> 核融合研究開発の経過 (07-05-01-03) 核融合反応装置の形式と作動原理 (07-05-01-05) トカマク型核融合装置の研究開発 (07-05-01-06) 慣性核融合装置の研究開発 (07-05-01-10) <参考文献> (1)狐崎晶雄、吉川庄一:新。核融合への挑戦、講談社ブルーバックス(2003年) (2)関昌弘監修:核融合炉工学概論、日刊工業新聞社(2001年) (3)J・ヴァイス、本多力訳:核融合エネルギー入門 白水社クセジュ文庫(2004年) (4)近藤育朗、栗原研一、宮健三:核融合エネルギーのはなし、日刊工業新聞社(1996年) (5)日本原子力産業会議(編):[核融合研究開発の波及効果に関する調査]、1987
|

