|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
原子燃料および被覆材の組み合わせは使用目的と技術の進歩によって左右される。発電用原子炉では、当初は天然ウラン金属を用いたコルダーホール型や重水炉も開発されたが、原子炉のコンパクト化が可能な、濃縮ウラン酸化物−ジルカロイ被覆の組み合わせが大半を占め、重水炉も低濃縮ウラン酸化物を使用するようになった。研究炉は目的に応じていろいろな燃料が使用されているが、U-AlまたはU-Si化合物燃料とAl被覆の組み合わせが多い。 <更新年月> 2004年08月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
原子燃料(核燃料)はいろいろな意味に使われるが、狭い意味では、中性子を吸収して核分裂を起こす物質(またはその化合物)を指し、ウラン(U)、プルトニウム(Pu)、がこれに該当する。また、トリウム(Th)の核変換で生成する233Uも含まれる。広い意味では、狭い意味での原子燃料(またはその化合物)と被覆管(または板)で構成された燃料棒(または燃料板)、更にこれを集合体に組み上げた燃料集合体(燃料要素)を指すこともある。 原子炉システムで燃料に要求される役割は、 (1)核反応を継続させる、 (2)核分裂生成物(FP)を閉じ込める、 であり、発電用原子炉ではこれらに加えて、 (3)質の良いエネルギーを経済的に取り出す(現行の発電炉では高温の水蒸気を得る) が要求される。 一方、研究用原子炉は使用目的によって炉のシステムが異なり、使用される燃料と被覆材もこれに従って異なってくる。 上記の役割は燃料のみが負担するわけではないが、少なくとも、上記の要求を阻害する物質を用いてはならない。また(2)については、溶融塩炉のように、燃料にFP閉じ込め機能を要求しない炉型もあるが、殆どの炉型では、燃料(狭義の燃料)に第1段階(固体燃料の場合)、被覆材に第2段階のFP閉じ込め機能を求めている。特殊な炉型を除けば、原子燃料集合体は、燃料棒とそれを集合体にまとめる付属品とでなりたっている。そして、燃料棒は狭義の燃料と被覆管が主要な構成材であり、それぞれ下記のような性質が要求される。 (a)燃料 物理的な安定性が高いこと 化学的な安定性が高いこと(被覆材および冷却材との両立性がよいこと) 上記の性質が放射線照射によっても劣化しないこと(または劣化が少ないこと) 中性子吸収断面積が小さいこと (b)被覆管 上記の燃料に対する要求の他に機械的性質が良好なこと、すなわち、燃料の変形や内圧および冷却材の外圧に耐えうる強度と延性が要求される。 原子燃料および被覆材として候補に挙がった物質の性質を表1および表2に示す。 発電用原子炉の開発初期においては二つの考え方があった。一つは天然Uを用い(濃縮工程を行わなくてよい)、中性子吸収が少ない燃料棒およびこれを取り巻く減速材および冷却材で炉心を構成する方法で、具体的には下記の2つの炉型が実用化された。 (ア)黒鉛減速−炭酸ガス冷却炉(コールダーホール型) 金属U燃料−マグネシウム合金被覆−黒鉛減速−炭酸ガス冷却 (イ)重水炉(主にCANDU型) UO2燃料−ジルコニウム合金被覆−重水減速−重水冷却 天然Uは核分裂を起こす235Uの割合が少ないので、核反応を持続するするためには、単位体積中のU量を増やすか、中性子の減速中の損失が少ない(減速比が大きい)減速材を用いる必要がある。表3に減速材の諸性質を示すが、減速比がもっとも大きなものは重水(D2O)であり、次いで黒鉛が大きいが、重水は高価であるという欠点がある。また被覆材の耐食性や被覆が破損した場合に燃料と冷却材が接触することを考慮(良好な耐食性が必要)すると上記の2炉型が実用化された。但し、これらの減速材は減速能が軽水(H2O)よりも小さく、多量の減速材が必要になるため炉体が大きくなり、また、使用済燃料の発生量が多いという欠点がある。また、U濃縮費用の低下と使用済燃料の処理費用が予想より高いことが判明したため、後述の軽水炉が主流になった。 第二の考え方は濃縮Uを用いる方法であり、材料選択の自由度が増したが、下記の組み合わせがもっとも経済性がよいので、現在はこの炉型が主流になっている。 (ウ)軽水炉 UO2燃料−ジルコニウム基合金(ステンレス鋼)被覆−軽水減速兼冷却 この組み合わせには沸騰水型(BWR)と加圧水型(PWR)があり、現在は両者とも被覆材にジルコニウム基合金(ジルカロイ−2、ジルカロイ−4)を用いているが、初期には、機械的性質が良好なステンレス鋼が(中性子吸収が大きいという欠点があるが)PWRに使用された時期もあった。BWRでは、初期からジルコニウム基合金が使用された。なおソ連で開発されたVVERも加圧水型で、被覆管のジルコニウム基合金組成(Zr-1%Nb)が異なることを除けば同様な組み合わせである。 表1中のUO2は熱伝導度および耐熱衝撃性や単位体積中のU含有量が3者中でもっとも悪いが、融点が高く、被覆材や冷却材の水との両立性が他の2者よりはるかに優れているので、軽水炉に採用された。UCは融点がUO2より僅かに低いのみで、U含有量も熱伝導もUO2より優れているが、化学的な安定性に欠け、特に水との反応が激しいので、冷却材に水を使用する炉型には使用できない。しかし、高速炉では液体金属を冷却材に使用するので、この炉型に使用される可能性はある。但し、現在は高速炉でもUO2が使われている。 表2中のAlとBeは被覆材として有望な性質を数多く備えているが、Alは融点が低く高温強度も低いので炉心の温度を高くすることができず、高温の水蒸気を得ることができない。しかし、研究用原子炉の中には高温にする必要がないものもあり、被覆材として用いられることが多い。Beは殆どの性質が優れているのにかかわらず、照射によって延性が極端に低下するので被覆材候補になり得ないが、展延性が要求されない部材、例えば中性子の反射体に使用されている。 なお、Puの性質はUによく似ており、またU化合物に少量(数%程度)混ぜて使用されることが多いので、U-Pu混合燃料の性質はU化合物とほぼ同じと考えてよい。 現在、発電におもに使用されているBWRおよびPWRの燃料集合体の構造を図1に示すが、この設計に到達するまでに、経済性と安全性向上のために多くの改良が行われた。しかし、基本的な部分の変更はない。 研究用原子炉の燃料は目的に応じていろいろな形状および材料が用いられているが、多くの研究炉に採用されている板状燃料集合体の形状を図2に示す。この燃料は当初U-Alの金属間化合物をAl素地に分散させたものであったが、軍事用に転換され得る高濃縮Uを使わないようにするという世界的な取り決めのため、単位体積中のU量を大きくできるU-Siの金属間化合物が使用されるようになった。被覆には、燃料や冷却材との両立性がよいAl合金を使用しているが、この材料は加工性がよいので、除熱しやすい板状にして使用されることが多い。 <図/表> 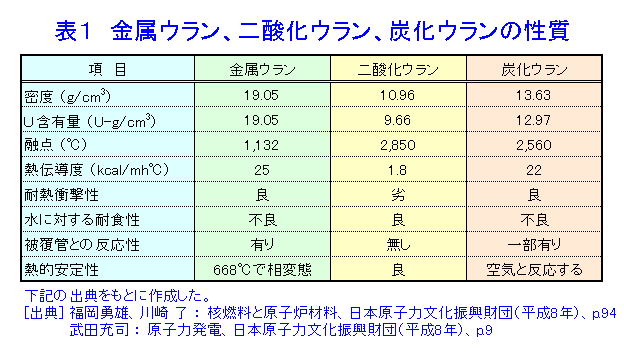
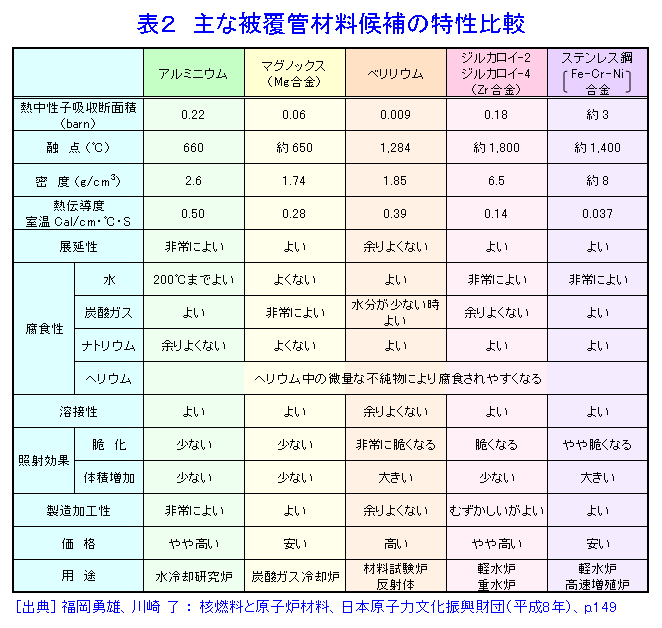
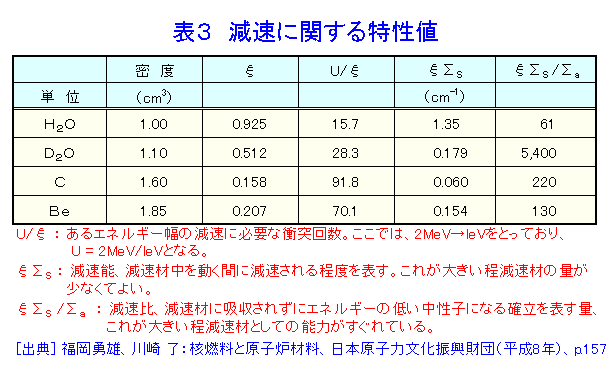
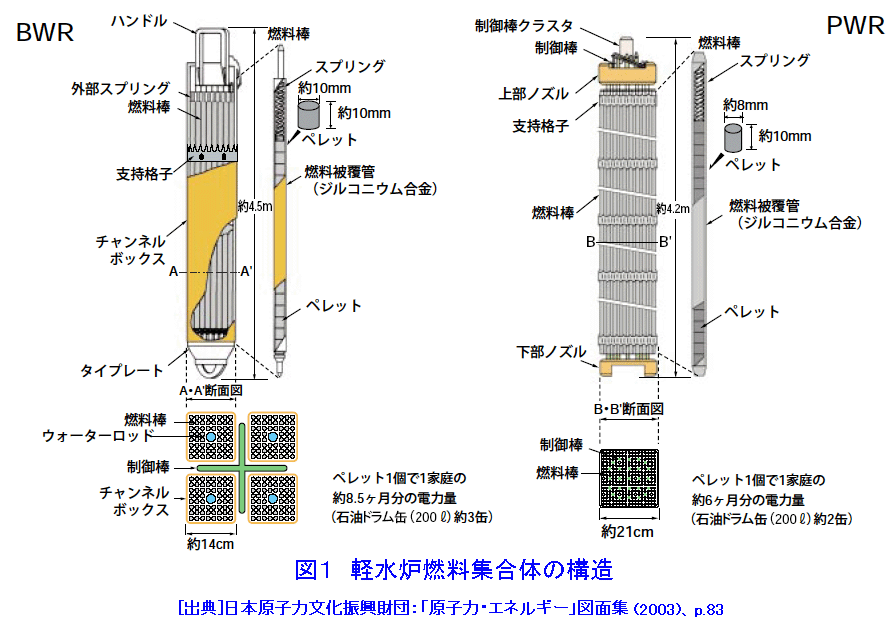
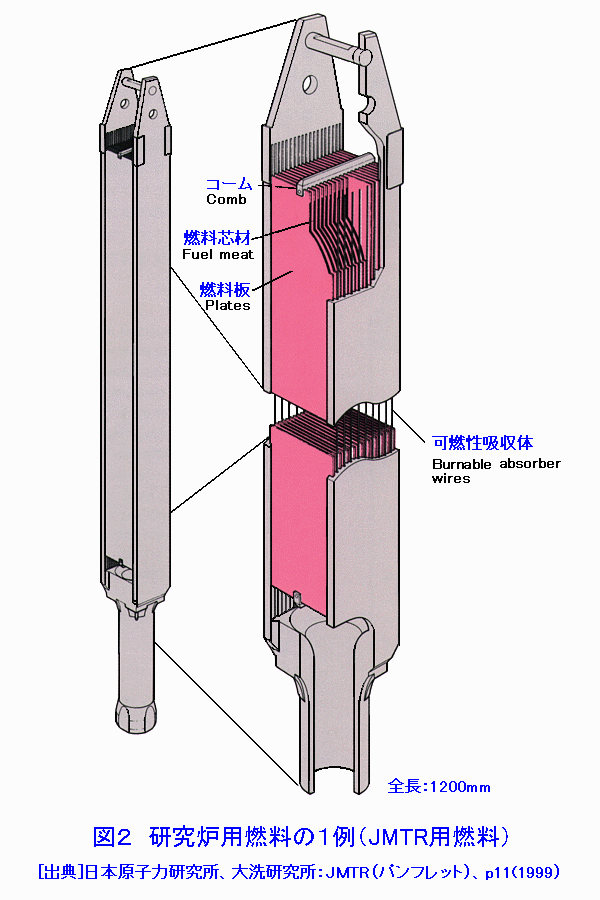
<関連タイトル> 原子核と核反応 (03-06-01-03) BWR用ウラン燃料 (04-06-03-01) PWR用ウラン燃料 (04-06-03-02) <参考文献> (1)福岡勇雄、川崎了:核燃料と原子炉材料(平成8年)日本原子力文化振興財団 (2)武田充司:原子力発電(平成8年)日本原子力文化振興財団
|

