|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
プルトニウムには質量数が232から246までの多数の同位体が知られており、そのすべてが放射性である。同位体の中には239Puのように核分裂を起こしやすいものが多く、またアルファ線を放出するα放射体であることが多い。239Puは、物理的半減期が24,100年と長く、人体内での生物学的半減期も骨からのそれが50年に近いなど他の元素に比し長い。また、アルファ線は生物効果が大きいこともあって、プルトニウムの毒性は高いといえる。これらのことにより、プルトニウムの取扱いについては、内部被ばくを防止するため、細心の注意をもって行われている。 <更新年月> 2007年10月
<本文>
1.プルトニウムの物理的性質 プルトニウムは、原子炉内で主として238Uの中性子捕獲によって生成され、さらに次々と同位体が生成されてゆくが、その中で放射線管理上問題となる同位体は、236Pu、238Pu、239Pu、240Pu、241Pu、242Puおよび243Puの7核種である。代表的なプルトニウム同位体の性質を表1に示す。これらの同位体で特に問題視される核種は、最も大量に生成され、熱中性子による核反応を起こしやすい239Puである。239Puはα崩壊する核種であり、半減期約24,100年で235Uに変換してゆく。原子炉のプルトニウム燃料としては、化学的に最も安定な二酸化プルトニウムにして用いる。この酸化物の密度は約11.5g/cm3、融点は2,300℃で、水にはほとんど溶けない。 239Puは主としてエネルギー約5MeVのα線を放出し、同時に娘核種から平均エネルギー17keVのLX線(L殻電子の放出に伴って発生する特性X線)が放出される。他の同位体もほぼ類似のエネルギーの放射線を放出しており、プルトニウムの肺沈着量の推定の際には、このLX線放出率を同位体ごとに正確に測定することによってその源となる同位体の存在比を明らかにしている。なお、241Puはβ崩壊し、約14年という短い半減期で娘核種241Amになる。241Amもほぼ同じエネルギーのα線とLX線を放出しているが、さらに59.6keVのγ線も放出している。肺モニタによる肺沈着プルトニウムの定量は、このプルトニウムLX線と、プルトニウムと類似した体内挙動を示す241Amのγ線を検出することによって行われている。 2.プルトニウムの体内での挙動 プルトニウムの体内への摂取・侵入経路は3つある。吸入摂取、経口摂取および傷口のある皮膚を介しての血中への侵入である。ここでは、通常に見られる侵入経路である吸入摂取および経口摂取後のプルトニウムの体内挙動について述べる。各種の放射性元素の体内残留の比較(ネズミの実験結果)を図1に示す。 (1)吸入摂取 原子炉やプルトニウム取り扱い施設で事故が発生し、プルトニウムを含む化合物が直径100〜0.1μm程度の微粒子の粉塵(エアロゾル)となって、室内雰囲気または屋外大気中に飛散し、浮遊した場合、その場の空気を吸入することにより人はプルトニウムを体内に取り込む。特にプルトニウム取り扱い施設などの職場環境では、食品の摂取が禁止されていることもあり、摂取経路として吸入摂取が重要である。 肺に沈着したプルトニウムの体内での挙動は、そのプルトニウム粒子側の要因と、吸入する人体側の要因の影響を受ける。粒子側の要因としては物理的特性(特に粒子サイズ)、化学形(特に体液への可溶性)が重要であり、人体側要因としては吸入条件(特に吸入時間)、各個人の生理機能(特に年齢および呼吸率)などである。挙動の概略は以下のようである。 吸入したプルトニウム粒子は、その一部がそのまま呼気として吐き出されるが、多くは呼吸器系(鼻咽頭、気管、気管支、肺胞領域)に沈着する。鼻咽頭領域に沈着した粒子はそのまま体外に出され、気管気管支に沈着した粒子の多くは繊毛運動により咽頭まで運ばれた後に嚥下され消化管に入る。肺胞領域などを中心に呼吸器系に残留したプルトニウム粒子は年単位の有効半減期でゆっくりと吸収され、体内に移行する。肺組織から吸収されて体内に移行する割合は、可溶性の高い化合物などで1千分の1以下、不溶性の酸化プルトニウムなどでは10万分の1以下と小さい。 この体内に移行し吸収されたプルトニウムの体内動態を図2に示す。そこでの速度定数を表2に示す。プルトニウムは全身に分布するが、主要な行き先は肝臓と骨格であり、骨格では骨の表面部に沈着する。これらのプルトニウムは最終的にゆっくりと糞および尿中に排泄される。すなわち、吸入により肺に沈着したプルトニウム化合物は、年の単位で肺に残留し、その間にごくわずかの量が体内に吸収され、その最終の落ち着き先は主として肝臓と骨格であると言える。この間、それぞれの組織は長い期間にわたってα線照射を受けることになる。 このようなプルトニウムの体内動態から、たとえば成人が1Bqの酸化プルトニウム(239Pu)を吸入した場合についてみると、肺、骨表面および肝臓の線量が他の臓器に比し高く、実効線量は16μSvと計算される。 (2)経口摂取 (表3参照) 同じプルトニウムでも経口摂取される場合には、吸入摂取に比べ危険度が低いといえる。すなわち、粒子状のプルトニウムはもとより、食物や飲料水中のプルトニウムも概して水や体液に溶けにくく、経口摂取されても胃腸管からの吸収率が低い。胃腸管でのプルトニウムの吸収割合は、可溶性の比較的高い硝酸塩で1千分の1以下、不溶性の酸化物では10万分の1以下と非常に小さい。胃腸管で吸収されなかったプルトニウムの大部分は直接糞中に排泄される。この吸収割合で体内吸収されたプルトニウムは、吸入摂取され体内に吸収されたプルトニウムと同様の挙動をする。経口摂取の場合には、骨表面と肝臓の線量が高いが、吸入摂取のときに高かった肺の線量は低い。成人が1Bqの239Puを経口摂取した場合を考えると、実効線量は0.97μSvと計算される。上記の吸入摂取時に値の165分の1と大幅に低いことが分かる。 3.環境に放出されるプルトニウム粉塵 事故時に、環境に放出されるプルトニウム粉塵の挙動は、密度の低い可溶性の他の核種と比較すれば次のとおりである。 a)密度が高いため、大気中でも水中でも沈降速度が大きくあまり遠くへは広がらない。チェルノブイリ原発事故時のプルトニウムの環境への規制値(3.7GBq/km2)を超えた飛散範囲は30km以内であり、セシウム、ヨウ素などがヨーロッパにまで拡散したのと大きな違いがある。 b)ほとんど水に溶けないため、広い範囲に浸透、拡散してゆかないと同時に海産物・農産物にはほとんど吸収されず、またそれらを経口摂取しても体内吸収は極微量で、一般的には危険性は必ずしも高いものではない。 c)大地に降下したプルトニウム粉塵は風による再飛散の可能性が高く、吸入汚染の心配も高いため、場所によっては表土の処理が必要となる。事故後の環境汚染チェックには細心の注意が必要である。 4.まとめ プルトニウムは水や体液に溶けにくく、人体中での挙動はゆっくりとしている。経口摂取の場合には体内への吸収率は低く、そのほとんどが糞中に排泄される。しかし、吸入摂取されると一部が肺の中にとどまり、ゆっくりと吸収される。吸収されたプルトニウムは骨格と肝臓に分布し、それら臓器からの排泄もきわめてゆっくりしている。このように体内からの排泄に時間がかかること、ならびにプルトニウムが放射線生物効果の高いアルファ線を放出することから、単位放射能あたりの実効線量値が高く、その意味で毒性の高い放射性核種であるといえる。プルトニウムを取り扱う場合には、このことに十分留意する必要がある。 (前回更新:2003年2月) <図/表> 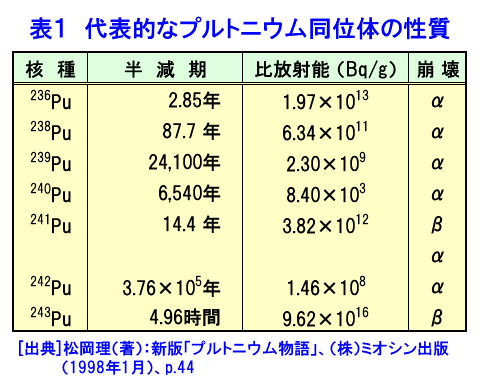
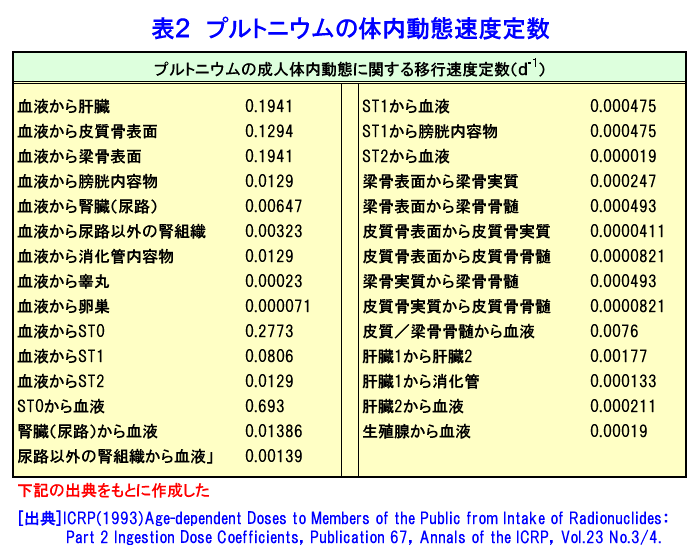
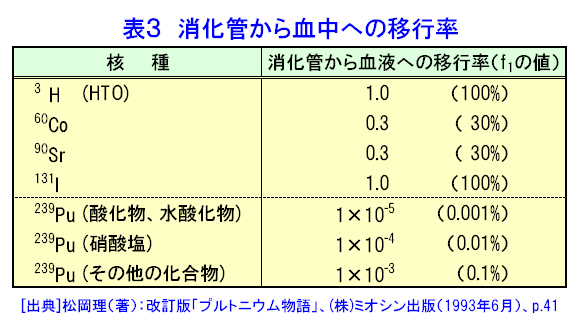
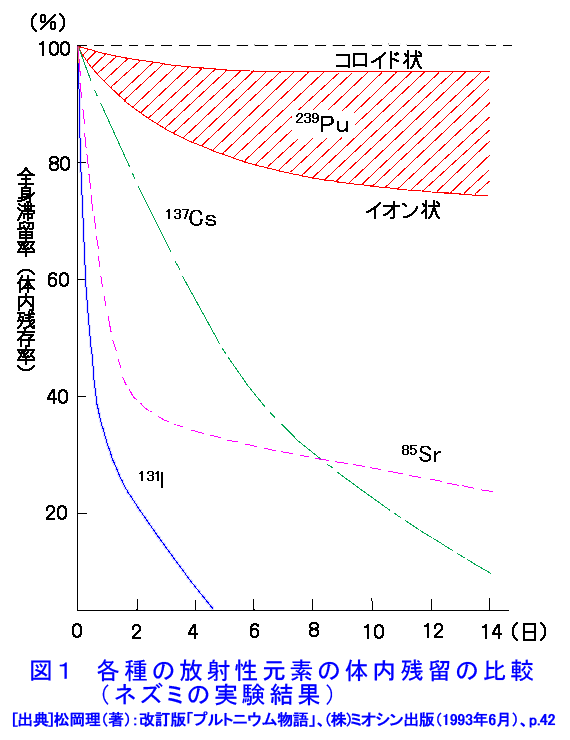
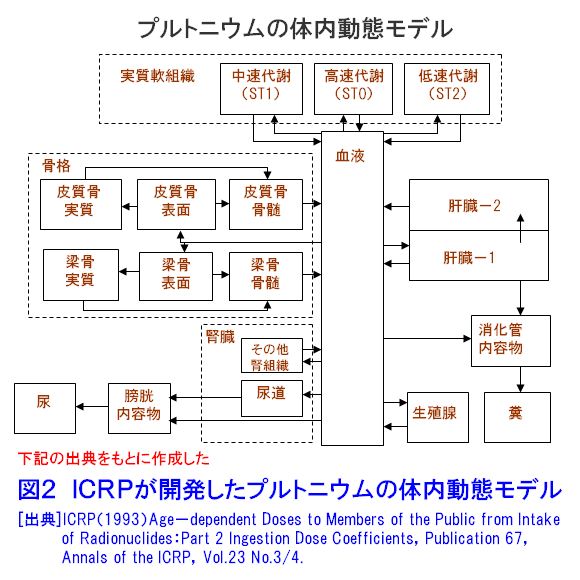
<関連タイトル> プルトニウムの毒性と取扱い (09-03-01-05) プルトニウムの放射能濃度測定 (09-04-03-23) <参考文献> (1)松岡理(著):新版「プルトニウム物語」、(株)ミオシン出版(1998年1月) (2)ICRP(1986)The Metabolism of Plutonium and Related Elements,ICRP Publication 48. Annals of the ICRP,Vol.16 No.2/3. (3)ICRP(1989)Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides:Part 1 Ingestion Dose Coefficients,Publication 56,Annals of the ICRP,Vol.20 No.2. (4)ICRP(1993)Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides:Part 2 Ingestion Dose Coefficients,Publication 67,Annals of the ICRP,Vol.23 No.3/4. (5)ICRP(1995)Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides:Part 4 Inhalation Dose Coefficients,Publication 71,Annals of the ICRP,Vol.25 No.3/4. (6)松岡理(著):改訂版「プルトニウム物語」、(株)ミオシン出版(1993年6月)
|

