|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
日本にあるプルトニウム燃料製造施設は、現時点では核燃料サイクル開発機構、東海事業所(現日本原子力研究開発機構・核燃料サイクル工学研究所)にあるプルトニウム燃料センターのみである。同センターにはプルトニウム施設は3種類あるが、製造を目的とした施設は、第二開発室および第三開発室で、前者では製造工程の機械化が相当程度図られ、後者ではコンピュータ制御により自動化されている。 プルトニウム燃料施設の製品は、いずれもウランとプルトニウムの酸化物を混合して成型加工した混合酸化物燃料で、高速実験炉「常陽」、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」および新型転換炉原型炉「ふげん」に供給されている。平成16年度第2四半期までに約170tMOXの混合酸化物燃料を製造した。 なお、MOX燃料の商業用燃料加工事業については、平成12年11月から、日本原燃株式会社が、青森県六ヶ所村に新規立地のための建設計画を進めている。 <更新年月> 2004年12月
<本文>
1.日本のプルトニウム燃料製造施設建設の経緯 原子力発電規模の増大とともに、日本国内の発電炉で生成されるプルトニウムは、年々増えている。日本の原子力開発は、使用済燃料を再処理してこのプルトニウムを取出し、再び核燃料として有効利用すること基本路線としている。 日本におけるプルトニウム取扱施設は、当初日本原子力研究所(原研)・東海研究所(現日本原子力研究開発機構・原子力科学研究所)に建設され、プルトニウムや燃料の物理的化学的性質や原子炉物理等の基礎的研究が実施されてきた。昭和36年(1961年)原子力開発利用長期計画には、上記基本路線に基づきプルトニウムの熱中性子炉および高速増殖炉への利用を目標として、原研と原子燃料公社 (元、核燃料サイクル開発機構(現日本原子力研究開発機構))が協力して開発を推進すべきであることが示され、燃料の製造開発については原子燃料公社が分担することになった(文献1)。 この基本計画に基づき、動力炉・核燃料開発事業団(元、核燃料サイクル開発機構(現日本原子力研究開発機構))の東海事業所では、昭和40年(1965年)にプルトニウム燃料第一開発室を米国からの技術導入により完成し、プルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料の「基礎物性」、「燃料設計」、「MOX燃料製造技術の確立」等に必要な、各種の試験・研究を実施してきた。この成果は純国産で建設した、その後の本格的なプルトニウム燃料製造施設である第二開発室や、さらに一歩進めて完全自動化した第三開発室に繋がっている。図1にプルトニウム燃料取扱い施設の流れを示す。 2.日本のプルトニウム燃料製造施設の概要 第一開発室は、当初ペレット燃料の試作と共に、ゾル・ゲル法による振動充填燃料の試作も行われたが、現在では、高速炉用MOX燃料の性能および経済性を向上の開発として、中空燃料ペレット製造技術開発、ショートプロセス開発および粒子燃料開発などの研究・開発を行っている。特に量産規模のMOX燃料製造施設を想定したショートプロセスは、溶液段階で製品燃料仕様のPu/Uに混合し、MH転換法(硝酸プルトニウム溶液と硝酸ウラン溶液を混合し、マイクロ波加熱によってPuO2−UO3脱硝体にし、その後、水素雰囲気中で焙焼還元して、PuO2−UO2粉末とする方法)で流動性の良い粉末を製造して直接ペレットに成型し、大幅なコスト低減化を図っている。また、第一開発室では、燃料の物性測定、分析技術の高度化、燃料設計技術の開発、プルトニウム施設の安全解析などが行われている。 わが国最初のMOX燃料製造施設である第二開発室は、第一開発室の技術成果に基づき昭和47年(1972年)に完成し、同年4月からの重水臨界実験装置用燃料(DCA)に続いて、高速実験炉「常陽」の炉心燃料、新型転換炉原型炉「ふげん」燃料および敦賀1号炉のプルサーマル照射用燃料の製造が行われた。新型転換炉原型炉「ふげん」の燃料製造を行ってきた第二開発室におけるMOX燃料の製造は、平成13年11月(2001年)をもって終了し、現在は施設内に保管している核燃料物質を再利用するための回収処理作業を行っている。 引き続いて、高速増殖炉用および新型転換実証炉用の混合酸化物燃料の製造を目的として、昭和57年(1982年)より第三開発室の建設工事が進められ、高速増殖炉用混合酸化物燃料を製造する施設が昭和62年10月(1987年)に完成し、昭和63年10月から「常陽」燃料の製造を開始、昭和64年10月より「もんじゅ」燃料の製造を開始した。なお、新型転換炉実証炉用燃料製造施設は、平成7年8月(1995年)に原子力委員会によって新型転換炉実証炉計画の中止が決定されたため、設計のみで終了した。 「常陽」および「もんじゅ」用燃料製造は、3種類(MOX、PuO2、UO2)の原料粉末を混合し、成形、焼結工程などを経て燃料ペレットを製作する。この燃料ペレットを被覆管に充填し燃料要素とし、「常陽」用では127本の燃料要素を束ねて1集合体、「もんじゅ」用では169本の燃料要素を束ねて1集合体とする。図2に「常陽」および「もんじゅ」の高速増殖炉用MOX燃料製造工程フローを示す。 「ふげん」用MOX燃料製造は、3種類(MOX、PuO2、UO2)の原料粉末を混合し、成形、焼結、研削工程などを経て2種類のプルトニウム濃度の燃料ペレット(高富化度、低富化度)を製作する。同じ種類の富化度の燃料ペレットを被覆管に充填して燃料要素とし、これを同心円状に内層4本、中間層8本(それぞれ高富化)、外層16本(低富化)の計28本を束ねて、燃料集合体とする。図3に新型転換炉実証炉用MOX燃料製造工程フローを示す。なお、燃料製造における品質検査は、燃料ペレット、燃料要素、燃料集合体の各段階で適宜実施される。 プルトニウムの安全取扱技術の一つとしては、グローブボックスの導入が挙げられる。第一開発室では、グローブボックス内に収納された機器を運転するため、頻繁なグローブ操作を必要とし、燃焼度の高い軽水炉使用済燃料からのプルトニウムの利用に当たって作業員の被ばく量の増大が懸念された。そしてある程度の量産を必要とする第二開発室の設計に当たっては、機械化、遠隔操作化を大幅に採用することとした。 ペレット製造工程では、最優先として先ずグローブボックスへの張りつき時間の長いペレットの外径や密度の検査装置が、装置自動化の開発の対象として取り上げられ、次いで、プレスは機械化されていてもその後の長時間の操作を要するグリーンペレット(焼結前のペレット)の皿への整列などの工程装置の機械化が図られた。その後、装置の入れ替え更新等を経て、核物質の搬送のための容器への充填、排出機構などが、機械化された。 また、燃料棒加工工程でも、燃料棒検査工程のガンマ線検査(ガンマ・スキャン)や高速炉用のワイアスペーサの自動巻き等が最初に自動化され、ペレット充填・端栓溶接工程でも清浄域と汚染域を明確に分けて作業の効率化が図られた。 第三開発室は、国際的に厳しくなったプルトニウムに対する安全対策を盛り込んで環境への放射能放出低減と被ばくの低減を図り、かつ上記のような第二開発室の機器開発の経験を生かし、進歩したコンピュータ技術を取り入れて、自動化、遠隔制御技術をほぼ全面的に工程に採用することによって、安全性と生産効率の向上の両者を大幅に改善した施設である。第三開発室における図4にMOX燃料製造工程を示す。 また、工程機器の自動化以外に特に注目すべき点として、 図5に示すような中間貯蔵庫の採用とそれに伴うグローブボックス( 図6参照)の採用が挙げられる。すなわち、核物質は中央に遮へいされたペレットおよび中間製品を一時貯蔵する中間保管庫を置いてその両側に搬送トンネルで接続された製造設備を内装したグローブボックスを櫛の歯状に配置した構造とし、工程の流れをスムーズにしたこと、各工程の終了時には核物質は中間保管庫に入るので、設備のメンテナンス時の被ばく線量が著しく低減し、設備の更新および新増設を容易にしたことである。このシステムにより自動化施設の計量管理および検認の容易さ、保障措置の適用の容易さなどのメリットが生まれた。 3.日本国内におけるプルトニウム燃料の生産量 表1に各施設の製造能力を、図7に平成16年度第2四半期(2004年)までのプルトニウム製造量に示す。混合酸化物燃料の累積製造量は、平成12年12月末までに約167tMOX(5.6tPu)、平成16年第2四半期までに約170tMOXである。内訳は、ふげん: 約139tMOX(Pu含有率約2%)、常陽: 約8tMOX(Pu含有率約18〜30%)、もんじゅ: 約10tMOX(Pu含有率約20〜30%)、DCA: 約12tMOX(Pu含有率約1%)、英国SGHWR照射試験用: 約2tMOXになっている。 このうち、特に第二開発室で製造された「ふげん」の燃料は累計で約139tMOX、772体、ペレット収率90%以上という高効率である。高速炉および熱中性子炉を含めて、単一の炉のためにこれだけの量のMOX燃料を製造した例は欧州の先進国でも現在まで見当たらない。 また「ふげん」のプルトニウムには、核燃料サイクル開発機構東海再処理工場で軽水炉燃料から回収したプルトニウム(昭和59.5)や、「ふげん」自身の使用済MOX燃料から回収したプルトニウム(昭和63.5)が再利用された。なお、新型転換炉原型炉「ふげん」はプルサーマル計画の進展、ATR実証炉建設の遅延、経済性などを理由に2003年3月で運転を終了した。 また、プルサーマル計画で使用するMOX燃料の商業用燃料加工事業については、平成12年11月から、日本原燃株式会社が、青森県六ヶ所村に新規立地のための建設計画を進めている。最大加工能力は年間130tで、操業人員300人、総工費約1200億円、2009年運転開始の予定である。 <図/表> 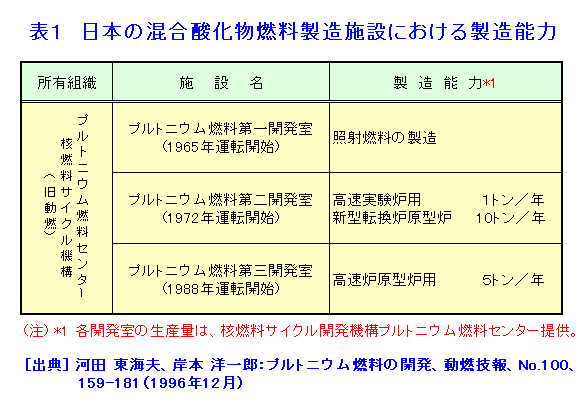
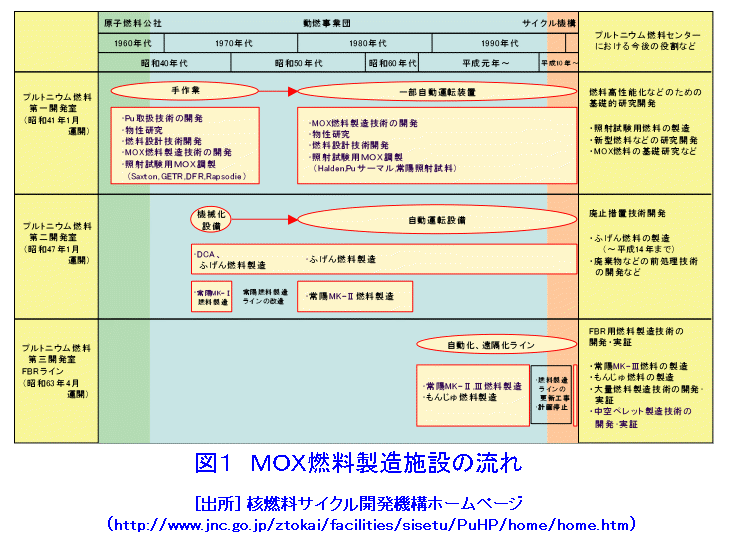
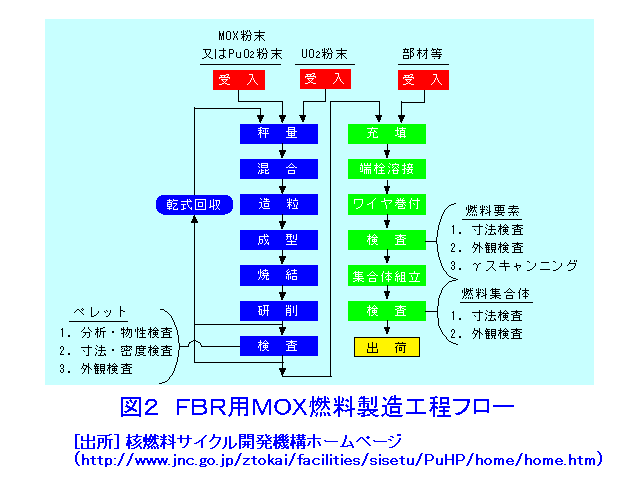
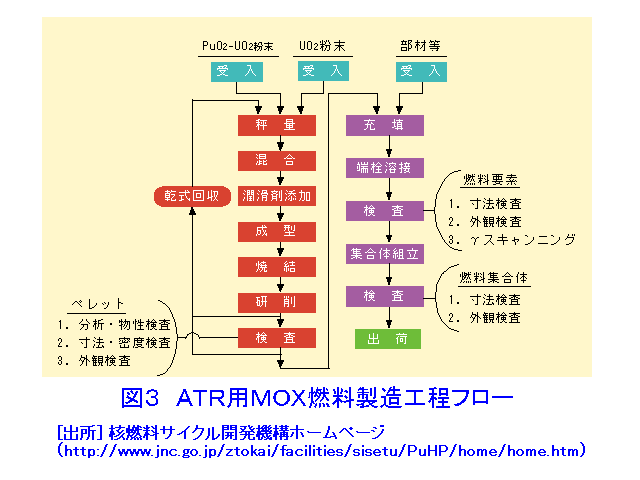
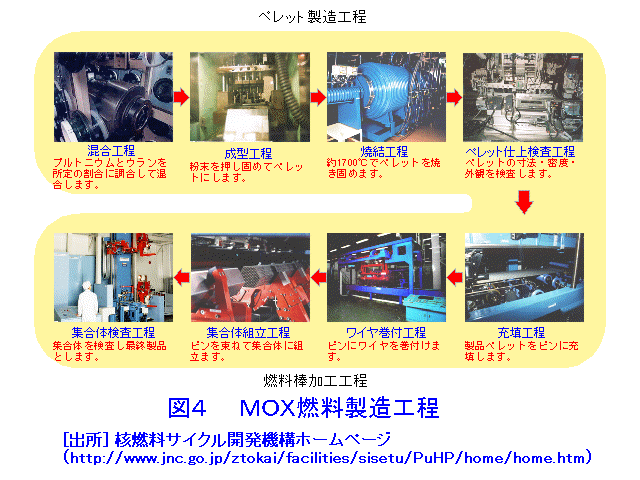
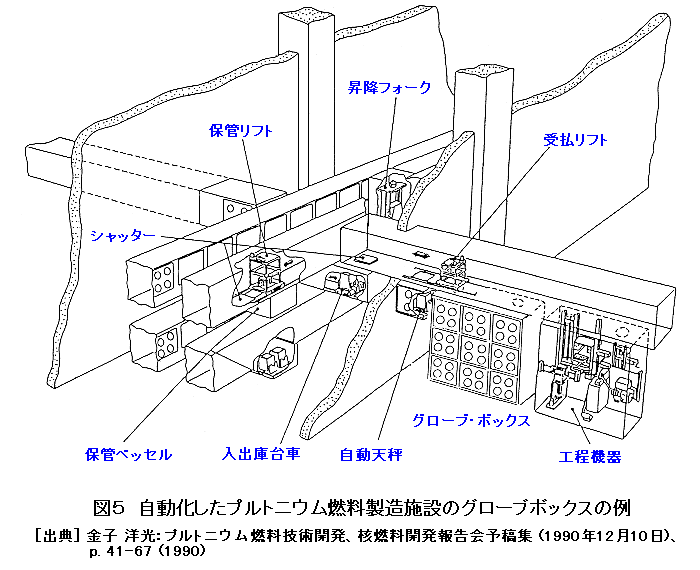
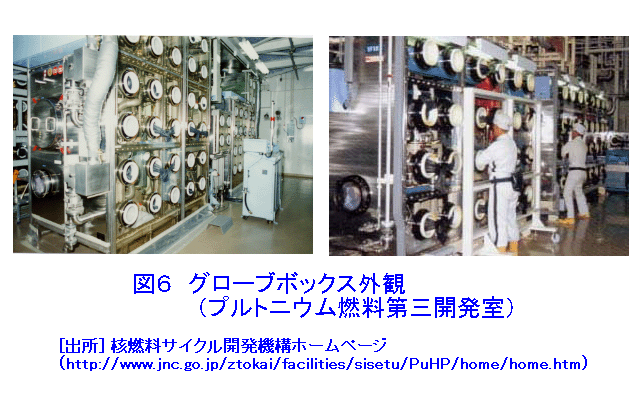
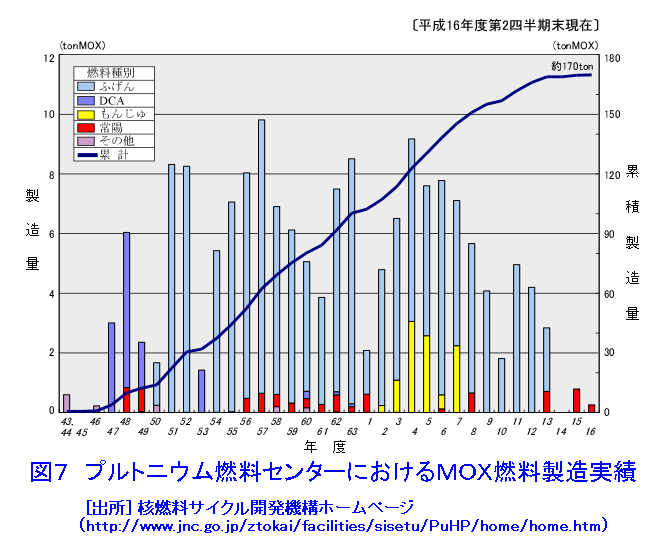
<関連タイトル> 海外のプルトニウム燃料製造施設 (04-09-01-06) <参考文献> (1)動力炉・核燃料開発事業団:動燃三十年史、p.276 (1998) (2)三島 良績(編著):核燃料工学、同文書院(1972年10月) (3)金子 洋光:プルトニウム燃料技術開発、核燃料開発報告会予稿集 (1990年12月10日)、p.41−67 (1990) (4)河田 東海夫、岸本 洋一郎:プルトニウム燃料の開発、動燃技報、No.100、p.159−181(1996年12月) (5)核燃料サイクル開発機構ホームページ (6)飯島隆、片野好章、久芳明慈、清水武範:プルトニウム利用技術の確立及び実証、サイクル機構技報、No.20別冊−3、p.27−62(2003年9月)
|

