|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
2度の石油危機を経験した先進消費国では、省エネルギー、石油から非石油への最終需要の燃料転換、石油代替エネルギーの開発導入などの対策をとり、石油需要はほぼ横ばいで推移した。それにより、原油価格は比較的安定した推移を示していた。近年、生産国は、協調減産による生産調整の動きを示しており、原油価格は、上昇傾向にあリ、特に2004年以降諸要因の複合的作用により大きな変動を繰り返しながら原油価格は高騰し、高い水準で推移している。環境保護による石油供給の不安定化と石油需要の増大に向かっている可能性が強く、今後とも先進消費国では、従来の政策を堅持していくことが重要である。 <更新年月> 2005年08月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.生産国の政策 1.1 OPECの動向 1960年9月ベネズエラと中東四か国が石油輸出国機構(OPEC)を設立した。当初は、石油の公示価格が低下し、石油収入が減少するのに対抗する手段として設立されたものであった。これによって公示価格の決定は、石油企業と産油国の協議事項となり、1960年代は公示価格は不変であったが、同年代後半には石油需要が拡大し、加えて、米国の石油生産の頭打ちによって原油供給が逼迫し産油国の地位を相対的に強化し、1967年の中東戦争勃発直後の石油の禁輸措置の効果とともに、1970年以降のOPEC台頭の伏線となった。その後1973年に第4次中東戦争が勃発し、同年10月17日OAPEC(アラブ石油輸出国機構)は緊急閣僚会議を開催し、アラブの石油の生産制限を決定した。いわゆる第一次オイルショックである。さらに1975年から1976年にかけて、油田を国有化し原油価格決定権を取り戻した。1979年2月イランに革命政権が成立し、イランの原油生産は殆どストップした。いわゆる第二次石油危機の始まりである。1980年9月にはイラン・イラク戦争が勃発し、OPECは石油価格を引き上げていった。 一方、2度の石油危機の経験から、OECD(経済協力開発機構)諸国を中心として、省エネルギーの推進、石油代替エネルギーの導入が進められ、石油消費量は1980年〜80年代半ばまではおおむね漸減ないしは横ばいの傾向で推移した。また、1980年代後半には、北海油田やアラスカ油田など非OPEC諸国の増産による石油の需給緩和のため、OPEC諸国の中には、公式販売価格に違反して、値引き販売を行う加盟国が続出した。この結果OPECの価格カルテルとしての力は弱体化した。この間に、1976年12月OPEC総会での二重価格の決定以来、穏健派のサウジアラビアと強硬派のイラン、リビアが対立し、OPECの結束力は弱まった。原油価格が市場取引によって決定されるようになり、OPECは、生産量の調節により、間接的に価格に影響を及ぼす生産カルテルに変質した。OPECは1982年以来、OPEC全体で原油の国別生産枠を設け、サウジアラビアを調整役として生産の調整を図ってきたが、収入の増加を図るための生産枠の違反が恒常的に起こっていた。また、国連制裁の部分解除により、イラク原油がOPECの政策外で増産されるようになったこと等から、OPECの、生産調整を行うカルテルとしての性格も急速に薄れた。1992年9月以来、南米のエクアドルが、1996年6月にはアフリカのガボンが、OPEC脱退を表明した。1997年以降は、原油価格の大幅な下落に耐えられなくなり、非OPECとともに協調減産(石油市場の安定化を目指した減産・増産政策)に踏み切っている。 1.2 イラク原油 1990年8月のイラク軍のクウェート侵攻に対し、国連は直ちに経済制裁として対イラク全面禁輸を実施したが、1991年2月の停戦から間もなく、同年9月には、国連安保理は、イラクが食糧、医薬品を緊急輸入する財源策として6か月間で16億ドル分の石油輸出を認める決議を採択した。1996年12月、ガリ国連事務総長がイラク原油の禁輸措置部分解除を認める最終報告書を国連安保理に提出し、原油輸出は約6年半ぶりに再開された。この限定的石油輪出は、半年間で20億ドル分の石油を国連の管理下で輸出し、その代金を食糧、医薬品などの人道物資購入等に充当するというものである。1998年5月、国連は、1998年6月からの第4期の輸出計画について、半年間で52億ドル分の石油輸出を認める暫定輸出枠拡大を承認した。また、1998年6月には、最高3億ドルの石油生産設備修復用スペアパーツの購入を承認している。その後は、第5期、第6期輸出計画(1999年6月〜12月)と、同じ条件で輸出が続いており、輸出量は200万バレル/日を超える規模となって、世界の供給全体に一定のポジションを占めた。2003年2月までは約250万バレル/日の原油生産量を記録していたが、同年3月20日の米軍主導のイラク攻撃開始に伴い、4月には約15万バレル/日まで低下した。2004年3月には250万バレル/日まで回復したが、4月以降低下し、8月には179万バレル/日となった。BP統計2004によれば、2003年の生産量は約133万バレル/日となっている。 1.3 北海・中南来など非OPEC産油国の増産 1980年代から1990年代を通じて国際石油会社の技術進歩をもとに、北海油田、中南米、西アフリカ等、非OPEC産油国の増産は顕著に進んだ。これら非OPEC産油国の増産は、OPECの生産抑制や米国、旧ソ連の減産を埋めてなお余りある状態であり、原油価格の上昇にブレーキをかけた。 北海油田は、1980年代から生産の限界が近いといわれながらも、次々と新規油田を開発するとともに、回収率向上により、生産量を伸ばしてきた。北海では、生産施設やパイプラインの共有化、小規模油田の大規模油田への連結・集約による操業費の節約、地震探鉱技術の高度化、水平掘削技術の高度化等により、原油価格が10〜15ドル/バレル程度でも、利益が確保できる体制になったとされている。2003年の生産量は513万バレル/日となっている。 中南米産油国は、石油産業の国有・国営政策を1990年前後より見直し、上流部門への外資導入、国営石油企業の改革、民営化を推進してきている。ブラジルでは民営化は他国より遅れているものの、深海での開発が積極的に行われており、原油生産量、埋蔵量ともに増加している。2003年の生産量は155万バレル/日である。 西アフリカは、北アフリカとともに豊富な原油埋蔵量を有する地域であり、政治的なリスクを伴いはするが、大手石油会社を中心に積極的な探鉱、開発が進められてきた。アンゴラ、コンゴ、赤道ギニア等での原油の探鉱、開発が1980年代後半から盛んとなっており、最近では、これら諸国の深海域での開発も進められてきている。 ベトナムでは、1986年の「ドイモイ」(刷新)と呼ばれる新経済政策により対外開放が進み、石油・ガス産業が有力な外資獲得産業になるとの認識から、1988年に政府が探鉱、開発の活発牝のため、外国企業の参加を呼びかけて一定の成果を収めた。2003年には37万バレル/日を記録した。また、オーストラリアでも、北西大陸棚(西オーストラリア沖合)およびティモール海峡を中心とした地域での探鉱、開発が盛んとなった。 1.4 旧ソ連地域の動向 旧ソ連は、戦後、着実に原油生産を伸ばし、1987年には、1,250万バレル/日にも達し、全世界生産量の2割以上を占めるに至った。しかし、1988年以降は減退傾向にあり、1998年は738万バレル/日(うちロシア618万バレル/日)となっている。ロシアは既存油田の老朽化、資機材の不足、国内需要の減退、資金不足の深刻化等を背景に減産傾向が継続している。2000年にプーチンがロシア大統領に選出されて以来の政治的安定、ルーブル安による投資コスト低下および原油価格の高騰により、ロシアの石油生産は驚異的な回復し、2004年には919万バレル/日に達した。カザフスタンは、旧ソ違では第2位の原油生産国であるが、1992年以降減少に転じ、現在は約54万バレル/日の生産水準で推移している。第3位のアゼルバイジャンも、1988年以降減少を続けており、生産水準は24万バレル/日程度である。 これらカスピ海周辺地域は、サウジアラビアに匹敵する規模の埋蔵量をもつと見込まれ、メジャーズを始め外資の関心が急速に高まってきた。カザフスタン、アゼルバイジャンとも、外資受け入れの法整備がなされ、既発見未開発油田を中心に外資との生産分与井(PS)契約が成立している。 1.5 産油国の協調減産 1998年3月、サウジアラビア、ベネズエラ、メキシコの3か国の石油相が会談し、OPECと非OPECが協調して、最大200万バレル/日減産することを呼びかける共同声明を発表した。これを受けOPECは、3月の第104回OPEC臨時総会で、1998年4月以降、合計124.5万バレル/日減産することを決定し、さらに6月の定例総会では、7月以降135.5万バレル/日減産目標を追加した合計260万バレル/日の減産を行うことを決定した。非OPECの国も、相次いで減産ないし輸出削減を約束した。しかし、アジア経済危機の拡大による世界石油需要の低迷などから、原油価格は低迷し、1999年2月には、1986年の価格暴落以降12年ぶりの安値をつけた。これに対し、産油国は再び危機感を強め、1999年3月、OPECと非OPEC産油国で合計210万バレル/日という大幅な追加減産に合意し、産油国はおおむね合意に則った減産を実行し、原油価格は上昇基調に転じた。1999年9月開催の第108回OPEC総会で、現行の減産を2000年3月までは、継続することが決定されたため、原油価格は需要期を控えて高騰し、ドバイ原油スポット価格は、20ドルを超える水準に達した。原油の生産量を図1、生産動向を図2に、貿易量を表1に示す。図3に長期的原油価格の推移を示す。なお、2004年以降、原油価格は大きな変動を繰り返しながら、さらに高騰し高い水準で推移している(図4および表2)。中国をはじめとする世界の石油需要の増加、余剰生産力の低下といった構造的要因と、産油国における供給リスクの顕在化、自然災害等の短期的要因に石油市場に投機資金の流入が加わり、これら諸要因が複合的に作用した結果もたらされたと考えられている。 2.IEA諸国の政策 地球環境間題に対する世界的関心は、1980年代後半から高まり、1988年11月には「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)が設置され、1990年5月には、温室効果ガスの増加が地球の温暖化につながることを明確に認める内容の報告書を発表した。1997年12月に京都で開催された「第3回気候変動枠組み条約締約国会議」(COP3)において、先進国の温室効果ガス排出量を、2008〜2012年の間に1990年対比少なくとも5%削減することを約束する「京都議定書」が採択され、温室効果ガス排出抑制の数値目標が合意された。また、この際には目的達成のための方法に柔軟性をもたせるための措置として、(1)排出権取引、(2)共同実施、(3)クリーン開発メカニズムといった様々な手法が示された。また、すでに排出された温室効果ガスを吸収する技術の開発等、現実的で効果的な手段の開拓が引き続き望まれている。なお、京都議定書は、2004年11月にロシアが批准したことにより、2005年2月16日発行した。 仏、独、日、米、四か国およびIEA全体のGDP(国内総生産)当たりの二酸化炭素排出量の推移を図5に、1人当たりの二酸化炭素排出量の推移を図6に示す。GDP当たりの排出量は定常的なエネルギー消費が飽和しているため、近年減少傾向にあるが、1人当たりの排出量はやや増加傾向にある。図7に仏、独、日、米、伊5か国の単位消費エネルギー当たりの二酸化炭素排出量の推移を示す。フランスは原子力のシェアの増加によっての著しい減少を達成している。ドイツは石炭の利用を減らしているがIEA平均よりは大きい、イタリアは、まだ石油火力の割合が多いので二酸化炭素排出量が多い。 1973年から1997年までの単位消費エネルギー当たりの二酸化炭素排出量と一次エネルギー供給中の化石燃料のシェアの関係を図8に示す。1985年から急速に減少しているのは、石炭のシェアの低下が関係していると思われる。1985年から1997年までの単位消費エネルギー当たりの二酸化炭素排出量と一次エネルギー供給中の石炭のシェアの関係を図9に示す。 多くのIEA諸国は温室効果ガスの低減のため、いろいろの政策を進めてきている。 財政的な方策としては、税制がもっとも一般的である。フランスは、汚染行為に対する税制を中間的なエネルギー消費にも拡大しようとしている。ドイツは環境税の第一歩として、ディーゼル、ガソリン、暖房用石油、電気にエネルギー税を課している。イタリアも、1998年に発電用燃料に新税を導入し、2005年から完全に実施する。イギリスは1999年予算で、気候変動税を導入した。これは事業、農業、および公共部門のエネルギー使用に適用される。発電部門と輸送部門には適用されない。 補助金制度も多く使われ、オーストラリアは、再生型エネルギー供給に基金を創設し、フランスは、エネルギーの効率改善に5億フランの補助金を用意している。 規制や自発的発議も多様である。フランスは1000MWの新風力発電を要求し、日本は意欲的な省エネルギー法を成立させ、自動車にトップランナー方式で高い効率を求める一方、原子力発電の59%増加を求めている。スイス議会は、1999年に法律を制定し、二酸化炭素を2010年までに、1990年水準の10%削減を求めている。米国は連邦政府の消費と排出の削減に力を入れている。2010年までに、政府のビルのエネルギー使用は1985年の水準から35%削減する。エネルギーを使用するビルからの二酸化炭素排出は、2010年までに1990年水準から30%削減する。 多くのR&D政策も採用されている。これは短期には成果を期待できないが、長期的には有用である。例えばカナダの「Technology Early Action Measures」である。これは電気自動車エタノール生産プロセスプロジェクトなどに5千6百万カナダドルを充てている。スウェーデンは輸送部門のR&Dに力を入れている。米国は、クリーンエネルギー技術開発プロジェクトに約14億ドルを充当している。 各国とも、IEAのメンバー国として、IEA ”Shared Goals” に沿って、エネルギー政策を進めている。省エネルギー、石油代替エネルギー開発、石油備蓄という、従来の石油政策に加えて、上述したように、ガソリン、軽油の増税、二酸化炭素税の導入などである。 <図/表> 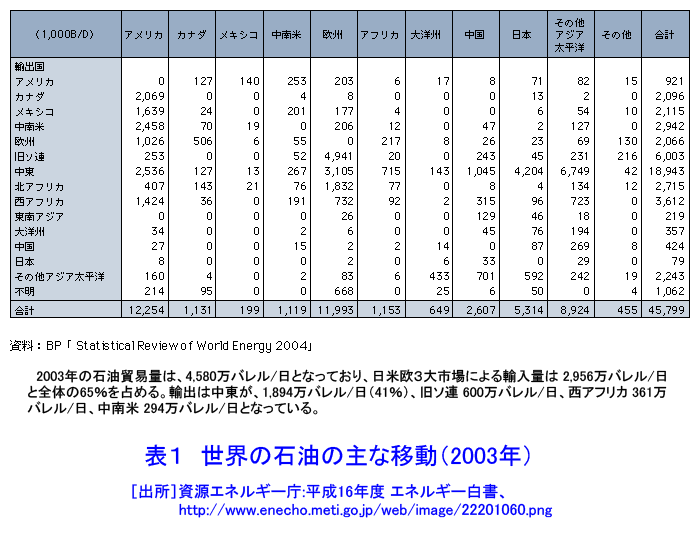
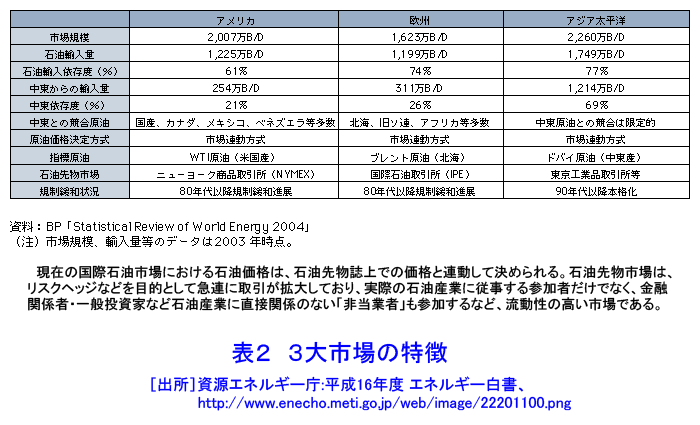
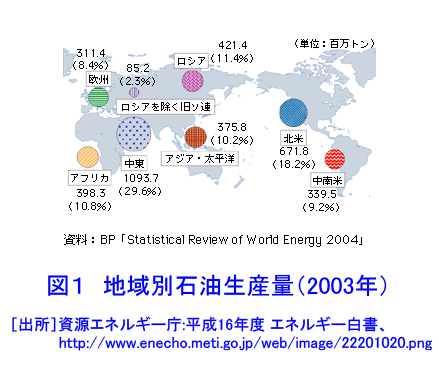
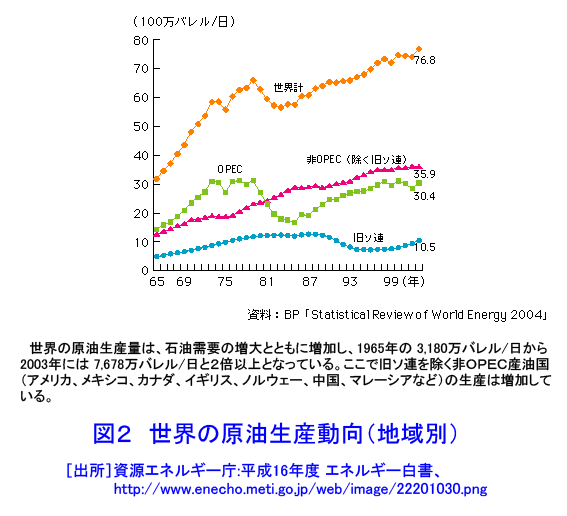
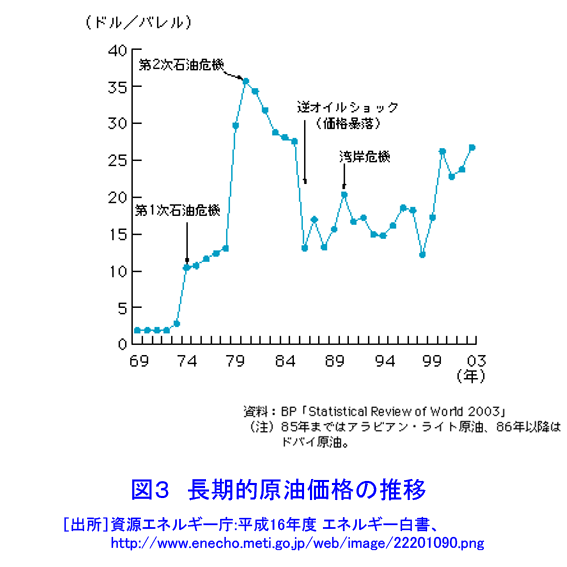
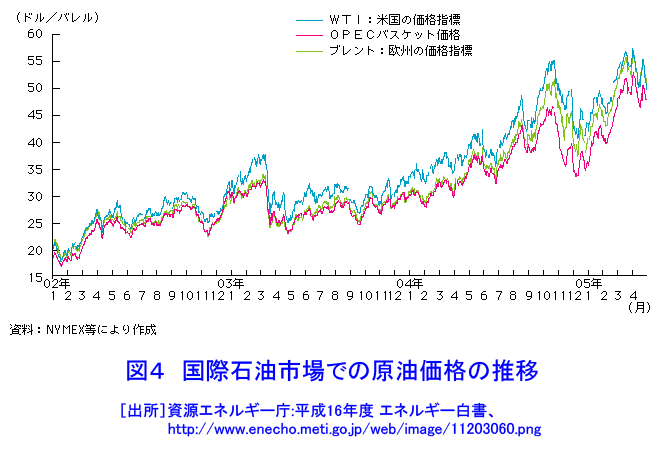
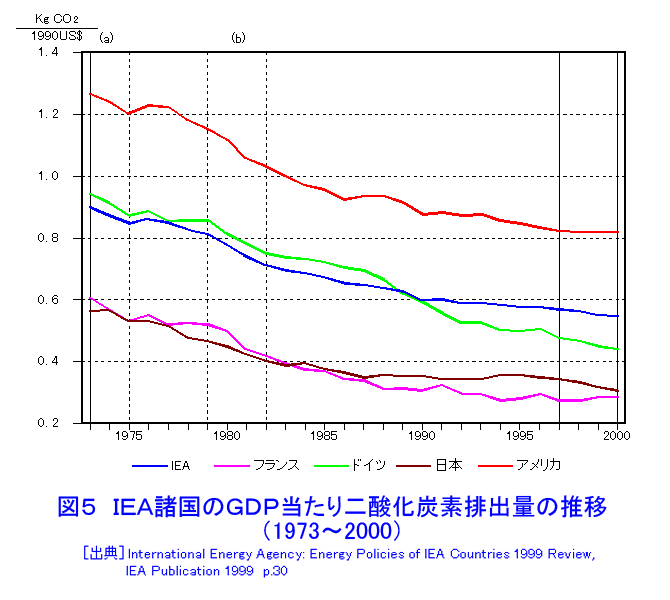
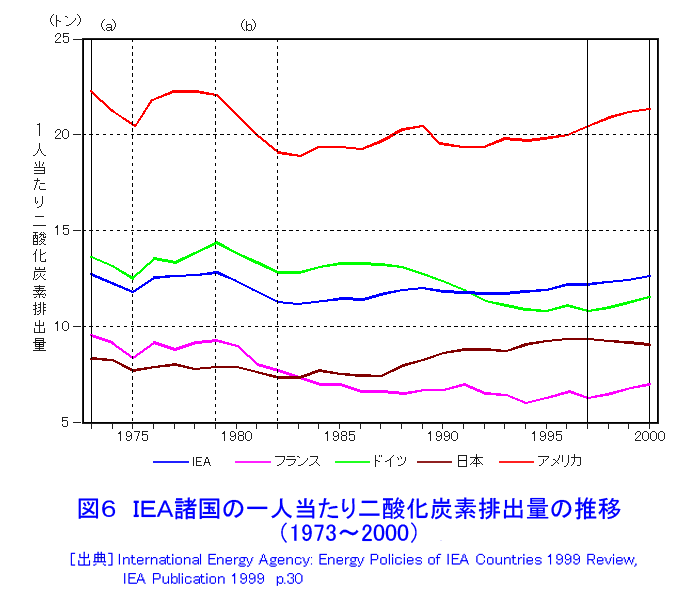
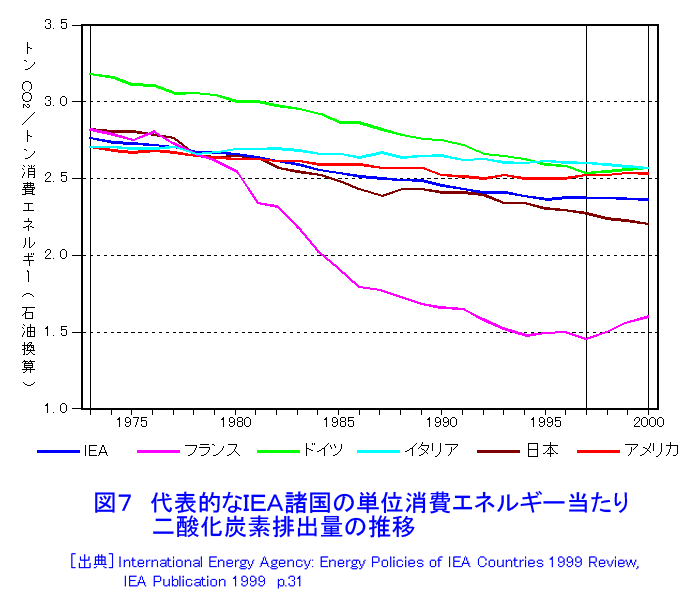
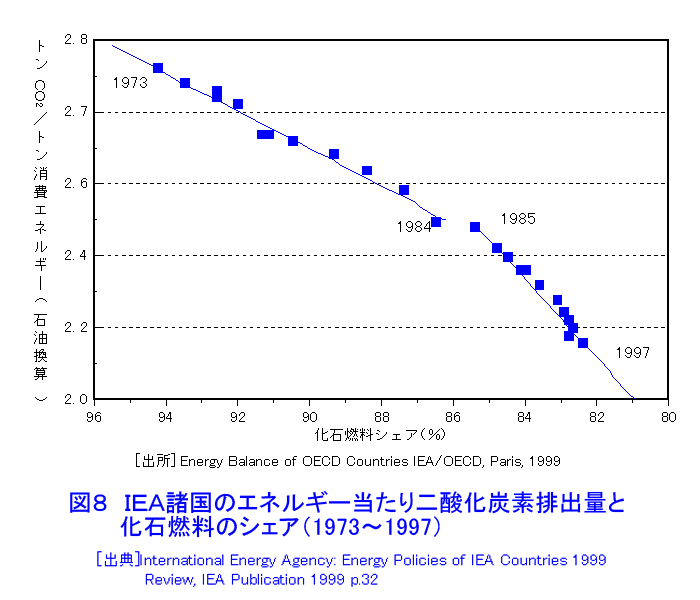
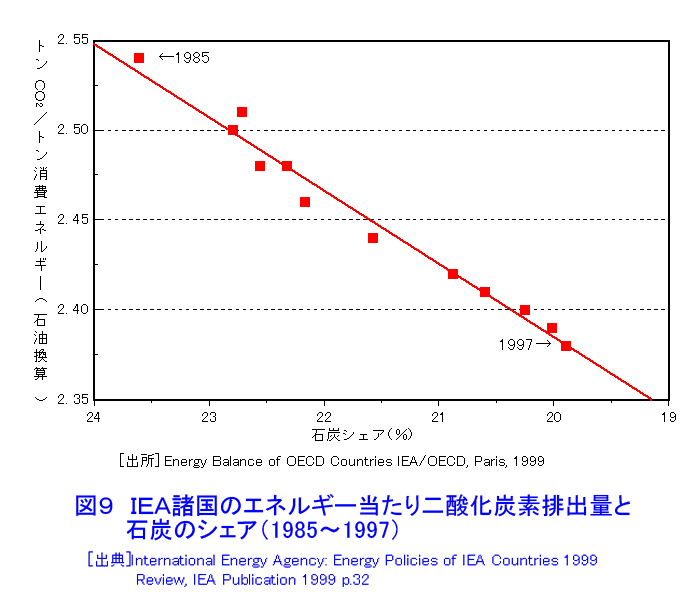
<関連タイトル> 日本の石油エネルギー政策 (01-09-03-05) <参考文献> (1) (財)日本エネルギー経済研究所エネルギー計量分析センター(編):EDMC/エネルギー・経済統計要覧(2000年版)、(財)省エネルギーセンター (2000年1月) (2) International Energy Agency,World Energy Outlook 1998 Edition,paris 1998 (3) 日石三菱株式会社(編):石油便覧 2000 燃料油脂新聞社(2000年3月),p.3-46 (4) International Energy Agency: Energy Policies of IEA Countries 1999 Review,IEA Publication 1999 p.18-44 (5) International Energy Agency: Energy Policies of IEA Countries The United States 1999 Review,IEA Publication 1998 p.15-53 (6) 資源エネルギー庁(監修):1999/2000 資源エネルギー年鑑、通産資料調査会(1997年2月)p.147-191 (7) 資源エネルギー庁:平成16年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書) (8)平成16年 石油資料、(株)石油通信社(2004年9月)、p.124-127 (9)資源エネルギー年鑑編集委員会(編):資源エネルギー年鑑2005-2006、通算資料出版会(2005年4月)、p.283-289
|

