|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
ベトナムは国土の全域に水力資源、北部に石炭、南部に石油・天然ガス資源がある上、国内で電力が不足した場合、隣接したラオス、カンボジア、中国から融通を受けやすい環境にある。ベトナムの電源構成は水力が全発電設備容量の約50%を占める。包蔵水力は820億kWhと豊富な水力資源を有するが、ダム建設に伴う環境破壊と年間降水量が雨季(通常6月中旬から11月中旬)に約60%も集中し、1年を通しての電力の安定供給が困難となっている。ベトナム政府は、経済成長に伴う電力需要の急増から、エネルギー政策が重要であるとの認識のもとにエネルギーの多様化と安定確保をめざした火力・原子力発電所の建設を最優先オプションと位置づけた。 ベトナム政府は、2020年〜2022年までに1,000MW・2基の原子力発電所を2カ所に建設し、2025年を目処に倍増して計8,000MW(1,000MW・4基を2カ所)にするとしていた。しかし、電力不足に対応するため、さらに2030年までに1,000MWと1,300〜1,500MW級の発電所を6カ所に建設する計画を、政府は2010年6月に承認した。建設予定地はホーチミン市の北東約300kmに位置するニントゥアン(Ninh Thuan)省で、第1期フォック・ティン(Phuoc Dinh)の2基はロシアが、第2基ビン・ハイ(Vinh Hai)の2基は日本が受注している。ベトナム政府は原子力導入計画を推進する一方、法整備、人材育成に努めている。 <更新年月> 2014年12月
<本文>
1.ベトナムの国情 ベトナムは南北に長い国土を持ち、その面積は日本の九州を除いた規模とほぼ同じ大きさ(32万9,241km2)である。森林資源に恵まれ、メコン川に代表される水資源も豊富で、北部では石炭などの鉱物資源も確認されている。 人口は約9,170万人(2013年末、国連人口計画推計)であり、そのうち7割近くが農業人口である。2005年〜2010年の年平均人口増加率は1.2%であった。急速な経済成長とともに人口増加による都市化、生活水準の向上で電力需要が確実に伸びているほか、1998年の「全方位外交」の推進などにより、ベトナムの国際的な発言力は飛躍的に高まった。 ベトナムでは、1986年の第6回共産党大会においてドイモイ(刷新)政策が決定され、従来の中央計画経済を放棄し、市場経済システムの導入と対外開放化を柱とした政策へ転換、近隣アジア諸国同様、高度経済成長路線の軌道に乗ることに成功した。その結果、1995年7月にASEAN(東南アジア諸国連合:Association of South‐East Asian Nations)へ、1998年11月にAPEC(アジア太平洋経済協力:Asia-Pacific Economic Cooperation)へ、2007年1月にWTO(世界貿易機関:World Trade Organization)へ正式加盟を果たした。 一方、ドイモイ政策の進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓廷、官僚主義の弊害などのマイナス面も顕在化した。経済は目覚しい発展を遂げ、1986年から1995年にかけてエネルギー消費の年平均伸び率は9.0%で、国内総生産(GDP)の年平均伸び率(経済成長率)の6.0%を大きく上回った。1997年に入り、成長率の鈍化等の傾向が表面化したのに加え、アジア経済危機の影響を受け、外国直接投資が急減。また、輸出面でも周辺諸国との競争激化に晒され、1999年の経済成長率は4.8%まで低下したが、2000年代に入って海外直接投資も順調に回復・増加し、2000年〜2007年の平均経済成長率は7%前後の高成長で推移している。2008年はリーマンショックに加え、物価上昇率が23.0%となったが、インフレ抑制政策を実施したことで、経済成長率は5.7%、2009年以降は5〜6%台の成長を維持している。近年、ベトナムでは一層の市場経済化と国際経済への統合を推し進めているものの、不透明なマクロ経済状況、金融業界の不良債権問題、未成熟な投資環境、国営企業の非効率性等が懸念材料である。2014年10月時点の国際通貨基金(IMF)統計によると2013年のGDPは約1,706億米ドル、一人当たりGDPは4750米ドル、物価上昇率は6.6%、失業率は2.2%(都市部:3.6%、農村部:1.6%)である。ベトナム政府は、2011年〜2015年の5年間の年平均経済成長率を7.0〜7.5%と設定している。2014年からの法人税率引き下げ(25%から22%へ)による国内企業の活性化、外資系企業の誘致強化などの景気対策等により、成長率達成を目指している。 2.ベトナムのエネルギー資源 ベトナムの一次エネルギー生産量は1990年の石油換算1,828万トンから1995年には2,643万トン、2000年には3,992万トン、2005年には6,076万トン、2010年には6,639万トンと推移してきた(表1参照)。2012年の一次エネルギー国内供給量6,486万トンの内訳は、石油31.6%、石炭25.5%、バイオマス燃料23.2%、天然ガス12.5%である。バイオマス燃料としての木材利用は環境問題を伴うが、ベトナムでは主要なエネルギー源のひとつとなっている。 ドイモイ(刷新)政策がスタートするなか、1987年にバクホー(Bach Ho)油田から石油生産を開始した。以来、原油生産は順調に増加し続け、日本向けを中心に輸出が行われている。また、Bach Ho油田からの随伴ガスを利用したパイプライン建設も1995年には完了し、天然ガス生産も急速に拡大した。ベトナムは外国企業の投資を許可し、探査活動を拡大したことで、石油と天然ガスの生産量を増加させた。これはベトナムに急速な経済成長と工業化をもたらし、輸出市場の促進、国内のエネルギー消費量の拡大に拍車をかけた。最終エネルギー消費量は1990年の石油換算1,606万トンから、2000年に2,509万トン、2010年に4,873万トン、2012年には5,403万トンに増加している。しかし、2004年以降、ベトナムの原油生産量の約半分を占めるBach Ho油田の産油量は徐々に減少し、産油量は2003年の26.3万バレル/日(BPD)をピークに、2011年には9.2万BPDに低下し、2014年には2.0〜2.5万BPDまで落ち込むと予測している(表2参照)。一方、国内のエネルギー消費量は増加を続けるため、2011年には石油生産量(32.6万BPD)を上回り、ベトナムは石油の純輸入国に転じている。ただし、石油探査活動はCuu Long海盆を中心に活発に行われている。天然ガスは国内市場に供給され、約90%は天然ガス火力発電用に使われている。 石炭資源は主に北東部に賦存する。石炭の種類は無煙炭、半無煙炭、瀝青炭及び褐炭である。石炭は中部と南部にも分布するが、中部のクアンガイ周辺に賦存する小規模の無煙炭と石墨(グラファイト)を除いて、泥炭あるいは褐炭・亜瀝青炭である。ベトナム北部では、クアンニン堆積盆(炭田)の無煙炭、ハノイ南部のハノイ堆積盆の亜瀝青炭が代表的である。低品位炭は国内の発電に利用され、高品位炭は中国等へ輸出している。 BP(英国石油)の統計によると、2013年の石油埋蔵量は約44億バレル(アジア太平洋諸国では第3位)、1日あたりの生産量は34.8万バレルである。天然ガス埋蔵量は6,171億立方メートル、年間生産量は97.5億立方メートル、石炭埋蔵量は約1億5,000万トン、年間生産量は4,120万トンとなっている。 3.電力事情 ベトナムでは北部に石炭、南部に石油・天然ガス、全国的にバイオマスと水力のエネルギー資源が賦存している(図1参照)。また、隣国であるラオス、カンボジア、中国とは陸続きのため、それらの国々との電力の相互融通が行われている。包蔵水力は3,000億kWh以上(北部:1,810億kWh、中部:890億kWh、南部:300億kWh)で、820億kWhが開発可能と推定され、ベトナムの電源構成の半分以上を水力発電が占めている。しかし、雨季と乾季から成るモンスーン気候の影響を強く受けるベトナムでは、降雨量に左右される水力発電は年間を通じて安定的に供給できる電源とは言えず、政府は火力発電の増強に加えて原子力発電の開発を進めている。 3.1 電気事業体制 エネルギー政策の策定は、首相府及び商工省(Ministry of Industry and Trade:MOIT)が所管し、MOIT内にエネルギー総局が2011年10月に新たに設置された。また、ベトナム電力規制庁(ERAV)が2005年9月に設立され、エネルギー総局直属となっている(参考文献11)。ベトナムの電力事業はベトナム商工省(MOIT)の管轄下にある国営のベトナム電力公社(EVN:The Electricity of Vietnam)が発送電事業を行い、傘下の地域配電会社5社(北部(NPC)、中部(CPC)、南部(SPC)、ハノイ市(HANOI)、ホーチミン市(HCMC))に電力を卸売りしている。NPCやSPCでは工業分野への給電が約60%前後と高く、HANOIは民生分野の占める割合が約55%である。ベトナム全体では、工業用が50%以上を占めている。図2に電気事業体制を示す。 3.2 電力需給バランス 2012年末の発電設備容量は26,837MWで、水力発電が発電設備容量の約半分を占める。2012年には合計2,592MWの容量が新規で運転を開始したが、そのうち71.4%は水力発電所であった。また、2012年の発電実績は1,228億kWhで、その内訳は水力43.5%、天然ガス35.8%、石炭17.9%、石油2.7%で、20億kWh(1.6%)は中国からの輸入電力であった(表3参照)。なお、消費電力量は2012年に1,096億kWhであったが、2013年には150億kWh増加して1,246億kWhとなった。 3.3 電源開発計画 ベトナムの経済計画は、10カ年の計画を定めた「社会経済開発戦略」と、その戦略期間を前後2期間に分けた「社会経済開発5カ年計画」とで構成されている。現在実施中の2011年〜2020年の開発戦略は第3次戦略と称され、2011年1月の第11回党大会で承認された。2011年〜2015年の5カ年計画は第9次計画と称され、2011年11月に国会で承認された。 また、ベトナム政府は政府組織法(2001年12月公布)と電力法(2004年12月)に基づき、2030年までの長期ビジョンを含む「2011年〜2020年の国家電力開発計画(Power Development Master Plan7:PDP7)」を2011年7月に発表した。なお、国家電力開発計画は5年ごとに改定される。PDP7の具体的な目標は次のとおりである。 (1)国内電力需要に応えるために、生産・輸入電力量は2015年が約1,940億〜2,100億kWh、2020年が約3,300億〜3,620億kWh、2030年が約6,950億〜8,340億kWhを目標とする。 (2)再生可能エネルギー源の開発を優先し、再生可能エネルギーが総発電電力量に対する割合を、2010年の3.5%から2020年には4.5%、2030年には6.0%まで増加させる。 (3)電力消費量の対GDP弾性値(伸び率の比)を2010年の平均2.0から2015年には1.5、2020年には1.0まで減少させる。 (4)農村・山岳地帯での電化事業を促進し、2020年までに農村電化率100%を達成する。 PDP7では電源毎に具体的に開発計画が示されている。ベトナムは石炭火力を発電の中核とする方針で、大型の石炭火力発電所の運転を順次開始する計画であり、2030年には石炭火力が発電容量全体の約半分を占めるとした。現在、石炭火力発電所は北部クアンニン省で採掘される国内炭を利用しているため北部に集中しているが、2015年以降は、南部でも輸入炭を用いて運転を開始する計画である。PDP7では、総発電設備容量を2020年には75,000MW、2030年には146,800MWにする予定であり、さらに2020年には南部ニントゥアン省において原子力発電所の運転開始を予定している。表4にPDP7におけるベトナムの電源開発計画を示す。 4.原子力開発 4.1 原子力開発推進体制 ベトナムの原子力開発が本格的にスタートしたのは、首相直轄機関としてベトナム原子力委員会(VAEC)が発足した1984年7月である。その後、ドイモイ政策の一環として行政改革が行われ、1993年に原子力開発は科学技術環境省(現、科学技術省)の所轄になり、同時にVAECも同省の管轄下に置かれた。VAECは、(1)ベトナムにおける原子力分野の方針、戦略、計画立案と、調査研究計画策定、(2)原子力技術に関する基礎及び応用研究の実施、原子炉技術と核燃料に関する研究、(3)原子力に関する法整備、規制文書の作成、(4)放射線防護と原子力安全に係わる技術の調査・研究・開発、(5)原子力分野における技術系人材養成・訓練、(6)原子力分野における国際協力などの役割を持つ。VAECの下には放射性希元素技術研究所(ITRRE、ハノイ)、原子力科学技術研究所(INST、ハノイ)、原子力技術センター(CNT、ホーチミン)、放射線技術研究開発センター(RDCRT、ホーチミン)、原子力研究所(NRI、ダラト)、原子力技術工業応用センター(CANTI、ダラト)、ハノイ放射線照射センター(HIC、ハノイ)、技術応用開発会社(NEAD Co.、ハノイ)等がある。研究所は、原子力・放射線技術を利用した食糧生産や医療、水質管理、環境保護など多岐にわたる分野で貢献している。図3に原子力関連機関図を示す。 一方では、将来の原子力発電所の建設に向けて法整備の作業が進められている。1994年7月には、ベトナム放射線防護・原子力安全機構(VARANSAC)が科学技術省の下部組織として設置され、1997年1月には、放射線利用や放射性物質の輸出入向けの検査、評価、許可等の放射線規制・管理の根拠となる放射線安全・管理法を公布・発効した。組織は2003年から科学技術省の直轄組織となっている。また、原子力関連の規制・管理の法的枠組みを形成する上で重要な役割を果たす環境保護法(1994年1月公布)や労働者保護法(1992年1月公布)など他の法律も整備された。2003年にはベトナム原子力法を制定することを決定した。原子力法は2008年6月の国会で審議承認後に立法化され、2009年1月1日から施行されている。表5にベトナムの原子力関連開発年表を示す。 4.2 原子力発電導入計画 ベトナムの原子力発電導入計画は、ベトナム工業省(MOI)のエネルギー研究所(IE)とベトナム原子力委員会(VAEC)が1996年に着手した「ベトナムへの原子力発電の導入に関する総合調査プロジェクト」をもってスタートした。1999年8月、VAECはMOIが国際原子力機関(IAEA)の支援を得て「原子力発電導入に関する予備的調査報告」を作成して首相府に提出。2015年までの原子力発電所の1号機の運転開始と、そのための準備委員の設置を求めた。また、工業省(MOI)と電力公社(EVN)の「2001年〜2010年の電源開発基本計画(マスタープラン)」(2020年までの開発計画)を首相が承認。同計画では2017年から2020年の間に合計120万kWから400万kWの原子力発電の導入が盛り込まれ、原子力発電のプレ・フィージビリティ・スタディ(プレFS:Pre-Feasibi1ity Study、事前・可能性調査)を2001年までに実施し、首相に報告すること、プレFSの主管を工業省(MOI)とすることなどが了承された。プレFSでは原子力安全技術・法規制、国際協力・協定、人材養成計画・国産化・技術移転、PA、原子力発電技術概要、核燃料取扱・放射性廃棄物処理、原子力発電計画・必要性、サイト選定、環境影響評価概要、建設計画・管理概要、運転・保守概要、財務、経済性概要の項目が調査され、2003年10月末に取り纏められた。プレFSは、政府内で各種の検討・修正・調整を慎重に行い、2007年5月に首相が基本的に承認、2008年2月に共産党政治局も基本的に承認した。2007年8月の省庁再編において、工業省(MOI)が商業省(MOC)と統合して生まれた商工省(MOIT)が原子力発電導入の主管となり、2008年9月には計画投資省(MPI)内に設置された「原子力発電国家評価委員会(National Appraisal Committee for Construction of Nuclear Power Plant)」にプレFSの審議が移行した。その後、プレFSの微修正を重ね、政府から国会に提出し、2009年11月に国会で承認された。 経済発展が続くベトナムでは、2020年〜2022年までに1,000MW・2基の原子力発電所を2カ所に建設し、2025年を目処に倍増して計8,000MW(1,000MW・4基を2カ所)にするとしていたが、工業化とともに増加する電力需要に対応するため、2030年までにさらに1,000MWと1,300〜1,500MW級の発電所を6カ所に建設する計画を、政府は2010年6月に承認した。建設予定地はホーチミン市の北東約300kmに位置するニントゥアン(Ninh Thuan)省で、第1期フォック・ティン(Phuoc Dinh)の2基はロシアが、第2基ビン・ハイ(Vinh Hai)の2基は日本が受注している(図4参照)。なお、ベトナムでは2011年3月の福島第一発電所の事故後、原発の安全性強化を求める声が強まり、事業化調査と人材育成や法整備の遅れも目立つことから、2014年1月にベトナムのグエン・タン・ズン首相は第1期原子力発電所の着工を2020年ごろまで延期するとし、4基計4,000MWの代替として5,000MWの天然ガス発電所を確保するよう指示している。 (前回更新:2007年8月) <図/表> 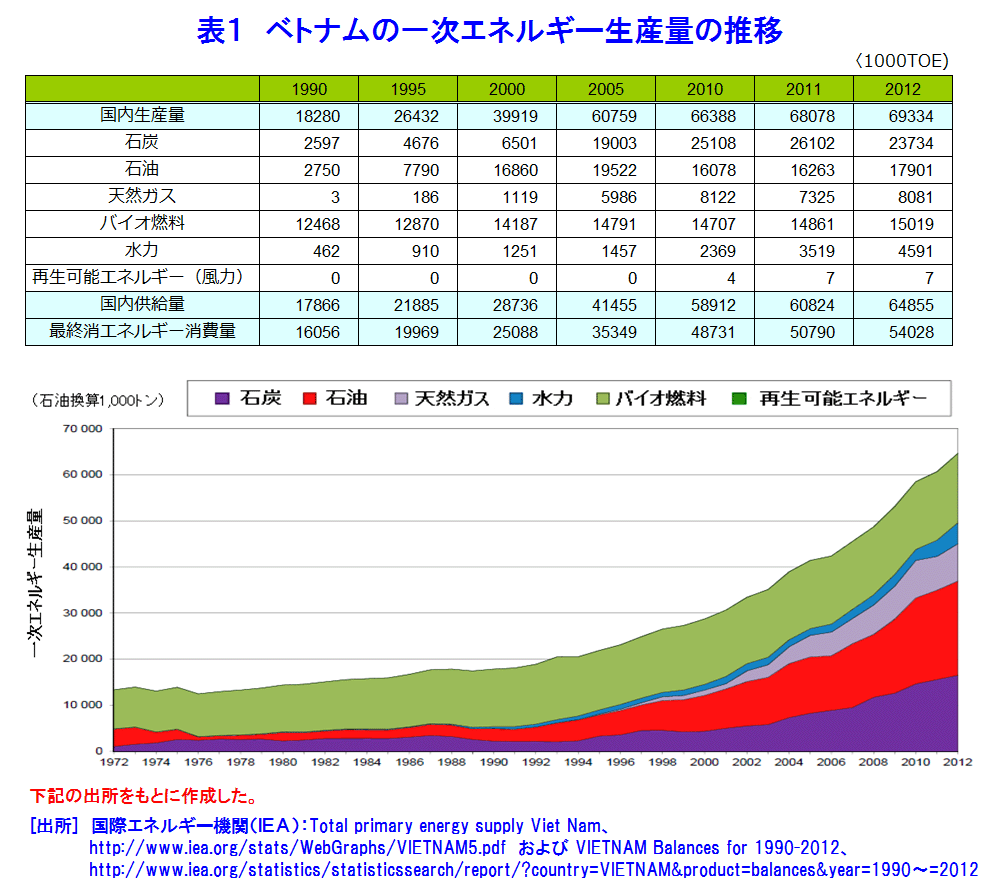
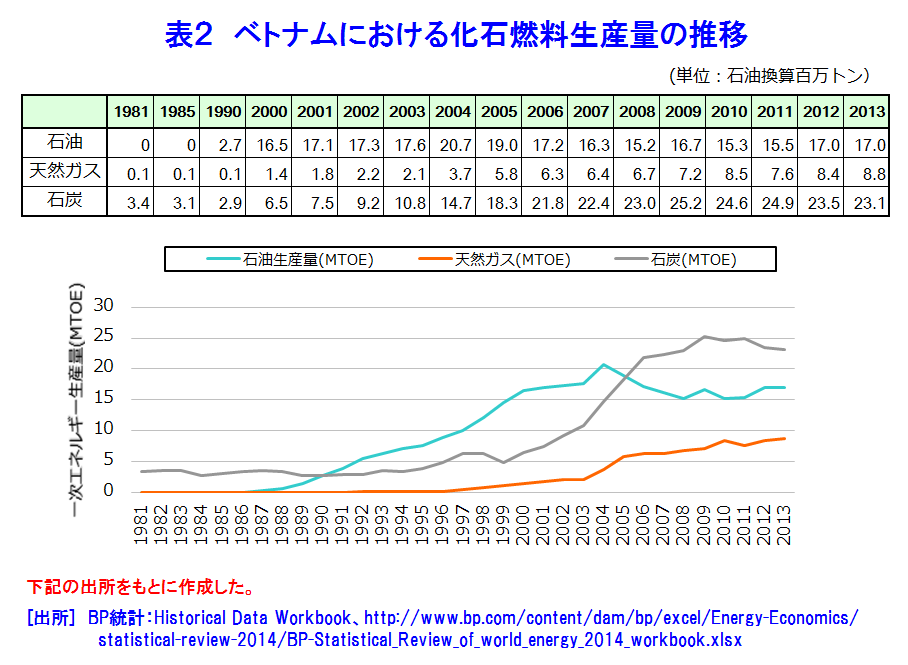
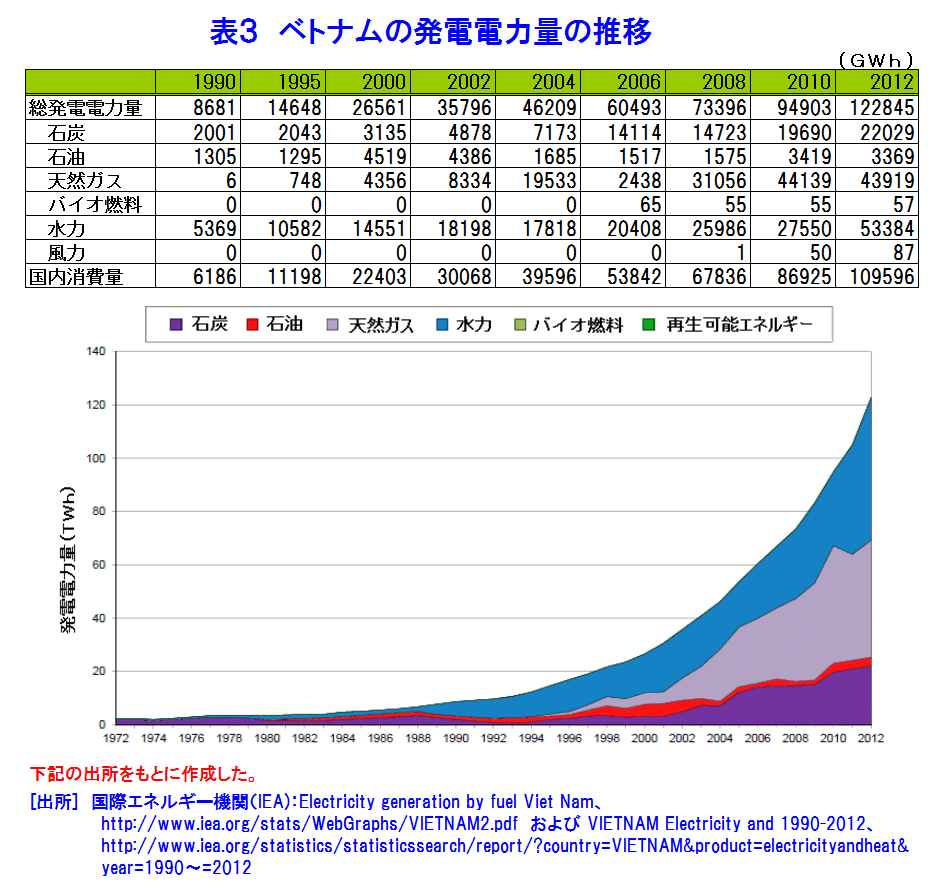
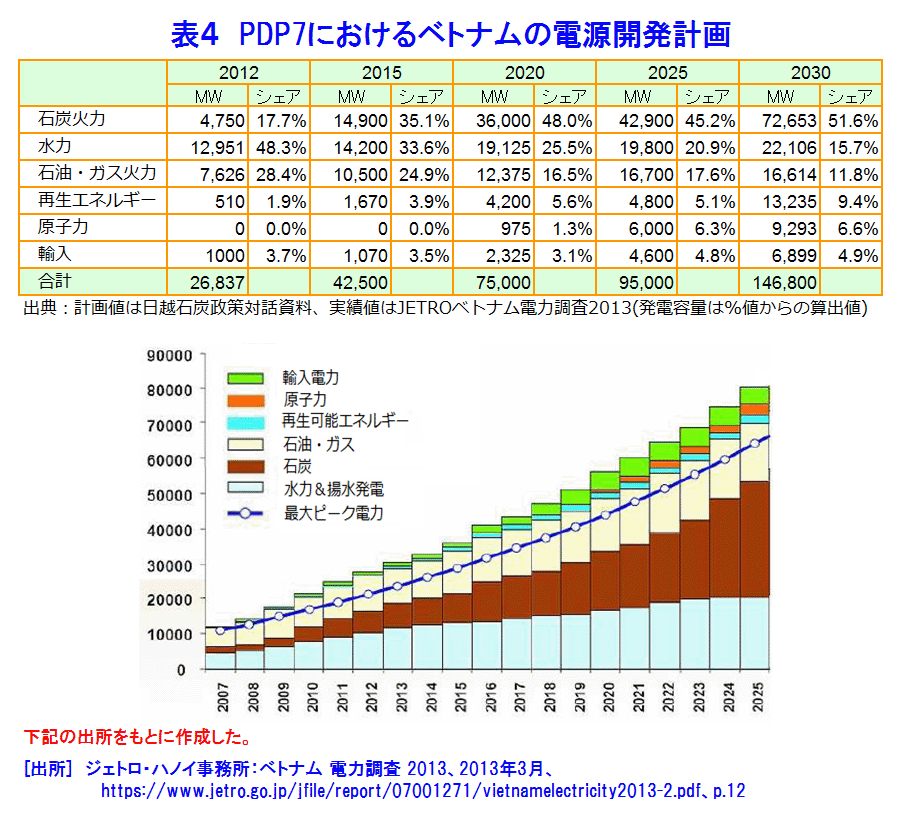
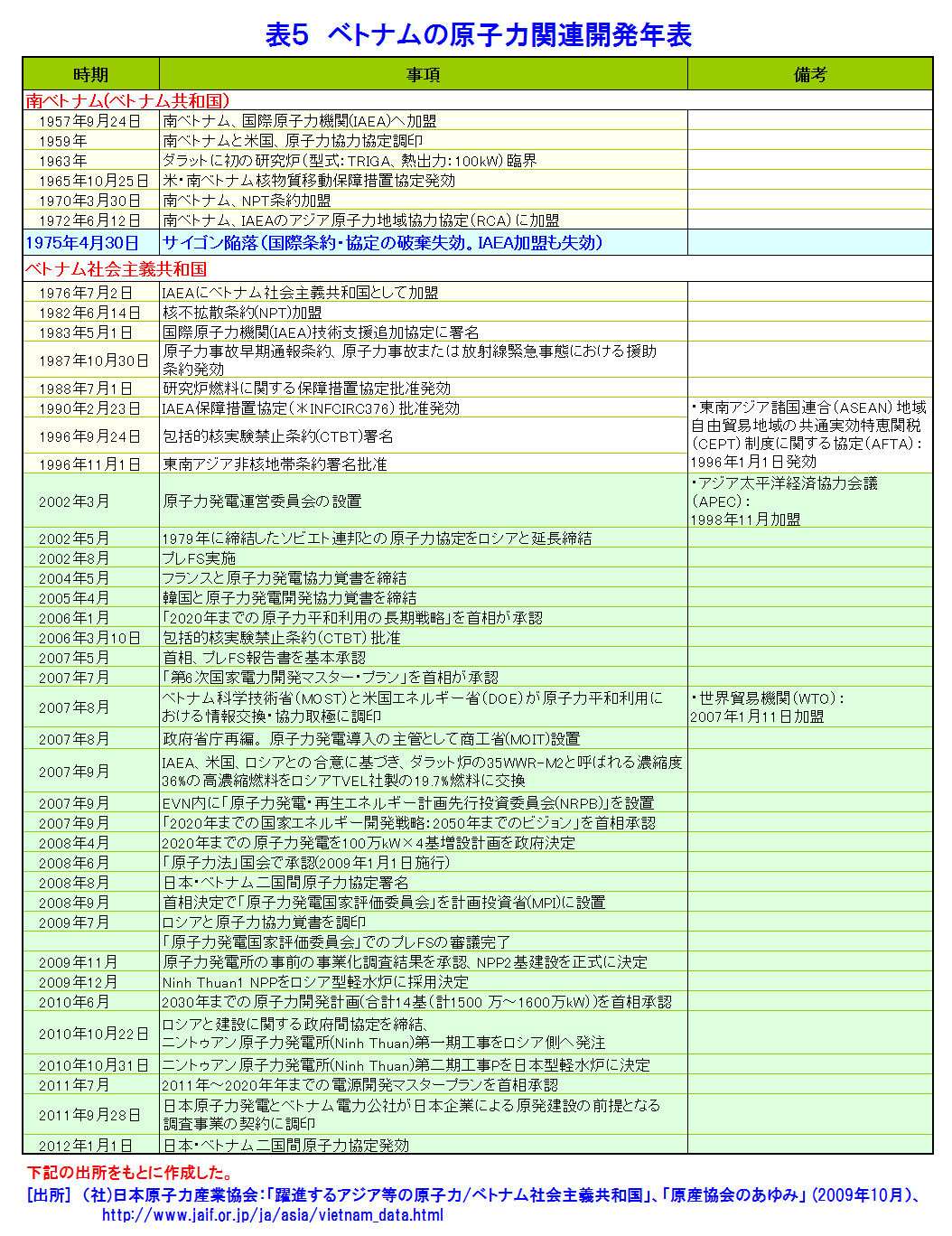
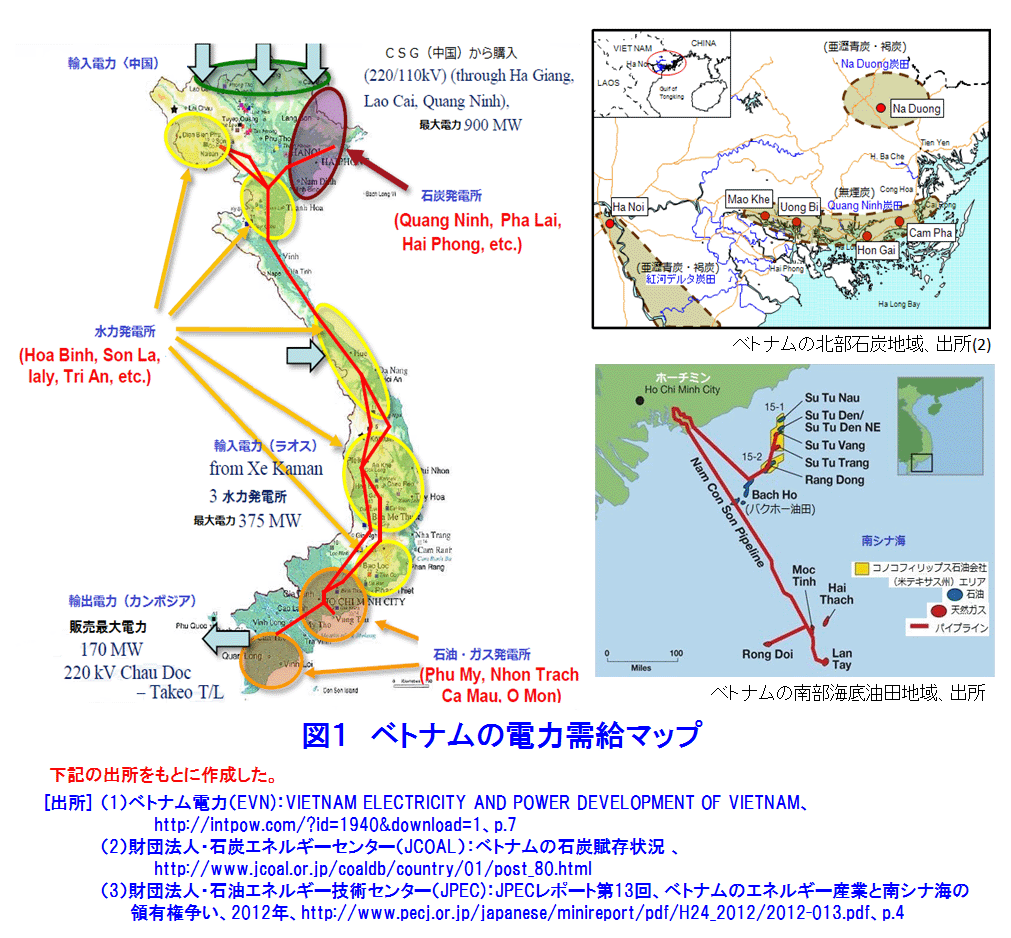
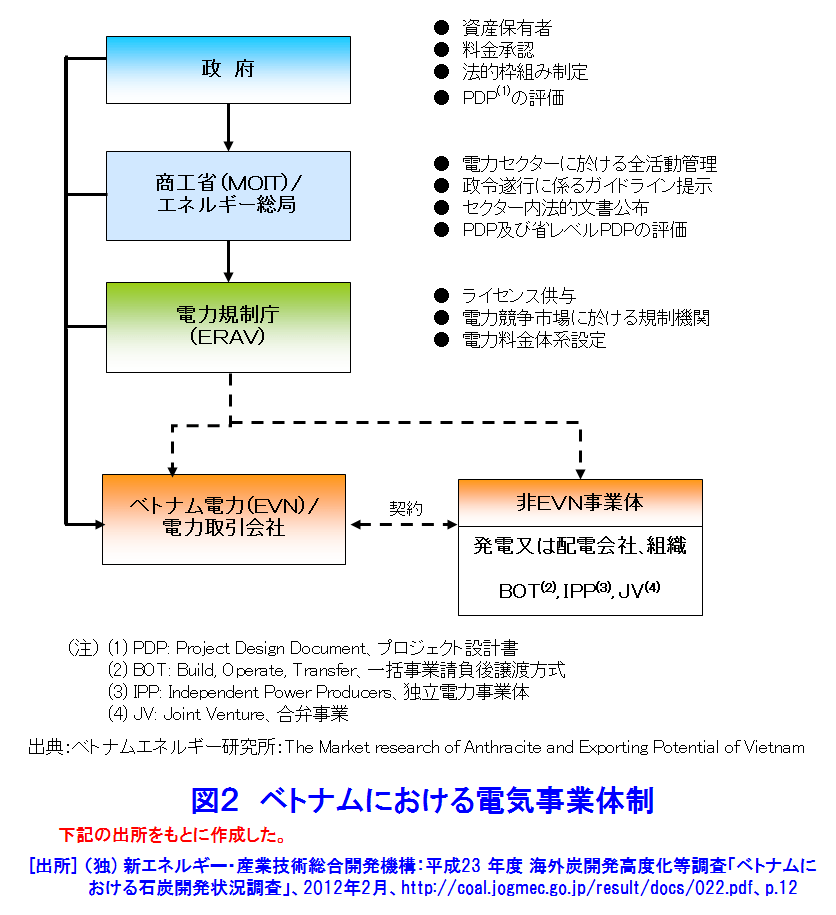
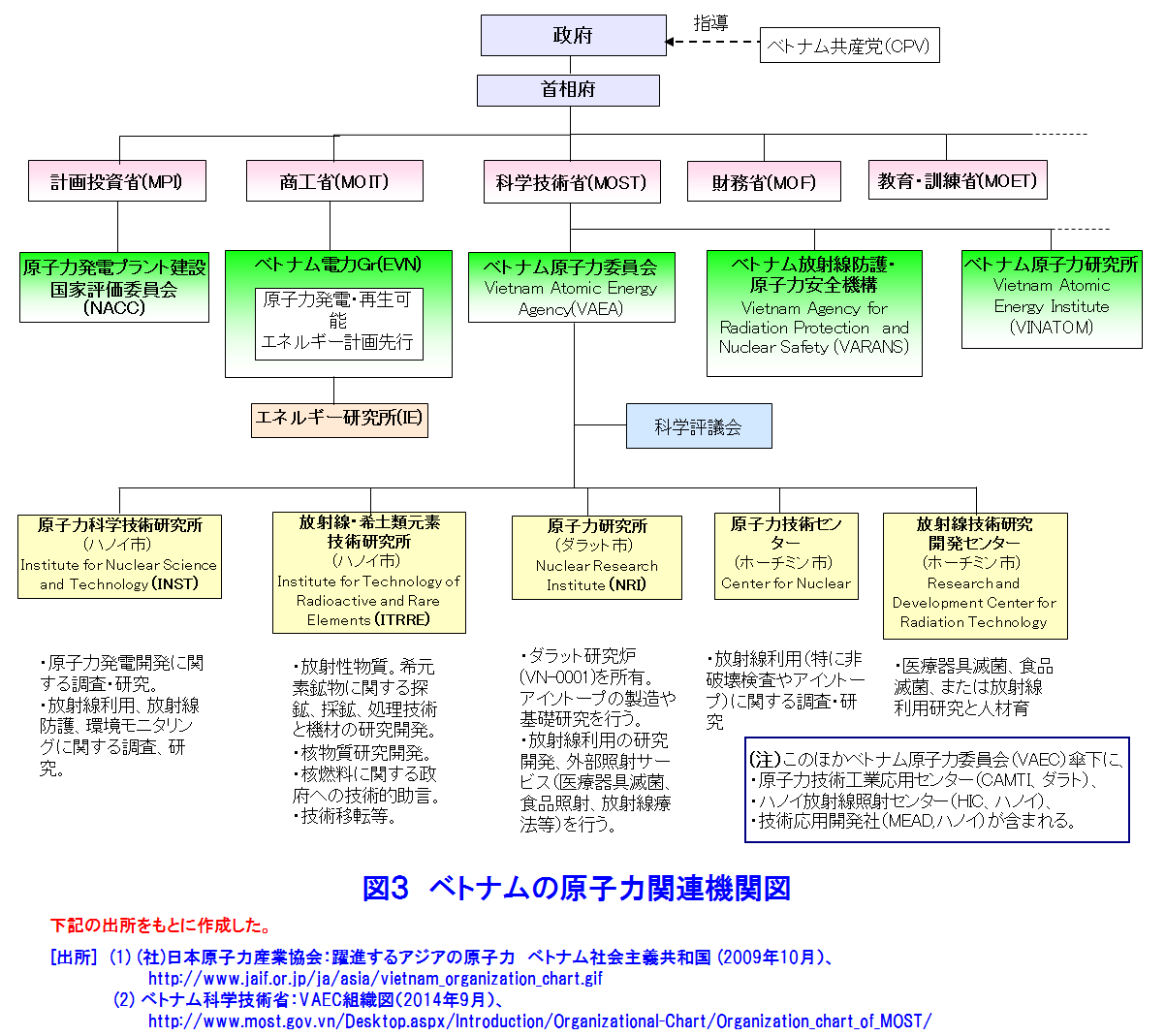
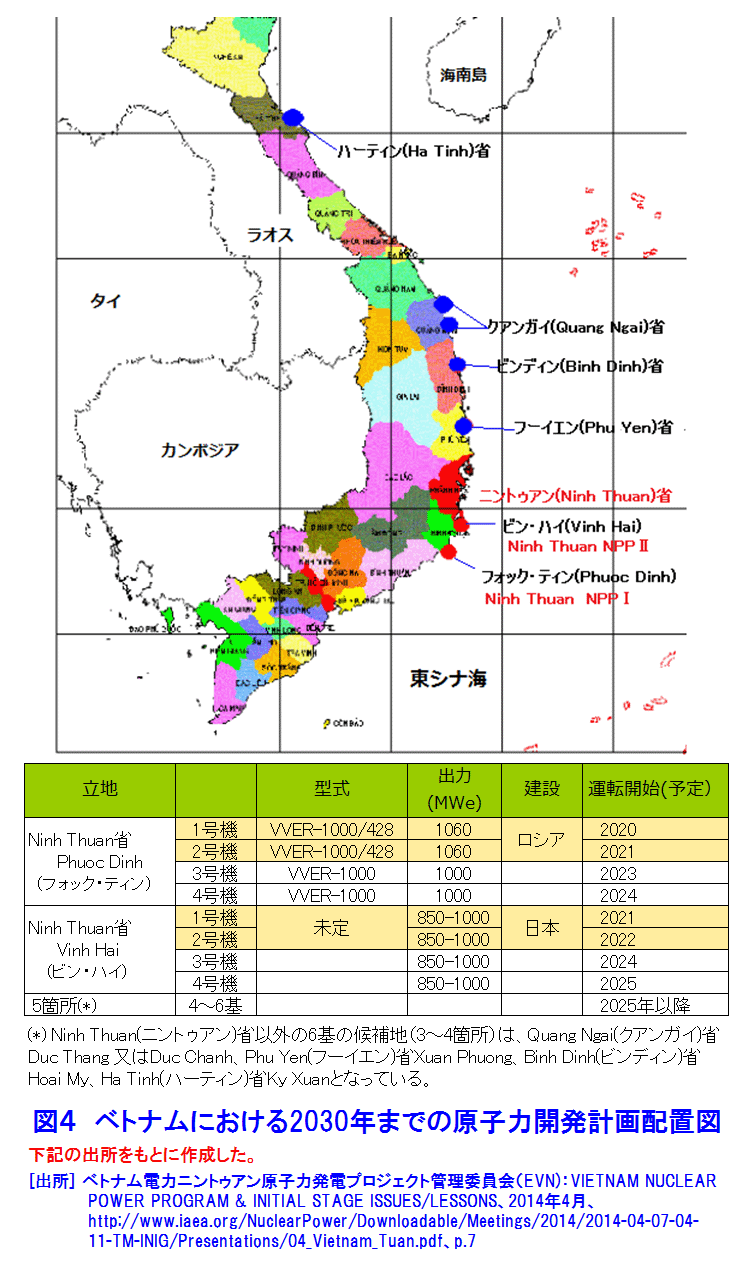
<関連タイトル> 世界の原子力発電の動向・アジア(2005年) (01-07-05-02) ベトナムにおける放射線利用の動向 (14-02-07-02) <参考文献> (1)日本原子力産業協会:原子力年鑑2014(2013年10月)、ベトナム (2)海外電力調査会:海外諸国の電気事業・第1編 追補版2(2011年2月)、ベトナム (3)ジェトロ・ハノイ事務所:ベトナム 電力調査 2013、2013年3月、 (4)国際エネルギー機関(IEA):VIETNAM Electricity and 1990-2012、 (5)BP統計:Historical Data Workbook、 (6)ベトナム電力(EVN):VIETNAM ELECTRICITY AND POWER DEVELOPMENT OF VIETNAM (7)(社)日本原子力産業協会:Atoms for Asia アジアの原子力開発状況 ベトナム(2003年3月) (8)財団法人・石炭エネルギーセンター(JCOAL):ベトナムの石炭賦存状況、 http://www.jcoal.or.jp/coaldb/country/01/post_80.html (9)財団法人・石油エネルギー技術センター(JPEC):JPECレポート第13回、ベトナムのエネルギー産業と南シナ海の領有権争い、2012年 (10)ベトナム電力ニントゥアン原子力発電プロジェクト管理委員会(EVN):VIETNAM NUCLEAR POWER PROGRAM & INITIAL STAGE ISSUES/LESSONS、2014年4月、 (11)(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構:平成23年度 海外炭開発高度化等調査「ベトナムにおける石炭開発状況調査」、平成24年2月、
|

