|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
環境問題が世界的な関心事となっている中、国際協力による援助事業においても、環境への配慮が、不可欠のものとして位置づけられている。その背景には、援助事業が自然破壊を引き起こしているという批判や、環境配慮が不十分だったために地元の反対にあって中断した事例に対する反省がある。一方、環境に限らずさまざまな分野で、倫理の重要性が認識されつつある。環境に対する倫理−環境倫理は、環境配慮の根拠を明らかにし、自然と人間との共存の方向性を示すものである。環境倫理の考え方によれば、通常の価値観や人間と自然との位置関係について見直しが迫られる。それを直接現場に応用することは無理があるにしても、環境配慮にかかわる問題を解くための糸口となることが期待される。 ここでは、環境倫理の考え方を紹介し、政府開発援助(ODA)による国際協力や民間企業による海外進出において、環境配慮がどのように行われているかについて述べるとともに、現場への応用として、今後の環境配慮のあり方について考察する。 <更新年月> 2005年06月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.環境倫理の考え方 環境倫理(Environmental Ethics)は、ひとことで言えば、倫理の対象を人間(社会)だけでなく、人間をとりまくもの、すなわち環境まで拡張するという考え方である。その対象には、人間以外の生き物だけでなく、岩や景観などの無生物まで含まれる。環境倫理はもともと、文明に対する疎外感や自然への回帰願望に端を発している。しかし現在それが重要視されている背景には、工業化による自然破壊や公害問題が無視できなくなったことや、地球環境問題が人類生存の基盤まで揺るがしかねないものとして、社会的な関心事となってきたということが考えられる。環境倫理の代表的な考え方について、以下に述べる。 (1)義務論と結果論 倫理的問題に対処する実践的な方法として、「義務論」と「結果論」というふたつの対照的なアプローチがある。ここでいう義務とは環境に対する義務のことであり、たとえば倫理的基準として人間の世界に適用されるモーゼの「十戒」を、人間以外のものにまで含めた考え方と理解できる。それに対して結果論は、義務を破っても結果を重視するという考え方である。現実的には、実践の場において義務論が適用できる場面はごく限られており、結果論が優先される場合が多いと考えられている。 (2)ディープ・エコロジー 環境に対する義務論の背景となる代表的な考え方として、ディープ・エコロジー(Deep Ecology)がある。いわゆる一般に言われている「エコロジー」をさらに深めた考え方と理解することができる。ディープ・エコロジーは一般的な世界観と異なる独自の世界観に基づくものであり、とりわけ際立っているのは、生物中心的平等(Biocentric Equality)という考え方である。それは、各々の生き物や自然の対象物(景観も含む)は、人間にとっての利用価値があるかどうかにかかわらず、それ自体に内在する価値を持っているとするものである。この考え方に基づけば、現在、地球環境問題のひとつとなっている生物多様性保全や、日常生活ではスローライフといわれるようなライフスタイルまで、広範な示唆を得ることができる。 (3)その他の倫理理論 環境に関する倫理理論としては上記以外にも、宗教に根ざした倫理、実存主義、フェミニストの倫理等さまざまな倫理理論がある。その詳細については省略するが、それぞれの立場に基づいた世界観と、環境の捉え方を理解する糸口となるものである。これらの倫理理論は、個別の問題に直接答えることはできないが、与えられた情況の中で問題を客観的に捉え、解決の手がかりを探ることを可能にしている。 2.国際協力における環境配慮 (1)開発事業にともなう環境配慮 平成15年に改訂された政府開発援助大綱(ODA大綱)のII.「援助実施の原則」の中では、「環境と開発を両立させる」と明記されている。ODAの実施機関であるJICA(国際協力機構)とJBIC(国際協力銀行)では、それぞれ独自に環境配慮のためのガイドラインを制定し、開発事業にともなう環境社会配慮を義務付けている。いずれも事業の透明性や説明責任(アカウンタビリティー)の確保を目的として制定されたものだが、JICAは技術協力、JBICは円借款というそれぞれの事業の特性を反映した内容となっている。それらについて概要をまとめると表1のようになる。 (2)環境ODAの実施 ODA事業の中には、環境保全そのものを目的としたもの、いわゆる環境ODAも含まれている。1992年6月の国連環境開発会議(UNCED)では、1992年度より5年間で環境分野の援助を9000億円から1兆円を目途として大幅に拡充・強化する方針が発表され、その目標額は、1年前倒しで達成された。なお、環境ODAの内容としては、従来、居住環境改善(上下水道、ゴミ処理等)、防災(洪水防御等)のシェアが大きいが、今後はそれらの他にも、公害対策、森林保全、自然保護、省エネルギーについての協力も強化される見通しである(外務省ウェブサイト)。環境ODAのうち技術協力のための予算は、1992年の100.3億円から2002年の269.3億円と、2倍以上に増加している(図1)。 (3)民間投資における環境配慮 上記の政府開発援助に伴う環境配慮、あるいは環境保全事業のほかに、民間企業による海外展開について、経団連は1991年「地球環境憲章」を制定している。その中には「海外進出に際しての環境配慮事項」として、10の環境配慮事項を掲げている。特に2.の「進出先国の環境基準等の遵守とさらなる環境保全協力」では、「最低限進出先国の環境基準・目標を遵守することは当然であるが、進出先国の基準がわが国よりゆるやかな場合、あるいは基準がない場合には進出先国の地域の状況に応じて、(中略)適切な環境保全に努めること。」とし、いわゆる上乗せ基準による環境配慮を謳っている。また、1996年には「経団連環境アピール」をまとめ、1997年には「経団連環境自主行動計画」を発表し、経済団体として環境配慮のための自主的取組を行っている。 3.国際協力と環境倫理 (1)開発途上国の課題と環境配慮 開発途上国においては一般に、道路や橋などのインフラ整備が不十分であるという認識から、それらの建設が最優先の開発課題とされることが多い。しかし最近の傾向として、すでに述べたように開発事業にともなう環境社会配慮は不可欠のものとなりつつあり、開発のための資金を提供する金融機関も、環境影響について厳しくチェックしている。そのため、事業者だけによる環境評価だけでは不十分であり、反対者の意見も含めて、多方面から事業の妥当性を評価することが必要とされてきている。そこで、開発事業に際しては利害関係者(ステイクホルダー)の合意形成が、重要な手続きとして位置づけられている。援助の対象国でも、合意形成に関する手続きが法律で細かく規定されていることが多い。 さらに環境面から言えば、利害関係者といえども対象地域の環境状況を完全に把握している訳ではないというのが実情である。そのため、世界的に見て動植物の貴重な生息(生育)環境となっている地域や生物多様性の高い地域(ホットスポット)での事業を実施する際には、外部の有識者を交えた事業計画の検討が必要になる場合もある。また、環境に関する法令や基準も十分に整備されていない場合や、判断材料となるデータが不足していることもあるので、その点を十分考慮することが、環境倫理の面からは必要となる。 (2)環境倫理からのアプローチ 国際協力には、安全性や快適さを提供する物質文明を、開発途上国が共有するという側面がある。しかし、そのような手法が時として既存の社会あるいは環境への大きな負のインパクトを与えてきたことも事実である。環境倫理の面からは別のアプローチが可能であり、無理の無い形で環境負荷を軽減するものとして、中央集権的な「α構造」と、分散的な「β構造」の併用が提案されている(表2)。開発途上国の社会や自然環境への影響を避けながら開発を進めるために必要とされる「適正技術」に関し、実践的な方向を示すものである。実際には、開発の大枠は援助の受入国が決めるものであり、現場において環境倫理的アプローチを実践することには大きな制約がある。そのような中で、多くの国で採用しているGNPを指標とする経済開発に代わり、GNH(Gross National Happiness)を国の指標として掲げているブータンの取組が注目されている。 (3)国際協力事業に見る環境倫理 最後に、環境倫理と関連の深い国際協力事業の事例を挙げ、その概要と課題等について以下に述べる。 1)生物多様性保全事業 熱帯雨林など、特に高い生物多様性を有する地域において、その現状を把握し、保全するための事業である。これまでにインドネシアやマレーシア、コスタリカ等で協力が行われてきた。この分野における日本の技術的蓄積は、他の援助供与国に比較してまだまだという段階であり、現場での経験の蓄積と人材の養成が課題となっている。 2)再生可能エネルギー開発事業 化石燃料の使用や森林伐採によらないエネルギー供給手段として、小水力、風力、太陽光発電、バイオマス等の再生可能エネルギーの開発が進められている。遠隔地にも単独で設置することが可能なため、農村地域の生活レベル向上手段として需要は多く、日本の得意とする技術分野のひとつでもある。一方、機材のメンテナンスや蓄電のために使用される鉛のリサイクルルートの確保等が課題となっている。 3)参加型手法の導入 多くの国際協力事業において、合意形成の手法として住民参加によるワークショップが導入されている。それによって、環境も含めた地域の現状と問題点の詳細な把握が可能となる。参加者の意識や経歴は様々であることから、問題点を共有し議論を深めるには、事業者から適切な形で情報を提供し、偏りのない形で議論を進めることが必要であり、中立な立場で進行に携わる人材(モデレータ)の養成と確保が課題となる。 <図/表> 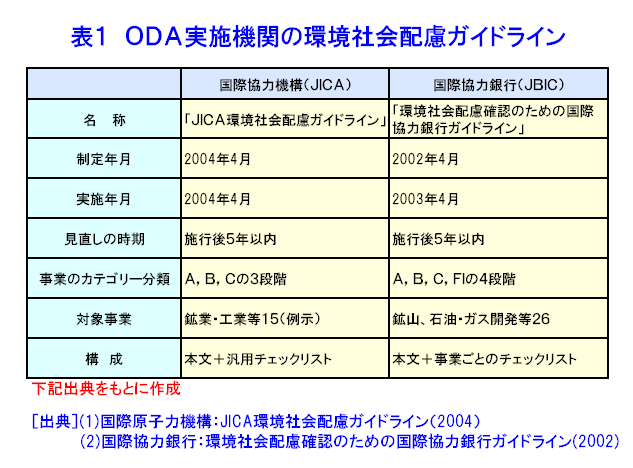
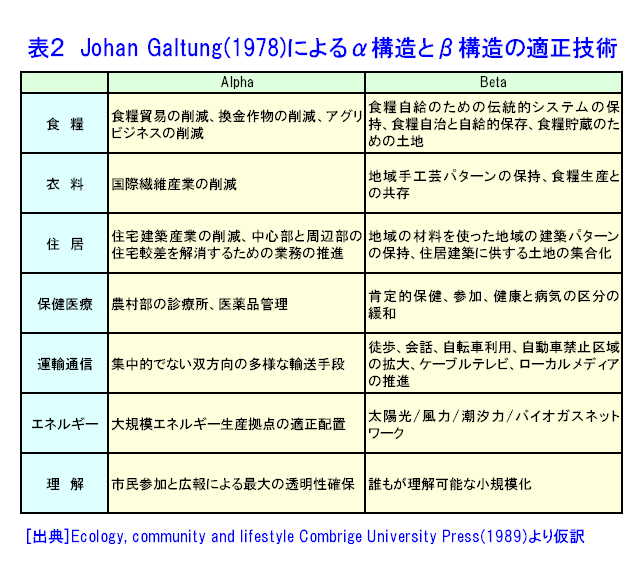
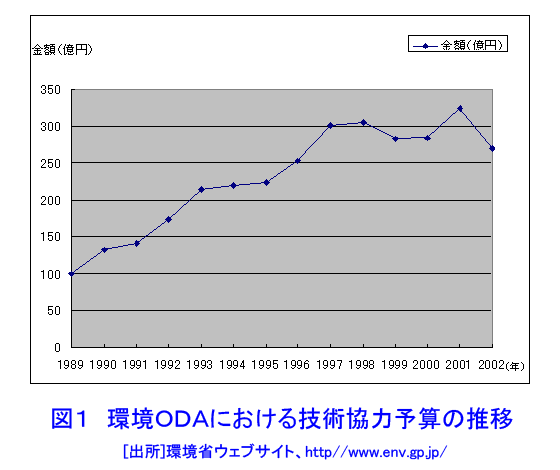
<関連タイトル> 地球環境問題が人類に及ぼす影響・その1(大気環境問題) (01-01-02-02) 地球環境問題が人類に及ぼす影響・その2(水環境問題等) (01-01-02-03) 原子力産業界におけるISO認証取得への取り組み (10-07-04-01) 技術者倫理概説 (10-08-01-01) <参考文献> (1) Bill Devall: Deep ecology George sessions,Gibbs Smith Publisher (1985) (2)Arne Naess: Ecology, community and lifestyle,Cambridge University Press (1989) (3)経団連地球環境憲章(1991) (4)ベジリンド・ガン著、日本技術士会環境部会訳:環境と科学技術者の倫理、丸善(2000) (5)環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン(2002) (6)政府開発援助大綱(2004) (7)JICA 環境社会配慮ガイドライン(2004)
|

