|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
蛍光X線分析法(X-ray fluorescence analysis,XRF)は、試料にX線を照射し、2次的に発生するX線(蛍光X線)を用いて元素の定性・定量分析を行う方法である。この蛍光X線分析法は各種元素分析法の中でも代表的な手法の一つと考えられ、様々な材料の評価分析に定常的な分析手法として確立したものとなっている。元素分析としての蛍光X線分析法は一般に市販の自動化された装置を用いて行われている。蛍光X線分析法の特徴は非破壊かつ迅速な測定にあるので、工程管理に広く用いられる。また一般の材料評価においても元素組成を調べるために必須の分析法である。さらに非破壊の特徴を生かして、考古学・美術資料等の貴重資料の分析や専用装置による野外での分析などにも用いられている。また最近では、シンクロトロン放射を用いた高感度・微小領域分析や全反射法を用いた超高感度微量分析法などが発展してきている。 <更新年月> 2009年02月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.はじめに X線は波長の短い電磁波である。その波長領域は定義によって異なるが、広義には0.1Å〜100Å(100eV〜100keV)程度を指すことが多い。X線は物質に対する透過能が高いことから、医療応用や工業材料の非破壊検査などに用いられるとともに、材料分析法としてはX線回折法を用いた物質の構造解析や蛍光X線分析法を用いた元素分析が広く利用されている。ここでは、蛍光X線分析法の原理と応用を概説し、最近の新しい応用の展開についても簡単に触れる。 2.原理と特徴 X線を試料に照射すると、原子の内殻電子が励起されて放出し、内殻に空孔が生じる。この内殻空孔に外殻電子が遷移する時、その元素の電子のエネルギー準位差に対応したエネルギーがX線領域の電磁波(特性X線)となって放出される。これを蛍光X線と呼ぶ(図1)。蛍光X線スペクトルは元素に固有であるため、得られたスペクトルより、試料を構成する元素の同定が可能となる(定性分析)。また蛍光X線強度は、第1近似では試料中の元素濃度に比例するので、その強度から元素濃度を求めることができる(定量分析)。 もう少し入射X線エネルギーと蛍光X線エネルギーを詳しく説明すると以下のようになる。試料を励起するための入射X線のエネルギー(波長)は目的元素の吸収端エネルギー(波長)より高い(短い)必要がある。吸収端とは、物質によるX線の吸収スペクトルを測定したとき図2のように急激に吸収が増加するエネルギーであり、これは内殻電子を励起するのに必要なエネルギーに対応している。図に示したK、Lなどは励起される内殻電子のエネルギー準位を意味している。一般に内殻電子の吸収端エネルギーはX線の波長領域にあるので、蛍光X線を励起するためにはX線が必要である。一方、蛍光X線は電子遷移のエネルギー準位に関係しており、図3に示すような名称が使われている。主に分析に使われるのはKαとKβであり、重元素についてはL系列である。 蛍光X線分析法の特徴をまとめると次のようになる。 a)一般に測定試料は化学的前処理を必要とせず、また試料は測定により破壊されることが無い。固体・液体試料の測定が可能である。 b)蛍光X線分析の対象とする元素は主にNaからUまでの全元素である。 c)蛍光X線スペクトルは比較的単純であり、解釈も容易である。 d)半導体検出器を用いたシステムでは多元素同時分析が可能である。 e)分析可能な濃度は主成分(%以上)から微量成分(ppm)までの広い範囲にわたる。 f)一般に定量精度が高い。特に標準試料を用いて比較すると、高い分析精度(0.1%)が得られる。 3.測定方法 蛍光X線分析装置は、試料を励起するためのX線発生装置、試料室、発生した蛍光X線の任意の波長および強度を求めるための分光系(検出器を含む)およびスペクトルを記録するためのエレクトロニクスからなっている。 試料を励起するためのX線源には原理図を図4に示すようなX線管球が用いられる。X線管の対陰極物質(ターゲット)には主にWやCrが用いられる。 試料からの蛍光X線の分光系は2種類に分類される。一つはブラッグの法則を使って分光結晶により分光する方法(波長分散型、Wavelength Dispersive System;WDS)、もう一つはエネルギー分析能力をもつ半導体検出器を使用する方法(エネルギー分散型、Energy Dispersive System;EDS)である。図5に2種類の分光系の概念図を示す。 波長分散型に用いられる分光結晶は、LiF、EDDT(エチレンジアミン四酢酸)、TAP(フタル酸タリウム)などが用いられる。LiFはK以上の元素の分析に広く用いられ、EDDTはアルミニウム以上の元素、TAPは、酸素以上の軽元素の分析に用いられる。波長分散型では結晶により分光するため、エネルギー分解能は高いが(数10eV)、スリットにより特定の方向に放射された蛍光X線のみを取り出すために効率はあまり高くない。定性分析、材料研究開発に適している。また複数の分光器を用いる方法は、高速測定に向いており、工程管理などに適している。図6に波長分散法によるステンレス鋼の蛍光X線スペクトルの例を示す。Fe以外にCu、Ni、Coなどが検出されている。 一方、半導体検出器のエネルギー分解能はあまり高くないが(Feの蛍光X線は、6.4keV程度で150eV前後)、試料からの蛍光X線を直接エネルギー分析するので効率が高い。装置が比較的小型で済み、微量試料の分析に向いている。図7にエネルギー分散法による植物(りょうぶ)の葉からの蛍光X線スペクトルの例を示す。K、Ca、Mnなどが検出されている。 X線管球の替わりにラジオアイソトープ(55Fe、109Cdなど)をX線源に用いると装置はコンパクトになり、メッキ厚のオンライン測定や野外での簡便な測定に用いられる。 4.分析法 測定用の試料は多くの場合そのまま測定できるが、定量分析のためには試料調製が必要になる。蛍光X線は基本的にバルク測定法とされているが、試料の組成と測定元素によっては分析深さが数ミクロンになる場合も多く、試料表面の状態に注意が必要である。固体塊状試料では、試料表面を研磨して試料とする。要求される平坦度は試料の組成や目的とする定量精度による。粉末試料では、必要ならばバインダーを加え加圧整形し、ペレット状にする。液体試料では液体試料用の容器にそのまま封入し測定する。測定対象となる元素濃度が低い場合には、各種濃縮法を用いて、実質的な感度を上げることができる。以上は定量分析の場合の注意であるので、定性分析の場合には、調製手順を簡略化することができる。 蛍光X線分析における定性分析は、蛍光X線スペクトルの各元素への帰属を決定すればよい。波長分散型の場合には、蛍光X線信号のピークの角度をブラッグの法則により波長に変換する。エネルギー分散型では横軸がそのままエネルギー軸になっている。各元素の蛍光X線の波長は表(文献3)になっているので、それを使って各ピークの帰属を決める(図3参照)。 一方、定量分析は蛍光X線ピーク強度を測定することにより行われる。一般には測定試料と化学的組成や表面状態が類似した濃度既知の試料を準備し、分析元素濃度と蛍光X線強度の検量線を作成する。この検量線を用いて測定試料中の目的元素の濃度を決める。普通蛍光X線強度は濃度に比例するが、かならずしも直線関係が得られるわけではない。蛍光X線強度は共存元素、特に主成分元素の影響を受ける。このような効果をマトリックス効果と呼ぶ。このため、上に述べたような測定試料に類似の参照試料を準備することが望ましい。マトリックス効果を補正する各種の手法が発達している。 5.主な応用例 1)工業材料の分析評価 原材料の組成や金属、化合物、複合材料等の組成評価に用いられ、蛍光X線分析としては最も広く利用されている分野である。利用形態としては、工程管理としての利用、材料開発としての利用、製造品の検査など多様である。現場における材質調査の主流は蛍光X線分析法である。 2)生物学的、医学的試料の分析 植物、動物における元素の取り込み、蓄積、排出の仕組みを明らかにすることにより生物学的な機能の形成過程、反応機構、生理機能などを明らかにすることができる。このような分析では、損傷の少ない、また場合によっては乾燥などの試料調整の不要な蛍光X線が適当な場合がある。また、有害金属物質などの生体への取り込みや蓄積などの過程を明らかにすることもできる。 3)環境分析への応用 大気を吸引してそのエアロゾルをろ紙上に集めたものを分析し、環境評価に用いられる。大気中のエアロゾルは工場の排ガスなどに起因する物質などが含まれている場合もあり一様な分解溶液化が困難な場合もあるが、蛍光X線分析に適している。また、植物や海産物には元素の蓄積効果のあるものも知られており、地域の環境評価にも用いられる。 4)貴重資料の分析 博物館資料に代表されるような貴重な資料では非破壊で行える分析が重要である。美術品や考古学資料の組成分析で、製作年代や地域の特色、作製法などについての分析が行える。逆に特定の対象の製作年代や製作者が分かる場合もあるため、蛍光X線分析法が分析化学の考古学への応用研究を質的に大きく変えてしまった。非破壊性を利用して、犯罪捜査資料の鑑定に用いられることもある。 6.特殊な分析法 1)全反射微量分析法 平坦かつ滑らかな表面を持つ試料の高感度表面分析には全反射蛍光X線分析法が用いられるようになった。図8に示すように、試料表面にX線がすれすれに入射するとX線全反射が生じるが、この時X線は表面のみ(深さ数nm)で散乱される。このため表面近傍の感度を著しく増加させることができる。全反射蛍光X線分析装置が市販され、薄膜の分析やシリコンウェハーの極微量表面汚染分析に用いられている。後者の検出限界は109 atoms/cm2程度に達している。 2)マイクロビーム分析 蛍光X線による微小領域分析はX線の集光が難しいためにこれまで実現されていなかった。最近、中空キャピラリー(毛細管)を用いてX線ビームを絞った専用市販装置が実用化され、数10ミクロンの領域の微小・微量分析が可能になっている。 3)状態分析 蛍光X線スペクトルを高分解能X線分光器を用いて測定すると、蛍光X線スペクトルが化学結合状態に応じて僅かに変化することが知られている。このことを使って、溶液表面の化学種の動的な分析など化学状態分析を行う手法も発展している。各種材料の特性は、組成のみでなく、結合状態に強く依存するので、状態分析の重要性は増している。 4)シンクロトロン放射の利用 市販装置のX線管球の代わりに励起X線源として、円形加速器からのシンクロトロン放射(放射光)を用いることも近年盛んになっている。放射光蛍光X線分析により、蛍光X線分析法の高感度化が実現し、また吸収端の化学状態依存性(ケミカルシフト)を利用することにより、状態分析が比較的容易に行われている。また、全反射蛍光X線分析の感度が上昇し、X線マイクロビームによる局所分析ではサブミクロンの分解能も得られるようになった。放射光蛍光X線分析は、大型加速器を用いることから定常的に行える分析には適さないが、これまでの蛍光X線分析の限界を超えたものとなり、ppmレベルの微量元素を分析することができる。 (前回更新:2000年3月) <図/表> 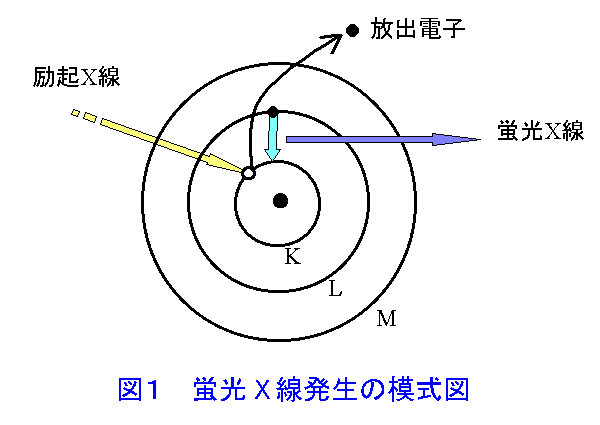
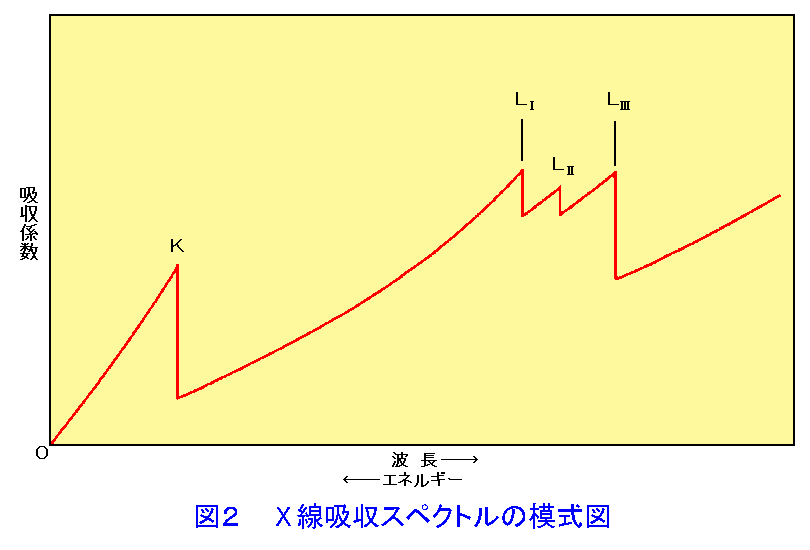
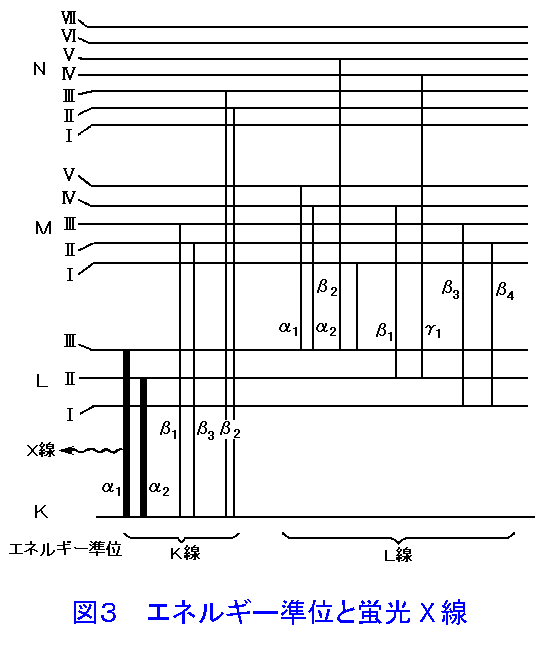
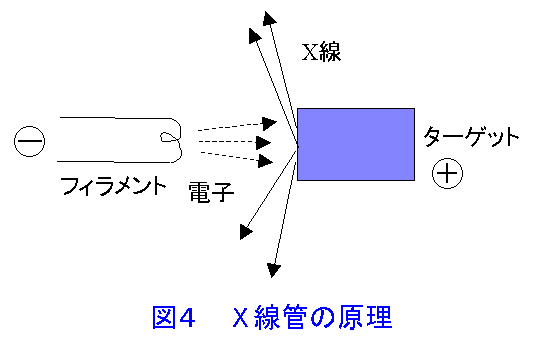
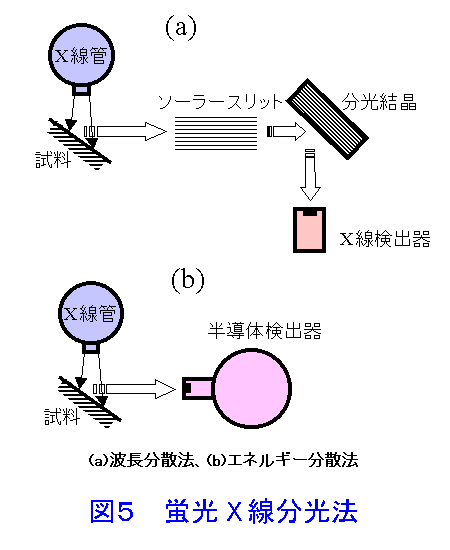
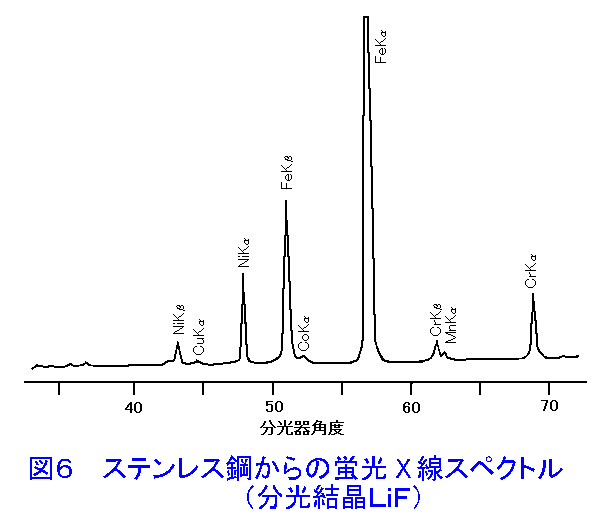
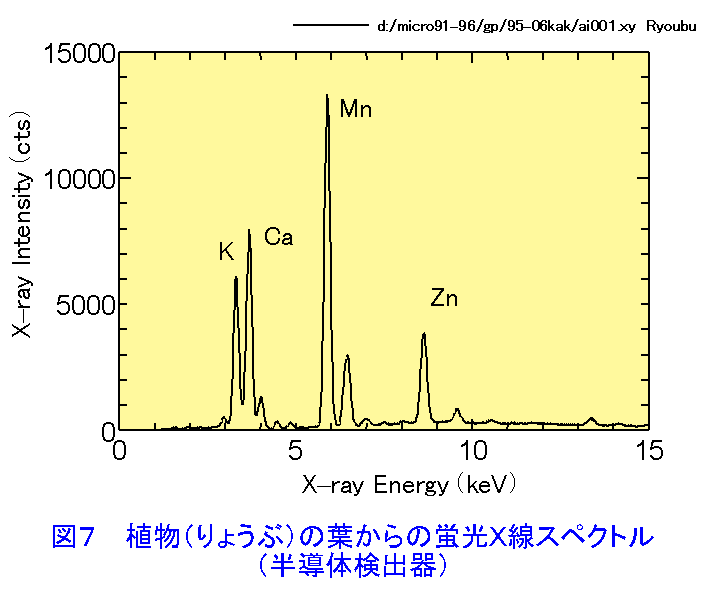
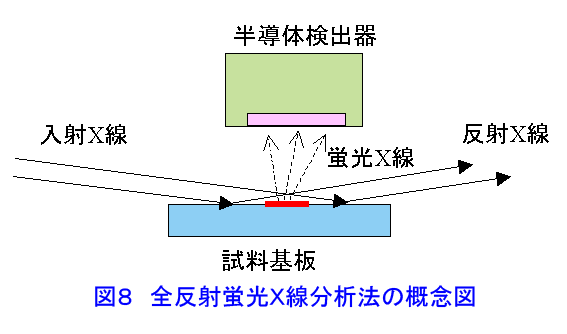
<関連タイトル> シンクロトロン放射光 (08-01-03-08) SPring-8計画 (08-04-01-06) RIの分析計測機器への応用原理 (08-04-03-03) <参考文献> (1)大野、川瀬、中村:「X線分析法」共立出版1987 (2)”Handbook of X-ray Spectrometry”,eds.R.E.Van Grieken and A.A.Markowicz(Marcel Dekker,Inc.NewYork,1993 (3)R.Tertian,F.Claisse ”Principles of Quantitative X-Ray Fluorescence Analysis”,(Heyden,London,1982) (4)Xray Emission Line Wavelength and Two-Theta Table (ASTM DATA SERIES DS 37)
|

