|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
核燃料サイクル開発機構(旧 動力炉・核燃料開発事業団、現 日本原子力研究開発機構)では、日本のプロジェクトとして1972年以来、人形峠においてウラン濃縮に関する遠心分離法の開発を行ってきた。パイロット・プラントを建設し、試験運転によりプラント運転制御と保守技術の確立を行う一方、年間当たり200tSWU規模の原型プラントを建設し、13年間の連続運転により遠心分離機の長期安全性を示すとともに、約350tUの濃縮ウランを生産した。また、新素材高性能遠心分離機の開発を行っていたが、核燃料サイクル開発機構のウラン濃縮事業の整理に伴い、2001年9月末でウラン濃縮に関する技術開発を終了した。現在、施設の廃止措置に関する技術の開発・実証が行われている。 <更新年月> 2007年12月
<本文>
人形峠におけるウラン資源および濃縮に関する技術開発は、1955年通商産業省工業技術院(現独立行政法人産業技術総合研究所)地質調査所が岡山県および鳥取県境付近でウラン鉱床の露頭を発見し、1957年に原子燃料公社に人形峠出張所が置かれてスタートした。人形峠出張所は探鉱、採鉱、製錬の試験を実施していたが、1967年動力炉・核燃料開発事業団となり、ウラン濃縮パイロットプラント、原型プラントから製錬転換施設およびウラン濃縮施設を順次建設・運転した。その後、1998年に核燃料サイクル開発機構(現 日本原子力研究開発機構、以下同じ)人形峠環境技術センターと改称し、製錬転換施設は1999年7月に、ウラン濃縮施設は2001年3月に使命を達成し運転を終了した。 ウランの濃縮に関する技術開発は、1972年に遠心法ウラン濃縮技術がナショナルプロジェクトに指定されて以降、国の方針に基づき、核燃料サイクル開発機構が中核となって進められた。 開発当初は、試行錯誤を繰り返したが、1976年までには現在の遠心分離機と基本的に同一の上下部軸受構造、駆動モーターの型式、回転胴の構造、ガスの給排気方式を確立した。また、分離性能も徐々に向上するとともに、回転安全性も増した。図1に遠心分離濃縮法のしくみを示す。 1976年に原子力委員会は、金属胴遠心機の開発で得られた成果を踏まえ、パイロットプラントの建設を決定した。パイロットプラントは3期に分けて建設し、第1運転単位の第1期(OP−1A)は、1979年9月に、第1運転単位の第2期(OP−1B)は、1980年10月に運転を開始した。また、第2運転単位(OP−2)は、OP−1Aより2倍の性能の遠心分離機を採用して1981年3月に運転を開始した。1990年3月に試験運転を終了するまでの約10年間の成果として、(1)約7000台規模の遠心分離機の生産およびプラントでの長期運転(約5万時間)により信頼性のある遠心分離機の生産技術の見通しを得たこと、(2)約51tUの濃縮ウランを生産し、プラント性能を実証したこと、および(3)カスケードを中心としたプラントの運転制御技術、UF6の分析技術、保安点検技術の確立などを挙げることができる。また、一部のウラン製品は新型転換炉ふげんに装荷され、日本における核燃料サイクルの輪を閉じることに貢献した。図2にウラン濃縮技術の開発ステップを示す。 1982年には、原子力委員会の決定を受け、200tSWU/年規模の原型プラントの建設・運転計画を策定した。原型プラントは、2期に分けて建設し、第1運転単位(DOP−1)は1988年、第2運転単位(DOP−2)は1989年に操業運転を開始した。プラントは順調な運転を継続し、1999年にDOP−2が、2001年にDOP−1が生産運転を終了した。この間、約13年に渡り、遠心分離機は連続運転を継続し、無故障であった。原型プラントの主な成果は、(1)電気事業者との役務契約に基づき、約350tUの濃縮ウランを生産したこと、(2)13年間の連続運転により遠心分離機の長期安定性を示したこと、(3)プラント運転技術のシステム化の確立、設備・機器の大型化および合理化などを挙げることができる。また、この間、東海再処理工場で生産された回収ウランを原料として運転を行い、濃縮ウラン約35tUを生産した。原型プラントの目的は達成でき、その技術をベースにプラント規模を拡大し、遠心機の高性能化を進めることで、国際競争力のあることが実証できた。図3にウラン濃縮原型プラントの外観および内部、図4にウラン濃縮施設の構成図、図5に遠心分離法濃縮プラントの開発、図6にウラン濃縮原型プラントの構成、図7にウラン濃縮原型プラントでの役務処理量の推移を示す。 1986年に原子力委員会が新素材高性能機の開発を決定したことを受け、電気事業者および(株)日本原燃と共同研究を開始した。この開発計画では、回転胴の材質が異なることから、これに関する開発項目に重点が置かれた。また、実用規模カスケード試験が、人形峠で約1000台の遠心分離機を用いて行われた。約2年の運転期間において1台の故障もなく、将来の新素材胴遠心機の先駆けとなった。その後、国際競争力を有する先導的な遠心分離機に必要な高周速化、長胴化の技術開発を行っていたが、1989年の原子力委員会報告で技術開発は民間が主導的に役割を担うことが提言されたことから、(株)日本原燃が中心となって開発を進めることとなった。その後、ウラン濃縮事業は整理することとなり、2001年3月に施設の運転を終了し、2001年9月末に開発業務は終了した。これまでに進めてきたウランの探鉱、採鉱、製錬、転換、濃縮の技術開発は、その成果の一部を民間の事業体に引継ぎ、その役割を達成した。 今後、多くの核燃料施設が廃止措置段階を迎えることから、廃止措置に必要な技術の開発・実証・費用の低減などが重要な課題になっている。人形峠環境技術センターでは、現在、精錬転換施設の解体を進めるとともに、廃止措置に関する解体技術、除汚技術、減容技術の開発・実証を行っている。その一環として、ウラン濃縮施設で使用した遠心分離機の処理技術開発に関し、汚染部分を分離除去して放射性廃棄物を大幅に低減する試験を行っている。また、使用した遠心分離機の内部には固体のウラン化合物が付着しているため、解体に先立ってこれらのウランを回収することが必要となる。付着ウランを再度ガス化して、六フッ化ウランとして回収する技術も開発している。人形峠環境技術センターの廃止措置を図8に、遠心機処理技術開発の概要を図9に示す。 一方、日本のウラン濃縮事業を進めるにあたり、核燃料サイクル開発機構は、事業主体として設立された(株)日本原燃と1985年に「ウラン濃縮施設の建設、運転等に関する技術協力基本協定」を締結し、六ヶ所ウラン濃縮工場の建設、運転等に必要な技術情報の提供、要員の派遣および受け入れを実施するなど技術移転および技術支援を行っている。2000年11月に(株)日本原燃は、今後の開発体制の一元化を図るため、青森県六ヶ所村にウラン濃縮技術センターを設置した。これに合わせて従来の協定が改定され、先導遠心分離機関連の技術情報の提供、要員の派遣を行っている。 人形峠環境技術センターでは、 ウラン資源および濃縮に関する技術開発の業務終了に伴い、ウラン鉱山等の跡措置について恒久的な安全確保のための措置を行い、跡地を有効活用する計画を進めている。対象施設は、主に岡山県、鳥取県に点在する捨石たい積場と、人形峠環境技術センター内にある鉱さいたい積場および選鉱施設である。探鉱および採鉱で発生した捨石は周辺の岩石と同様に花崗岩、礫岩および頁岩などにより構成され、合計22万立方メートル、平均U−238濃度は0.09以下〜0.42Bq/gである。製錬でウランを回収したあとに残った土砂である鉱さいは約3.4万立方メートル、平均U−238濃度は約3.0Bq/g、平均Ra−226濃度が16Bq/gである。その他、施設解体物が約1万本(ドラム缶換算)と予想されている。 (前回更新:2001年12月) <図/表> 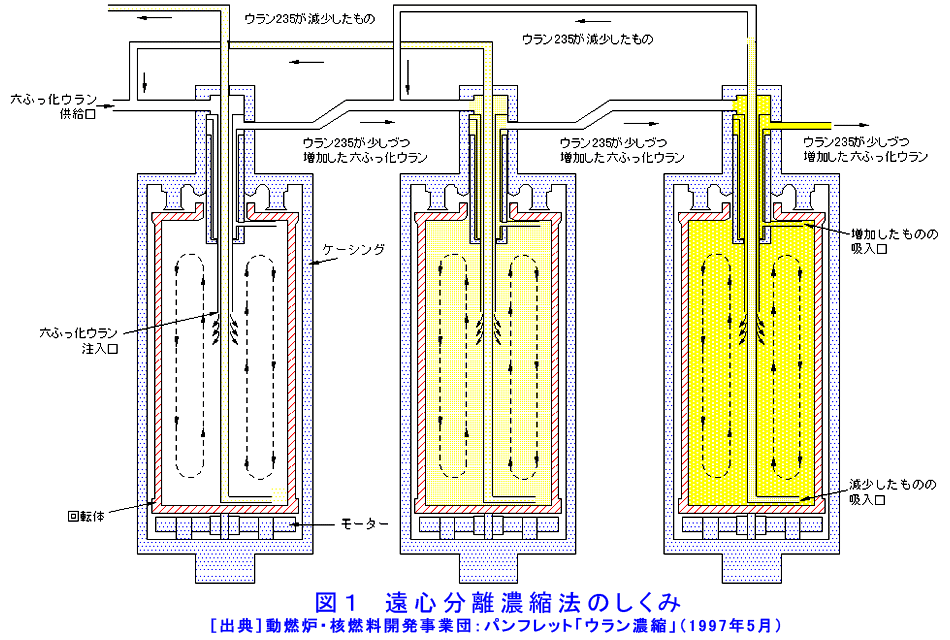
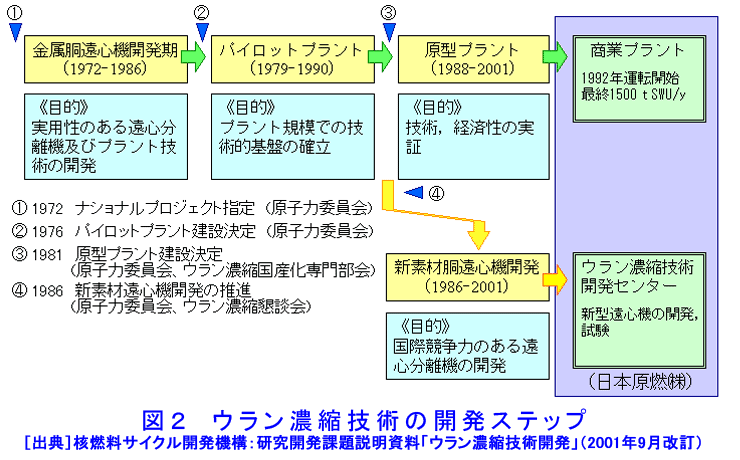
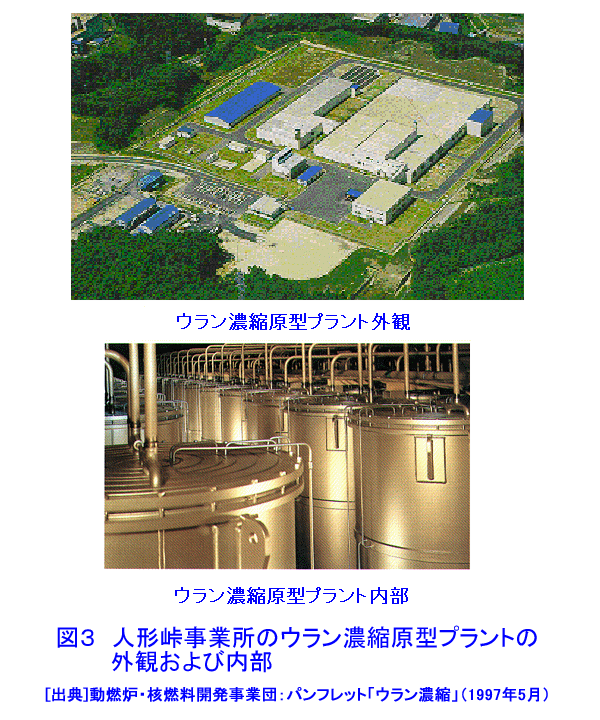
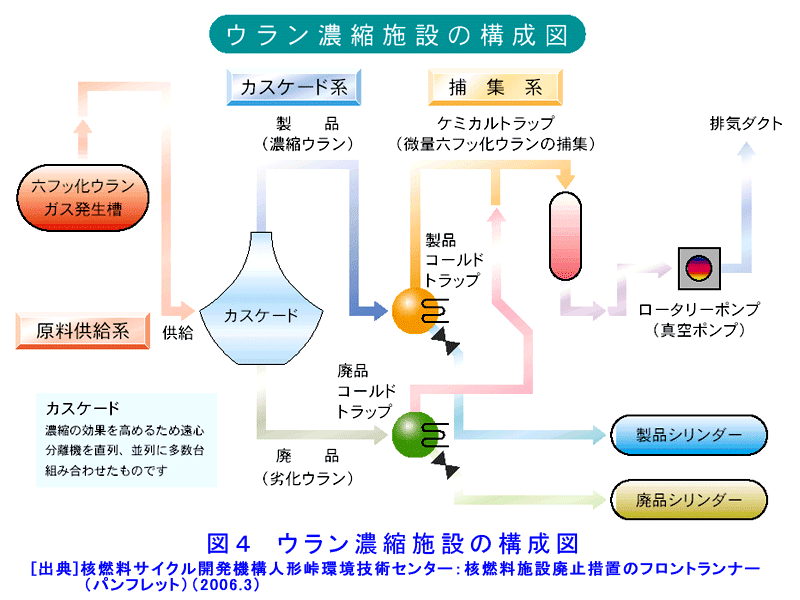
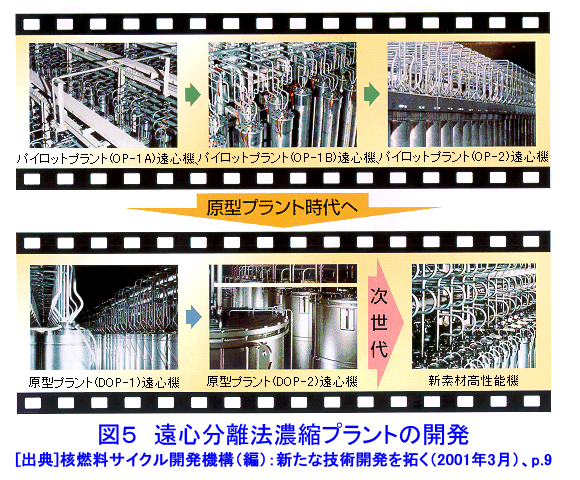
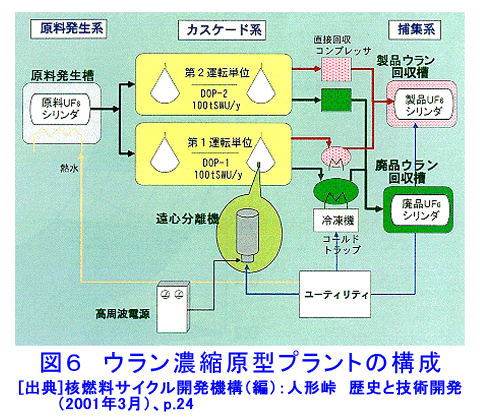
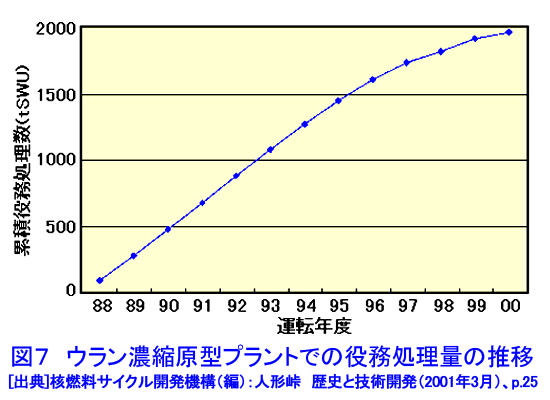
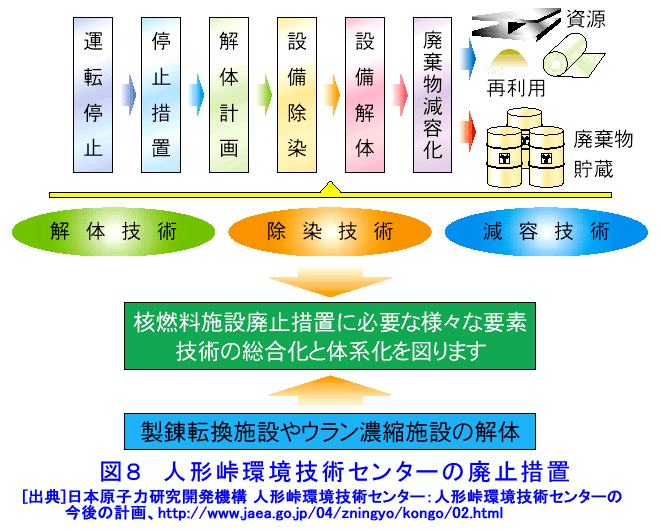
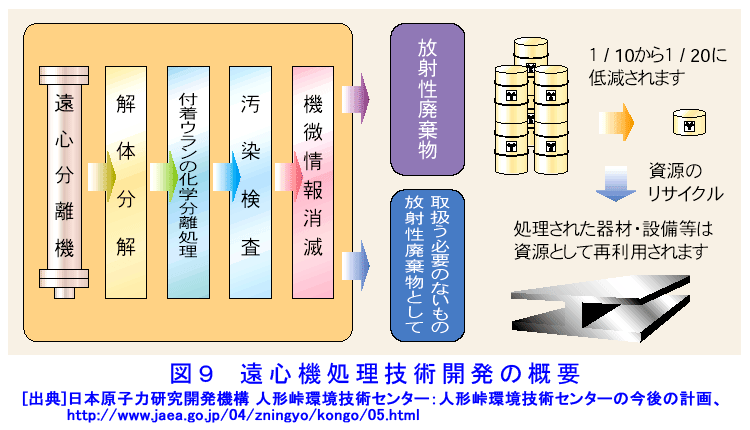
<関連タイトル> 六ヶ所ウラン濃縮工場 (04-05-02-03) <参考文献> (1)核燃料サイクル開発機構:研究開発課題説明資料「ウラン濃縮技術開発」(2001年9月改訂) (2)動燃事業団(編):動燃30年史(1998年7月)、p.365−372 (3)伊香修二、遠藤裕治:ウラン濃縮プラントにおける遠心機処理技術の開発、原子力eye、vol.47、No.1(2001年1月)、p.68−72 (4)遠藤裕治、片岡忍ほか:ウラン濃縮プラントにおける遠心機処理技術の開発、サイクル機構技報、No.7(2000年6月)、p.31−37 (5)杉杖典岳、松原達郎:ウラン濃縮原型プラントの目的と運転実績、サイクル機構技報、No.10、別冊(2001年3月)、p.3−9 (6)核燃料サイクル開発機構(編):人形峠 歴史と技術開発(2001年3月) (7)核燃料サイクル開発機構(編):新たな技術開発を拓く(2001年3月) (8)動燃炉・核燃料開発事業団:パンフレット「ウラン濃縮」(1997年5月) (9)日本原子力産業会議(編):原子力年鑑1996年版(1996年10月) (10)柴田朋文、甲斐常逸:遠心法ウラン濃縮技術の開発、動燃技報、No.100(1996年12月)、p.151−158 (11)核燃料サイクル開発機構:平成14年度研究開発課題評価(中間評価)報告書、課題評価「人形峠環境技術センターにおける環境保全技術開発−製錬転換施設とウラン濃縮施設における廃止措置及び放射性廃棄物処理に関する技術開発−」、JNC−TN1440−2003−001 (2003.6) (12)核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センター:核燃料施設廃止措置のフロントランナー(パンフレット)(2006.3) (13)佐藤和彦、時澤孝之:人形峠における鉱山跡措置に関する基本計画、日本原子力学会「2002年秋の大会」 (14)日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター:http://www.jaea.go.jp/04/zningyo/index.html
|

