|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
地球上には、大別すると天然起源の放射性核種と人工的に生成された放射性核種の2種類が存在している。天然起源の放射性核種は地球起源のものと、宇宙線と大気中の元素が反応して生成されるものに分類できる。一方、人工放射性核種は多々あるが主要なものは原子力発電に伴い発生する放射性核種と核爆発実験により生じた放射性核種である。天然起源の放射性核種については地球上の現存量を示し、人工放射性核種については、主として国連科学委員会の調査を基に、原子力発電を中心とする核燃料リサイクルの各工程で発生した主要核種の単位発電量当り放出量を、また核爆発実験に関しては生成されたストロンチウム(90Sr)の各年降下量を示した。最後にこれら放射性核種による人類の年間線量をまとめた。 <更新年月> 2020年09月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.はじめに 地球上には、天然起源の放射性核種と人工的に生成された放射性核種の2種類が存在する。天然起源の放射性核種はさらに地球起源の放射性核種および宇宙線起源の放射性核種に分類できる。また人工放射性核種は原子力発電に伴い生成されたもの、医療、工業等の利用のために生産されたもの、および核爆発実験で生じたものに分けることができる。 放射性物質はα、β、γ、中性子などの放射線を出す元素を含む物質である。周期表に見られるどの元素も放射線を出すものと出さないものに分けられる。各々、放射性同位元素、安定同位元素と呼ばれる。例えば質量数127のヨウ素は安定同位元素であり、質量数125、129や131〜135のヨウ素は放射性同位元素である。放射性同位元素は放射性核種とも言う。以下に、地球上の天然放射性核種と人工放射性核種の量を概観し、最後にこれら放射性核種から人類が現在受けている放射線量を示す。 2.天然放射性核種 (1)地球起源放射性核種:これらの核種は地球誕生以来存在していたもので、その主なものはウラン(238U)を親核種とし最終的には安定核種である鉛(206Pb)に至るウラン壊変系列上の核種、トリウム(232Th)から鉛(208Pb,安定)に至るトリウム壊変系列上の核種およびウラン(235U)からアクチニウム(227Ac)を経由し鉛(207Pb,安定)に至るアクチニウム壊変系列上の核種である。図1に各壊変系列、各核種の半減期(その核種の放射能が1/2に減衰するまでの時間)および壊変する時に放出する放射線を示す。天然ウランでは238U(約99.3%)と235U(約0.7%)が主体なので両壊変系列の放射性核種が生成する。表1には天然ウラン1トン中で放射平衡(壊変系列の1つの核種が崩壊して生成される娘核種の放射能とその娘核種が崩壊して減少する量が同じ状態をいう)にある放射性核種の質量を示す。このほか40Kのように壊変系列を構成しない核種がある。主な核種を表2に示す。天然カリウムは豊富に存在し、例えば海水1トンに約0.38kg含まれているので、40Kは約10kBqの放射能となる。また人体中の40Kは約3.9kBqである(文献4、p.164)。 (2)宇宙線生成放射性核種:宇宙線と大気低層の主成分原子である窒素、酸素、アルゴンなどとの核反応によって約20種類の放射性核種が常に生成され、崩壊している。宇宙線の強度も、宇宙線と反応する原子の大気中濃度も変化しているので、生成される放射性核種の生成速度は一定ではないが、長期間を考えれば各々の核種の生成量と崩壊量がバランスしており、地球上の存在量はほぼ一定していると見ることができる。表3は主な宇宙線による生成核種の半減期、平均生成速度および地球全体の地表における存在量を示している。 3.人工放射性核種 原子力の平和利用および軍事利用によりさまざまな人工放射性核種が発生しているが、以下では原子力発電と核爆発実験の各々から生じた放射性核種の量をまとめる。 3.1 原子力発電に伴い生成された放射性核種 原子力発電に伴う核燃料サイクルは、ウラン鉱石の採鉱と精錬、235Uの濃縮、燃料体の加工、原子炉による発電、使用済み燃料の保管・再処理、原子力施設間の核物質の輸送、そして放射性廃棄物の保管・処理等の多くの段階を含む。 原子力発電においても核分裂によって、核実験とほぼ同様の放射性核種が生成されるが、生成された放射性核種のほとんどは施設の中に格納されている。これらの放射性核種は、核燃料サイクルの各段階で、気体や液体の形で少量ではあるが環境への放出がある。 放出された放射性核種による被ばく線量は、自然放射線によるものに比べほとんど無視できる程度である。しかし事故のときは短期間ではあるが、その影響を無視できない。 また、採鉱、精錬等に伴い生ずる尾鉱からは、半永久的に気体状の222Rnが放出されるが、適当な処置により、この放出を大幅に減らすことが可能と考えられる。 これらの放射性核種によりフォールアウト放射能と同様な経路で人間が被ばくする。被ばく量の観点から重要な核種として、14C、3H、希ガス、ヨウ素等が挙げられる。また重要な放出経路として、発電炉からの気体状の放出ならびに再処理からの液体状の放出が挙げられる。詳細については「人工放射線(能)<09-01-01-03>」を参照にされたい。 原子力発電に伴う人工放射性核種は、発電量の増加に伴い増えてきているが、現在の時点では、自然放射性核種やフォールアウト放射能に比べると極めて少ない。単位発電量当りの放出放射性核種量は減少の傾向にある。 なお、原子力発電に起因する環境放射能の中には、通常運転中に少量ずつ放出されるものの他に、事故時に大量に放出されるものも含まれる。今までに、米国スリーマイル島発電所、旧ソ連チェルノブイル発電所等で大きな事故が発生しており、特にチェルノブイル発電所の事故の際には大量の放射性核種(希ガスおよびその他の核種とともに約2×1018Bq(5×107Ci))が環境中に放出された。 3.2 核爆発実験からの放射性核種 核爆発実験は1945年−1980年に大気圏内で実施され、その後は殆ど地下実験となった。大気圏内実験の内訳は、アメリカが1945−1962年に197(+22)回、旧ソ連が1949−1962年に219回、イギリスが1952−1953年に21(+12)回、フランスが1960−1974年に45(+5)回、中国が1964−1980年に22回、合計543回となる。( )の数字は安全性実験である。爆発収量は約440Mt(メガトン)(このうち核分裂によるものは約189Mt)である。表4に示すように3Hから241Puまで種々の放射性核種が発生するが、その中で代表的なものは30年前後の半減期を持つ90Srと137Csである。90Srの年間降下量を表5に示す。同表から理解されるように、アメリカおよび旧ソ連が大気圏内実験を1962年に打ち切ったため年間降下量は1963年をピークとしてそれ以降は減少している。この様子は137Csその他核爆発実験起因の放射性核種についても同様である。北半球での核実験が多くまた北半球は人口も多いので、核爆発実験による人類全体が受ける放射線影響の中での比率は高い(表6参照)。 4.人類が受けている放射線量 地球上には以上のようにさまざまな放射性核種が存在し、人類は放射線を受けている。国連科学委員会(2008年報告書)はこれまでに人類が受けている放射線量を調査し、文献2にまとめている。そのまとめを表7に示す。表中の実効線量とは、異なった複数の臓器・組織に吸収された線量の影響が、ガンあるいは遺伝的障害(以下「確率的影響」という。)と関連づけられるように、それぞれの臓器・組織に加重係数を乗じることにより求めた線量である。組織加重係数は、全身が均等に照射された結果生じるガンとか遺伝的影響等の損害の総計に対するそれぞれの臓器・組織の相対的な寄与を表わす。確率的影響の発生確率は被ばくした臓器・組織によって異なるため組織加重係数を用いて異なった複数の臓器・組織の確率的影響の全体を実効線量で表現する。 <図/表> 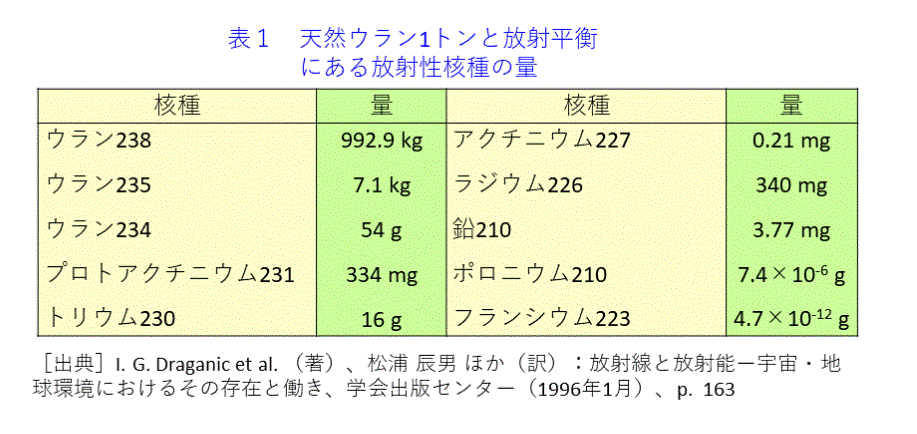
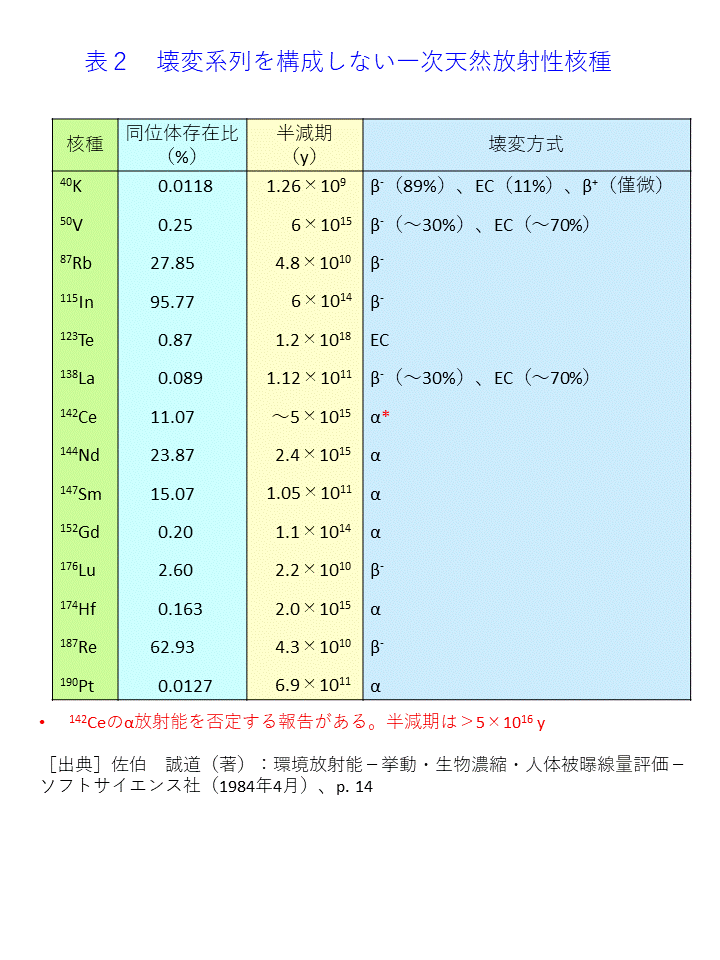
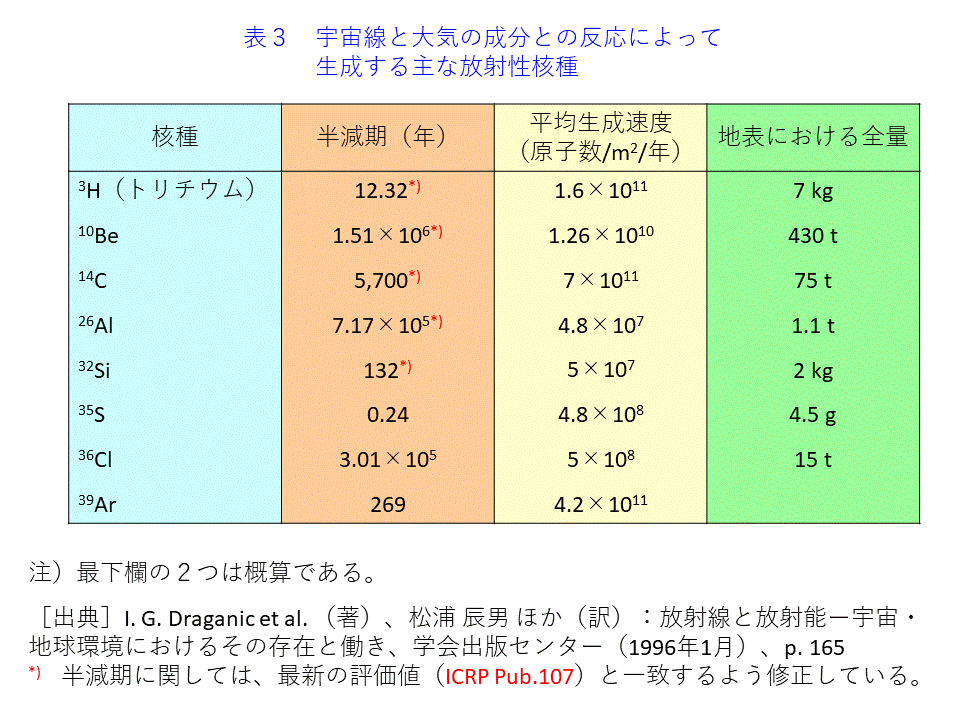
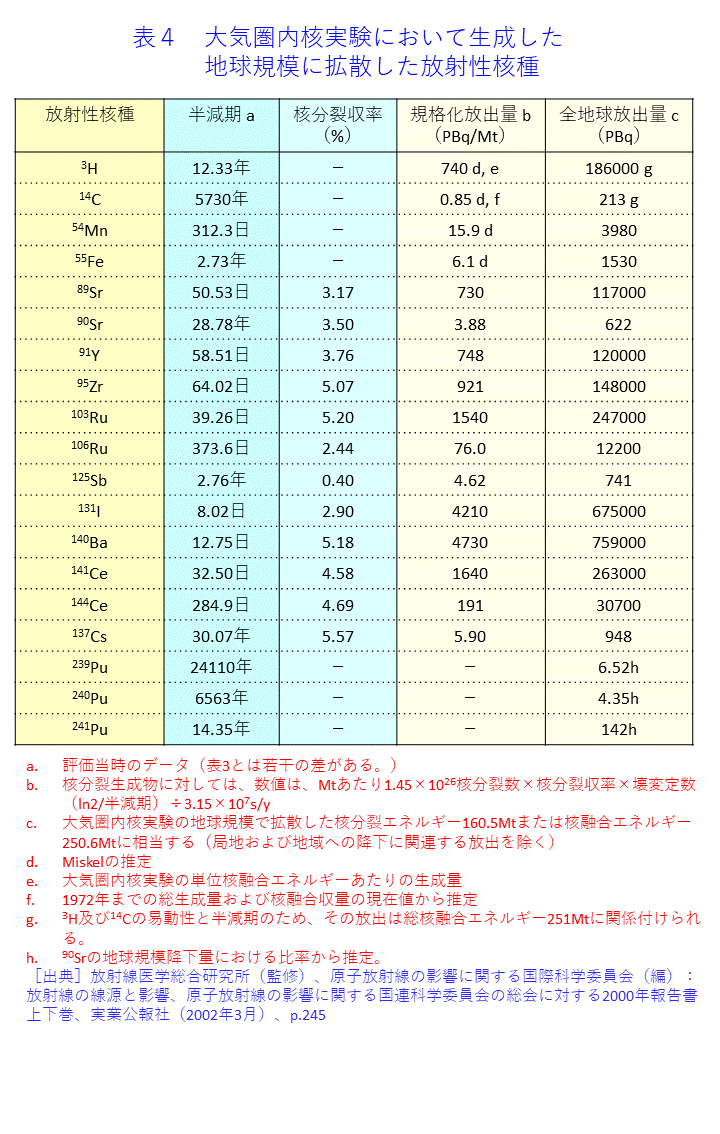
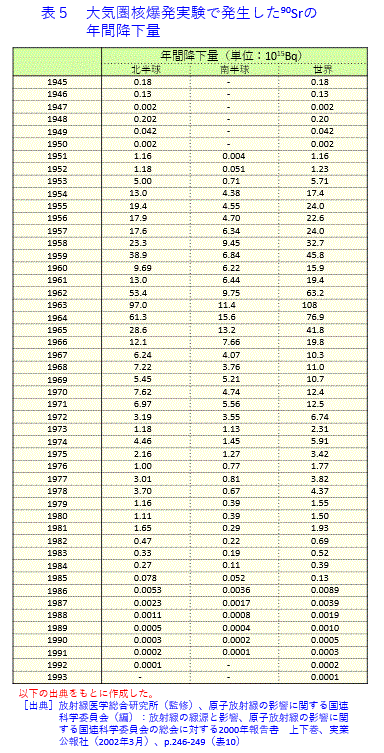
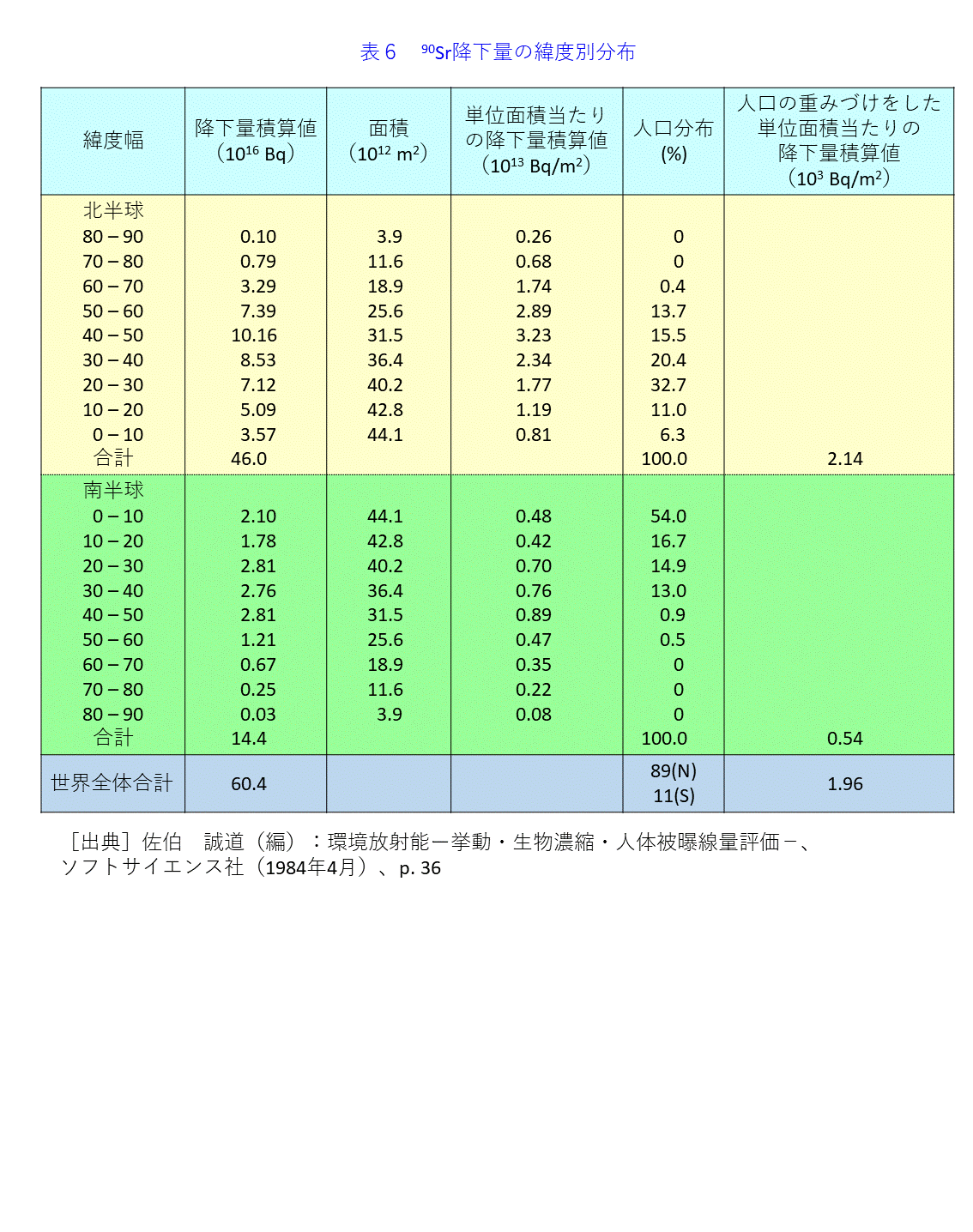
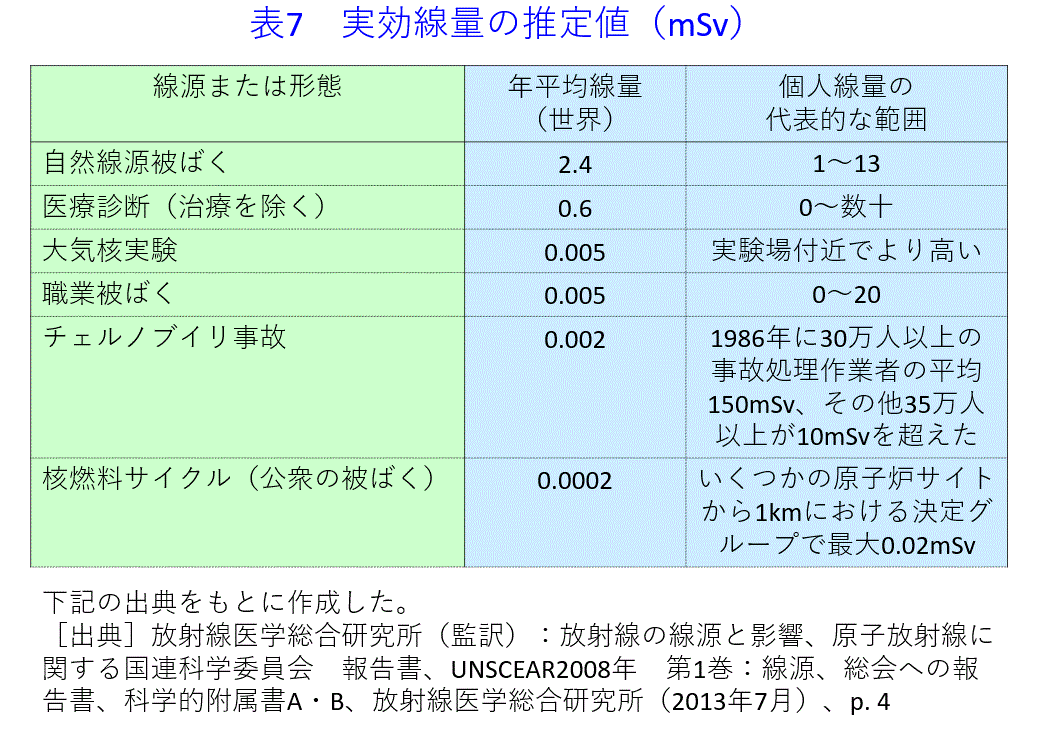
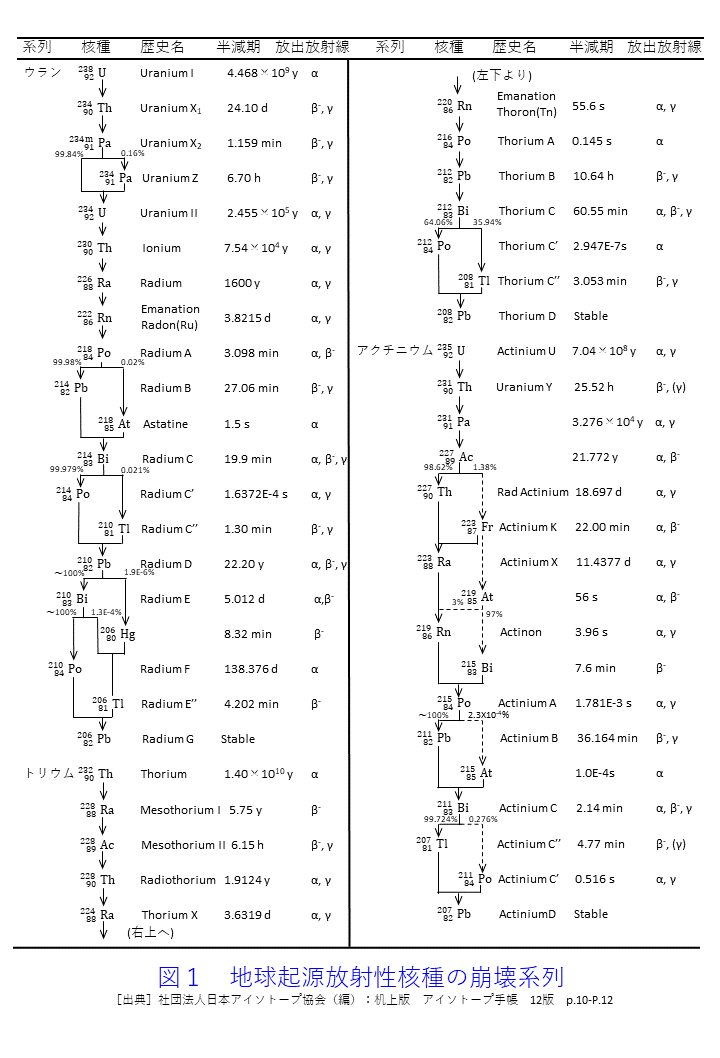
<関連タイトル> 壊変系列図、主な放射性核種の半減期 (18-03-01-01) 自然放射線(能) (09-01-01-01) 人工放射線(能) (09-01-01-03) 自然放射線による被ばく (09-01-05-04) 人工放射線による被ばく (09-01-05-06) <参考文献> (1)放射線医学総合研究所(監修)、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(編):放射線の線源と影響、原子放射線の影響に関する国連科学委員会の総会に対する2000年報告書 上下巻、実業公報社(2002年3月) (2)放射線医学総合研究所(監訳):放射線の線源と影響、原子放射線に関する国連科学委員会報告書、UNSCEAR1988年 第1巻:線源、総会への報告書、科学的附属書A・B、放射線医学総合研究所(2013年7月) (3)佐伯 誠道(編):環境放射能−挙動・生物濃縮・人体被曝線量評価−、ソフトサイエンス社(1984年4月) (4)I.G.Draganic et al.(著)、松浦 辰男ほか(訳):放射線と放射能−宇宙・地球環境におけるその存在と働き、学会出版センター(1996年1月)
|

