|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
X線CTは、通常のX線写真が被写体(人体)に一方向からX線を照射して、透過してきたX線の強度分布を直接画像化しているのと異なり、被写体に多方向からX線を照射し、透過してきたX線強度分布を検出器で測定し、得られたデータから計算によって被写体内部のX線の透しやすさの分布を3次元的に再構成する技術である。1972年に開発された当時は、X線を細いビームにして機械的に走査しながら照射し、計算も逐次近似法という方法が用いられていた。しかし、現在は撮影時間を短くするため、扇状のビーム(ファンビーム)を用いている。計算法も膨大な計算を短時間に行うため、逐次近似法ではなく、フィルター補正逆投影法を用いるのが一般的である。さらに、多数の断面を短時間に撮影するために、ファンビームの走査を連続させてらせん状に行ったり(らせんCT)、円錐状のビーム(コーンビーム)を用いる方法が行われている。 <更新年月> 2009年02月
<本文>
1972年、イギリスのEMI社のSir G.N.Hounsfieldによって開発されたX線CTは、従来のX線単純撮影写真では描出不可能か、または不可能に近かった頭蓋内部の様子を極めて鮮明な映像で表示した。X線吸収の大きい骨で囲まれた脳内の模様や、X線吸収係数の差の少ない脳組織をX線画像上で識別できたため、当時の医学界に大きなセンセーションを巻き起こした。 1.X線CTの原理 CT、すなわちComputed Tomographyでは、投影データから計算して断面像を作成する。このことを再構成というが、その意味は多方向から求めた一次元投影を組み合わせて、二次元(面)情報(すなわち画像)を作り上げることである。再構成処理法は数学的には非常に興味深い問題であり、多様な方法があるが、ここでは、現実のX線CTで使われている方法を原理的に述べる。 図1、図2は断面として、CTの撮像視野内にX線の吸収率が大きい、すなわち、高吸収の点状物体(図の例では釘)が1個ある場合を想定している。 (1)逆投影法:この方法は実際に使われてはいないが、再構成法の基礎となるものなので、最初に考えてみる。いま、X線管と検出器が対となって視野を横切るように走査すると、図1(a)のように、釘の位置に対応した場所にピークを持つ投影データ(一次元情報、第一投影)が得られる。逆投影とは再構成される画面に対応して設けられたメモリに、ピークの高さに比例した数値を、投影を求めた方向と同じ方向に等しく分配する。図1(a)の下の図はそれを示しており、斜線の部分のメモリに数値が均等に割り当てられる。つぎに、1回の走査が終わると、X線管と検出器はともに一定角度だけ回転してから再び走査して、図1(b)に示す投影2を求め、前に逆投影したメモリに重ねるように数値を分配する。続いて、投影3では、投影1からみて直角方向まで回転、走査後、逆投影される。図1(c)は、このような逆投影を多くの方向から行った結果であって、すべての逆投影が重ね合わされ、中心の重なりは釘の位置に等しい高濃度の場所となる。しかし、その周囲にも投影された数値が尾を引いて、スポーク状のボケが生じてしまう。とはいえ、よく見ると、このボケは高濃度の点状物体からの距離に反比例して減少する性質を持っていることがわかる。つまり、逆投影によって得られた画像は、元の断面のX線吸収係数分布を(距離)の−1乗という関数でぼかしたものなのである。 (2)フィルタ補正逆投影法:本法は、逆投影法で生じる(距離)の−1乗というボケを除くことを狙ったものである。逆投影法では、求められた投影の大きさに正比例した数値を逆投影するのであるが、本法では投影データに対して、ある種の変換を行ってから逆投影しようとするものであり、その変換のことをフィルタ処理という。その方法を図2によって説明する。まず、原断面は図1(a)と同じく、視野内に高吸収物体(釘)が1個だけあるものとする。投影も前と同様に、角度に応じて投影1、2、3・・・と得られるが、それらの投影に対して、ある特性を有するフィルタによる処理を行い、図2(a)に示すフィルタ補正後の投影を計算する。したがって、フィルタ補正後の投影も角度によって、1、2、3・・・と求められる。 フィルタ処理に用いられる演算は重畳積分といわれ、どのような周波数特性を持つフィルタを用いるかによって、再構成される画質が異なってくるため、さまざまな種類のフィルタが発表されている。 ここでは定性的な説明にとどめるが、実は、よく使われているフィルタは図2(a)に示したように、原点が正で、それ以外では負であり、原点から遠ざかるに従って0に近づくような関数である。図2(b)は点状物体に対して、フィルタ補正後の投影を各方向から逆投影して重ね合わせた再構成像である。フィルタ補正後の投影データは(a)に見られるように、点状物体に対応する場所が正、それ以外は負であるから、直観的にわかるように、中心の正の部分の交差する点は重なり合って高濃度となるが、その点以外は、正の部分と周囲の負の領域とが相殺し合って、ほぼ0になる。そのため、高濃度の点が残り、周囲のボケが消えるような結果となり、忠実に元の断面が復元される。 X線CTの特徴としては、1)1次取得した元データからの再構成画像から、位置情報と吸収値がデジタルデータとして得られるため、さまざまな画像処理ができることは大きな特徴である。マトリックス数を増やせば、一般撮影並の空間分解能にも近づけられるし、任意の断面の再構成のような多次元の画像再構成も可能となる、2)良好な密度分解能が得られるため、一般のX線撮影では識別できない水と実質組織が同じ厚みでも識別可能である、3)一般の断層撮影では、画像の歪みを生じる障害陰影のない人体横断像が取得できる、などがある。 2.性能と限界 X線CT装置(図3参照)の性能は、大まかには、X線ビームをどれだけ精度よく照射して計測できるか、また、限られた時間でどれだけ大量のデータを得て計算できるかにかかっている。現在利用されている医療用X線CTでは、高画質・高分解能・高速スキャンによって断面像を再構成するだけの性能がある。そして、その像は従来の断層撮影に比べて信号対雑音比(S/N比)が極めて高いため、わずかなX線透過性の差を画像の上で検出できる。 しかしX線CTにも絶え間ない進歩がある。それらのうち、最近の大きな進歩は次の2点である。その一つは撮影速度の向上である。CTでは「被写体は走査中は動かない」という前提で計算をするので、走査中に被写体が動くと再構成画像が乱れてしまう。これに対しては、走査中に呼吸を止めるなどの努力である程度の解決が計られてきたが、心臓や腸管など生理的に動きを止めることができない臓器に関しては、適用に限界があった。その解決策の一つが、X線ビームを電気的にスキャンさせるタイプの超高速CTの出現である。 もう一つの発展は、体軸方向のデータの質の向上である。通常のX線CTでは、1回の走査で得られるのは数ミリないし10ミリメートル厚さの一断面であり、大きな臓器全体についての情報を得るには、一断面ずつずらしながら繰り返してデータの採取を行なっていた。これには複数回の走査が必要となるため、現実には十数分以上という相当の時間を必要とするし、断面と断面のすりあわせも位置精度が不十分であった。その解決策として発明されたのが「らせんCT」(ヘリカルCT、スパイラルCTなどとも呼ばれる;図4参照)である。「らせんCT」では、X線管を患者の周りで連続的に回転させ、そのなかを通り抜けるように患者の体を移動するので、多断面のデータ採取が連続して可能になる。 3.X線CTの応用(図5参照) X線CTが開発され、最初にその恩恵をうけたのは脳血管障害(脳出血・脳梗塞やクモ膜下出血)や脳腫瘍の診断であった。当時、この種の疾患の障害部位を診断するのは容易ではなかったが、頭部は体幹に比べて小さく、固定をしっかりしておけば比較的長時間不動を保つことができたことから、撮影可能な断面積が小さく、分解能も悪く、スキャンに時間を要した初期の装置でも、その果たした役割はたいへん大きかった。 その後の周辺技術の進歩により性能が飛躍的に向上した現在、造影技法との組み合わせなどにより、全身のほとんどの部位の診断に何らかの貢献をしているといってよい。また、人体のX線透過性に関する分布が、デジタルデータとして3次元的に得られるところから、放射線治療の際の実際の線量分布の計算や、推定のためのデータ源としても利用されている。 4.被ばく線量 X線CTは、X線被ばく量が単純撮影に比べると多い。皮膚表面の一番たくさんX線が照射されるところで考えると、胸部単純撮影としては比較的線量が多いといわれる間接撮影でも0.34−0.74mGyであるのに対し、CTは20ないし40mGyである。実効線量で考えると、CTで胸部全体を撮影した場合の6ないし10mSvに対し単純撮影は0.05mSvである。とはいえ確率的影響が起きる量に比べれば何桁も低いし、確率的影響にしても一般臨床での使用を前提にリスクとベネフィットのバランスを考えれば問題にならない。 (前回更新:2002年3月) <図/表> 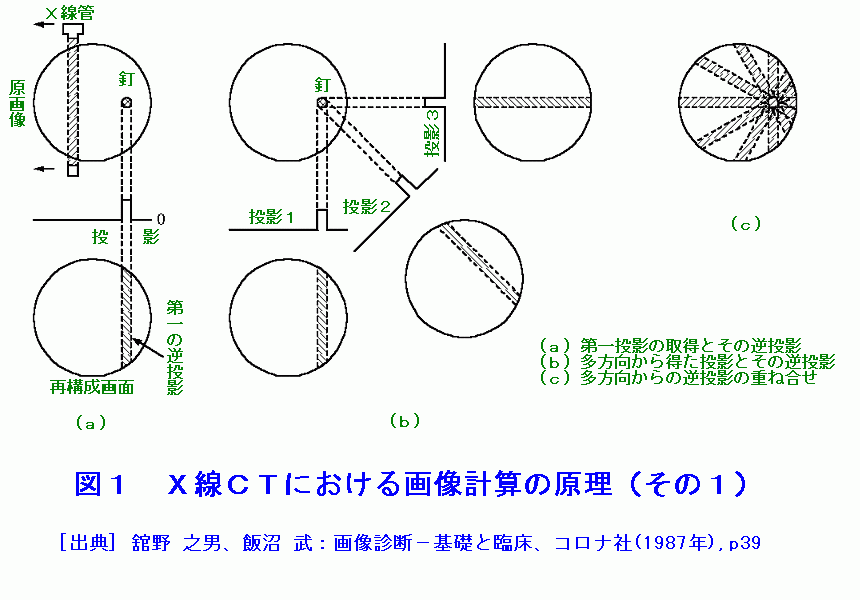
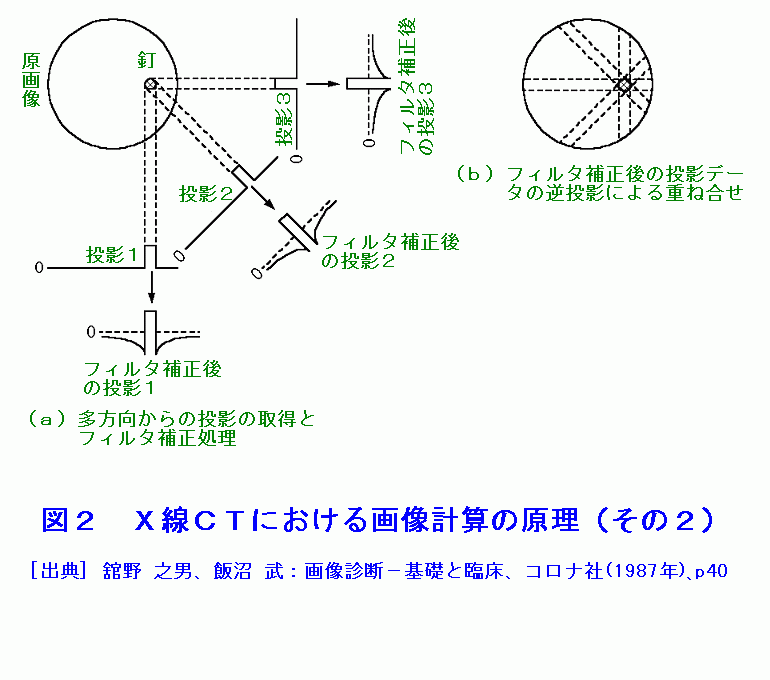
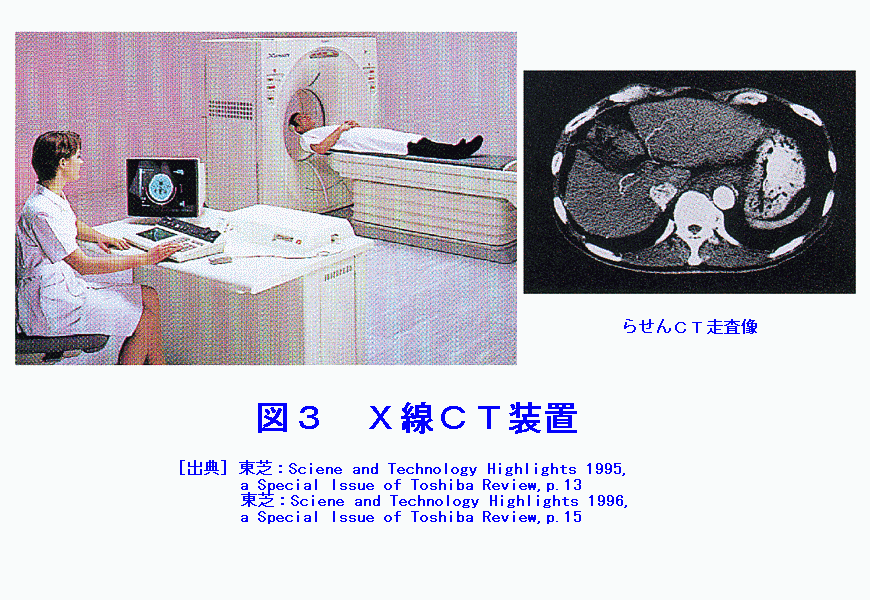
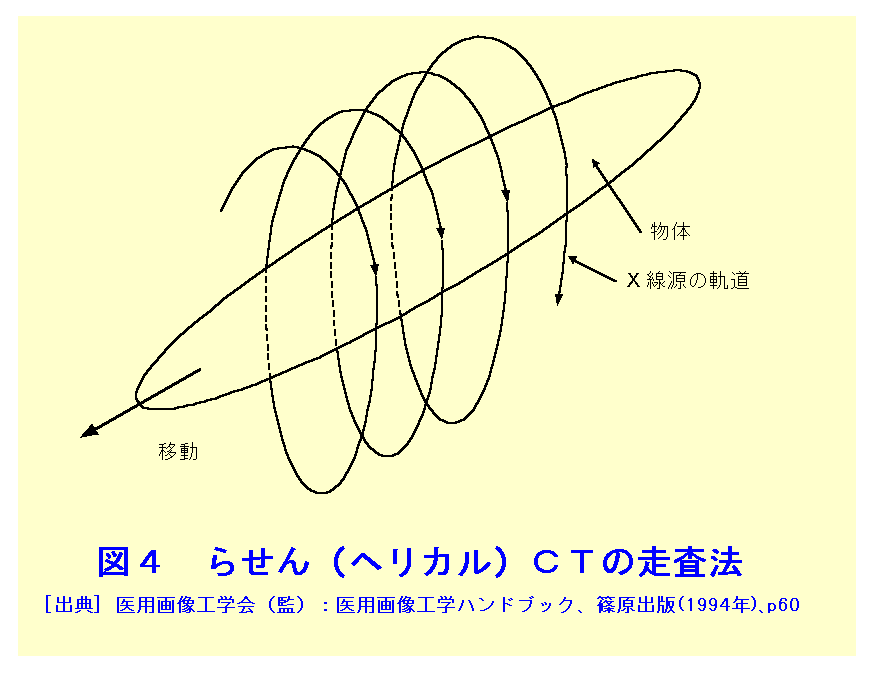
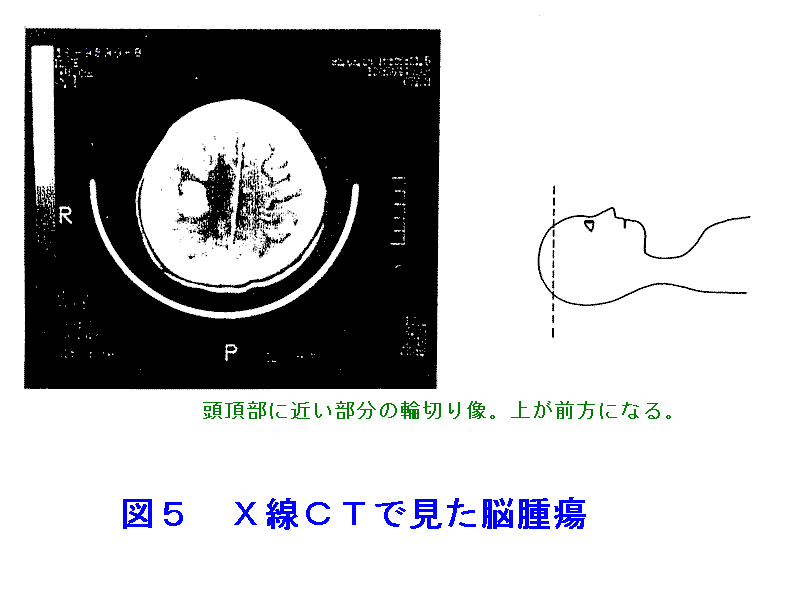
<関連タイトル> X線診断 (08-02-01-01) 医療分野での放射線利用 (08-02-01-03) 医療被ばく(患者の診断・治療時)の評価 (09-04-04-09) <参考文献> (1)舘野 之男、飯沼 武:画像診断−基礎と臨床、コロナ社(1987年) (2)医用画像工学会(監):医用画像工学ハンドブック、篠原出版(1994年) (3)舘野 之男ほか:超高速CT、医学書院(1991年) (4)丸山 隆司、岩井 一男、神津 省吾:胸部集団検診における臓器・組織線量と実効線量、厚生省がん研究助成金による各種がん検診の共通問題に関する研究、平成6年度研究報告(1995)p80 (5)西澤 かな枝、丸山 隆司、高山 誠、岩井 一男、古屋 儀郎:CT検査による被験者の被ばく線量、日医放会誌、55(11)、37−42(1995年) (6)東芝:Sciene and Technology Highlights 1995,a Special Issue of Toshiba Review,p13 (7)東芝:Sciene and Technology Highlights 1996,a Special Issue of Toshiba Review,p15 (8)河野 通雄・木村 修治(編):放射線診断学、金芳堂(1996.4)
|

