|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
1997年11月20日、日本原子力研究所東海研究所(現日本原子力研究開発機構原子力科学研究所)のウラン濃縮研究棟で発生した火災事故に関し、火災事故発生前後の事実経緯、火災原因、事故の再発防止対策などについて調査、検討が進められた。その結果、火災事故は、ウラン屑が試験装置の解体中に水で濡れ、このため可燃性ガスが発生し、それが爆発的に燃焼して起きたことが判った。ここでは、火災事故の経緯、原因調査の結果、再発防止対策及び事故現場のその後の措置について述べる。 <更新年月> 1998年10月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.火災事故発生までの経緯 (1)試験終了後の措置 日本原子力研究所東海研究所(現日本原子力研究開発機構原子力科学研究所)ウラン濃縮研究棟の原子蒸気実験室(図1)に設置した多目的長尺セル(図2、以下、「セル」という)を用いた試験が終了し、使用したウラン金属をセルから回収し安定化措置を施すこととなった(図3)。作業マニュアルでは、ウラン金属は一次酸化措置の後に金属缶に収納され、金属缶内は不活性ガスに置換される。その後、ウラン屑は二次酸化措置により安定化することとなっている。 一次酸化措置とは、セル内を真空引きした後に空気を大気圧まで導入・密閉し、表面酸化によりウラン金属の化学的安定化を図る操作を繰り返す作業である。この際、セル内に導入した大気中の酸素の減少による圧力低下が認められなければ、一次酸化が終了したと判断する。この段階で生成した粉末状の物質は、ウラン屑と称される。二次酸化措置とは、ウラン屑を大気中600〜800℃で重量変化が認められなくなるまで加熱・酸化する処理である。ウラン屑は大気中での安定な化合物、八酸化三ウラン(U3O8)に転換される。 (2)ウランの回収・収納措置 回収にあたり、真空排気と大気導入の操作を7回繰り返した後に、セルは10月18〜20日の間は大気を導入したままに密閉・放置され、セル内の圧力低下の生じないことが確認された。 11月11〜19日にウラン屑が回収された。ポリエチレン袋に入れられたウラン屑は内缶と外缶から構成される11個の金属缶(図4)に収納された。金属缶は原子蒸気実験室に重ねて置かれた(図5(1))。また、この作業で発生した可燃性固体廃棄物(濡れウェス、タイベックスーツ、ゴム手袋など)を収納した約20個のカートンボックスは金属缶の近くに置かれた。 ウラン屑の回収と並行し、セル内の蒸発容器(以下「るつぼ」という)のウラン金属塊が回収された。この際に、るつぼ全体を解体することが必要となった(図6、図7)。そこで、11月12日からるつぼの冷却水が排出された。11月19日に、るつぼ側壁内の冷却孔に接続されているフレキシブルホース(成形べローズ管)がカップリング部分で取り外された際に、るつぼ側壁内及びフレキシブルホースに残っていた数百ミリリットルの水が漏れ出てウラン屑の一部を濡らした。水に濡れた約4キログラムのウラン屑はポリエチレン袋2袋に分けて入れられ、11月12日までに回収された乾いたウラン屑の1袋と共に11個目の金属缶(No.11金属缶)に収納された。 これら金属缶内は11月20日以降に不活性ガスに置換される予定であった。 2.火災発生から鎮火までの経緯及びその後の措置 (1)消火活動 11月20日午前1時15分に、中央警備室で原子蒸気実験室の火災報知器の警報が発報した。自衛消防隊は、午前1時18分に出動し、午前1時32分頃1階の階段室付近から2階にかけて煙を確認し中央警備室に通報した(図1)。中央警備室は東海村消防署へ火災発生を通報した。 火災発生時には原子蒸気実験室の給・排気系は運転されていたが、火災発生後、排気系のフィルターが目詰まりを起こしたため同実験室の負圧が維持できなくなり、原子蒸気実験室から煙が流出した。そこで、給気系をいったん停止し排気系フィルターの交換が行われた。なお、煙流出による管理区域外の放射能汚染は認められなかった。 11月20日午前2時35分に、職員と東海村消防署員が、原子蒸気実験室に入り燃えていたカートンボックスの火を消火砂で消し、午前3時40分に鎮火が確認された(図5(2)、図8)。 (2)鎮火後の措置 火災と同時にウラン濃縮研究棟への立ち入りは管理され、同棟の除染が行われた。また、ウラン屑の入った金属缶内はアルゴンガスに置換された。その後、金属缶の表面温度測定と外観の監視を継続しているが、表面温度、外観共に有意な変化はない。 火災事故の原因を検討するため、火災現場の調査と共に、金属缶の内容物、周辺の飛散物などの試料の採取と分析、試験及びその結果の評価が行われた。 (3)環境への影響など 排気ダストモニタによる排気中の放射能濃度の記録を評価した結果、周辺環境への影響はなかった。鎮火後の綿密な汚染検査の結果、階段室の入口近くに消火にあたった作業者の出入りによると推定される点状の汚染が一点のみ認められた。消火作業などに携わった消防署員、職員などの被ばくは検出下限以下であった。 3.火災発生原因及び事故経過の推定 (1)火元の検討 火災現場を調査し火災発生の原因を、(a)実験室内への不審者の侵入・放火、(b)実験室内の電気機器の過熱・漏電、(c)ガス器具の過熱・ガス漏れ、(d)発火性薬品及び(e)ウラン屑による発火に分けて検討を行った(表1)。その結果、(a)〜(d)は今回の火災事故の原因とはならない事が判明し、カートンボックス或いは金属缶中のウラン屑が何らかの原因で発火し火災事故となったものと推定された。 (2)カートンボックス中のウラン屑による発火の検討 分析などの結果から、カートンボックス内の可燃性固体廃棄物にはウラン屑の付着は殆ど無いことが判った。また、No.11金属缶の約1メートル以内に金属缶からの飛散物とみられるウラン屑があり、さらに、No.11金属缶の内缶内のウラン屑は、内缶と外缶の間で見つかったウラン屑よりも酸化が進んでいた。このことから、カートンボックスが先に発火した可能性は小さい。 (3)金属缶のウラン屑による発火の検討 火災現場の調査、金属缶の調査、内容物及び飛散物の分析、試験及び評価(1)などから発火の原因が検討された。 (a)No.11金属缶外蓋の調査 ウラン屑を収納した11個の金属缶のうち、水に濡れたウラン屑が収納されていたNo.11金属缶の外缶の蓋(以下、「外蓋」という)だけが金属缶から外れ、約1.5メートル離れたところに飛んでいた(図8)。外蓋の床に面していた面(缶の内側)は、表側(缶の外側)に比べウランによる汚染は著しく少なかった(表2)。また、外蓋には、内圧上昇によると考えられる変形はあったが、熱による変色は殆ど無かった。 金属缶の内圧上昇試験及び有限要素法による外蓋の変形の解析を行った。その結果、ゆっくりとした金属缶内の圧力(内圧)の上昇では外蓋と金属缶の隙間からガス漏れが起きるだけで外蓋は外れない。しかし、内圧を0.05秒間に2.5気圧に上げると外蓋を金属缶に固定する金具が変形し、外蓋は金属缶から抜け飛ぶことが判った。また、外蓋の実際の変形と解析結果の一致は良い(図9)。 以上のことから、内缶中で可燃性ガスが発生し、それが金属缶内で爆発的に燃焼したため外蓋が抜け飛んだと推定された。 (b)可燃性ガスの発生の検討 No.1、2および8金属缶から採取したウラン屑の性状分析を行い、この結果を1989年度発煙事故時に回収したウラン屑と比較検討すると共に、ウラン屑の加水分解試験を行い結果を評価した。 今回のウラン屑はウラン炭化物及びウラン金属の割合が高かった(表3)。その加水分解試験により、メタン及び水素を主成分とする可燃性ガスの発生がみられた(表4)。No.11金属缶内のウラン屑に約2kgのウラン炭化物と数10〜100ミリリットルの水が混入していたとすると、8〜9時間内に約500ミリリットルの可燃性ガスが発生した可能性がある。また、加水分解反応によりウラン屑の温度が上昇すると、可燃性ガスの発生量がさらに増加する可能性がある。 密閉された内缶(容量約4.5リットル)内部で、可燃性ガスと空気の混合気体が爆発的に燃焼する組成に達するには、300〜400ミリリットル以上の可燃性ガスが必要であり、試験結果から金属缶内で爆発的に燃焼する混合気体ができることが判った。また、加水分解反応に並行し、空気で発火し易いウラン水素化物(UH3)がウラン屑の中に生成し易い。 (c)火元の検討 ウラン金属は空気中の酸素との反応によって自然発火する可能性があり(文献2)、ウラン水素化物は空気中の酸素と反応して直ちに発火することが知られており(文献2、文献3)、また、米国で水素化物の爆発的燃焼の事故例がある(文献4)。 (4)事故経過の推定 上記の試験・検討の結果から、火災事故の経過は以下のように推定された。 (a) 11月19日、るつぼの分解作業中、少量の水が漏れセル内のウラン屑を濡らした。 (b) 水に濡れたウラン屑の入ったポリエチレン袋は、乾いたウラン屑のポリエチレン袋と共にNo.11金属缶の内缶に密閉された。内缶は外缶に密閉された。この金属缶は、2段に積んであった金属缶の上に置かれた。約20個のカートンボックスはその間近に置かれた。 (c) 金属缶の内缶の中で、水に濡れたウラン屑の加水分解反応が起き、メタン、水素などの可燃性ガスが溜まっていった。ウラン屑中にウラン水素化物が生成した。 また、ウラン屑中でウラン金属と空気の反応、ウラン水素化物と空気の反応などの発火元になる酸化反応が進んだ。 (d)発火元の反応により、可燃性ガスと空気の混合気体の爆発的な燃焼が起き、外缶の蓋が抜け飛び新たな空気が金属缶内にが流入した。引き続き、流入した空気とウラン屑により激しい酸化反応(燃焼)が起きた。一部のウラン屑は激しく燃焼しながら半径約1メートルの範囲に飛散し、カートンボックスに火をつけ火災が発生した。 4.再発防止対策 事故の再発防止のため、以下の改善策を講じることとなった。 (1)ウラン屑などの発火性物質の取扱について、化学反応による潜在的危険性を周知する安全教育を行う。また、その取扱について所内の専門家の意見を得る体制をつくる。 (2)発火性物質は、所定の場所への適切な保管を徹底すると共に、使用計画のない物質は速やかに安定化措置を施す。 (3)可燃性固体廃棄物は、その日のうちに所定の廃棄物保管場所に保管する。廃棄物保管場所は、不燃材料による区画に改善する。仮置する場合には、明確に区分した延焼のおそれのない仮置場を設定する。 (4)排気系フィルターの目詰まりについては、適切な給排気系の運転方法及びフィルターの交換方法を検討する。 (5)実験室における使用物質、その使用状況、防火(消火)上の注意等の情報を、研究施設及び実験室毎に適切に表示及び提供する方法を検討する。 5.事故現場の措置等 (1)除染・復旧作業 ウラン濃縮研究棟の管理区域の除染は1998年1月27日に終了した。ウラン屑は核燃料貯蔵庫に収納され、実験室内の空気中放射能濃度は検出下限値未満である。また、当該管理区域における放射線レベルは通常状態に復帰した。同棟内外で放射線管理上の問題はない。 (2)ウラン屑の措置 原子蒸気実験室にあったウラン屑は、12月19日迄に全て不活性ガス(アルゴン)雰囲気の金属缶に収納され核燃料貯蔵庫に保管されている。ウラン屑の二次酸化措置は1998年10月までに実施される予定である。 なお、詳細は日本原子力研究所より報告されている(文献5)。 <図/表> 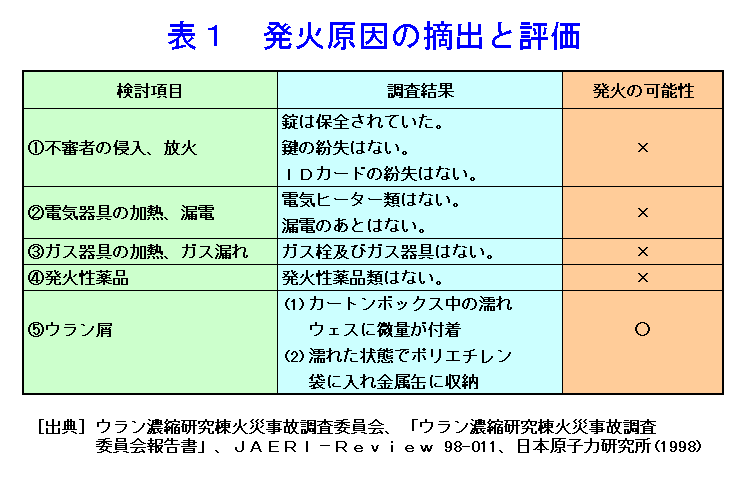
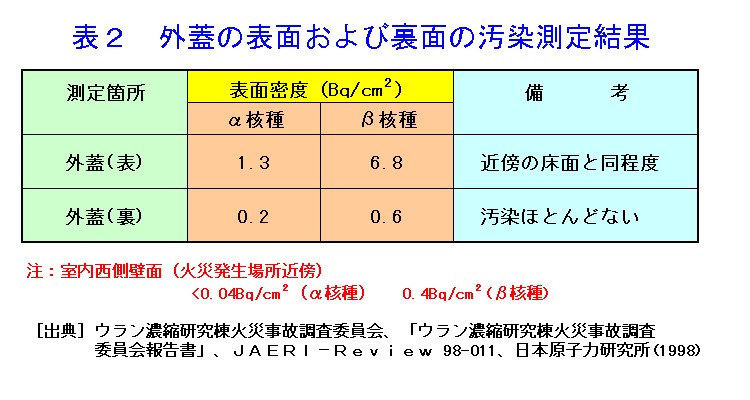
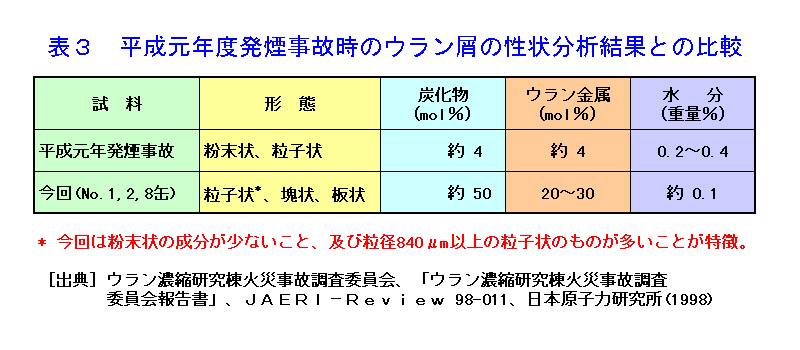
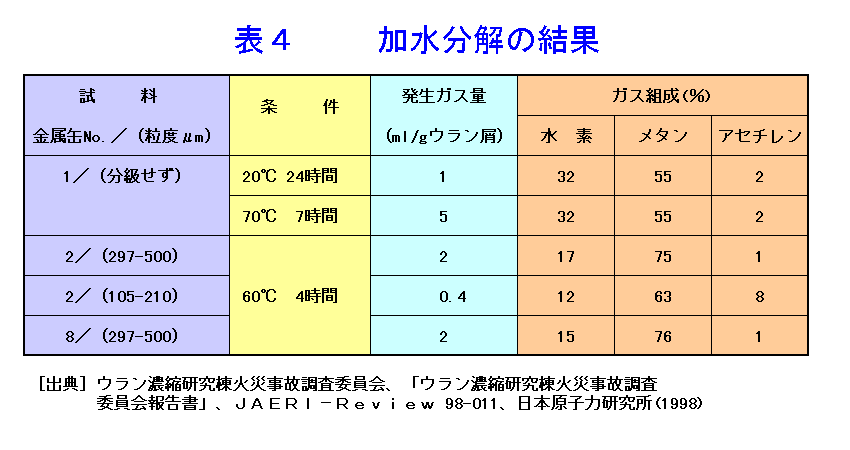
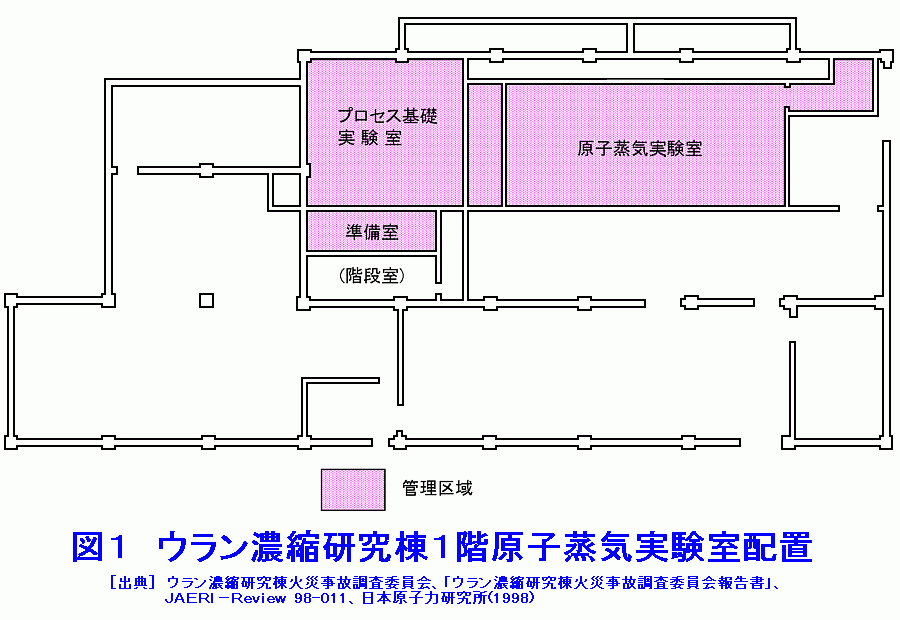
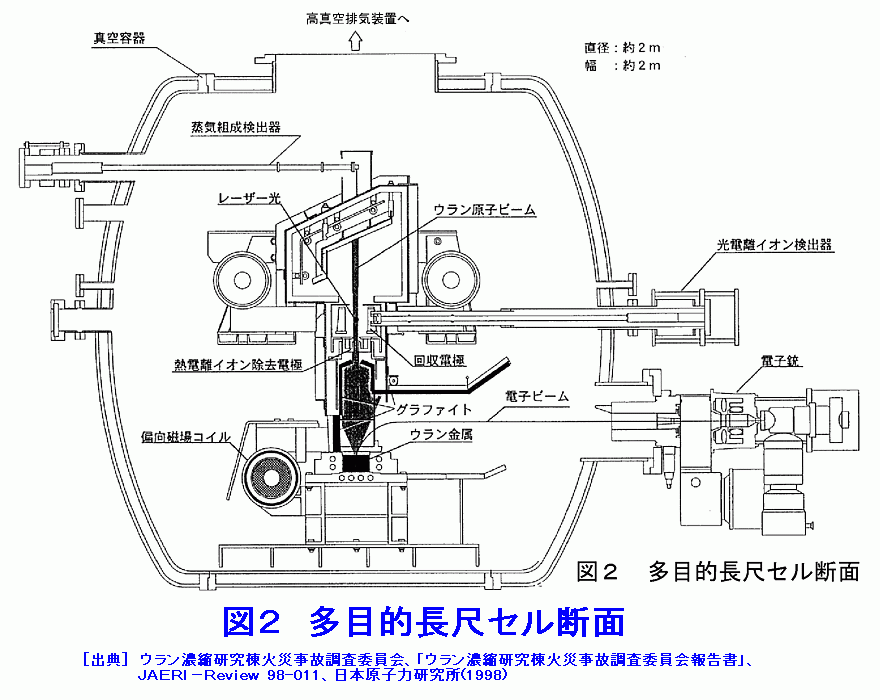
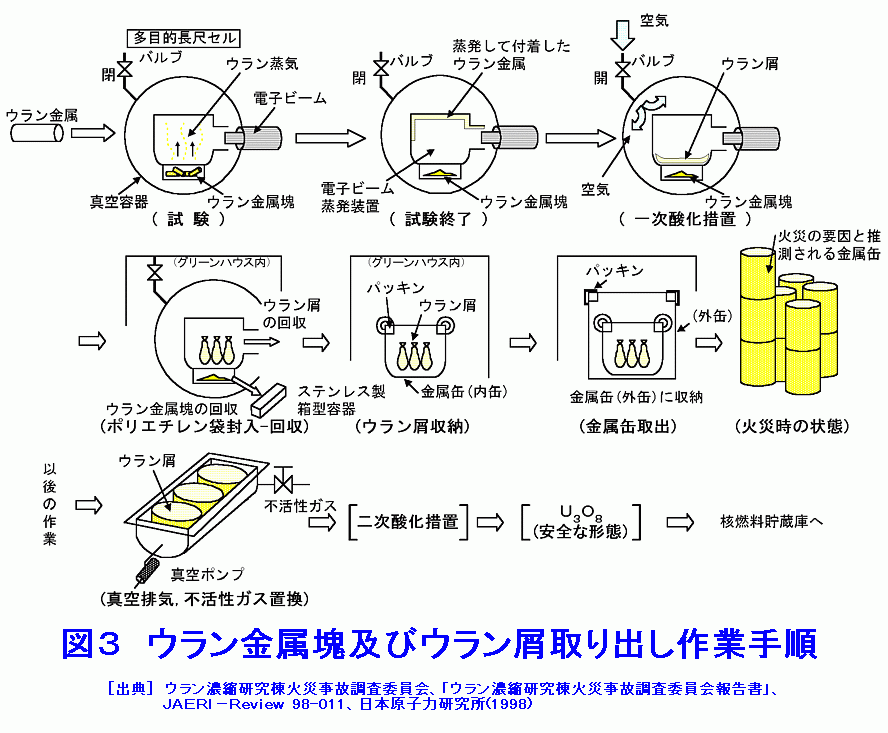
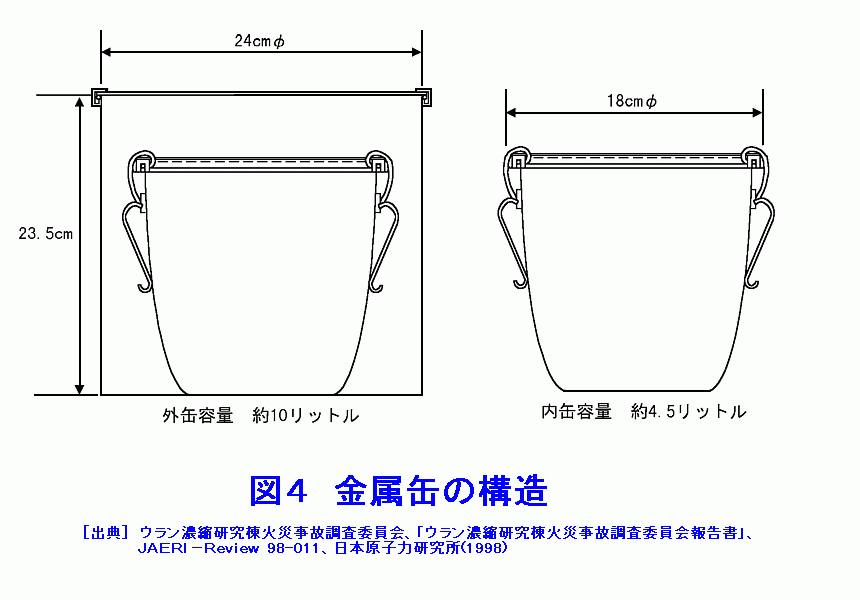
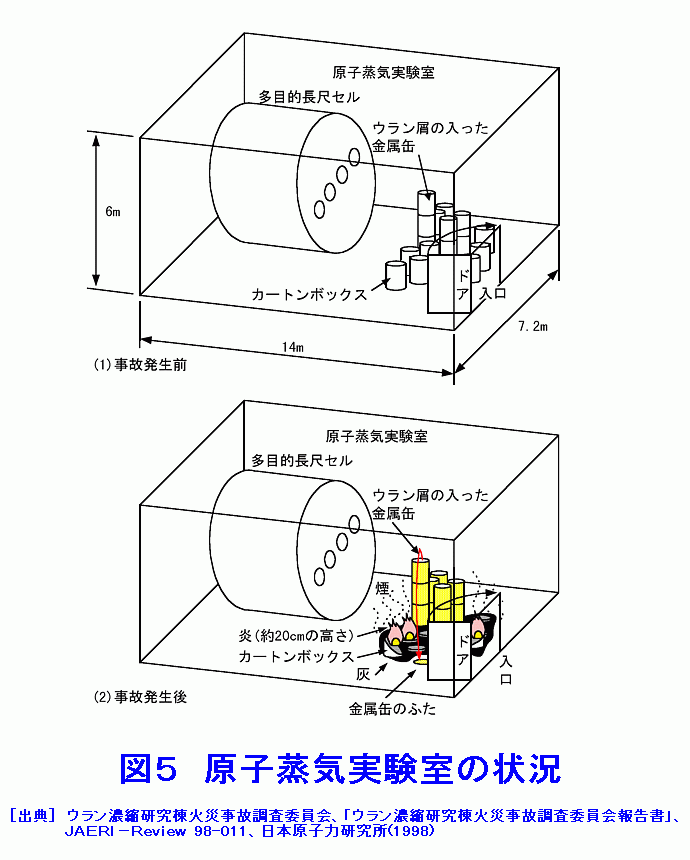
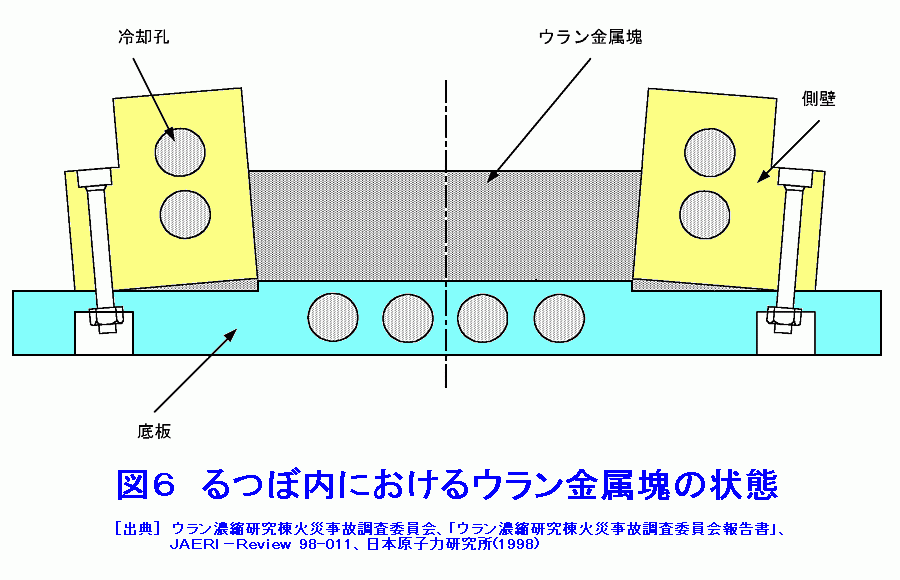
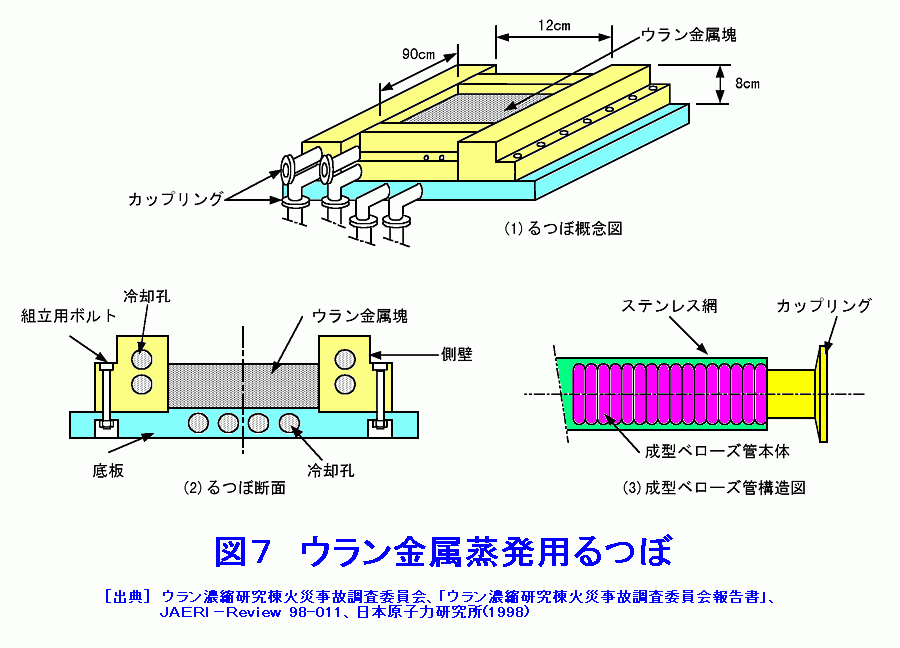
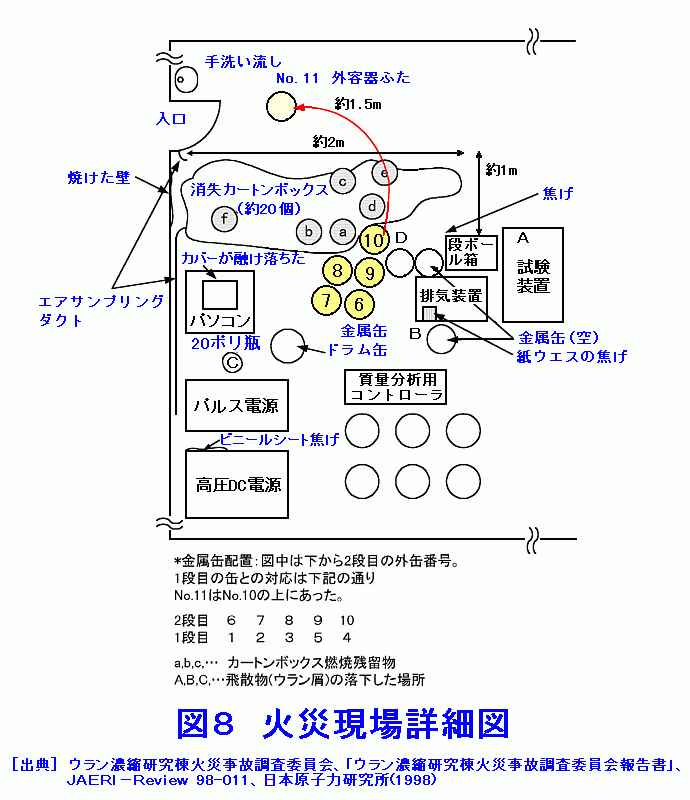
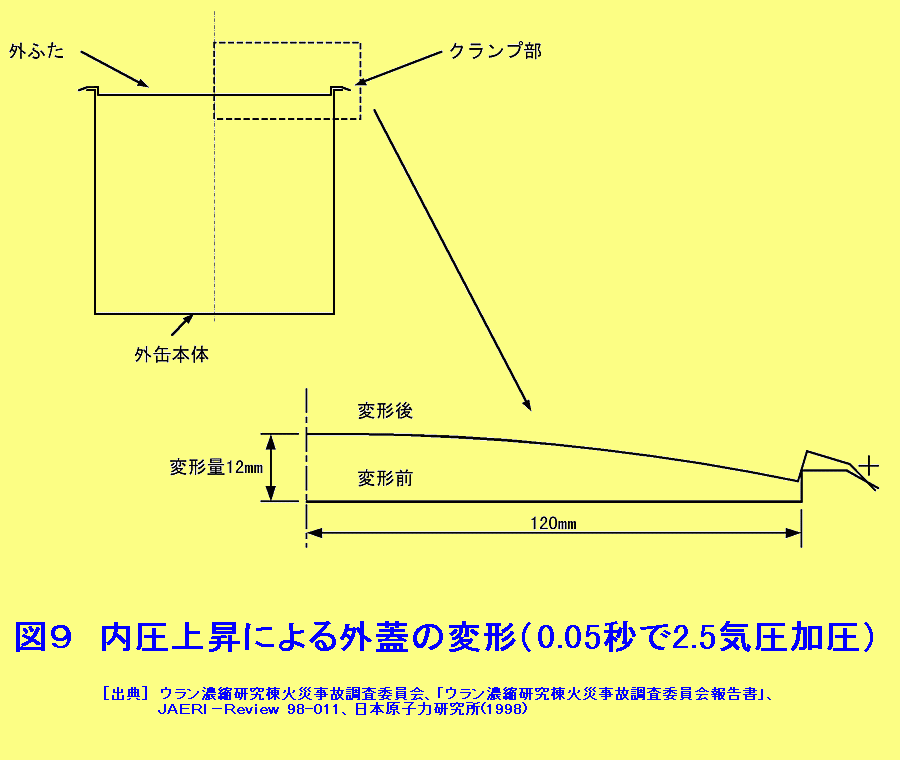
<参考文献> (1)火災事故分析ワーキンググループ:「ウラン濃縮研究棟火災事故調査−資料採取と分析−」、JAERI-Tech 98-014、日本原子力研究所(1998) (2)柴田 雄次(監修):「無機化学全書」、XVII(放射性元素)-1(1953)、ウラン、丸善、(1953年)p.131、p.155-156 (3)K. Kondo,F. H. Beck and M. G. Fontana:”A gas chromatographic study on the kinetics of uranium oxidation in moist environments”,Corrosion,30(9),330-339(1974) (4)C. W. Solbring,J. R. Krsul and D. N. Olsen:”Pyrophoricity of uranium in long-term storage environments”,ANL/TD/CP-84441(1994) (5)ウラン濃縮研究棟火災事故調査委員会、「ウラン濃縮研究棟火災事故調査委員会報告書」、JAERI-Review 98-011、日本原子力研究所(1998)
|

