|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
事故に伴って環境に放出された放射性物質の量は、事故発生後10日経過し、放射性物質の放出がほぼ終了した現地時間1986年5月6日の時点で半減期補正した値で、希ガスは、内蔵量の約100%に相当する5,000万キュリー、希ガス以外の放射性物質の量が約5,000万キュリーとされている。希ガス以外のものの核種ではヨウ素131が20%、テルル、セシウムが10〜15%その他燃料そのものが約3%といわれる。 数日間で30km圏内から住民約13万5千人が避難した。避難住民のうち外部放射線被ばくに起因するがん発生による死亡者の増加は、今後70年間に自然発生がんで死亡が予想される人数の1.6%以下と推定されていた。事故時に発電所敷地内に444人の従事者がおり、急性放射線障害と診断された人の数は203人で、事故当日に重度の火傷で死亡した1人、行方不明1人を含めて、死者総数は31人(いずれも入院治療のあと)と報告された。 <更新年月> 1998年07月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
(本データに掲載された数値はその後見直しが行われています。<関連タイトル>のより新しいデータを合わせてご参照ください。) 1.放射性物質の放出とソ連国内での影響 事故に伴って環境に放出された放射性物質の量は、事故発生後10日の放射性物質の放出がほぼ終了した5月6日の時点に半減期補正した値にして、希ガスが炉内全量の約5,000万キュリー、それ以外ではヨウ素131の炉内量の約20%、テルル、セシウムが10〜15%、その他の主要な核種がそれぞれ2〜6%放出され、合計で3,000〜5,000万キュリーと見積られている。また、燃料では敷地内に炉内量の0.3〜0.5%、20km以内に1.5〜2%、20km以遠に1〜1.5%が飛散したと報告されている。 図1は、希ガスを除く環境への1日ごとの放出量である。4月26日、爆発に伴い燃料の破砕片が飛散し1,200万キュリーという大量の放射性物質が放出された。その後、5月1日までは、ヘリコプターからの投下による石炭岩や鉛、土砂等のため放出率は低下した。しかし、その後燃料の崩壊熱等により加熱され再び放出率が増加した。5月6日までに、炉心下部よりの窒素ガス注入に成功し、放出率は一挙に低下した。 キセノン133、クリプトン85m、クリプトン85などの、希ガスは、炉心上部の構造物が吹き飛んだため、内蔵量の殆ど全量が放出され、揮発性放射性物質のテルル131、テルル132、セシウム134、セシウム137等は、その10〜20%が放出されたとされている。 1979年3月28日に起きた米国のTMI事故の際、環境に放出された放射性物質の量は、希ガスが約250万キュリーおよびヨウ素131が約15キュリーと評価されている。これと比較すると、今回の事故は、放出の規模において非常に大きいといえよう。 ソ連国内での放射能汚染状況に関するソ連の報告によると、事故炉の30km圏内での空間線量率は10〜100mR/時の値が事故後20日以上も続いており、これは自然放射線レベルの1000倍以上の値である。また、事故炉から120km離れたキエフ市での空間線量率は、事故直後の約1mR/時が50日間経った時点で約0.1mR/時と波を打ちながら減少している。すなわち、自然放射線のレベルに比べて約100倍から10倍程度になっている。図2は、5月29日時点での事故炉近辺の地表面の空間線量率分布である。事故後1ヶ月以上たった時点でも、かなりの放射能汚染が続いていることがわかる。 土壌中の放射性物質濃度については、5月6日に原子炉から1.5〜30kmの土壌について分析が行われ、ヨウ素、ルテニウム、セシウム等が検出された。 ソ連各地で、事故後2〜3日で牛乳中のヨウ素131の濃度が上昇し、白ロシア南部で1マイクロキュリー/リットル程度の、摂取制限値0.1マイクロキュリー/リットルの10倍もの濃度が検出されている。一方、葉菜類、食肉、魚等を含む食品からもヨウ素、セシウム、セリウム、ルテニウム等の放射性物質が検出された。 2.住民の避難および健康への影響 事故炉の北西約5kmの所にあるプリピアチ市では、事故発生当初とそれに続く火災の間は、市を避けた形で風が放射性物質を運んでいたが、その後、風向きの変化等により、放射性雲が市を覆い、汚染が進行した。 4月26日夜、放射線レベルが上昇し始め、やがてソ連における無条件で避難すべきレベル、全身75レム以上を受ける予測値に達した。測定結果に基づいて、避難ルートが選ばれ、27日に大型バス約1,000台を用いて約4万5千人が避難した。また、医療対策もとられた。 このほか30km圏内から事故後数日間にさらに約9万人の住民が避難した。この措置は、住民の外部および内部線量当量の予測および事故後の放射性物質の拡散を考慮してとられたものである。 表1は、避難した住民の外部被ばく集団線量当量の推定値を発電所からの距離別に示した。プリピアチ市の線量当量が低いことが注目される。4月27日中に避難した効果であると推定される。これらの外部被ばくに起因するがん発生での死亡者の予測される増加は、避難住民約13万5千人が今後70年間に自然発生がんで死亡する予想人数の1.6%以下と推定されている。 ソ連ヨーロッパ部の公衆に対する外部被ばくによる集団線量の予測値は、その人口7,450万人に対し昭和61年中で860万人レムであり(一方自然放射線での1年間の集団線量は約1,000万人レムである。)、今後50年間で2,900万人レムである。これらの外部被ばくに起因するがん発生による死亡の増加は、今後70年間に自然がんでの死亡予想数の0.05%以下と推定されている。 ヨウ素131の摂取による今後30年の甲状腺がん死亡は、自然発生の甲状腺がんでの死亡の予想人数の約1%に相当しセシウム134およびセシウム137の内部被ばくによる今後70年間のがん死亡は、自然発生がんでの死亡の予想人数の0.4%と推定されている。 3.原子力発電所従事者、消防士の被ばく 事故のとき、発電所敷地には444人の従事者がいた。このうちの一部の人々が過度の線量を受けた。これに加えて、消火活動のために現場にかけつけた消防士等が大量の放射線被ばくを受けた。 事故発生直後の救急措置は当直の医務要員等により行われた。4時間後に救急班が12時間後には内科、放射線科等の専門班が現地に到着した。事故数日後には、医師、看護婦等が多数動員され、治療、救助活動が行われた。 急性放射線障害と診断された被災者は203人である。事故当日に重度の火傷で1人が死亡、行方不明が1人の2人を含め、死者総数は1986年8月21日現在で31人であった。1989年10月末での調査でもこの数は変わっていないとソ連当局はいっている。 4.ヨーロッパ諸国を中心とする放射能の影響 事故に伴い放出された放射性物質は火災による上昇気流となって、上空1000m以上に達したと推定されている。このため大気中に広く拡散し、4月28日朝(スウェーデン時間)に初めてスウェーデンで検出されて以来、ヨーロッパ諸国をはじめとする諸外国において、4月末から5月初めにかけて放射線レベルの増加が見られた。 図3は世界保健機構(WHO)が1986年6月5日に発表した数値に基づくヨーロッパ諸国における空間線量率の最大値である。これらのヨーロッパ諸国の一部では、食料品、飲料水、牛乳等の摂取制限、野菜、肉類等の市場出荷制限、牛の牧草供与および放牧制限、放射能汚染食品等の輸入制限、車両および船舶の検査、海外旅行者対策、子供の外出制限等さまざまな対策が実施された。 1986年5月6日にコペンハーゲンで専門家グループによる会議を開催し、これ以上放射性物質の大量放出はないと推定されること、ヨーロッパ一帯の大気圏によって薄められること、短半減期のものは減衰したことなどから、初期の段階で一部の国でとられた措置はもはや必要ない旨の勧告を出した。この結果、上に述べた措置は徐々に解除された。表2にヨーロッパのOECD加盟国での被ばく線量当量を示した。 5.我が国への影響 我が国でも飛来した放射性物質が検出され、観測が強化されたが、幸い放射能は極めて少なく、健康上支障を与えるようなレベルのものではなかった。 <図/表> 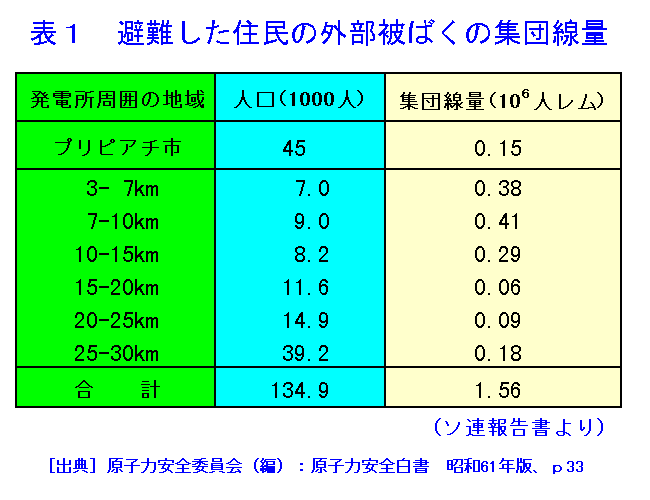
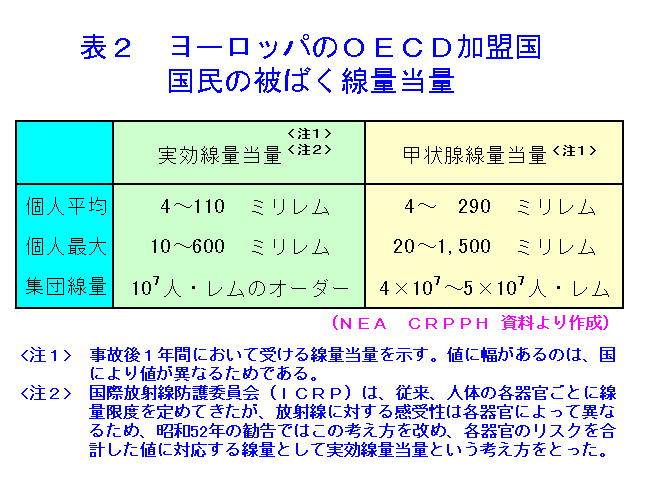
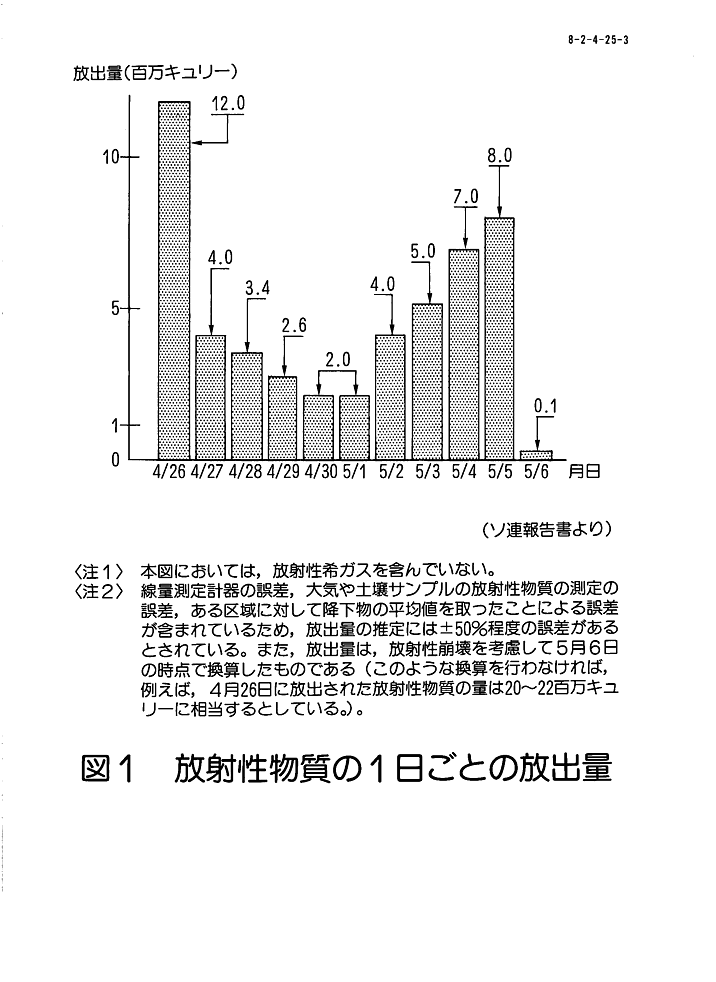
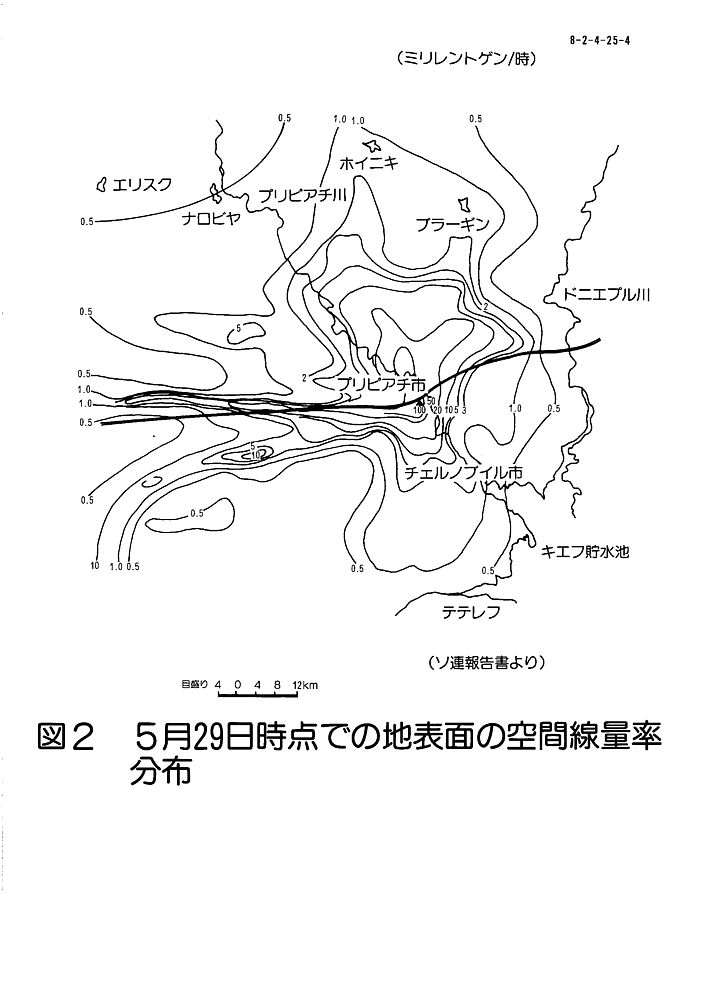
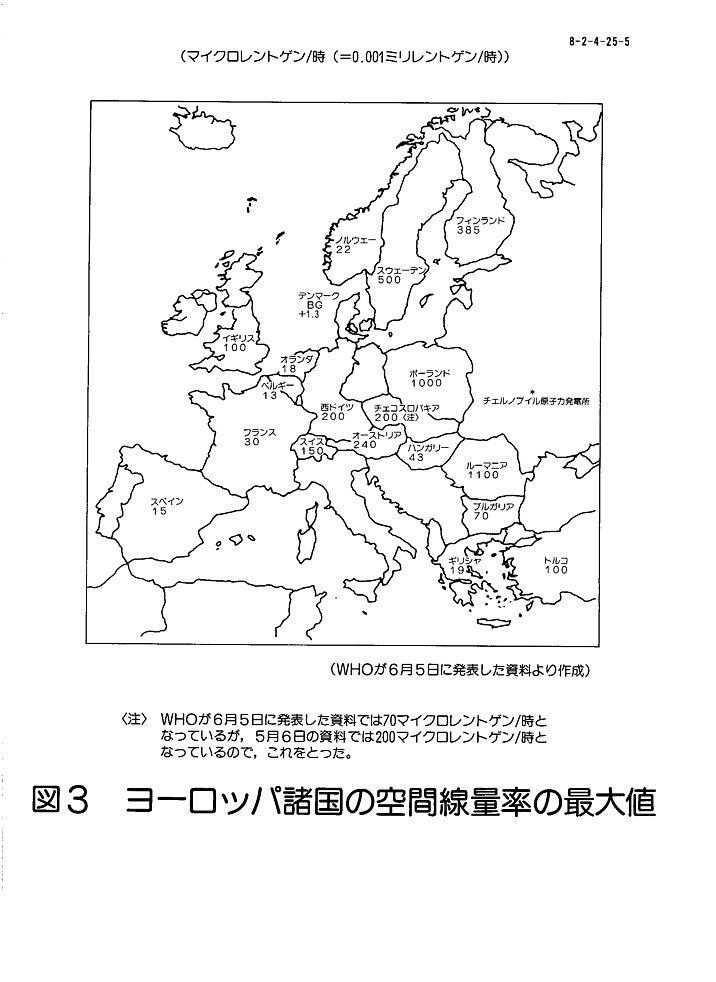
<関連タイトル> チェルノブイリ原子力発電所事故の概要 (02-07-04-11) チェルノブイリ原子力発電所事故の経過 (02-07-04-12) チェルノブイリ原子力発電所事故の原因 (02-07-04-13) チェルノブイル原子力発電所事故と我が国の対応 (02-07-04-16) チェルノブイリをめぐる放射線影響問題 (09-01-04-10) フォールアウトからの人体内セシウム(40年の歴史) (09-01-04-11) チェルノブイル事故による健康影響 (09-03-01-06) 旧ソ連チェルノブイルから10年−放射線影響と健康障害−(OECD/NEA報告書) (09-03-01-07) チェルノブイリ事故による放射線影響と健康障害 (09-03-01-12) チェルノブイリ事故による死亡者数の推定 (09-03-01-13) <参考文献> (1)原子力安全委員会(編):原子力安全白書(昭和61年版)
|

