|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
1997年12月、京都において開催された「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」では、京都議定書を採択し、具体的削減数値については、付属書1締約国全体の目標として2008年から2012年までに、二酸化炭素など温室効果ガスの排出量を1990年に比べて少なくとも5.2%削減することを定めた。アルゼンチンのブエノスアイレスで開催された同条約第4回締約国会議(COP4)では、京都議定書を具体化させるための「ブエノスアイレス行動計画」を全会一致で採択した。環境問題は多様化し、国際化して、従来のような規制的手法だけでは成果があがらないとの認識の下、経済的手法が注目されてきている。経済的手法には、環境税、課徴金、排出権取引などの手法があり、欧米諸国では活用事例もある。我が国では、規制的手法、自主的取組などに加えて環境省から2004年11月に環境税の具体案が提示されており、より実効性があり経済効率的な方策として国民的な討議が求められている。 <更新年月> 2005年07月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.地球の温暖化問題と京都議定書 人間の経済活動により、温室効果ガスの大気中の濃度が上昇し、温室効果が強まって、気温が上昇する恐れがあるとの問題が指摘されている。気温の上昇により、海水の膨張と陸上の氷の融解により海水面が上昇し、沿岸地域で浸水や浸食により被害が発生すると思われる。世界中の臨海都市、エジプトのナイル川、バングラデシュのガンジス川などの大河川の流域河口部、珊瑚礁の上にあるモルジブなどの島国は水没する恐れがある。降水量、降水時期の変化や、高温障害、病害虫の発生の様子の変化、土壌水分の変化等は、農作物に影響する。動・植物の生態系は、気候の急激な変化に耐えられず、植物群落の荒廃、種の絶滅が加速される恐れもある。また、気候と関係のある感染症の分布変化等により、人間の健康にも影響する可能性がある。 「地球の温暖化問題」が現実になれば、人々の生活に与える影響は極めて大きい。また、その影響が明白に認識されるようになった時点で対策を講じても、大気中の温室効果ガスを急速に減少させることは不可能なうえ、一度起こってしまった気候変動や海面上昇を回復させることも至難の技である。手遅れにならないうちに必要な対策を実行していくことが重要であるとの認識が高まり、1997年12月、気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)(地球温暖化防止京都会議)が、京都において開催され、京都議定書を採択した(表1参照)。 1998年11月2〜13日、気候変動枠組条約第4回締約国会議(COP4)がアルゼンチンのブエノスアイレスで開催された。この会議では、京都議定書を具体化させるための「ブエノスアイレス行動計画」(Buenos Aires Plan of Action)を全会一致で採択した。行動計画では、 (1) 先進国が途上国の温暖化防止策を支援し、削減分の一部を自国分に算入できる「クリーン開発メカニズム」を重視しつつ、温室効果ガスを削減するための国際制度を2000年(平成12年)の第6回会議(COP6)までを目標に交渉する。 (2) 資金制度として世界銀行などが管理する「地球環境ファシリティ」(GEF:Global Environment Facility,地球環境資金制度ともいい、地球環境保護のため開発途上国へ資金を提供する。1991年に発足)を活用し、途上国が自国の温暖化対策の現状などを条約事務局に報告する仕組みを整えるための交渉を進める。 (3) 温暖化で水没が懸念されたり、化石燃料の消費減少で経済状況が悪化すると主張する産油国への保証問題、削減目標が達成できなかった場合の罰則規定の強化などについて専門家会合などで検討する。ことなど6項目についての今後のスケジュールや期限が明記されている。 京都議定書の運用ルールの国際法文書は、第5回締結国会議(COP5,1999年10〜11月、ボン)、第6回締結国会議(COP6,2000年11月、ハーグ)、第6回締結国会議再開会合(2001年7月、ボン)を経て、第7回締結国会議(COP7,2001年10〜11月、マラケシュ)で「マラケシュ合意」として合意された。そして我が国は2002年6月に締結し、2005年2月16日に議定書は発効した。 日本は2010年前後に温室効果ガスの排出量を1990年比で6%削減することが規定されているが、原子力発電所の新規建設計画が予定通り進まず、数基程度は火力発電設備に置き換わると見られる。また、運輸部門の化石燃料依存からの脱却は、早急には進展しそうにない。一方、米国は、開発途上国問題への対応を不満として、京都議定書の批准はしないとの立場を堅持しており、実効性ある排出削減数値目標の達成は、国内的にも、国際的にも困難に直面している。 2.環境税 環境問題が多様化し、国際化して、従来のような規制的手法だけでは成果があがらないとの認識の下、経済的手法が注目されている。経済的手法は、市場のメカニズムを通じた最少コストで最適な努力の配分をもたらす利点がある。環境税・課徴金は、こうした経済的手法の代表例で、すでに欧米諸国では活用事例があり、環境保全に効果をあげている。 (1) 欧米における温暖化対策の動向 欧米における温媛化対策としての経済的政策措置(環境税や排出権取引)を中心にみてみると、その取り組み方は地域によって異なっている(表2参照)。欧州では、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、オランダなど北欧地域で90年代初頭に環境税(炭素税)が導入され、1990年代後半に入りドイツ、イタリア、イギリス、フランスといった経済規模の大きな国で、温暖化対策の一環として環境税の導入、あるいは、その検討が行われてきた。また、欧州では、既にイギリスやデンマークで国内排出権取引制度が導入され、2005年にはEu域内で電力やエネルギー多消費産業に排出枠を設定し、企業間の排出権取引によって排出削減するキャップ&トレード型の排出権取引制度が創設され、京都メカニズムともリンクを可能とする制度となった。カナダでは、2003年、政府と産業界の基本合意がなされ、現在制度設計が行われている。 ここで、炭素税のほかに、硫黄酸化物税、使い捨て飲料容器税などの税も環境税の1つであり、課徴金は、不用物の排出抑制、あるいは、不要物処理のための公共施設・サービスの利用に当てる費用のことである。 (2) 環境税の意義 経済的手法は直接規制に比較して、 第一に、市場のメカニズムを通じて、それぞれの主体が最も経済的な行動を自主的に選択することにより、少ないコストで最適な努力を達成できる。 第二に、規制的手法では、規制値を超える汚染量削減の動機が希薄に成るが、経済的手法は、汚染量の削減が経済的な利益に結びつくため、継続的な効果があるとされる。 また、経済的手法は各企業体に対し費用と便益に基づく自主的な判断を求めるため、直接規制に比べ、より自己責任を求めることになる利点がある。 環境税・課徴金はこうした経済的手法の代表例であり、諸外国において、環境政策の重要な手法として活用されている。環境への負荷の少ない持続可能な杜会の構築を標榜するわが国においても、考慮すべき問題とされている。 3. 環境税をめぐるわが国の動向 日本では、温暖化対策としての環境税に関する検討は、90年代初頭より行われていた。その後の京都会議を経て、近年ではその議論がより活発化している。98年に、環境庁(現環境省)によって「環境政策における経済的手法活用検討会」が設置され、2000年3月に公表された報告書のなかで、環境税の有効性に主眼をおいた「ポリシーミックス」の必要性が指摘されている。2000年7月には通産省(現経済産業省)が、その必要性も含めて検討を行う旨を公表している。政府税制調査会も7月に公表した報告書において、環境問題における税制活用の必要性を引き続き示唆しており、社会的に導入の議論が高まりつつあるようにうかがえる。産業界は、自主行動計画が対策として有効であるという立場から、一貫してその導入に反対している。政府税調と環境庁(現環境省)の主張では、環境対策における税制の優位性を主張している点で共通しているが、その税収の使途が「一般会計に組み入れる」、「環境対策に充当する」といった点で異なっている。 産業界は、これまで自主行動計画の有効性を主張してきているが、最近では京都メカニズムも有効であるという趣旨の立場をとりつつあり(表1参照)、2005年から排出抑制設備の導入に対する補助金と排出枠の貸付を受ける参加者を含む事業者の自主参加型国内排出量取引制度が導入された。 さらに、環境省は我が国の温室効果ガスの排出量は、1990年比約8%増の現状に鑑み、温室効果ガスの排出量に応じ、工場や企業、家庭などから幅広く負担を求めることができ、公平性、透明性、効率性、確実性に優れた施策として、環境税の具体案を2004年11月に提示し、国民的討議を求めている。(図1参照)従来から温暖化対策に取り組んでいる産業界の国際競争力の維持や低所得者・中小企業への配慮等の軽減措置も考慮され、温室効果ガス約4%強程度の削減を期待している。 4.環境税と排出権取引の比較 (1) 削減目標達成への効果 新たな政策措置としての要件は、導入済みの政策による効果を補完して、京都議定書における削減目標達成を確実にすることである。 環境税は、目標とする削減量を実現するための適正な税率を設定することに問題があると指摘されている。環境税によって削減目標を達成するには、導入の効果を評価しながら幾度かの税率変更が必要と考えられる。排出権取引は、初期に割当を適切に行うことができれば、その量的目標達成の可能性は高い。これまで省エネルギーを進めてきた日本では、国内だけで削減措置を実施する場合、その削減コストは、国際的に比較して非常に割高であり、仮に削減目標を環境税のみでまかなうとするならば高い税率が必要となる。そのため、当初は低税率の環境税とその追加的な税収を用いた対策の組み合わせが現実的な選択となる。しかし、これまでの省エネルギー進展やすでにエネルギー関連諸税の税収を用いた同様の取り組みが行われていることから、環境税収による追加的な省エネルギー投資などの誘発効果がもたらされるのかどうか、その評価が分かれるところである。 排出権取引は、その国際的な制度の枠組みが構築され、国内制度をそれに適応するように整えれば、日本に比べ削減費用の低い他国との取引を通して、国内における対策費用を国内のみの制度に比べ大幅に軽減することが期待されている(表3参照)。 (2) 制度設計面での相違 環境税の持つメリットとしては、既存のエネルギー関連税制の経験を通して、その制度設計が比較的容易であるという点が挙げられる。つまり、日本における既存の税制を考慮に入れた場合、既存のエネルギー関連税制をたたき台とすることが可能であるという考え方である。ただその導入にあたっては、すでに多額の税が課せられている石油諸税との調整が必要となる。すでに多額の税が課せられているうえ、炭素税的にみれば大幅に偏った現行のエネルギー関連税に対して、別種炭素税を独立して課税することは問題があると指摘されている。一方、産業の国際競争力に対する懸念や企業間の負担格差をいかに是正するかも、課題として挙げられる。日本の主たる貿易相手国である米国やアジア諸国を考えれば、相手国・地域において環境税などの導入可能性が低いため、貿易産業にとっての競争力は環境税の導入によって低下する。この問題解決のためには国際的な共通環境税の導入や、国境税調整などの手段も考えられるが、現時点では実現が難しい。 また、素材系産業は相対的に追加的コスト負担が他産業に比べ大きくなることが予想され、こういった産業間の調整を考慮することも課題として挙げられる。他方で、エネルギーという財を考えると、環境税の逆進性(最低限のエネルギー消費が各人必要なため、低所得者の負損が大きくなる可能性がある)やエネルギー消費の地域特性による負担格差是正も課題の一つと考えられる。排出権取引の場合、その制度設計にあたっては、これまで国内外における知見が少なく、国際的な検討動向や日本の特性を考慮した検討が必要である。特に、初期段階での排出割当については、制度の運用コストや実現性といった点に留意して、割り当てを行う方法や対象を検討する必要がある。欧米などでも実際に検討されている自主的取り組みとの組み合わせ可能性などのオプションを考慮するなど、今後さらなる制度構築のための比較検討が必要である(表4参照)。 5. 今後の課題 京都議定書の国際的な内容の検討や、議定書の発効可能性・時期など、国際的な温暖化対策を巡る環境はいまだ不確実な点が多々ある。これまで北欧諸国で導入されてきた炭素税は、税率が一様でなく、エネルギー多消費産業には殆ど課せられていない。これは国際競争力の問題のためといわれている。多国間で調整すればという議論もあるが、現実には、主権の問題も絡んで、多くの政治的困難が生じるであろうといわれている。しかしその一方で、第1コミットメント期までの時間も残り少なくなってきている。我が国の削減約束(6%)を確実にするためには、規制的手法や自主的取組、経済的手法など様々な施策可能な限り排出削減をすすめていく必要がある。企業や国民全員が温暖化対策に参加していく仕組みの構築が必要で、環境税の導入により、各分野における温暖化対策の取組がより一層促進される支援や雇用の促進など企業活力の維持・向上に税収が活用されよう。 <図/表> 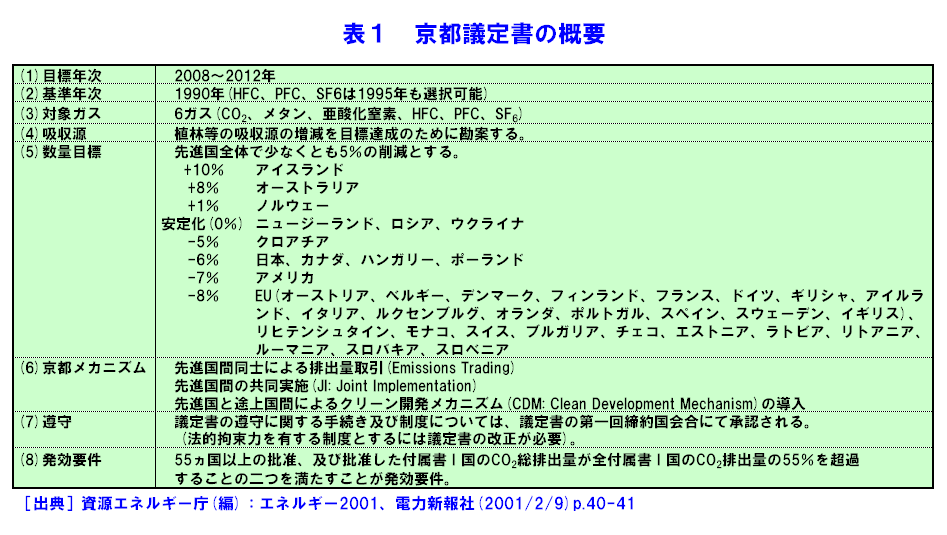
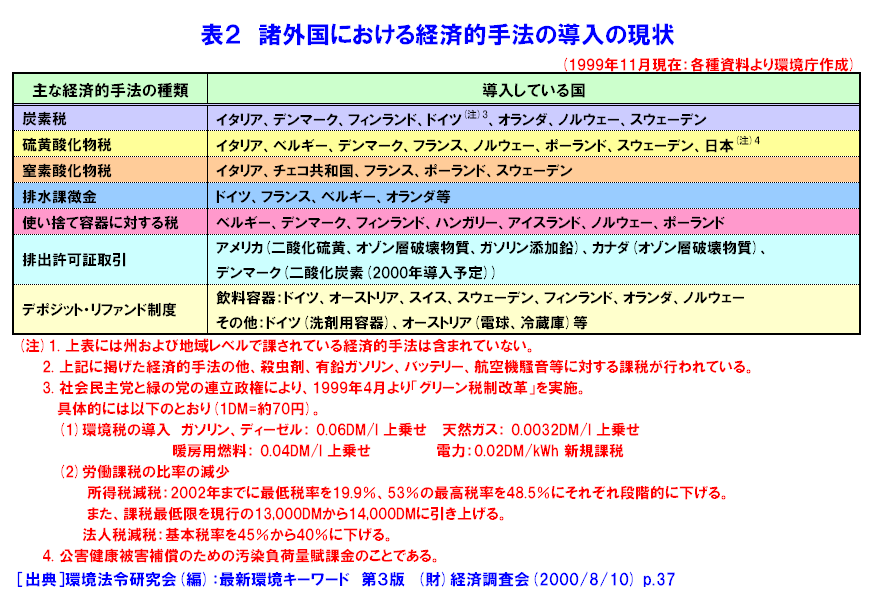
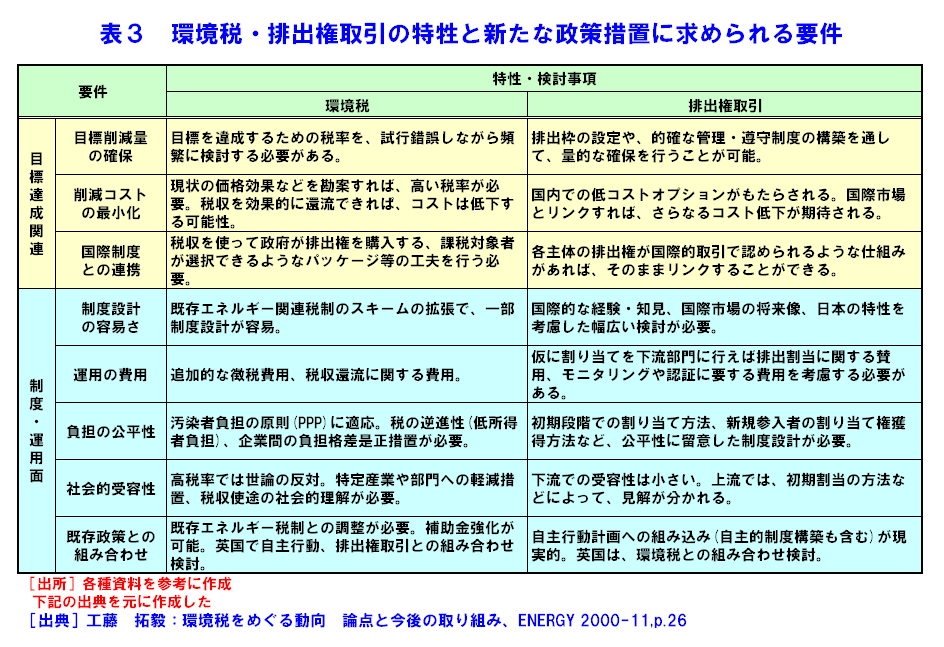
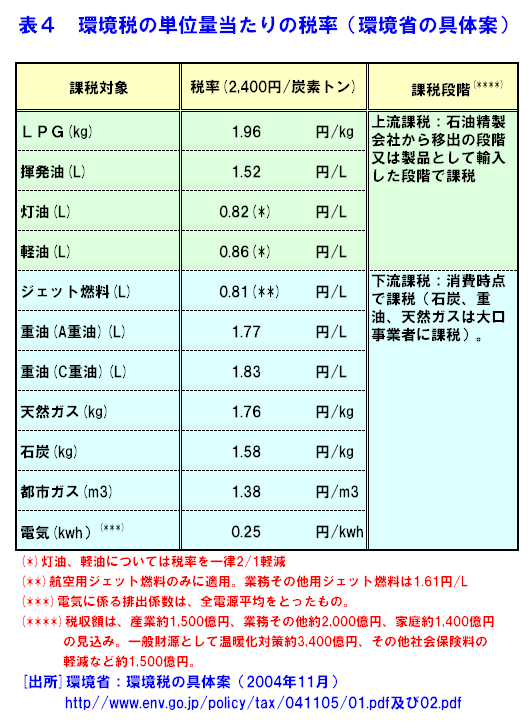
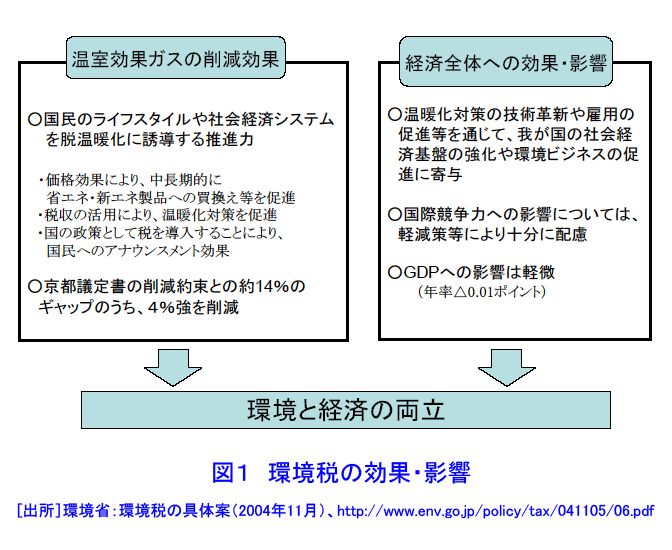
<関連タイトル> 地球の温暖化問題 (01-08-05-01) 地球温暖化防止京都会議(1997年のCOP3) (01-08-05-15) ブエノスアイレス行動計画(1998年のCOP4決定) (01-08-05-19) 国連気候変動枠組条約第5回、第6回および第7回締約国会議(COP5・COP6・COP7) (01-08-05-20) <参考文献> (1) 工藤 拓毅:環境税をめぐる動向 論点と今後の取り組、エネルギー Vol.33 No.11(2000/11/1)p22-29 (2) 環境法令研究会(編):最新環境キーワード 第3版 財経済調査会(2000/8/10) p.36-37 (3) 資源エネルギー庁(編):エネルギー2001 電力新報社(2001/2/9)p.40-41 (4) (財)地球産業文化研究所(編):地球環境 2000−’01 株式会社ミオシン出版(2000/2/21) p.39-46 (5) 環境省:環境税(温暖化対策税制)について、http://www.env.go.jp/policy/tax/kento.html
|

